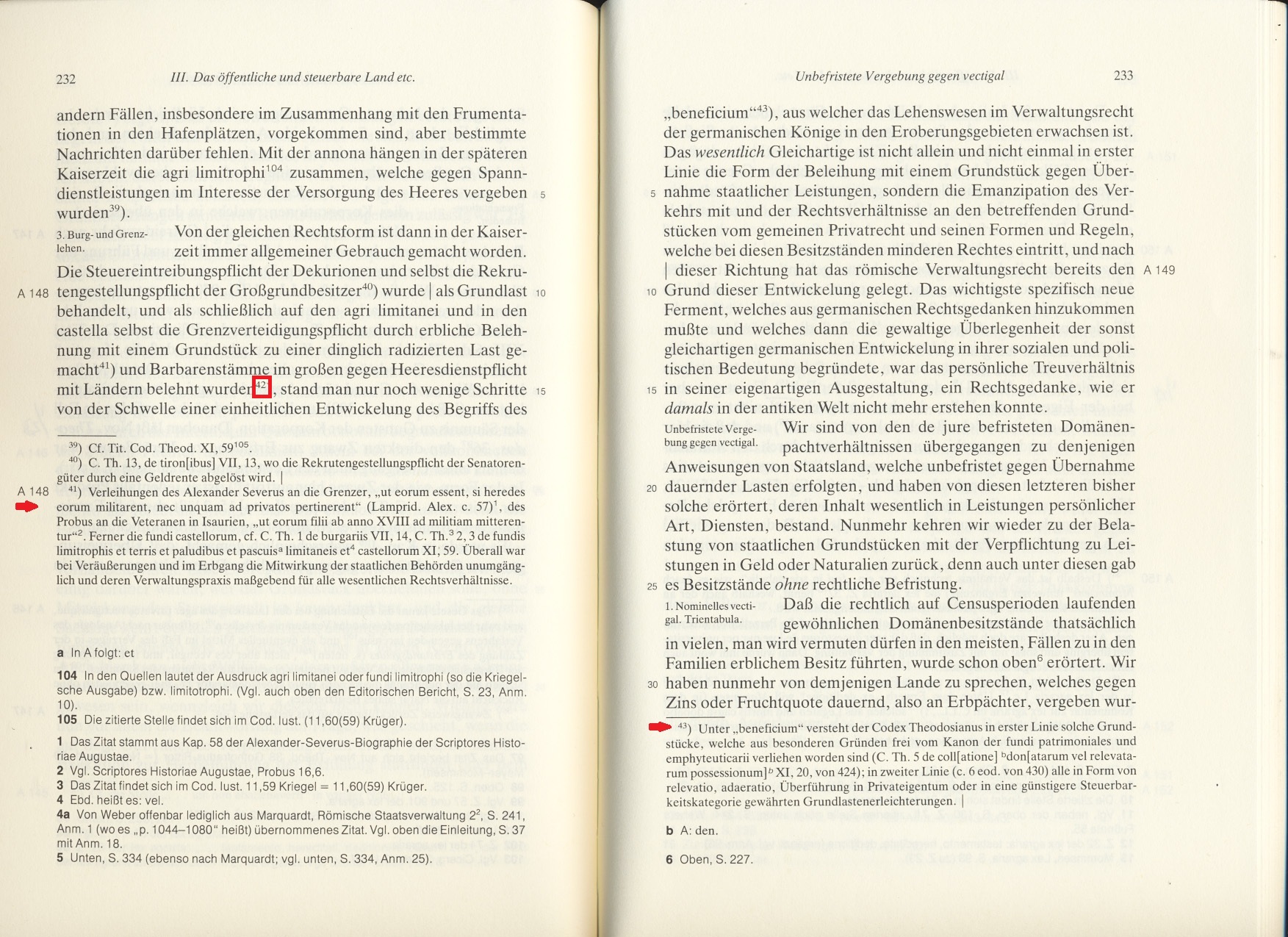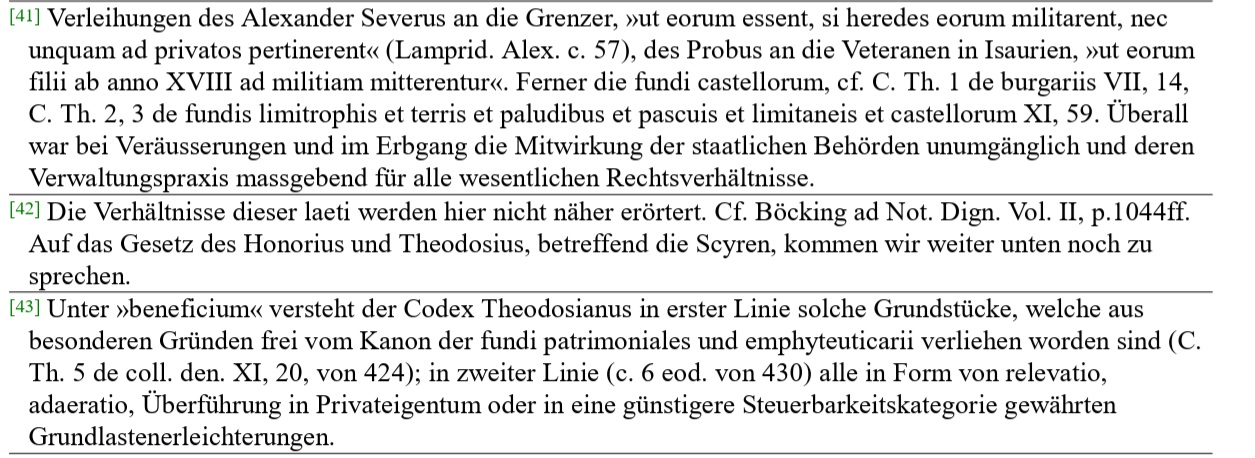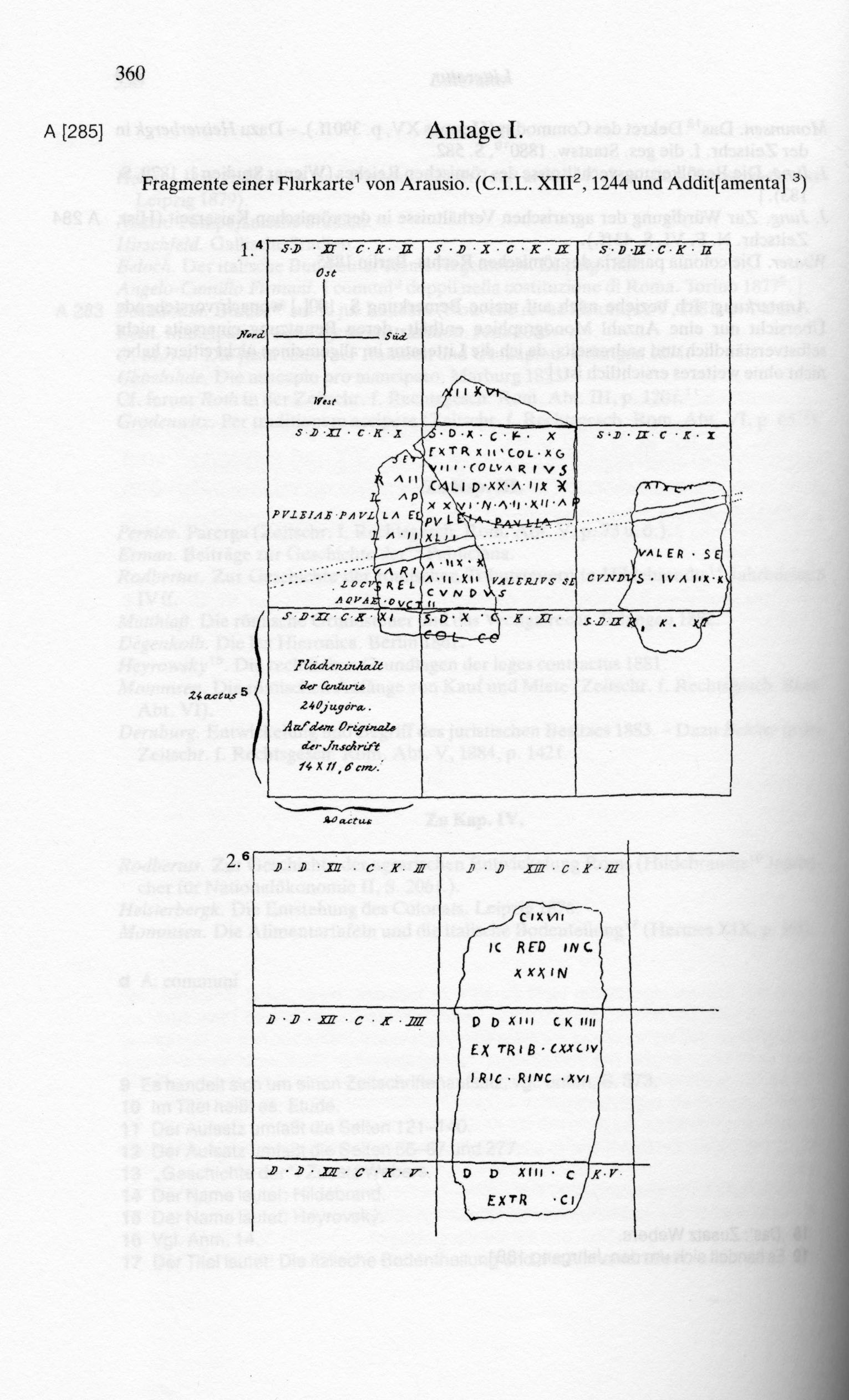「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第67回目です。ヴェーバーはここを書いていた時期、丁度軍隊で訓練を受けており、そのせいか農場での奴隷の生活を軍隊とそっくりと描写しています。しかしこれについては本当にそう単純化していいのか、という疑問があります。また農場の管理人達が単婚制で一般の奴隷はそうではない、と何度も述べていますが、これも眉唾です。この時代ともかくも単婚制になる前は乱婚制だったという誤った歴史認識がはびこっており、ヴェーバーも間違いなくそういうバイアスを受けていると思います。
===========================
そういった居住の仕方は次のような場合にもまた同じであった。つまりコローヌスが奴隷の進化した者として現れており、かつそれ故にまず第一には労働者である場合で、そういった労働者は土地の管理人である actor や villicus の厳しい監督下に置かれており、それはコルメッラが前提としていることであるが、特にそのコローヌス達の食事が農場の側で供給されねばならなかった場合にそうであり、そうされた理由は夫役の日数が自由な日の日数より多かったからである 105)。
105) ガリアでは次のことが起きていたと思われ、それについては敬愛する顧問官のマイツェン教授が私に気が付かせてくれたものであるが、ある邸宅を取り囲むような集住が次のようなやり方で、つまりコローヌス達が農場主の邸宅の周りを囲むように集住して村落を形成し、また方形の耕地がそこに置かれる、というやり方で起きていたということである。このことは私の考える所では、ただ次の意味だけを持っていた。つまり大地主が奴隷をもはや相当な程度の数で抱えておくことがなく、そのために今や全ての耕地にただ夫役に従事するコローヌス達のみを配置し、要するにこういった好都合な、夫役に従事する農民とまさに同じ者達を使うしかなかったのであり、そしてコローヌス達のフーフェ制度のやり方に従って形成された村落によっての地主の邸宅の囲い込みが要望され、そしてその結果土地のの新たな分割割当てが行われ、その際に他方では大地主その配下の者達を、軍事上の理由から自分の邸宅の近くに集めたのである。しかしながらこのことが起きたのはドイツの植民地建設[民族大移動の結果による]の後であり、それ故この時代に起きたことではない。
コルメッラはそれ以外に次のことも規則的に起きたこととして認めている。それはコローヌス達が大地主が管轄する領域から離れた場所に居住していた場合もあった、ということである。それ故にコローヌスの大地主に対しての位置付けというものはもはや、コローヌスに対して実際に成立していた従属性の程度と社会的な状態については、一般化出来るようなことはほとんどない。glebae adscriptio [土地の付属物]という表現は、それが何らかの新しい要素を包含している限りにおいては、コローヌス達の地位が悪化したという意味は持っていない。
地方における労働者という身分の運命
そういったコローヌスの状況に対して、奴隷の状況についてはいくつかの発展傾向が新たに確立されていた。我々が先に見て来たように、奴隷を使った農場経営はその頂点を極めた時、つまり帝政期の初期においては、強度に軍隊風であった。奴隷達は兵舎のような共同の宿舎で眠り、一緒に食事を摂り、単婚制的な男女の関係は一般的にそこではほとんど見られなかった。≪これはヴェーバーの思いこみで正しくない。実際は同棲形態で暮らす男女の奴隷は多くいた。≫軍隊での10人組風のやり方で朝になると集まり、男性または女性の管理人によって点呼を受け、そして3-10人の単位で仕事場に連れて行かれ、「現場監督」(monitores)の監視の下で働かされた 106)。
106) コルメッラ 1, 9;12, 1。
労働のためのグループ分けは各奴隷の体力に応じて行われ――体力のある者は穀物畑に、逆に体力に劣る者はブドウ畑に振り分けられ 107)、――更には残った者はブドウ畑とオリーブ畑に割り振られ、また先に詳述したように、価格の安いかつほとんどが鎖につながれたままの通称有罪奴隷もそちらに回された。
107) コルメッラ 1, 9。
――奴隷に与えらる衣服は、我々が兵舎で支給されるものと同様のもので、その兵舎[宿舎]の中での決まった場所に保管されていた。奴隷は毎年チュニック≪2枚の長方形の布を肩で結んだトーガの下に着る内着≫を、2年に1回サガ≪外套≫(カトー 59)を受け取っておあり、それと並んでその者は仕事の時に使うための継ぎを当てた上着(centones)を所有していた。月に2回員数点検が行われた 108)。
108) コルメッラ 11, 1。
祝祭日用の飾りつけは男性奴隷は女性の管理人に対して「部屋の中で」行うことになっていた。女性の管理人達は調理場を共有し、同様に機織り機もであり、それを使って女性の奴隷が衣服の必要を満たすために機を織っており、また病室も同様に共有していた 109)。
109) コルメッラ 12, 1。
通常の奴隷の上に、既に言及したように、管理人である villicus がおり、大抵はその農場で生まれ育った奴隷の一人であり、後にはより上位の管理人である actores が出現している。後者については、コルメッラが言及するところでは、より上質の衣服を着用していたとされている(12, 3)。actores は単婚制を取っており、時には農場主の食卓に招かれることもあり 110)、そして大地主と共有する財産というプレミアムを与えられていた。≪全集の注によればこのプレミアムはインセンティブ的に一般の奴隷にも与えられていた。≫全く同じことが奴隷の区分けに権限のあった praefecti [praefectus の複数形]にも言え、その者達も単婚制を取っており≪ヴェーバーは単婚制を actores や praefectus の特権であったように書いているが、一般の奴隷においても婚姻権こそ無いものの、contubernium 、字義としては「同じテントで寝る」、という同棲婚が多く行われていた。これは奴隷に子供を作らせる上でも有効なため、コルメッラの農業書などでも奨励されていた。≫、また同じくプレミアムを与えられていた 111) 、――この二つの身分はしばしば同列に扱われていた。
110) コルメッラ 1, 8。
111) ウァッロー 1, 17。
奴隷の供給が封印されればされる程、そのために地方の奴隷達がまさしく自分達だけで何とかやって行くしか方法が無くなった程、そしてそれによって耕地で農作業を行う奴隷の人口が減っていけばいく程、それだけ一層奴隷達の組織は確固たる形で構築されねばならなかった。コルメッラの農業書では magistri officiorum ≪ローマ帝国の最後期での最上位の行政管理官≫が言及されているが 112) 、奴隷達はそれ故にただ純粋に「会社組織のように」階級や10人組制度に従って組織化されたのではなく、そうではなくまたその仕事の内容に従って、またその労働力の種類によって組織化されたのである。
112) コルメッラ 11, 1。
そのことは農場で必要とされる技術がより一層細かくなり高度化したことと関係がある。カトーやウァッローのようなより早い時期の農業書においては、多くの場合ただ家畜の世話をする飼育係だけが他と区別されており、他の全ての人員は operarii [作業者]として一まとめにされていた。コルメッラがしかし言及しているのは、新たに次のことにより重点を置かなければならない、ということで、それは例えばブドウの栽培であり、それに対してそれまでは最低価格で購える人員が使われていたのであるが、熟練の vinearii [ブドウ栽培人]を雇い入れなければならないと主張しており 113)、そういった者達は当然のこととしてその部門に継続して留まったのである。
113) コルメッラ 3, 3。
そういった人員間の区別は次の場合にはより一層はっきりしたものになったに違いない。それはより規模の大きな農場で、自前の手工業者を組織化し始めた時である。コルメッラが更に言及していることは 114)、fabri [手工業者]は多くの場合購入奴隷であったということで、――もしかするとそういう者達は相当規模の学校出身であり、しかしより確からしくは都市の親方達の元で技術を取得した者達であっただろう 115)。
114) コルメッラ 11, 1。
115) 法的史料にしばしば見られるのは手工業に従事する奴隷の訓練についての契約書である。
しかし後の時代になるとこれに対して、既にパラディウスの時代には、上述したように、手工業者を自分の農場内で養成するようになった。より後の時代の農場の組織においては、農業労働者の部門の――officia――と手工業者の部門――artificia 116)――がはっきりと区別されるようになった。
116) D. 65 de legat[is] :ある奴隷が officium から artificium に異動させられた場合は、その労働の対象が変わることによってその奴隷が持っていた[土地などの]相続対象物の権利は消失した。familia rustica 「地方での一族郎党]と familia urbana [都市での一族郎党]の明確な区別についてはより古くからあるものであるが、後の時代のものについては D.99 pr. de legat[is] 3;D.10, §4, de usu et habit[atione] 7, 8 と比較せよ。共和制期においては、不要となった人員を familia urbana から地方へ持って行くことが行われていたが、これは後になると変わり、コルメッラは familia rustica が基本的にはより高い地位に置かれるようになっていたことを確認しようとしていた(コルメッラ 1, 8)。
二つの部門のどちらに所属しているかということは、いずれの場合もその奴隷の奴隷舎からの解放が実現するとすぐに明らかにされ、そして手工業者にとっては一般的に行われたことは、その所属の地位が事実上相続可能なものとなったことである。農場での共通の奴隷舎からの解放が一般論として決定的な発展の主因となっていた。農場の管理人達、つまり officiales においては、既に述べたように、それらが確立したのはコルメッラの時代であり、その者達は単婚制を取っており農場主からプレミアムを受け取っていた。≪先に書いたようにどちらも管理人達だけの特権ではない。≫既に帝政の初期においてその者達と自由民の結婚が行われていたし、≪奴隷には正式な婚姻は認められておらず、ここでの話はおそらく解放奴隷のことと思われる。≫大地主経営する農場に属している者達は、こういった形でまさに大農場の中で組織分けされている限りにおいて、その状態を一種の身分と捉えており、共同宿舎からの解放はただその農場の中においての昇進と思われていた 117)。
117) 奴隷と自由民の結婚については C.I.L., X, 4319.5297.6336.7685。villicus と自由民の結婚を記録しているのは C.I.L., II, 1980。自由民と管理人の結婚については C.I.L., X, 6332、actores の単婚状態については:C.I.L., V.90.1939; XII, 2250。通常の奴隷の確固たる同棲婚の例としては C.I.L., V, 2625.3560.7060。servi dispensatores [財務担当の奴隷]はしばしば富裕な者達であり(ヘンケン≪1816~1887年、モムゼンと一緒に古代ローマの碑文の解読を行った文献学者≫, 6651)、そしてそれらの奴隷が解放されなかった理由は、モムゼンの推測によれば(C.I.L., V, 83)、その者達が会計管理人として場合によって[不正なことをした場合には]拷問にかける可能性があったからではないかとしている。確固たる同棲関係が古典法学の時代に規定として認められていたとしたら、その場合には既にその当時そういった関係を継続性があるものとし、良く知られた「奴隷の内縁者」として認めていたのかもしれない。
こうした発展の道徳的な意義については、ここでは特段何かを述べる必要はないであろう。