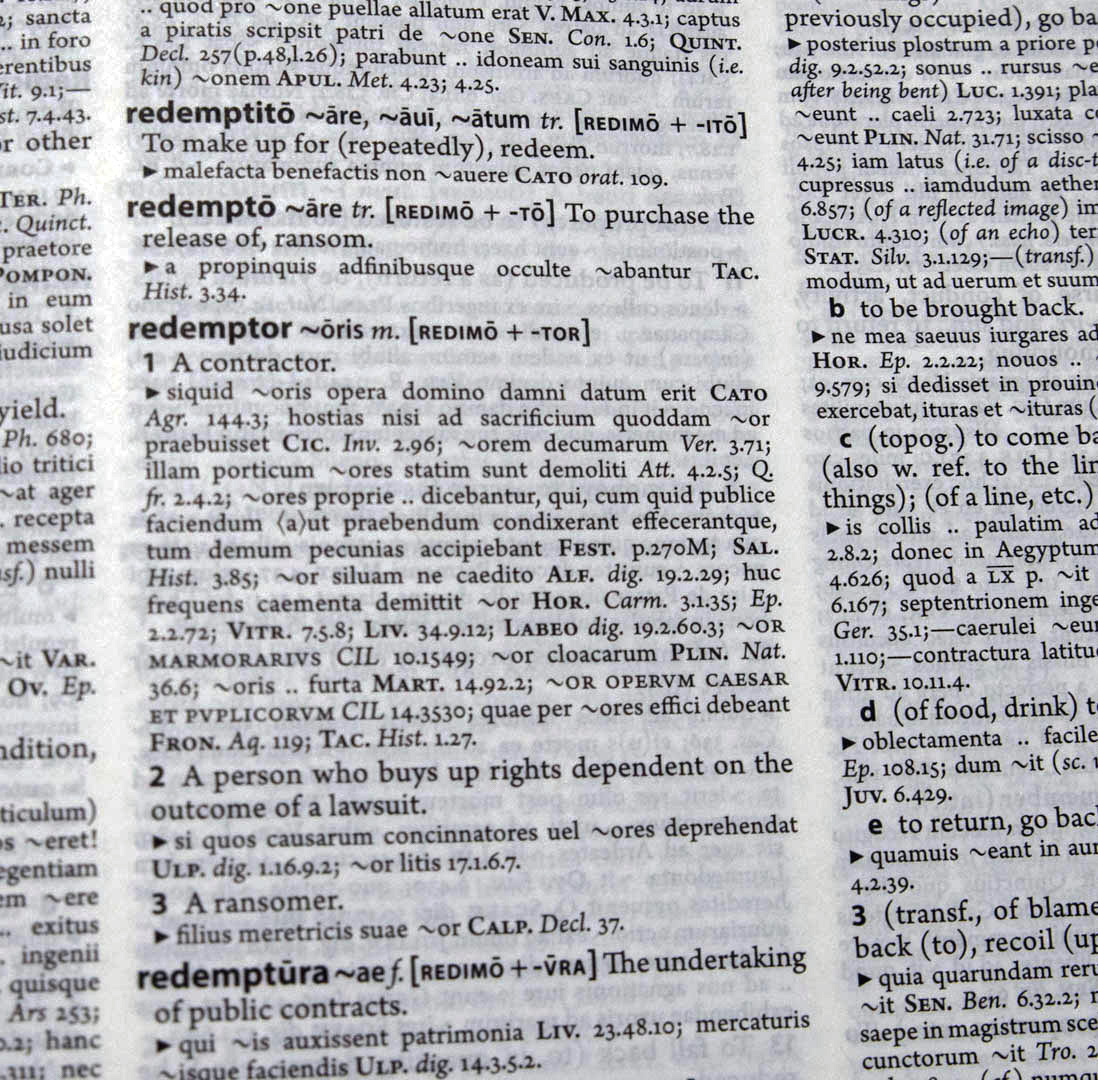「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第66回目です。ここでも次第に農奴的な存在になっていって奴隷と同じく、土地の売却の際には土地と一緒に売却されるようになっていくコローヌスの姿が分析されます。残り12ページになりました。
==================
しかし事実上はローマ帝国全体に荘園制度網が張り巡らされたのであり、その状況において諸ムニキピウムは産業的な生活や、資本形成という欠くべからざる中心点を自分の中に置くことなく、また市場という不可欠なものにもなることもなく、結局のところは国家の税収管理においての単なる税金吸い取り装置という状態に留まったのである。
大地主制の内部の組織
ここで我々は占有の内部の状況についてそれを観察する必要がある。占有者達は自分の地所を、それについては既に見て来たが、次のように管理していた。つまりムニキピウムの官吏を真似してその土地領域に管理人を置いて管理させたのである。管理人[villicus]は確かに帝政期においてもなお、大地主制においての業務遂行者であるのを見て取ることが出来るが 95)、しかしながらその者と並んでそして事実上はその地位を置き換えているように見える者として、”actor”[代理人]が登場して来ており 96)、それはムニキピウムの同名の役職に相当しており、既にその名前にほのめかされているように、その者は官庁の業務について、準国家的な行政管理業務を委託されていたのであり、それは文献史料にも示されている 97)。
95) C.I.L., V, 878.7739; X,1561.1746.4917。
96) C.I.L., V, 90.5005.1939; VIII, 8209; XII, 2250。
97) この後に引用する箇所を参照せよ。コルメラの 1, 7では actor は familia [一族郎党]に並記されている。
Villicus の場合と同様に actor は通常奴隷であった。管理規模の大きい農園においては actor の上位または actor の代わりに procurator [上級管理人]が置かれ 98)、それは皇帝に所属する官吏の名称を借用したのであるが、その者は解放奴隷であった。
98) 私人である Prokurator については C.I.L., V, 4241.4347; VIII, 2891.2922.8993。皇帝の官吏である Prokurator については例えば X, 1740.6093。
こうした上級の管理人は一般的な管理業務は免除されており、また人員や資産のリストを作成することになっており、その者達は国家のまたは皇帝の管理担当の官吏と全く同等に扱われた 99);現金の出納業務については規模の大きい、特に皇帝領の土地においては、dispensator [管財人]100) がその者達を支援したが、その管財人も多くの場合は奴隷であり、財産目録の作成においては fabularius [会計士]がその者達を支援していた 101)。
99) C.I.L., X, 3910:ある者で、元々公的な官吏であった者がある(もちろん非常に重要な)私人の “praefectus”[任命された者]になったのである。このことは明らかに次のケースと同じである。つまり[ヴェーバー当時の]今日ある者が国の官吏からある貴族の所有する森林の管理人になって登場することである。”praefectus”という表現は当時間違いなく官職としての仕事を意味していた。ウァッローの 1, 17 によれば”praefecti”[praefectusの複数形]は農場経営においての監督者であって villicus の下に置かれたが、しかしやはり奴隷であり、しかしながら一般には一夫一婦制を取っていた。”Procuratores”[ procurator の複数形]はウァッロー(3, 6)においては鳥小屋の管理人として登場し、コルメラの(9, 9)においては養蜂場の管理人として現れ、それ故に当時はまだ純粋に経済的な機能を果たす者であった。
100) C.I.L., V, 83; XIV, 2431。
101) C.I.L., VIII, 5361(私人の)、3290 (皇帝の)。
こうした農場における官吏達の干渉については度々訴訟沙汰となっており 102)、それもその理由の大部分はアフリカにおいての夫役への苦情と同じであった。コローヌスの位置付けは、特にムニキピウムによる管理外とされた個人地主によって支配されていた場合には、色々な面で不安定なものであった。
102) テオドシウス法典 I, 7, 7。そこでは有力な procuratores が拘束され受刑することになっている。同法典 1 de jurisd[ictione] 2, 1;同法典 1 de actor[ibus] 10, 4。
以前見て来たように、コローヌス達は事実上その耕作する地所に縛り付けられていたのであり、それはつまりまず第一に、その土地領域から切り離されて立ち去ることが出来るような状態にはなかったということである。それにもかかわらず、こうした自由な移動権の制限はほとんど負担になるものとしては受け取られておらず、というのもここでの自由な移動権は単なる可能性としての意味しか持っておらず、その可能性としては耕作している土地を放棄する、ということであるが、それ故に価値の高い権利としては全く受け取られていなかったのかもしれない。コローヌス達にとってはるかに重要であったのは次のことで、つまりその者達が地主の意向に逆らってまでなおその耕作地との結び付きを許されるかどうかであり、それ故に地主達にとってはコローヌス達は、通常の自由民である賃借者のように、解約の予約をしたり、あるいは賃借期間が満期になった時に賃借料を引き上げることを許された、そういう存在ではなかったのである。ある土地領域に定住している人が、猶予期間無しにその土地領域から退去させられることが可能であったということは明らかである。というのはどのゲマインデもその者を受け入れることを義務とはしていなかったからである。先ほどのコローヌス達にとってはるかに重要であったことが実務的に意味していたのはつまり:地主が農民をその土地に「配置」し、そして日雇い労働者についてはその扱いを改めるなどしてその土地区画を取り上げ他の者に与えることが出来たかどうか、ということである。明らかなのは、地主が[その従属下の]誰かが死んで相続が行われる時に、そのやり方に干渉し、かつ土地の引継ぎについて取り決めることが、ほとんど随意に行うことが出来るものであった、ということである。その他第3章で我々は次のことを見て来た。つまり土地改革法[lex agraria]はアフリカの国有地の賃借人あるいは 1/10 税の義務のある占有者に対して、lex censoria によって賃借料他を値上げすることを禁止することに利害関心を持っていた、ということである。leges censoriae には渥取行為に基づく国有地の賃貸借契約において、確かに同様に大規模賃借人が小規模[2次]賃借人 に要求出来る賃料の上限を定めた条項が含まれており、このことは皇帝領の賃貸しの場合にも同様であったし、更にまた同様にコローヌスから土地を奪うことについての許可についても、それに関する規定が含まれていたのである。そのようにコンスタンティヌス帝のシチリア、サルディーニャ、そしてコルシカの国有地の管理についての指示を規定しているので(テオドシウス法典、[de] comm[uni] div[idunde] 2, 25)、その結果として土地を分割する際には家父長達と永代借地契約者達は奴隷達の血縁者 [agnatio]を一緒のままで居られるようにし、恣意的にその者達を分割することが禁じられた。こういった純粋に訓令的でかつ奴隷に関しての規定からトリボニアンは良く知られた “coloni adscripticae condicionis”[ケンススに登録された身分としてのコローヌス、実際にはコローヌスではないのにケンスス上でそう扱われた者を含む]に関しての法律(C.I.II comm[uni] div[idundo] 3, 28)を作り出し、そしてその規定は全く一般的に個人である占有者達に関連付けられた。この規定は本来は全くもって私人に関するものではなかった。より一層私人に対して関係付けられていたのは、コンスタンティヌス帝による法規であり(C.I. 2 de agric[olis], 11, 47)、その中で禁止されたのは、ある土地を売却した者がその土地のコローヌスを自分の元に引き留めて他の目的に使用することであった。そういった禁止は市民法やまた行政法に従った場合には、それ自体必要不可欠なものであったことは全く無いと思われるが、――というのは土地に従属するコローヌス達は元々その土地に対して自分の出生地として確かに縛りつけられているからであり、――もし私法と行政法の複合したものが先の禁止に相当する解釈に達し得なかった場合でも、コローヌス達は所属という観点では私法的な意味においてのその主人[地主]に属していたのである。奴隷に関する法をコローヌスに対しても適用するというまさに法律の濫用は、コローヌス達を人員として奴隷と同様に売却することを可能にしようとする試みであった。コローヌス達はその土地に本来は単に住民として所属するものであったので、このことは法学的には問題外であった。しかしその後試みられたことはコローヌスの状況について次の混同を引き起こすことであり、それはつまりある者が小さな土地区画を売却した際に、その土地区画と共にその土地を耕作していたコローヌス達についての主権と処分権をも一緒に移転させた、ということであり、その結果として事実上コローヌス達も売却可能にする、ということが試みられたのである 103)。
103) 似たような困難さは、尚≪ヴェーバー当時の≫今日我々≪プロイセン≫においても、大地主の土地領域を構成している土地を分割する際には生じている。実務的な取扱い方法はその際にぞれぞれの地方にて異なっている。
この方向を歓迎し、そしてユスティニアヌス法典 7 の前掲部がこの禁止令を更に servi rustici adscripticae condicionis [ケンススに登録された身分としての地方の農場の奴隷]に拡張適用しようとしたものであり、これが意味しているのはコローヌスと奴隷という者達は、地主の財産のケンススへの登録リスト上、特別にその[人頭税の]税率と共に記帳された、ということである。コローヌス達とこれらのコローヌスに接近したものとなった奴隷達は土地の分割売却の際にはぞれぞれの面積に応じて[pro rata]分割されて引き渡されることとなった。コローヌスの地位を奪うことの禁止は、それ以外では文献史料において明確に記載しているものはない。しかしながらただ現にある耕作地についてそれをその耕作者の土地とみなすことを許す行政上の保護が行われていたようには思われ、何故ならば地主が[購入した土地に付属している]コローヌス達を競り落とそうとする試みに対してある種の特別な手続きが許されていたからである 104)。
104) ここでは市民への裁判について述べているのではなく、「犯罪行為を立証する」[facimus comprobare]ことについて述べているのであり、そしてまた任意の判決内容を求めることが許されていたのであり、――もちろん、というのも地主の土地領域においては正規の司法当局というものは成立していなかったからであり、そしてもまた裁判を行えるかということについても疑わしいものであったに違いないからである。
そういった干渉行為はただ任意のものであったので、その結果現金による納税義務者による大土地経営においては例えば第3章で述べたことに従って≪ager stipendiariorum はローマの領土として取り扱われており、そこでは法的な訴えは起こすことが出来ず、ただ行政上の処理のみが適用可能であったということ。≫おそらくは常に許可されており、そしてもしかするとそこからそういう状況が生じて来た可能性もある。[コローヌスの家父長の]死亡の場合においては地主に対して次の可能性が与えられた。つまり相続資格のある者達について、誰を相続者にするかと指定する、ということで、それは決してその者達の中から人を削減することが可能になったのではなく、相続者以外の残った者達は結局 “inquilini” [同居人]となったのである。私人の土地領域でどの程度まで実際に「農民保護」が行われたかについて、知り得る情報は無い。その他の点では地主は一般的にコローヌスの扶養までは必要とされておらず、というのは農場主自身が、既に論じたように、自費と自己責任で生活して耕作している農場の従属者であって、種蒔きと収穫の際に労働者として使用出来る者達の扶養の方に関心があったからである。――コローヌス達の独立性の程度とその一般的な状態は非常に様々であったのであり、もしかするとそのためにある土地への植民のやり方もまた非常に様々であったかもしれない。アフリカにおいては――しかしながらまた砂漠の諸部族からの襲撃を考慮して―― die vici der plebeji [平民の住む村々]が置かれており、というのはそこでは現金による納税義務者について言っているのであるが、全ての居住者、コローヌス、手工業者、商人が住む村々がそういった納税義務者の邸宅を取り囲むようにして防御する形になっており、それを”in modum munitionum” [要塞の境界線上に]と測量人達は先に引用した箇所において描写していた。