「ローマ土地制度史」について、これまで訳出済みの部分をまとめたものです。
============================================
「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」
マックス・ヴェーバー著
2つの図付き
シュトゥットガルト、1891年、フェルディナント・エンケ出版
感謝と尊敬の意を込めて枢密参事官・教授
A. マイツェン≪1822~1910年、ドイツの農制史研究家、統計学者≫博士に献呈す。
まずは校正の時に見逃してしまった誤記を訂正させていただきたい。
P.256の14行目の「マタイによる福音書」は「ルカによる福音書」の間違いです。
この論文の校正作業は、私の軍役により中断を余儀なくされており、そのことによってまだ幾許かの誤植が残っていることを懸念しております。親愛なる読者各位におかれましては、こうした誤りについてどうかご寛恕いただければと願う次第です。
シャルロッテンブルクにて、1891年8月 司法官試補 博士 マックス・ヴェーバー
目次
緒言 … P.97
序文 P.97
ローマ史における土地制度史の問題 P.101
文献情報 P.105
Ⅰ. 土地測量人による土地の分類とローマの国土についての国法と私法上の等級との関係 … P.107
土地測量人による土地の分類 P.107
測量の技法 P.108
1.Ager scamnatus [東西に走るScamnaと呼ばれる測量線で分けられた土地区画] において P.109
2.Ager centuriatus [ケントゥリアと呼ばれる正方形で区画された土地単位] において P.109
区画の利用。植民市における土地区分けと個人への分与。 P.112
正方形の土地単位を用いた土地区分と、東西に走る線 [scamna] と南北に走る線 [strigae] による土地区分との違い。 P.116
異なった測量方法が存在する理由。Ager scamnatusにおける課税の可能性。 P.122
scamna による区画分けの利用 P.123
植民市における課税可能な土地の測量 P.127
Ager quaestorius [財務官{クワエストル}が収入を得るために売却する公有地] における測量方法とその法的な性格 P.129
Ager per extremitatem mensura comprehensus [領域の外周部のみが測量され、その内部が区分けされていない土地] について P.136
属州における課税法規との関係 P.139
Ⅱ. ローマにおいての非課税の土地の法的かつ経済的な意味 … P.141
1.土地区分けの行政法的な作用について P.141
イタリアにおける植民の一般的性格 P.141
ローマ人による植民市開拓の特性 P.145
領土の行政法上の意味 P.147
土地区分けの領土管理上の効果 P.147
Forma[測量地図]の意味。プラエフェクトゥラ P.149
Fundi redditi, concessi, excepti [返還された土地、許可された土地、例外扱いされた土地] について P.151
区分けがされていない領土の法的な位置付け P.152
公有地化されていない土地について P.153
植民市における法制定の状況 P.154
2.免税農民の私法上及び経済上の性質 P.157
免税農民の特権 P.157
ケンスス [財産・人口調査、現代で言う国勢調査の走り] の対象となる可能性 P.157
Per aes et libram [奴隷解放の儀式。奴隷の対価として天秤量りに銅または青銅の小片を載せていく行為。] の業務 P.158
合法的売却 [mantzipation] と遺言の経済的意味 P.158
対物訴訟 P.160
土地測量についての議論となっている区分け P.161
土地の面積と場所についての議論 P.162
土地の面積についての議論の法的な性質 P.163
土地の場所についての議論との関係 P.166
Modus agri の元々の意味。Modus Agri の売却。 P.168
分割売却と区画売却 P.170
ローマにおける土地単位についての基本法 P.171
Usukapion [実質的な土地占有者の時効による所有権取得] の土地制度史上の意味 P.174
所有財産保護の土地制度史上の意味 P.177
土地単位についての基本法に対する決定的な違反 P.184
ローマにおける不動産取引 P.187
ローマにおける不動産信用 P.188
Ager privatus [私有地] の現物抵当と地役権との関係 P.190
Ager privatus の法的取り扱いの経済的原理 P.193
土地の併合と分割 P.194
植民市法 [ius coloniae] の土地制度上の意味 P.197
ローマとその時代における土地制度上の土地の転用 P.201
Ⅲ. 公有かつ課税の土地とそれに従属する権利の所有について … P.207
Ager publics [公有地] の性格 P.207
地方共同体 [ゲマインデ] の共有牧草地 [Gemeindeweide] 。Ager compascuus [隣人間での共有牧草地] 。 P.208
占有の期限。Mark [市の公有地] とAllmende [市の共有地] P.212
土地資本主義 P.216
占有とAger compascuus [隣人間での共有牧草地] の終焉 P.218
その他の公有の形態 P.220
ケンススの場所選定 P.221
ケンススの場所選定の経済上の帰結 P.224
公有地の小作人、大規模な小作人 P.226
公有地についての無期限の所有、個人の職務遂行に対抗する土地証券。
1.Viasii vicani [重要な道路沿いの土地。占有者は永続的に所有し譲渡不可。その代りに道路の維持義務を負う。] P.228
2.Navicularii [船主に対して、穀物をローマに供給する代償として土地が与えられた] と穀物供給の約束を前提とした前線の土地の供与 P.231
3.城主の領地と辺境の領地 P.232
地代の支払いを条件とした無期限の譲渡
1.名目地代。Trientabula [公的債務の返済の内1/3が土地で支払われるもの] P.233
グラックス [兄弟] の改革による土地分配 P.235
2.実質地代。永代借地。 P.235
トーリア法による所有 P.235
アフリカにおけるAger privatus vectigalisque [私有地と課税公地の両方の性格を持つ土地] P.236
Ager privatus vectigalisqueにおける、vectigal [課税] の性質 P.238
相続税が課せられる長期の小作契約 P.239
測量の方式 P.242
後代における譲渡可能となった永代小作権 P.244
Vectigalisの地租への変化 P.246
国有地所有の法的な性格 P.249
行政上の手続き P.250
現物に対する強制執行 P.250
自治都市におけるvectigalis P.252
地方共同体 [ゲマインデ] の法と財産 P.252
土地貸しによる地代の徴収 P.254
Ager vectigalis の法的性格 P.259
永代小作契約 [Emphyteuse] P.259
国有地ではない属州の土地 P.260
シチリアにおける十分の一税 P.260
法的な特性 P.261
小アジアにおける十分の一税 P.264
アフリカにおける stipendarii [固定割合の貢物付きの土地] P.265
税制上の地方の自治体 [ゲマインデ] の自治の後代においての運命 P.270
ウルピヌスの時代における土地の売却 P.272
ディオクレティアヌスによる土地税制の整備 P.274
ユガティオ [土地税] とカピタティオ [人頭税] と属州における課税 P.279
地方共同体 [ゲマインデ] における課税自治権の剥奪 P.282
土地税の統一 P.286
エピボレー [Επιβολή、3世紀末から行われた不耕地に対しての耕作強制] と peraequatio [税の等額負担] P.287
ユガティオ以外の特別税 P.289
物納税。Adaeratio [物納を金納に変えること] P.289
動産への課税 P.292
土地に関する法律の統一 P.292
Ⅳ. ローマの農業と帝政期の大地主制 … P.297
農業経営の方式の発展 P.297
穀物栽培の運命。オリーブと [ワイン用] ブドウの栽培。 P.302
牧草栽培、広大な牧草地の経営と villaticae pastiones [放牧農場、コルネラの著作に出て来る用語] P.304
大農場と小規模農場 P.307
共和制期の農民 [coloni] P.308
分割小作の生存条件 P.311
農民 P.312
帝政期初期における農業危機 P.318
続き。労役義務を負った農民 [小作人] を使った農場経営の発展 P.320
大地主制についての法整備の状況 P.326
Fundi excepti [非課税の土地] P.326
Stipendarii [固定割合の貢物付きの土地] 。公有地の小作人。 P.327
土地区画での居住者に対する法整備の状況 P.328
出生と行政上の本国送還 P.330
地主である農民と自由農民 P.334
類似の状況。城砦。非ローマ人の定住。 P.334
土地所有についての法整備の状況 P.335
地主における内部組織 P.341
農業従事者の運命 P.345
結論 P.352
付記 Arausioの銘文 . C.I.L [Corpus Inscriptionum Latinarum、ラテン碑文集成] , XII, 1244 P.353
文献表 P.357
図Ⅰ:Arausioの耕作地図の断片(C.I.L.XII. 1244とその追加分) P.360
図Ⅱ:Hyginによるager vectigalisの測量(de lim.const.P.204) P.361
緒言
序文
以下の研究においては、人がその表題から期待するような内容を完璧に行うことは、まったくもって約束出来ない。この研究はローマの国法と私法に関する様々な諸事実をある見地、即ちそれらが様々な土地制度の発達を促したという実質的な意義という見地から取上げる。
最初の章では次のことを試みている。つまり、ローマでの耕地に対する様々な測量方法とそれらの耕地自体との相互関係を明らかにすることと、そしてその耕地の国法および私法においての価値評価方法と、更にはその価値評価方法が持っていた実際的な意義を解明することである。そこではまた、次のことも試みている。つまり、後代の諸事象からの帰納的推論によって、ローマにおける土地制度の発展の出発点についての見解をまとめることである。その際に私は次のことについては自覚しているつもりである。つまり、この最初の章の記述において、[事実を淡々と追いかけていくのではなく]本質的にはひたすら何らかの仮説や理論を[強引に]作り出そうとしているだけではないかという非難を受ける可能性が高いということである。だからといって、この領域においての仮説・理論構築的なアプローチが無駄であるなどとは、この時代の文献史料の状態[不足している、断片しか残っていない] ≪ローマ法はオリジナルの十二表法等はほぼ失われており、同時代の法学書に引用されたものなどから一部が復元されている。そのもっとも大がかりなものがユスティニアヌス帝の学説彙纂であるが、その編纂において当時の編集者が元の条文を恣意的にいじったのではないかという疑いがあり、特にヴェーバーの時代にその見直しが行われていた。≫ を知っている者は誰もそうは言わないであろう。そしてまさに土地制度史の領域においては、次のような場合が存在するのである。つまり、「事物の本性」≪ドイツ語で Natur der Sache、ラテン語で De rerum natura、ルクレティウスの同名の詩参照。ここでは法律が存在しない場合に判断基準となる社会通念や公序良俗概念のこと≫ からいくつかの結論を得て先へ進み、他の領域におけるよりも相対的に見てより確からしさを高めることが出来た、そういう場合である。土地所有ゲマインシャフトの諸組織は、いくつかの条件が満たされている場合には、まさに限定された種類のものが存在していた可能性を確認出来る。ここでは純粋に実験的な研究を、次のテーマについて行うということが課題であった。そのテーマとは、ローマの土地制度の本質のある一面として、何千年紀の間の時間の中瓦礫に埋もれながらなお何とか我々に把握出来る状態にある史料類[文献史料、碑文類]を、すべての土地制度史家におなじみの概念に沿う形で評価しようとする場合と、その本質として他のインドゲルマンの土地制度に関しての法形成を促進する根本原理となっている場合において、その根本原理が[他の社会制度との]調和をもたらしているのか、それとも何も影響を与えていないのか、あるいはまったく逆に不協和をもたらしているのか、そういうことを研究するということが課題であった。――そして私としては、調和をもたらしたというのが正解であるという印象を得たのである。まず始めに、次の証明が試みられる。つまりローマの土地の土地測量上の取り扱いが、一般的に言ってある一面では当該の領土の公法における取り扱いと、また別の面では地所の私法における取り扱いとが、それぞれ密接に関連しているということについての証明である。その際にどの程度まで個々の事例においてそういった取り扱いの仕方の証明に成功したかということについては、私はあまり自信が無い。しかしながら次のような場合には成果を上げたと言えるであろう。つまりある何かと別の何かの関連性が一般論として存在している場合に、それを発見出来たという証明を――私はそう信じたいが――、きちんと行うことが出来た場合である。そうした証明について同意していただける方は、私はそう願いたいのであるが、さらにまた色とりどりの花をまとめた花束のような様々な仮説と、その花束というのはこの公法・私法と土地制度の関係性という点でこの論文の叙述の中にちりばめられているのであるが、そして更には数多い、場合によっては必ずしも目に見えるようなはっきりとした形では把握出来ない観察事項をも、一般的な形で余録として受け取ることも出来るであろう。あるいは逆に寛大な心で次のように判定してもらえるであろう:二つの歴史現象 [公法・私法と土地制度] が単純な抽象的な記述ではなく、それ自身として閉じているまとまった見解として、どのようにしてこういう関係が具体的に形作られたのか、そういう見解として述べられると。
私がこの論文の最初の3章の幾重にも仮説・理論構築的な性格を多少なりとも正当化することを試みているとしたら、その場合でも最終章 [第4章] については、その章はローマの農業についての経済史的な観察を行っており、またサヴィニー≪Friedrich Carl von Savigny、1779~1861年、ドイツのローマ法学者、ドイツに入ってきたナポレオン法典を排除するかどうかの法典論争をティボーと行ったことで有名。またローマ法に基づくパンデクテン法学を発展させた。≫以来未だに論争の収束する気配の無いコローヌス [共和制末期から現われたローマの小作人] がどう発展して来たか詳しく論じているのであるが、その章については1~3章に見られるような仮説-理論構成的な動機から書かれた部分は少ないのである。というのも、周知の通りこのローマの農業という領域では、ロードベルトゥス ≪Johann Karl Rodbertus-Jagetzow、1805~1875年、ドイツの経済学者で剰余価値の研究でマルクスに影響を与えた。≫ 以来、あらかじめ設定された何らかの思考的枠組みから導かれた[=アプリオリな]国民経済学における様々な仮説が、非常に多くの方面においての成果物を噴出させて来たのであり、あの偉大な思想家 [ロードベルトゥスまたはマルクス?] の模倣者達が、その者達の止まる所を知らない想像力が、非常に重大な誤りを含んでいる場合でも、本能によってすぐれて実用的な観察結果によって構成された確かな大地に拠って立つことが出来たのであるが、ここにおいて一般的な国民経済的な観察において、余りにも沢山の良き成果が勝ち取られて来たのである。 ≪唯物論や発展段階説、国家有機体説のような枠組みから短絡的に多く歴史的諸事実を簡単に処理して法則化しているようなやり方を皮肉っていると思われる。≫ それらの研究では、私が思うには、特に国法的・行政法的な視点について、十分ではないと言え一応は入手出来る文献史料を用いてその [仮説・理論の] 裏付けを取るということが、行われていないのである。更には仮説そのものがこの研究では不可欠であるということも自明である。何故ならば、相対的に見てより確からしさが高いと思われる成果であっても、この研究では厳密性へのこだわりという意味でまだ仮説の域に留めざるを得ないからである。もし例えば中世の法制史・経済史の問題を取り扱う場合に、人は一体何をもって研究の成果とみなすことが出来るのであろうか?≪まさしく中世の法制史・経済史の問題を取り扱った「中世合名・合資会社成立史」の結論部で、ヴェーバーはその研究の法教義学的な意義について「このような考察についてそのような意義をある程度はっきりした形で切り出すことは出来ない」と記している。≫そしてそういった成果とは次第に文明化して行く地球において、次第に拡大して行く500年もの間にも及ぶ遠大な発展の図式を、文献史料や著述家達の残したものの中から取りだした、ほんの数十箇所の部分的に曖昧さを持った箇所から得られたものに過ぎないのであるが。確からしさという概念は、まさに相対的なものなのであり、歴史的な研究というものは、その成果の到達範囲の限界をわきまえなければならないのである。
さらにまた、ローマ帝政期については、個々の諸事実から得られる一般的な経済史上の結論というものは、経済の領域においての広がりとして見えてくるような、そんな巨大さを持ったものではあり得ないのである。というのもこの経済領域というものは、その発展段階において、それぞれの部分が非常に異なって見えていながらも、同時に相当高いレベルで統一性を保っているからである。例えばイタリアの辺境領域に対しての関係が、植民の動向という点で、ある大都市の都心部の郊外の町に対しての関係と似通っているとするならば、その場合また部分的にはそれと対立するような現象が現われてくるのが通常である。そのため、私の考え方では、科学的に正確に述べようとするならば、次のようになる:都心において既に支配的になっている市壁の外の町への発展の傾向が、[ここでは]まだはっきりと現われて来ていない。何故ならばその傾向は根本的に対立するような別の諸傾向によって相殺されているからであると。発展法則というものは一般的に言って次のような意味で確かなものとすることが出来る。つまりその種の「法則」というものが、様々な傾向として描写出来るのであり、そういった諸傾向はその場所においてより強く作用するもの同士として相互作用を及ぼし合うという可能性がある、という意味での確実性の向上である。以上のことから、私には次のことは方法論として正当であると思われる。つまり、ローマ帝国で高度に発展した属州でのある土地制度の発展において、現象についてひとまず深く細部を調査していくことを保留し、そしてその理由から当面は例えばユンク ≪Julius Jung、1851~1910年、オーストリアの古代史家。≫ によって何度も利用された文献類、それは教父神学やそれに似た事項について地方における社会状態の[代表的な]文献史料となっているが、そういうものをあまり重視しないという、そういう方法論である。
長年に渡って伝承として伝えられてきた文献引用については、私は可能な限りそれらについて最小限の準拠に留めるようにした。そして文献史料については、それが不可避である場合を除き、――それは容易に判別出来るであろうが――、その文献史料の外延的な拡がりという観点で、その史料のどの部分をどのように先行の諸研究が利用したのかということについては述べるつもりは無い。そして私はここで設定された問題についてより詳しく調べたいと思う方のために、この論文の最後にまったく完全なものではないが、研究論文目録を付け加えておいた。
専門家に対しては特に改めて断ることではないが、研究方法について、以下に続く論文ではただ確固たる理論的な土台の上で議論しているか、あるいはしようと努めている。その理論的な土台とは、まず何を差し置いても、モムゼンがローマの全時代の国法・行政法の研究について確立したものである。しかし私は一方で、以下のことを告白するという喜ばしい義務を負っている。それはつまり、私の尊敬する先生である枢密参事官のマイツェン博士・教授から、個人的にご厚誼をいただくようになって以来ご教示いただいたことによって、古代ローマ時代の土地制度の研究を行う上で、理解を深めるための多数の実際的な研究上の見地が私に利用可能になったということである。我々がここで扱う歴史的素材の状況について次のことは確かである。つまり古代に関しての土地制度・植民史を直ちに師の偉大な著作 ≪1895年の「西・東ゲルマン、ケルト、ローマ、フィン、スラブ諸民族の集落と農業事情」のこと、全集の注釈による≫と肩を並べるレベルで書くことは不可能であるということである。――しかしそうは言っても私は次のことは試みている。つまり我々にローマの土地法として立ち現われている現象の観察において、その法の実際的な意義を見極めるために、その法の利害関係者を調査するということである。その手法の意義の評価については私は到底マイツェン先生のレベルには到底及ばないし、またそれについて詳しく学ぶ機会も持てていない。
以下の論文では、歴史上の素材を歴史の中での連続性を保持したままのものとして叙述するということは出来なかった。何故なら、ほとんど常に結果から原因を推し量るという帰納的推論を用いなければならなかったし、それ故に歴史的な流れでの中では先行する状態について、我々に伝えられている後の時代の状態から遡って推論するしかなかったからである。色々な形で次のことも度々必要となった。つまり統一性を持った歴史上の諸現象について、様々に異なった個別の側面からその本質に近付くと言うことが。そのことによってまた、何度も同じようなことを繰り返し述べているという印象も避け難くなった。
我々はまずはローマ史のいくつかの問題について、手短かに描写することを試みる。その問題への解答には土地制度史が、若干ではあるが貢献するし、また適当であると見なすことが出来る。
ローマ史においての土地制度史上の諸問題
古代の確かな情報、つまり我々がローマ史として知っていることにおいて、ローマの都市が海外の領地と、また明らかに海事政策において、それぞれと深く関わっていることが示されている一方で、その後の時代になると我々の眼前にて、ローマの大陸への侵略という暴力劇の上演が開始される。その侵略とはローマの都市の政治的な優勢状態を拡大するということを意味するだけでなく、また同時に絶え間ないローマの植民の拡張と、ローマに征服された地域での資本家による搾取をも意味していた。その一方でローマの海上支配の優勢はこういった拡張と少なくとも同一の歩調を取っていた訳ではなかった。ここにおいて次の疑問が生じる:誰がこれらの侵略戦争を主導したのか?――それは次のことについての疑問ではない:どこからこれらの軍事力が出てきているのか?もちろんこの問いについても詳論に値するが、というのはもしローマの大帝国がゲルマン民族の大移動に対して、それより600年前のイタリアがケルト人[ガリア人]に対してそう出来たように、同様の軍事力を使うことが出来たとしたら、そうであったら結果はほぼ同等のものであったろう、――そういう疑問ではなくて:どのような社会の諸階層と経済上の利害関係者集団が政治的な意味で [侵略戦争の] 推進力を作り出したのか、そしてまた: [ローマ史において] 叙述されているローマの政治における明らかな重心の移動がどのような諸傾向を作り出したのか、ということについて、その重心の移動というものは主として特定の利害関係者集団の努力によって意識的に作り出されたものかどうか、という疑問である。
我々が更に次のことも見て取る。 [オプティマス{元老院派}とポプラレス{民衆派}の間の] 党派抗争の時代に、戦いにおいての本来の戦利品、つまり勝者が得るものとして、公有地、つまり ager publicus という土地制度が作り出されたのである。実際のところそれまで大国において政治的支配というものが、そこまで直接的に貨幣価値に結び付けられた例は存在しなかった。既に古代においてそういう風になっていたということは、確かに非常に高いレベルで独自の位置を占めていた。その位置においては、 ager publicus を経済的・法的な考慮の結果として受容しているのであるが、その場合さらに次の疑問が生じる。つまりどのような基本的な考え方がこういった位置付けを発生させたか、ということである。ある公的な権力の、法的に見て非常に不安定な公地への居住に対しての激しい対立があり、その居住への法的な保護はただその土地への権利侵害の場合にのみ行われていたが、その権利侵害は我々の概念では、懲罰の対象となる犯罪と見なされるべきものである。更にはそれは地所についての私有権の侵害でもあり、その私有権は所有者に基づく自由な処分と、それによる [例えば売却という] 極端な帰結への最大限の可能性という個人主義的な動機を産み出していたが、そういった公的権力と公地への居住は、その外見において、意図的な行為と近代主義的思考の様相を身にまとっていた。――その場合次の疑問が出て来る:こういった所有権の概念に関わる土地制度の領域において、どのような経済上の考え方がそれに適合していたのか、という疑問である。その考え方は今日でも我々の法的な思考を支配しており、ある者はその論理的帰結の故にそれに賛嘆しているし、また他の者 [例えばマルクス主義者] はそれを諸悪の根源として我々の土地所有権の領域において非難しているのである。
さて、周知のように、ローマの支配の拡大が常にローマの経済圏の拡大を伴っている場合、その場合はまさしく次のように言うことが出来る:それはつまりローマの農地の拡大であり、その結果この農地は結局のところはイタリアにとっての数多い戦利品を分配する中の一部であり、その場合さらに次の問いが出て来る:どのようなやり方でこのような広大な土地が割当てられたのであろうかと?周知のように、この土地配分は少なくとも部分的には植民のために利用されていたし、また同時にそういった植民というものは、ローマの支配を固定化するためのこの上ないほど効果的な手段であったし、そして多数の否定的に捉えられてきている諸政策、例えば穀物の収奪だとか債務免除など以外で、唯一の肯定的に捉えうる大規模な社会政策であり、それによってローマの国家は、その社会全体が激しく痙攣を起こすような病気にかかることを回避することが出来たのである。昔からデマを撒き散らす扇動家達によって主張されていた危険な大衆からの人気取りの手段が、Ager publics [公有地]への植民という形で実現し、その規模はグラックス兄弟が決めたのであるが、それは結局のところ全ての、確かに法的には不安定ではあったが、しかし実際には深く根を下ろしていた[土地の]所有状況を根本からひっくり返すことになったのである。ある土地制度の根本的な改革策としてU.C.643年 [ローマ市建設以来の通算年、=B.C.111年] に公有地分配法[lex agraria]が制定され、それによってローマの土地制度に空いた大穴を、最低限イタリアとアフリカ及びコリントの属州地において何とか塞ごうと試みたのであるが、同時にその法は私有財産においての、不安定でかつ新しく作り出されていた所有状況を変えてしまったのであり、またそれより下位にある諸権利の所有における権利関係を修復することにより、さらにまた最終的には公有地の不安定な所有状態が発生することになった古い制度を廃止することにより、要するにイタリアにおいてある種の物権に関する新しい法を制定することにより、安定状態を創り出そうとしたのである。ただ始まりかけていた専制政治といくつかの内乱と、特にスッラに関連する複数の内乱と三頭政治の下において、強権による差し押さえ、買い占め、そして連戦連勝の軍隊への土地の再配分を通じて、所有地に関する全ての所有関係についての新たな革命が起きたのである。そしてそれらは結局のところ、共和国の最後の数世紀において、植民地の土地の再配分を引き起こしたのであり、それは量的な規模について言えば、それに匹敵するのはただ後代の民族大移動だけであるというレベルのものであった。ここにおいて次の疑問が生じて来る。経済的・法的に見た場合、これらの植民はどのような形で実現したのであろうかと。
次にイタリアにおける公地の吸収の結果――一部は譲渡によりまた他の一部は個々の地方都市への委託によって――そういった土地の吸収によって得られた利益というものは、帝政の始まる頃には既にすっかり枯渇してしまっていた。そういう状態の後では、帝国の財政力の点では、属州から上がってくる税金収入がもっとも重要なものとなっており、そういった属州では、古代においては常にそうであったように、様々な形で行われた所有地の譲渡がもっとも重要であった。この時代になるとローマ人が属州に対して課税した方法についてもまた疑う余地が無いほど多様であったが、それはただその当該の土地においてのその前の時代の課税政策がそのまま引き継がれたのであるが、そうはいってもともかく非常に多種多様であった。そこで次の疑問が出て来る:土地の併合においての権利関係の改革は、その現地で行われたのでなかったら、どこでより強力に推進されたのであろうか?どこで行政の実地においての、確実に存在しまたそれぞれの地域に等しく見られるような諸傾向が確認出来るのか?そしてもし属州の土地についての取り扱いがイタリア半島において既に利用されていたやり方と関連していないことが確認出来るとしたらどうなるのか?
結局のところ、次のことは何を置いてもまず調べてみる価値がある。つまりローマの大土地所有者の農場経営が、その所有地についてのローマ特有の法的・社会的状況の下においてどのように形作られて来たのかということと、その後の数世紀の時の流れの中でその農場経営がどのように変化していったかを調べてみることである。その調査では特に大規模農場経営の発生とその体制に注目し、さらに帝政期においては疑う余地も無く何よりもその諸々の経済的な背景について理解しようと試みる:その背景とはつまりコローヌス [永久小作地] における、その耕作地に縛り付けられた隷属的な農民のことである。このしばしば論じられて来た権利関係は特に次の理由から読者に不審の念を抱かせるのであり、さらに包括的に詳しく論じることも必要となって来る。その理由とは、多くの者がそういった権利関係をローマの私法の形態と関連付けて説明しようとし、そしてことごとく失敗して来たからである。この研究においては、隷属的な農民の発生の諸々の経済的背景についての研究以外に、よりむしろ次のことが問われなければならない。つまりそういった権利関係がローマ帝国の行政法において、一般的公法としてどのような位置を占めることになるのかということである。というのもそれについては次のような疑問が生じ得るからである。つまり私法と契約の自由という原則に従う限り、そのような [コローヌスという] 制度は本来成立し得なかったのではないかという疑問である。さらにはその制度とローマの帝政期における大規模土地所有者の意義についての問題は、その大規模土地所有というものはその後拡大し中世の初期にまで連綿とつながっているのであるが、不可分な程に密接に関連しているのである。
この土地制度史は、次のことを敢えて行うつもりは無い。それは先に厳密に規定した諸問題についてそれなりに解答出来るようにすることであり、それは先行研究の状態から見て更なる解明に期待する需要というものが存在する場合に限ってのことであるが、そうではなくてこの土地制度史の研究はただ次のことを確認している。つまりその研究において利用出来る諸々の概念と実用的な観察上の見地に基づいて、土地制度史というものがそれ自体としてどういった位置を占めているかということである。
この後に続く詳論については、次のような幻想を期待されてもそれにはまったくもって貢献出来ない。つまり前述の諸問題に対して何らかのこれまで予想もされなかった新しい光を投げかけるということや、あるいはこの問題の専門家に対して本質的に新しいことを伝えることが出来るということであるが、――その種の様々な成果というものは、文献史料が豊富に利用出来ることによってのみ期待出来るであろうが、そうではなくてただ入手可能な史料に基づいて上述した諸問題に答えを与えんとする限りにおいては、そういう答えというものはそうした史料の本質的な並びの中で、既に答えが[ほとんど]確定してしまっているからである。しかしながら発展をもたらした多くの契機のそれぞれについて、どれが重要でどれが重要でないかについては、現時点ではまだ争う余地が残っているであろうし、そしてそれ自体が良く知られている諸現象と、それらを実際的な土地政策的・経済的意義から見た観察と組み合わせることにより、私はそう考えるが、さらに新たな観点を勝ち取ることが出来るであろうし、それは私の見解では詳論に値する。
文献史料
以上挙げて来たような出発点から始まる研究のために、文献史料という点では、それほど重要ではない歴史家によるいくつかの注釈と、そうは言っても特別な碑文として残されている史料の解明という点で見た場合には、結局の所、我々が自由に参照出来るものは、ラハマン≪Karl Konrad Friedrich Wilhelm Lachmann、1793~1851年、ドイツの文献学者・神学者≫の”Schriften der römischen Feldmesser”[ローマの土地測量についての文献集]という名前で[1848~1852年に]出版された文献集である。その中身としては、一部は土地測量を実地に行っていた人によって書かれた土地測量の技法についてのガイドブックであり、また別の一部は幾何学について書かれたものの抜粋であり、また法律の断片であり、更には”libri coloniarum” [植民地の文献] という名前で知られているイタリアにおいて分割された土地に対しての、現存している[法的]様式の目録であり、そしてさらにまた研究の経済的側面にとって特に[有用なのは]、”scriptores rei rusticae” [農業に関する諸著作] ≪大カトーの「農業論」、コルメッラの「農耕について」などだと思われる≫であり、それはつまり農場経営の初心者向けの便覧であり、その著者の内例えば大カトー≪Marcus Porcius Cato、BC234~BC149年、ローマの政治家、曾孫のカトーとの区別のため通常大カトーと呼ばれる。≫について見れば、明らかに多くの箇所で確認出来るように、この土地制度という領域で手当たり次第に一種のディレッタント的な知識を寄せ集めたようなものでは無かった。今言及した2つの文献史料集成≪”libri coloniarum”と “scriptores rei rusticae”≫においては、その明らかに非常に有用な中身が、それを学術的に利用するにあたって、伝承としてのみ現在に伝えられそれが故にいつの時代の話なのかがはっきりしない文献素材という性格によって、その[史料的]価値が損なわれてしまっている。従ってそれを利用するに当たり、度々その信頼性の確認が必要である場合には、まずは著作者達の言明を具体的にはいつの時代を指しているのかを不明として分析し、それからおおよその推定の時期を、それが実際的にはまあ妥当であろうというレベルで読者に伝え、そして時期の推定に問題がある事項については、ただ「以前の時代の」あるいは「以後の時代の」という形で処理することとする。土地の測量人に関することは、次のことだけを確かなものとして扱う。それはつまり、全ての彼らの[測量]技術に関する言明は、太古の昔より伝えられている実際的な取り扱い方法に基づいている筈であると見なすことである。その理由は、その当時のローマ人が一般的に直接習い知っていた幾何学のレベルについて検討するのは全く不毛であるからである。 以下の叙述においては我々はまず土地の分割のやり方と、土地の法的な等級付けの関係を明らかにすることを試みる。その目的は、それに続けて後者について個々の事例に立ち入って調査することである。
I. 土地測量人による土地の分類とローマの国土についての国法・私法上の等級との関係
土地測量人による土地の分類
ローマの土地測量人は、周知の通り、彼ら独自の基準によって地所を次の3つの主要カテゴリーに分類していた1):
1.ager divisus et assignatus [区画に分けられ割当てられた土地]――このカテゴリーがさらに次の2つの下位カテゴリーに分けられる。
a) ager limitatus, per centurias div[isus] et assignatus [小路=limitesによってケントゥリアと呼ばれる正方形の区画に分割され割当てられた土地]、
b) ager per scamna et strigas divisus et assignatus [東西に走る線=scamnaと南北に走る線=strigaeによって区画割りされ割当てられた土地]、
2.ager per extremitatem mensura comprehensus [全面積が測量されているが区画に分けられておらず、その境界が自然物{川など}による土地]、
3.ager arcifinius, qui nulla mensura continetur [それまで敵地であったなどの理由で測量も区画割りも行われていない土地(例:ポエニ戦争終結後のカルタゴの土地)]。
1)フロンティヌス≪Sextus Julius Frontinus、c40~103年、ローマの技師・軍人・著述家。皇帝ネルウァの時にローマの水道長官に命じられ現在でも名高いローマの水道網を整備した。Frontinus 作とされる土地測量についての著作が存在する。≫、De agr. qual. p.1f.(ラハマン前掲書)参照。
次のことは特に吟味しなくても当然のことと見なして良いであろう。つまりこれらの異なった土地の区画割りの方法を利用するということは、何がしかの形でまた当該の領域の法的な規定に適合していた、ということである。だがしかしどのような形で?――それについて確実に述べることが出来るのはごくわずかな部分のみであり、その他のほとんどの部分については、[いくつかの事例からの]帰納法による仮説を提示出来るのみである。それにも係わらず、次のことは考慮に入れなければならない。つまりここではまた、全く疑いようの無い法的原理が、その適用においては例外を伴っていたものの形成されているということであり、ただ場合によっては非常に多くの例外が伴っていたこともあり、その結果として言えるのは、その法的原理はただ一時しのぎの間に合わせ的なものとして作られているということである。それは土地がこのように分類されていたという事実から、何らかの法的原理を抜き出して確立しようとする場合に、[そう判断することが結果的には]歴史的な現象の法的な把握をほとんど放棄したのと同じであろう。
もっとも簡単に評価することが出来るのは極端な事例の場合である。例えば次のことはある一面を見た場合には疑いようが無い。つまり、海外での地所、つまりローマ帝国の全ての[海外の]自治市の中で、ある種の盟約によってローマ帝国の権力の直接的な影響が少なくとも理論上は及ばないと免除されているもの[の耕地]は、すべて ager arcifinius としてのみ分類されているということである。というのもローマが比較優位の立場にある自治市相手との盟約は、例えばアスパルティア2)≪エーゲ海南部のドデカネス諸島の一つで、ローマの自治市。BC106年にローマと盟約を結んでいるが、それはヴェーバーの説明とは異なり、表面的にはまったく平等な立場でのものだった。この島がローマの対ギリシア政策の上で何らかの重要な役割を果たしていた可能性が歴史家によって指摘されている。≫との盟約が挙げられるが、その自治市の耕地についての規定はまったく含まれておらず、さらにはその自治市のそれまでの領地がそのまま保持されるという規定も含まれていなかった。そういった盟約はつまり、ある種の政治的な capitis deminutio [法による個人等の権利・地位・資格の剥奪]と解釈されていたのかもしれない。別の一面を見てみると、次の事も同様に疑いようが無い。つまり、実質的にローマの市民によって開拓されたと考えられる全ての植民地における耕地と、その他のローマの領土における耕地の分類は、全て ager divisus assignatus [分割され割当てられた土地]であるとされていたことである。しかしながら、数多い中間的な性格の耕地の分類と、個々の分類の実地における運用方法を確認することは、ローマでの耕地の分類と割当ての技術的な側面を一瞥する機会を与えてくれている。
2)Corpus Inscriptonum Graecarum, II, 1485≪全集注では正しくは2485≫、ベック≪August Boeckh、1785~1867年、ドイツの古典学者、古文献収集家。≫編を参照。
耕地測量の技術
ローマにおける土地の区画分けと、東西南北の方位に平行に定められたその境界線の双方が規則的な性格のものであった。そしてこれらの作業は原始的な十字型の照準儀≪グローマと呼ばれ、棒の片端に十字架上の棒を組み合わせ、その十字架の先端から重りを垂らした構造のもの。下記のイメージ図参照。写真はここなど。≫を使って行われた。
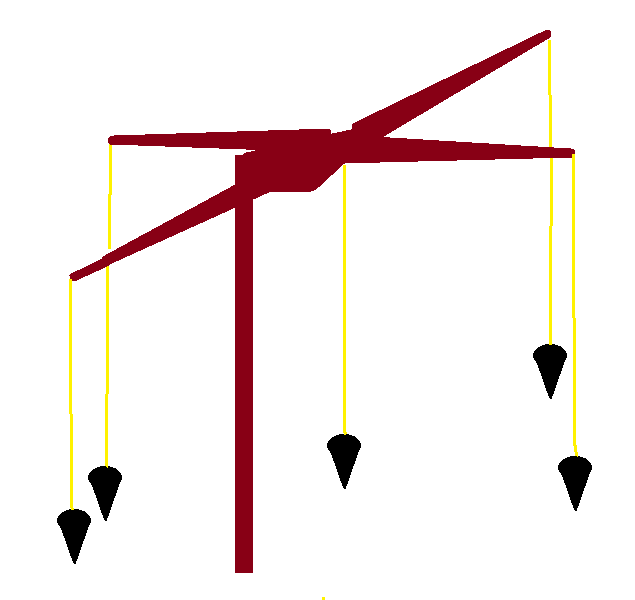
それを用いてまずは――この作業は明らかに夜間には行われなかった、視界不良で子午線を確認することが出来なかったので――日の出の方向にグローマの照準を合わせることによりおおよその3)東西の線を確定し、次に decimanus (=「分割点」)を、そしてその分割点上に垂直線を引き、更に cardo (=軸、天軸)をそれぞれ確定させ、それらを示すために杭を打った。
3)日の出の正確な方向が季節によって変動することによって、この東西線の方向もまた変動した。既にポー平原の郊外の村の測量においてもそうであった。(ヘルビヒ≪Wolfgang Helbig、1839~1915年、ドイツの考古学者≫、Die Italiker in der Poebene)。後の時代になってようやく正確に東西に平行な線が確定されるようになった。(ヒュギヌス≪Hyginus Gromaticus、1~2世紀のローマの技術書の著作家≫、De lim. const. p.170, 187)
以上のやり方が原則的な方法であったが、次のようなことも起きていた。それはその土地の周辺の地形との関係に応じて分割点の設定をその土地の形状において面積が最大になるように加減したり、または海岸においては、海に向かう方向に[基準線を]合わせるとか、あるいは場合によっては[基準線を]子午線[南北線]に合わせるといったやり方である。さらにこれら以外のやり方を見て行くにあたって、我々は土地の区画分けの方法として、strigae [南北の線]と scamna [東西の線]による[長方形の区画による]区画分けと、centurias [正方形の土地の区画単位]によるそれとを区別する。これらに共通しているのは直線による区画分けであるということであり、その違いについての記述は、当時の測量人達の著作の中で多くの箇所で行われており、さらにはその者達より後の時代の測量人達によっても言及されているが、つまりは区分けされた土地の形が正方形か長方形かという違いである。我々はこの点については、そうした相違点が唯一のものではなく、また本質的なものでもないということを見て行くことになる。
1. Ager scamnatus [東西方向が長手である長方形の土地]の場合
まず何より ager per scamna et strigas による土地の割当てに関係するのは、それの個々の場合での分割の方法は後で詳しく述べる特別な場合においてのみ知られているのであるが、その測量による結果はしかしながら、常に耕地を長方形の区画によって分割するということであり、そしてその長方形の区画の長手方向が南北の場合に strigae 、東西の場合が scamna と呼ばれていた。一箇所の耕地において、この二つの一つだけが使われている場合と、同時に使われている場合があった。しかし scamna だけを使った区画割りの方がより多かったようである4)。
4)M・ユニウス・ニプサス≪Marcus Junius Nipsus、2世紀のローマの数学者≫は、ager centuriatus と並記してただ ager scamnatus だけを挙げている。(p.293、ラハマン前掲書)
こういった区画割りの方法での一区画の面積が一定であったかどうかは不詳である。ある耕地における全ての区画が同一面積であったかについても同様に不詳である。フロンティヌス5)の著作の中の図(その年代は当然ながら不明である)を見れば区画の面積は一定ではない。
5)ラハマン前掲書、図3 [ager divisus et assignatus の中での]2つのカテゴリーの対立において、そこで ager limitatus と呼ばれている形態では、それによって[区画と区画の間にスペースを空けて]典型的な道路システムが作り出されているが、そのことは ager limitatus の説明に出て来る limites [小路]という語によって示されている。しかしそれは ager scamnatus の方については本質的な特徴ではない。
個々の strigae と scamna によって区画分けされた土地は、推論する限りでは、それからどのような手続きでかは不詳であるが個々の受領者に割当てられ、そして地図の上の境界線で囲まれた土地の上にその者の名前が書き込まれた。
2.ager centuriatus [ケントゥリア{=正方形の土地単位}によって区画分けされた土地]の場合
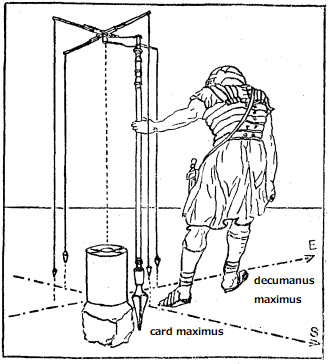
測量人達が我々に伝えている ager centuriatus においての ager per centurias divisus assignatus [小路=limites によってケントゥリア単位で区画分けされ割当てられた土地]における手続きについては、その教示する内容はより広範囲に及ぶものである。というのはこの形態の土地の区画分けと割当ては、彼らにとっては標準的なものであったのと同時に、もっとも完成度が高いものであったからである。さらにその形態は、おそらくは、シーザーと三頭政治の執政官達が広範囲の土地の割当てを行った際にには、ほとんど唯一のやり方であり、実務的に最重要なものだったからである。その区画割り作業は次のような手順に拠っていた。つまり最初に定められた2本の基準線――decumanus maximus [東西の線]と card maximus [南北の線]――にそれぞれに平行に[2本の]線が引かれ、――この decumanus maximus と card maximus を基準として[ローマにおける都市の街路システム=一種の条里制である] decumani と cardines のシステムが作り出されるのであるが――、規則的に――必須とはされていなかったが――それぞれの[4本の]線によって囲まれた正方形の区画で、それぞれの一辺の長さが20 actus [≒710.4m]であり、1 actus = 120 ローマ・フィートであり、その面積はそれ故400平方 actus [約50.5ヘクタール、15万3千坪]となった。
その区画はさらに 1 actus x 2 actus の長方形の区画= jugera [約765坪]に分けられ、つまり面積としては200 jugera となり、その面積の区画がケントゥリアと名付けられていたのである。そのケントゥリアとケントゥリアの間に decumani と cardiness という小路が様々な幅で作られていたが、そのサイズは変遷しており、しかし帝政期のイタリアでは8ローマ・フィート[≒2.37m]になっていた。
それぞれ5番目毎のcardoとdecumanusが、5番目の意味のラテン語でquintariusまたはactuariusと呼ばれ、より広い道幅――帝政期には多く12ローマ・フィート(≒3.55m)であった――の道路であった。このactuariusの道路で囲まれる25[=5 x 5]ケントゥリアの土地区画が、帝政期には技術用語ではsaltus 6)と呼ばれ、cardo maximusとdecumanus maximusで囲まれた土地区画より広い区画であった。これらのcardo maximux、decumanus maximus、そしてquintarius [複数形: quintarii] が公共の道路であり、それを個人が占有することは許されていなかった。その他のlimites [小路] は単なるlinearii、つまり幅を持たない直線であるか、あるいはsubruncivi、つまり地方道であって、その保持については公権力は関与していなかった。
6)ウァッロー≪Marcus Terentius Varro、 116 – 27BC、 共和制期ローマの学者にして政治家≫の時代には、4ケントゥリアが1 saltusとされていた。その当時においてはより広い面積のquintariiについてはまだ一般的なものとはなっていなかった。
以上述べて来たような測量のやり方は、地所が何らかの形で利用され、かつ土地配分への要求が存在した限りにおいて継続して行われていた。ある一まとまりの平地の一番外の境界線に沿って、その境界線とその平地の中でもっとも境界線に近い所にある正方形の土地単位との間の土地は、subsiciva[余剰地]と呼ばれ、他に既に使用出来るようになっている土地の面積がそこでの土地需要を十二分に満たしている場合には、そのまま使用せずに残され、ager extra clusus [正規の土地分類以外のその他の土地] の一種と分類された。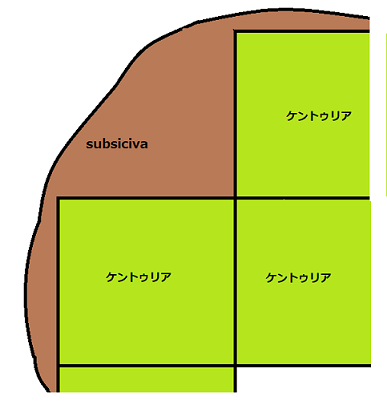 測量によって定められたケントゥリアは、次の手続きとしてその四隅に石で境界標が設置され、さらにはその土地の測量地図が作製された。その地図――forma――の上には、その平地における limites [小路] と外周の境界線が描き入れられ、その結果として [subsiciva以外の] ager extra clususと境界線近くに出来たsubsicivaが表示されることになったのである。7)ある特定の土地割当てによる土地所有が明示的に例外として扱われた場合――loca exceptaとrelicta [放置された、捨てられた] ――は、それを示す境界線も地図に描き込まれ8)、同様の例として注意深く作製された地図においては、ケントゥリアの内部での余剰地とされた地所についても外周に沿った余剰地と同じ扱いでsubsicivaという名前で記載された。9)
測量によって定められたケントゥリアは、次の手続きとしてその四隅に石で境界標が設置され、さらにはその土地の測量地図が作製された。その地図――forma――の上には、その平地における limites [小路] と外周の境界線が描き入れられ、その結果として [subsiciva以外の] ager extra clususと境界線近くに出来たsubsicivaが表示されることになったのである。7)ある特定の土地割当てによる土地所有が明示的に例外として扱われた場合――loca exceptaとrelicta [放置された、捨てられた] ――は、それを示す境界線も地図に描き込まれ8)、同様の例として注意深く作製された地図においては、ケントゥリアの内部での余剰地とされた地所についても外周に沿った余剰地と同じ扱いでsubsicivaという名前で記載された。9)
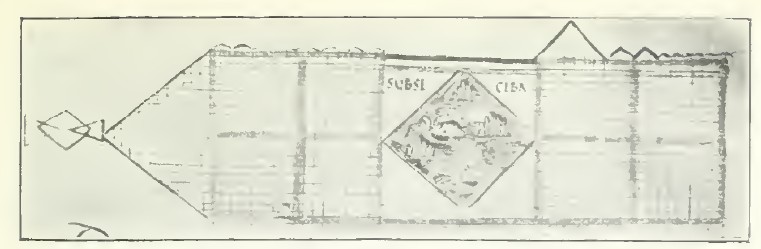
その次の過程として、分割のために用意された土地について、その分配の手続きが開始された。その具体的な進め方については、後の時代になってヒュギヌス≪De condicionibus agrorum, p.117≫が描写している。割当て対象の耕地について、それぞれに10人の植民者のグループを一つのチームとし、各耕地をそれぞれのチームに割当てるための籤(くじ)が用意された。最初に全植民者をこの10人組に編成するのがやはり籤によって行われる。それぞれの10人組 [の代表者] が引いた籤の結果で、その10人組に割当てられる土地区画が決まった。そしてそれぞれの10人組に割当てられた土地についてさらに各構成員10人にそれぞれの区画――accepta――が割当てられた。あるいは――ベテラン兵士≪40歳~45歳の退役5年前以内の老兵士≫である植民者に対しては先の手続きより前に別の処置が行われた――帝政期においては明示的に一人のベテラン兵士に対し規則的に1ケントゥリアの1/3が割当てられ、それぞれのベテラン兵士にその配当区画として引き渡された。10)
こうした手続きは、植民者 [で地所の割当てを受けた者] の名前をその平地の地図に記入することで法的な効力を得た。各植民者の名前は、彼らが地所を割当てられたそのケントゥリアの中に、測量の結果得られたユーゲラで書かれた面積表示(modus)の横に記載された。そしてまた明らかに規則的なこととして、その地所が土地分類の中のどの種類 [species] ――[例えば]耕地、森、牧草地――のどれであるかも描き込まれた。
7)ヒュギヌス、De condicionibus agrorum、p.121、16行以下を参照。
8)ラハマンの書籍のp.184にある図21・22がこのことを示している。
9)ヒュギヌス、前掲書、p.20。
10)ヒュギヌス、p.200。
こうした地図上への各種情報の記載のことを技術用語でadsignatioと呼んだ。複数のケントゥリアは地図への記入の際に、その四隅に置かれた境界標と同様に次のような形で記入された。つまり測量官がcardo maximusとdecumanus maximusの交点上に立ち東向きに見る方向で、またそのケントゥリアを囲んでいるcardo maximus とdecumanus maximusがそれぞれ南北と東西でその平地で何番目のものなのかが数えられる。そしてそのケントゥリアが(測量官が東向きの方向で)左右方向で [南北方向で] 何番目と何番目の cardo の間にあり、また前後方向で [東西方向で] 何番目と何番目の decumanus の間にあるか、その2つによってそのケントゥリアの地図上の位置が決定された。11)
もし土地分割割当てのための籤の参加者の中に、その植民市のそれまでの住民が含まれていた場合には、自明のこととして別のやり方が行われなければならなかった。――そしておそらくアンティウム≪現在はアンツィオで、イタリア共和国ラツィオ州ローマ県にある都市≫の場合、それは [植民市として] 知られている最古の例であるが、その場合に見られたのは新しい植民達の間に単純に等しい権利が与えられた訳ではなく、その植民それぞれの元々の所有物 [所有地] との関係に応じて分割されねばならなかった。それからこうした所有物の所有権の確定には、その所有者の職業が何であるかによってあらかじめ判定されねばならなかった。同じ原則に従って、所有権の確定のやり方は、ある場合には特定の植民者の元からの土地区画の所有がそのまま認められ、つまりはその土地区画は分割の対象から除かれたのである:その場合にはある種の登記書類にその者の所有する土地区画の面積がユゲラの単位で記録され、redditum summ [返還地] と呼ばれた――あるいは植民者は自分自身の土地の所有権を再度承認してもらう代わりに、税評価においてそれと等しい新たな土地を割当てられることもあった:そういった土地は commutatum pro suo [代替地] と呼ばれた――あるいは一部分は自分自身の土地で、その他は別の土地を配分されるという場合もあり、それは redditum et commuattum pro suo [返還地と代替地] 12)と呼ばれた。これら全ての場合において、当然ではあるが上述したような籤による土地の配分は、こういった修正が施された上で実施された。しかし更に、こうした籤による土地の配分がどの程度まで一般的に行われていたのかということについては、若干疑わしい部分も残っている。
籤の使用。植民市での土地分配と均等分配。
いくつかの事例においては、土地分配が籤引き無しで行われたということは疑いようが無く、そのような例としては ager campanus ≪第二次ポエニ戦役でハンニバル側に味方したカプアの町とその周辺の地域をローマが差し押さえたもの≫や、スエトン≪Gaius Suetonius Tranquillus、70頃-140頃、ローマ五賢帝時代の歴史家・政治家≫の注釈によれば、シーザーによる campus Stellatis ≪カンパーニャ地方の肥沃な平野≫の分配があった。UC643年[=B.C.111年]の公有地配分法 [lex agraria] は、グラックスにより土地配分の対象となった耕地が特別扱いされており、それは “sortito ceivi Romano” [ローマ市民への籤による土地配分、ceivi=civi] という名前が使われていた。これまで説明してきた土地の割当ては疑いようが無く均等割当て14a)であった。この均等割当てについて、モムゼンは15)次の2つの仮説を提示している。つまりそれが植民地の土地割当ての方法としてそれが規定されていた、ということと、そこで実施されていた籤がその証拠であるということである。
11)付図1(下)のローマのアラウシオ≪古代ローマの属州ガリア・ナルボネンシスの都市≫の平野の地図の断片とそれについての解釈と比較せよ。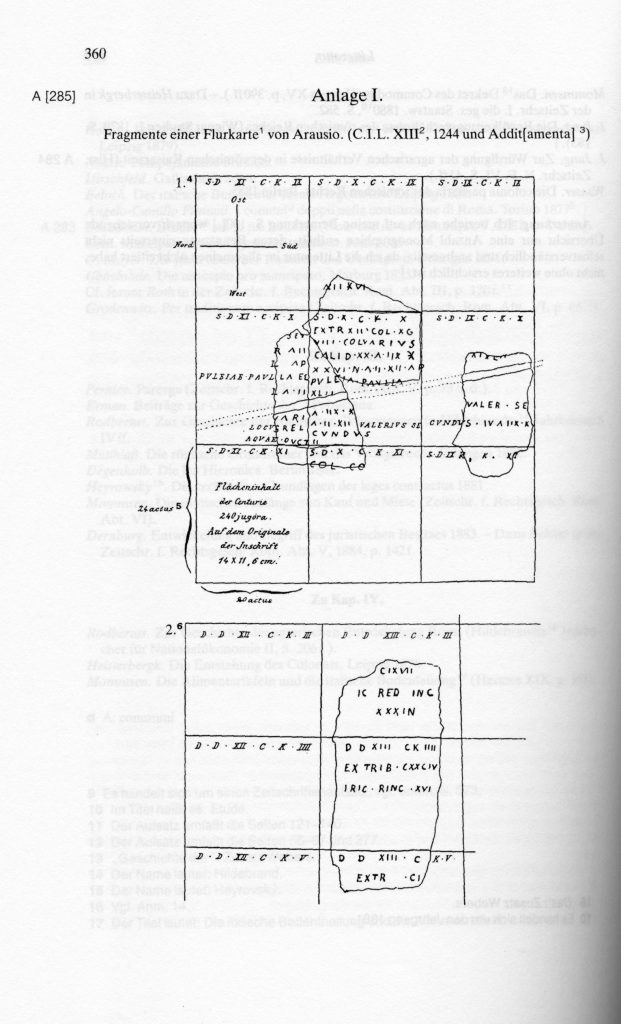
付図1(クリックで拡大)
12)シクルス・フラックス≪Siculus Fluccus、生没年不明、ローマの土地測量人≫の書のP.155を参照せよ。
13)スエトン、De vita Caerarum、第20章:Campum Stellatem…agrumque Campanum…divisit extra sortem ad viginti milibus civium… [南カンパニアの平野を…それと平地を…籤びきによらずに2万人の市民に分配した]
14)Corpus Inscriptionum Latinarum≪C.I.L.、ラテン語金石碑文大成、モムゼンをリーダーとする学者グループによるローマの碑文の解読集成。≫、I、200 P.3、4、またブルンス≪Karl Georg Bruns, 1816 – 1880, ドイツの法学者・法制史家≫のFontes iuris Romani AntiquiのP.72を参照。
14a) この概念については後述部分参照。
15) C.I.L.、I、 200、3、4行への注釈を参照。
今や次のことは明白である。つまり、籤が土地配分という目的のために使用されたということは、個々の区分けされた土地それぞれと、その受け取り人同士がお互いにはっきりと等価でありかつ同等であるということが明確に理解されていたということである。ここにおいて新しいゲマインデ [地方共同体] が形成される際や、丁度植民市がまさにそうであったように既存のゲマインデが作り替えられる場合には、そう見なすことはまさに政治的な意味で必要だったのである。ここに至っては、植民市の土地において籤によって土地が配分されるということは通常のことであったと考えるしかないが、そのことは更に配分される土地の面積に関して、また別の特異性を生じさせているのである。
古代ローマ当時の最初期の植民市がある共通経済的な土地制度に強く依存していたか、あるいはかなりの部分そうだったということは、モムゼン16)の著作において一定の確からしさをもって証明されている。共通経済から個人経済への移行においては、土地の分配に関してまったく同じ問題が出て来る。それはつまりこの例においてはまだ [領主とその臣下といったような] 専制主義的な形で組織化された土地ゲマインシャフト17)といったものは成立していないということである:それはつまり同じ面積の土地区画が必ずしも同じ価値を持っていた訳ではなく、同じ面積の土地区画を単純に分配する際においても、各人が必ずしも同じ面積の土地を得るのでは無いということである。
16)Röm. Staatsrecht III, P.26, 793参照。
17)そういったものの中で、例えばケルト人の間では、この方式での土地分割における問題は存在していなかった。というのはケルト人の部族長はこうした土地の断片を自分の裁量で好きなように分配することが出来たからである。このためにアイルランドでは不規則な土地の分割の結果として、様々な異なる大きさの土地の断片が残っている。
[ヴェーバーの時代の]ドイツの植民においては、こうした問題は解消されていた。そこにおいては平野がGewanneと呼ばれる四角形の耕地に分割され、そして各植民者にそれぞれのGewanneの一区画の土地が与えられる、というやり方が知られている。そこに見出されるのは、その証明は後述するが、次のことについての証拠である。つまり、ドイツの例と同様にイタリアでも、ドイツにおける土地分割方式が始まった頃とそう遠く離れていない時代に、似たようなやり方が行われたということであり、――というのはそういった考え方それ自身がゲノッセンシャフト≪比較的同じ身分の人々を基盤とする団体≫的な団結の中で生れたからであり、土地の [金銭的] 評価が [まだ] 行われていなかった限りにおいて、そういった考え方が忌避されることは無かったからであり――そのやり方が広く知られていた訳ではないが、繰り返し行なわれて来たlaciniae(=土地の区画単位)についての分割方法についてここでは説明しているのである。18)しかしながらこうした土地の分配方法が、十二表法の時代の不動産についての法に既にどのくらい適合していたかといういことはここでは述べられていないのであり――その意味については後で更に詳しく述べることになるが――、次の事を伝えているのである。つまり、こうした分割割当てでは常にager assignatus [割当て地] と分類された土地のみが割当て分配されているということである。
18)アンティウムにおける最古のローマ市民による植民市においては――UC416年(=B.C.228年)のことと推定されている――その植民市は同時にここで設定した問題 [ゲノッセンシャフト的な団結が現われていたかどうか] に対して考えるための意義を持っており、何故ならばそこでの説明は、他の古代の海外植民市においてのただそこに駐留する軍隊 [の兵士] への土地の配分という意味を持つだけでなく、全ての植民者に対して土地を分け与えることによって、その平野のある地域全体でのある実際的な組織を作り出しているという性格を明らかに持っていたからである。――Liv.VIII, 14――こうした分割の仕方は、liber coloniarum のP.229の第18行に書かれているように(「アンティウムの人々はこう説明した。latinaeの土地区画はager assignatusであると。)帝政期まで保持された。その他オスティア≪テベレ川(古称ティベリス川)河口にあった古代ローマ都市で港湾都市≫においても部分的に断片的な土地について説明されている。この問題については後で再度取上げる。)
しかしながら更に、割当てのための土地区画は、たとえその各々が等しい価値でなければならなかったとしても、しかし同時にそれらが必ずしも同じ面積に分けられている必要は無かった。それよりもそれぞれの面積は事前に行われていた土地の価値査定の結果と整合している必要があったし、その平野における該当の部分の土地の質によって[価値査定額が]異なっていても構わなかった。そういった土地の価値査定は、それはかなり大雑把なものであったかもしれないが、ただ既に開墾済みの土地が割当てに使われたので、それほど困難なものではなかった。実際の所、土地測量人達は、割当てに使われる土地の面積については、その土地の価値査定に合わせて加減していたと記録に残している。(ラハマン、p.156, 15行、参照:p.222の13行;p.224の12行)19)
19)そういった割当てられる土地の面積が様々であった証拠として、U.C.643の公有地配分法(第60章)のある箇所が注目に値するが、以下のように規定されている:
neive unius hominis (nomine quoi . .. colono eive [sive] quei in coloneinu)mero scriptus est, agrum quei in Africa est, dare oportuit licuitve, amplius jugera CC in (singulos homines data adsignata esse fuisseve judicato . ..)[.]
[ある一人の者の(名前に対して、その者が植民者であるか、あるいは植民者の資格があると登録済みの場合、その者に対しアフリカの土地を割当てることが明確に要求される。その土地の面積は200ユゲラより大きく、一人の者に割当てられるか、あるいは既に割当てられているかである。)]
モムゼンは(C.I.Lのad h.l.->Lex agraria, P.97)次のことを確実視している。つまり、土地の所有に関して様々なやり方が存在しており、例えば一人あたり200ユゲラだったり、或いはそれより少なかった場合もあった。実際の例では、ポンペイでの例が示すように(参照:ニッセン≪1839~1912年、Heinrich Nissen、ドイツの古代史家。≫のPompeianische Studien, 1877年、P.5881)、割当てられる土地の等級はその都市においてあらかじめ決められていた。しかしそれに関連する法は、割当てられる土地の面積の最大値だけを定めており、200ユゲラという面積がある特定のカテゴリーの植民市における、規定された標準面積と見なすべきだとは一言も言っていない。私はむしろ次のように考えたい。割当て用の土地の面積はその土地の価値査定に応じて異なっていたのであり、ただ1ケントゥリア以上の土地を一個人が所有することのみが原則的に禁止されており、例外的なケースとしてそれ以上の面積の土地を所有する場合には、法技術の上でそれは latus fundus [広大な土地資産、の意味。後に生じた大土地所有制は ラティフンディウム [latifundium] と呼ばれた。](ラハマン)、157、5)というカテゴリーで扱われたのである。
ここで植民市における土地の割当てにおいての籤による accepta [10人組に割当てられた土地] の決定を通常のこととして考える場合、しかしそのやり方はより古い時代の均等割当てにおいては明らかに例外的なやり方であったのであるが、そうではあっても次のことは疑いようが無い。つまり手間のかかる土地の価値査定と accepta の面積測量を行って、その結果定まったその土地の価額で調整するような割当て方の代わりに、機械的に同一面積の土地区画を分割するやり方の方が一貫して普通のやり方だったということである。というのは、我々は均等割当ての際に、「一人一人に同じ面積の土地が供与されねばならない。」という原則が規則的に付け加えられていたことを既に知っているからである。この土地の分割割当てにおいてはまた、各植民市のそれぞれ異なる事情にも合わせる形で調整されていた。各植民市においては、そこに入植する十分な数の志願兵を集めることが出来ない場合には、強制徴集もされており、その徴集された人員は強制的に形の上だけでもある新規のゲマインデ [地方共同体] の構成員とされた。より古い時代においては、住む場所も強制的に決められていたが、時代が下るといくつかの異なるゲマインデの中から一つを選ぶという形での、住む場所の [限定的な] 選択権が与えられた。その強制徴集の代償としてそれぞれに均等に分割された土地区画を提示された者は、その者の自由意志でそれを受領するかしないかを決めることが出来た。もし受領した場合は、それはその者が adsiduus という名前の土地所有者に成ったことのみを意味し、それ以外の何らかの新たな義務を負わされることは無かった。
ベテラン兵≪ローマの軍団兵は45歳になると退役したが、その退役前5年以内の40~45歳の兵士のこと。白兵戦には参加せず、比較的軽い軍務が割り当たられるなど優遇措置が適用されていた。≫による植民は、それに対する土地の割当ては測量人達にとって、実務上もっとも重要な仕事であったが、その [全てのベテラン兵を対等に扱うという] 原則に従って、均等割当てが採用された。20)
20)既に古代のベテラン兵の植民の場合の土地割当ても均等割当てであったし、ハンニバル戦争 [第二次ポエニ戦争] 時のベテラン兵(リヴィウス、Ab urbe condita、31、4)への土地割当てにおいても同じであった。その他、より古い時代での均等割当ては、また一種の戦利品の分配の形態を取っていた。
というのは同様のやり方で、acceptae についても、それは前述したようにヒュギヌスが(De limitibus constituendis、p.200)”Conternationsverfahren” [3つで1組の処理、土地の3等分割処理]と呼んでいるものであるが、1ケントゥリアを3分割するやり方、つまり1/3ケントゥリアずつの割当てで進められたが、その一区画の面積はケントゥリア自身の面積が3種類あったため、66 2/3、70、または80ユゲラであった。――あるいは全く逆に、1ケントゥリアの面積が、3つの均等割りされた土地区画の合計として、200、210、または240ユゲラと定められたのである。それに対してヒュギヌスの上述の箇所で述べられた別のやり方、つまり10人組に土地を割当てる方法を述べている箇所で、――ヒュギヌス、(De limitibus constituendis と De condicionibus agrorum、p.113)――次のようなことが起きていたらしい。つまり、その際に、それぞれの10人組に分配された modus agri (16、17行目参照)[その土地の面積] がそれぞれに異なっていたということである。更には次のことも間違いないと思われる。つまり、均等割りされた土地区画は、その全面積がいつもある一つのケントゥリア内に規則的に含まれている訳では全くなく、その結果として、[ケントゥリアの境界線を成す] limites [小路] も各区画の境界線と規則的に一致したりはまるでしていなかったということである。私はこれらのベテラン兵への土地配分について次のことを仮説として提示したい――というのはここではまたそのようなことに言及されているからであるが――古代での均等土地配分の実施方法(modus procedendi)が、それより古い時代の植民市における土地配分でのやり方と混ぜ合わされていると。そのことは次の現象によって示されている。つまり後者の根源的かつ固有である acceptae の籤による配分の方式が、そこにおいてはより本来のやり方と見なされているということである。後者の籤による土地配分はさらに、「事物の本性」≪die Natur der Sache、法律が完全には規定出来ていない部分を補完する一般的道理のこと≫にも合致していた。というのはそのようなある意味力ずくの大規模土地配分においては、ベテラン兵は元々のその選定方式の疑わしさや自分達への劣悪な取り扱いについて苦情を申し立てる権利を留保していたのであり、そしてまたその者達の不平不満は場合によっては [その植民市にとって反乱などの] 危険なものになる可能性があったからである。更にはまた、そういった理由から違法性の明白な証拠となることも避ける必要性もあったからである。これらのベテラン兵に割り与えられた土地区画はそれ以外にも、単純な均等割当てとはまた違う、長年の兵役経験者に対する恩給的なある決まった価額 [の土地] の給付という意味もあった。それ故に個々に割当てられた土地区画の価額は同じでなければならなかったし、現実的にそれが無理な場合でも最低限ほぼ同額である必要があった。それらの理由から、この割当て方式は本来の均等割り方式とは違い、測量の方法もその土地の価値査定に基づくやり方が採用されていた。しかしながらいずれにせよ、私は次のことは確からしいと考える。つまり、1ケントゥリアを3分割して3人のベテラン兵に割当てるというやり方は、10人組にそれぞれ土地を割当てる古代の均等割当てのやり方や、またそれより古い時代での植民市における土地配分のやり方に倣ったものである [まったく新しいやり方ではない] ということである。
ケントゥリアをベースにした土地配分と scamna と strigae をベースにした土地配分の違い
これまで取り上げて来た土地配分の二つの方法――ケントゥリア[正方形]をベースにする方法と scamna と strigae [長方形]をベースにする方法――の違いについては、ここまではただ前者に対してのみ境界線として limites [小路]というものが使われていた、ということを確認して来た:ただ limites が [境界線として] 使われている場合のみ、本来は測量された土地区画がケントゥリアと呼ばれた。しかしながら当時の測量人達が残した著述を見ると、そこには二つの方法を混合したやり方も見出せるのである。それはつまり[scamna と strigae を使った] ager scamnatus であるにも関わらず limites によって区切られており、[scamna と stirgae の組み合わせで構成された長方形の] ケントゥリアを単位として測量されているのである。このやり方がより後代の二つが混合されたやり方であるというのは自明であるが、しかしながらその混合方式が採用された理由については、測量技術の観点でもう少し詳しく見てみる必要がある。M. ユニウス・ニプサス≪Marcus Iunius Nipsus、生没年2世紀、ローマの測量人兼著述家≫の注釈(p.293)によれば、ager scamnatus においての1ケントゥリアは、[200ユゲラではなく] 240ユゲラだったと述べられている。それはヒュギヌスが(De limitibus constituendis のp.206で)この混合方式による土地分割についての、非常に理解が困難な箇所についての一つの解釈として述べている詳細な説明によれば、同じ面積の土地区画を作り出すための一つの方法について述べているのであり、そこから解釈出来ることは、この240ユゲラという総面積は80ユゲラの土地区画が3つ、という形で構成されているということである。ヒュギヌスは当該の箇所に先行する箇所で次のように述べている。この方法は、ager arcifinius pro vincialis ≪地方にて不規則な境界線、例えば片側が河川で区切られているなど、を持っている土地≫の測量方法を説明しているのであると。それに続けて、まず論拠を説明してから、その論拠については後述するが、通常のケントゥリアをベースにした測量方法以外の方法を採用する必要性があったのだと推論している:
“Mensuram per strigas et scamna agemus. Sicut antiqui latitudines dabimus decimano maximo et k[ardini] pedes viginti, eis limitibus transversis inter quos bina scamna et singulae strigae interveniunt pedes duodenos itemque prorsis limitibus inter quos scamna quattuor et quattuor strigae cluduntur pedes duodenos, reliquis rigoribus lineariis ped[es] octonos. Omnem mensurae hujus quadraturam dimidio longiorem sive latiorem facere debebimus: et quod in latitudinem longius fuerit, scamnum est, quod in longitudinem, striga.”
「我々は strigae と scamna を使った土地測量を [以下のように] 行う。古人達がそうしたように、まずある広がりを持った土地に対し、それぞれ20ローマ・フィート [約5.92m] 幅の decumanus maximus [東西の基幹道路] と cardo maximus [南北の基幹道路] を [その土地の中央で交差するように] 設置する。そして外周の境界線をそれぞれに直角になるように設置する。その境界線の内側が、2つの scamna [東西に長い長方形] と1つの strigae [南北に長い長方形]を組み合わせた形状を一単位として、それと幅12ローマ・フィート [約3.55m]の街路によって区切られる。同様に我々は直線で囲まれその中に4つの scamna と4つの strigae を含んでいて幅12ローマ・フィートの街路で囲まれた単位区画を設定する。残った部分については8ローマ・フィート [約2.32m]の幅の街路で囲まれる。全ての測量された土地は、縦長の長方形または横長の長方形によって分割されねばならない:横長の長方形が scamna であり、縦長の長方形は strigae である。 」
ここにおける [変則的な] ケントゥリアは――それは長方形として記述されているので――それ故に縦が横の1.5倍の長さとなっているかあるいはその逆であり、つまりはそれぞれの辺の長さは20 [約710.4m]と30 actus [約1,065.6m]であり、その面積は [1ユゲラは2平方 actusなので 20 x 30 / 2 で] 300ユゲラ [約75.6ヘクタール、228,690坪=東京ドーム敷地の16個分] であり、それを3等分した時の一つ分の面積は100ユゲラ [約25.2ヘクタール、76,230坪] である。しかしもしかするとそこには思い違いがあり、ヒュギヌスはニプサスの著述におけるケントゥリアを20 actus x 24 actus [240ユゲラ]と見ているのかもしれない。その場合の考え方は以下のようになる。つまり、ここでのケントゥリアが1つの土地区画が3つの区画要素の組み合わせにより構成されると述べられており、それ故1つの strigae と 2つの scamna からなる [長方形の]ケントゥリア(あるいは逆に2つの strigae と1つの scamna からなる [長方形の] ケントゥリア)を単位としてより広い土地がその複合体として構成されているのであると。そこにおいては saltus [5 x 5 または 4 x 4 ケントゥリアの広さの土地単位]の代わりに通常の ager centuriatus [ケントゥリアによって区画された土地] が出現しているのである。その [変則ケントゥリアをベースにしたより広い土地単位の] 一つの辺は decumanus maximus に平行であり、ヒュギヌスによれば4つの strigae と3つの scamna から出来ており、もう一方の辺については cardo maximus に平行であり、2つの scamna と 1つの strigae の組み合わせを単位として構成されており、この二つの辺 [x 2]で境界線が作られていた。[添付図2を参照] このような前提から検討し、土地が不規則な場合について私は次のように仮定したい。つまり、206ページの第10行と第12行に出て来る prosis [縦の] と traversis [横の] は入れ替えて読むべきであると。その場合ヒュギヌスが想定している耕地図としては、添付図2の2つの地図の内の一つに該当すると考えられる。添付図2の下の地図は、ヒュギヌスが述べている 20 actus x 30 actus のケントゥリアに該当し、上の地図はニプサスが述べている 20 actus x 24 actus のケントゥリアに相当すると考えることが出来よう。
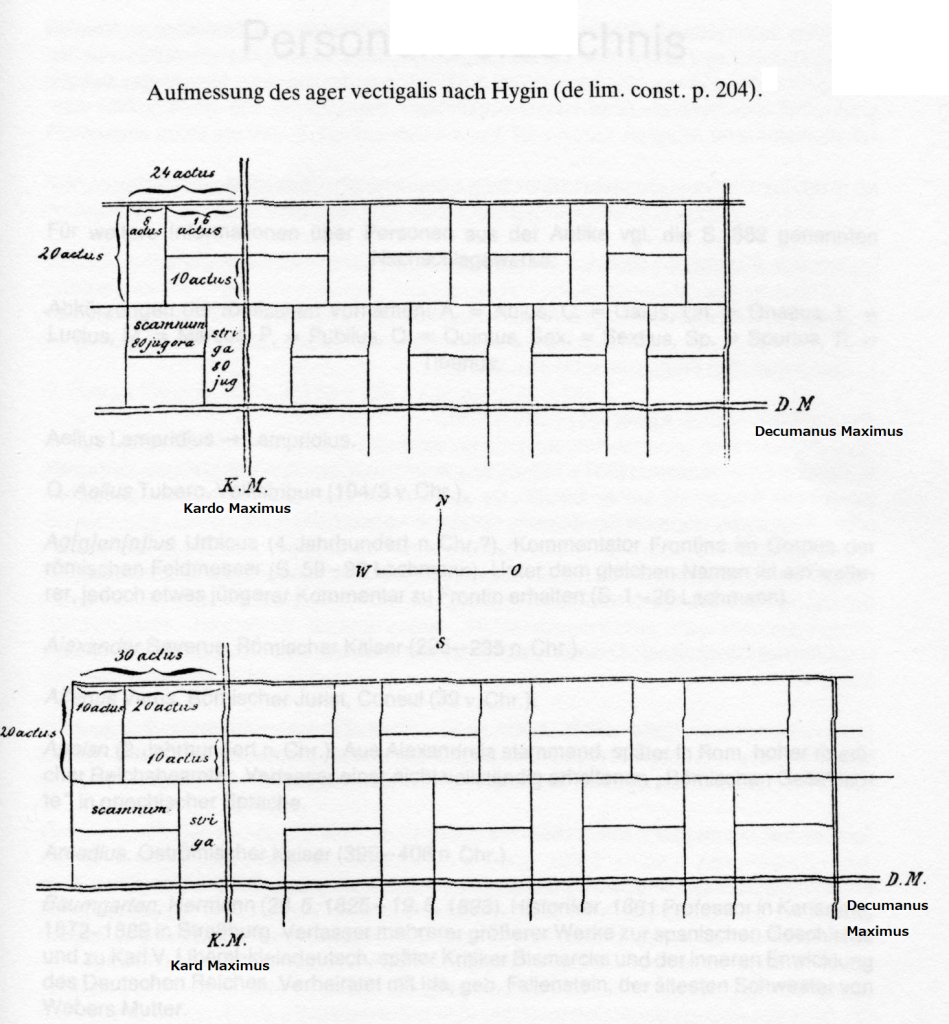
これらの数字は、ラハマンがその書籍中にて復元を試みているいくつかの毀損の激しい図の中から取りだした数字と、かなりの部分で一致している。測量人達は長方形のケントゥリアについて、それを2つの [原文は3つであるが、最大3つの部分に分けるには外周以外では2つの平行線で十分である] 平行線にて区切る代わりにに――strigae と scamna を用いて――切り分けるのであり、それ故に分け方としては、まず長方形の横線の1/3の所で strigae を切り出し、次に残った部分を同様に縦線の1/2の所で切って2つの scamna を得たのである。22)≪左図参照≫
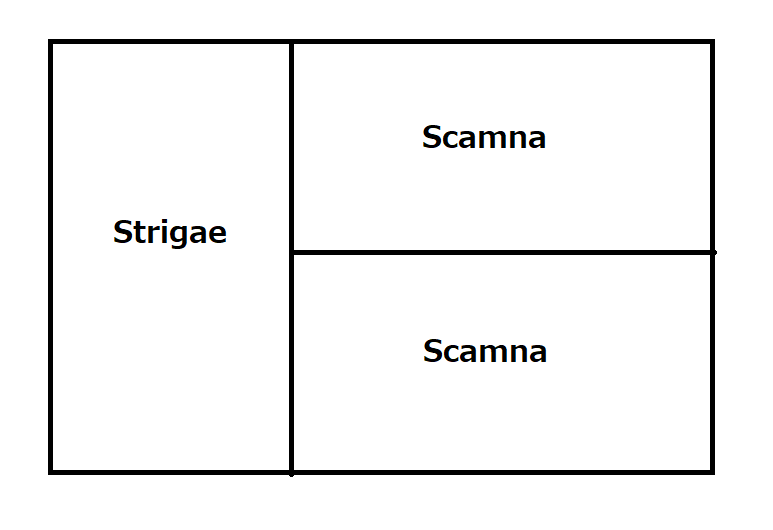
22)おそらくはローマの属州にて(イタリア半島にも存在したが稀であった)通常のものであった長方形のケントゥリアが、このやり方への誘因の一つとして説明出来るであろう。添付図1に付けられた銘文が示唆しているように、測量人達はこうした長方形のケントゥリアを用いる際に、長手方向をそれぞれの地域によって変えるのが常であった。
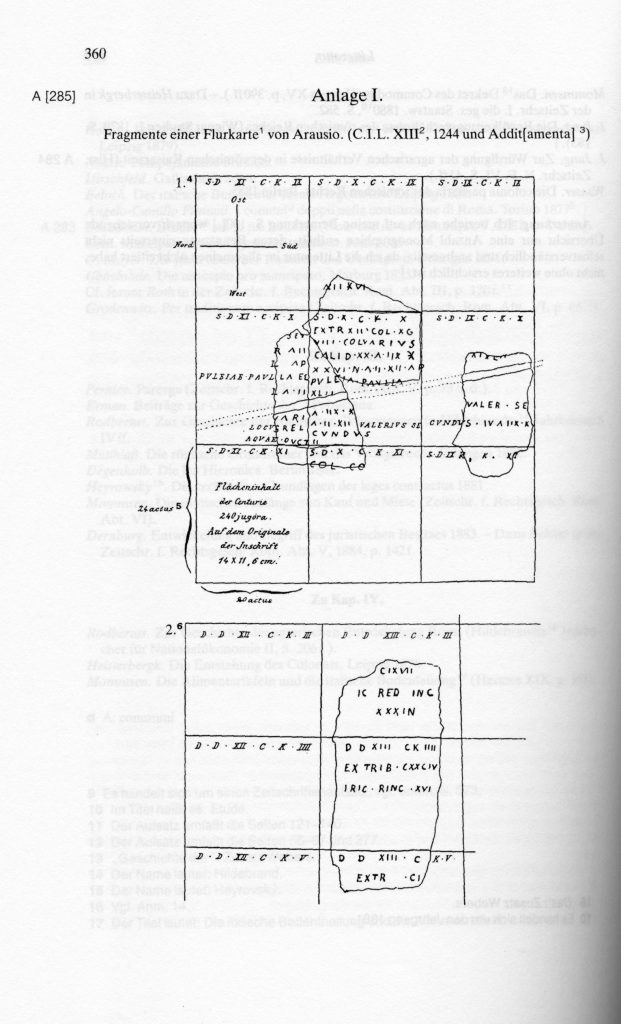
アラウシオにおいては、まさしくそのように見えるのであるが [付図1参照]、左側の地域 [付図1の上の地図] においては東西方向を長手に、右側の地域 [付図1の下の地図] においては南北方向を長手にしている。[この付図1の地図は左が北、右が南となっていることに注意。] このことと整合するのは、[長方形の] ケントゥリアを scamna と strigae に分割する際も、その分割の結果の配置はその都度異なっていたということである。こういった組み合わせ方式を採用する際に、技術的に考慮されていることは明白である。[現実の複雑な地形に対しては] 単純に平行線だけで土地を分割するより、それぞれの区画を切り分け、その方向を決めるにあたっては、そういうやり方による分割の方が簡単だったのである。
いずれにせよ特徴的であったのは、それが本当に真実を語っているのかは良く分らないが、limites [小路] とケントゥリアを使って測量された耕地に対して、更に scamna と srigae を使用したということと、また耕地全体がそれでもなおケントゥリアの複合体として構成されていたということである。――そしてそういった特異性からは次のような疑問が生じる:一体どのような理由から測量人達はこのように手の込んだ複合的な方法を採用したのか、そしてその疑問はさらに細部に関しての別の疑問を生み出すのであるが:概してどのような場合に scamna と strigae を使った土地分割が行われたのか、ということである。これらの疑問への答えを見つけるために、我々はまず次のことを確認しようと思う。つまりケントゥリアによる土地の割当てと scamna と strigae によるそれの、本質的な違いは何かということである。Limites の存在の有無という点は、二つの方法の違いではないか、あるいは少なくとも主要な違いではない、ということは明白である。というのは limites は我々が調べている時代においては、前述の測量人達の著作が示しているように、ager scamnatus においても使用することが出来たからであり、またその際にも ager scamnatus の本来の特性は失われてはいなかったからである。またその違いはケントゥリアが [正方形ではなく] 長方形であるということでもない。というのは、ケントゥリアは前述の通り、正方形以外の形状を取ることも可能だったからである。違いは何か別の点にあるということは間違いない。
我々は前述の箇所で次のことを確認した。即ち ager limitatus においては、測量地図上に次に挙げる要素以外は何も含まれていなかったということである。つまり区画割り対象の一まとまりの土地単位の外周 [の基準線] としての cardines [南北の線] と decumani [東西の線]、そしてその土地区画の受領者がそれぞれのケントゥリア内で得ることが出来た土地の面積 = modus agri の [公的な記録としての] 記載である。各ケントゥリアの境界線と、受領者が得た個々の土地の境界線は全くのところ一致していなかったので、個々の人員の所有する所となった土地のぞれぞれの境界線は、通常の測量地図には含まれていなかった。これについては後述の箇所で(P.121)ではっきりと確認することになる:
Nuper ecce quidam evocatus Augusti, vir militaris disciplinae, professionis quoque nostrae capacissimus, cum in Pannonia agros veteranis ex voluntate et liberalitate imperatoris Trajani Augusti Germanici adsignaret, in aere, id est in formis, non tantum modum quem adsignabat adscripsit aut notavit, sed et extrema linea unius cujusque modum comprehendit: Uti acta est mensura adsignationis, ita inscripsit longitudinis et latitudinis modum. Quo facto nullae inter veteranos lites contentionesque ex his terris nasci poterunt. Namque antiqui plurimum videbantur praestitisse, quod extremis in finibus divisionis non plenis centuriis modum formis adscripserunt. Paret autem quantum hoc plus sit, quod, ut supra dixi, singularum adsignationum longitudinem inscripserit, subsicivorumque quae in ceteris regionibus loca ab assignatione discerni non possunt, posse effecerit diligentia et labore suo. Unde nulla quaestio est, quia, ut supra dii, adsignationem extrema quoque linea demonstravit.

[ 最近この地域において、あるトラヤヌス帝≪Marcus Ulpius Nerva Trajanus Augustus、53~117年、98~117年の間のローマ皇帝でこの皇帝の時にローマの版図は最大となり、後世ギボンによって五賢帝の一人と称賛された。≫により召集された兵士で、軍務に服する一方で、また我々の職業(測量人)についても精通している者が居り、その者は我々と共にパンノニア≪ローマの属州で現在のオーストリア東部,ハンガリー西部,旧ユーゴスラビア一部から成る地域。B.C.14年頃にローマに征服された。左上の地図参照。≫において、トラヤヌス帝のご意志とご恩寵によって土地をベテラン兵達に分配した。その者は割当て内容を青銅板の上に地図として記録したが、ただ一人一人に割当てた面積を認定して記録しただけではなく、また一人一人の取得した面積の土地の外周の境界線もその地図上に記載した。そこで行われたのは、adsignatio と呼ばれた土地割当てのための測量方法であり、それによって個々の割当てられた土地の境界線の縦と横のサイズが地図上に書き込まれた。このやり方によってベテラン兵達の間でこれらの配分された土地についての訴訟や争い事が起きることは全くあり得なかった。というのも、より古い時代においてはこの手の争い事が非常に多く見られたのであり、それは割当てられた土地が完全なケントゥリアとして扱われず地図にそのサイズが記載されなかったためである。しかしながら、これらのその者の成し遂げたことの改善の程の大きさは、まことに注目すべきものである。何故ならば、先に私が述べたように、その者は一つ一つの分割された土地のサイズと同時に、また剰余の土地(subsiciva)のサイズも地図上に記載したのであり、この subsiciva は他の地域では個々人に割当てられた土地と区別することが出来なかったのであるが、彼はこれを自分自身の献身と労力で成し遂げることが出来た。これらのことによって、前述したように、土地の領域の最外周や個々の割当て地の境界線がきちんと記録されているということについては、疑うべきことは何も無い。]
それ故に:ager centuriatus において、測量地図上に個々の割当てた土地の境界を何らかの形で判別出来るようにするやり方は、測量人達の間では新しい方式と見なされていた。その理由は個々の所有地を地図の製作においてそれらを載せるということは、本来の forma [測量地図] の目的とする所ではなかったからである。それをやった理由は、トラヤヌス帝が初めて次のことを命じた23)からである。
23)ヒュギヌス、De Lim. p.172、6行目
それは個々の acceptae の土地はその命令以降は termini roboris [termini roborei、オークの木による土地の境界表示] によって区切られなければならないということである。一方でそれ以前は、ただケントゥリアにのみ石による境界標が [四隅に] 設置され、測量人達は土地の受領人に対して、その者が自分の土地の境界を termini “comportionales” [私有地で用いられた境界標] や 他の手段ではっきり示すことについては、その者達の自由に任せていた。土地割当ての対象となり、公的に保証されたのは、ただ割当てられた面積 [modus agri] のみであった。24)
24)このことから考えて、次のことが元々起きていた可能性がある。それはつまり、戦いにおいての興奮状態において、元々対象者があるケントゥリアの中で、既にそれぞれに譲渡されていた土地よりも、更により多くの追加の面積の土地が分割して割当てられたということである。その例としては、ガイウス・センプロニウス・グラックス≪Gaius Sempronius Gracchus、BC154~BC121年、BC122年の護民官で土地制度の改革案で有名なグラックス兄弟の弟の方。≫によるカルタゴにおいての土地割当てがあり、その騒乱を巻き起こしたという性格から、実際にかなりの程度までそういうことが行われていた可能性が高い。こういう風に本来の割当て面積よりも多い土地を割当てるということを、U.C.643年の公有地配分法 [lex agraria] が、均等な面積の割当て対象の土地を何倍にも重複して与える場合、ということで規定していた。(第65章以下)
ager scamnatus の更に他のやり方について述べてみたい。ager scamnatus は、”per proximas possessorum rigores” [厳密に既に存在する他の所有地の土地の境界に沿って] 割当てられた 25)という記述については、「その隣に立地している土地の境界に沿って」を意味することは明白である。
25)フロンティヌス≪Sextus Iulius Frontinus、35/40~103年頃、ローマの軍人・建築家・測量人でローマの遺構として有名な水道橋の設計者。≫、p.3。
ここ [パンノニア] において測量地図には個々の所有地の境界も記載されており、各人に割当てられた土地区画が地図上に記載されるのと同時に、更にその区画が誰に与えられたものなのかも明記されたのである。
こういったそれまでとは違う測量-地図作成方法の根底にある意味は何であろうか?それについてはヒュギヌスが、204ページ以下のまとまった説明の導入部において、教えてくれており、そこについては既に一度(p.117)部分的な解釈が行われている。そこでは次のような説明がなされている:
Agrum arcifinium vectigalem ad mensuram sic redigere debemus ut et recturis et quadam terminatione in perpetuum servetur. Multi huius modi agrum more colonico decimanis et cardinibus diviserunt, hoc est per centurias, sicut in Pannonia: mihi (autem) videtur huius soli mensura alla ratione agenda. Debet (enim aliquid) interesse inter (agrum) immunem et vectigalem. Nam quem admodum illis condicio diversa est, mensurarum quoque actus dissimilis esse debet. Nec tam anguste professio nostra concluditur, ut non etiam per singulas provincias privatas limitum observationes dirigere possit. Agri (autem) vectigales multas habent constitutiones. In quibusdam provinciis fructus partem praestant certam alli quintas alii septimas, alii pecuniam, et hoc per soli aestimationem. Certa (enim) pretia agris constituta sunt, ut in Pannonia arvi primi, arvi secundi, prati, silvae, glandiferae, silvae vulgares, pascuae. His omnibus agris vectigal est ad modum ubertatis per singula jugera constitutum. Horum aestimio nequa usurpatio per falsas professiones fiat, adhibenda est mensuris diligentia. Nam et in Phrygia et tota Asia ex huius modi causis tam frequenter disconvenit quam in Pannonia. Propter quod huius agri vectigalis mensuram a certis rigoribus comprehendere oportet, ac singula terminis fundari.
[ager arcifinius ≪それまで敵地であったなどの理由によりローマによる測量も区画割りも未実施の土地で課税対象のもの≫の測量については、我々測量人は次のように実施しなければならない。即ち、それによってその土地の所有者と境界線を確定させ、それを継続的に保護することである。多くの測量人達が、この種類の土地を、植民市のやり方で decumanus [maxmus] と card [maximusu] によって分割した。それはつまり、ケントゥリアによって土地を区画割りしたのであり、パンノニアで行われていたやり方と同じである:私の考えではしかし、この種の土地の測量については別のやり方で実施すべきと思う。(実際の所、どの測量人も)土地を免税のものと課税のものとに分けるべきである。これらの土地はそれぞれ法律上の取り扱いが非常に異なっているので、その測量においてもまた二つをそれぞれ区別して実施しなければならない。我々の職業においてもまた、ある個人所有の境界線で区切られた土地区画について、調査する権限が与えられていないということは無い。しかしながら、多くの課税対象の土地については、様々な種類のものがある。ある地方においては、利益の一部に対して定率の税金が課せられており、ある場合は利益の1/5、別の場合は1/7を現金で支払う必要があり、また土地の収益性 [地味や用途など] によって税率が定められていた。土地の価格はその土地の種類によって固定されており、その種類はパンノニアの例では一級耕地、二級耕地、牧草地、森林、木の実の採取林、平民による共有の森、そして牧場である。これら全ての土地の種類について、課税額はその面積と1ユゲラ当たりの収益性毎に定められている利率によって決められている。これらの土地資産について、その所有者による誤った主張に基づく不正行為を行わせないために、測量は注意深く行わなければならない。実際の所、フリギアと小アジアの全ての地域で、このような規定から、パンノニアの場合と違って、多くの法的な争い事が起きているからである。こういった理由から、これらの課税地については、測量を確実かつ厳密に、一本の境界線も疎かにせずに実施する必要がある。]
それ故に、その土地が課税対象か否かがヒュギヌスによればこのような違ったやり方の測量が行われる理由であり、それ故に scamna と strigas による土地の分割が行われるのであり、だからこそ、それによって混乱が生じないように、その土地は “a certis rigoribus” [確実かつ厳密なやり方によって] 線引きされねばならないのである。このことはただ次のようなやり方によってのみ達成される。つまり、測量人達が rigres [はっきりとした線]、即ち所有地の境界線を地図上に記載し、誰でも見られるようにするというやり方である。26)
26)同様のことが、またエジプトにおける神殿の財産についての、レプシウス≪Karl Richard Lepsius、1810~1884年、プロイセンの考古学者・エジプト学者≫(Abhaandl. der Berl. Ak. der Wissensch. 1885年)によって解釈が行われたエドフ≪ナイル西岸のエジプトの都市、神殿があった。≫の象形文字で書かれた銘文についても見て取ることが出来る。そこでは、少なくとも各土地区画が記載された場所において、縦と横の境界線の長さが正確に記載されており、それもまた同じ理由からである:個々の土地区画を正確に確認出来るようにするためである。
おそらくはヒュギヌスはここで述べられている地所の新しい形での登録について、つまりパンノイアにおける区画分けが、「最近」(nuper) アウグストゥス(トラヤヌス帝)の命令で行われたとしており、それが決定的な意味を持ったことを強調している。測量人達は、各所有地の境界を地図の上に記載しようとして、それ故にケントゥリアの内部で、その本質的な意味が所有地の境界の確定とそれを地図に載せることであるような土地分割のやり方、つまり scamna と strigae を使ったのである。
様々な測量方法が存在する理由。Ager scamnatus への課税の可能性。
[様々な測量方法が存在した]その理由は明白である:本来の意味での土地への課税が行われていた所では、つまりある決まった金額の支払い、[その土地からの] 農作物または他の収穫物へのある決まった割合の税が、ある一定の大きさに区切られた地所に対して課されていた所では、国家行政は課税対象の目的物をはっきりさせるという目的で、これらの土地の区画の状態を公的に確立させることに関心を持っていた。そのような関心は、地所がそのように課税される形にまで整備されておらず、実際に課税されていない地域では存在していなかった。その場合はただ、本来課税されるべき人々の所有するその他の財産物件と同じように、土地も一般的な財産税の対象とされたのみである。この被課税者の土地所有に対する財産税課税においては、更に先へ進んだ本質的な課税対象の目的物を [法的に認められるという意味で] 作り出そうとする意向があった。良く知られている後者の例としてはローマ市民への課税があった。
このような固有の土地税に関連付けられるか、あるいは少なくとも理論的には関連付けられた土地において――、個々の土地区画の境界線を測量地図上で明確に識別出来るようにすることについては、行政面では何の価値も無かった。ケンスス≪ローマにおける市民の登録とその所有財産の調査で今日の国勢調査の走り≫においてはしかし、土地のユゲラ数――即ち面積 [modus] 26a)――を申告する必要があったし、その申告においては、最初にその土地の割当てを受けた時の測量地図 [forma] を添付する必要があった。従って、個人財産の証書類の提出 [の一つ] としてケンススにおけるよりよい管理という目的のために利用された可能性がある。それにもかかわらず、フロンティヌスが(p.4)特別に注記していること、つまり scamna と strigae による土地の分割は、”ava publica in provinciis coluntur” [属州においてその時点で耕作が行われていた公有の耕地] においてのやり方であると言っているということであるが、それに関して次のことは疑いようが無い。つまり、こうした土地の分割においては、特定の測量理論に従って実施されねばならなかったのであり、その場合はその土地は ager optimo jure privatus [非課税の私有地] にはならず、特に次のような場合において行われていたということである。その場合とは、土地が地代の納付という条件を了解することを条件として与えられたか、あるいはある種の土地税またはその土地からの収穫物への税が課せられたか、そういう場合であり、[フロンティヌスが] 完全な所有権が与えられると説明している場合には、そこでは [scamna と strigae によるのではなく] ケントゥリアによる境界線引きと土地割当てが行われねばならなかった。ケントゥリアによる土地割当てにおいては、それ故にいずれの場合でも:die coloniae civium Romanorum juris Italici [イタリアの法によるローマ市民の植民市] だったのであり、それは一人一人に [私有地として] 分割し分け与えられた土地区画であり、それに対しては完全なローマにおける土地所有権が貸与されたのである。
26a) キケロの”Pro Flacco”の32,80に “majorem agri modum” [その土地の面積の大部分を] という記述がある。
Scamna の適用
Strigas と scamna を使った土地の割当ては、次のような理論に従って行われていたのかもしれない:全ての agris vectigales [課税対象の土地] は、ローマの役人によってそういうものとして [ケントゥリアとは別のものとして] 貸与され、そしてその土地には国家への納税義務が付随していた。更にそのような属州の土地は、その土地の以前のまたは新しい所有者に対し、個々の土地区画に対して、現金による税支払いや、または農作物の引き渡しなどの、その土地に対する物上負担 [人ではなく物が負担すべき一種の債務] として一般的に課せられる支払いを条件とした上で引き渡されていた。更に分析を進めるとすれば、我々は次のフロンティヌスの記述に着目すべきであろう。それは scamna と strigae による土地割当ては、arva publica [公有の耕地] を分割貸与する際に使われたのであり、次のことを結論付けている。つまり、この形の土地分割方法は元々、公有地において定期賃貸借の形で与えられる土地に対して適用された方法と同じであり、その場合は次の目的で測量されることが多かった。つまり、測量上の併用方式、即ち limites を用いる方法と scamna を用いる方法を併用し、その場合法的には ager privatus と ager vectigalis が同時適用された “ager privatus vectigalisque” [私有地であって課税される土地] という形式に適合しているのである。
国家の名において賃貸しされた耕地が、法の取り決めに従って測量地図上に記載されなければならないということは、グラニウス・リチニアヌス≪Granius Licinianus、2世紀のローマの歴史家、その著作については若干の断片のみが現存している。≫の著作に一部に出ている。その記述によれば、部分的に個人によって占有された ager Campanus [カンパーニャ地方の耕地] の [所有権の] 変更に当たって、元老院によって全権委任された執政官の P. レントゥルス≪Publis Comelius Lentulus Spinther、BC101~BC47年頃、BC57年に執政官を務めた、ローマの政治家・軍人≫が語ったところに拠れば――それはモムゼンのC.I.L., X P.386における解読に従えば――:
Agrum (e)u(m) in (fundos) minu(t)os divisum (mox ad pr)et(i)um indictu(m locavit et mu)lto plures (quam speraverat agros ei rei) praepositus reciperavit formamque agrorum in ae(s) incisam ad Libertatis fixam reliquit, quam postea Sulla corrupit.
[ 彼が小さな単位に分割した土地を、次にあらかじめ決められた価格によって契約を結んで貸与した。そういった資産としての土地を、その担当者は、あらかじめ予測されていたものよりもはるかに多く、復元させることが出来た。彼はその土地の測量地図を青銅の板に刻み、それを自由の女神{リベルタース}の神殿に設置して残した {測量地図を含むケンサスの記録がこの神殿に保管されていた}、後にそれはスッラによって破壊された。]
もっとも確からしいと思われることは、ここではある土地を地図に載せて登録するという目的に沿って、個々の土地区画の境界線が測量地図上に記載された、ということである。その理由は、そうでないとしたら、何のためにそのような [余計な手間のかかる] 地図を作成しているのかの目的がどこにも見出せなくなるということである。Ager Campanus は、というのも、シーザーの時代においてすら、未だに ager vectigalis (スエトン、Div. Jul. c. 20)であったからである。いずれにせよ、より確からしいのは、当時の測量人達が limites を用いた測量より、strigae と scamna を使ったやり方の方をより頻繁に行った、ということである。Limites を用いる方法は、その本来の目的では、一般にこの地域では使うことが出来なかった。というのはこの記述の部分では、元老院からの土地評価の要請に基づく行政行為としての測量のみが扱われているからである。
我々が次のことを正しいと仮定する場合、つまり scamna と strigas を使った土地割当ては、既にかなり早い時代においても、また後の時代においても、もっぱら公共の土地あるいは半ば公共の土地の測量についてのみ利用されていたと仮定する場合、だからといって次の2つはいずれも正しいとは言えない:
1.scamna と strigas がそういう場合だけに使われたということ
2.公共の土地あるいは半ば公共の土地は常に scamna と strigas を使って分割されたということ
この2点については、むしろ逆であったことが証明出来よう。[scamna と strigae を使うのは他の場合の方が一般的だった、公共の土地の分割については他の方法の方が多く行われていた。]
フロンティヌスによれば、scamna と strigas を土地割当ての手段として使うやり方は、概して古代のやり方であると記述されている。我々は scamna と strigae が若干の自治市において行われているのを確認することが出来る。それらの自治市については後に論じる。そしてそれはローマ市民によって建設された2つの植民都市でも使われていた:それはオスティア 27)≪オスティア・アンティカ、ローマの外港でテヴェレ川河口にあった港湾都市。≫スエッサ・アウルンカ 28)≪現在のセッサ・アウルンカ、アッピア街道とローマ街道の中間にあり、紀元前4世紀以降ローマ市民による植民が行われた。≫である。オスティアの方は、ローマによるローマ市民の植民市として知られている最古の都市であり、古代における植民市の特質について論じる場合には、何をおいても真っ先に取り上げられるべき都市であり、その成立の実際についての議論がこれまで行なわれて来ているし、そしてまた [後に] 皇帝アウグストゥスの植民市にもなった。それに対してスエッサ・アウルンカの方は、元々はラテン人≪ラテン植民市の市民で、ラテン語を話すがローマ市民よりは一段下に扱われた。≫の植民市だったのであり、ローマの同盟市戦争≪BC91年から数年間、イタリア半島南部の都市国家や部族がローマ市民権を求めて蜂起した戦争。≫以来のムニピキウム [都市国家] であり、三頭政治の時にローマの植民市となった。スエッサについてまず言えることは、scamna と strigae を適用するに当たって、何か特別な理由があったように思われることである。フロンティヌスは次のように述べている(P.48、16):
“et sunt plerumque agri, ut in Campania in Suessano, culti, qui habent in monte Massico plagas silvarum determinatas.” [そのほとんどが次のような土地であった。それはつまりカンパーニャとスエッサにあった耕地で、マッシコ山の麓にあった平野で森に囲まれていた。]
それ故に、この記述からは、ある理由から次のことについての必要性があらかじめあったように思われる。それはフロンティヌスが記述しているように、森林の利用の規制である。つまり、森林のある一部を伐採して土地を拓いた場合、――それは特定の種類の土地区画に割当てられねばならなかったし、またそれを可能にするために、測量人達はまずは他のことに先駆けて、既に所有権が誰かに与えられている土地の境界線と同様に、[伐採された] 森林の中の土地の境界線も測量地図上に明記する必要があった。つまりは scamna と strigae を使ったのである。その他の詳細については不明であり、いつ誰によってこうした土地分割のやり方が始められたのかは分からない。しかしながら三頭政治時代の争乱の中で実施された行政手続きについては、既に存在していた土地の分割割当ての方法を単純に引き継いだと考えるのが、全くの所正しいと思われる。28a)
27) l. Col. (Liber coloniarum) 236, 7, Ostensis ager ab imp[eratoribus] Vespasiano, Trajano, et Hadriano, in praecisuris, in lacineis et perstr iga s, colonis eorum est adsignatus. [オスティアの土地については、皇帝ウェスパシアヌス、トラヤヌス、そしてアドリアヌスによって、切り分けられ、境界を与えられ、そして strigae を使って、その地の植民者達に割当てられた。]
明らかなこととして、互いに隣接し合っている土地の割当てのやり方は、それより以前の土地割当ての方法が引き継がれており、ここに言及されている3人の皇帝によってそのやり方が継承されている。
28)フロンティヌス、P. 3。
28a) このことから、スエッサのラテン市民による植民市については、次のように推論すること、つまり土地の分割割当ては全て scamna と strigae を使って実施されたのであると、そういう風に結論付けるのは性急過ぎるであろう。
オスティアに関しては、――仮説構築を試みることは出来るであろうが――むしろどうやったら仮説に留まらず事実に近付けるだろうか?――この地における scamna と strigae を用いた土地の分割は、そこにおける都市住民と関連付けて考えるべきであろう。その都市住民は、明らかに少なくともオスティアの人口の一定部分を占めていたのである。それ以外にまた、オスティアはイタリアにおける2番目の大きさの穀物の輸送港であり、それはUC560年(BC194年)に建設されたと推定されているローマ市民の植民市であるプテオリ≪現在の Pozzoli、ナポリ市内のコミューン。≫に続く規模であり、さらにその下位にはコルシカ島の [これはヴェーバーの間違いと思われ、正しくはサルディーニャ島の] トゥリス・リビソニス≪Turris Libyssonis、現在のポルト・トッレスでサルディーニャ島の北西端部に位置する港町。≫の港町がそれに続いている。更に仮説として提示出来るのは、まさに scamna と strigae を使って測量され地図に記載された耕地の法律上の特質が次のようなものであったということである。その特質とは、まず当該の土地を割当てられた者が、その土地を Landtribus [平民の私有地] として扱うことが難しかったということである。次にその割当てられた耕地の質に関して、それぞれにその土地が産み出す利益との関連付けが、改めて行われていた、ということである。その利益に対して、当該の土地の所有者は、首都であるローマへの穀物供給という点で、viasii vicani ≪公道の側の土地の所有者でその公道の管理義務を負わされた者。≫や navicularius ≪小型の船舶の所有者、例えばポンペイウスはBC57年にローマへの穀物の海上輸送に従事させる目的でこうした船主にローマの市民権を与えている。≫と同様に、何らかの税(義務)が課されていたのであり、分割されて与えられた土地区画は、そういった条件付きであったが故に、[完全な] ager privatus [私有地] として割り与えられることはなかったのである。29)
29)モムゼンが確認した所によると、オスティアの住民の中にはヴォトリア人≪ローマの古代の有力な種族で、オスティア・アンティカを最初に建設したとされる。≫がいた。他方、ある銘文によれば、オスティアの住民の中にはパラティーナ人≪イタリア半島に古くから居た種族で4都市部族の一つ。≫もいたことは疑いようがない。そのことに適合するのは、土地分割における顕著な区別、つまり lacinae [断片状の土地]、praecisurae [境界で分けられた土地]、と strigae であった。lacinae については既に前に [注18参照] アンティウムにおいての、方形の土地単位による分割と、最初期の耕地ゲマインシャフトとして形成された可能性が高いものとして説明済みである。もしこの説明が正しいのであれば、オスティアにおける lacinae は古い植民市における耕地として説明出来るであろう。これに対して strigae と scamna は、その土地の受領に当たって、ローマ市への穀物供給においての一定の義務を課された所有者の耕地に対して使用されたのかもしれない。それはアウグストゥス帝の指令によるものか、あるいはもっと古くから存在したかもしれない。しかしながら、次のようなことまで述べるのは、奇を衒い過ぎているであろう。つまり、これらの3つの港湾都市について、直接的にその意味を穀物輸送 [だけ] と決めてかかり、また各都市において [それに専任で従事した] 諸部族の存在を前提にする、ということは。Navicularii[船主、単数主格:navicularius, 複数主格:navicularii] については但し、知られている限りでは、オスティアではそのような [船による穀物輸送の] 義務は課されておらず、そこでの銘文に記載されている navicularii は本来のオスティア人ではなく、よそ者である。Naviculariiは――Codex Theodosianusu のXIII、5-7を参照――むしろおそらくはただ海上輸送のための穀物積み出し港に [オスティアは積み出し港ではなく、ローマの穀物需要を満たす上での陸揚げ港] より多くいたのだと思われる。それに対してオスティアでも多数いたことが銘文によって証明されるのは、その時々の穀物価格 [annona] の決定に関与している同業者組合 [collegia、ギルド] のメンバーである。――プテオリにおいては、周知のこととして、UC560年(BC194年)に建設されたと推定される植民市と並んで、古い形での自治コミュニティ [municipium] が成立しており、それは帝政期まで続いた。植民市が存在したことの証明はそこから――その当時の状況からして妥当な理由としては――おそらくはただ穀物供給の確実性を高めることか、あるいは少なくともそれが理由の一つであったと言うことが出来るであろう。C.I.L.、X、1881の銘文は、関連する市民への金銭の分配について述べており、そこから読み取れるのは、第一の身分としてはデクリオーネス [decuriones]≪ゲマインデの議会の議員で指導者≫ が居り、二番目が皇帝アウグストゥスの配下の者達、それに続いてギルド [corporati] に属する自由市民とベテラン兵士、そして最後に自治コミュニティの構成員という順番になっており、それぞれに分配された金銭の割合は、12:8:6:4であった。ベテラン兵士は本来は手工業者のギルドのメンバーでは全く無かったので、ここの妥当な解釈は、まずはギルド [Korporation] が穀物の流通に従事していることについて述べているのであり、ベテラン兵士については土地区画を受け取る代償としてその土地に関係付けられた一定の義務 [税] が課されたのであり、自由民 [ingenui] がこの碑文では自治コミュニティの構成員 [municipium] に対立する存在として扱われていることから分かるように、古くからの植民市の市民としてその義務 [税] を負わねばならなかったのである。これに類似の例として、viasii vicani [公道の管理義務を負う公道の側の土地の所有者] や navicularii [穀物輸送の義務を課された船主] があるのである。オスティアにおいては、この種の金銭を受け取ることで、ウェスパシアヌス帝、トラヤヌスス帝、そしてハドリアヌス帝の時も継続して穀物供給義務が課されていたのではないだろうか。何故ならば、穀物流通のための労働力の需要は増大したに違いないし、また新たに割当てる土地も枯渇するようになっていたと考えられるからである。
その他イタリアにおいて、そこにおける土地の割当てが部分的に scamna と strigae を使って行われたと、liber coloniarum [植民市の本]が注記しているのは次の場所である:
アラトリ≪Aletrim→Aletri、現在ラツィオ州フロジノーネ県のコムーネ、BC306年にローマの植民市となった。≫(ケントゥリアと strigae)30)、
アナーニ≪Anagnia→Anagni、現在ラツィオ州フロジノーネ県のコムーネ、BC306年にローマに併合された。≫(strigae)31)、
アエクイコリ≪Aeqicoli、イタリアの山岳地帯に古くから住んでいたアエクイ族の土地をBC304年のアエクイの戦いでローマが支配下に置いたもの。≫(ケントゥリアの中での strigae と scamna)32)、
アルフェデーナ≪Afidena→Alfedena、現在アブルッツォ州ラクイラ県のコムーネ、BC298年にローマに征服された。≫(ケントゥリアと scamna)33)、
トリヴェント≪Terventm→Trivento、現在モリーゼ州カンポバッソ県にあるコムーネ、BC3世紀のサマニウム戦争の結果ローマの植民市となった。≫(praecisrae [境界で分けられた土地] と strigae)34)、
ヒストニウム≪Histonim、現在のヴァストでアブルッツォ州キエーティ県のコムーネ、アドリア海に面する。シーザーの時代にローマの植民市になったとされる。≫(ケントゥリアと scamna)35)、
ボヴィアヌム――おそらくはヴェトゥス≪Bovianm Vets、ローマの植民市とされるがその時代も場所も不明、現在のピエトラッボンダンテ=モリーゼ州イゼルニア県のコムーネであるという説があるが、2022年現在では疑われている。≫(ケントゥリアと scamna)36)、
アティーナ≪Atina、現在のラツィオ州フロジノーネ県のコムーネ、サマニウム人の都市であったがローマに征服された。≫(部分的に lacineis [断片状の土地] と strigae によるもの)37)、
リエーティ≪Reate→Rieti、元々サビニ人の土地でローマに征服された。現在のラツィオ州の都市で、「塩の道」の要衝だった。≫とノルチャ≪Nrsia→Norcia、現在のウンブリア州ペルージャ県のコムーネ、元々サビニ人の都市で第2次ポエニ戦役の時のローマの同盟市。≫(ケントゥリアの中での strigae と scamna)38)
である。 今挙げた全ての場所は後にムニキピウム [自治都市] ≪元老院ないしローマ皇帝から自治を許されていた都市≫となっている。それらの中の一部の都市は、証明可能なことであるが、プラエフェクトゥラ≪praefectura、ローマのいくつかの属州をまとめたものがディオエケシス=dioecesis=管区とされ、いくつかの管区をまとめたものがプラエフェクトゥラ=道{どう}とされた。≫の前段階であった行政単位の中に組み入れられた。それらの都市とは、アナーニ、リエーティ、ノルチャ、アティーナ、及びまたアエクイコリであったと思われる。ボヴィアヌム・ヴェトスについては一般に得られる情報が不足しており、詳細は不明である。また以下のことについても分っていない。つまり strigae と scamna を使った土地割当てが最初に行われたのが、ベテラン兵への土地割当ての時がそうだったのか、あるいはその時には既に先行してそういう割当てのやり方が存在しておりそのやり方が引き継がれただけなのかということである。またこのような特別な土地割当てのやり方について、何か特別な理由があったのかどうかも同様に不明である。
今挙げた全ての場所は後にムニキピウム [自治都市] ≪元老院ないしローマ皇帝から自治を許されていた都市≫となっている。それらの中の一部の都市は、証明可能なことであるが、プラエフェクトゥラ≪praefectura、ローマのいくつかの属州をまとめたものがディオエケシス=dioecesis=管区とされ、いくつかの管区をまとめたものがプラエフェクトゥラ=道{どう}とされた。≫の前段階であった行政単位の中に組み入れられた。それらの都市とは、アナーニ、リエーティ、ノルチャ、アティーナ、及びまたアエクイコリであったと思われる。ボヴィアヌム・ヴェトスについては一般に得られる情報が不足しており、詳細は不明である。また以下のことについても分っていない。つまり strigae と scamna を使った土地割当てが最初に行われたのが、ベテラン兵への土地割当ての時がそうだったのか、あるいはその時には既に先行してそういう割当てのやり方が存在しておりそのやり方が引き継がれただけなのかということである。またこのような特別な土地割当てのやり方について、何か特別な理由があったのかどうかも同様に不明である。
30)liber coloniarum 230, 8: Alatrium, muro ducta colonia. populs deduxit. iter populo non debetur. ager eius per centurias et strigas est adsignatus.
[アラトリという町は、(ある)植民市において壁によって区切られていた(区画にあった)。(ローマの)人々がそれを拓いた。そこでは道路は個人の所有にはなっていなかった。そこの土地はケントゥリアとstrigaeによって分割割当てされた。]
31)上掲書、P.230、17行目
32)P.255、17行目
33)P.259、19行目
34)P.238、10行目(正しくは14行目、全集の注による)
35)P.260、10行目
36)P.231、8行目
37)P.230、5行目
38)P.257,6~26行
こうした特別な土地の分割割当ては、例えば売却禁止の土地を与える場合に使われたのかも知れない――そしてこのような割当てはアウグストゥス帝によっては行われなかった、という仮説は、考慮の余地がなく誤りである。その理由は、周知のこととして、この種の土地の売却が禁止されていたということが、その土地に課せられることになっていた税金に対する [皇帝の] 承認によって法的に明確に示されていたからである。アエクイコリの耕地は更に、[アエクイ族の] 鎮圧がされた後にいずれにせよ [ローマの新たな土地として] 公にされたのであるが、しかし多数の文献情報によればそれは個々人には割当てられず、おそらくは [小作地として] 賃貸しされたのであり、だからこそ scamna [と strigae] を使って土地が分割されたのである。プラエフェクトゥラにおいては、少なくとも部分的には同様の事情が存在していた。そういった場所は多くの場合同様に戦争に勝利した結果として得られたものであり、その理由から [元々の] 土地所有者の立場としては、おそらくはその土地に対する権利がいつでも取り消されることがある、という前提に置かれていた。ボヴィアヌム・ヴェトスについては、そこが別名として Bovianum Undecimanorum [1/10税が免除のボヴィアヌム] と呼ばれていたことから推定して、十分確からしいと考えられることとしては、それは元々の土地の所有者に対して、その土地の使用料を徴収する権利が与えられた、そうした人々が集まった自治組織であったと解釈することが出来る。リエーティについてシクルス・フラッカス≪2世紀に生きたと推定される古代ローマの測量人・著述家≫が言及している内容によれば――P.136、20行目――多数の agri vectigalis [課税対象の土地] が存在しており、ピケナム≪Picenum、現在のマルケ州の南部、元はガリア人の土地だったのをローマ人が入植を進めた。アウグストゥス帝が定めた行政区分であるRegio Vとなった。≫についても同様であり、ヒストニウム≪Histonium、現在のアブルッツォ州キェーティ県のヴァスト、元々フレンターノ人の土地で、植民市ではなくムニキピウム [自治都市]。≫においての scamna で分割された土地ももしかするとピケナムの土地と同様に扱われたのかもしれない。≪ピケナムとヒストニウムはかなり離れており、原文直訳の「ヒストニウムの土地がピケナムに属していた」、という記述の真意は不明。ここでは同様のやり方が適用された、と解釈した。≫最後に残った可能性は、ある特定の場所のある部分において、つまり liber coloniarum の中でケントゥリア及び strigae と scamna によるよる土地の分割として言及されているような [ある土地のある] 部分は、単純に以前(全集版原文のP.111)ここで述べたベテラン兵への3分割した土地の割当てとして行われたというものである。そしてそれは次のようなやり方で行われていた。つまり、測量人が一つのケントゥリアを2つの [原文は3つの ] 平行線で3つに分割し、そしてそれぞれの [長方形の] 部分を縦が長い場合に strigae、あるいは [横が長い場合に] scamna と名付けられたのである。これが行われた理由はおそらく次のことによる。つまり、ヒュギヌスの時代において新しい方法として言及されているものが39)、つまり分割したそれぞれの土地の境界線を、ager centurias [ケントゥリアによる分割地] であった土地についても測量地図上に記載するということが、既に一般化していたということによる。
いずれにせよ以上見て来たような実例が示していることは、特にスエッサ・アウルンカの例は、ager privatus として strigae と scamna を用いて土地を割当てることも十分に可能であったにも関わらず、別のやり方が採用されており、その大部分の場合で、それぞれ何か特別な理由があってそうされたのであろうということは、かなりの程度間違いが無いということである。
39)P.121(全集注によれば正しくはP.119f)、前掲書
課税可能な植民市の土地の測量
他方、scamna と strigae を使って、その土地の権利を制限された形で [ager privatus としてではなく] 割当てられたのは、必ずしも [土地割当て対象者の] 全員ではない、ということもまた確かである。課税可能な属州の土地の後の時代における割当てについて、ヒュギヌスは先に引用した箇所で、ヒュギヌス自身はそれに反対していた立場だったようであるが、はっきりと次のように証言している。それはつまり、scamna と strigae を使った割当てが、通常のケントゥリアと limitesを使った方法において [併用する形で] しばしば行われていた、ということである。そのことの実例におそらくなるのは、添付図1の中の銘文であり、そこに書かれていることによれば、明確にそれは測量地図のコピーの一部であると述べられている。
土地の分割がケントゥリアによって行われたということは、その測量地図の断片上の表示から明らかである。≪以下の文の原文中のMaaßeはMaßeとして解釈した。≫ここでのケントゥリアの各辺の寸法は次の比率となっている。[ヒュギヌスが引用している] ニプサスの書に出ている scamna によって分割された耕地は、240ユゲラの面積のケントゥリアにおいて分割が行われたのに違いなく、その場合の辺の比率は(6:5)[24 actus : 20 actus] となる。ニプサスはここでは明らかに、scamna によって分割された土地を課税対象の耕地として捉えている。というのもアラウシオにおいての scamna による分割地においては、そこの地図 [添付図1] が示しているように、単純な均等割当てが行われたのではなく、明らかに個々の土地所有者 [割当て対象者] に対し、様々なケントゥリアにおける様々に異なった土地面積の実質的価値に応じた割当てが行われたからである。それは課税されることがなかった植民市における土地分割のやり方とまったく同じであった。モムゼンによる信頼性の高い原文修復の結果によれば、それぞれのケントゥリアでこのやり方は繰り返し行われている:”ex trib(utario) [tributario = 課税対象の、課税対象の土地から] ――その部分に対して数字が記載されている――red(actus) in col(onicum) [植民市において非課税の土地として与えられた]”――こちらについてもまた数字が記載されている。ヒュギヌスがP.121で描出している箇所は、まさにこういった場合についてであり、そこでの描写は次の通りである:それまで測量がされておらず、割当てもされていない(arcifinisches)[新たに占領した敵地など] 課税対象となるべき属州の土地が測量され、そして(免税とならない)アラウシオの植民市における境界線で分けられた耕地において、(新たに課税対象地としての)土地割当てが行われた。アラウシオは [ガリア遠征による] シーザーが征服した土地における植民市である;そこでの全ての耕地がその当時分割され割当てられたかは不明である。しかし碑文が刻まれた石自体が元の測量地図と同じくらい古いものである必要はない。何故ならばそれは単なるコピーに過ぎないからである。
“redactus in colonicum” [植民市において与えられた] という表現は次のことを示している。つまり、その領土のある部分は、植民市の土地としてようやく後の時代になってから [土地割当てなどの用途に] 転用されたのであると。アラウシオにおける耕地の分割は、常に、[様々な文献で]何度も引用されているマミリア法 ≪Lex Mamilia Roccia Peducaea Alliena Fabia、Corpus Agrimensorum Romanorum の中に3つほど断片が収録されている、割当ての際の土地の最大の面積を定めている法。≫ の中のシーザーによる命令に従って行われている。シーザーは良く知られているように、海を渡った土地の植民市について、最初にそれを大規模に切り開いたが、 そのことから明らかなこととして推測出来るのは、このマミリア法における彼の命令が、属州の土地に対しても適用されたということは、ケントゥリアによる土地の割当てが非課税の土地についてだけでなく、課税対象となる土地についても適用されたということの、まさに証拠であった。この形の土地割当ては、植民市における平地の測量においても、次の理由から不可欠なものであった。つまり、測量人達は規則に従いながら異なった面積の土地を、それぞれの価額に応じて分割せねばならなかったのであり、それを scamna を使ってやると多大な労力が必要だったのに対し、他方ケントゥリアを使えば単純にあるケントゥリアではXユゲラ、別のケントゥリアではYユゲラが、それぞれ等しい価値を持つものと設定出来た、そういう理由からである。
ager quaestorius [財務官{クワエストル}が収入のため売却した公有地] における測量とその法的な性格
それにも関わらず、以上見て来たようなある意味原則からの逸脱とも考え得る現象から更に見て取ることが出来ることとしては、通常 [の私有地として] よりも権利が制限された耕地が存在したということである。そういう耕地は scamna をベースにした土地割当てが行われていなかった。これらは ager quaestorius であり、つまり次のような土地であった。それは定期的な土地使用料の支払い ≪Rente≫ を条件にして国家から与えられるのではなく、一回だけのお金(資本)の支払い [購入] を条件として与えられた土地である。
この ager quaestorius の場合の土地分割については次のやり方が知られている。つまり、limites を用いて四角形の土地(laterculi または plinthides)を切り出し、それは一辺が10 actus の正方形=面積50ユゲラ [10×10÷2] の平面、として作られ、これらの土地区画が――規則に則って、オークションのようなやり方で――購買希望者に対し公開され、それからその測量地図が作られ、その地図の上にその土地を買った(受け取った)者の名前が、その者に売却された土地の面積と一緒に記載されたのである。40)
40)上掲書のP.115、P.110の8行目、P.125の下部、P.136の15行目、P.152、P.153の3行目、P.154。
この ager quaestorius と ager centuriatus の本質的な違いは、laterculi の面積がケントゥリアとは違うという点にあるのではなく、limites がここでは小路 [道路] ではなく、その文字通りの意味の通り単なる境界線 [リミット] となり、事実上は単に decumani の線を「分割するもの」となっており――それはこの名称が東西と南北の方向に関係なく使われていることからも分る。ここにおいての limites は [ケントゥリアの場合そうだったような] 公的な道路システムの意味で使われているのでは全くなく、ただ Raine [境界] の意味で使われており、それはそこにおいて土地の売却が行われた、個々の土地区画の境界を形作るものであった。それは scamna における rigores [直線] と同じ意味であり、その証拠としてシクルス・フラッカスは”limites, id est rigores” [limites 、それは直線である。] と書いている。ここでの limites は一番最初の土地分割の際の境界設定という意味しか持っていなかったので、その他の場合においてはその土地の継続的な権利保持の保証にも根拠にもならなかった。それ故に所有者が変わった場合には、limites 自体は消滅してしまっていた。そのために(フロンティヌス、P.154、5行目)次のような記述が残されている:”emendo vendendoque aliquas particulas ita confuderunt possessores, ut ad occupatoriam condicionem reciderint” [私はある土地区画の境界線を修正した上で売却する。そのように土地の所有者達は個々の土地区画を合筆し、新たな{売却のための}占有契約のために新しい境界線を設定する。]。
様々な種類の土地の法律上の性質については後で更に詳しく述べるが、次のことを理解することが不可欠であると思われる。つまり、ager quaestorius については、土地と法律の関係という問題を先取りしていたということである。というのはこの制度において本質として理解すべきことは、事実上分割の方法と分割された土地の法律上の価値との意識的な関連付けが行われていたことである。
ager quaestorius の法的な性質については、これまで不十分な形でしか解明されていない。当時の測量人達の情報によれば、それは征服によって獲得された耕地に対して、ローマ市民から財務官(クワエストル)への委任に基づいて売却された土地であるとなっている。しかし私はモムゼンの推定 (C. I. L., I の lex agraria の c. 57. 66)と一致して、ager quaestorius はローマ市民の決定に基づくのではなく、元老院が決定し財務官に委任したものであると考える。更には次のことも想定できよう。それはこのやり方と関連がある trientabula (後述)≪国家債務の返済の際にその金額の内の1/3を現金ではなくそれに相当する価額の土地で返済すること≫のやり方を参考にすると、lex agraria の規定から派生したこととして、その土地の所有権を完全に購入者に与えるのではなく、ただ “uti frui licere”[使用する権利、(貸すなどして)利益を得る権利、売却する権利]だけが約束されている[つまり買い戻す権利が留保されている]ものであるということである。従ってここで扱われているのは、[完全な]売却という行為ではなく、財産管理上の[ある意味で勘定科目の変更のような]行為なのであり、それはケンススを実施する上での[ある土地の]場所の確定という目的にも沿っていた。何故ならば、ager quaestorius は財務官が国家の財産を[一時的に]売却することにより現金を得る形態なのである。それは言い換えれば資本の払い込みに対し使用権を引渡すことであり、ケンスス上の扱いでは、それは賃貸し、つまり使用権を与える代わりに使用料を取るということである。モムゼンが述べているこのことについての理由以外に、またそこからさらに発展させ、私はまた次のことが確かに言えると考える。つまり ager quaestorius は、例えば名目的な承認に基づく使用料(地代)の支払いという観点では、使用料(地代)支払いを義務として強制するような性格のものではない、ということである。それではこの場合、[土地を購入した]ローマ市民に対して継続的な所有権が認められるという[法的な]効果[通常の売却-購入との違い]は、この方式のどこにおいて現れるのであろうか?純粋に私法的な関係においては、所有権の移転[vindikation]と握取行為[物件を移転させる際に契約以外に必要とされる一種の儀礼的行為]が行われない、という点にそれは現れている。国家権力との関係については、再度モムゼンによって示された(C.I.L、上掲箇所)推定と一致するが、次のことが非常に確からしいと思われる:それは ager quaestorius の trientabula との類似ということで、そのようにモムゼンは引用の箇所で主張している。trientabula が最初に行われたのは a.u.c. 552年[B.C. 200年]のことであると、リヴィウスは1. 31の13章で述べている。
“Cum et privati aequum postularent nec tamen solvendo aeri alieno res publica esset, quod medium inter aequum et utile erat, decreverunt, ut, quoniam magna pars eorum agros vulgo venales esse diceret et sibimet emptis opus esse, agri publici, qui intra quinquagesimum lapidem esset, copia iis fieret. Consules agrum aestimaturos, et in jugera asses vectigales testandi causa publicum agrum esse imposituros, ut si quis, cum solvere posset populus, pecuniam habere quam agrum mallet, restitueret agrum populo.” [その市民達の要求は正当であり、そしてそれにも関わらずローマ共和国が要求された金額を支払うことが出来なかったので、元老院は次の処置を行ったが、それは正当性を実現しようとしたのとその場しのぎの中間にあるようなものだった。それは国家の土地で、大部分が公的に売りに出されており、その購入には現金での支払いが必要とされたもので、ローマから50番目の里程標の内側にあるものが、それらの市民に対し[現金で返済する代わりに]与えられることが出来るとされた。コンスルはそういった土地の価額を見積もり、そしてその土地について課税対象として使用料金を定めることとなった。その理由はそれらの土地が元々国家の土地だからである。そしてローマ市民でありローマ共和国への債権者である者の内の誰かが、土地よりも現金を選んだ場合には、その者は土地をローマ市民に返却することが出来た。]
法的な観点で分析した場合、ここでの手続きはつまり次のようなものである。ここで描写されている耕地は、ローマ国家に対する債権者達に後で買い戻すことを前提として売却されている。その土地の売却価格としては、借り入れ金の内未返済のものの1/3の金額が使われており、そこから trientabula [triens = 1/3]という名前で呼ばれた。土地を再度買い取らせる権利を持っていたのはその土地を買った者達だけであり、それもローマの人民がその資金を払うことが出来る場合のみであり、売主である国家がではなく、ローマ人民が、である。このように全くのところ国家の債務の整理を目的とした業務、まあそう言っても構わないであろうが、国家による個人への土地の売却という形を取っている。そしてそれはその法的な本質としては明らかに売却という大きな枠組みの中でのみ行われ、そして個別の特別な事例に適合する協定を取り結ぶことによって、ager quaestorius においての売却のやり方とは異なっていた。その当時債務者であった国庫は、この方法を非常な困窮の中でやむを得ず行ったのであり、だからこそ次のことが理解出来る。つまりこの売却の特殊性が協定という形を取らざるを得なかった理由であり、その場合に買い主は一般的な場合と比べてより有利な形で土地を買うことが出来た、ということである。次のことは自明である。つまり、こういう買い主に対する特別扱いに見出すことが出来るのは、土地の買い戻しを実行させる権利を持っているのは、買い主であって国家ではない、ということである。私見ではその他の場合ではこれは逆であったであろう。この点について考えられるのは、ager quaestorius の本来の法的な特性は、国家に帰属する買戻し権であった、ということである。41) この一度売却した土地の買い戻しの権限は、ローマ法の規定にもある”habere uti frui licere”[所有すること、使用すること、それを使って利益を得ること、それを売却すること]≪元は”habere possidere uti frui licere”であり、 possidere =占有すること、を抜いた形で引用されている≫にも合致している。その規定は公法的には不安定な土地所有というものを言い表した”εχειν εξειναι”[所有することを許されている]という S. C. de Thisbaeis ≪引用元は後述される≫の表現と法的には同じである。更に ager quaestorius [の買戻し権]が本来国家に帰属する権利であるということは、次のこととも矛盾しない。つまり、この形での土地の授与の基礎が築かれたのは元老院勧告によってであり、(明らかに)民会の決議によってではない。しかも更に、おそらく次のことも想定出来る。それは国家が所有権を購入という形で移転させるのであり、そのため公的な建造物の贈呈と引き渡しの際には、[それに付随する]余剰の土地は監察官[ケンソル]によって「(公有地から)私有地に転換する」形で売却されたということである。(Liv. AG40 40. 51, 5. cf. 41. 27. 10)しかしながらこの贈呈の手続きについては民会の決議を必要としたので、この場合の[土地の売却の]手続きもまた前もって特別な売却として[法的な]効力を与えられていた。42) いずれの場合でも元老院勧告は国家の所有物[である土地]を、規則に沿った形で完全に私有物化することを認めるまでには至っておらず、一方民会の決議は更に厳格に無条件に売却した土地の買い戻しを定めており、その当然の結果として土地の購入者はその購入の際に支払った金額全額の返還を要求するようになった。このことにより、推定して来た本質的な土地の買戻し権というものが成立しているのである。モムゼンが仮定しているように、ager quaestorius による土地の売却がローマの国庫の一時的な資金需要に応えるものであったとしたら、その場合我々は信用引き受けのこうした原始的な形態を見ると、直接的に中世における金融経済においての Satzung [不動産を抵当に入れた借り入れで、占有を条件とする古質(こしち)とそれを条件としない新質がある]及び買い戻しが前提である土地売却が思い起こされる。中世における諸都市においてと同様に、より洗練されたやり方であるRenteによる借り入れ[地代徴収権売買、レンテンカウフ]がまだ認められていなかった限りにおいて、古代ローマの場合はそれ故特別な場合での資金創造の形態としては次の2つに限定された:強制税(=tributum )と土地の買い戻しを約束した上にで売却するという形態での自然物の質入れである。その他の ager quaestorius による売却のやり方としては、当時の測量人達が述べているように、征服し占領した土地について即時に現金化するやり方もあった。――実際に存在したのは、前述の箇所で確認を試みたのであるが、国家のそのような買い戻し権の方であり、それはそれ自身がある種の土地の強制収用権であり、ager privatus に対して[の公有地化の方法としては]それ以外のものは知られていなかった。――そして植民市の耕地についてである限りは、例えば水道を設置するという目的等で行われたに違いなく、[ローマ法の]建築に関する法規の中で特別な権利として留保された。その例としては lex colon[iae] Genetivae c. 99 (Eph. epigr. II, p.221f.)があり、――そして次のことが考えられる。つまり何かの代償と引き換えによる、三頭政治の時代における強制収用が、ある場合はこの ager quaestorius において生じた[買い戻しの]権限に関連付けられ、また別の場合には古くからのやり方である占有による所有の不確実性に関連付けられた。そして後者の場合は、強制収用は統治者[三頭政治の政治家]の特別に完全な権力により、それによって収用された土地は ager privatus per nefas [違法な私有地]へと転換されたのである。43)
41) ルドルフ[Rudorff, Adolf]は(Gromatischen Institutionen の中で)次のことを仮定している。つまり国家は購買しようとする者との関係に応じて、それぞれ異なる内容の協定を締結していたと。売却対象の耕地のみが、我々には唯一の統一された制度として把握される。
42) Liv. 40, 51, 5 の場合は”M. Fulvius … locavit … basilicam … circumdatis tabernis, quas vendidit in privatum” [M. フルヴィウスは…契約した…その会堂を…その周りにある小さな建物については、私有物化する形で契約した]という箇所は、つまりある国家の所有物の譲渡が民会の決議無しに行われており、またそこに見出されるのは、その建築物の敷地については建物を譲渡する前に始めて購入されたのであり、その建造物の完成と譲渡の認可を得るまでの過程において、敷地については売却側の役所がそれを自由に処分出来るものであったと思われる。Liv. 41, 27, 10については、譲渡に際して in privatum [私有物化された]とは書かれておらず、おそらくそれは実際にそうであったのであろう。
43) 三頭政治の時代の土地の強制収用の法的根拠は、それが[征服した]敵の所有物を没収するのではない場合にははっきりしない。そういったケースの一部ではそもそも法的根拠がまるで存在しなかった。強制収用が如何に容赦なく行われたかをもっとも良く示しているのは Siculus Flaccus (p.160, 25)の注記である:ある数の土地占有者は公的な宣告を受けて[zur professio]その占有地を召し上げられた。その表向きの理由は土地の[再]割当てとケンススへの登記である。しかしそれが宣告された後に、その土地の占有者は宣告に基づいてその土地の税金相当額が支払われた上で没収された。その没収について裁判となった場合にも、それは結局[没収した側に]罰金刑が言い渡されるだけであり、その金額は当初の宣告の際のその土地の評価額に一致していた。ここではただ強制的な購買について述べられているのであり、また別の土地占有者への補償について言及されている箇所では、その補償自体が問題とされている。こうした土地の占有者に関しては、測量人達の間では、以前グラックス[兄弟の兄]が使った表現である「以前の占有者」[vetus possessor]が思い起こされていた。(C. Ⅲ 参照)
今の議論で得られた仮説としての成果[ager quaestorius と強制収用の共通性]をager quaestorius の実際の分配の仕方――おそらくそれはまた trientabula の分配方法でもあったと思われるが――にて比較検証してみた場合、対象の土地に測量が行われている場合で、それについてはリヴィウスの報告が明らかにしているが、その場合に両者のやり方は非常に良く合致している。というのはその際に個々の土地区画に対して何らの課税もされず――あるいはただ名目的な税のみがあったか――というものであったからである。limites の確定は課税対象となるべき土地区画の所有境界を明確にすることを可能にしたであろうが、行政管理上の目的はほとんど持っていなかった。なるほどもしかするとそのような土地区画の境界線の確定は、国家が買い戻し権を行使する際の払戻金についての簡易的な確認証の役目を果たしていたのかもしれないが、しかしながらそのような 買い戻しの執行において、通常はそのようなことはまったく考慮されていなかった。しかしそれでもそういった買い戻しの執行が実際に行われており、それは当時半分革命的なやり方として人々に捉えられていたのである。強制収用[を後になった行った者達]はそこにおいて、土地の境界が limites の確立という形で修正させられた場合に、そのことがその土地の元の権利者達がその土地に対し以前いくら支払ったかを証明出来ていたかどうかといいうことに注目していた。測量地図上にはいずれの場合も売却された総面積の範囲が地図の技法で描かれており、そしてその面積の数字と、売却した相手方、更に売却価格が記載されていた;しかしながら limites がいつも描かれていたかどうかは疑問がある。43a) このことについては、私は以下のように考えたい:つまり、より古い時代においては scamna と strigas による土地の配分はケンソルの目的のためには [ケントゥリアによる測量と]全く同じく典型的な方法であったのであり、それは locatio [賃貸し]という[法的]概念に適合していた。それは limites で境界付けられた四角形の土地[latercui]が財務官[quaestor]の[一時的に現金を得る]目的のために分配されたのと同様のことであった。そちらはvendito [(買い戻し権付きの)売却]と呼ばれた土地の譲渡であってより少ない権利しか買い主には与えられなかったのであり、その一方でscamna と strigas による譲渡の場合は[「賃貸し」という名前の通り、使用料としての税金が課せられたものの]完全な所有権が与えられたのであると。
43a) もっとも測量地図上に土地のサイズが記載されていたかどうかも推測の範囲でしかない。
しかしながら後の時代になると、既に述べてきたように、様々な土地配分の方法が混同されるようになってきて、それについて可能性があるのは、グラックス兄弟による公有地配分政策がそのきっかけになったということである。グラックス[兄のティベリウス]によって市民に分配された土地は ager privatus [私有地]にはされなかったにも関わらず、グラックス[兄]は明らかに[本来は ager privatus 用の測量方法であった ]ケントゥリアの[1ケントゥリア以上の土地を個人が所有出来ないという]制限を好都合な道具として利用したのである。ある一面ではこのやり方は lex agraria に示されているように、まず同一面積のケントゥリアを設定し、それを2等分割するするという土地割当てが頻繁に行われることにつながったのであり、また概して言えば、大きな混乱ももたらしたのである。もしかするとこういった純技術的な欠陥が、彼の政策を失敗に終らせそして公有地の私有財産への転換を必然的にした、決して小さくない理由の一つかもしれない。
ここまで[ager quaestorius について]詳論してきたことの成果としては次のようになる:二つの測量方法であるケントゥリアによるものと、scamna によるものの間の関連が、土地に対する法的な評価という点において、これまで述べて来たような内容で存在しているということである。その際に、ヴォイクトの説のように、二つの土地分割の方法がそれぞれ別の民族的起源を持つ可能性がある、ということまでは主張していない。

Von Iron Age Italy.png: DbachmannIron Age Italy.svg: Ewan ar bornabgeleitetes Werk Timk70 – Iron Age Italy.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31433614
もしイタリアのポー平原上の郊外村落が、実際に長方形の土地で区画され、方向付けされているとしたら、そのことは長方形区画を使った測量方法が、古代イタリアのウンブリイ-サビニ族≪ラテン-ファリスカー族連合と対立した古代イタリアの有力部族連合、左の地図参照≫によって確立されたものであるということを非常に確からしくするであろう。正方形による土地分割を使った測量方法の場合、グローマを使った[最初の]測量人自身が、エトルリア人[ローマの先住民]であったのではないかと推論付けられているが、それが正しいかどうかは未定とするのが正当であろう。またその際にギリシア人の影響もあった可能性がある。≪グローマの起源は紀元前4世紀以前のメソポタミアであり、それがギリシアからエトルリアに伝わり、クラネマというエトルリア人がローマに伝えたとする仮説がある。≫しかしながら以上のような二つの測量方法の起源に関する議論は次の事実に何も影響を与えない。それはつまり、この二つの方法が[ローマに伝わった]後にローマの行政によって注目され[両方が]使われるようになった、ということであり、それについてはここまで詳論してきた。
Ager per extremitatem mensus comprehensus [領域の外周部のみが測量され、その内部が区分けされていない土地]について
我々は次にグローマで測量された土地の第三のジャンルである ager per extremitatem mensus comprehensus を取上げる。それはその名前[外周を取り囲む境界線のみが測量された土地]が示す通り、耕作地の地図において、ただ外側の境界線のみが描かれていて、[scamna/strigae またはケントゥリアによる]個々の区画割りが行われていない土地のことである 44)。ここにおいて、この分類名で測量された領域についてその法的な意味を説明出来るとすれば、次のことが確からしいであろう。つまり第一に[何らかの理由で]ローマの領土から外されたか、あるいは敵の降伏によってローマの領土となったものの一部分の領域が特別扱いされた場合に適用されたということである 45)。一方ではその領域は ager privatus [私有地]としては扱われず、他方では特別扱いされたといっても依然としてローマの行政管理下にあったものであり、しかし結局のところは個々の土地区画の所有者のローマの国家に対する納税義務のある土地とはならなかった、そういう領域である。このことを裏付けるのは、この分類の土地がまず第一に神殿[教会]付属の土地について適用されたということである。(Hyg., de cond, agr. p.117, 5; Sic. Flacc. 162, 28; Hyg., de lim. 198):その土地は非課税ではあったが、しかし[本来は課税される] ager publics [公有地]のままとされ、国家は疑いようもなく、[行政管理上]その領地の[場所や面積の]確認とその領域を確定させることの可能性について関心を持っていた。しかしこの種の測量は更に言えば、その領域に依存することになる神殿[教会]の占有に先立って行われ、その後その神殿[教会]はその領域を一定の支払いを代価として、譲渡されるかあるいは占有を認められた。神殿[教会]はその土地をそのような性質のものとして受け取り、また今度は神殿[教会]自身が[その構成員に対して]割当てを行ったのである。そう言える根拠はフロンティヌスがはっきりと次のように述べているからである。Ager per extremitatem mensus comprehensus は測量された[分割されていない]土地の全体がローマの市民[=ローマの国家]または[神殿や教会に]従属する人民に割当てられた場合に適用されたのであると。
44) フロンティヌス、p. 4
45) Per extremitatem として測量された非課税の土地及び山林、そして土地の範囲とそれらとのローマの行政組織との関連については、第4章の関連箇所にて論ぜられる。
フロンティヌスはこの測量方法が実際に行われた例として、ルシタニア≪現在のポルトガルおよびスペイン西部≫のサルマンティカ≪現在スペイン北西部レオン地方のサラマンカ県の県都サラマンカ。第二次ポエニ戦争の時にローマの属州となった。≫及びスペイン方面に派遣されたパラティーニ≪Palatini。ローマ皇帝の護衛を勤める精鋭部隊。≫について述べている。[しかしながら]サラマンカ・パレンシア≪現在スペインのパレンシア県の県都。属州の中でのローマ軍が駐屯した都市。≫で発見されている碑文の内容は、これまでの我々の議論をほぼ完全に破綻させてしまう。何故なら Aggenius Urbicus≪4世紀後半に生きたと推定されるローマの技術書の著者。Corpus Agrimensorum Romanorum の中でフロンティヌスが彼の著作についてコメントを加えて紹介しているものがある。綴りは何種類か有り確定していない。≫は最初のゲマインデ[サラマンカの地方共同体]を vicus [ローマの村落]と呼んでおり、そして[サラマンカとパレンシアの]2つ共が課税された自治都市であった。しかしながら更にフロンティヌスが注記しているのは――こちらの方がより重要なのであるが――次のものである:”compluribus provinciis [tributarium] solum per universitatem populi est definitum.”[いくつかの属州においては、課税対象となる土地は、ただ住民の総意によってのみ決められた。]≪オリジナルのテキストでは”tributarium”が入っているがヴェーバーの引用では抜けている。≫ここについてはただ[その属州の]種族で、まだローマの都市法が適用されていなかった者達に関連付けられるであろう。実際にこの表現に適合する文献史料が存在している。それはサルデーニャ島にいた種族である Patulcenser と Galilenser ≪どちらも詳細は不明であるがサルデーニャ島のエステルツィーリ近辺にいたと推定される。なお後者の綴りは正しくは Galillenses。≫についてのものであり(C. J. L. X, 7852)、その耕地は a.u.c. 640-643年の間[BC114-111年の間]において、M. Marcellus [M. Caecilius Metellus、BC115年のローマの執政官。]によるその属州の一部への新法の適用の際に測量が実施されている。二つの種族間の境界を巡っての争いは――測量人達の間で controversia de territorio [領土を巡る争い]と呼ばれているその意味で 46)――[ローマによって測量が行われ作成された]測量地図を巡って行われた。それは三部作成され、一部がローマ市において保管された。そしてそれがローマにおいての測量地図の基準を満たしている場合には、それに関する争いはローマの地方総督≪Proconsul、執政官は1年任期であるが、それを辞めた後執政官の代理として1~3年間ぐらい属州に派遣された。≫によって裁かれた。この場合各種族の土地の区分けと個々の割当てについてが問題となったのではないであろうから、むしろ特徴的なことは、それぞれのゲマインデ[地域集団、ここでは二つの種族のこと。]がそれぞれの種族の[自分達が自領と考える]全部を一まとめにしてこのような訴訟を進めたのであり、それ故にこの場合争いの対象になっている土地は、ただ Ager per extremitatem mensus comprehensus であったと考えられる。
46) モムゼンは(C. J. L. 1.c.)において、この判決を決定通告[Schiedspruch]と呼んでいる。私はこれに反対である。何故ならば和解のケースは言及されておらず、逆にまず明らかに一方的な訴えが先立って行われており、そしてそれに対する相手方の異議申し立てと[判決の結果としての]強制執行がそれに続いているからである。[つまり通常の裁判形式そのものである。]少なくとも私はそれが課税対象の[ゲマインデの]共通の財産[である土地]を問題にしているが故に、それが通常の法的な訴訟であるとう考え方は、もちろん特別法の形態ではあるが(更に現物執行も行われているし)、まったく無理がないと考える。
しかしながらこの[Ager per extremitatem mensus comprehensusという]測量方式は、また都市部の諸ゲマインデにおいても使われたに違いない。S. C. de Thisbaeis (Ephem. egigr. I p. 278f)によれば地方総督は[執政官から]5人の男達に対して土地の割当てを委託することを命じられている。その目的は、[第三次マケドニア戦争の結果マケドニア属州の一部となっていた]ティスバイ≪Θίσβη 後にまた Θίσβαι。ギリシアのボイオティアの都市、ヘリコン山の南の麓≫との関係を整理することであった。(οις τα καθ’ αυτους πραγματα εξηγησονται[誰であっても、自分自身に関係することについて説明されるであろう])それから地方総督は5人それぞれに委託した土地の割当てについて、どのような[法]原則に基づいてそれを行わせるかについての指示を与えられた。ティスバイの人々は、碑文に示されている通り、元々[旧来の支配者によって]課税されていたのであり、それはそのまま維持されねばならなかった。その耕地についてはローマに降伏したことにより、ager publics [公有地]となったのであるが、それがこの場合意味するのはそれらの耕地はティスバイの人達にとっては、”ημων ενεκα εχειν εξειναι”[私達が所有することを許された]ものであった。そのことによって[改めて]土地の割当ては行われず、その代わりに外周の境界線が[正規のローマの土地という意味で]設定され、そして次にその土地の測量地図を作成することが決定された。その理由はその領土がその土地の人々に改めて返還されるのはただ行政行為、つまりローマの公法に基づいた請願という形でのみ行われるためである。次に周囲の境界線の確定は、その土地に対して将来何か別の処理(例えば場合によっては植民市化など)を行うケースを留保するという意味で、国家にとって本質的に利害関心があることだったからである 47)。中でもまさにこの目的のために行われたのが、次の委託命令であったことは明らかである。それはカエサル[皇帝]が行った5人の男達への[行政事務の]委託であり、その委託[に基づく土地のAger per extremitatem mensus comprehensusによる測量]によって、法律が定める一般的な方法に適合した形で、[ティスバイの]土地が[合法的にローマに]譲渡された。その方法とは、[様々な文献で]何度も引用されている lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia [マミリア法]で規定されているものである。Ager per extremitatem mensus comprehensus 以外のさらに別な[例外的な]測量方法については、これ以上ここでは述べることはしない。
47) また別の例として、lex agraria (a.u.c. 433年=BC111年、土地改革法)はまた、アフリカの土地[第三次ポエニ戦役で完全に滅亡したカルタゴの土地がローマの属州になったもの]について規定しており、それは課税地としてローマに譲渡されており。これもまた公共の測量地図の中に記載されねばならなかった。しかしそのことは属州としての法的地位の決定の際と、またグラックス兄弟の兄による土地配分の際に、概念の混同によって、結局行われなかった。我々はここで、カルタゴでは一体誰に結局土地が割当てられたのかいう疑問について、第三章でまた取上げる。
属州における税制との関係
しかし私は一般論として次のように考える。つまり全ての本来の意味で課税地である諸ゲマインデ[地方共同体]について、その本来の意味とはそこの資産が[ローマとの]自由な協定に基づくのではなく、支配する方のローマ国家から見て取り消し可能な[一時的]取り決めに基づいているということであり、そしてその際に――これがもっとも重要なのであるが――支配する方の国家に支払う税は個々のゲマインデの個別の成員に課されたのではなく、そのゲマインデ全体に対して[まとめて]課されたのであり、そのように執行され、またそれぞれにある決まった基準に従って執行されたに違いなく、そしてこの考え方は上記に引用したフロンティヌスの言葉[Ager per extremitatem mensus comprehensus は測量された[分割されていない]土地の全体がローマの市民[=ローマの国家]または[神殿や教会に]従属する人民に割当てられた場合に適用されたのであると。]にもっとも良く適合するのである。
次のことは周知のことである。つまり帝政期の属領において、またとりわけ拡大していた皇帝直轄領においても、更なる税制の構築が進められていたということである。ある種の発展、それは既に[初代皇帝であった]アウグストゥスによって始められていたし、その本来の意味での初回のものが多く語られてきたイエス・キリストの生誕の際の帝国全体のケンスス≪参照:新約聖書、ルカ2「1 その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に、登録をせよとの勅令が出た。 2 これは、キリニウスがシリア州の総督であったときに行われた最初の住民登録であった。」(聖書協会共同訳、2018年)≫だったのであり――そのケンススは帝国の全ての課税対象地についての一般的調査ではなかったのは間違いなく、そうではなくおそらくそれは全てのまたは大多数の皇帝領において同時に執行しようとしていた[新たな]課税手続きであり、それは土地に対しての税のみを、概して直接税のみを諸ゲマインデの毎年の土地税として設定しようとしていた、そういう傾向を示していた。この[税制構築という]実務が遅遅としてしか進まず、しかもしばしば完全に中断されたこともあったのは明らかである。しかしながら皇帝による課税政策はまた急務でもあった――これについては後でまた述べることになるが――そのことは次の結果から判明する。つまりこの課税政策はコンスタンティヌス一世の時代になると最重要政策として実施されていることが見出されるのである≪同帝は様々な都市や建造物の構築を進めたため、その財源確保として徴税が強化された。≫:帝国による課税、また更に帝国の行政官の監視下での課税、その際に更に諸ゲマインデに対しても税徴収ノルマの責任が課され、それはもっとも元々[その内部では]課税されていた諸ゲマインデで行われたのではあるが、つまりは二つの[徴税]システム[帝国によるのとゲマインデ自身によるのと]の複合であった。ローマ皇帝の直轄領である属州において、直接課税の原則が、元老院直轄の属州に比べ、非常に短期間にかつ広範囲に広まったということの結果、皇帝領の方は provinciae tributariae [貢納税の属州]と呼ばれ、一方元老院領の方は provinciae stipendiariae [金銭納税の属州]と呼ばれたのであるが、その場合に、古くから存在していたが、しかしまた技術的な用語としては常に意味が定まっていたのではない、次の二つの対立概念が導入された。一つが tributum = 現物貢納、もう一つが stipendium = 税の金銭納付、である。以上のことは、測量人達が Ager per extremitatem mensus comprehensus について付記している些細な注釈:「この方式は既に廃れてしまっている。」の意味を説明している。≪つまり、Ager per extremitatem mensus comprehensus は本来非課税地であったが、税制構築が進んだ結果そういう土地は無くなってしまった、ということ。≫
私は次のことが確かであると説明出来たと信じる。つまりこの対立概念は、一方[tributum]は sacamna[と strigae]を使った測量に対応し、他方[stipendium]は Ager per extremitatem mensus comprehensus の測量に対応するということである。帝政期とその先駆けの時代、つまり民主政[共和制]と帝政の混淆期における様々な傾向が、ローマ国の全ての住民の違いを平準化し最終的にはローマ市民とペレグリヌス≪peregrinus、非ローマ市民のローマ帝国民。紀元1~2世紀においてローマ帝国民の8-9割を占めていた。原義は「外国人、異人」。≫の区別を[最終的に]単一のローマ帝国民という概念でその区別を解消したように、同様の傾向はグラックス兄弟によって始められ≪ローマの同盟市の住民にローマ市民権を与えるという法案を提案した≫、最終的にはユスティニアヌス帝による jus Italicum ≪イタリア権法。ローマ帝国の特権都市の住民にローマ市民権を与えたもの。≫の制定という形で収束する発展も見られた。さらには同様に土地の種類の測量法と法規による区別も、早期に消失していっていた。それ故に、こうした土地の種類の違いについては、ただ帰納法的推論と仮説提示という形でのみ読者に伝えることが出来るのである。
これまでの議論で、以下のことについての証拠を示すことを試みていたとしたら、そのこととはローマの耕地の質的価値という意味で、それが測量方式の違いと国法上の区別のそれぞれに関連しているということであるが、その場合我々の議論は次に個々のケースにおけるこうした区別の法的な性質と、ローマの耕地の分割の手続きの意義を観察するということを、社会的、経済的、そして法的状態に関して行う、という方向に向かう。
II. ローマにおいての非課税の土地の法的・経済的な意味
I. 土地の割当ての行政史における作用≪目次では「行政法」における≫
我々はまず、国法及び行政法において、該当の領域との関係において[国家が法律上]最も強い権利を持っている場合での耕地の授与の作用について論じる。それについて完全な叙述を行うことを意図している訳ではなく、そういった関係を目に見えるように描写することを意図するのであり、その関係はまさに耕地の授与の際にその存在が明らかになるのである。当時の測量人達の異口同音の、また疑う余地の無い証言に拠れば、耕地授与の作用としてはまず第一は、当該の面積の土地をそれまでの耕地共有団体と地域団体[の所有]から分離させることである。そういった土地の分離がどういう実際的な意味を持っていたかということ、この分離のはっきり知り得る別の側面は何であったかということについては、ローマの全歴史を考えた場合に統一的な答えを得ることは不可能である。そうではなくてここで確認すべきなのはまず第一に、同盟市戦争≪BC91年からのローマの同盟市の一部がローマ市民権を求めて起した戦争≫の後の時代[においての土地の分離]と、それが引き起こした行政法に対する影響であり、その中にはまず何よりもユリウス法[lex Iulia municipalis]≪ジュリアス・シーザーとアウグストゥスの時代に制定されたローマの市町村(ムニキピウム)の組織や運営に関する規定≫が含まれるが、それら[によって分離された土地]をその前の時代に分離された土地から区別して確認しなければならないし、次にまた土地の割当てによってもたらされた植民というものの特性も、その本質的な特徴は何かという点において確認しなければならない。
イタリアにおける植民の一般的性格
イタリアにおける植民は、我々が推測出来る限りにおいては、ゲルマン民族のそれと同じでかつケルト民族のそれとは異なっており≪ケルト族によるハルシュタット文化の末期での身分の高い人物の豪華な墓が発掘されており、ケルト民族の植民はかなり早期に身分制社会になったと思われる≫、共通の重要な契機として存在していたのは、ゲノッセンシャフト≪主としてギールケらのゲルマニステンが、ゲルマン民族~ドイツ民族における人間集団形成の基礎原理として重視したもので、お互いに対等な人間同士が友愛・仲間意識などの「ヨコ」の関係によって形成した集団のこと。対立概念がヘルシャフトでこちらは支配-服従の「タテ」の関係に基づく人間集団。≫的なものであり、クランシャフト≪血縁関係による集団形成原理≫的ではなかったものである。つまり、最古の耕地での人間関係について我々が帰納的推論によって推測出来る限りにおいて、その耕地を占有した経済ゲマインシャフトは、一人の世襲専制君主によって統治された拡大された家族ではなく、まだそれほどはっきりした行政組織にまとめられていない、お互いに平等である個々の家族の集合体であるゲノッセンシャフトの性格を持っていた。ゲルマン民族においては、このゲノッセンシャフトは村落に定住しており、それはフーフェ≪ゲノッセンシャフト全体の合意に基づき、一家族が生きていくのに必要な面積として各家族に等しい大きさで割り振られた耕地のこと≫の取り決めを伴っており、その結果としての耕地の分割が行われていた。ポー川流域の Terramare ≪ポー川中流域の渓谷において、BC1700~BC1150の青銅器時代中後期に栄えた農耕文明。原義は「黒い土」。≫が、ヘルビヒが確実なことだと主張しているように、[インド・ヨーロッパ語族による]民族大移動の終了の前にイタリア半島にやって来たイタリック人≪イタリック語派の言葉を話す諸民族の総称で、主にイタリア半島に定住した、ローマを建国したラテン語族を含む≫の一部そこに残った人々により築かれたとしたら、その場合彼らのその地への定住は、またある閉じた、村落状の共同居住として、もはや遊牧民的な耕作ではない形で行われたということは確実であろう。そのことからしかし、避けようのない必然性をもって、何らかの形の耕地ゲマインシャフトが次に発生する。それはその初期の成立の時期においては、またローマの耕地においても発生したのである。それについてはこの先で様々な機会に述べるつもりであるが、そのような確実性を持った数多くの現象は、しかし同時に次のことを否定している。それはつまりそういった諸事実が言葉の正しい意味で[100%]確実であると断言したり、その意味を人が一般に「確実さ」として扱うような形で[アプリオリなこととして]語ろうとするやり方である。そう言う訳で、もちろんその耕地ゲマインシャフトが発生したということについて、それがより詳しくはどういうものであったかという問いには答えることが出来ない。ローマの全ての土地が、ドイツの村落におけるマルク共同体[Dorfmark]≪ゲルマン民族~中世ドイツにおける村落共同体のこと。マルクはその共同体の総有地のこと。≫がそうであるような、ある種のゲマインシャフトである経済領域ではあり得なかったということは自明である。ローマにおける最古の経済的ゲマインシャフトは gentes ≪gens=氏族の複数形。古代ローマでは10の gens が curia となり、10の curia が集まって tribus=部族、が作られていた≫であり、そしてもし後の時代の Landtribus[tribus の私有地]が氏族ゲノッセン[氏族仲間共同体]においての氏族共有地[Gentilmark]の分割によって生じたものだとするならば、我々にまた良く知られている全ての事実、特にクラウディア氏族≪サビニ族を先祖とする伝説を持つ古代ローマの有力氏族の一つで多くの貴族=パトリキを輩出した。≫の耕地マルク共同体についての文献史料に適合することは、[ローマの]全領土が、各地方において中心点となる氏族[共有地]によって分割されていた、と考えることが出来るということである。氏族の社会組織については周知の通り全く解明されていない。氏族について、親族関係に基づくジッペ[氏族団体]であるという伝統的な理解は、次のように誤解されてはならない。つまり、それを血統により分節化された人間集団と考えることである。そういった誤解はつまりドイツにおいての、ゲノッセンシャフト的でフーフェ原理によって組織化された村落のマルク共同体において良く知られた、「系統学」≪それぞれの家がどの先祖から出たかを研究するもの≫からの単なる類推に過ぎない。個々の氏族の共有地の中で何らかの特権を与えられた諸家族が存在していたかどうかということと、特に個々の家族がそれぞれの耕地ゲマインシャフトの中で、[ローマの]ager publicus の先駆的存在と考えられるような、共同体の一部において何らかの特別な権利を与えられた地所を所有していたかどうかということと、さらには氏族がどのような組織を持っていたかということ、これらの問題は土地制度史において何らかの仮説的な答えを出すには史料が余りにも不足している。これらの問題についての可能性のある仮説というと、多くのものが考えられる。同様に古代の pagi [土地共同体]の耕地ゲマインシャフトの中での位置付けを調べることも、ここでは試みることは出来ない。この pagi がそのゲマインシャフトのマルク共同体関係と関連があるということは、lustratio pagi ≪Ambarvalia という豊作を祈る儀式の中で、pagus の中の土地の境界が決められた。≫以外にも、後の時代の多くの残滓が語っているし、同様にまたゲルマン民族のマルクゲノッセンシャフトについての説明をそのまま流用することも行われている 1)。
1) pagus は pango [契約により確定させる]から派生した語である。それ故に pagus は共同体の全員による契約によって分離され、境界付けられたマルク領域と関係付けられているのは明白である。
古代の耕地の人間関係についてのいくつかの帰納的推論は、次章の冒頭で ager publicus について述べる時に更に試みることとする。ここではまず第一に、他の、確実に認め得るイタリアでの植民の特質を取上げる。ゲルマン民族の植民における人間関係との本質的な違いはつまりは次のことにあると考えられる:民族大移動の時のイタリック人が住み着いた領域における政治的状態と移民者の高い技術には、次のことが必然的に伴っていた。

それはつまり、ドイツの諸村落とは反対に、イタリック人のそれは既に杭上村落≪BC5000~BC500年の間にアルプス山脈周辺の湖畔や川辺に杭を打ってその上に作られた村落、写真参照≫において、少なくとも部分的には、防御性を考慮した場所であったということである。
しかしながらそのことによって、イタリック人の植民には最初から半都市的性格が消し去ることが出来ないほどはっきりと刻みこまれていた。この種の村落はまた、農民がまた住民として定住した小都市になるという傾向を持っていた 1a)。そしてそのことにより再び[その時代の]農業全体において、きわめて早い段階から近代的経済の見地から評価出来るような[進歩的な]傾向が付加されていたのである。そしてこの傾向が、後にローマの植民の性格を決定付けたのである。
1a) 既に最初から家々または村々が壁によって仕切られて互いに隣接していたということは、後のローマの植民の領域が及ぶ限りにおいて――例えばロートリンゲン≪現在のフランスのロレーヌ地方≫において――それは村において村道が設置されたことの結果であり。それは本来のドイツの村落には観られなかったものである。このドイツの村落にこうした構造が欠如しているという外から見て注目すべき現象は、タキトゥスが(ゲルマニア16で)ゲルマン民族の農民の家が一つ一つ孤立している状態にある、と述べているのと同じことであり、村落型の定住の反対概念としての個々の孤立した農家ということだけを想定しているのではない。
ローマの植民の特性
ドイツの東方における植民が百年一日の如くでまったくもって型にはまったやり方≪全集注によれば中世後期からのフーフェと四角の耕地分割による植民≫で行われていて、それが民族大移動時代の耕地分割と原理的に異なっていなかったのに対し、ローマにおける植民は近代アメリカでのそれに類似していた。この近代アメリカ式植民と同様に、ローマの植民の実際は次の二つの可能性しか無かった:一つが都市建設または都市の再構築(植民市の再構成)の形によるもので、もう一つが組織化されていない個々の家々による植民(viritane Assignation)≪非計画的に、あるまとまった数の人々に、同じサイズの小面積の土地を機械的に割当てる形の植民≫である。colonia[植民地]、モムゼンの見解によれば農民共同体[Bauernschaft]、が氏族の耕地を取りまとめる組織のより進んだものであるとするならば、しかしそれはその意味以外にもある防御性を持った場所、つまり都市であるが、の中へ第三者が侵入することを防ぐための組織という意味を持っていた。viritane Assignation の方はしかしながら、概して言えば、言葉の本来の意味での colonia を作り出すことは無かった。
それ故に viritane Assignation が明らかに与えられた一区画の土地を完全なローマにおける個人資産に付け替えるプロセスで、その中に常に全ての種類の耕地ゲマインシャフトから分離された土地を包含していた一方で、ローマ市民の植民市の建設は、個人の所有権というものがローマ法の全体を既に支配していた時代において≪個人の所有権というものを確立させたのがローマ法の大きな功績であり、そこから物権や契約法などが発達した≫、またある別の性格を持っていたように見える。ローマの植民市は常にゲマインデ[地域共同体、コミュニティ]の設立と組織化を伴っており、それ故に[そのゲマインデの]住民数は限定されており、古代のローマ市民の植民市[coloniae civium Romanorum]においては、ここではそれのみについて述べているのだが、通常は300人であり、そしてそれについて我々が更に知るところでは、個々の入植者は2ユゲラ≪約5,000㎡≫の土地を得るのであり、[その知り得る情報によれば]しかし各入植者へ割当てられる土地の面積が、その2ユゲラに限定されていたという仮説は排除される。≪様々な文献史料から各入植者に2ユゲラ以上の土地が割当てられた場合があることが確認出来る。この2ユゲラは「最低限度」である可能性が高い。しかしヴェーバーは後に「古代農業事情」の中でこの2ユゲラ以上の土地が割当てられたという自分の説を間違いだったとしている。≫というのはむしろ植民者は無条件に農民であったと考えられ、この2ユゲラという土地の面積はロムルスの時代の標準的な割当て面積に一致するし、また同様にゲルマン民族の耕地における Wurt ≪盛り土をして洪水の害を避けた小高い土地≫にも、更に個人に私有物として耕地ゲマインシャフトの土地から切離して与えられた家や庭のための敷地にも相当し、それらは2ユゲラより狭いということはなく、時には2モルゲン≪約6,000㎡≫よりかなり広かったのである。余った土地はそれ故耕地ゲマインシャフトの中に含められたままにされねばならなかった。しかしこのことは後代には自明なこととして違って来ている――たとえばグラックス[兄]は[ポエニ戦争の結果としてローマの領土となった]カルタゴの植民市の土地について、ある場合は200ユゲラを、また別の場合にはおそらくそれ以上を――つまり間違いなく個人の所有物として――割当てており、そして当時の測量人達が言及しているのは、ただ個人への割当て用に用意された土地においての、土地の[個人への]授与である。植民市における入植が、ただゲマインデの組織の形成ということに留まり、その反面としてそれまでの植民地化されたゲマインデにおける[それ以前の]耕地団体を完全または部分的に消滅させたということが、つまり植民市におけるゲマインデ団体の始まりである。viritane Assignation の場合は、それに対してゲマインデ組織の形成につながることは無かった。それが意味したのはただ農村トリブス≪ローマの行政区で都市トリブスに対比され、郊外にあったもの≫におけるローマのゲマインデの権力の及ぶ範囲の拡張であった。同盟市戦争の後、そういったやり方は廃止された:全てのローマの土地はそれ以降は原則的にローマの完全市民のゲマインデに属するようになった。植民市の建設が目的ではない限りにおいて、つまりは viritane Assignation においては、割当てられた土地区画は、既存のゲマインデに帰属させられたか、あるいは新しい[ゲマインデ]組織がそのために作り出されねばならなかった。ここで次のことを問うてみるならば、つまりこれらのより後代の行政組織において、ある地所のあるゲマインデへの帰属は、どのような人間関係にとって意味があったかということであるが、その答えは次のようになる。
領域の行政法的意味
1.裁判権と警察権。植民市の建設に使われた書式の中にこの事項が含まれている。(ヒュギヌス, De cond. agr. P.118、21):
“Quos agros etc. dedero assignavero, in eis agris juris dictio cohercitioque esto coloniae illius.”
[私が与え割当てた土地など、その土地においては裁判権[jurisdiction]と警察権がその植民市のものとなるべきである。]
部分的にしか明確にされていない権限の範囲内での、その植民市の領域内の土地区画に対する民事裁判権についてと同様に、またその領域内で起こった犯罪行為への追及についても、その植民市の市政官達が管轄権を持っていた。同様にその市政官達に権限が帰属したのが、警察権を持ったことの帰結として、とりわけ該当の領域における市場を取り締まる警察権である。
2.ケンススは同盟市戦争の後では、それぞれのゲマインデによって執り行われていた。各地所もその地所が存在するゲマインデでのケンススによって基礎付けられていた。我々がそれ故にここで見出すことが出来るのは、各ゲマインデでは、お互いに次のことについて訴訟を起しているということである。そのこととは、ある土地区画がケンスス上では、一体そのゲマインデの中の誰に帰属するのか、ということである 3)。
3) ヒュギヌス, de cond. agr. P.114, 11
帝政期には、イタリアはまだ課税されておらず、またほとんどの場合徴兵制も無かったのであるが、そのためにイタリアでのある特定のゲマインデでの土地の帰属は、属州においてよりも少ない意味しか持っていなかった。属州では周知の通り、ゲマインデは税金の徴収についても新兵の募集についてもノルマを課されていたのであり、それ故に自身に帰属する土地区画の確定については利害関心を持っていた。
3.土地所有は、その土地のあるゲマインデにおいての、特定の私有財産に対して課せられた負担義務[munera patrimonii]に直接的に結び付けられることを意味していた 4)。
4)同じ理由から、ゲマインデ間においての法律上の領地についての訴訟能力が発生する、P.52、21。
土地の割当ての結果として発生した[ゲマインデの]領土境界の変更は、それでは一体何に基づいて決定されるのであろうか?
土地割当ての領土の確定への影響
決定的なことはまず第一に、植民と原住民立ち退きの進行が同時に発生した場合に、それを完結させる諸契機:つまり土地の分割と割当てである。その二つの内どちらか 5) が先行した場合には、何かの特別な規定が必要だった。それは[市政官の]職権についてであり――-それによって先に紹介した権限[裁判権と警察権]を一つにまとめるためであり――その職権は新しいゲマインデのそれであり、当該の耕地に対して土地の分割または割当てを行うためのものであった。土地の分割[divisio]は次のような場所では行われなかった。そこは測量地図[forma]によって図示された境界線[limites]の座標系の外側にあり、その耕地は元々その土地が持っていた境界によって区切られており、それ故に境界が確定していない不規則な土地[ager arcifinius]という扱いで植民市に帰属させられていた。それに先行した事情は、植民市の数が[ローマの征服によって]増えたことにより、分割によって利用出来る土地の面積が不足することとなり、その結果として植民市に隣接する土地が[まだ測量されていないが]利用されるようになった、ということである 6)。
5)P.154, 9: “Divisi et assignati agri non unius sunt conditionis. Nam et dividuntur sine assignatione et redduntur sine divisione. Dividuntur ergo agri limitibus institutis per centurias, assignantur viritim nominibus.”
分割され、割当てられる土地は、一様ではない。というのは分割だけで割当てが無い場合があり、逆に割当てが分割無しに行われる場合もあるからである。従って、土地はケントゥリアの単位で設定される境界線によって分割され、割当ては個々人の名前に基づいて行われる[という本来別のプロセスである]。
6) P.160, 14:Aliquando … in limitationibus, si ager etiam ex vicinis territoriis sumptus non suffecisset, et auctor divisionis assignationisque quosdam cives coloniis dare velit et agros eis assignare, voluntatem suam edicit commentariis aut in formis extra limitationem: “monte illo, pago illo, illi jugera tot”, aut “illi agrum illum, qui fuit illius”. Hoc ergo genus fuit assignationis sine divisione … Sunt vero divisi nec assignati, ut etiam in aliquibus regionibus comperimus, quibus, ut supra diximus, redditi sunt agri: jussi professi sunt quantum quoque loco possiderent.
時々、土地の境界の設定において、もし隣接する領域から獲得した土地でも不足する場合には、分割と割当ての責任者[市政官]がある植民市にローマ市民を入植させ、彼らに土地を割当てたいと望んだ時、彼はその意志を公文書や地図に境界線を図示するという以外の方法で明らかにする:例えばあの山を(誰々に)、あの集落を(誰々に)、そしてこの人にはこの面積[ユゲラ]の土地を、とか、さらに別の人には他の人の土地だったものを与える、などである。この種の割当ては従って分割無しに行われる…一方で実際には分割も割当ても行われないケースも存在し、私達がいくつかの地域において見出したように、上述のようなやり方で土地の割当てが行われた場合、各人にどれだけの面積が実際に割当てられたのかを申告することが命じられていた。
隣接する土地それ自身は、その部分が公式の測量地図に載っておらず、従って[植民者への]割当ての面積が同じく測量地図に記入されることによって新しいゲマインデへの所属が定められていない限りにおいて、それまでのゲマインデ団体に[そのまま]所属するとされた 7)。
7)このことは、ヒュギヌスの記述から類推すれば、かなりの争いを引き起こしている。P.118, 9ff, 特に119, 8f.:
… quidam putaverunt, quod … repetendum arbitror, ut eis agris qui redditi sunt veteribus possessoribus, juris dictio esset coloniae ejus cujus cives agros adsignatos accipiebant, non autem videtur … alioquin, cum ceteros possessores expelleret …, quos dominos in possessionibus suis remanere paddus est, eorum condicionem mutasse non videtur …
ある人々は次のように考えた…元の土地の所有者達に土地を返却する裁定を受け、その土地が元の所有者達に戻されるべきだと。そして、その土地に関する司法権は、その土地が割当てられた市民が属する植民市にあるが、測量地図上にはそういった記載はない…その場合でも、もし新しい所有者が他の所有者を追い出していたとしても、彼らがその土地の所有者のままでいることが許可される。しかしそういった所有権の変更についても測量地図上には記載されていない。
ager extra clusus ≪正規の分類以外のその他の土地≫やager subseciva [subsiciva] ≪耕地の外側の境界線とケントゥリアによる区画の間の半端な土地≫においては分割も割当ても行われなかった。それらの土地は植民市の耕地の外側の境界線と[ケントゥリアなどの]四角の区画の土地の間にある土地であり、測量地図には記載されているが、余分な土地とされたものである。ケントゥリアの四角の土地の中にある subseciva [subsiciva]≪ケントゥリアの中に沼地などの使えない部分があってその沼地以外でケントゥリア内部の土地など≫においても割当ては行われなかった。更には loca relita ≪捨てられた土地≫の場合にも割当ては行われなかった。loca relita とは、ケントゥリアにより境界線を測量地図の中に描いて行き土地を分割する方式の中に取り入れられず除外された土地のことである。
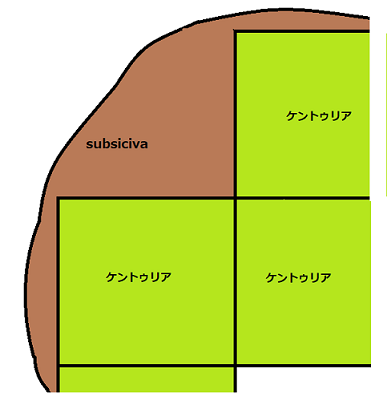
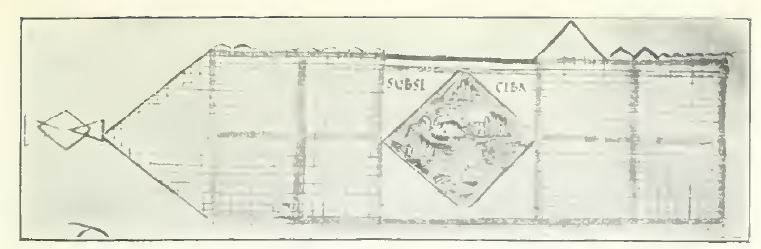
![]()
ager extra clusus、subseciva、そして loca relicta の全てを合わせた地所は、法そのものの効力によって新しいゲマインデの職権に支配されているのではなく、帝政初期においては、土地を割当てる植民市の役所の権力下に、ただ法律上形式的に留められていたに過ぎない 8)。これらのその他の領土については、[通常の土地種別とは]異なったやり方で取り扱われていた可能性がある 9)。この種の土地が、特に loca relicta の場合にもっともしばしばあったことであるが――ゲマインデによって共有地として、つまり pascua publica [共有の牧草地]として、または売却や譲渡の対象から除外された樹木地に割当てられた可能性がある。あるいはその土地での放牧権が定められ、多くの場合境界線の無い―― fundi [牧地]として割当てられたのかもしれない――つまり ager compascuus [隣人間で共有される牧草地]である 10)。あるいは別の可能性としては:これは ager extra clusus の場合にしばしばあったことであるが、ゲマインデが自分のものとしたか、あるいはまた一時的にかあるいは賃借料と引き換えに誰かに引き渡されたかである 11)。仮にそういった土地について何も規定が無かった場合には、それらの土地はローマ市民の ager publicus [公有地]に留まるのであり、ゲマインデまたは私人が、それは subseciva の場合にしばしばあったことであるが、その土地を開墾した場合、共和政時代の公有地の占有[Okkupation]と同様の法的な位置付けの土地となったのである。そういった土地の利用で利益を得ることは非常に不確実だったのであり、いつでも新しい割当てによってその土地が没収されたり、または国家によって賃借料を課されたりする、ということがあり得たのである 12)。皇帝ウェスパシアヌス≪在位AD69~79。皇帝ネロの死後の内乱期の後、60歳で皇帝になりローマの財政建て直しや公有地貸し出しの見直しを行った。≫がこういった政策を精力的に行い、そうした土地の所有者に大いに不満を抱かせる結果となった。そして皇帝ドミティアヌス≪在位AD81~96、ウェスパシアヌスの次男、前皇帝ティトスの弟≫までに、永遠に続くかと思われた諸ゲマインデの不安は全て解消された。その過程でドミティアヌスはこれらの古い意味でのイタリアの公有地の残りの部分を、その占有者に対して、当時の測量人達の内の一人によって言及されている一般的処分を行った。それについての実例が碑文として(C.I.L. IX, 5420)≪ドミティアヌスがファレリ人とフィルマ人の間の土地争いを裁定したもの。≫残されている。
プラエフェクトゥラの測量地図の意味
前述のことから、測量地図[forma]がこうした[土地の]状態に対して持っていた大きな意味が確かに確認出来る。植民市に組み込まれた耕地の内、測量地図、つまり耕地図に記載されていない部分は、これまで見て来た土地のカテゴリーのどれにも該当しなかった。それに対して統一された測量地図が作成された場合、または多少疑わしくとも統一的な耕地の領域 14) までその地図が包含している場合、そうした場合おそらくはその領域がそれまでのゲマインデの耕地の大部分または一部分を含んでいた。測量地図[forma]に載せられた耕地領域が十分ではないという理由で、隣接する耕地の一部がある独立の座標系を用いて分割され、そして――常に疑わしかったことではあるが 15) ――この領域に対しての特別な測量地図も作成され、そしてこの領域、つまり単なる畑地は、その領域の中に本来その土地が属していた町の中心部分を含まず、そしてそれらが主要な植民市に組み込まれた場合には、その領域はなるほどその植民市の市政権力の下に置かれるのであるが、しかしそれらはただ相対的な意味での付属地としてプラエフェクトゥラと呼ばれた。何故ならばそのような領域については、特別なプラエフェクトゥラ≪~の管轄下にある、が原義≫として植民市の市政官の司法権の執行下に委ねられたからである 16)。
14) このことは少なくともヒュギヌスの Polemic P.118に拠れば支配的な考え方であり、それはまた測量地図とその土地の面積[pertica]の確定が行われていたこともその根拠となる。P.154,18: .. . quamvis una res sit forma, alii dicunt perticam, alii cancellationem, alii typon, quod . .. una res est: forma.
[ある測量地図があったとしても、別の者はそれを pertica [長さの単位、面積の単位、土地の地味の評価単位]と呼び、さらに別の者はそれを cancellation [格子状の土地、ケントゥリアとほぼ同じ]と呼び、また別の者はそれを typon [測量計画図]と呼ぶ、それらは全て一つの物:つまり forma を指している。」
14a) ] P.164, 5f.: .. . multis .. . erepta sunt territoria et divisi sunt complurium municipiorum agri et una limitatione comprehensa sunt: facta est pertica omnis, id est omnium territoriorum, coloniae ejus in qua coloni deducti sunt. Ergo fit ut plura territoria unam faciem limitationis accipiant.
[多くの(近隣ゲマインデの)領域から領土が奪われ、多くのゲマインデの土地が分割され、一つの測量地図の中に包括された:すなわち、全ての領土が測量され、そ(れら)の土地はそこに定住する植民者たちに割当てられて植民市のものとなった。その結果、複数の領土が一つの測量地図に取り込まれることを(各ゲマインデは)受け入れさせられることになった。]
15) 次の Siculus Flaccus からの引用箇所を参照せよ。
16) P.26, 10 (フロンティヌス 1.II)
quidquid huic universitati (der Kolonie) adplicitum est ex alterius civitatis fine, praefectura appellatur, — p.49, 9: .. coloniae quoque loca quaedam habent adsignata in alienis finibus, quae loca solemus praefecturas appellare.
[この(植民市の)ゲマインデに付属する土地は全て、元々他のゲマインデの領土だったものであり、それはプラエフェクトゥラと呼ばれた。-p.49, 9…(それらのゲマインデ全体を統括する)植民市もまた、他のゲマインデの領域の中に割当てられた土地を所有しており、その領域をも(我々測量人はまとめて)プラエフェクトゥラと呼ぶようになった。]
特にしかしながら シクルス・フラッカス: Illud praeterea comperimus,deficiente numero militum veteranorum agro qui territorio ejus loci continetur in quo veterani milites deducebantur,sumptos agros ex vicinis territoriis divisisse et assignasse; horum etiam agrorum, qui ex vicinis populis sumpti sunt, proprias factas esse formas. Id est suis limitibus quaeque regio divisa est et non ab uno puncto omnes limites acti sunt, sed, ut supra dictum est, suam quaeque regio formam habet. Quae singulae perfecturae appellantur ideo, quoniam singularum regionum divisiones aliis praefecerunt, vel ex eo quod in diversis regionibus magistratus coloniarum juris dictionem mittere soliti sunt (teilweise verderbter Text).
[「そういった土地(プラエフェクトゥラ)については、我々はまた次のことも見出している。ヴェテラン兵士に(長年の兵役に対する褒賞として)与えるべき割当て地の数が、彼らが定住すべき土地を含む(植民市の)領域において不足している場合、近隣のゲマインデの土地から奪った土地を分割して(ヴェテラン兵士に)割当てたということを。またこれらの近隣の住民から奪った土地についても、特別な測量地図(forma)が作成されたということを。それはつまりそれぞれの領域はそれ自身の境界線によって区切られており、そしてある一点で(ある一点を中心点として座標系を作成して)全ての区画割りが行われるのではなく、前述したように、それぞれの領域で(それぞれ区画割りを行い)測量地図を作成し保持したのである。それぞれの領域がプラエフェクトゥラと呼ばれる理由は、特定の地域の個々の分割地がそれぞれ異なる者の管轄下に置かれている(=praefecerunt)からであり、または各プラエフェクトゥラにおいては、植民市の行政官が植民市では本来無い異なる領域であるにも関わらず司法権を通常行使していたからである。(部分的にテキストが欠損)≪いずれにせよ praefectura という単語は「~の管轄である、~に司法権が与えられている」という原義から派生した単語である。≫]次のことをいぶかしく思う人もあるであろう。つまり、これらのテキストの中に逆方向の因果関係について触れられておらず、つまり次のことが述べられていないこと:新たに設定された司法権の及ぶ区域に対して、その区域についての測量地図が作成された、ということである。次のことは確かなこととして主張することは出来ない。つまり、特別な測量地図を作成する必要性があり、その法的な理由が新たに委任された司法権についての管轄地域を作り出すためであったということである。それにも関わらず上述のテキストは無作為に選んだものではない。[そのテキストから考えて]次のことは非常に特徴的である。つまり本当にそういうものがあったか疑わしさもある統一的な耕地分割システムはまた――例外がP.162, 3に出てくるが――それ自身が独立して成立した行政上の管轄権と適合的である、ということである。帰納的に推論して我々は次のように考えよう。つまり、このこと[耕地分割システムと行政上の管轄権の適合性]は次のことに根拠を持っている:古代のローマの領域においての個々の耕地ゲマインシャフトが、自明なことではあるが、根源的にはある何かのやり方で行政上お互いに区別された形で成立したのであり、そしてゲマインシャフトの[土地の]それぞれの成員への分割割当てが行われたのであるが、そしてこれらの分割された耕地が――それぞれの土地にある特別な座標系を使った境界線引きが行われていたとしても――その後の時代になっても依然として、いずれにせよある時期まではその昔に行われた[古の]行政上での区分形態を[まだ]保持していたということである。こうした行政上の分離をトリブスとパギ≪いずれもローマの土地共同体、パギはロムルスの時代のもの、トリブスも共和制時代のそれではなく王政時代のもの≫に関連付けるということは、この土地制度史では2つを区別して取り扱うことが出来ないために、私はここでは試みることはしない。しかし先に詳しく述べたことがおおよその所正しいのあれば、その場合実際には個別の[行政上の]区別は、プラエフェクトゥラの司法管轄権の特別な地位の成立よりも歴史的に先行しているのである。この[プラエフェクトゥラの]表現についてはまた、ここで測量人達のテキストにおいて述べられた意味においてのみ使用されているということは自明のことである。≪praefectura のこうした意味はオックスフォードラテン語大辞典によればもっとも古い意味であり(小型ラテン語辞書には出ていない)、後になると行政命令とか地方役所、(単なる)行政区という意味になる。また後に”praefectura praetorio”というもっと広大な行政区を指すようになる。ちなみに日本の「県」を英語でprefectureというのは、直接的には中期フランス語 の préfecture からだが、更に遡ればこの”praefectura praetorio”まで行き着くと考えられる。≫
返還された、許可された、例外扱いされた土地
ある領域が境界線によって囲まれることによってそこに土地区画が出現している一方で、その土地区画が個々人への割当ての対象から外れていたということがあった。まず我々が第一に知るのは 17)、確かにそれは一部の測量人の意見に過ぎないが、土地の分割-割当てにおいては、それまでその耕地に定住していた者にも[改めて]割当てが行われた[ことがあった]ということであり、これらの者達に対してあるいはその者達の一部に対して、彼らのそれまでの所有地が元の境界線のままで返還されたのであり、――それは耕地地図上では「返還資産」[redditum suum]と書かれていた――その該当の土地区画はその後植民市の行政権力の特別な取り決めには従うことがなかったのである。
17) ヒュギヌス、p.118、更にp.116、16.160、24.178、5.197、14.を参照。
そのような地所についてはその地所の元々の所有者の個人的な事情が斟酌されたのではなく、おそらくはそういった地所は植民市において新しくロジカルなやり方で作り出されたものではないということであり、というのは以前の所有者がその者の以前の所有地を別の新しい地所と交換させられたり、またはそれまでの所有地のただ一部だけが返還され、残りの部分が新しい地所と交換させられた場合、――”commutatum pro suo”[その者の所有地と交換された]あるいは”redditum et commutatum pro suo”[(一部)返還され(残りは)交換された]と耕地図上に記載された場合――、その場合当該の領域は植民市の耕地団体の[所有地の]中に登場するのである。[以上の推論よりも正しいと思われるのは]そうではなくて、この土地について言えるのは、それまでの 地所の[法的な]地位が維持された、ということである。土地の割当ては、第1章で見て来たように、土地の面積を基準として行われたのであり、そしてまた植民者達が事実上、最終的に具体的な耕地を分割したものを得た場合も、そこで有効となるのは面積のみであり、というのは耕地図は個々のケントゥリアにおけるそれぞれの割当て地の面積のみを記載しているのであり、法的な意味としてはこれらの土地は割当ての[行政]手続きを通じてのみ確定されたのである。これについて次のような見解が考えられる。つまりある土地区画が明示的に”redditum”[返還された」と、つまりその地所の元々の境界線とその内部で[改めて]割当てられた部分が測量地図上に記載され、本来なら第一に記載されるべき面積ではなく、ある具体的なまとまりの耕地が割当てられたとされ、それ故にその場合には本来の割当ての[行政]手続きが欠如しているのであると。というのも土地の返還が次のようなやり方で行われた箇所では、つまりただ境界線のみが確定したものとして耕地図の中に描かれるやり方であるが(ラハマン≪Lachmann、”Schriften der römischen Feldmesser”[ローマの土地測量についての文献集]≫の図185{下図}を参照)、 法の効力によっての植民市の耕地へのその土地の編入はされなかったからである。そういった土地が特別な取り決めによって植民市の行政権力下に置かれた場合は、そのような領域は fundus concessus [許可された土地]と呼ばれ、そこから除外された土地は fundus exceptus [例外扱いの土地」18) と呼ばれた。
法の効力によっての植民市の耕地へのその土地の編入はされなかったからである。そういった土地が特別な取り決めによって植民市の行政権力下に置かれた場合は、そのような領域は fundus concessus [許可された土地]と呼ばれ、そこから除外された土地は fundus exceptus [例外扱いの土地」18) と呼ばれた。
18) p.197参照。
測量の対象から外されたり、そしてまた司法権の特別な適用によってあるゲマインデの下には置かれなかった、植民が行われた領域でのそのような土地についてはどのような法的な状態が新たに作り出されたのであろうか?
割当てられなかった領域の法的な位置付け
ある植民市の測量された土地[pertica]とその植民市の別の領域のある部分が一まとめにして把握された所においては、法の存立の状態は疑いなく元の古い状態のままであった。場合によってはこういう残余の土地はごくわずかでまた偶然生じたようなものであり――カウディウム 19) ≪南イタリアのサムニウムの地名でサムニウム族系のカウディニ族が住んでいた。≫ではそうであった――全体の領域が植民市が測量によって境界線を設定することで把握され、それからムニピキウム[自治市]の役所の権力は城壁の内側の地域に限定され、また実際はほとんど市場を取り締まる警察権と市場への司法権に限定された。
それに対し植民市が測量によって設定した土地が元々あったゲマインデの領土のほんの一部に過ぎなかった場所では、そのゲマインデの内部に植民市の土地が設定され、把握され、2つのゲマインデがお互いに二重都市という形で成立することとなり、新市と旧市という形で並立した 20)。
19)C.I.L. IX, 2165. lib. col. p.232, 部族もまた異なっていた。参照:C.I.L. IX, 2167(ベネヴェント≪南イタリアのアッピア街道沿いの中小都市≫のステラティーナ族の植民市)、また2168(カウディニ族のフォレーリア)≪この注を含む数ページの注でヴェーバーはC.I.L.(Corpus Inscriptionum Latinarum、ラテン碑文集成)とすべきものをC.J.L.としている。おそらく誤記でCD-ROM版のテキストではC.I.L.である。しかし全集版の文献リストにC.J.L.は無く全集による説明もまったく無い。ius-jusのように、ラテン語でiとjの両方が特定の綴りで使われるケースはあるが、この場合はIしか考えられない。≫
20) おそらく Interaminia Praetuttianorum ≪現代のイタリア共和国アブルッツォ州北部のテーラモ。プラエトウッティ族の土地だったのをBC290年にローマが征服し植民市としたもの。≫がそう(Frontin、 p.18による。C.I.L. IX、5074とも一致する)。更にはポッツオーリ(Tac. Ann. 14, 27)、ヴァレンシア≪スペイン≫(C.I.L. II, 3745)、アプラム≪ルーマニア、ローマの要塞があった≫(C.I.L. III p.183)そしてティグニカ≪現在のチェニジア南西部≫。
そういった二重都市となった領域の実際の状態と相互の関係、つまり公的権力においての境界設定、がどういうものであったかについては、個々のケースについてそれを突き止めることは出来ないが 21)、少なくともそれが存在していたということについては疑いようがない。
21) そういった二重都市の司法権の相互関係については学説彙纂27§1のウルピアーヌス≪ローマ古典期晩期の法学者で学説彙纂の法文の内約1/3は彼の著作から取られている。≫の断片 ad municipalem et de incolis (50, 1)[ムニキピウムとその住民について]が扱っているように見える:ある者で常に植民市ではなくムニキピウムに滞在し、全ての祝祭等に参加する者は、そこで諸々の物を買い入れ、”omnibus denique municipii, nullis coloniarum, fruitur”[結局のところ、(その者は)ムニキピウムの全て良きものを享受し、植民市の何物をも享受していない]、その者は彼の domicilium in municipium [ムニキピウムの中での住居]を持ち、の所である。しかし、[学説彙纂の](リテラ・フロレンティーナ[写本]での)”colendi causadeversatur”[耕作のために住む]の所ではない。特徴的なのは、”rus colere”[耕作のための地所]というのが植民者の本質であるように見えることである。
同盟市戦争の時代には、それ[fundi excepti]は単に農村トリブスの中で登録されたのかもしれない。しかしその後の時代ではそれはもう可能ではなくなっていた。測量人達の記述によれば、それはむしろより独立した領域として構成されていた。そういった領域はゲマインデの領域に関しての手続きによって定められており、ケンススにおいては明確に独立したものとして一般的にはただローマの中央官庁の管轄下にあるのみと記載されていた 22)。
22) P. 53, 197, 10。類似のものについて第4章で取上げる。
同様にそういった領域は、時においては警察権力の一部としての市場についての司法権の管轄下にあった場合もあった 23)。
23) C.I.L. VIII, 270. Ephem. epigraph. II, P.271を参照。
確かにこういった関係は、ケンススによって課税と徴兵が実際に行われていた属州においては、イタリア半島においてよりも大きな意味を持っていたし、そもそもイタリア半島においてはこういった関係自体が稀であった。測量人的な視点においては、我々はそれを明白に ager per extremitatem mensura comprehensus [外周のみが測量され内部が区画分けされていない土地]のカテゴリーに関連付けることが出来る。それについてフロンティヌスはこう言及している:fundi excepti としてまた測量地図上に記載されている領域は、確かに耕地図上にまた per extretatem として測量されその領域が描かれている。既に次のことについては言及して来た。つまりフロンティヌスの地図(Fig. 4)が既に明らかにしているように、区画分けされていない地所は、ある統一的な特定の種類の区域として法的に定義されたものに、必ずしもなる必要がなかったように見える、ということである。この領域を巡るその他の公法的・行政法的諸関係については、それは古典期での物権の引き渡しにおいては非常にみすぼらしくしか見えないものではあるが、またローマにおける土地(農業)経済の発展において非常に重要な役割を演じたことははっきりしており、後で特別に詳細に取り扱うことにする。(第4章を参照)。――
植民市内部における法整備の状況
我々が次の問いについて考えようとするや否や、我々のそれについての知識が非常に貧弱な状態に留まっていることが明らかになる。その問いとは、あるローマの市民植民市において、その当該のゲマインデの内部においての法整備の状況がどのように変遷したか、どのような作用を及ぼしていたかということである。元からの居住者の植民者に対しての関係が、統一的な法形式としてどのように規定されていったかという問題はここでは取上げない。ノーラ≪カンパーニャ地方のもっとも古い都市、第2次ポエニ戦役で3度戦場になった。≫についてモムゼンは元からの居住者はここでは plebs urbana ≪ローマにおける最下層の平民≫に格下げされたという仮説を唱えているが、実際のところは、全ての領土が没収されたという、常に起こりうることがここで起きたのである。これに対立するもっとも極端な例は、古代のアンティウム≪ローマの南の海岸沿いのラティウムにあった都市、アンツィオ≫で起きたことで、そこでは元々の住民が全て植民者に編入されている。ポンペイについては以上の2つの偶発的なケースとは違い、何かの、おそらくは法的に不平等である2つの住民カテゴリーが作られ、おそらくは住民の異なった地位によって耕地の割当ても違ったやり方で行われていたように思われる 24)。
24) ニッセン≪Heinrich Nissen、1839年~1912年、ドイツの古代史家≫のPompeianische Studien[ポンペイ研究]とモムゼンのC.I.L. XIVを参照。もちろん詳細については全く不明である。次のことはすぐに確かなものと確認することは出来ない。つまり、北部の1/3の領域が他の領域から scamna と strigae によって区切られていたのかということである。そこにおいてはスッラの植民市がその領域を秘密裏に所有していたのと、または元からの住民がそこを課税地として所有していたからである。モムゼンは一般論として旧住民が市の複数の門の前方へ(つまり市外へ)追いやられた可能性を示唆している。≪Thoreを普通に「門」(複数)として訳したが、表現が非常に不自然であり(単に市外に追放したなら、市壁または城砦の外へと書く方が普通)もしかするともしかするとポンペイの西にあって、ポンペイと同時にヴェスヴィオ火山の噴火で滅んだ(現在の)トッレ・アンヌンツィアータのことではないか。Torre(伊)、Turris(羅)は「塔」の意味。トッレ・アヌンツィアータに相当する地名が当時もあり(ここの遺跡の地名はオプロンティス)、その固有名詞中に含まれる普通名詞を間違って「門」と解釈したのではないか。ここは二重都市についての注なので、元からの住民がトッレ・アヌンツィアータの方へ追いやられ、ポンペイと二重都市を構築したと考えるのは自然。ちなみにポンペイ最大の門は西側のマリーナ門であり、それには12の塔がある。そしてその門の外側はトッレ・アヌンツィアータなので、結局は「門」と訳しても同じことを意味しているかもしれない。この部分C.I.L.の原文を探しているが未確認。≫我々が知り得ている情報だけによって「二重都市」という名称を使うのは無理がある。そういった関係だと言っても良いのは、例えばヴァレンシアにおいてのように、2つの階層[ordines]と、それ故に2種の公権力がお互いに排他的な競争状態にあることが確認出来る、そういう場合のみである。そうでないとほとんどの植民市が「二重都市」ということになってしまう。
文献史料の状態が劣悪なため、いずれにせよ次のことを行うことは出来ない。つまり新しく連れてこられた植民者と元からの住民の関係を詳しく調べることである。後者についてはある特別な法的地位に留められたかあるいは何かの原理に基づく存在として(その原理から)還元されて考えられたかではあるが、ここで出来るのはただそうした原理について調べることぐらいである。様々な植民市については、そういった原理という点でお互いに甚だしく異なっていたように見える。それについては我々は次のような考え方をすることが出来よう。つまり市民植民市でもあった諸ゲマインデについて、帝政期においてもまた、ローマ国家としてのそういったゲマインデとムニキピウムとの等しい法的な取り扱いにも関わらず、ムニキピウムと他のローマの諸ゲマインデの内的な関係については、ある観点に沿って見た場合には異なっていた、という考え方である。モムゼン 25) は次のことに言及している。つまりその他のゲマインデとは反対に、ある種のゲマインデでローマの[古代からの伝統的な]集団形成が先行していた所では、つまりクリアに分けられていた場合、植民市 26) においてはそれがトリブスになっていると。ローマにおいてはトリブスへの分割は疑いもなく耕地の分割と関係があったので、次の結論は明らかである。つまり、この2つに関係があったことは市民植民市においてもそうであり、それ故市民植民市の土地制度の状態は帝政期においてすらある本質的な識別のための目印を作り出していたということである。
25) Epehem. epigraph. II p.125参照。
26) アウグストゥスの植民市 Lilybaeum≪リリュベエウム、今のシチリアのマルサーラ。ポエニ戦争にて対カルタゴの前哨基地として栄えた。≫ と、Julia Genetiva Ursonesis≪スペインのセビリアにあったカエサルの植民市≫においてがそうであった。
そうした事情があったとしても、次のような可能性について確たることを言うことは出来ない。つまりアフリカ 27) の植民市においてクリアによる分割が行われたかということである。
27) 当時の Hippo Regius ≪現在のアルジェリアのアンナバ。フェニキア人が作ったとされ、後にローマの植民市となった。≫と Lambaesis ≪アルジェリア北部にあったローマの植民市で、ローマ軍によって作られた。≫についてそこでのクリアについて言及されているか、またそもそも本当に植民市であったかもはっきりしない。それに対してこのことは、Julia Neapolis ≪カルタゴの旧領、現在のチェニジアに作られた植民市≫の場合は該当していた(C.I.L. VIII, 974)し、更にはトラヤヌスス帝が作った植民市の Thamugadi ≪現在のアルジェリアのティムガッド≫もそうであった。(C.I.L. VIII, 5146)
そのことから考えて、ローマそれ自体においてはクリアとトリブスが隣接して存在していたということは、ある時代からの植民市法の該当のゲマインデへの適用の源泉となっているが、その時代においてはゲマインデにおける市民団体は都市参事会[デクリオネス]によって政治権力を奪われており、それは丁度ローマにおいて市民の権利が元老院によって奪われていたのと同じであり、それ故、言及されている土地制度の相違があった場所においては、それは続けて市民を新たに分割し直すという目的はもはや持っていなかった 28)。また帝政期において各植民市に対する純粋な等級としての称号の付与ということが多く起きるようになったのかもしれない 28a) ;そこにおいては確かに単に外面的な把握の仕方について争われたに違いなく、それは例えばあるゲマインデの地位が植民市の中で変えられた時に、そこでは新たな住民を[何らかの原理に従って]演繹的に作り出すということは行われず、必然として純粋に呼称について、その内部での人間関係についての実質的な意義は全く無しに、単なる表向きの称号だけ――例えば「四人組」[quattuorviri, IV viri]管轄地域ではなく、「二人組」[duoviri, II viri]管轄地域など≪「四人組」、「二人組」はその名前の通りの人数の者が委員として組んで植民市の行政に携わるもの。地位としては「二人組」の方が上。≫――が問題となっていたのかもしれない。
28) 唯一の例外はネアポリス[ナポリ]であったかもしれない。もしそれがカエサルの植民市であったとしたら。しかしこのことは全く確からしくない。(プリニウス≪ガイウス・プリニウス・セクンドゥス、23年~79年、「博物誌」の著者でかつローマの属州総督。≫はこの植民市を知っていない。
28a) D.1 §3 de censibus [ケンススについて]50, 15: Ptolemaeensium … colonia … nihil praeter nomen coloniae habet. [プトレマイオスの植民市は、名前は植民市となっているが、その中身で植民市的なものは何もない。]
そういったことと対立することとしては、測量人達が、植民市におけるムニキピウムについて、法律が変更された 29) というケースを、はっきりと彼ら自身に関係する問題として取り扱っているということである。更にゲリウス≪115年頃~180年以降、ローマの著述家、Noctes Atticae(アッティカの夜)の作者。≫(16、13) 30) に拠れば、ハドリアヌス帝≪在位117~138年、五賢帝の一人≫の時代にはそのことが実質的な意味を持つようになっていた。そしてその結果として我々が知っているのは、プラエネステ≪ローマの東35Kmにある都市、パレストリーナ≫がティベリウス帝≪在位BC42~AD37年、アウグストゥスの後を継いだローマ2代目の皇帝≫の時代に、植民市の地位からムニキピウムに戻してもらいたいという要請をしているということであり 31)、それについては何か現実的な理由があったのに違いないのである。このことから次のことが直ちに推定される。つまりその理由は、ローマ式の測量方式を植民市の土地に適用するということに関係があり――しかしそこにおいての実際の動機を知ろうとすることは、次のことを行った後にやっと見解を得ることが出来る。つまりどのような法的かつ経済的な特性をこの測量方式の適用はもたらし、そしてどこにおいてその実質的な意義があったかということを明らかにすることが出来た後である。その際に我々としてはまずイタリア半島において、一貫して市民植民市に適用されたケントゥリアによる分割、つまり土地税が免除されたローマの耕地から考察を開始すべきであろう。
29) P.203, 8はそのように読める。
30) イタリカ≪スペイン南西部の植民市≫とユーティカ≪古代フェニキア及びカルタゴの都市で、後にローマの植民市となったもの。≫について述べられている。
31) ゲリウス、1.c. 参照。
II 私法的・経済的な非課税耕地の性質
原則的なこと:ただ次のような耕地、つまり割当ての手続きの際に土地税もその他の現物負担も無い状態で譲渡された耕地と、またはその耕地について特別法によってその耕地の法的な分類が特別に与えられた耕地は、それらが土地改革法の全体と関連付けられていたということは、疑い無く正しいと考えられる。そういった耕地の特権とは、それらは特に643u.c.(BC111年)の土地改革法からもまた生じたのであるが、次のようなものである:
耕地に与えられた諸特権
1.そういった耕地は censui censendo ≪ケンススに登録すべきもの≫であり、つまりケンススの登録簿の中に入れても問題無しとされた耕地で、そのことは兵役や納税義務の、及び政治的な権利の基準となったのであり、ケンススの帳簿に登録されるべきものであり、それによって専ら賃貸借の際の公的な引き渡し保証等の目的に使用されたのであり、その際に相続された家族の所有地(ager patritus [先祖代々の土地])について、ある確かな、しかし詳細はよく分っていない優先権が与えられたのである。
2.そういった耕地は、ただそれのみが、ローマの国家で認められた取引きの形態の、特に土地の購入の、それ故に更にまた対物訴訟においても対象とされ、その手続に従うものであった。
ケンススに登録される資格を持つということ
上記の1について:グラックス兄弟による viritane Assignation ≪組織的ではない、個別植民への土地割当て≫は、それが ager vectigalis [課税地]とされた場合にはケンススに登録すべき土地とされた。またある耕地に viasii vicani ≪重要な道路(例:アッピア街道)沿いにあり、その道路の維持義務を負わされた土地≫の義務が課された場合にもその耕地はケンスス登録対象となった 32)。[しかしそれ以外の]グラックス兄弟によって割当てられた土地は完全な所有権に比べると譲渡権を持っておらず、クィリタリウム所有権≪quiritarisches Eigentum、ローマの市民のみに与えられたもっとも上位の所有権≫よりも劣った権利しか持っていない他の全ての土地はケンススの登録対象ではなかった、ということが結論付けられよう。ケンススにおいて、bonitarisches Eigentum≪善意による所有権、正規の法的な購入手続き以外の方法で入手された土地への[そしてそうとは知らず入手した場合の=善意の]所有権、クィリタリウム所有権より法的保護の面で劣る≫をどう扱ったかという問題については、私は同様に間違いないこととして次のように考える。つまりその種の所有権の土地はケンスス登録対象ではなかったのであり、ケンススへの登録対象であったかどうかということは、むしろ法律上のローマ市民の[完全な]所有権についての実質的側面であったのであると。上記の2についての更なる論述は後で、私はそう信ずるが、より高い明証性を持った根拠にのっとって提示される。
次のことは、ローマにおける土地所有権の全体の位置付けにとって更に特徴的である。それは土地改革法がそれによって私有地と宣言された土地の、ある一定のカテゴリーの売却可能性を、規模の大きな投機業においての担保物件の目的で使うことを、それについてはローマの行政がそういう機会を提供したのであるが、特別に規定した 33) ということである。
33) P.28
ローマにおいての最上位の権利を持った地所は、まさに他の何よりも、抵当物件として資金調達を可能にする資産でもあった。
銅片と天秤による取引き≪この表現は通常は奴隷解放の儀式のことであるが、ここでは物的取引きまたは対物訴訟のことか?≫
上記の2について、同様に特徴的なことは、銅片と天秤を用いた物的取引きの制限であり、そして――根源的には――ローマの非課税の耕地に対するローマでの対物訴訟の制限であった。この点についてまずより詳しく述べてみることとする。
不動産の売買による所有権移転[Manzipation]と遺言の経済的な意味
不動産とそれに付随する権利の引き渡し形態である Manzipation は、全ての家族の負債と共通経済的な拘束事項から自由である土地について適用されるのであり、それは家族の遺言における無制限の[所有権移転を伴う]処置がそういった自由な土地に適用されるのと同じである。特に後者[=遺言]が本質的に土地政策上の意義を持っていたことは明白である。もし有形物、つまり実質的には不動産とその付属物についての、actio familiae (h)erciscundae [家族間での遺産の分割行為]に対する根源的な制限が、次の条項の結果として:”nomina sunt ipso jure divisa”[法律上は、帳簿(名目)上の資産・債務が分割される](相続人とその相続物という言葉の上での組み合わせに対しても適用される制限)、そういった有形物[不動産]は直ちに諸権利の中で家族との共生経済を故意に重視することと、そして家族間の均等分割の原理により家族の所有する地所が分割されるという危険を生じさせるのであるが、次の事実と結合している。それはそういった[遺産としての不動産の元の大きさのままでの]保持がもっとも重視された 35) ということと、同じく土地所有の政治的な意義においてもやはりそのことがもっとも重視されたに違いない、ということである。
34)より古い時代においても確かにそれらは帳簿上の財産として制限されており、それは「不動産という]その名前が示している通りであるが、その理由は明らかにその当時は私的な土地の所有権がまだ存在していなかったからである。
35) 参照:放蕩者に対する禁治産者宣告の書式と、既に考察して来た praedium patrium [先祖代々の土地]への優先権。
十二表法の制定は、ローマの農民に対して形式的な制限に結び付けられた遺言の自由においてのみ、次のような手段を彼らに与えた。それは生きている間においての家父長権と、また当該の遺産対象の財の選択をいつでも新しい遺言によって変更する可能性と結びつけられた上で、考えられるもっとも明確な形で、[ヴェーバー当時の]現代における我々が相続法と財産引き渡し契約によって達成しようと努めるのと全く同じ目的を追求するための、同時にまた家長の権威を無傷のまま保つための手段であった。後の時代において、こうした手段がどの程度までなお使われたかということは、次のことを扱う法源≪法の存在根拠、ここではその根拠を決定付ける事項≫の範囲によって示されており、それは遺言の単なる言葉の上での解釈と、特に相続に関係する集団である廃嫡者と代襲相続人≪ある正規の相続人が死んだりいなくなった時に代わって相続人になる人≫についての所である。相続人のためにローマにおける家父長は、その相続人以外の他の息子達を相続対象の財産 36) から排除した;それらの息子達は、「相続人の座に居る」者、つまり adsidui ≪ローマ市民の中で納税義務を負いまた軍人になる資格を持つ者≫に対比して、プロレタリウス≪ローマ市民の最下層の身分、プロレタリアの語源≫に所属する者に留まるのであり、その身分についてはまず「子供を設けることが出来ない者」と呼ばれたのであるが――それは蔑視的な表現だったと思われるが、法律上の公式な表現ではそのような言い方はまず許されていなかった――そうではなく「子孫」37)――つまり定住した市民の、――として表現されており、それ故そういった単にその理由のみで cives [ローマ市民]であった者達であり、それは彼らの祖先達がかつては土地所有者であることにより cives だったからである。
36) このことはここで採用された方策の目的と相反するように見えるかもしれない。しかし次のように考えることが出来る。つまり人間関係の政治的側面が確かに経済的側面より重視されたのであると。それに拠って生きるための地所の確保ということが目的だったのではなく、相続する息子とその子孫が、その手中に家のお宝を保持し、トリブスにおけるフーフェ[地所]の所有者として、かつ同等のケンススにおいての階級に留まるということが目的だったからである。
37) 参照:hidalgo (スペイン語、庶子)=fijodalgo, filius alicuius (その他の息子)
これらのプロレタリウス達は、それ故かなりの部分が字義通りの意味で廃嫡者であった。そして確かにまさに次のようなローマ民族の中のある階級の前景に登場するような破片の如き者だったのであり、その階級とは彼らの土地獲得への渇望が(グラックス兄弟の)土地の割当てとローマの侵略戦争[による外地の獲得]によって鎮静化された、そういう階級のことであるが、彼らはその耕作地に居住する[正規の]農民にしてもらった訳でもなく、また都市の小市民という身分にしてもらった訳でもないのである。土地所有についてのその処分の自由の厳格な実施とその完全な流動化を勝ち得たいという願望がローマの対外的な拡張を推進する上での強力な梃子となった 38)。
38) (ローマの)征服戦争によって勝ち取られた領土においての(相続の権利のない)その他の息子達の扶養がもし不可能であったとしたら、その場合はそういった息子達を相続から除外することによって家族の所有地をそのままの大きさに保つことも不可能になっていただろう。同様の状況はゲルマン民族においては領土獲得欲を刺激されることとなった。ドイツにおけるいわゆる農民フーフェ≪村落共同体農民の所有する耕地≫の閉鎖性が長期間保たれたということは、農民自身の所有地は大地主[グルントヘル]へ依存している[から借りている]土地に比べれば最小限のレベルの面積に過ぎなかったという事情をまず考慮すべきであろう。ただ大地主から借りている地所において、ローマではそれが ager vectigalis ≪納税または農産物の貢納義務のある土地≫であったが、ドイツにおいては隷属農民がそういった土地を使用しており、そういった形でのみ地所が継続して分割されずに一体性を保つことが出来ていた。――そのことに関連し、その他の特徴としてそれらの文献の中で主張されている次のような関連事項が存在する。それはつまりローマの耕地領域の[対外侵略による]拡張が完了し、そして[植民市の建設とそこでの土地割当てという形で]定住のための土地が実質的に意味ある形で用意された後に、[相続を限定するための]遺言の自由が非公式の法的な擬制として百人組[ケントゥリア]裁判所で実践的に処理されるようになった、そういう事項である。――部分的に植民地開拓政策の意味を持っていたローマ古代の ver sacrum ≪聖なる春。古代ローマで凶作の秋や戦争に負けて危機にあった時の翌年春(3月、4月)に生まれた新生児を神への捧げ物とし、その新生児が成長して一定年齢になると新植民市の開発のため未開の地に送り出した故事。≫は、それが故郷のゲマインデの中で余分な人間とされ、扶養家族の埒外に置かれていた者達の中から選ばれた者が、つまりはその理由のため新生児の時に神に捧げられその者が成長した若者を意味する限りにおいて、次のことは正しい。またこのやり方が神々への捧げ物という神聖な儀式として行われているということも、同様に次のことを正しいと思わせる。それはつまり、この ver sacrum が行われたのより更に古い時代の人口政策、つまり神への生け贄が、どちらもその目的は同じだったのであると。それは諸民族において、限られた食料自給体制の中で、対外的な拡張でそれを解決するのが不可能だった場合(例えばインドのドラヴィダ人≪インドでのアーリア人が優勢になる前の先住民族≫の例)に[口減らしのために]利用されていたのが、より後の時代になってもなお ver sacrum という形で[新植民地開拓という建て前で]まだ利用されていた、ということである。その他の同様な組織での例としては、ゲルマン民族において良く知られている故郷ゲマインデの何度も繰り返された移住であり、それは古代のゲノッセンシャフト≪タキトゥスのゲルマニアで描写されているような、主従関係のような縦の関係ではなく、同輩・仲間の横の関係を重視する人間集団。ギールケによって上下関係であるヘルシャフトの反対概念としてドイツの集団の本質的な特徴とされた。≫的集団においても見られ、また同じく後の時代の余剰人口についての非組織的に行われた公知の土地への追放があり、その一部は既に存在している耕地であり、またその他の場合はゲマインシャフトが侵略戦争によって獲得した土地であり、こういったやり方が後の時代の土地制度の骨格を作り出すことになった。フロンティヌスは strat. の 4, 3, 12. において侵略と土地の割当ての段々と強まっていく相関関係について述べている。
物的訴訟
特徴的なことは、非課税の私有地[ager privatus]に対する正式な返還手続きについての元々の制限である。(土地という)現物への強制執行という手段が無かったことと、先行する判例に従った利害関係の現金化は、訴訟において原告側の本来の土地の所有者に対し、土地を返還する代わりに、その土地の価格相当の現金を与えただけであったのだが、それは(19世紀末の)今日の取引所法の強制手続きにおいて、(証券の)差額の現金による精算執行と明らかに類似している。こうした類似が偶然のものではないということは、土地を巡っての人間関係についての訴訟においては一般的に採用されているやり方であるということが観察されることによって裏付けられている。
土地測量人が関わる訴訟の類型
ここにおいて、agrimensorische genera controversiam についてより詳しく見ていく必要があるだろう。それはある[測量人が関わる]訴訟類型のことで、その訴訟において土地測量人達が、ある場合は裁判官への技術的な助言者として、また別の場合は彼ら自身が権威のある専門知識を備えた第一審の裁判官として務めたのであり、それはその訴訟が土地の所有権に関するものである場合に限定されていた。測量人達は訴訟の争点となっている所有関係を”de fine”と”de loco”に分ける。前者 39) は土地の(周りの土地との)境界線がどうなっているのかという争いであり、我々にとっては取り敢えずは関心外のものであるが、後者は最初のカテゴリーの争点を超える土地の所有権とその所有そのものについての訴訟である。”de loco”に含まれる訴訟は問題となっている土地の各辺の長さが5ローマフィート(約1.48m)または6ローマフィート(約1.77m)を超えるものについてであり、何故ならそういった面積の土地についての争いは土地の境界についての規則の根本原則に基づいて取り扱うべきものであり、それ未満の面積の土地は正規の所有権訴訟においても、また正当な方法での獲得においても規則外と扱われたからである。”de loco”(広義での)の争点に含まれるのは、境界線の判定以外の全ての土地に関しての争点であり、取り分けde loco(狭義での土地の場所について)のものと、de modo(面積について)の訴訟のそれであった。
39) P.12. 37. 41. 126参照。
この2つの違いについては、特にフォイクト 40) ≪Moritz Voigt、1826~1905年、ドイツのローマ法学者≫が言及している。しかし私の考える所では、それは不当にもその2つの違いを単に裁判の際に使われた証拠の違いにしてしまっており、controversia de loco の場合は単なる何かの資料、controversia de modo の場合は本質的に返還請求と同等の意味を持つ任意のその他の何か、と特徴付けている。もちろん controversia de mode の場合にある一定レベル以上の文献資料を証拠として挙げることは本質的なことであり、controversia de loco の場合はそうではなかったが。しかしながらこの2つの違いはそれぞれにおいて異なっている訴訟原因と申し立ての法的な性質に関係しているのである。
Controversia de mode と de loco
Controvesia de mode はある当事者の次のような主張の結果としてそう分類される。それはその当事者の土地の所有は耕地測量図[forma]に拠るのではなく、証拠能力のある所有権移転行為――特に(正規のやり方での)購入――の権利書式に拠るのであり、そのためその耕地における当該の面積の土地がその者に帰属する、という主張である。その当事者はここにおいて次のような主張をしているのではない。つまりここかどこかの特定の土地区画が法によってその者のものとなっており、それ故その者に引き渡されなければならない、という主張である。そうではなくて、(de modoと)書かれている通り、ただ事実上その者の所有となるべき一定の面積が公の測量地図においての面積とは一致せず、その者に本来帰属すべき全面積が測量地図に記載されていない、ということである;その者が要求するのは事実上の耕地同士の配置の変更とその者が権利を持つ全面積 42) の土地の割当てである。これに対して controversia de loco の当事者は逆に、その者に既にある特定の土地区画が帰属し、その返還を要求し、その土地区画が測量地図の上では彼に帰属すべき面積の土地としてその所有とされていないと訴えているのではなく、むしろただ権利の保護、つまりそれによって彼が実際の土地の獲得が保証されること、それを要求しているのである。2つの訴訟の本質的な違いはそれ故にまず第一は、controvesisa de loco の方は多くの場合 ager arcificius ≪未分割の土地≫について起きているが、しかし de loco の方は既に分割割当てが済んでいる耕地に対しても起こされることがある。一方 controversia de mode の方はそれに対し、ただ既に測量地図に載っている耕地に対してのみ起こされることが可能であった 44)。
40) Ges. d. Wiss. Phil. – Hilst の第6巻の論文の CL. 25, P.59 (1873) 参照。
41) P. 13, 45, 76, 131 参照。
42) それ故に643u.c.の土地改革法において、C.グラックスがカルタゴにおいて市民に与えた土地の内で一部のあまりにも大面積の土地区画を制限しようとした時に、以下のように規定している。
neive (IIvir) unius hominis (nomine) … amplius jug. CC in (singulos
homines data assignata esse fuisse judicato).
[もし(二人組委員会により)一人の男(の名)に対して…200ユゲラ以上の土地が割当てられている場合は(一人に割当てられている、またはそう判定される場合には)]
controversia de mode はそれ故より広い面積の土地を得ようとすることは許されていなかったか、またはたとえ訴えることが出来ても何の成果も得られなかったかであり、その訴えが何とか認められたとしても、耕地に対しその認可の結果として耕地の(再)整理が行われ、そして権利者に対してごくわずかの面積の追加が認められたぐらいである。ただ面積のみが割当ての対象であり、具体的な地所が対象物なのではなかった。
43) ラハマンのP. 13, 43, 80, 129を参照。
44) フロンティヌ P. 13, 3 controversia de loco について:haec autem controversia frequenter in arcifiniis agris … execetur.
[この類型の訴訟はしかししばしば ager arcifiniis に対して行われている。]
しかし同じ書のZ. 7には:de modo controversia est in agro assignato. [controversia de modo は割当てられ済みの土地に対して行われている。]同様のことが前注で引用した箇所でも引用されている。
Controversia de modo の法的性質
まず第一に controversia de modo について考察してみたい。その実際の成果について、学説彙纂の D. 7 (actio) finium regundorum (10, 1)[境界線確定訴訟]が規定している:De modo agrorum arbitri dantur, et is, qui maiorem locum in territorio habere dicitur, ceteris, qui minorem locum possident, integrum locum assignare compellitur. [ある土地の面積について裁定が行われ、ある者で、その地域で大きな面積の場所を割当てられている者は、他の者で、より小さな場所しか持っていない者に対し、全体の場所を(再度)割当て直す(それによって自分の土地の一部をより少なくしか持っていない者に渡す)ことを強いられる。]
全く同様のことが測量人達の言及する別の文書中にも登場しており(P.29, 45)、その結果として該当の耕地の一部分において事実上の新たな分割が行われており、境界線を新たに引き直すことにより、それぞれの土地の所有者に対してその者に帰属すべき面積の土地が(新たに)割当てられている。
45) フロンティヌス、de contr. agr. II P, 39, 11ff. 47, 21ff。
測量人はその際に forma に付属する土地の外形図を用い、その境界線を引き直し 46)、測量地図[forma]が個々の引き受け地の面積情報を提供している明細 47) を用いて、元の境界線をなるべく再現するよう努力する。その際にその土地の耕作状況についての手がかりとなるものを提供し 48)、あるいは測量人は新しい境界線を引いて、それによって各自に帰属すべき面積が保たれるようにする。
46) フロンティヌスのP. 47, 21, 48とニプススのP.286, 12f. 290, 17fを参照。境界線というのはただこの目的のためだけにあった。P. 168, 10ff。
47)つまりはフロンティヌスのP. 55, 13を参照:si res publica formas habet, cum controversia mota est, ad modum mensor locum restituit.
[もしローマ共和国が controversia de mode の訴訟の際に、その土地の測量地図を保持しているなら、測量人達はその面積をそれによって再確認する。]
ここでは間違いなく公有地について述べているのであり、面積に関する争いの解決については測量地図[forma]に記載されているものが決定的な力を持っていたということである。
48) フロンティヌス、前掲書、Agg. Urb. P. 11, 8f。
こういった手続きは境界線を調整する通常のやり方ではなかった。何故ならば古い境界線を新たに引き直すのは、目的を達成する上で取り得る数多い手段の内の一つに過ぎないからである。この新しい境界線を引き直すというやり方は、権利を受ける者に対して国家が[測量地図という]書面で確認している土地の割当てに対して行われている。しかしそういった土地については、公の測量地図においては、はっきりした境界線を持った具体的な地所が割当てられているのではなく、ただ一定の面積のみが割当てられていたのである。この面積の割当てということが、この測量地図を作成して割当てを行う手続きの本来の目的である。しかしながら測量人達の時代においては、この手続きはその実施の際に様々な方向への本質的な改変を受けるようになっていた。まずはフロンティヌスが controversia de modo について次のように注記している(p. 45. 11ff):
Quom autem in adsignato agro secundum formam modus spectetur, solet tempus inspici et agri cultura. Si iam excessit memoria abalienationis, solet iuris formula (non silenter) intervenire et inhibere mensores, ne tales controversias concipiant, neque quietem tam longae possessionis inrepere sinit. Si et memoria sit recens, et iam modus secundum centuriam conveniat et loci natura indicetur et cultura, nihil impediet secundum formas aestimatum petere: lex enim modum petiti definite prescribit, cum ante quam mensura agri agatur modus ex forma pronuntiatus cum loco conveniat. Hoc in agris adsignatis evenit. Nam si aliqua lege venditionis exceptus sit modus, neque adhuc in mensuram redactus, non ideo fide carere debebit, si nostra demonstratio eius in agro non ante finiri potuerit quam de sententia locus sit designatus.
[しかし(再)割当てにおいて、いつ測量地図の土地について面積が見直されるかは、多くは検査の時と耕作(開始)の時期であった。所有権の移転がいつ行われたのか既に分からなくなっている場合は、測量人達は(無効になっていない)権利証を介在させ使うことで、そのような議論が行われるのを防止し、長期間の所有の平穏さが乱されるのを許さないようにする。もし所有権移転の日時が最近のもので、既にその土地がケントゥリアの形で割当てられ、また具体的な地所の場所が指定され、耕作も行われている場合は、測量地図[forma]に則ってその土地の再評価を要求することを妨げるものはなかった。法は実際に間違いなく、面積の再評価(要求の権利)を規定しており、以前どのようにその土地の測量が行われ、その土地の公表された測量地図による面積が決められたか再調査を要求出来た。このことは土地の割当ての際に実際に行われていた。もし何らかの土地の売買に関する法律に則り、その土地の売買契約にて面積が除外されており、さらにまたその土地の測量が行われていない場合、その土地の割当てに関する判断が完了する前に我々測量人がその土地の面積の証明を出来なくとも、そのことによって我々の信用が失われるべきではない。]
つまりここにおいては、いつ成立したか分からない所有状態と新しい割当ての実施が対立するものとなっている。フロンティヌスの叙述から分かる結果としては、測量地図に基づく請求権はもはや使えず、そのために本来の土地の面積に関わる訴えは進めることが出来ないということである 49)。しかしながらまた、いつ成立したか不明の所有状態が存在していない場合でも、公的な測量地図と正式な証拠による土地割当ての要求は、その請願人に帰属すべき面積について次のような考え方が適用されるまでには至ってはいなかった。それはある特定の土地区画が通常の Usukapion ≪長期にその土地を使用していたことの結果としての時効的なその土地の取得≫によってとまたローマ人の間での一般原則によって、さらにまた善意≪法律用語で、ある事情について知らなかったこと≫による獲得と引き渡し[emtio= emptio とtraditio]を理由とするその土地の利用の事実によって、その土地がその当事者の所有物としてそのまま認められる、という考え方までは適用されていなかった。ここにおいては、ある特定の土地の権利と例外としての面積についての要求は対立しており、そういう権利状態は、書類上の所有権と実質の所有権の間の、同様の状況として常に繰り返される[対立]関係を思い起こさせるのであるが、それについては後で更に広範に論じる。ここから既に生じていることは、古い耕地区画においての面積に関する訴えは稀であったということと、また早期の土地割当ての分については、そこでは非常に数多くの所有権移転が起こりまた土地区画の新規設定が行われたのであるが、それについて面積の訴えを起すことは多くの場合もはや実際的なことではなかった 50)。それについても測量人達がやはりそう述べている 51)。
50) ヒュギヌスが controversia de modo について述べている箇所(P. 131、16)を参照:
hoc comperi in Samnio, uti quos agros veteranis divus Vespasianus adsignaverat, eos jam ab ipsis quibus adsignati erant aliter possideri, quidam enim emerunt aliqua loca adjeceruntque suis finibus et ipsum, vel via finiente vel flumine vel aliquolibet genere: sed nec vendentes ex acceptis suis aut ementes adicientesque ad accepta sua certum modum t axaverunt, sed ut quisque modus aliqua, ut dixi, aut via aut flumine aut aliquo genere finiri potuit, ita vendiderunt emeruntque. Ergo ad aes quomodo perveniri potest … ?
[サマニウムについて私は以下のことを発見した、つまり神聖なるウェスパシアヌス帝≪在69~79年、皇帝ネロ死後に内戦状態になり3人の軍人出身皇帝が短期間に乱立した後を収拾し、初めてアウグストゥスの血統以外の者で皇帝になった。ローマの皇帝は多くが死後神格化した。≫がここにおいてどのように土地をヴェテラン兵達に割当てたかを。そういった土地は割当てられた人達自身によって様々に異なった形で所有されていた。ある者は他の場所の土地を購入し自分に割当てられた土地にそれらを追加した。別の者の土地は[ケントゥリアの本来の境界線を越えて]道路が境界線になっていたり、あるいは河川やまた他の種類のものが境界線となっていた:しかし彼らが割当てによって得た土地の一部を売ろうとしたり、または新たに買った土地を割当てられた土地に追加しようとする場合、彼らは[元々の割当てられた土地の]正確な面積の情報を持っていなかった。しかしながらともかくもそれぞれの土地の面積を何とか算定し、また前述したように道路や河川や他の何かが境界になっている場合の土地の境界線を確定し、売買出来ている。しかしながら一体どうやって金銭的価値を査定することが出来たのであろうか…?]
51) controversia de mode と de loco の間の全体の関係は、全ての土地制度史家に次の事項を思い起こさせるに違いない。デンマークの≪ヴェーバーがこれを書いている時はドイツ帝国領≫シュレースヴィヒ=ホルシュタイン地方において行われたReebning≪デンマーク語でReebはRebの古形でロープの意。ロープを用いた測量・囲い込みが原義でヴェ-バーがここで言及しているのは測量を定期的にやり直して耕地を再分配する耕地整理のこと。ここはドイツ領になる前から多くのドイツ零細農民が入植していた。≫においてのいわゆる Stufland≪ハンセンの書によれば、ドイツでのいわゆるフーフェの割当て地を分割時の大きさの観点でJard、Drömel、Acker、Bredeの4種に分類したもので、その結果長方形に分割された土地が帯状(=階段状)に並んでいたことから。それらが売却・譲渡の対象となった。 Georg Hanssen, Agrarhistorische Abhandlungen, P.216: Uüberträgt man diese vier Abstufungen auf die Hufen verfassung selber so würden , wenn der Acker die ursprüngliche Quote der Vollhufe in jeder Gewanne war, korrespondiren Halbhufen mit Jard, Vollhufen mit Acker, Dreiviertelhufen mit Drömel Anderthalbhufen mit Brede .≫である。この Reebning の処理は知られている所では(ハンセン≪Georg Hanssen、1809~1894年、ドイツの土地制度史家・国民経済学者≫のAgrarhistorische Abhandlungen の第1巻のP. 54以下)、次のような状況で行われている。それはフーフェの制度に従って、つまり地主が耕地の中に点在する形で配置された耕地全体への新規の土地獲得さらに個々の地主の新規獲得というそれぞれが、というのはその処置によって土地所有の状態に混乱が生じており、土地を割当てられている地主達は、それらの個々人に新規に割当てられた土地、あるいは全体で得られた新規の土地については、もはや従来のフーフェの制度で割当てられた面積での所有に留まるのではなく、新たに測量し直し、必要な限りにおいてフーフェ法(ユッチュ[ユトランド]法、I. 49, 55;シェラン島[ゼーラント]法、II. 54)に基づいて、新たに分配されるべきと主張してからである。本来(のフーフェ制度での土地譲渡)は疑い無くただ一定の区画面積での譲渡(1/2、1/3、1/8 フーフェ≪ここでのフーフェは面積の単位≫など)のみが許されており、それもただ遺産分割の際においてのみであった。後に――それもかなり早い時代に――また(面積だけでなく)具体的な土地区画を切離して譲渡することが許されるようになった。そしてReebningの手続きが行われるようになった時代になると、次のような結果となった。つまりそのような titulo singulari ≪原義は単一のタイトルでの、遺産相続以外の方法で獲得した、の意味≫として獲得した土地、つまり Stufland であるが、Reebningの手続きに関係せずそのままに置かれていた限りにおいて、それらの土地は再分割対象の土地には入れられなかったに違いなく、そうではなくその所有者に対して所有についての何らかの証明が存在することを前提として、元の土地の境界がそのまま保たれた。(更にハンセンの前掲書のP. 56に引用されている、1770年1月26日のシュレースヴィヒにおける囲い込みによる土地の整理、を参照。≪このシュレースヴィヒにおける耕地整理については、https://core.ac.uk/download/pdf/144438104.pdf 田山輝明 著、「十九世紀北部ドイツにおける耕地整理法の生成」を参照。≫)それはまさに titulo singulari 一般によって獲得された土地に対しての処置と同じであったが、――後で述べることになる本来的な権利状態についてここで付け加えて言っておくべきことは:それは controversia de modo の結果として新たに分割し直された時効取得された耕地と同じことであるということである。この類推については後で更に述べることになる。――次のことは明白である、つまり土地区画の分割譲渡がしばしば行われていた耕地においては、Reebningの手続きはすぐに非現実的なものになったに違いない、ということである。
その他にしかしながら、我々が知っている裁判手続きに従って、裁判での争いが最後まで終らなかった場合には、controversia de modo の訴訟についての調査は、史書に登場する時代においては、所有状態を実際の土地について変更するということにはならず、どちらかへの金銭支払い命令といういことになったのであり、土地の面積に対しての要求は、先に引用したフロンティヌスの箇所が示している通り、aestimatum petere ex forma [測量地図に基づく査定請求]へと変化したのであり、その当時はそれ故確かに通常の所有権移転請求[vindikation]の特別な場合だったのであり、ただ特別な訴訟を起す動機だったのである。実際の土地の再測量は次の場合にのみ行われた。それは訴訟の当事者達が測量地図修正の判決に従った、その再測量は測量人達の協力によって実現したのであるが、そういう場合である。そしてそのことにより、controversia de modo は確かに効果の点においては根本的な所ではそれとはっきり区別されている controversia de loco に近付いていったのである。
controversia de loco との関連
この de loco については、通常の場合、ある特定の土地区画についての所有名義が保護されるのであって、その返還を目的とした合法的な、または actio publiciana ≪プブリキアーナ訴権、法務官プブリクスによって新たに認められるようになった、正式な所有権を証明出来ない場合でも、一定の時間の占有などでの事実上の所有者を保護する法的手段≫に基づく所有権移転請求である 52)。
52) フロンティヌス、P. 44, 8, そこでは controversia de loco の提起が、Interdictum Uti possidentis ≪執政官(praetor)が正式な所有権を証明する証拠書類を持っていない事実上の所有者の権利を保護するために発する命令のこと≫と vindicatio ex jure Quiritium ≪ローマ市民としての正規の所有権に基づく土地の返還請求≫と同一視されている。更にヒュギヌスの P. 129, 12: De loco si agitur. Quae res hanc habet quaestionem, ut nec ad formam nec ad ullam scripturae (= Munizipationsurkunde) revertatur exemplum. Sed tantum hunc locum hinc dico esse, et alter ex contrario similiter.
[もし土地の場所について訴えが起された場合。その土地の現状についての調査に基づき、例え測量地図への記載も無く、また何らかの購買の証拠がな無い場合でも、該当の土地が返還されるべきだと主張する、但しこの場所についてそのように主張したとしても、相手側も同様に反対のことを主張する。]
測量人はこの形式の訴訟においては従属的な役割しか果たしていなかった。それについては測量人達自身がそう述べている 53)。ある耕地の一断片の測量をやり直すなどということはここではもちろん全く考慮されておらず、ここで問題となっているのはただ、ある具体的な面積の地所が、法的に認められた所有の根拠に基づいた土地となるかどうかということであった 54)。つまり controversia de loco という訴訟形式の適用可能性と実務的な意義は、時が経つにつれて(成功の確率が低い)controversia de modo のそれを犠牲にすることにより、地所を獲得することが出来るかどうかであった。
53) ヒュギヌス、引用済みの箇所、P. 130, 1:Constabit tamen rem magis esse juris quam nostri operis, quoniam saepe usucapiuntur loca, quae in biennio possessa fuerunt.
[それにも関わらず、このこと(controversia de lolo)については我々測量人の仕事と言うより法の問題であるということをより認めるようになるだろう。何故ならば次のような場所はしばしば正当に獲得したとされる、つまり2年以上使用されていた場合である。]
54) ヒュギヌス、引用済みの箇所、Agg. Urb. P. 13, 9 参照。
ある耕地の中のある区画の譲渡が行われ、その際に売却された土地区画の面積が全く定められていないかあるいは少なくとも測量人による実測に基づいておらず、そうではなくてただ何かの適当な査定としてのみ購買客がそれを了承していた場合、後になってその土地の(正しい)面積を測量地図に記載するということは非常に困難であったか、または全く記載されないということがあり得たのであり、ただその場合での何らかのトラブルの調停は ただ controversia de loco の原則に基づいてのみ可能であった。
55) ヒュギヌス、引用済みの箇所、P. 131 参照。
controversia de modo は以上見て来たような権利状態においては、既に述べたように、ある特別な状況においてのみ適用可能な返還請求及び境界線再設定の訴えについての訴訟種別であるように見える 56)。
56) この境界線再設定の訴えについてはパーピニアーヌス≪Aemilius Papinianus、142~212年、ローマの有名な法学者。≫が先に引用した箇所 D. 7 finium regundarum にて規定しているように思える。controversia de modo が単なる境界線再設定の訴えと少し異なっているということは、既に言及したし、また後に再度論じられる。
土地の面積の本来の意味
しかしながら土地の面積を巡る諸関係の元々の位置付けは異なっていた。
面積による土地の売却
文献史料に従えば次のことは認めなければならない。つまり古典法学が確立する時代までは、ある土地区画が測量による正確な面積の確認無しに譲渡されるということが、それ自体正常なこととは見なされていなかったということと、それに対して全く逆に次のことが当時であっても何か普通のことと見なされていたということである。それはつまり、ある決まった数のユゲラ[面積の単位]があるおおよその大きさの――もしかすると 56a) ケントゥリアの数に拠っているか、あるいはその土地の隣人からの申し立てによる、売却されようとしている部分の境界がどうなっているかという情報に基づき――その申し立てられた耕地におけるある箇所について、モルゲン[ドイツでの面積の単位]当たりの単価を決めて売却されたということである。更にはこの契約の履行においては、申し立てられた面積に相当する地所が測量され、そして買い主に提示された、ということである。それは例えば 1.5 pr. における、si mensor falsum modum dixerit (11.6) 57) [もし測量人が間違った面積を報告した場合]として取り扱われている事例において前提とされている。
56a) このようなやり方で購買対象物件の表示は公的な土地売買において行われたのであり、それについては u.c. 643年の土地改革法が規定している。
57) ウルピアヌス≪Gnaeus Domitius Ulpianusu、170年頃~228年、古代ローマの著名な法学者。学説彙纂に採用された学説の内、1/3はウルピアヌスのもの。≫の、I. XXIV ad Edictum [布告に対して]。Si mensor non falsum modum renuntiaverit, sed traxerit renuntiationem, et ob hoc evenerit, ut venditor laederetur, qui assignaturum se modum intra certum diem promisit etc. [もし測量人が誤った面積を報告せず、さらにその報告を継続してしない場合、これが起きたことにより、どのように売主が糾弾されるか、その売主は面積の確定していない割当て地をある一定の日数の内に売却しようとしているが、等々。]
つまり:売却されているのは面積なのであり――いずれにせよ価格はユゲラ当たりいくら、で決められており、そして次に測量人がこの面積に相当する土地区画を実測することになり、それによって売主はその土地を確かにそういう面積を持ったものとして、ここに言及されているように、買主に売却することが出来る。逆の注解では、ある特定の土地区画が売却されることになっていて、その面積が価格の確定のために後から決定されることになっているのは、それ故に許されておらず、その場合は売主の側が[売却後に]何らかの訴えを起すことは不可能となったからであろうからである。このことにはしかし前提があり、もし、それは実際に起こったことだったが、面積そのものが購入の対象として通用し、そして売主がそれ故に適切な時期までにこれらの面積の[確定と]引き渡しを行うことが出来なかった場合、それは取引きの中止につながった。
もちろん当時通常のやり方であったのは、ある決まった面積の土地に対して、それが購買対象として検討され、そしてある一定のモルゲン当たりの価格が取り決められる;それからその土地が測量され、その結果に従って購買価格が決定される 58)。
58) このことは D.40, 51の de contrahenda emtione [購買取引について]にて規定されている。(両方ともパウルス≪Julius Paulus, 2~3世紀、ローマの著名な法学者≫による。)
D.45の de evictionibus (21,2)[明け渡し、または取戻しについて]においてアルフェヌス≪Publius Alfenus Varus, BC1世紀のローマの政務官・法学者≫はそれにもかかわらず次のことを必要なこととしており、それを特に強調している。それは売却された面積の土地が[測量の結果]取り決められた面積と違っていた場合、疑わしさを含む引き渡し義務については、最初に取り決められた面積の方が決定力を持つ、ということである。ユゲラの数[総面積]を売却し、そして価格を1ユゲラ当たりの単価によって[取り決める]という慣習と、購買の対象が土地の面積であるという見解は、次の考え方よりもはるかに強い実効力を持っていた。つまり、一部の土地の引き渡しにおいてパウルスが1.53の同じ箇所で更に次の意見を主張しており、それはそういった場合には引き渡された土地の実質的な価値に拠るのではなく、売主はただ実際に引き渡され所有権が移転した面積に対して[実際の面積との違いの分の]賠償責任がある、という意見であり、それは同様にまた D.4,§1の de actionibus empti venditi [売却と購買の行為について]において売主の責任を何よりもまず約束された数のユゲラに関連付けているからでもあり 59)、スカエウォラ≪Scaevola, 共和国初期の英雄的人物。ここではその一族の法学者の D.Cervidius Scaevola のこと。≫の D.69,§6の de evictionibus (et duplae stipulatione)[合法的売却について]も同様である。
59) ただある一定の数のユゲラのぶどう畑、オリーブ畑等が売却される場合、――土地台帳上の分類に依拠するのであるが――その土地の価値評価はその土地の[面積だけでない]実質価値に応じて成されなければならなかった。パーピニアーヌスは D.64,§3 de evictionibus にて、それと対立するより近代的な主張をしており、部分的な引き渡しの際は常に土地の実質的価値に依拠すべきとしている。
ついにはこのように意図された取り引き慣習は、測量人達のある種の弁済義務から、彼らが Si mensor falsum modum dixerit [測量人が間違った面積を申し立てたとしたら]という表題の法 (11,6) によって、測量人の資格が剥奪され、次のような事態が生じる。つまり、そういった罪状が次の形で出されるということであり、――1.5 pr. の引用済みの箇所で――ある者が一定の面積の土地を売り、そしてその測量人がその該当の面積があるとされる区画の土地を測量することを委託され、そしてその際に虚偽のやり方で、実際の面積より多く(1.3,§3 前述の箇所)あるいは少なく(1.3,§2 前述の箇所)測量の結果を申し立てた、という罪状である。一般に理解されていたのは、土地区画の購入は全く本質的に面積のみに関連付けられるものである、といいうことである。次のことは全く不思議ではない。つまり土地という物は本質的に次の考え方に基づいているということであり、それは正規の購入は、ある限定された地所の現物の引き渡しであり、それはまだ所有権の移転ということが知られていない時代において、それ故に法学的にはある特定の地所ではなく、ある決まった土地の面積の引き渡しであったという考え方である――そしてそのことは再びその該当の土地について、測量地図は割り当ての際にただ面積のみを記入しており、またケンススの担当官に対しても面積が報告されたのであると。というのは次のことは確かなことと考えられ得るからである。つまり我々に伝えられている、市民の地位のその財産の金銭価値による分類が、同様な考え方の土地の耕作面積の大きさによる分類を先導したのであり、特に何らかの種類の耕地ゲマインシャフトの基礎となる土地制度がまだ成立していた限りにおいては≪ヴェーバーの当時、古代ローマでも昔はゲルマン民族と同じように耕地をフーフェとして共有する耕地ゲマインシャフトが存在したと考えられていた。しかし後にこの考え方は歴史的事実と必ずしも合わないとされた。ヴェーバーの「一般社会経済史要論」(講義録)を参照。 ≫、次のことは非常に確からしいと考えられる。それは土地面積の金銭価値の評価は、まさにより古い土地制度を除去することによって成立し、また同時に地所についての個々人の所有権の断固とした導入も行われたのであり、そしてしかしまたそれは、罰金を科す際の、土地の面積当たりの法的な金銭価値換算相場の決定にも非常に類似していた。そのために発生したのが、個々の市民がその時々に所有している土地の面積を確認する可能性についての直接的・公的な関心であった。
61) シクルス・フラックス(p.138, 11)は土地の占有者と土地の分割割り当ての間の対立について述べている:Horum ergo agorum nullum est aes, nulla forma, quae publicae fidei possessoribus testimonium reddat, quoniam non ex mensuris actis unus quisque modum accepit …
[それ故にこれらの土地の金銭価値は0であり、所有者によって公衆の信用のために証拠として提出される測量地図も無く、何故なら誰も測量の実施によって確定した面積の土地を受け取っていないからである。]
しかし測量地図は土地の所有者にそのような公的な証拠としてその土地区画の境界線を与えるのではなく、この部分でまた述べられているように、ただ面積のみの情報を与えるのである。それ故に考えられるのは、売却した面積を権利の引き渡し書式とその他の必要文書の中に記載することは、法的には元々必須だったということである 62)。
62) これらの諸関係の実務的な側面の評価においては、現代的な考え方を自制することが必要であり、正規の購買手続きを所有権移転の際に利用するという伝統は、必ずしも必要なものではなかったのであり、それについては既に述べた。ある決まった面積が正規購入された場合、その売却された耕地における土地の測量がまだ行われていない段階では、これらの面積に対しての買主の請求権さえもまだ生じていなかった。次のことは自明であるとは言えないであろう。つまりただ具体的な境界線を持った地所のみが購入可能であったということは。全てのフーフェ原理によって――常に個々の事例でその原理が形成されたように――組織化された土地制度は、土地の分割売却が一般的に可能になるや否や、最初は割り当て地の(面積の)売却が行われ、次にようやく具体的な地所の売却が行われる、という風に変化して行く。次のことが想定される。つまり、このことがローマ法の発展の中でおそらくは全く同様に起きていた、ということが。
我々はそれ故により古い時代については、面積に基づいた売却と面積についての訴訟は、割り当てられた土地について特徴的なことであったと考えるべきである。2つの現象[controversia de loco と de mode]の発展史と意味については、さらにいくつかの推論を行うべきであろう。
割り当て面積の売却と土地区画の売却
元々フーフェで割り当てられた土地全体を売却することと、その際にまた元々の割り当てられた土地区画の一部を分割して売却することが全く許されていなかったのが、早い時期においてどのように一般に許されるようになったかの過程は、もちろん我々は全く知ることが出来ない。我々が唯一結論付けることが出来るのは、譲渡が出来る方向に向かって、耕地全体から相対的に完全な個人の所有地へと分離された相続された土地がまずは譲渡不可というルールから除かれたということであり、また耕地ゲマインシャフトというものが――常にそういう性質を持ったものとして――成立していた限りにおいて、一般的な何らかの売却の制限が広範囲に存在していたのであり、このことは更に言えばより古い発展段階にあった全ての耕地ゲマインシャフトにおいて自明のこととして存在していたことからも裏付けられる。≪前注で述べたように、このころはいわゆる発展段階説で世界中の全ての地域で、社会は耕地ゲマインシャフト=一種の原始共産制という段階を経るという考え方が支配的であった。≫しかしより普通でないと思われるのは、ある耕地ゲマインシャフトにおいての、個々の実際の土地区画の売却であり、それが起きたのはある一人のゲノッセンシャフトの構成員に対してある耕地の広がりの中で帰属させられている(土地所有の)権利の一部分の譲渡が、より古い時期においてしばしば可能であると認められるようになっていた 63) 時代である、耕作地の面積単位での売却は、ここで述べた見解に従えば、合法的売却の本質を成しているのであるが、その位置付け自体は割り当て地の面積単位での売却と具体的な地所単位での売却とのおおよそ中間にあった。更に確実なことと考えるべきなのは――なるほど耕地ゲマインシャフトの形成はそれぞれ個別に発生したのであるが、そのゲマインシャフトの志向としては、一般論ではあるが、そしてローマにおいては全く疑いようがなかったことであるが、つまりはそれは氏族を中心とした集団形成ではなく、ゲノッセンシャフト的に組織化されたものであった≪ヴェーバーはここで元々ゲルマン民族の社会形成の原理であった筈のゲノッセンシャフトが古い時代にはローマにもあったとしていることに注意≫――、最初から次の2つの権利概念は厳密に異なるものとして発展したということであり:フーフェの権利(この表現を使うとしたら)、つまり耕地ゲマインシャフト一般に参加する権利の付与、そしてそこから発生する個々の受益者に耕地の個々の部分において帰属せられる特別な資格の[権利の]範囲である。後のものは前のものの結果であるが、ただフーフェの権利付与についての問いが、個々のそこから導かれる諸権利、例えば hereditatis petitio [相続請求]から相続においての個々の対象物への請求[権]の源泉となっている。
ローマにおけるフーフェの制度
ゲノッセンシャフトの成員の[土地に対しての]権利を表現する技術用語は、[ラテン語では]”fundus”[農場、一区画の土地の意味]である。この語のこの意味はイタリアの連邦法[都市国家間の連合での共通法、ius inter gentes]においてもまだそのまま残っていた。あるイタリア半島の連邦に属する国家があるローマのゲマインデの決定を自分の国でもそれを受け入れ布告する場合、その場合それはその国でも””fundus fit”[作り出された土地への権利]と呼ばれた。その意味は、その場合その国は(ローマとの関係で)法ゲノッセ[法ゲノッセンシャフトの成員]になるということである 64)。
64) マルクヴァルト≪Joachim Marquardt、1812年~1882年、ドイツの歴史家、古代ローマについての書籍の著者≫は”fundus fieri”[作り出された土地への権利]と”auctor fieri”[作り出された売却者]を同じものとしている。ここでその2つの語句の差異について述べる気はないが、差異は間違いなく存在している。元老院が人民が決定したことに対してどのように関与したかについては確かなことは言えない:patres fundi fiunt. [土地の父(所有者)が作り出される。]
この語はゲリウス《Aulus Gellius、125年頃~180年以降、ローマの文筆家、法律家≫(アッティカの夜,19.8)によっても全く同様の意味で使われており、彼はある法案の発議に対し賛成している。
“Fundus”はゲマインシャフトの中で他の成員と同じ地位にある者、つまりゲノッセとしてそのゲノッセンシャフトの一員となり、そしてこのことはまたここで想定されているローマと連邦関係にある他の国家においても全く同じ意味を持っていた。というのもこのやり方は、どの優越した力を持ったゲマインデにおいても禁じられていなかったのであり、それらのゲマインデはローマの諸制度をそれが好ましいものである場合は自分達自身の法にするという形で取り込み、両者を統合したのである。あるイタリア半島のローマとの連邦国でローマの”fundus”となった国は、その制度を、それは明らかに表現としては特別な法的価値を持つものという意味であったが、その当該の法をローマ由来のものとして、多くの場合はその首長から認められたその国家自身の法として作り直す、という形で受け入れたのである。連邦の国家によって fundus fieri [発生した fundus]という形で受け入れられた法を通じて、それ故に同時にまたゲノッセンシャフトの権利と連邦の権利が創出された。そしてもっとも確実で間違いの無い法的な帰結としては、その国に属している諸都市によるその法の一方的な改変は許されていなかったということが言えるだろう。この考え方が正しければ、ローマは連邦の国家の法に対して主導権を持っていたのであり、そしてローマの国家法の中でこういった権限がどのような役割を演じていたかということや、それが国法上の foedus aequum [国同士の相互に対等な条約、同盟]の性格にどういった影響を与えるかということについてはここで述べる必要はないであろう。
fundus の意味が「地所」であるということに関係することは、それは帝政期になってもなお認められることであるが、全ての任意の境界線によって区切られた土地区画が fundus と呼ばれ得る訳ではないということである。無条件に fundus に属するものとされたのは、一方では villa ≪都市外での小農場を伴った宅地、別荘のこと≫であった。また他方では、全ての所有地及び土地への権利で、新規にその所有権を獲得した場合に、それが常に fundus に属するものとされた訳ではなく、ただその土地が家族の地所という形で家計の中に組み入れられた時に初めて fundus と認められたのである 65)。
65) D.27 §5, 20 §7 de instrumento [手段・道具について](33, 7) 参照――両方ともスカエウォラによる、またD.60. 211 de verborum signifiatione [用語の意味について](ウルピアーヌス)参照。
fundus はほぼ常に法的に認められたものというより、事実上成立したという性格のものであり 66)、そしていずれの場合も一まとまりの財として成立していた 67)。
66) 参照 D.26 de adquirenda vel amittenda possessione [獲得した、または失った所有物について]と比較せよ。そこについては部分的に分割された fundus の所有権の可能性について特別に主張されており、それ以外にも D.24 §2 de legatis [遺産について]Iの目立つ表現(maxime si ex alio agro qui fuit ejus …adjecit)[特にもし、ある誰かの土地についてそれを獲得し自分の土地に加えた者が…]がある。
67) これに属するものとしては、また何度も言及されている “dos fundi” [嫁資である土地]がある。それについては、モムゼンの Hermes XI p.390ff の記述と比較してみるべきである。
確かなこととしてある氏族の別名として[その氏族が住んでいる]地名の末尾に “-ianus” を付けたものが使われた≪例:Catullianus≫というのは、ただその氏族のフーフェを代表する土地に対してだけそうなったのである。≪地名に接尾語がついて主として貴族の姓になったというのは、スラブ諸語のーsky、-skiも同じ。例:Александр Невский、ネヴァ川のアレクサンドル→アレクサンドル・ネフスキー≫そういったことを置いておいても出現してくるのは、私はそう思うが、農耕地ゲノッセンシャフトの内部での fundus の古い意味である、フーフェの権利、ゲノッセンの権利に対しての郷愁である。その後共有地の分割が始って以降、――我々はこの先行の現象を「分離」68) と呼ぶことが出来、それが共有地の分割が目差していたやり方なのであろうが――古い時代の、常にそういう性質を持っていたフーフェの権利に関する争いの位置に、fundus 全体の合法的な売却が登場してくるのであり、そして以前に分割されて細切れになった土地区画を再度整理するという希望が、測量人達によって伝えられた来た形での controversia de mode として登場してくるのである。
68)ゲルマン諸族の耕地ゲマインシャフトへの対立概念として、カエサルはガリア戦記IV, 1の有名な箇所でそれを “privatus ac separatus ager” [私有地と分割地]と描写している。≪Sed privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco colendi causa licet.[しかし、彼らの間では私有地や分割された土地は存在せず、また耕作のために一年以上同じ場所に留まることは許されていない。]カエサルによるゲルマン民族のスエビ族についての叙述。≫
これら2つの訴訟形式、つまりゲノッセンとしての権利自体の[土地全体の]請求と、耕地におけるどこか一部に対するゲノッセンとしての持分の[再]割り当て請求(ドイツにおける再統一請求≪17世紀以降のドイツにおいて、分割されて細切れになっていたり、売却されてしまった土地を再び元の状態に戻そうとしてする請求のこと≫とデンマークでの耕地整理[Reebning]≪既出≫請求に相当する)は、訴訟として見た場合で同等の価値を持つものとして取り扱われるべきだ、という考え方は疑わしく思われる 69)。むしろ前者はただせいぜい土地ゲノッセンシャフトの内部の司法手続きによって解決され得るものであり、その一方後者は、既に論じて来たが、更に後でまた本質的に技術的な個別の問題として取り扱う。
69) 測量人達は、controversia de propritate [個人専有物についての訴訟]を controversia de modo と de loco の2つとはっきり区別しており、後の2つは funudus の拡張という位置付けであり、それに対し de propritate の方は、地所全体を一かたまりのものとして扱うものである――p.15, 48, 80. 古代の vindicatio gregis [一群の家畜の返還請求]に相当する法的手段である。
十二表法の時代より後になると、耕地の定住者がトリブスに組織化され、更に後にはそれが百人官裁判[Centumviralgericht→iudicium centumvirale]≪BC3世紀頃に作られた当初は100人の男性で構成された民事関係を扱う裁判所≫に変わって行くのが見出されれる。後者は35のトリブスからそれぞれ3人ずつを選出することで[合計105人で]構成され、誰が相続人、つまり相続権に基づくフーフェの正当な所有者であるかいう問題を扱う法廷となった。ここで更に見出すことが出来るのは、不動産訴訟の領域において、おそらくは百人官裁判と通常の裁判所の間で管轄争いが起きたということである。この点について、私は次のことを疑いようが無く正しいと考える。つまり一般的に土地に関する訴訟について百人官裁判の占有的な管轄権が生じていた限りでは、このことはヴラザック≪Moriz Wlassak、1850~1939年、オーストリアの法学者、法制史家≫の見解 70) と反対であるにもかかわらず、それ自体非常に確からしく――このことが土地の権利についての訴訟で、つまりフーフェの土地全体への認定請求で起きたに違いない、ということである。このことはまた、先決の訴え≪元々の所有権が自分にあるという訴え≫としての legis actio sacrament [in rei] ≪所有権に関する訴訟で、訴えの濫造を防ぐために、原告・被告の双方が供託金を出す制度。裁判で勝った方にはそれは戻され、負けた方はそれを没収される。≫の制度形態とも、さらにはまた所有権請求の対抗訴訟の必要性とも合致しているが、それは≪後に採用される≫ formula petitoria ≪書面による申し立て≫とは対立するものであった。とある2者がどちらがあるフーフェの土地に対しより正当な所有権を持っているかということについて争っている場合、その時々にどちらの権利が相対的に強いかを根拠に基づきはっきりした裁定を下す必要があった。そうでなければ公法に基づく人間関係の中に、耐え難き真空状態が発生してしまう。それに対してある特定の土地区画の返還について争われている場合は、訴えが却下された場合はその帰結としてはただ全てが元の所有者に戻るというだけであった。古きローマの国家の本質に関わる根本原理が段々と失われていくに連れて、もちろん fundus の古い意味への郷愁も消えていったのであり、そしてまた modus agri [土地の面積]の技術的な価値もそれに従って次第に浸食されていったのであり、その結果として、その価値については、ただ貧弱な残余の部分から、つまりは controversia de mode という形で我々に把握出来るものから、逆算して還元して考察することが出来るのみである。
70) Römische Prozeßgesetze [ローマ訴訟法]の各所にて。
土地制度史上の Usukapion ≪土地の実質的使用者による時効による所有権の取得≫の意味
既に述べて来たように、土地における面積原則は Usukapion が認められるようになって以来、根底から突き崩されていた 71)。
71) controversia de loco についてヒュギヌスは p.130.1 にて次のように述べている:Constabit tamen rem magis esse juris quam nostri operis, quoniam saepe usucapiantur loca quae in biennio possessa fuerint. [しかしながら、これは我々測量人の仕事というよりほとんど法の問題です。何故ならばしばしば2年間占有された土地が(時効として)所有を認められるからです。]
つまり:土地の時効取得を認めるということの意味は、測量人達のある種の業務を排除したということである。先に引用した箇所と比較せよ。
というのも、このことが意味したのは次の理由に基づく所有権獲得の可能性であるからである:
1.何かの正当な理由[justa causa]による;――この表現の意味は「法的に有効である」ということで、まず第一に書面による契約に拠らない土地の購入として把握することが、実際は広く行われるようになっていた、ということである;
2.引き渡し;――この点においてこの制度の意味がもっとも明確に現れている:古い形式である Manzipation [合法的な購買]であったがしかし引き渡しが前提とされていなかったものは、フーフェの割り当て地の売却がそのほとんどであった、というよりむしろそれとまったく等しいことであったのであり、というのはその対象となったのは[引き渡しの具体的な約束が伴わない]面積のみであり、それも厳格な意味でのフーフェの割り当て地の面積の売却であり(もしそれが fundus 全ての土地が対象になっていない場合も含めて);新しい土地の獲得の仕方はそれに対して既に具体的な境界線を持った土地区画に対してのものであった。何故ならばそうした具体的な土地区画だけが(実際に)引渡されることが可能だったからである。
3.2年間の占有
このような土地獲得の方法が許されるようになったことの意味は、言ってみれば、従来の面積原理に並立する同等の力を持つ土地の場所[locus]原理の導入であった。というのは Usukapion の目的と実際的な意味は後になって出て来たことで、当初はそうではなかったが、本来正式な所有権を持っていないボニタリー所有権者≪正当な理由(justa causa)に基づいて物件を取得したが、正式な mancipatio 等の手続きを経ていないため、完全な所有権であるクイリーテース所有権を持たない者。manicipatioの手続きには5人の証人と1人の秤持ちが必要で、広く行われるまでには至っていなかった。≫を保護することであった。より古い時代においては、執政官の布告により、それと全く反対のことが起きていた。レネル≪Otto Lenel, 1849~1935年、ドイツの法学者、ローマ法研究家≫の研究により次の事が明らかにされた。つまり2つの布告の内古い方は、(実質的使用者の所有権の)保護を目的としたプーブリキウス訴権≪Lex Publicia に規定された訴権で、正式な手続きを踏まないで土地を取得したボニタリー所有権者が、正規の所有権者であるクイリーテース所有権者を訴えることが出来る権利≫について、善意の(正式な手続きを経て獲得した)取得者の所有権よりも、ボニタリー所有権者の保護を目的としていたのであり、つまりある者で res mancipi ≪土地や奴隷などの価値あるもの≫を本来の所有者から正式な手続きで入手したのではなく、何らかの justa causa [正当な理由、例えば遺言書による遺贈、贈与など]に基づいて(ボニタリー)所有権を得たが、その正式な引き渡しについてはただ口頭で伝えられていた者の保護が目的であった。こうした執政官の(所有権への)干渉は、しかし既に十二表法で認められていた法的な発展を更に一歩進めた、というだけのものであった。
というのは、この布告が発せられた前提はしかしながら、後にそう呼ばれるようになったボニタリー所有権者が、Usukapionの権利が認められるようになる前の段階では、クイリーテース所有権者に対して不安定な状態に置かれたいたということである:ケンススに対してはクイリーテース所有権者のみが正当な所有権者として認められ、同様にクイリーテース所有権者は exceptio rei venditate et traditate ≪売却されたまたは引渡された物への抗弁、所有権訴訟での防御手段で、売却・引き渡しが合法的に完了していることを示すもの≫が成立していない場合においても、次の場合にはその土地に関する権利を容易に取り戻すことが出来た。その場合とは、その者がその土地を暴力によって獲得したのでも、または「秘密裏に」そうしたのでもなく、それによって法廷での争いにおいて占有の保護[interdictum]を与えられ、同様にその土地の獲得に関して Usukapion の時効がまだ満期に至っていない期間は、第三者に対してその所有権を保護された、そういう場合である。(ボニタリー所有権者の土地は)獲得から2年経ってようやく、その土地をケンススに登録する権利が認められ、また個人所有権としての保護の対象となった。こういった全ての措置はただ土地を(面積としてではなく)具体的な区画として購入した場合のみに認められていたのは今や明白である:Mancipation はそれ自体非常に便利な所有権移転の手続きであり、それが利用可能だった場合は、ただ7人もの証人≪実際は5人で7人はヴェーバーが何か別の仕組みと混同している可能性有り≫を呼び寄せる面倒さは、まずはともかく(Mancipation 無しでの)購買契約を結び、そして土地を引き渡してもらい――しかしながらその2つの手続きは後に訴訟になった場合に証拠となる書面を取り交わす形で行われ――そしてその後の2年の経過を待つ、といった(Mancipation ではない場合に)必要な手続きをわざわざ執り行うことの動機には通常なっていなかった。それに対して、こういった Mancipation ではないやり方は次の場合には大いに意味があった。それはその土地の購買者が時効成立の2年間が経過するまでの間において、その特定の地所で引き渡しの対象であったものを継続して保持することが確実だった場合で、かつ測量図やケンススへの登録や、または Mancipation の証拠書面を根拠にした耕地に関する規制に基づいての、その土地の面積や場合によっては境界線の変更の訴えに対抗して、十分にその土地の取戻しが可能となっていたような場合である。それはつまり、デンマークの土地法においての Reebning ≪既出≫の際に、各 Stufland ≪既出≫の権利を保持出来た場合と同じである。前述のより古い時代のプーブリキウス訴権の布告は今や変更が必要となり、土地を獲得した者は、2年の時効期間が満了する前において既にクイリーテース所有権者と同等の権利を得たのである。ただケンススへの登録のみがクイリーテース所有権が認められるまでは行うことが出来なかったが 72)、それは執政官がそれについて何も指示しなかったからである。
72) クイリーテース所有権と Usukapion のケンススとの関係について更なる史料を希望する者は、それを usukapio pro herede ≪相続財産について、相続人がいない、または相続人が相続しない場合に、その財産をある者が一定期間占有することで所有権を得ることが出来るもの≫から引き出すことが出来る。この場合は遺産、つまり被相続人のフーフェの権利の全体について扱われているのであり、その他の Usukapion のように個々の物についてではないが、この場合は単なる占有が1年続けばそれで十分であり、元のフーフェによる農地所有者の死による所有権の停止といった法的根拠なしに、Usukapion の時効を満たしたものとされた。この理由としては、あるフーフェがその所有者の死後直接的な意味で、ケンススに対しても神々に対しても誰も正当な所有者がいない、という事態が許されていなかったからであり、それ故に本来の正当な相続人が1年以内にその権利を行使しない場合は、わずか1年後にはその占有者は単純にそのフーフェの所有者として認められ登録されたのである。
これに対して生きている人間同士の(生前の)売却においての時効までのより長い期間は、それほど問題になることはなかった。何故なら時効が成立した場合に所有権を得る者がその期間が満了して成立した所有権を証明するまでは、元のクイリーテース所有権者がフーフェの権利者あるいは所有者として、元の土地の面積に対して単純に有効な権利を保持していると見なされた≪所有の空白期間が無かった≫からである。usucapio pro heredes について公法的な意味で特徴的なことは、プブリキアーナ訴権の布告における言い回しによれば、ここでの時効による権利取得予定者は、時効成立までの期間において、プブリキアーナ訴権と同様な法的手段を持っていなかったということである。Usukapion の時効が成立するまでは今や次の2つの権利が相互に対立した。つまり de jure の[法律上の]クイリーテース所有権者の「期間限定所有権」であって公法的な意味で有効だったものと、引き渡された土地面積を善意で持っていた者の実質的な[de facto の]所有権の対立である。
所有保護の土地制度史的意味
それでは Usukapion の時効が成立する前において、土地の占有とまた具体的な土地区画の獲得に対して何の保護も与えられなかったのであろうか?(逆に)フーフェの権利を与えられていた者は、例えばあるそれまで彼の所有物として存在していたある面積の土地を、法的な根拠無しに奪われたり、不法に占拠されたり、該当の耕地領域に対して、丁度 controversia de mode がそうであったように、常に測量のやり直しという手段に訴えなければならなかったのであろうか?そういった状況は、耕地ゲマインシャフトが成立する際の耐え難き法の混乱状態だったのかもしれない。ただもちろんこういった形の権利の保護は、通常の正規の訴訟手続に従って行うことは出来なかった。というのもこの正規の手続きにおいては、ただクイリーテース所有権のみが有効であるとあれたのであり、そしてこういった訴訟手続きの対象となったのは、それ故面積原則に基づくある一人の者の支配という形での、ただ総体としての fundus であり、つまりはフーフェの権利の認可であり、そして面積の大きさ、つまりフーフェ農民の個々の耕地領域(ケントゥリアの中から分離された耕地の中においてや、または耕地ゲマインシャフトの中で「獲得」またはそれに相当する[ばらばらになった土地の]一本化においての)においての割り当て地の要求権であった。そして同様に、ある土地区画の所有に対しての保護は、それぞれのフーフェ農民のそれぞれに異なった権利の保護であり、獲得した土地またはケントゥリアについて新しく測量を実施すること(”Reebning”)は認められ、そしてまさにそうだからこそ、というのはそこではある単なる de jure の[法律の上だけでの]一時的な所有状態だけが付随していたから、またただ所有状態に対しての特別に認められた、自分にとっては損害となる法的請求を招いたのであり、しかしながらある特別な、個々の所有者の実質的な権利状態を法的に詳細に意味があるように記述して確認する、ということにはならなかったのである。ある特定の面積の土地に対する実質的な権利が本来存在しないのだとしたら、いつでも行われうる測量のやり直しの可能性のために、所有状態の全体は、ある厳密に考えて純粋な事実に基づくものであり、権利としてはただ面積として表現された持分へのそれとしてのみが有効だったのである。ここで我々が知っている法的手段の内、どのようなものが当時の耕地における分割状態を承認する上で有用であったのかを詳しく検討してみると、直ちにそこに現れてくるのは所有に関しての(各種)禁止令である。周知のように、土地区画に対して制限を加え、また土地の所有者がその権利を侵害しようとする者に対して利用することが許されていた Interdictum de vi ≪暴力による不法な土地の占有に対し、回復を命じるもの≫は次のように命じている 73):”Unde in hoc anno tu illum vi dejecisti aut familia tua dejecit, cum ille possideret, quod nec vi nec clam nec precario a te possideret, eo illum quaeque ille tunc ibi habuit restituas.”[その場所でこの1年の間に、あなたがその土地について暴力による侵害を受けたり、あるいはあなたの家族がそういう侵害を受けた場合、あなたが(元々)その土地を暴力によってでもなく、秘密裏にでもなく、また借用という形でなく所有したのであれば、その場合はその土地は全てあなたの所有に戻される。]実務的な見地から観察した場合、つまりは個々の所有者についてその時点の前年において発生している所有状態は、「暴力」[vis]という概念に当てはまる形での権利の侵害に対して、保護されるということである。その土地における耕作との関係については、耕作を行っている家族が(暴力によって)追い出されたことについてのはっきりした言及から明確に認めることが出来る。2番目のケースである具体的な土地区画についての違法な占拠(の禁止)は、interdictum de precario [借用物返還命令]がそれに該当し、ローマの土地経済において最古の時代から重要ではあるが社会的にはしばしば悲劇的な役割を演じてきた借地人(小作人)を対象とするものであった:Quod precario ab illo habes … id illi restituas. [そこで土地を借りている者は…それを返還しなければならない。]ここではつまり、事物の本性≪法までにはなっていない社会の公序良俗のルール≫に従う形で、(前年に所有していたといった)時間の限定は含まれていない。もっとも確からしいと思われることは、この禁止令はある第三者に対し、後に実際的ではなくなった第三者に対しての特別な布告を、常に暴力と借用によって獲得された場合と一緒にして悪意ある所有状態、更には秘密裏の占拠[clandestina possesio]と名付け、確かに所有状態の保護を1年前までの状態までに限定したものであろうということである。それ故にここで見て取れることは、土地の所有者に対してその者によって耕作されている面積について暴力による奪取、秘密裏の占拠、そして借地人による占拠などに対する保証が与えられているということである。というのはその面積、土地が所有権争いの対象になっているということは、まずは事実関係そのものが争われ、その後また測量人達によって、彼らは彼ら自身の判断基準から rei vidicatio ≪物に対しての返還請求≫と(上記の)返還命令が等価であり、その時々の状況に応じて実務的に利用出来る可能性があると見ていたのであるが、奪われた土地は返還されるべきとはっきりと宣言されたのである 74)。
73) レネル≪既出≫の Restiitution [返還]に拠る。
74) フロンティヌス p.44. De loco, si possessio petenti firma est, etiam interdicere licet, dum cetera ex interdicto diligenter peragantur: magna enim alea est litem ad interdictum deducere, cujus est executio perplexissima. Si vero possessio minus firma est, mutata formula ex jure Quiritium peti debet proprietes loci. [もし土地の占有が請求者に取って確固たる事実である場合は、禁止令の公布が許可される。その際に他の手続きは禁止令に従って慎重に行われるべきである。というのも禁止令を求めて訴えを起すのは大きなリスクが伴い、その執行は非常に面倒だからである。もし真の所有者が誰かがより確かでない場合は、書式を変更して、クイリーテース法に準拠してその土地の所有権を請求すべきである。]
これまでに考察してきた2つのやり方以外に考慮すべきは3つの禁止令であり、それらは元々はどういった場合においても(財産)保全命令と見なし得る禁止令である:Uti possidetis eum fundum quo de agitur, quominus ita possideatis, viin fieri veto,[お前達が所有している土地について、これまでと同様に所有し続けようとすることを侵害する目的で、暴力を行使することを私は禁ずる、]この禁止令は公有地に対して――そこにおいてそれは所有状態の成立状況を――つまり locus を――それまでに既に生じていた何らかの侵害を無視して保護しようとするものであったが、多くの場合は実務的な意味を持っていた 75)。しかし後には”quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis”[お前達がお互いに暴力によってではなく、秘密裡にでもなく、また借用によってでもなく所有している場合は]という留保条件の追加と法学者によるそれへの解釈によって所有を再認可する応急的な法的手段になった、ということが一般に起こったのである。多種多様の土地の所有に関する禁止令の実際的な意味と歴史的な発展についての更に立ち入った議論は、そういう研究の立ち位置を考えてその研究を行うことが望ましいと思える場合であっても、ここでは試みることは出来ず、それについての特別な詳論は現時点では保留にしておかなければならない。しかしそうではあっても次のことは私には疑いがないことと思われる。それはローマ法のpossesioの所有の構造は、それは一方では所有に関しての手続きに該当する諸決定においての法的に見ての[de jure]暫定的措置という性格であり、他方では詳細まで定められた手続きであって、それ自身がまた複雑にもつれあった保証関係を伴っており、(例としては)競売やその他の禁止令が定める諸手続きであり、ローマ法で決定されなければならなかった所有に関する根本原則は、全てのそういった特性で、それは古代においての土地法での所有に関する手続きの位置付けから説明されるものであり、しかしそれは我々が使っている(ヴェーバー当時のドイツでの)所有に関する仮処分とはまったくもって適合していないものである。
75) というのはその禁止令は、その時の時点における所有状態の調査とその確認ということを行うという目的を持っていたのである。次のことは私には決して疑わしいものではない。つまり、所有に関する禁止令の主要な適用領域は、デルンブルク≪Heinrich Dernburg、 1829~1907年、ドイツのローマ法学者≫がそう主張しているように、ager publicus [公有地]であった、ということである。しかし公有地だけに限られていた訳では決してなかった。
75a) “funditus”≪根本から、根底から≫のフーフェ法に拠る意味についての研究が不足している。
というのは土地法のあるもっとも重要な適用領域において、所有の手続きはただ単なる一時的な決定のみだけではなく、公有地に関しての確定的な処置も生み出したのである。この領域においては面積の概念は登場せず従ってクイリーテース所有権も登場せず、ただ”locus”[その土地の場所]のみが扱われており、それ故に法的手段としてはただ”locus”を保護しようとするもののみが登場するのである:つまりそれが所有に関する禁止命令である。これに対して個人に割当てられた土地[ager assignatus]についてそれと根本的に対立しているのは、フーフェの権利総体に対して適用される legis actio sacrament ex jure Quiritium [クイリーテース法に基づく供託金付きの裁判≪双方が供託金を出して、敗訴した方はそれを国家に没収される裁判≫]が対象とする fundus という点から見てであるが:ある法的手段であってフーフェの権利に基づく所有状態に対応する個々人の持つ土地面積を新たに規制したもの:つまり controversia de modo であるが、――そして別の法的手段で土地の場所[locus]とその面積でそれらを個々人が耕作していたものを保護していたものがあるが、しかし当然のこととして、ここでの locus とは法的にはただ土地の面積の射影に過ぎなく一時的な性格のものであるとされた限りにおいて、その面積の請求権に基づいた決定的な土地の境界線の再調整は留保されたままとなった:つまりそれが所有に関する禁止命令である。この所有に関する禁止命令と面積に関する争いの関係は、その後帝政期になっても尚同様のままであった。それについては、次の紀元330年のコンスタンティヌスの定め [konstitution konstantins] ≪コンスタンティヌス帝がローマ教会にローマを寄進するという内容の寄進状。後世に作られた偽書であることが分っている。ヴェーバーのここでの引用は Codex Justinianus(勅法彙纂)より。≫が定めている通りである:C. Theod. 1 finium regendorum [支配している(土地の)境界線の]II, 26 (= C. Just. 3 の先に引用した箇所 III, 39 76) ):
Si quis super invasis sui juris locis prior detulerit querimoniam, quae finali cohaeret cum proprietate controversiae, prius super possessione quaestio firiatur et tunc agrimensor ire praecipiatur ad loca, ut patefacta veritate hujus modi litigium terminetur. Quodsi altera pars, locorum adepta dominium, subterfugiendo moras altulerit, ne possit controversia definiri ad locorum ordines, directus agrimensor dirigatur ad loca et si fidelis inspectio tenentis locum esse probaverit, petitor victus abscedat, etsi controversia ejus claruerit qui prius detulerit causam, ut invasor ille poenae teneatur addictus, si tamen ea loca eundem invasisse constiterit; nam si per errorem aut incuriam domini loca dicta ab aliis possessa sunt, ipsis solis cedere debeant.
[もし誰か≪元々の土地の所有者だったのが別の者にその土地を占有された者≫が自分の土地の所有権について先行して訴えを起していた場合、その訴えが境界線と所有権に関するものである場合は、まず所有に関する調査が行われ、その後に測量人がその面積の争いについて判明した事実によって境界線を確定させるために任命される。もし他方の当事者≪何らかの理由でその土地を占有して使用していた者≫がその土地について(占有によって)獲得したとする所有権について、訴訟の結果が元の所有者のその土地の所有の継続という判決にならないように、裁判を遅延させるような行為を行った場合には、任命された測量人はその土地についての調停を行い、もしその土地についての調査の信用性が認定された場合には、訴訟を起した者≪元々の≫は相手≪占有者≫を打ち負かすことを放棄する。しかしながらその訴えにおいては、それにもかかわらず相手方≪占有者≫がその土地の(不法)侵入を行っていたことが確認された場合は、まずはその侵入者を罰するという裁判が行われることを明確にする。しかしそうはいっても、前述の土地の(元の)所有者が過誤や不注意によってその土地を他人に占有された場合は、その土地はその者に与えられなければならない。]
76) 編集者達はこの法規を次のように改悪している:
Si quis super sui juris locis prior de finibus detulerit quaerimonium, quae proprietatis controversiae cohaeret, prius super possessione quaestio finiatur et tunc agrimensor ire praecipiatur ad loca, ut patefacta veritate hujusmodi litigium terminetur. Quodsi altera pars, ne hujusmodi quaestio terminetur, se subtraxerit, nihilominus agrimensor in ipsis locis jussione rectoris provinciae una cum observante parte hoc ipsum faciens perveniat. —
[もし誰かが自分の所有権について先行して苦情を申し立てた場合、それは所有権に関する訴えであるが、まず所有についての調査が行われ、その後測量人がその土地について判明した事実に基づいて境界線を確定させるために任命される、もし訴訟の相手方が、その土地についての調査で境界線が確定されないようにし、それによって土地が奪われないようにするならば、それにもかかわらず測量人はその者の土地について属州長官の命令に基づき、訴え人の立会いの下でこの土地の調査を行う。]
ここで見てとれるのは、この部分で元々述べられていたことの全く逆になってしまっているということである。しかしもちろん controversia de modo はユスティニアヌス帝の時代には既に長く忘れられたものとなっていた。
編集状態の良くない、あるいはまた改変された可能性もある≪ヴェーバーの時代には、学説彙纂の頃のローマ法文(オリジナルは失われており、全てが多数の法律書の引用から復元されたもの)は、その時代の編集者達が自分達の考えに合わない部分について元の法文を改変したことが多くあったと考えられていた。しかし20世紀になって研究が進むと、この時代での改訂はほとんど誤記の訂正レベルであって、大きな改変は無かったことが確認されている。従ってヴェーバーのこの種の記述は割り引いて読む必要がある。≫この部分の意味についての私の見解は以下の通りである:ここで扱われているのは2つの訴訟であり、2人の間で争われ、それぞれの測量された土地が隣接しているのであり:なので controversia de loco なのであるが、それはしかしこの引用箇所が全体で明確に述べているように、(問題とされているのは)所有に至ったプロセスと手続きであり、”finibus de proprietate controversia”[境界線と所有権に関する争い]としてであり――というのはこれこそがこの毀損した関係詞句 77) の言わんとした意味として書かれているということである。この所有権についての争いは明らかなこととして、当時しばしば実務的な controversia de modo としては描写されていなかったに違いなく、それは帝政期においてはよりむしろ境界の一辺の長さが5もしくは6ローマフィート≪1ローマフィートは約30cm≫を超えるものについての境界線確定訴訟の拡大版として把握されていた。何故ならば境界線と所有権の争いの双方で境界線を新たに引き直すことが手続きの目的であったからである 78)。
77) 私見ではこの部分は次のように読むべきである:”quae cum finali cohaeret de proprietate controversia.”[その苦情は境界線に関係した所有権についての争いである。]
78) controversia de modo が境界線に関しての訴えと同じではなく、例えばそれについてのある特別なケースのようなものである、ということは明らかである。というのは境界線の訴訟は土地の面積の割り当てを目的としておらず、そしてまた土地の割り当てが行われる前にそれが問題になることもないからである。しかし後になって面積についての訴訟が単に例外的にどのような場合にも利用出来る手続きになった時には、controversia de modo はもちろん、というのは原則的にそれは現実の土地の境界線の引き直しを目的としていたからであり、容易に幅5または6ローマフィートを超える大きさの土地を対象にした境界線訴訟の拡張版として把握されたのであり、それが実際に起きたことなのである。境界線訴訟と controversia de modo を区別するもう一つのことは、前者に対しては Usukapion が適用されることはなかった、ということである。
訴訟の片側が所有に関する訴えを行っていて、もう片側はそれに対し土地の面積を決める手続きをどう行ったかについての訴えとしてそれに対抗して回答しているが、――ここでの問題は:この両方の側は双方が原則的にお互いに排他的な関係にある訴訟でどう振るまったのか、またそれは単純に所有に関する争いとして展開されたのかどうか、何故ならばその決着として、新しい測量が既にそこで提案されていても、しかし実際はそれが(なかなか)行われれなかったからであるから(そういう疑問が起きるの)であるが。それについての答えは:どのような場合もまずは所有に関しての争いがまず行われたということである。それから測量人は問題となっている場所に赴き、土地の継続的所有について、つまり測量地図とそれに付随する書類をあたって、関係者の各方それぞれに帰属すべき土地の面積を調査する。所有についての争いで勝った方が――つまりその土地についての所有権[locorum adepta dominium]79)を獲得した方が――controversia de modo の面積に関する争いの進行を遅延させる場合は、直ちに測量人が派遣され、所有についての争いでは負けた元々の所有者[tenens]に対して、係争中の面積については controversia de modo の基本原則に従って判決が出されねばならないということを明らかにする。そのため所有に関する争いで訴えた方[petitor]は(etsi controversia ejus clarueit qui prior detulerit [しかしその訴えは先行して行われたことを明らかにする])調査においては勝者となっても、(所有権の争いでは)敗訴した者として扱われ、もし悪意での行為が認められた場合には、その土地を返還するだけでなく罰金(fructuum-Lizitationssumme [その土地から得られる収益相当の競売価格]など)が課される判決を受けた。禁止命令を誘発したもの、つまり通常の(土地の)返還請求と controversia de modo は、それ故争いの双方にとって異なったやり方であり、(それでも)同じ結果を目的とするものであり、その2つの内から人は訴訟において、あくまで実務的に見てどちらかのより良く自分の訴訟の役に立つ方を選ぶのである 80)。
79) ここで意味するのは:所有の不正確な表現から、ここで対立しているのは単に2つの並行して行われる訴訟の対象物である:面積と具体的地所、が想定されていることが分る。
80) シクルス・フラックスの既に引用済みの書籍のp.44を参照せよ。
ここで土地区画の時効取得が許可される前の権利状態について想定してみれば、その場合土地区画を借用[precario]の形で保持している場合は、第三者に対してはその所有は保護されたが、その土地の貸主に対しての所有権の保護は無かった 81)。
81) 次のことはローマ法の所有に関する法規の本質的に積極的な性格を確かに表している。それは暴力によるか秘密裏での所有権の獲得に並記して、不正な所有[vitium possessionis]としてまた地主から借りている土地についてもそれに該当するとしており、そしてそのことから万一の場合には、所有に至った経緯について詳細に述べる必要があり、このことが所有ということが「純粋に仮構的な」性格を元々その中に持っていたということを十分に証拠付けるものである;――後にはもちろん、法律化によって所有を法的概念として定式化することが試みられたが、しかしそれは、古い所有の権利がその実務的な意味において、もはや識別することが困難になるほど変化した後に、ようやく行われた。
それ以外の方法である土地区画を獲得した者は、フーフェの農民に対しては同様に無権利なのであり。その土地の本来の支配者のみがケンススに拠れば占有者であった。その場合、その者が使用出来た手段としては新たな測量(controversia de modo)を提議することによってその土地区画の所有者を排除することであり 82)、またそれ以外には、純粋に法の上では[de jure]、その土地の支配者の自力での干渉に対抗して、所有権についての暴力による獲得と秘密裏の獲得の禁止を利用し、その土地区画を再び入手することが出来た。そしてその際に2つの概念の実務的に重要なケース一般への周知の拡張可能性によって、その者が前年においてその土地の占有者であったことが証明出来る場合は、つまりは前会計年度においてその者が耕作を行っていたその程度に応じて保護されたのである。つまりそれによって次のことに対してのあらかじめの配慮がなされていた。それはその者が手続きの瑕疵が無くかつ不正手段によってでもなく[ohne vitium possessionis]入手した土地からの収穫物を自分のものとすることが出来たということである。Usukapion を行使することによる所有権の更新は、それ故ただその土地区画の獲得が正当な権原によってなされていた場合、その者は2年後に、元の所有者による排除行為に対しては新しく測量をやり直すという手段でその権利を守り、最終的にクイリーテース所有権者となったのである。それ故に、ある地面の獲得の保護に関連することは、より古い時代にはイェーリング≪Rudolf von Jhering, 1818~1892年、ドイツの法学者、ローマ法研究家≫の次の表現がその文字通りに正当である。つまり占有の保護は所有の保護より先行する、ということである。
さて、ここで面積原則がたどった運命についての観察に再度立ち帰ってみることにしよう 83)。
82) こういった権利状態はドイツにおける角形の耕地[Gewannfluren]での各 Stufland ≪既出≫の個別の所有権を認めるのに先立った Reebning ≪既出≫(とそれに伴った新規の土地割り当て)の手続きにおけるものと全く同様の所に位置している。フーフェの農民で、ある土地区画を切り離して売却した者は――我々が遡ってみることが出来る範囲での古い時代ではいずれの場合でもそれの前提となっていたのは――その土地区画を買った者を簡単には排除出来ずまたその土地も買い戻すことが出来ない、ということである。しかし獲得した土地(を含む一帯)について新規の測量が提案された場合は、その土地もその対象に含めて、買主はその後でフーフェの農民に対して、新規の測量によって新たな境界線が作られ、元々の土地の形状が消失してしまった場合もその土地を購買したという権利を維持し続ける。
83) 同様に本質的な土地制度史上の意味を持っている Interdictum uturbi ≪動産についての占有権の維持命令≫について少しだけ言及してみたい。”Uturbi hic homo majore parte huiusce anni nec vi nec clam nec precario ab altro fuit, quo minus is eum ducat, vim fieri vero.” [この男について今年においてそのほどんどの期間で、暴力によらずまた秘密裏でもなく借用ででもなくその者が所有し、もう一方の者がそうでなかった場合には、もう一方の者がその男を連れ去ることを私は禁ずる。]この命令は土地に関する命令と同じ内容を動産について命じたもので、その動産の中でもっとも重要な物は、標準書式が明らかに示すように、奴隷であった。それ故にそこで問題となったのは、その奴隷がその時点から1年前までの間に、誰の下においてもっとも長く労働を提供したかであった。
フーフェの基本法に対しての決定的な違反
それ故に Usukapion がより古い時代の土地に関しての基本法に対しての原理的な違反だとしたら、どのようにそれが共通経済においての争いの調停においてまず第一に作り出されねばならなかったかは、それは次のことが起きるや否や、より最終的かつ決定的なケースとして作り出されていたのである。そのこととは、それまで独立していた諸ゲマインデとその領域が、それらは元々ローマの法原則に従って分割されたりも割当てられたりもしていなかったのであるが、それらが[ローマの]完全市民の団体の耕地の中に取り込まれ、ローマの土地法の管轄下に置かれケンススに登録されるようになった、そういうことが起きた時である。半市民≪ムニキピウムの住民でローマの市民権が与えられたが、投票権までは与えられなかった者。モムゼンがそう命名した。≫の諸ゲマインデにおいては周知の通りこういった違反は起きていなかった:カエレ≪現代のチェルヴェートリ。ローマとエトルリアの戦争でエトルリア側に付き、BC353年にローマに併合され、その市民に半市民権が与えられたという説がある。≫の耕地は、その住民への投票権無き市民権[civitas sine suffragio]の付与によってケンススの登録の対象にはならず、いずれにせよその地における土地所有者が完全市民[adsidui]の団体の中へと、つまり土地トリブスの一員とはされなかったという意味であり、カエレ人の表[Tabulae Caeritum]≪ローマ市民で懲罰の結果その投票権を剥奪された者のリストをこう呼んだ。≫はトリブスのケンスス登録の外側において作られていた。また別のこととして、そういったゲマインデは、シュノイキスモス≪古代ギリシアでポリスが村落の合併によって発生したこと≫を発生させることなく、完全にローマ社会の中に組み込まれ消失したのである。そのような[シュノイキスモスを発生させた]ゲマインデの例としては、それはまたローマへの同化の時期がはっきりしていない場合であるが、そうはいっても最古の例の一つであるが――例えばガビイ≪ローマ東方20Kmの古代ラテン都市。BC5C頃ローマと同盟関係になった。≫であり、それは十二表法が作られた後ではもはや主権を持ったラテン都市国家としては機能しておらず、それについては多くのことが知られ、何故ならば彼らは血統の違う氏族としては扱われておらず、また半市民のゲマインデでも無かったからである。しかしその一方で彼らの耕地が取上げられたり、または Viritanassignation ≪既出≫の対象になったということも逆に何も知られていないのであるが。ここにおいては――そしてより後代の同様のケースにおいては、さらにはまた半市民が完全市民の団体に編入された際においても――そこの耕地は耕地測量の観点では ager arcifinius ≪既出≫であったのに違いなく、ケンススやローマで取引上使用される書式に関して対象外とされたのであり、そしてこのことが間違いなくウァッロー≪既出≫による土地の種類の分類(1. L. 5, 33)が導入された理由に違いない:Romanus[ローマの土地]、Gabinas[ガビイの土地]、peregrinus[外国人の土地]、hosticus[敵国の土地]、incertus[不確定の土地]84)。
84) 私はこの5つのカテゴリーは次のことを意味していると考えたい。ager Romanus はつまり割当てられた土地であり、ager Gabinus は完全な地権はあるが未測量・未割り当ての耕地、ager peregrinus は同盟している国々の耕地、ager hosticus はカテゴリー上は最後に来るもので、それはローマと[同盟関係にはないが]通商関係にあった国に属する耕地であり、そして最後に ager incertus は法的にはローマに支配されていない外国の耕地である。ager Gabinus の予期される比較劣位の状態は、境界線が設定されておらず割り当てもされていないことと関係がある。この名称は「カエレ人の」表と似たような言い回しである。――ガビイが u.c. 331または375年において既に市民ゲマインデであったということは、ベロッホ≪Karl Julius Beloch、1854~1929年、ドイツの古代史家。≫が主張したように、これらの年において、Antistii ≪Antistia gens、ガビイ出身とされる平民の氏族の一つ≫が、それは碑文によればガビイ出身の氏族であるが、ローマにおいて公職者として言及されている、ということと適合している。しかしもちろんこのことは完全な論証にはなっていない。
ローマ式のやり方で割り当てられた耕地が、また金額としても評価され登録されることが許されるようになり、また Uskapion によって獲得された土地区画が同様に特別な金銭評価を許されたということから 85)、ケンススへの登録の許可を得ることもそれ自体困難なことではなくなっていた。
85) 金銭評価に基づいた土地台帳の作成は、土地区画への Usukapion の許可と長期的に見た土地割り当て原則の廃止という観点で必要性のあることであった。(もちろんそれらは、だからといって金銭評価による土地台帳作成の例えば唯一のとか、またはもっとも本質的な理由ではなく、多くの中の一つである。)
いまやしかし、ケンススへの登録が可能になったということの結果はまた、元々伝統的に必要とされていた諸手続きを全て度外視するような[新たな]引き渡し形態にはほとんど適合していない[昔からのフーフェの]耕地に対して、Manzipation をその購買に適用出来るということでもある。もしかするとより古い時代のボニタリー所有権を保護するためのプブリクスの布告は、まさにその種の耕地をローマの耕地領域に収容することを目的として発布されたのかもしれない。いずれにせよこれらのことが示しているのは、[土地における]locus 原理の広範囲での勝利であり――、それは先に論じたその表現の意味においてであるが――、それは測量人達が ager arcifinius を controversia de loco の本来の発祥地として取り扱っていることからも裏付けられる。ローマの土地法を借用して ager arcifinius に適用することは、そこからさらにはるか先に進むこととなり、もっとも広範に行われたのが u.c. 643年の土地改革法によってであり、それは ager publicus に対する所有のあり方を変更したのであるが、また別の機会は同盟市戦争の結果としてであり、その際には完全市民団体に収容された同盟市における全ての耕地を、ager optimo jure privatus ≪クイリーテース所有権を持つ、もっとも強い所有権が与えられた土地≫に変えたのである。
controversia de modo と(ここでそう名付けた)面積原則は、おそらくBC1世紀においての暴力的な Viritanassignation ≪既出≫を経験する前に、実務的には行われなくなったのではないだろうか。Manzipation はかつては、それについては既に見て来たように、面積としての土地を売買することを可能にする手段で、それは[ヴェーバー当時の]我々が株の信用取引でその時々の相場価格で取引きするのと同じで、それは言ってみるなら手間はかかるがある種の儀式性を持った制度として、AD337年のコンスタンティヌス大帝による法(C. Th. 2 §1 de contrahenda emptione [売買契約について]3,1) 86) が、今後は[土地は]面積と所有権に基づくという以外のやり方で、隣人による境界線の証明に準拠して売却される、として Manzipation を禁止するまでは存続したのである。ここでの儀式性という意味は、それが土地取引における何かの抜け道的なやり方[in exquisitis cuniculis]として理解されるべきではない。
86) 売却の儀式性という意味についてはあまり穿った見方をすべきではない。というのもそれは、それまで確かでかつ真正な所有権が、つまり確かな面積[certus modus]の反対である特定の土地領域が、その隣人によってそのことが証明された――つまり測量や境界を示す杭打ちによって土地の場所、正確な位置が証明されたということを意味するからであろうからである。実質的にはそれ故その関係性はいまや逆になっているのである:元々は測量というものは測量人によって売却の後に行われていたのが、いまや先行して行われなければならなくなったのである。”a vicinius demonstretur” [隣人によって証明された]というのは、まず隣人への照会とその承認に基づいて、売却者に対してその隣人によって確認された境界線の内部の土地の売却を認可するということを関連付けたという意味であろうし、実際にその可能性がある。しかしまた別の可能性としては、たとえこの表現が言葉の上では強制的な響きを持つとしても、それが意味するのは、ただ境界線は “a vicinius” [隣人によって]、つまり隣人の土地区画の境界線からその土地の境界線が確認されるというだけのことであり――それ故に私はここの意味を別にこう読むべきと解釈した。≪どう解釈したかは欠落。全集の注によれば「隣人からの情報に基づいて」≫この部分に続くのは以下のようになっている――ここは土地制度全体の目的として本質的な部分であるが――”usque eo legis istius cautione decurrente, ut etiamsi [subsellia vel ut vulgo aiunt] scamna vendantur, ostendendae proprietatis probatio compleatur” [それ故その法律の規定が適用される場合は常に、もし[subsellia [テーブル状の土地、測量人達の呼び方]または一般的な言い方では]scamna [と strigas で囲まれた土地]が売却される場合であっても、所有権の証拠が示されねばならない。]ここでの話は、subsellien の売却についてではないということは明らかであり、[]内の部分は疑い無く写字人≪法令を複写した人≫による文法的な解釈としての改竄であることは間違いない。≪全集の注によれば、この[]内の部分はオリジナルの法文に既に存在しており、ヴェーバーのここでの決めつけは間違い。ここもヴェーバー当時の学説彙纂の法文の多くの箇所が書き換えられているという誤った先入観による間違いの例。subsellia と scamna はここでは同じものを指している。≫そうではなくて、ここで述べられているのは、ager scamnatus 、つまり境界線が測量地図上にはっきりと描かれている地所の売却についてであり、それ故に “certa proprietas” [はっきりした所有権]と書かれており、それ故に法律の公布の理由について――テキストを参照――この ager scamnatus と同等の他の土地にも適用されたということは整合的ではなく、ここで語られてもいない。コンスタンティヌス大帝の時代においては土地についての課税上の観点からの様々な分類がもはや実用的なものではなくなっており、それ故また他の新しい観点による分類を使って統一されていた。――controversia de modo は特別な手続きとしては C. Th. 4. 5. の finium regundorum [境界線の確定]2, 26 (AD392年)によって廃止されており、その法令では locus は finis [境界線]の反対概念として、例えばフロンティヌスの p. 9. 2 などで書かれていた。
ローマにおける不動産取引
こうした[面積としての土地を売却するための手段という]動機付けは、Manzipationとその本質にとって特徴的なことであった。何故ならば実務的にはその意義は実際、人が自分の好む場所で、7人のローマ市民の証人≪実際は5人の証人と1人の秤持ちの合計6人≫を集めることが出来れば、[古代]イタリアの土地を、それがローマの領土[orbis terrorum]である限り、売却することが出来る、ということにあったからである。その結果として起きたことは、こういった面積ベースでの土地の売却においては、時によっては売却者が実際に所有している土地の面積以上の面積が売却されることがあったということであり、それはまさに[ローマの国による]面積単位での土地割り当ての結果起きたことと同じであり、例としては C. グラックスによる騒乱を巻き起こしたカルタゴの土地の割り当てにおいては、1ケントゥリアにおいて[多くの場合]その中に存在する以上の面積が割当てられたのである。――しかしこれらの Manzipation のもっとも重要な特性が引き起こした結果で主要なものは、ローマにおける不動産取引をある程度まで活性化させることが出来たということであり、このことはこの後の時代でも前の時代でもまたどこの場所においても二度と起きることがなかった。人はそこでは耕地図とケンススへの登録証を所持していた場合、この双方が ager assignatus における所有関係の情報を提供したのであり、そしてまたボニタリー所有権に関してもある一定の根拠となるものを提供したのであり、そして公的な小規模小作地の競売と、ager quaetorius ≪既出≫として[国の借金の返済の代わりとして]譲渡される土地の競売においても使われ、その結果はローマを世界の不動産取引所にしたのである。ここでは「取引所」という単語を自信を持って使うことが出来る。何故ならば 1.5 D. si mensor falsum modum dixerit 11, 1≪実際は11, 6≫(前掲のp. 168 ≪日本語訳 p. xxx≫参照)において、不動産の先物取引について詳細に語られている場合があるからであり、そして同様のものが lex commissoria ≪契約の不履行時の罰を規定している法律≫に基づいた取引の場合にも見られるし、そして “in diem addictio” ≪売主がある者と売却の契約をした場合に、一定の期間内により高い価格の買主が現れた場合は、元の買主との契約を取り消すことが出きる取引≫は、買主が契約解除の許可の取り決めに関して直接または間接に契約解除による返金を認めるので、実質的にそれは[ヴェーバー当時の現代の]取引所規則に定められた不動産におけるオプション取引とほぼ変わらない。≪オプション取引が正式な制度となるのは1980年代始めであるが、歴史的には既に例えばロンドンの取引所で17世紀末には行われていた。ヴェーバーはこの論文の3年後に「取引所」という労働者向けの解説書を出しており、取引所についてはこの論文時点でも相当程度精通していたと思われる。≫
しかしより本質的なことは、ローマはまた特別な場所で、そこにおいてローマにおいての土地の所有権についての特別なやり方による価値評価の機会が提供されたということであり、それについては言及済みである:つまり、国による[土地の]賃貸しや[民間のソキエタースなどに]何かを請け負わせる際の抵当設定としての利用である。全体的な法の発展に対してのローマの行政法の意義という点において、この抵当設定ほど特徴的なものは他にはほぼ存在しない。それはこの抵当の制度の実行においての手続きと、個人の物的信用の権利形態との比較という観点としてである。
ローマにおける不動産信用
国家においての信用保証は、良く知られているように保証人(praedes)によってかあるいは不動産(praedia)によって行われねばならなかった。praedia による信用保証は考え得る限りもっとも簡単な形で行われた:抵当に入れられるべき不動産に対する、その取引きに参加する者からの口頭での説明に基づいた公職人による保証という形でである。その不動産についてのもっとも新しい所有権者であるという証明は、その本人によって、ケンススにおいての申告と同様に、つまり確からしく思われるのは測量地図と Manzipation においての各種書類、あるいは単純にケンススの登録リストを参照して確実に行われていた。更に考えられるのは、ただクイリーテース所有権の場合のみ公職人の保証が与えられることが出来たということであり、善意による取引きの2形態≪クイリーテース所有権の土地とボニタリー所有権の土地の取引き≫の実務における違いをここでも確認出来る。praedia patria、つまり相続した家族が所有する不動産であるが、それは優先権を与えられて取り扱われた 87)。その理由は、頻繁な不動産取引と、またケンススの登録は土地区画に対して Usukapion が行われたことにより、本当の所有者について必ずしも常に信用出来る情報を提供出来なかったためであり、「古くからの確かな不動産」が担保設定の対象物としてその地位を高めたのであり、それは Usukaio pro herede≪既出≫がもたらしたものと同じであり、それの公的な人間関係での意義については既に述べて来たが、相続ということが所有においての最良の理由付けだったのである 88)。
87) ただ相続された土地 [ager patrius]のみが一般的に優先権を与えられていたことは lex agraria 28の1においては何の説明も無い。逆にそこでの表現の仕方は、次の事を示唆しているように思われる。つまり相続遺産による担保は、他の農民との関係で許可されていた担保一般の中のある特別なケースに過ぎなかった、ということである。次のことは考えられる。つまり抵当設定しようとしている土地の面積とその抵当が担保しようとしている金額の比率は、相続遺産の場合は他の場合の土地所有よりも有利に計算されたのだと。
88) 土地所有に関しての権利関係が複雑または不透明であった所では、至る所で同様のことが起きていた。例えばイングランドでは、相続によって自己の権利を守ろうとする請求者の seien ≪イングランドでの封建制の下での占有地≫がそれ故権利的にはもっとも強いものであった。
不動産による保証は完全に抵当権設定としての効力を持っていたのであり、更には私有地の売却を通じて――多くの場合購買を頻繁に行う者の不確実な債務保証について――譲渡可能性が欠けている他の債務保証の方法とは反対に、実現可能性が高いものとして優先的に採用されていた。こういった洗練されたやり方での不動産抵当の構成は、それはもちろん債務保証を行う公職人である監察官に関係することであるが、それを唯一の公的な登録であるケンススのリストに依存するやり方、それは個人所有の不動産信用において利用可能ではあったが、不動産抵当と比べると、後者はより貧弱なやり方という印象を受ける。より古い時代において存在していたのはただ mancipatio fiduciae causa ≪担保の目的で自己の所有権を相手に一時的に渡すこと≫だけであり、それはつまりクイリーテース所有権の引き渡しであり、抵当権設定者(債権者)に対してケンススの登録に基きまた私法における第三者との関係に基いて所有権者がその権利を第三者に提供出来るようにしたものである。その後にボニタリー所有権による動産抵当(質権)が登場し、最終的にはギリシアから伝わった不動産に対する抵当権が使用されるようになった。これについては望ましい権利形態として使われるようになったが、この形式を利用した個々人の行為は公的な登録[であるケンスス]と無関係に行われており、そして債務と所有権の関係の不透明性によって、規制の元での現物信用を目的とするものではなく 89)、それは例えば土地改良のための融資や、何らかの意味のある範囲での利子付き抵当を利用した資本投下が可能にしたであろうやり方とは違っていた。
89) 債権者が不動産の獲得についての証拠書類を提出してもらうこと≪だけ≫を保証されていたとしたら、その場合債務者は再び、D. 43 de pigneraticia actione [抵当設定行為について](13、7)が規定しているように、事実上は不動産を譲渡する以外は出来なかったであろうし、そして債務者の状態は、一時的な抵当とより古い時代の無定形な質契約が可能にしていたものと比べて不確実なものに留まっていた。
後の時代の pignora publica ≪公的な債務についての担保≫と quasi publica ≪準公的な債務、例えば公共性がある事業に使う資金への担保≫に対してもまだ十分な保護は与えられておらず、いずれにせよその状態については≪ヴェーバーの時代の≫今日のフランスにおける現物信用のレベルに留まっており、そのフランスの場合では良く知られているように、古代ローマと同じような理由から「確かなデータ」付きの証拠書類が重要な役を演じているのである。ここにおいて有用であったのは単に次の手段のみであった。その手段とは一方では個人の財産について、その所有する不動産に対して利子付きの資本を何かの目的で(多くの場合は公共への寄付としての何かの建造)調達するために担保設定し、そして他方では諸ゲマインデがその所有する資本を確実に利子を得る目的で投下しようと欲し、その手段を利用した 90)――つまり利子払いの条件でゲマインデの地所を個人の財産へと引き渡し、その地所を得る個人に対して永久に支払い続ける地代[Rente]を ager vectigalis[課税付きの土地]として希望する利子を課して返済の義務を負わせたのである。≪このゲマインデの例はいわゆる Rentenkauf と同じである。初期の Rentenkauf は説明されているように支払う利子が本体の償還に及ばず、永遠に払い続けなければならず。Ewiggeld[永久金]と呼ばれた。≫それからゲマインデは「最初の抵当」をこの(永久払いの)利子に対して持つことになったのであるが、その成果はただ地所を ager optiomo jure privatus ≪既出≫から除外することのみによって達成されることになっていた。個人の債務者は、我々が知る限りでは、この手段を利用することは出来なかった。何故ならば課税のために土地を貸すことは国家の特別権だったからであり、そしてローマの国家と皇帝以外では、ただ諸ゲマインデのみがその昔日の主権 91) の名残りとしてこの権利を許されていた。
90) 小プリニウス書簡集7, 18、C.I.L.、 X5853、更にポンペイ住民による税受領書No.125と126、Hermes XII p.88f のモムゼンによる注釈を参照。
91) しかし実際に主権をかつて持っていた諸ゲマインデ(ムニキピウム)だけでなく、また諸コロニアでも(それ故ポンペイが入る)論証出来ることとして、課税目的での土地貸付けが可能となっていた。後者はしかし間違いなく特別権授与の結果であり、それはもしかするとカエサルによる lex minicipalis によるものかもしれない。
ager privatus の物的負担と地役権との関係
こういった[不動産に関する]権利状態によって、地所に対する継続的な抵当権設定の負担について、今日我々≪ヴェーバー当時≫において可能でありかつ事実上使われているやり方≪例えば土地を担保に金融機関などからお金を借りて家やビルや工場などを建てること≫が除外されていた。既に見て来たように、このことによってまた、土地所有者がその土地を流動化しやすい資本として利用出来るように解放されるということが全く行われてなかったとしたら、そうではなくむしろ全く逆のことが起きていた場合――土地所有がなるほど抵当権設定の対象物であったとしてもそれは単なる投機目的のためのものであり、その土地所有自体には資本流入という形で信用が与えられて利用出来るということにはならずに――、しかしその場合でも次のことは達成されたのである。つまりローマにおける不動産信用が動産信用と比べて法的にも経済的にも原則的には違いが無かったということと、今日の我々において事実上起きているような、最も強い所有権を持っている土地に対しての地代・地租納入義務を課されることを避けることが出来た、ということである。このことが実際の所本質的なことなのであり、ある一般的な因果関係に基づいているのである。もし誰かがローマ市民においては、ドイツの物的負担に相当する仕組みが知られていないと主張するならば、そのことについては次章で論じられるが、全く正しくないかあるいはまたひょっとしたら次の場合においてだけ正しく、つまりローマにおいてある者がもっとも強い所有権を持っている耕地に対して、私人間の法律行為としてのそのような負担を受け入れることが出来なかった場合であるか、あるいはまたそういった負担をその土地に適用するというということが、その土地のカテゴリーにおいては認められていなかった、それは既に我々は見てきているが、そういう場合である 92)。
92) 更に言えば、こうした考え方の中には、人が最初にそれを少しだけ見た時に思うであろう、より正しい考えが含まれている。ロードベルトゥスの土地所有の永久地代[Renten]の形での債務負担の考えは、その債務を負担する土地について対応した captis deminutio ≪法的な地位の悪い方への変更≫が無く、相続や譲渡に関連したもので、今日から見るとユートピア的なものである。このことは明確で実務的な把握の仕方として、もっとも輝かしい印の一つであり、その把握の仕方はポーゼン西プロイセン州の入植者受け入れ委員会が、通常の Rentengutsvertrag≪土地を譲渡せずに使用だけを許し一定期間定期賃料=Rentenを支払ってもらうもの≫§8 Abs 3(その規定は「また相続に関しての」もの)(プロイセン衆議院の1889年No.42の草案XIIIの印刷物)において、結論としている把握の仕方である。≪つまりローマでのやり方と全く同じ Renten の支払いを条件とする土地譲渡がヴェーバーの時代のプロイセン他で行われていた。またついでに言えば、ドイツでの農奴解放も、レンテン銀行が農奴に融資して地主から買った農地が農奴に与えられ、その農奴が一定期間 Renten を支払うとその土地がその農奴のものになった、ということが行われている。≫
イタリアにおける土地制度史においていつも見られる状態とは、これらの土地の種別を拡張していくという歴史と共にあるということであり、その結果として我我が参照している文献史料はただその種別についてのみ言及しているということになっている。
我々の言う意味での物的負担の欠如と同様に、また根本的なこととして土地に地役権≪契約によって、その土地を占有はしないが何かの特定の目的に使うことを許される権利、例えばその土地の通行権≫が設定されていなかったことが、ローマの ager privatus の本質的な特徴であり、そのために地役権が設定された耕地は少なくとも ager optimo jure privatus の分類としては把握されていなかった 93)。
93) 明らかにこの表現[ager optimo privatus]で規定されているのは「併合されてそれから分離された」耕地であり、それは何よりも共通経済的な地役権や耕作強制を免除されていた。というのは測量人達の時代になってもなお、また ager privatus ex jure Quiritium [法律上クイリーテース所有権が認められた私有地]においても、後で詳しく述べるがシクルス・フラックスの P.152で述べられているように、イタリアにおいては錯綜地≪Gemengelage、耕地整理前の土地で複数の地主の断片的な土地が複雑にまじりあった状態の土地≫が存在していたからである。(次のことに言及しても問題はないと思うが、ブレンターノ教授≪Lujo Brentano、1844~1931年、ドイツの国民経済学者、後にヴェーバーと資本主義の起源を巡って論争することになる。≫もまた、私の友人の一人の[大学在籍]当時の講義ノートから判断した限りでは、この錯綜地について書かれている箇所を、ドイツの耕地において我々が考えるそれと同じ意味のものであると解釈していると思われる。)しかし錯綜地が発生している場所においては、シクルス・フラックスが先に引用した箇所で言及しているように、お互いに必死になった土地の奪い合いという事態を避けたい場合は、そういう状態は多くの場合、ゲマインデが設置した道路を境界線に使うというやり方では解消されなかった。その場合には耕作強制に類似した何かがより古い制度の残余物として存在していたに違いない;-もちろんその場所での法令に従った農耕に対する規制を行う立場にあったり、そのゲマインデの長であった者について、pagi ≪古代の共同体≫やその長やその他の類似する何者かが本当にあった/いたのかどうかということについては、私はここでは敢えて見解を差し控える。
ある土地に地役権を設定するということは、特徴的なこととして、その土地を譲渡する時と同じ法的書類を必要としていた。地役権設定の件数は非公開であり、ある土地に強制的に地役権を設定した事例は、それを基礎づける法規がその権利を明示的に留保していない限りにおいては、知られていない 94)。
94) それ故に水道橋設置という利害関心での強制収用権は、植民市のゲネティヴァ・ユリア≪現代のスペインのオスナにあった植民市≫の条例の C.99 において留保されている。(モムゼン、Eph. epigr. II P.221fにて)ルッジェリ≪Odoardo Ruggieri、19世紀のイタリアのローマ法学者≫(Sugli uffici degli agrimensori [測量人の事務所において])は正当にも次のことに言及している。つまりただ私的な処分のみが、非公開の地役権の件数として記録され本棚の中に封じられたのだと。それに対して、各種の土地法によってもこうした強制的な地役権設定というものは作りだされなかったのである。(D.17 communia praediorum [農場の公共財]を D.1 §23 de aqua et aquae pluviae arcendae [水と貯められた雨水について]と比較せよ。)
契約による地役権が設定された土地は同様に、地所の境界それ自体を管理するのと同じく、境界石を設置して管理されるのが常であった 95)。
95) 地役権を示す碑銘が、私が Corpus Inscr. Lat を通して読んで見つけたものだが、先行して記録されており、それは全ての場合ではなかったにせよ、割当てられた耕地においては広く行われていた。
ager privatus への権利設定における経済的な基礎
次のことは明らかである。つまりそのような[地役権の設定された]権利状態はただ、ある耕地についてその分割の仕方が、個々の所有者に対して個人の経済行為の完全な自由を可能にしていた場合にのみ可能となっていた。というのはこのことはまたローマの測量においてのもっとも顕著な経済的傾向だったのであり、特別にかつ相当に強い程度において、ケントゥリアによる測量[と分割割当て]の場合がそうであった 96)。
96) 次のことは既に述べて来たが、ager scamnatus に設定された limitesも同様に先行して行われており、後の時代になって liber coloniarum に書かれているように、規則的に行われ、そしてまた土地区画の中のある制限された数の面積についてのみ許可されており、そういった例の中では、スエッサ・アウルンカにおいてのように、ただ森林だけが特別に分割されていたという例もあった。
ローマの測量制度は土地の所有者に関連してまず第一に――それについては既に他の学者が言及しているが――その地所に対しての[第三者の]完全な立ち入りの自由を許していた。limites は公共の道路であり、そしてこの性格において、考え得る限りもっともはっきりした形で次のことに対しての保護が与えられていた。それはつまり誰に対してでも、また本来そこに対して何の利害関係の無い者に対しても、そこでの通行が許可されたのであり、そして例えそれがただの権利の濫用≪ChikaneまたはSchikane、シカーネ禁止原理=他人を害する目的での権利行使の禁止≫の結果起きた場合であっても、自身の努力によりまたは禁止命令の手続きの力を借りて、その開放状態を保つことが強制されていた。
もちろんそこにおいては、ある別のもっとも重要な動機が含まれている。我々のドイツの錯綜地の場合と同様に、あるどこかの場所において次のことはほとんど不可能であったであろう 97)。それはつまり上記の目的:全ての土地区画に対してその所有者のそこへのアクセスを確保することを、ある耕地にてその閉じた平野の中において個々の所有者の土地区画が互いに隣接して並んでいない場合に、実現することである。
97) 既にP.192(原文)の注93にて言及済みである。
我々の時代における土地の分割と併合[耕地整理]は、というのもまた常により大きな一つにまとまった面積の土地を作りだし、その結果統一された道路システムの導入を可能にしているのである。我々が参照している文献資料は非常に確実なこととして、ローマにおける耕地分割もまた原則的に一つのまとまった面積の土地(continuae possessiones [連続した所有地])を作りだしていることを述べている 98)。既に論じたことであるが、より正確に言えば、次のようなことが先行して行われていた。つまりある農耕地の内部でのある特定の地所について、特定の森林区画が付属物[通路の代わり]として割り当てられていたということである。その例は、スウェッサ・アウルンカにおけるものであり、そこではそれ故にケントゥリアではなく、 scamna による土地割り当てが行われていた。しかしそういったケースは例外であり、特別な事情によりそれが行われたと説明されるべきものである;その他一般的には各人に割当てられた土地区画は、それらの個々の面積の大小に関係なく、ある平野の中でのみ割当てられた。
98) ヒュギヌス P.130, 3: respiciendum erit … quemadmodum solemus videre quibusdam regionibus particulas quasdam in mediis aliorum agris, nequis similis huic interveniat. Quod in agro diviso accidere non potest, quoniam continuae possessiones et adsignantur et redduntur.
[考慮されるべきことは…我々がある領域においてしばしば見るように、他人の土地の中にある小さな土地が入り込んでいることが、あなたはないようにすることです。このことは分割された土地では起き得ません、何故ならば連続した所有地が割当てられ引き渡されるからです。]
p.117, 14. 119, 15. 152. 155, 19. 178, 14.を参照。
土地の併合と分割
次に測量人達は次のことを我々に伝えている。つまりこの土地が一つにまとまって閉じていることは、次の状態と対立しているものであると。その状態とは多くの植民市においてその周りを取り囲む耕地において、まだ分割割当てとそれによる植民市の建設が行われる前の状態である。
我々は第1章で次のことを見て来た。つまり測量人達がローマによる測量がまだ行われていない耕地を ager arcifinius 、つまり「曲線によって境界付けされた(土地)」と名付けていたことを 98a)。
98a) ロビー《Henry John Roby、1830~1915年、イギリスの古典学者でローマ法に関する著作者。》のケンブリッジ・フィロソフィカル・ソサエティー II 1881/82 P.95 に学会録にそう記載されている。
そういった土地については、ローマの角型の土地とは反対のものとして表現されている。しかしそのことによって、その概念は不規則な土地ブロックに対する専権的な耕地分割と必ずしも結びつけられる訳ではない。ある人が初めてフーフェ原理によって展開されたドイツの耕地図を見たとしたら、まず言えるのはそこの根底にある原理をまったく見出すことが出来ないであろうと言うことであり、その人の目に入るのは所有権に関連する土地の境界が曲がりくねっているということであり、それは部分的には分割された角形の土地の価値についての調整の結果であり、更にはまた部分的にはその隣人の鋤による[長年の]耕作の結果である。≪ドイツで使われていた鋤を牛などに牽かせると、しばしば曲がりくねって耕すことになり、その結果土地の境界線が時間が経つほど曲がりくねることとなった。≫ローマ以前の土地分割についての統一的な原則は、全イタリアにおいてある程度判明しているものはほとんど存在しないが、しかしこの場合特徴的なこととして明白に理解されるのは、非常に膨大な数の耕地が、ローマ以前の分割の仕方に戻ってしまっているということである。このことはまさにシクルス・フラックスが次のように描写している現象である:
“in multis regionibus comperimus quosdam possessores non continuas habere terras, sed particulas quasdam in diversis locis, intervenientibus complurium possessionibus: propter quod etiam complures vicinales viae sunt, ut unus quisque possit ad particulas suas jure pervenire … quorundam agri servitutem possessoribus ad particulas suas eundi redeundique praestant.”
[多くの領域において我々測量人は次のことを見出す。それは土地の所有者達がそれぞれ連続してまとまった土地を所有しておらず、そうではなくて別々の場所にある複数の所有地を断片的な形で持っているということである。このためにまた、多くの近隣の道路について、ある者が自分の断片的な土地の一つにたどり着くために、多くの道路を経由しなければならず… 誰かの土地に対して通行する地役権を持った者達により、自分自身の土地に行き来するのに、他人の土地を通るということが行われている。]
同じ現象についてヒュギヌスも(gener. contr. P.130の先に引用した箇所)言及している。我々(ドイツ人)はこういった事例を見ると直ちにドイツの錯綜地に結びつけて考えるが、確かに実際の所、人が何らかの形の耕地ゲマインシャフト(耕地共有)から土地分割へと踏み出し、そしてその際にその耕地全体の(効率性といった)評価を十分出来ていない場合には、直ちに同様のことが発生しているのである。そのことについては既に次のことを確からしいこととして見て来た。それは laciniae [断片的な土地]における土地分割で、それが最古の植民市であるオスティアとアンティウムで起きた場合には、そこで見られたことは人々がその場合でも土地分割をなお耕地ゲマインシャフトの枠組みの中で行っていたということであり、そして更に後の時代になって耕地全体の分割へと進んだ場合でも、分割割当てについてのローマ式の原則にはなお従っていなかったということである。シクルス・フラックスの viae vicinales [近隣の道路]についての所見に拠れば、そのような耕地における耕作強制やあるいはそれに類似したゲマインシャフト的な土地耕作の形態は、規則的なやり方ではもはや行われておらず、そして実際の所そういったゲマインシャフト的な原理はローマにおける私有財産制と共存出来なかったのである。後の時代のローマの土地割当てはいずれの場合もむしろ、既に見て来たように、次のようなやり方に依拠していた。それは分割される土地区画をひとつの閉じたまとまった面積に保ち、それによって初めて整然とした道路システムが可能となり、個人の経済活動に対して完全な自由を保障する、そういうやり方である。錯綜地の成立に当たっては、近隣道路[viae vicinales]という不釣り合いに多くの面積を非生産的なやり方で要求する、先に述べたようなやり方無しには行われていなかった。
既に先の箇所で述べて来たことであるが、我々における近代的な土地の分離と併合[耕地整理]は、同じ手段で同じ目的を達成しようとするものである。それが成立するのは、錯綜地の中にある土地区画のその価値に応じた強制的な交換を行うのと、それによって可能になった共通経済的な関係から生じて来た地役権と所有権への制限を撤廃するという状況においてであった。全く同じ成果が次の場合にも得られていた。それは、ある耕地がそれまでの所有者によって分割されており、そしてローマ式のやりかたで割当てられた時、この後者が実施された場合である。この場合連続した所有地[continuae possessiones]が作り出され、そしてまたその手続きも同じであった:”particulas quasdam agrorum”[ある土地断片を]、シクルス・フラックスは言う(p.155)、”»in diversis locis habentes duo quibus agri reddebantur, ut continuam possessionem haberent, modum pro modo secundum bonitatem taxabant.”[異なる場所にいくつかの土地の断片を持っている二人に対して、その土地が(再割当てのために)返還された場合に、二人が連続したまとまった土地を改めて持つことが出来るように、それぞれの土地の面積について適切で公正な評価が行われた。]こうした耕地移転の手続きは測量人達の見る所では、植民市建設という概念から見て余りにも当り前のことだったので、ヒュギヌスは次のような見解に到達出来ていた。つまり土地の所有者達は、彼らには単純に元通りの面積が返還されるべきであり、また彼らの社会的な地位(condicio)は変えられる(mutata)べきではなく、そのため植民市の団体の中に編入されることが全くない、という見解である(p.119, 18)。我々は先に更に次のことも見て来た。つまり植民市の全耕地は根本的なこととして、ローマ式の耕地の分割と割当ての及ぶ所と一致していたということである。これについて、我々は次のことが定められていたとまでは主張するのではない。つまりこのようなローマ式の耕地分割のやり方が、この種のローマ市民の植民地にとって本質的なことであるとか 99)、またこのやり方が行われなかった場所ではローマ市民の植民地は全く成立していなかった、ということである。ローマの市民が植民した場所が植民市となるのではなく、イタリカ≪スペイン南西部の植民市≫においてのように 99a)、またある場所で全ての植民がローマ市民によって行われたということがそこを植民市にするのではなく、ローマ式の耕地分割が行われて初めてそこが植民市となるのである。
99) ここでは次のことを確実であると主張しているのではない:1) ――自明のこととして――全てのローマ式の耕地分割は植民市の建設を伴っていた、2)――土地制度が市民植民地の唯一の本質的な目印である。
99a) C.I.L., I 546 とモムゼンの引用済みの箇所を参照。
それ故にアグリゲントゥム≪現在のシチリア島のアグリジェント、元々ギリシアの植民市で後にローマの植民市となった。≫は植民市であったという推定にもかかわらず 99b)、ローマ市民の植民市では全くなかった。というのはそこでの耕地は外国の法に基づいていたのであり、同じく言えることとして、ローマ式の耕地分割は明らかにラテン人による植民市の市民植民市の目印の一つであるからである 100)。そのような植民市が事実上またはもっぱらローマの市民によって建設されたと推論される場合でも 101)、その植民市はそれによって直ちに市民植民市となるのではない。何故ならばそこの耕地は外国人の土地[ager peregrinus]に留まっていたからである。そして逆にあるローマの植民市がラテン人やその他の同盟者によって分割された場合、その分割方法がローマ式であった場合は、ローマ市民の植民市という性格は失われなかったのである。
99b) C.I.L. X, p.737 参照。
100) 我々はラテン人の植民市における耕地分割の実例を知っていない。またそもそもそれが一般的にローマ式に分割が行われていたのかどうか、またそれによって subceciva ≪分割の結果生じた非角形の土地≫が生じていたのかどうか、更にそこから何が生じていたのかについては、我々は判っていない。我々が文献史料から知ったのは、その耕地はローマの耕地とはされなかった、ということだけである。より古い時代での土地制度における異なった性格について明らかになっているのは次のことである。つまり市民植民市における(一日の)入植者の数は常にフーフェの成員300人であったことが推論される一方で、それはローマの一部族の成員数(の単位数)と一致しているが、ラテン人の植民市においてはそういった数的な条件は存在していなかった、ということである。
101) そのようにリヴィウスの34, 53 では述べている… Q. Aelius Tubero tribunus plebis ex senatus consulto tulit ad plebem plebesque scivit, ut Latinae duae coloniae … deducerentur. His deducendis triumviri creati, quibus in triennium potestas esset. [クイントゥス・アエリウス・トゥベロが護民官として元老院の指示により平民会に次のことを提案し、平民会がそれを承認した。それは2つのラテン人の植民市を建設することであった。この建設のため3人組委員会が作られ、その任期は3年であった。]ここでイタリアにおける植民市についての推論で正しいと思われるのは、それが純粋にローマの仕事として行われていたということである。
植民市法[jus coloniae]の土地制度上の意味
こういったやり方での土地制度の特質が市民植民市についての本質的な目印であったとしたら、後の帝政期には全ての政治的な差異がほぼ無意味になってしまった≪最終的に皇帝カラカラが属州の住民にもローマの市民権を認めた。≫ことを考慮すると、次のことを仮説として提示出来る。それはつまり、諸ゲマインデが、それはこの時代には徐々に植民市に変わり始めていたのであるが、まさにこういった土地制度を導入する上において、植民市への転換ということが実質的・本質的には土地の併合と分割を伴う耕地規制を受け入れることを意味していたのである 102)。
102) 私は既に私自身の公的な学位の昇進≪1889年8月にベルリン大学で法学博士号を授与されたこと≫の際に、我々の偉大なる学問の巨匠であるモムゼン教授と、ある[ラテン語から]翻訳されたテキストの解釈について議論を試みるという栄誉の機会を得ることが出来た。≪ヴェーバーの博士号論文である「イタリアの諸都市における合名会社の連帯責任原則と特別財産の家計ゲマインシャフト及び家業ゲマインシャフトからの発展」の公開審査の際に、テオドール・モムゼンがゲストとして招かれていたが、一番最後になってヴェーバーに対し、ヴェーバーがそれまでの議論の中で示したローマにおけるコロニアとムニキピウムの違いの説明について、それについて長い間悩んでいたモムゼンがヴェーバーの解釈について質問し、議論したもの。モムゼンはヴェーバーの説明に納得しなかったものの、「<息子よ、私の槍を持て、私の腕にはもうそれは重すぎる>と誰にもまして私が言いたいのは、私の高く評価するマックス・ヴェーバーに向かってであろう。」という祝福の言葉を与えて議論を打ち切った。おそらくその後も二人はこの問題について口頭で議論を続けていたようで、この注釈はヴェーバーからのモムゼンへの議論の続きであると思われる。≫モムゼン教授はその際及びまた後の機会に、私の仮説については決定的な証拠がない、と仰っていた。ただ私が信じたいのは、諸事実の全体の関係からそれについては一定の確からしさがある、ということである。ローマの歴史的諸文献の中に、ムニキピウムとコロニアの違いという論点において、この[土地制度という]側面が言及されているものを見出すことが出来ないということは、私の仮説を裏付ける根拠が与えられないということである:[しかし同様に]人が膨大な我々の近代の資料の中にプロイセンの耕地整理に対する評価を探し出そうとしても無駄であろう。ある近代の耕地整理されたゲマインデと(されていない)他のゲマインデの国法上の根本的な差というものは、ローマの帝政期のコロニアとムニキピウムの間の差と同様にほとんど存在しない。私は次のことを否定するつもりはない。つまりコロニアとムニキピウムの差異は歴史的には、かつそれに関わった者達のイメージとしては、まず第一に次のようなものとして成立しており、つまりコロニアの方がまずはほとんどの場合で全くの所非独立の外国における市民居住区であり、それに対してムニキピウムの方は多くは昔からの主権を持った都市国家が国家としての統治権を一部だけ残して大部分を失ったゲマインデになったものであり、この二つが国法上は帝政期に別々のものとして存在していたのである。しかし市民植民市が元々は市民の居住区として管理されていたのであろうという一方で、しかしそれはまた最初から本質的に同程度に耕地の分割とフーフェ組織にも依存するものでもあった。ラテン人の植民市が同盟市戦争の後全て例外なくムニキピウムになったということは、それはしかしまたローマ式の土地管理を行う組織が存在していなかったことにも強く影響されていた。全ての耕地整理が植民市の形成原理として不可欠なものとして行われたとは私は主張しない。しかし次のことは正しいと信じている。つまりローマの市参事会によって全ての耕地の統一的な配置換えが統一的な decumanus [と card]を使った測量とそれに基づいた測量地図の作成が行われた場所においては、耕地整理こそ植民市の形成原理だったのであると。-モムゼンは (Schriften d. r. Feldm. II, p.156)グラウィスカエ≪エトルリア人の都市、タルクゥイニーにある港≫とヴェールラエ≪現在のイタリアのヴェーロソ、ローマの東南東79Kmに位置する。≫を次のようなゲマインデの例として挙げている。それらにおいては耕地整理がそれによってゲマインデから植民市に昇格するという意図無しに行われていると。liber coloniarum の注釈 (239, 11)はヴェールラエについて次のように述べている:”»ager ejus limitibus Gracchanis in nominibus est adsignatus, ab imperator Nerva colonis est redditus”[そこの土地はグラックスの名前において設定された境界線によって割当てられており、皇帝ネルヴァ≪第12代ローマ皇帝、在位96年9月~98年1月≫によって植民者に引渡された。]の部分は私の見る所では、そこで起きたことの結果を記述しているものではない。そこでのグラックスによる境界線設定においては、ただ退役兵への非定期的・小規模な土地割当て、つまりは耕地のほんの一部分のことを扱っているに過ぎないのである。グラウィスカエの場合はまた事情が異なっている。この都市はU.C.573年[BC181年]に建設された市民植民市である。liber coloniarum はこの都市について次のように言っている(p.220, 1):Colonia Graviscos ab Augusto deduci jussa est: nam ager ejus in absoluto tenebatur. Postea imperator Tiberius Caesar jugerationis modum servandi causa lapidibus emensis rei publicae loca adsignavit. Nam inter privatos terminos egregios posuit, qui ita a se distant, ut brevi intervallo facile repperiantur. Nam sunt et per recturas fossae interjectae, quae communi ratione singularum jura servant. [グラウィスカエの植民市は、アウグストゥスの命令によって(新たにローマ植民市として)設置された。というのもそこの土地は(ローマによって)完全に保持されていたからである。その後皇帝ティベリウス・カエサル≪既出≫が面積を測り記録するという目的で境界石でその土地を分割し、ローマの人々にその土地を割当てた。それは個人の土地の間に境界を区別するために(境界石が)設置されたのであり、それぞれの境界は離されて設置されており、それは見分けることを容易にするためであった。というのも直線の溝が設置されており、それによって公共の方法として個人の権利を守っていた。]

――植民市の領地は――というのもその植民市は(ejus という語が示すように)またアウグストゥスのもの[皇帝領]としてあった、そして「彼の植民市」という語については、グラウィスカエに関してセルスス D.30 de legatis II でも使われており――アウグストゥス帝の時代には「完全に」[in absoluto]所有されていた。土地区画に対しての Usukapion の結果として、それは古いシステムを破壊して置き換わったのである。アウグストゥスはそれ故に、その都市を[市民植民市に]転換することを命じた。それはつまり、(nam という語で)関連性が示されているように、ただ:その都市をローマ植民市に置換し、面積ベースで新しい割当てを実施し、そして測量地図にそれを記入するということである。よって転換と置換は同じことを意味しており、それは前記の引用箇所の見解に合致するが、ティベリウスはしかし全く逆のこと、つまり個人の所有地の境界に(inter privatus)石を設置し、個々人の所有地を保証することをやったのである。ティベリウスはひょっとするとその都市が植民市となる資格、もしそれが成立していたとした場合であるが、それを反古にしたのであり、それは彼がまたプラエネスラ≪パレストリーナ≫でやったのと同じことであった。私の見解ではこの箇所は私がここで提示している仮説の証拠となっている。(しかし)この仮説が仮に正しいとしても、この論文の大部分の記述と同様に、そこにおいては学芸における最も困難なこと、つまり”ars ignorandi” ≪重要ではない情報を無視し、本質的な部分に集中するという学問・討論上の技法≫が何重にも失われてしまっているのである。私は次のことを確かに自覚している。つまり私の記述において明確化という意味で成功していない多くの命題が見出され、それらについては個々の[文献]調査によって再検証されなければならないということである。それについてはただ私が、ここで提示した見解について、それをより大きな因果連関の中で検討する試みをせず、ただそれを何としても記述しなければならないという強迫観念に駆られていたことに、自分で気が付いていなかったと言える。
逆にティベリウス帝によるプラエネステの場合のようにその土地をムニキピウムの地位に戻すことになった場合は、次のように考えることが出来るであろう。つまり元々の土地制度についての調整とそれに伴う一定の結果的処置が意図されていたのであると。そしてこのケースこそまさにそうであったと推論出来る。ローマにおける耕地の分割でもっとも面倒な要素は、道路をどう作り直すかということと、元々の境界線を開放することであった。プラエネステはこの場合、全ての耕地領域が既にキケロの時代において少数の大土地所有者のものとなっており、彼らにとって元々の境界線を開放することはまったくメリットが無いことであり、彼らの所有地をばらばらに分割している境界線は非常に取扱いが難しいものであり、(開放した場合は)そこからごろつきどもが彼らの邸宅の庭やテラスに入り込むことが出来てしまうのであり、このことを禁止令によって防止することが可能になっていた。彼らの便益のために、元の境界線の開放という必然性は取り除かれることになった。――
我々はここまでもちろん本質的にはイタリアの土地においての植民市の建設を我々の観察の中心に据えて来たが、その場合に結果として生じたのは、そこの土地をローマ式の非課税の個人所有地に割当てるということである。我々がその際にイタリアでの植民市化を属州と明示的に区別していないということは次のことに起因している。つまり、二つの概念の全ての相違点にもかかわらず、ここにおいての本質的・経済的な諸連関においては注目すべき差異が存在していない、ということである。全ての点においてイタリアでの植民市化と同じやり方の:非課税の個人所有地の割当てを、一属州に対しても適用するということは、C. グラックスがカルタゴに対して初めて行ったことである。しかしながらこれらの植民市はその後廃止され、そして後には属州においては植民市や他のゲマインデはただ例外的な場合にのみ構築され、それらに対しては設立の際に「イタリア権」[jus Italicum]≪イタリア半島以外にある都市に、ローマ皇帝がほぼローマに準ずる権利を特権として与えたもの。その都市で生まれた者はローマ市民権を与えられ、自由に財産を売買出来、また土地税も免除された。≫がその時にかあるいは後になって与えられたのである。その他の特徴として、またフロンティヌス(de contr. agr. II, p.36)が注記しているように、属州における植民市の領域は規則的なこととして納税義務を負っていた。しかしそのことによって例えば植民市の土地はローマ式に分割されるべきという原則が除外されてはいなかった。反対に第1章で分析したアラウシオの碑文からは、そこは免税の植民市では無かったが、そこでも[ローマ式の]土地の分割と配分が行われていたことを見て取ることが出来る。その碑文は土地の分割が耕地整理のためであることを明確に示している。(”ex tributario…redactus in colonicum” 103))[「課税地から…植民市の土地において与えられた。」]
103) おそらくはそこから更に割当てられる土地区画について、それぞれ異なる面積のものが作られている。この論文に添付した測量図[下図]を参照。
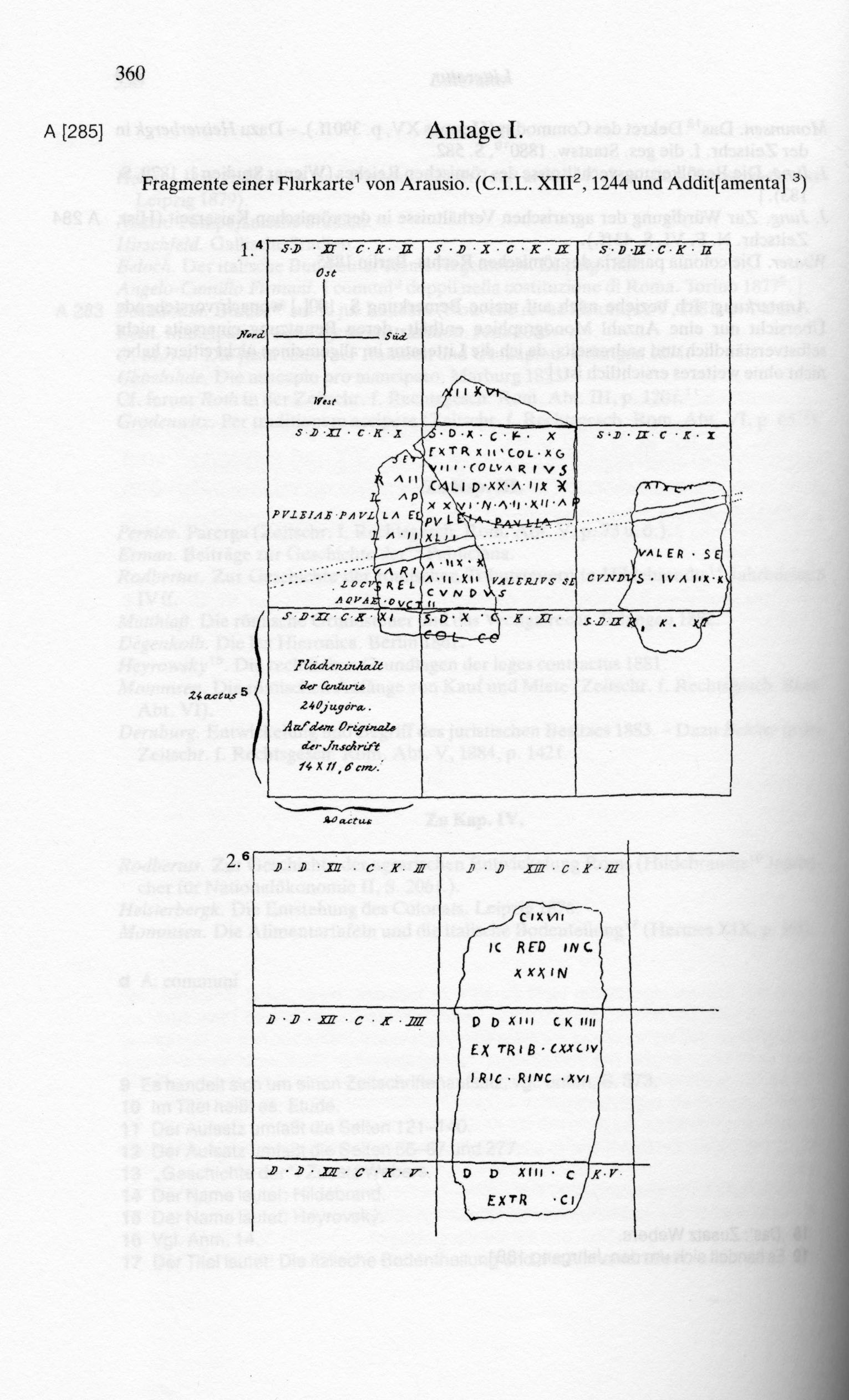
この碑文から同時にかなりの確からしさをもって見て取れることは、もちろんそれは他の史料によっても確認しなければならないが、属州内の植民市においての土地への課税は、個々の土地区画を単位としてされていたということである。そこの農民はそれ故、第1章で説明した意味において、土地に課された税を納める義務を負っていた。測量人達もこの碑文と同様に、――既に述べて来たことではあるが――、そこにおいては scamna と strigae [だけ]による線引きではなく、 limites [小路]によって[も]境界設定が行われていた≪つまりケントゥリアで土地分割が行われていた≫ことを述べている。このことは明確に、そこにおいては道路システム[limites]を無しで済ますことを避けようとしたのであり、また既に示して来たように、ヒュギヌスによって課税地に対する土地の割当て方法として推奨されている ager centuriatus per scamna assignatus [scamna と strigae による長方形に区切られた土地ながら、さらに limites によっても区切られており240ユゲラ≪標準的なケントゥリアは200ユゲラ≫の変則的ケントゥリアとして扱われたもの]がただ割当ての目的のためだけに使われ、その際には個々人には全て同じ面積の土地区画が割当てられたのであり、それ故に[属州の中にはない]他の植民市においてはこの方法を使う事が出来なかったのである。既に述べて来たように、いずれにせよ土地に対して課税出来るといいうことは植民地の土地割当てに対して、何らの他の経済的な損害を与えるものではなかったのであり、常にそこに内在していた要因は、目的と方法という点で近代的な耕地整理と同等の手続きの一つだったのである 104)。
104) 次のことは偶然であろう。つまりサルペンサ≪現代のスペインのウトレラにあったローマの同盟市≫とマラカ≪同じくスペインのマラガにあった同盟市≫の都市法について、耕地に関係するもの(灌漑、水道、道路)についての規定が含まれておらず、その一方でジェネティヴァ≪Genetiva Iula、ユリウス・カエサルが現代のスペインのオスナに建設した植民市≫の植民市の法にはそれらが含まれている、ということが。しかしおそらくは最初に挙げた2つの(ラテン)ゲマインデの法規は実際の所それらについては何も触れていない。その他の特徴として、カエサルにより制定されたマミリア法[lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia]はただ植民市のためだけではなく、また「この法律によって」[ex hoc lege]構築されたムニキピウムのためでもあり、そして limites についての規定があるということは、ムニキピウムの領域においての退役兵への(小規模で非定期的な)土地割当てにおいては自然なことであった。新規のムニキピウムは、この法令に基づいて、おそらくほぼ常に、既にスッラによって行われたように、農村トリブスの解体の結果として作られ、そのことから個々人に割当てられた土地はムニキピウムに従属するものとされた。limites によって区切られ割当てられた耕地の存在ではなく、土地の面積を統一された decumanus を使った測量システムと、同じく統一された測量地図の中において、各人にボニタリー所有権の土地として、フーフェ原理に従って割当てを行う全体の耕地を管理する組織の存在こそが、これまで何度も述べて来たように、植民市に固有のものであるというのが、ここで提示して来た見解なのである。非常に稀でかつ異常なことであるのは、植民市において2つの(別々で重なり合わない基準線としての)decumanus を用いた測量システムが用いられている場合で、その例はノーラ≪現代のイタリアのナポリ県の都市、アウグストゥスとウェスパシアヌスによって多くの植民市がここに建設された。≫で、しかしそこでは一つの統一された測量地図の中では、2つの decumanus の座標系が「右の」(dexterior)と「左の」(sinisterror)という風に結合されており、私がここで主張している耕地分割の統一性の原理はここに確かな証拠を見出すのである。≪2つの decumanus が存在する植民市であっても、それを「右」と「左」という形で測量地図の中に一緒にまとめることで統一性を保ち、測量され分割された土地の範囲=植民市であるという証拠になっている。≫
ローマとその時代における土地制度上の大変革
我々は次のことを見て来たし、また先に論じて来た観点を詳細に検討する上で次のことを疑うことは出来ない。それはつまり、ローマの ager privatus [私有地]は意図的な土地政策に見られたある傾向に起因するものであり、そこではかなりの部分まで作為的な方法を用いて土地所有権の経済的・法的な配分における無制約の自由とその可能な限りの高い流動性の確保を達成しようと努めたものであり、そして事実上、多くの社会的・経済的なマイナス点を伴うことなしにそれを達成出来たということである。我々は更に次のことも見て来たし、それどころかそれを確かめることもして来た。それは、こういった意識的に人々を動かし先へと進められた発展は、ある耕地ゲマインシャフトの存在していた場所で起きたのであり、その組織については個々のケースについて再現することは確かにもはや不可能であるが、後の時代の土地制度上の秩序においての確かな特性を、より古い時代の諸制度から新しいものへの転換として説明可能にしている、ということである。ここで最後に次のことを問うのは妥当であろう:それではこのような物事における秩序の古いものから新しいものへの革命的な転換は、一対いつ頃起きたと推定されるのであろうか?というのも、ここで取り上げている転換は、徐々に変化して来た結果としてのものではなく、近代での合併と分離[耕地整理]とはその点で全く異なっている。そのような進歩を実現した決定は、おそらくゲマインシャフトの長期に渡っての検討課題に留まり、もっとも激烈な階級闘争の対象となるのが常であったろうし、それを実施することは時によっては何世代にも渡っての仕事であったこともあろうし、それはプロイセンにおいての土地規制と統一された土地分割もそうであったのと同様であるが、しかしそこにおいて導入された原則というものは徹底して新しいものであり、その中身はもっとも偉大な革命の一つであり、土地制度の領域で実現されたものである。そういった革命は、全ての土地制度において、都市において法的思考を過剰に重んじるということが起きていた場合には、同様なまたは違った形で実現されることが出来たであろうが、ローマにおいてのように尖鋭的な形でそれが行われたケースは他にはほとんどなかった。
全てが私の思い違いでなければ、我々は十二表法制定の時代においての新しい権利状態について、部分的には確かに十二表法と関連付けてそれを確認するという決定を下さざるを得ない。既にこの論文の導入部で次のことに言及して来た。つまり我々が最も古いローマの政治について知っていることの全ては、それが大規模商業の観点をもっとも重んじているという性格を持っていたということである。それ故にカルタゴとの取引契約は、それはラテン人のこの都市国家との取引をローマが独占するものであり、そしてローマだけがラテン人の原産物の集散地となり、全ての海上取引による輸入品目の独占取扱い者となるというものであり、―ローマの市民植民市の沿岸地方への独占的設置は、他のラテン人の同盟市をそこから閉めだし、諸港湾都市をローマ市民の居住区へと変え、それらはローマによって、それらがまるでローマの自身の街区であるかのように管理され、―アンティウムにおいては、そこの(元からの)住民が自分達で海上取引を行うことは禁止された。そしてまたローマ史の頂点に来ることとして、伝承によれば王政期全体を通じてシュノイキスモス≪集住、小さな町や村が集まって都市が形成されること≫が持続的に起きていたということは、これまで述べて来たことと適合している。というのも、こうした経過もまた、古代における大規模な海上取引の拠点となった都市ではおきまりの現象だったからである。ただこういったプロセスがローマにおいては適当な時機に中止され、別の方針に席を譲ったが、その一方で例えばアテネでテミストクレスがその方向を更に推進し、それによって元々アテネの位置する場所の地理的な性質が元々持っていたリスクを増大させ、市場と後背地を結び付けていた神経網が後にずたずたに寸断されるという結果を招いていた。≪ヴェーバーがここでアテネについて言っていることを推定すると、おそらくはテミストクレスがペルシアを打ち破るために多数のガレー船を建造して海軍力を強化し、その結果サラミスの海戦で大勝利を得、そのおかげでデロス同盟という形でエーゲ海一帯を支配して大きな輸出市場を得ることに成功したが、その後にスパルタとの戦争に敗れて海軍力を失うと、アテネの経済の根幹であった貿易依存がまったく立ちゆかなくなったことを言っているのかと思われる。これと比較してローマはカルタゴとポエニ戦争を始めるまではほとんど海軍力を持っておらず、これはヴェーバーが言うようにどこかで海外市場開拓路線を止めたためかと思われる。≫このことは古代の特性に合致しているが、ここまで徹底して行われたのはただイギリスにおいて大規模植民地拡張の時代にそれが見直されたことがあるくらいだが≪ここのイギリスの説明はいつのことを言っているのか不明。イギリスがヴェーバーの時代に自由貿易主義から植民地中心主義に転じたことを言っているのか?≫、我々はここではまたローマにおいての世襲貴族を、大規模商業を推進していた大土地所有者[農場経営者]の身分として考えてみる必要があるだろう。その身分については、この2つの職業[貿易業者と農場経営者]の社会的評価という意味で、それに対する郷愁が後の共和国時代にも知られているように、まだ残っていたのである。こういった貿易と農場経営の結びつきは非常にはっきりした形で統合されたのであり、大規模事業経営についてその中に国際的な性格を取り込むことになり、また同じくそれに対して国家の政治においての服務という位置付けも与えられたのである。しかしもちろんまた次のことも読みとれる。それはローマの世襲貴族が古代アテネのそれと全く同様に、小土地所有の農民を相当にひどい程度までに搾取し、それによってその層と対立する者[自分達]を富ましたのであると。
古代ローマの陸上の戦争が行われていた間においていまや、覇権獲得のために必要であったアルバ・ロンガ≪ラティウム地区にあったラテン人の都市国家≫の制圧と暴力的なシュノイキスモスの形での周辺地域の吸収統合という観点で見た場合、そういった戦争はただ略奪戦争という性格のものであり――そのことはまた(外交)技術的な表現である”res repetere”[取り返すべきもの]が通告祭司≪ローマの祭司でまとまってコレギウム(同業者団体)を作っており、外交に従事し戦争の開始や終了の通告を行っていた。≫の最終通告の中で使われていることと矛盾しないが――十二表法制定の数十年後に始ったのは拡大していく、戦勝の度に強まっていく対外侵略推進政策であり、それは単に政治的な支配領域の拡大という結果になっただけではなく、また同時にゲマインデに所属する住民の耕作に用立てられる耕地の領域がとてつもない面積にまで拡大されたことにもなったのであり、そしてその反面の帰結として海外展開の政策は完全に抑制されることになったのである。それと同時にローマ内部における重大な内部闘争の結果は、ますます世襲貴族の側に不利なものに成っていた。モムゼンは次のことを正当に指摘している。つまりローマの平民の大きな政治的成果は護民官の選出が民会によって行われるようになった瞬間から始っており、そしてその革新において特徴的だったのは、平民で構成される民会の代表者がローマに居住している貴族ではない市民、それは中小規模の土地所有者であったが、その代表者になったということである。実際の所、この民会の目的は以下のものであった:既に慣例として認められていた権利の成文法化、借金の免除、土地所有者の地位から落伍した余剰人員の救済を、公地をその者達に分割割当てすることとそれに使う土地を侵略によって拡大することにより行うこと、であった。農民の、あるいはより正確には中流の農耕市民派≪Ackerbűrgerpartei、全集の注によればマルクス主義者のカール・ロードベルトゥスの用語≫の目的で特徴的なことは、そこにはそういう派が次の場合には成立していたに違いないが≪ヴェーバーは Partei = 党、という語を使用しているが、共和政ローマにおいて今日の政党のようなものは存在していないことに注意≫、その場合とはそういった市民が大規模商業と都市の本質的な部分に触れることにより、そういう小規模の土地所有者としてそこに更に事業者的な外見を付加された場合であるが、その外見は我々がローマの≪大規模≫農場経営者に刻印されたものとして見るものと同じであった。そういった傾向を本質的に推進したのはしかし、土地所有の法的・経済的な自由化であったに違いなく、それはまた14世紀のフィレンツェにおいての教皇党[グェルフ]が大土地所有者≪封建領主≫であった皇帝派[ギベリン]に対して行った戦いと同様であるが――ただフィレンツェでは都市のツンフト[ギルド]≪フィレンツェではアルテ・ディ・カリマラという毛織物業者の同業者組合がかなりの力を持っていた。≫が政治力を持っており、一方ローマでは2つの土地を巡る利害関係者グループ≪全集の注によれば独立手工業者と商人のそれぞれの組合、モムゼンのローマ史による≫がお互いに対立していたのである。土地所有の法的な解放が平民層に与えたのは、セルウィウス≪第6代ローマ王》の改革でのケントゥリア民会≪ローマ軍を構成する市民による兵士をその所有する財産の額で階級分けしたもの≫の結成にあたっての、フーフェの農民による土地台帳の作成≪フーフェとして共同体から割り当てられていただけの土地を自分自身の所有の土地にしたこと≫であった。そしてそこに随伴していたのは、十二表法においての取引の自由の原則的な認定であった。我々は次のことを仮定しなければならないだろう。つまり分離と併合という性格を持っている経済的な解放はまた、共通経済的負担のようなものからの自由な個人経済への勝利であり、また土地の分割によっての耕地ゲマインシャフトの完全な個人所有権への解体であり、それがまさに農耕市民派が目的としたことであり、また≪セルウィウスの改革や十二表法と≫同じ時代における成果であった、ということを。そういった解放は、次のような意味での個人所有権の概念を作り出した、あるいはよりむしろそういった概念を土地所有に適用したと言えるのであるが、その意味とは、それは利害調整の政治が反映された人為的な産物である一方で、他方はその論理的構成を徹底研究して技巧に走りすぎた結果としての、法学者の考えであるということだが、それがそのような性格を持っていた限りにおいて、それは支配的な考え方であったし、今日でもなおそれはそうである 105)。
105) ただ暗示的なこととして考えるべきことではあるが、ここでは次のことを想起することが出来る。それはアテネのソロン≪BC6~7Cのアテネの政治家で、貴族と平民の対立を緩和するためのいわゆる「ソロンの改革」を行った。≫が、新しく発見された≪1891年1月≫アリストテレスの書簡に記載されているように、似たような≪貴族と平民の≫対立を妥協に導こうとしたことである。もしかするとこの事実が周知の≪リヴィウス、「ローマ建国史」の作者の≫報告への注釈の原因になっている可能性がある。その注釈とはソロンによる立法が十二表法制定作業の開始にあたって調査の対象にされるべきとされた、というものである。
地所についての個人所有権の解放はしかし、農耕市民派の土地制度上の目標の一つに過ぎなかった。もう一つ別の目標は周知のように、ager publicus、つまり公有地に関連したものであり、この公有地に関する争いは良く知られているように、ローマ内部の争闘としては一般的に言ってもっとも程度のひどいものを引き起こした。我々はしかし ager publicus の運命についてそれでも取上げることとする。ここではそれについてそれ自身が提供する本質的な土地制度上の現象の中において、手短かに研究を進めるべきと考えるし、それも望ましくはローマの個人所有権の対象となっていなかった地所との関連においてそうすべきであり、これからその観察を進めることとする。
III. 公有地でありかつ課税可能な土地とより劣位の権利での所有状態について
ager publicus の性格
より後の時代におけるローマの土地制度の、大まかな形でありながらそれでいてはっきりと作り出された個人所有権への対立物である ager publicus の人為的な成立の経緯について明確に描写したものは何も存在していない。それがケンススの対象とはならなかったこと、法的な保護がただ禁止令という手続きによってのみ行われたこと、またその保護がほとんど犯罪的な性格を持つ侵害に対してだけ行われたこと、その譲渡の形式が定められていなかったこと、それら全ては単純化して言えば、それが権利の譲渡ではなく、ただ保護された占有状態においての地位を継承するだけのものだったからであり、事実上の力による占有が認められなくなることによって、占有していたある面積の土地への各人の法的な関係性が消滅してしまったことは、――それは公的な土地についての最古の所有状態の周知の特性である。こうした所有状態の発生の仕方は:単なる占有と耕作を通じてであり、ただまたむしろ人口がかなり多い土地では、こういった所有状態の発生は全く普通のことではなかったように思われる。
ager privatus と ager publicus の対立について人がまずしがちなのが、その対立を耕作地と放牧地の間の対立だという形で結びつけて考えることである。実際にある共和制期の公職人は彼がある土地の割当てにおいて ager publicus を作り出した作業について次の言葉を残している:”fecei ≪おそらく feci の誤記≫ ut de agro poplico agratibus cederent paastores” 1)[私は公有地の割当てにおいて、放牧者が(土地を)鋤(農耕者)に引渡すようにさせた。]そして監察官[ケンソル]によって賃貸しされた土地区画は、≪測量人達の≫技術用語としては、多く pascua ≪牧場≫と呼ばれた 2)。
1) C.I.L. I, 551 参照。モムゼンの推定によれば、U.C. 622年[B.C. 132年]の執政官ポピリウスによるグラックスの法の執行においても同様の記述が見られる。
2) プリニウス、H. N. 18, §11。キケロ, De 1. agr. 1, 1, 3 参照。
もちろん次のことは明らかである。つまり実務的にはローマの土地の領域において公共の(共有の)放牧地が、ドイツでの村落の耕地においてのものと似たような組織的なつながりを耕地と持っているということは、既に非常に早くからもはや問題とはされていなかった、ということである。≪ドイツのフーフェ制度では、牧草地は共有地[アルメンデ]として村落ゲマインシャフト・ゲマインデの中で位置付けられていた。≫もう一方で明らかなことは、農民のゲマインシャフトには、耕作地に隣接していてそこへの行き来が保証され、かつ(メンバー以外は使用禁止と)規制された牧草地の領域を持つことが必要であった、ということである。しかし次のことは確からしいと思われる。それは ager publicus の権利上の構造が、周知のように、古代での耕地ゲマインシャフトにおいての共同牧草地のそれではなく、我々はその共有牧草地の痕跡を後の時代においての、それとは別の破片のように散らばった現象において探さねばならない、つまりそれは ager compascuus ≪隣人間における共有の牧草地≫においてである、ということである。
共同牧草地 [ager compascuus]
この制度は測量人達の文献では、ただ時々のみ見出されるものとして言及しており、特にその中でも subseciva [という半端な余った土地]の転用という形である。Ager compascuus と一般的な牧草地である pascua publica [公共の牧草地]との違いは、2つの点にある。一つは、前者は測量人達の時代においてはただある特定の、多くは隣人同士である(proxim)土地区画所有者達が共有の牧草地として所有し、そしてその権利は彼らの土地の付属物として通用しており(所有権)移転の際には一緒に扱われる、という点にある 3)。
3) 測量人達の compascuus についての記述でもっとも重要な箇所は次のフロンティヌスの De contr. p. 15 である:Est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune; propter quod ea conpascua multis locis in Italia communia appellantur, quibusdam in provinciis pro indiviso.
[それはまた fundus の土地に付属する牧草地の所有権であり、しかしそれは共有される;このために、イタリアの多くの場所で牧草地は「共同のもの]と呼ばれ、ある属州においては「分割されないもの」と呼ばれる。
-さらにヒュギヌスの De cond. agr. p.116, 23:In his igitur agris (den zum Verkauf bereitgestellten überschüssigen Äckern) quaedam loca propter asperitatem aut sterilitatem non invenerunt emptorem. Itaque in formis locorum talis adscriptio, id est “in modum compascuae”, aliquando facta est, et “tantum compascuae”; quae pertinerent ad proximos quosque possessores, qui ad ea attingunt finibus suis. Quod genus agrorum, id est compascuarum, etiam nunc in adsignationibus quibusdam incidere potest.
[それ故これらの土地において(売却の準備が出来ている余剰の土地において)いくつかの土地は荒れ地であるか不毛の土地であることによって買主を見つけられなかった。それ故に測量地図上に次のように書き加えられた、つまり「共有の牧草地の状態にある」と。そして時には「ただ共有牧草地としてのみ(使われる)」と記載されることもあった。その所有権はその土地の境界が接する隣人達の(共有の)所有となっていた。このような種類の土地、つまり共有牧草地は、また今日でもいくつかの割当てられた土地において(隣接して)存在している場合がある。]
-シクルス・フラックスの p. 157:Inscribuntur et “compascua”; quod est genus quasi subsecivorum, sive loca quae proximi quique vicini, id est qui ea contingunt, pascua … (Lücke).
[(測量地図上に)「共同牧草地」と書かれているもの;それが subseciva の類いの土地であるか、またはその土地の近隣の複数の隣人達の(共有の)土地であるか、それがこの類いの土地が発生する理由であり、牧草地が…(テキスト欠落)。]
-ヒュギヌスス、De lim. const. p.201, 12:Siqua compascua aut silvae fundis concessae fuerint, quo jure datae sint formis inscribemus. Multis coloniis immanitas agri vicit adsignationem, et cum plus terrae quam datum erat superesset, proximis possessoribus datum est in commune nomine compascuorum: haec in forma similiter comprehensa ostendemus. Haec amplius quam acceptas acceperunt, sed ut in commune haberent.
[もし共有牧草地または森林が土地に付与されているならば、それがどういう権利で与えられているかを我々(測量人)は測量地図に書き込むだろう。多くの植民市において広大なサイズの土地を割当てることに成功し、そしてこれらの与えられた土地以外に余っていた土地があったので、それらは(近隣の)土地の所有者である隣人達の共同の所有物として compascuus の名前で与えられた:この土地については測量地図上においても同様に把握され、その旨我々(測量人)は明示する。この土地は元々(割当てで)受け取った土地以外の土地として受け取るが、しかしそれは共有の形で保持する。]
- Aggenius Urbicus≪フロンティヌスの著書で引用されている技術書の著者≫の引用部分である p. 15 については後で論じる。
(二つの相違点の内の)もう一つ明らかな点は、この Ager compascuus に対する権利の保護が特別なものであったということである。「もしその土地が Ager compascuus であるならば」とキケロは言う(トピカ 12)「その権利とは共有地で家畜に草を食べさせることである」≪キケロは comasucuus と compascere を同族語(coniugata)の例として出している≫その対立物は明らかであり、つまり公共の土地において、つまりpascua publica において、ある「種別」、つまりここでは個人の権利としての、訴訟において保護される牧草地としての権利への請求権は成立していないのである。この牧草地としての権利として保護された訴えがどういう類いのものであったかは、もちろん知られていない。ひょっとするとキケロの時代においては事実上、ペルニーチェ≪Lothar Anton Alfred Pernice、1841~1901年、ドイツのローマ法学者≫が推測しているように、イェーリング流の≪Rudolf von Jhering、1818~1892年、ドイツの法学者。責任ある市民は自分の権利擁護のために戦うべきという義務を主張した「権利のための闘争(Der Kampf ums Recht)」という書籍はベストセラーになり26ヶ国語に翻訳された。≫応急的な権利訴求手段である actio injuriarum ≪不正行為に対する訴訟、名誉毀損、肉体への暴力、プライバシー侵害などの行為に対して訴えを起すもの≫に訴えるものとして理解すべきなのかもしれない。より古い時代については私は次のように考える。つまり耕地に対しての正当な持分関係を確立するための手段として controversia de modo があったのとまったく同じように、牧草地としての権利を得る上でそれに使えるように構成された何かの法的手段が存在した、ということである 4)。
4) フロンティヌスの p. 48, 26, 49(そしてそれについての Aggenius Urbics の p. 15,
28):de eorum (scil. der compascua) proprietate jus ordinarium solet moveri, non sine interventu mensurarum, quoniam demonstrandum est quatenus sit assignatus ager.
[その(compascuaの)所有権については通常の法的手続きが進められることが多いが、測量が介在しない訳ではない。何故ならばある土地がどこまで割当てられているのかをはっきりさせる必要があるからである。]
こことまた先の注釈で引用した箇所についてフロンティヌスは compasucua を controversia de
proprietate ≪所有権についての訴訟≫のカテゴリーの中で扱っている。測量人達は概して fundus
への個々の付属物――耕地区画、森林の伐採権、牧草地としての権利への請求権の行使を――controversia de
proprietateとして取り扱っている。共有牧草地についての持ち分はまさに元々は全く同じように、かつまた実際的な行使においては大きく異ならない程度に「所有権」の対象物であり、それは耕地ゲマインシャフトの中で耕地についての持ち分と同様であった。そのことから、ドイツのアルメンデ[共有地]のように,それらが容易に普通の共有の所有権となることが出来るのは明らかである。もちろん D. 20 §1 それ自体の場合においても si servitus vincidetur (8,5)(スカエウォラでは: Plures ex municipibus qui diversa praedia possidebant, saltum communem, ut jus compascendi haberent, mercati sunt, idque etiam a successoribus eorum est observatum; sed nonnulli ex his, qui hoc jus habebant, praedia sua illa propria venumdederunt; quaero, an in venditione etiam jus illud secutum sit praedia, quum ejus voluntatis venditores fuerint, ut et hoc alienarent? [wird bejaht, sodann weiter:] Item quaero, an, quum pars illorum propriorum fundorum legato ad aliquem transmissa sit, aliquid juris secum hujus compascui traxerit? Resp., quum id quoque jus fundi, qui legatus esset, videretur, id quoque cessurum legatario)
[異なる農地を所有していたムニキピウムの複数の住民が共通の放牧地を購入し、それによって共同の牧草地を持つことにした。そしてその土地は彼らの相続人によっても保持されている;しかしこの権利を持っていたこれらの者の中で何人かは、自身の遺産であるその土地を売却した;私は問うが、その売却において、売主の意向がそうであった時に、その権利も共同所有権から分割されて土地と一緒に譲渡されたのか?【これは肯定される。そして更に:】同じく私は問う。fundusの所有権の一部が遺産として誰かに渡された場合に、この共同牧草地の分割された権利も移転されるのか?ある者が答えて、遺産として受け取った土地の権利が、その土地に付属するものと見なされる場合は、その権利もまた相続人に移転されると。]≪【】はヴェーバーの追記≫
という部分は、通常の共同所有権が本当に存在していたのか疑わしく思える。(権利分割請求か?)もっとも通常はそれはもちろん可能なことであったが。考慮すべきことはいずれにせよ個々の fundus を個々人の所有に属するとしている描写であり、そして次の可能性が考えられるだろう。つまり、ここで取り扱われているのは賃貸借によるか、あるいは永代借地としてか、または購入されたか(ager quaestorius の権利で)である公有地の耕作で所有権が与えられていない場合であるということである。この場合、次のように考えられるかもしれない。つまり、この文書で主張されているように、単なる行政的に保護された権限ではなく、ある権利が得られたのであり、――そこにおいては古い制度であるアルメンデへの準拠が起きているのかもしれない。比較すべきなのは:キケロの pro Quincto. c. 6 の最後の部分である。アリメンタ制度の表≪Alimentartafeln、皇帝ネルウァやトラヤヌスの時代に設けられた貧しい家庭の子供や孤児への福祉制度。その財源として土地所有者からの寄付が使われた。≫(Veleja col. 4,、84行目、 Baebiani col. 2、49行目)の中に付属物として共通の fundus とsaltus ≪小道≫について言及されている。この制度はつまり、私が思うには、次のような人間関係を否定している。その人間関係とは、例えば耕地ゲマインシャフトの成立の際のそれとか、そして後には農地の錯綜状態や古代の土地制度の残滓である諸状態がまだ支配的であったとか、あるいは存在していたに違いないというそういう人間関係である。全ての他の状態との類推の中で、当時に唯一適用出来るのが、耕地においてある者がゲノッセンシャフトの成員として持分を耕地において所有していたということであり、そして確かにその当時牧草地の権利の範囲はフーフェの権利に従って決められていたし、そして共同牧草地の権利というのは全ての土地区画所有者に与えられていたのではなく、ただ “fundus” の資格者にのみ牧草地において割当てられていた。同様に次に耕地の分割と合併が行われた時、個々の土地所有者に一定のユゲラの面積の土地が改めて割当てられたのであるが、その分割と併合はアルメンデの共有地においては、それが以前と同一の物として一般的にある土地ゲマインデの牧草地という古い形で成立していた限りにおいては、次の結果、つまり一定の面積の土地区画についてある決まった面積が――それが全員同じ面積であったというのは疑わしいが――飼育している家畜の数に応じて割当てられ、部分的にはまた使用料の支払いに応じて割当てられた、につながったのである。土地の(再)割当てによる耕地の併合においては常にまた共有地の設定が同時に行われており、そして明らかなこととしては、そこに植民市があったと推定される場所においては、それまでのそこの土地の所有者の権利を取上げることを意図せず、むしろアルメンデを拡張された領域の中に編入することで必然的に生じる土地面積の余剰部分が得られたのであり、また元からの土地所有者は分割割当てによって一つにまとまった土地区画を得ることと経済的に解放された地位を得ることが、アルメンデの喪失という損を埋め合わせた、と信じられていたのである 5)。
5) シクルス・フラックスの p. 155, 20 の併合された土地の所有者について: … in locum ejus quod in diverso erat majorem partem accepit … [彼らに割当てられた土地はそれぞれ面積が異なっていたが、彼らはその大部分を(不平不満なく)受け取っている。]このことは次の場合においてのみ可能である。つまり、土地の併合においてはまた、新たに割当てられる面積が以前耕地として持っていた総面積よりも大きかった場合であり、そしてこのやり方はただアルメンデを同時に分割することによってのみ可能であった。
というのもこういった農地の分配はまた、既に注記したように、おそらくはイタリアにおいて古代ゲルマンの土地制度と同様に根源的なものとして成立した基礎原理、つまりフーフェの土地を所有する農民のみが、その耕地に定住している全員ではなく、牧草地の権利を与えられたということと、またそれ故に古いフーフェのある種の土地ゲマインデが成立していたこと、そういったことを一掃してしまった、――そして実際のところそのことは、土地区画の(実質的)所有者が Usukapion ≪時効による取得≫が認められることによって、フーフェの土地を所持する農民と同列の位置に置かれるようになった後は、よる古い時代の(一部の農民にのみ認められていた)権利状態を得ることが、長い時間をかけずに≪時効取得は2年≫可能となり、それについて仮定されるのは、ここで考えて来たようなやり方で同様のことが実際に起きていたということである。フーフェの土地を所持する農民とそうでない者の違いはもはや確認することが出来なくなっていたし、また人がそこからその制度を存続させようとしていた限りにおいて、人は土地の正当な所有者を見分けるためには、牧草地の土地に境界を示すものを設置するような外面的な手段に拠るしかなかった 6)。
6) 注3で引用した箇所を参照。
こうした人間関係の全体の扱いは、それ故にまたより後の時代のローマの耕地制度のこれ以外の他の全ての共通経済においての敵対的傾向に合致するのであり、それについては既に前述の箇所で見て来た。
もちろん ager compascuus は意味においてこの側面のみに限定される訳ではなく、それは土地領域を ager publicus 6a) に取られてしまうことになったのである。
6a) ここで意味しているのは:一般的な家畜へ草を食べさせることの自由と占有権の基盤となる土地に対してである。
a.u.c. 643年(BC111年)の土地改革法は、イタリアの ager publicus について25行目で次のように規定している:
neive is ager compascuus esto, neive quis … defendito quo mi(nus quei v)elit compascere liceat.
[この土地は(もはや特定の権利者だけの)共有牧草地ではない、誰も…そこで家畜に草を食べさせようと欲する者を閉め出すことは許されない。]
ager compascuus と、共有牧草地ではない ager publicus との対比を明確にするならば、前者ではある特定の土地ゲマインシャフトのメンバーのみに排他的に牧草地の使用権を与えているのに対し、ager publicusの方では特徴的なことは、上記の lex agrari の同じ箇所で規定された、ager compascuus にぴての占有権の排除、といことが実際には本質的な要素であった。この両方について、周知のように、またゲルマン族のアルメンデと共有のマルク≪アルメンデよりも広い範囲での共有地≫が所有という面で対立していたのに対応している。ドイツのアルメンデとの類似はまた次の点にも現れている。それは compascua として存在している領域に対する管轄権に関して、統一された考え方は全く存在せず、しばしば直接的には非常に不透明なままであった、ということである。そのために、その領域に放牧権を持っている特定の所有者達は、compascua が通常の意味での共有物になっているということは全く当てに出来ず、いずれの場合も裁判による共有物の分割[actio communi dividundo]による調整によって、自由に随時分割するという方法は使えなかったのである。しかし他方では明白なこととして発生していたことは――そしてこちらの方が実務的にはより重要であったのだが――また非常に多くのケースでその土地に関連する人間関係と ager publicus の土地との境界についての疑念であった。フロンティヌスによる注解書では compascua について次のように述べられている(p.15, 26):certis personis data sunt depascenda, sed in communi: quae multi per potentiam invaserunt et colunt.[ある人達に放牧を行う権利が与えられたが、それは共有の形であった;そこに多くの者が力づくで侵入し耕作を行っている。]ここについては誰もが中世の末期で地主が垣による囲い込みで村のアルメンデを力づくで奪ったことを思い出すのではないだろうか?――そして実際の所、必要な修正を加えて考えれば[mutatis mutandis]二つの現象は同じ起源を持っているのである。
占有の起源。マルクとアルメンデ。
前章においては、次の前提から議論を進めて来た。つまりイタリアでの定住については、我々が知らされている限りにおいては、氏族社会に対立するゲノッセンシャフト的なものであったと。この見解はしかしながら、フーフェ制度の他の全てを説明し得ていないように思われる。公的な成果[戦争の勝利など]に基づく農地の分配やフーフェの土地に対する公的な権利に基づく測量といったことはゲノッセンシャフトとの相違点を示している。しかしそのことによって次のことを言おうとしているのでは全くない。それはローマ史の先史への入り口において、他のほとんどの国と同様に、そのより古い時代の社会組織については何も情報を持ってはいないが、家への隷属を伴う厳格な士族的組織が存在しており、その影の残余物が、例えばクリエント制≪ローマでのパトロンとクリエントという、一種の親分子分的な互酬の人間関係のこと≫やローマの家族制度の在り方において歴史時代においてもなお深く投げかけられているのであると 7)。
7) 我々の知る限り、歴史において人間のゲマインシャフトにおける組織の頂点に、純粋に経済的な観点から考えてそういった氏族組織が存在していた、ということはない。親族ないしは氏族団体を継承したのはむしろようやく後の時代に、土地制度以外の領域において――私が全く別の事例として私の論文である「中世合名・合資会社成立史(中世商事会社史)」において論証しようと試みたように≪おそらくは中世のイタリアで家計・家業ゲマインシャフトから合名会社などのゲゼルシャフトが発生したことを言っていると思われる≫――本質的に経済上の観点で組織されたものである。こういったことによって結果としてもたらされたのは、個々の家族がそれだけより緊密な形で一まとまりになったということである。≪家計ゲマインシャフトから生まれた合名会社はファミリーの財産を分散させずに一まとまりに保つのに貢献し、より巨大な財閥ファミリーへと発展するのに役立った。≫それ故にそれはもしかするとローマでも起こったことかもしれない。
我々はここでただ次のことに思いが至る。それはこれまで見て来た限りにおいて、確実かつ決定的なこととしてゲノッセンシャフト的な観点での「植民」が発生していたに違いない、ということである。そのように確実にあったと思われる植民が意味したことは、しばしば直接的に、家父長的支配からのある種の解放ということである。大規模家畜所有者は、主要な放牧中心の経済が半遊牧民的な耕作を伴っていた時代においては、たとえ氏族制度が形の上で成立していない場合でも、経済的には他の部族ゲノッセンシャフトの主人であり、それ故に彼らは常に全ての確実かつ決定的に行われた植民の生来の敵対者だったのである;耕作地においての自由な牧草地の利用権と移住してきた植民者のためのアルメンデは、そういった大規模家畜所有者達にとっては再度奪い取って権利回復させなければならないものだったのであり、彼らは常に移住してきた植民者のゲノッセンシャフトのために分離されたアルメンデを共有のマルクの中に取り込もうと試みていた。土地を家畜の牧草地として利用することはしかし、全くもってマルクを搾取するただ一つの方法ではなかった。古代ゲルマンではよりむしろ別の形に刻印されたビファンク権が知られていた。それは新規に荒野や森林を開墾した土地[Rottland]の占有について、開墾した者が新たに手に入れた領域を私的に利用している限り、またその間その者がそこで耕作している限りは、その領域を垣で囲い込むことが許されたものである 8)。
8) フェスタス≪Sextas Pompeius Festus、2世紀後半のローマの文法家、フラックスの De verborum significatione という百科全書の要約版を作り、そこに語源と意味を追加したものを著わした。 ≫参照:Occupaticius ager dicitur qui desertus a cultoribus frequentari propriis, ab aliis occupatur. [占有されている土地とは、その土地を耕作していた者がそこを放棄し、別の者によって占有されているものを言う。]
そして耕作の意義が増大するに連れて、そして牧畜経営にとっては家畜に牧草を与える土地を得られる余地がどんどん少なくなっていく、という点でこのことは意味を持っていた。ローマ国家によって法に規定された状態においては、この占有については、それが禁止されていなかった限りにおいて、その占有地についてその地域における権力者に使用料を支払うことが行われるということにしばしばなっていた。そしてその意味で私はカルロヴァ≪Otto Karlowa、1836~1904年、ドイツのローマ法制史学者≫の見解 8a) である、アッピアノス≪AD95頃~165年頃、ギリシア人でローマ市民権を得て、全24巻の「ローマ史」を著わした。≫が報告している、より後の時代の占有の状態として記述している、その土地の収穫高に応じた一定の支払いが義務付けられた、ということを非常に確からしいと考える。おそらくは通常論じられているようにこの使用料の支払い義務が忘れられてしまったのではなく、世襲貴族達はそもそもその義務自体を一度も認識したことがなく、ただその時々の政治的な力関係によって大なり小なりそれに従わざるを得なかっただけである。もちろん次の場合、それは先行して発生していたことのように思われるが、つまり国家によって征服されたとかあるいは敵に奪われた開墾済みの土地領域について、特別な公示によって全ての市民に対して自由な占有が開放され、そしてこのことが確からしいこととしては公共の土地の国庫上の利害関心においての最古の利用方法であり、ここでは確固たる公課の宣告が行われ、アッピアノスによれば耕地の場合は1/10、森林の場合は1/5の税が間違いなく課されたのであるが、共有マルクにおいての開墾地においてはしかし根源的なこととして、この課税ということが行われることがほとんどなかったのであり、この2つの状況をきちんと区別して同定することは、その課税対象の土地の所有者の利害関係に依存することであって、非常に区別が難しいのである 9)。
9) 同様の区別の難しさという点での混乱がまた、ager occupatorius ≪戦争の勝者によって占有され、元の住民が追放された土地≫の概念からもまた生じて来ると思われ、それが ager occupaticius ≪元の耕作者が放棄し、別の者が占有している土地≫とは別のものであるということが多くの者によって強調されている。(例えばモムゼンとルドルフ≪Adolf Friedrich Rudorff、1803~1873年、ドイツのローマ法制史家≫、―ブルンズ、フォンテス p.348 N.5、Roemische Feldmesser II, 252)まず第一に、今挙げた最後の文献の言及する所では、使用料支払い義務のある占有地という形で利用された(略奪による)占有地が成立していたのであると。シクルス・フラックスは p.138 で次のように述べている:
Occupatorii autem dicuntur agri quos quidam arcifinales vocant, quibus agris victor populus occupando nomen dedit. Bellis enim gestis victores populi terras omnes, ex quibus victos ejecerant, publicavere atque universaliter territorium dixerunt intra quos fines jus dicendi esset. Deinde ut quisque virtute colendi quid occupavit, arcendo vicinum arcifinalem dixit.
[しかし占有された土地と言われるものは、ある者が”arcifinales”(未測量の土地)と呼ぶ土地であり、勝利した方の国民がそれを占領することによってその名前が与えられた。戦争が終わった後、勝利した国民は全ての領地を、そこから敗れた者達を追放して占領した。勝者はその土地を公有地とし、そのすべてを領土と呼び、その中で司法権が行使される境界を定めた。それから各々の者がその耕作の能力に応じてある土地を占有した場合、その者はその土地に隣接する周りの土地を保護し、それを arcifinales と呼んだ。]
それに対して、ヒュギヌスが De cond. agr. p.115, 6 で言っているのは、明らかに同様に先に名前を出した ager occupatorius についてのものである:… quia non solum tantum occupabat unusquisque, quantum colere praesenti tempore poterat, sed quantum in spem colendi habuerat ambiebat(参照:シクルス・フラックス p.137, 20)
[何故ならば各人がその時点で耕作出来る土地を占有しただけではなく、また先々に耕作する見込みがある土地を囲い込んで持っていたからである]
事実上の耕作の範囲に依存していたのは、おそらくはただ新規開墾地の占有の場合だけでなく、収穫高に応じた税という条件での征服された土地の占有の場合もそうであろう。というのも国家は、1/10税を徴収する主体として耕作地の領域の範囲に利害関心を持っていたからであろうし、そして継続して未耕作の土地は他方では放棄されたのである。ここで言及されている占有、つまり「(将来)耕作する見込みのある土地を所有していた」は。2つのケース(占領によるものと、新規開墾によるもの)のどちらでもなく、通常の ager arcifinius について言っているのであり、つまりそれは市民ムニキピウムの土地で、ローマ式の測量が未実施のものである。というのも643 u.a.c. 年の土地改革法によって個人の占有が許された土地はほとんどがローマの征服地においての ager occupatorius だったからであり、そのためにそこの(新たな)住民は(未測量の)不規則な形の土地ブロックを全て自分の所有地と同一視したのである。それ故私には ager occupatorius はより範囲の広い、測量といういう観点で ager arcifinius と、そして将来の所有を期待するといういう意味でガビイの土地≪地権はあるが未測量・未割当ての土地≫と同一視すべき概念と思われ、一方 ager occupaticius の法はビファンク権≪開墾者がその土地の占有を許される権利≫から派生した所有形態の特別な場合と思われる。――以上述べたような土地の種類の同一視はまた次のことの理由でもある。それは何故 “vetus possessor”≪以前の所有者≫が、つまりモムゼンの納得の行く説明(C.I.L., Iでの lex agraria への)に拠れば “ager publicus”のある種の占有で、その所有状態がグラックス兄弟の制定した諸法律もしくは u.a.c. 643年の土地改革法の前に根拠付けられたものであり、その時々において一般的に未測量・未割当て地の所有者と同一視される、ということへの理由であり、そのようにシクルス・フラックスの引用箇所や、更には(より具体的な把握として)フロンティヌスの p.5, 9 や、同じくシクルス・フラックスの p.157, 22 とヒュギヌススのp. 195, 17 が述べている通りである。そしてこのことは更に次のことの理由でもあったのかもしれない。それは何故 ager arcifinius が一般に完全な個人所有権を認められたものになっていなかったということの理由であり、そのことは三人組委員会による土地の強制的な買い上げと、一般的に言って強制的なやり方でのそれまでの旧所有者達への全てまとめての新規耕地の再分配に現れており、それはそれらの文献において法的な視点で実質的なこととして表現されている限りにおいて、そうだと言える。
もちろん次のことも想定出来るかもしれない。つまり、十二表法の時代での耕地分割の際の公共地の牧草地としての使用への課税[scriptura]と同じく、それぞれの土地への課税が一般的に導入されたか、あるいは導入されねばならなかった、ということである。というのは単に普通の開墾済みのマルクの自由な占有だけではなく、牧草地のそれも認容されていたということは、私が考えるに、元々その者には権利が与えられていなかった領域でのビファンク権の侵害という性格も持っていたのである。古い耕地ゲマインシャフトが併合と分離の機会において、それが元々持っていたアルメンダがその際におそらくは一般的なこととして、ager publicus という容器の中に投げ入れられたのであり、またそれまでの所有状態については特定の個人の fundus に応じての compascua への割当てということが各地で行われたのであり、それはまさに後の時代の土地の割当てと同様であり、それこそ測量人達が述べていることである。土地資本主義
確からしいこととして――そのことは当時の(土地を巡る紛争の)和解についての性格全てに当てはまることであるが――当時の全ての市民の公共の土地への関係における形だけの権利の平等が、自由な牧草地利用を禁ずる制限撤廃の許可と同じく自由な占有の許可によって作り出されており 10)、そしてこのことにより当時の人々は少なくとも理論的な形で導入された土地税の支払いによって、このような類を見ない(土地)資本の獲得の奨励をカモフラージュしようと試みたのである。というのも、この自由な競争が小農民の土地所有者にとって有用だったのではなく、ただ大資本家、つまり世襲貴族とまた(裕福な)平民にとってのみ有用だったということが、しばしば強調されている。そういった自由競争は事実上は土地制度の領域における全く制限の設けられていない資本主義を意味するのであり、それは歴史の中でかつて実際に行われていたのであり、そしてこのことは既に述べた中世末期におけるグルントヘル(大地主)による土地の不法獲得と囲い込みとの対比という意味では、量的にも質的にもほぼ遜色の無いレベルにまで達していたのである。
10) というのも平民に対して、リキニウス・ストロ≪Gaius Licinius Stolo、 正確な生没年不詳、BC4世紀のローマの執政官・護民官。護民官の時にセクスティウスとリキニウス・セクスティウス法を制定した。その法律では500ユゲラ以上の土地の所有が禁じられた。≫が自分自身が制定した法律による土地の占有の上限を超えたことにより罰金を払ったという伝承が示しているように、決定的なこととして考えられるのは、既にそれが起きる以前の時代で占有ということが許可されていたに違いないということである。
経済的かつ社会的な階級の利害とこの自由競争の結果が一緒になって示しているものはまさに、ローマ史を通して一般的に、赤裸々な人間の姿であり、それは古代における政治家と近代の社会史家に等しく利点を提供しているのであるが、それは古典古代のファッションの実態が同時代の芸術を理解する上で有用であるのと同様である。それから ager publicus を巡っての階級闘争がより一層激しい段階へ突入したということは良く知られている 11)。リキニウスの提案は占有の上限を500ユゲラにすることでこれを是正しようと必死に努力していたものである 11a)。
11) ここにおいてはこの階級闘争の個々のケースについて追いかけることはしない。何故ならば土地制度史という見地に立った場合、様々な事実を見出すことが出来るのは確かであるが、それによってこれまで知られている階級闘争の実像について何も新しいものを付け加えることは出来ないからである。
11a) もしかするとこの時に初めて牧草地の使用料(税)というものが導入されたのかもしれない。いずれにせよ伝えられているのは、リキニウス・セクティアヌス法はまた非課税の家畜の飼育を伴う耕作の上限――牛・馬の場合は100頭、鶏などの小家畜の場合は500頭(羽)――を導入しているということである。(参照、アッピアノスの引用済みの1、8)。≪鶏はインド→エジプト→ペルシア→ギリシアのルートで、ギリシアにBC9世紀頃伝わり、その後ローマに入った。≫
公有地の分割割当てを求める声は、共和政の時代を通じて一度も社会から消えてなくなることは無かったが、しかしその声を上げていた多くの無産者が、その元々の性格を次第に失っていった時、その声に応えてローマの内部でその認可が行われることは無くなっていた。以前は(利用出来る)平地に対して植民の人数の過剰という状態があり、そのために廃嫡または遺産分割によって零落した農民である土地所有者の子供達は、耕地の新規分割割当てによって自分自身による耕作の新規開始と、また tribus rusticae に受け入れられることで、彼らの親達が属していた adsidui ≪税を納める義務のある一人前の市民≫に復帰することの可能性を得ようと必死だったのである。ただローマが大都市的な性格を強めていった結果、プロレタリアートはそのエネルギーを増大させていくことが出来なくなり、彼らは近代的な性格での都市の下層民として十把一絡げの状態になっていき、彼らについては土地所有者の身分上の体面という意味は加速度的に失われてしまったのであり、――そうした変化は同様の状況の場所ではどこであってももはや時間の問題であったことであるが、――その者達にとっては農民としての生計の基盤である土地が、より勢いを増しながら(他者の所有物へと)吞み込まれていったのであり、そして彼らの状況により大土地所有のための耕地整理の推進に対抗して自分の土地を守り抜く、というエネルギーが奪い取られたのである。割当てられた土地は色々な意味で投機の対象となり、植民者の所有物から換金の対象に変わり、その目的は大都市(居住者)の(投機という)享楽のためであり、グラックス兄弟、スッラ、そしてカエサルによる、新規植民者が入手した土地の売却についての購買の上限を設けることで制限しようとする試みは、常に失敗に終らざるを得なかった。その理由は、その政策が関係者の利害を、敵対者(世襲貴族)の利害と同じく、著しく損ねたからであり、また確からしいこととしてこの種の土地はケンススへの完全な登録を行うことが出来ず、それ故所有者の政治的な意味での階級としての権利を高めることがなかったからでもあった 12)。
12) 土地改革法の第38条に確かに起因していることである、グラックス兄弟が ager optimo jure privatus ≪非課税の私有地≫についてケンススへの登録を認めたこととはまた別のことである。しかし残念ながら確実なこととして、少なくともケンスス制度の何らかの部分的な改革について、つまりフーフェの土地の登録からある種の財産登録という変化については、何も知られていない。おそらく可能性があると思われるのは、その場合でもクイリーテース所有権による土地の占有はどういう形でも許されていなかったのではないか、ということであり、しかし私が確かなこととして考えたいのは、この種の占有はいずれの場合にも tribus rusticae における assidui ≪軍役を負担する市民≫への登録にはつながらなかったのではないか、ということである。キケロのフラックス弁護の80にて、ある者が小アジアのアポロニア≪現代のトルコのアナトリア半島の北西部にある湖とその周辺≫に土地を所有していて、それがローマでケンススに登録されたことによって、その者が利益を得た、とある。しかしキケロはその弁明に対して次のように異論を唱えている: Illud quaero: sintne ista praedia censui censendo? habeant jus civile? sint necne sint mancipi? subsignari apud aerarium aut apud censorem possint? In qua tribu denique ista praedia censuisti? [私は次のことを問う:その農場は(本当に)ケンススに登録されたのか?それは(本当に)法的な権利を持っていたのか?それは正式な売買手続き(mancipatio)に拠って獲得されたものかそうではないのか?それは国庫に登録されたのか、あるいはケンススに登録される形で獲得されたのか?どの部族にてその農場は実際にケンススに登録されたのか?]
占有と ager compascuus の終焉
土地政策と社会政策の性格を持つ最後の大規模な土地分配の試み、つまりグラックス兄弟の改革によってもたらされた全ての土地所有に関係することがらの大混乱は、先に見て来たように、次のような結果をもたらした。それは3つの新しい土地法であり、その最後のものが u.a.c. 643年の土地改革法であったが、それはそれまでの占有を、ケンススへの登録の許可を与えることと ager privatus の全ての他の特権をそれらの占有された土地にも許可することによって最終的に認可したのであるが、それはつまりグラックス兄弟によって推進された植民者の土地の売却制限 13) をケンススへの登録の許可という形で取り除いたのである。
13) ケンススへの登録許可は3つのここで想定されている法律の最初のもので既に認められていた。643年の法律はただこのことを間違いのないこととして再確認したのであり、その中で――これが第8条のまさに意味する所であるが――そういった占有された土地に対して正規の売却手続きを行う権利を付与したのである。
未来に向けて土地改革法は更にまた農民のアルメンデと徴税権の古くからの対立も取り除き、その中でその法はそういった形でまだ残っていた ager publicus の残りの部分について compascua として使うことと占有を許可すること 14) の両方を等しく終了させたのである。(25条)
14) グラックス兄弟は周知のようにリキニウス・セクスティウス法に修正を加え、その法で認められていた公有地の保有上限500ユゲラ以外に、息子2人まで各250ユゲラを追加で保有することを認めたが、更に修正を加え、その他、他の全ての占有を禁止した(C.I.L., Iのモムゼンの土地改革法への注記)。しかしながら後になって占有の認可が再度討議され、643年の土地改革法では一人あたり30ユゲラまでの占有は許可された。しかしその間に、lex Thoria agraria≪アッピアノスによると lex agraria の後に制定された3つの法の内の2番目≫によって、そのように見えるのであるが、占有に関して重要な変更が加えられており、それについてキケロ(Brutus, 36, 136)は次のように描写している:(Sp. Thorius) … agrum publicum vitiosa et inutili lege vectigali levavit. [ある者がその欠陥の多い無用な法律により公有地に課されていた税金を軽減した。]モムゼンによればルドルフ(Römische Rechtsgeschichte, 1, S41)による説明は以下の通りである:彼≪Spurius Thorius、lex Thoria の制定者とされる者≫は(公有地に)課税することで ager publicus をそのある欠陥の多い無用な法律から解放した。≪公有地の課税率が軽減された結果、私的な占有が加速したのを、lex Thoria が再度税率を戻すことによって、そうした私的占有に歯止めをかけようとした。≫この説明は文法的には全く無理がないとは言い難いように思えるが、しかし文脈の意味に従えば、私はそう信じるが、別の満足の行く説明をこの箇所に加えることは困難であろう。≪元の文章は悪法を制定したということを言っているように思えるが、このルドルフの解釈はそれをまた是正したとしている。levavit =軽減する、解放する、が税率のことを言っているの公有地のことを言っているのかという問題である。≫少なくともこの解釈はアッピアノスの次の説明(引用済みの箇所、1, 27)との連関で:”τὴν μὲν γῆν μηκέτι διανέμειν, ἀλλ’ εἶναι τῶν ἐχόντων, καὶ φόρους ὑπὲρ αὐτῆς τῷ δήμῳ κατατίθεσθαι”[その土地はもはや分配されず、現在その土地を占有している者のものになっており、その土地に関する税金は(本来は)民衆のために納められるべきである(のにそうなっていない)。]良い説明となっており、つまり:ager publicus の占有は ager vectigalis ≪課税される土地≫へと転換させられたのであり、それが意味するのは(理論的には成立していた筈の)現物貢納の支払いの代わりに、それは収穫物の内の一定割合を土地の使用者と親族関係にあるその土地の地主に払うもので、法的には不安定な低位の所有状態の証拠として捉えるべきものであるが、帝政期において非常にしばしば地主達がそれを得ようと努めかつ渇望していたのと同じように≪現物貢納は収穫高とその時々の穀物の相場で取り分が変動するので、地主には固定額の現金払いの方が都合が良かった≫、(現物貢納に換わって)確固たる現金払いが登場するのであるが、つまり adaeratio ≪現金での使用料払い≫が生じていたのである。そして更に、ある土地での使用料取り立て可という認定は、もしかすると使用料免除の場合だけにされた≪本来は使用料を払うべき土地であることを確認してから免除した≫のかもしれないが、しかしその他の場合では所有状態の不安定さを解消したのである。(後述の箇所参照)
同時に lex agraria は ager compascuus に対して次のように取り決めている(第14、15条、モムゼンの補完に基づく):Quei in agrum compascuom pequdes majores non plus X pascet quae(que ex eis minus annum gnatae erunt postea quam gnatae erunt … queique ibei pequdes minores non plus …) pascet quaeque ex eis minus annum gnatae erunt post ea qua(m gnatae erunt: is pro iis pequdibus … populo aut publicano vectigal scripturamve nei debeto neive de ea re sati)s dato neive solvito. [共有放牧地において大きな家畜(牛や馬)を10頭以上放牧しない者で、その家畜の中で生後1年未満のものについては、その後産まれたものについても、それらの家畜について…ローマ人民や公共の徴税人に対して土地の使用税やその他の税を支払う必要はなく、そのための担保を提供したり支払いを行うこともない。]私見としてそこから考えられることは、ager compascuus は、それがある耕地ゲマインシャフトのアルメンデという意味で成立していた限りにおいては――というのはここではただそういう ager compascuus のみを扱っているのであり、任意の個々人により共通に獲得された土地の断片に類したものを扱っているのではないからであり――、ローマの人民の公有地の一部としての意味で把握されるのであり、その土地については国家のための目的という建前で使用することが出来たものである。こういった見方に基づいて明らかに以前の時期よりこの ager compascuus に対しても使用税[scriptura]の支払いを義務化するという試みがなされており、その故にこの法律の中にはこういったアルメンデにおける非課税の牧草地利用の程度に関しての規定が含まれていた。その他、既に述べたように、この ager compascuus という制度はこの法律によって完全に死滅させられた。測量人達の記述によって我々が知っている土地の割当てという形ではアルメンデは上述したような解釈での法的な根拠を与えられることはなかった。Ager compascuus はその結果として、注記したように、ある個々の特定の fundus においての牧草地に過ぎなくなった。その他、こうした法律は、植民市建設が共通の敵に対抗し、かつ都市を新たに建設するという特性に適合しており、牧草地はただ pascua publica ≪公共の牧草地≫という形でのみ、つまりゲマインデに従属して自由に使用出来るものとして、個人の権利[jura singulorum]については、ager compascuus でそれが可能であったように、一部は自由な牧草地の区域が植民市に対して割当てられ、また一部は――既にその前からしばしば起きていたことであるが――取り消し可能な権利としては実際には廃止されていた。ビファンク権はイタリアにおいては ager publicus によって消滅し、それが再度出現するのは辺境の属州の中の Rottland≪荒れ地や森林を新たに開墾した土地≫と荒地においてのみであった(C. Th. 1 de rei vindicatione 2, 23)。ager publicus の運命は、それが開墾出来る土地から成り立っている場合は、イタリア人のために用立てるよう定められた。最後の特筆すべきまとまった土地をカエサルが自分の軍団のヴェテラン兵に割当てた。そして subseciva ≪の占有≫については、既に詳説したように、ドミティアヌス帝がそれを完全に無効にした。それ以後は本質的にはアプリア≪現在のプーリア州、イタリア半島の踵の部分≫に向かう公共の小道が通っている牧場と 14a)、個々の[土地ゲマインシャフトの中にある]放牧地のみが ager publicus 以外の土地として留まった。しかしその時までにはイタリアでは更に別の、今やここで検討すべき所有形態が発達していた。
14a) 碑文としては例えば、C.I.L., IX 2438, 更にはウァッローの res rusticae II, 1がこのことに言及している。
その他の公有地の所有の諸形態
全てのこういった所有形態において何はさておき共通していることは、それらの土地に対する保護はただその場所[locus]に対してのみ与えられた、ということである。古い時代の占有については、次のことは実務的により大きな意味を持っていたに違いない。つまりその占有はただ法務官の権限に基づいて相続財産と認められ、何故なら遺産に対しての法的な保護はただ法務官による相続財産引き渡し命令[Interdictum Quorum Bonorum]の中でのみ成り立っていたからであり、それ故に遺産相続権の認可は法務官のさじ加減次第であったのである。私にはこれは本質的なことではないが、部族や男系氏族に従属しているフーフェの権利から自由な善意に基づく法定相続権の発生についての一つの説明になっているとは思われる。土地貴族については、法務官の布告の中で、その相続のやり方については自分達の裁量によって決定することが出来るとされていた 14b)。
14b) この手段によって相続関係の中で実際に行われた専横的な処置については、キケロの「ウェッレス弾劾演説」≪BC73年から3年間シチリアの総督であって私利を貪ったウェッレスをシチリア島民からの依頼でその当時の担当財務官であったキケロが告発したもの。≫の第1巻と比較すべきである。
個々の場合においては所有状態の法的な性質については様々な発展段階が存在していた。
戦争によって獲得した土地と公的な土地一般の民族ゲマインシャフトの側からの占有による利用以外に、時が経過するに連れ国庫の利害に基づく財政上の理由からの土地の売却が登場した。収穫物全体に対しての一定割合の貢納を条件とする占有を放任したその元々のやり方は、[国家による]この目的に適合した土地のシステマチックな売却及び賃貸しに取って替わられた。その最初のものについては以前(第1章で)取上げたが、これについては更に後述する;ここにおいて我々は賃貸しの農地、つまり ager vectigalis の様々な実際の例における本質的な傾向の観察をひとまず保留しておいて、まずはそこにおいて属州での所有状態の変動が見て取れる権利形態の探求に向かう。
ケンススを実施する場所の決定
次のことは周知のことである。つまり公的な土地を個人が利用するか農作物を栽培する目的で譲渡する、という形態において、それが幾ばくかの(ほぼ例外なく年額での)賃借料の支払いまたは収穫物(の一部)を納めるのを条件とするというのは、ケンスス(への登録)によって取り決められるものであった。この手続きについては2つのステップに分かれていた:まずは耕地の、元々そこを耕作していた農民への(ケンススの登記上の)譲渡と、次にその公有地の総面積に対しての契約によって定められた賃借料による賃貸しの開始である。ここで我々に興味深いのは、この2つのステップの最初のものだけである。公有地の賃貸しの実施は、ローマ国家によって公有地についてのケンススの登記内容(の書き換え)に基づいて行われた 15)。
15) Tabulae censoriae、プリニウス、H.N.18, 3,11。キケロ、農地法について、1,2,4。
こうした個々の土地断片の集合について、全ての個々の土地区画にそういう区分状況を書き込んだ地図の作成は、対象となる土地が恐ろしい勢いで拡大した結果、ただより大きな単位の土地に対してであっても最初から大きな障害として立ちふさがっていた 16)。
16) このことは、C.I.L., VI, 919にて言及されている。帝政期においては、例えばウェスパシアヌス帝の下で(ヒュギヌス p.122, 20)可能な範囲でまあまあ正確である略地図が作成された。
特に収穫高の多い公有地で、そこで(略地図程度では)何か不都合があることが判明した場合は、例えば地味豊かなカンパニア地方≪現在のナポリ周辺、カンパニア州≫においては、第1章で引用したリチニアヌスが示しているように、それ故、測量人はその土地の測量と地図の作成のために土地の中を歩き回ったのであり、そこで既に言及されていたことであるが、そこで使われていた測量の方法は原則的には、実際は全ての場合ではないにせよ、strigae と scamna を使ったものであった。そういった地図が作られていた場合は、その土地での賃貸しの実行は間違いなくその地図に基づいていた。法的には賃貸借関係は各年の3月15日まで継続し、それは[前年の]その日に新しいケンススの登録の適用が開始されてから1年間ということである。この[賃貸借契約の]公的な適用の開始は、モムゼンがそれについて表現しているように 17)、あたかも全ての国家による賃貸借契約の[前年の分の]解約告知としての役割を果たしていた。
17) Staatsr. II, p.347,425 の注4。
実際の所は、賃貸借契約による土地の契約者ないしはその家族による所有は、非常に規則的なこととして、もっとはるかに長い期間継続するものであった。次のことは事物の本性≪既出≫に沿っている。つまり、形の上ではもしかすると新規の賃貸借と考えられたケンススに基づく賃貸しが、実際には圧倒的に多くの場合部分的には既に存在していた賃貸借契約の改定 18)という性格を持っており、更に別の部分では小作人の土地の所有状態の整理という性格も持っていたと考えるべき、ということである。
18) モムゼンが(Staatsr. II, p.428)a.u.c.585/6年の監察官についてのリウィウスの報告(Liv. 43, 14ff)に基づいて主張しているように、既に存在している契約の改定は、その他の監察官による「授業料徴収行為」≪Tuitionsakten, 全集の注によると監察官がゲマインデに対して収入と支出の規制を行ったことをモムゼンがこう表現したもの≫の先駆けとなった。
土地の所有者達に対しての調停と大規模な賃貸料の独力での引上げは、通常の場合は監察官にとっても、丁度フランク王国の国王が一度家臣に与えたレーエン≪土地と役職の両方の意味。フランク王国ではカール大帝の頃から一度家臣に与えられたものが世襲の特権と化する傾向が強かった。≫を取り戻すことがそうであったように、どちらも同じように困難なことであった。というのは ager von Leontinoi ≪レオンティノイの土地、レオンティノイは現在のレンティーニでシチリア島東岸部のコムーネ。元々はギリシアの植民市に由来する。≫というものがあり、それはシチリアの公有地の中で最も重要な部分であったが、事実上はその土地を代々所有している小作人の家族のものとなっており 19)、そしてそのことがより明白にするのは、その全領域がわずか82人に対して賃貸しされている場合に 20)、その者達の各人についてはそれ故、監察官でも無視し得ないような財力を持っていたことを意味したに違いない、ということである。
19) キケロのウェッレス弾劾演説 3, 97、及び3, 120を参照。そこで主張されているのはウェッレス≪ガイウス・ウェッレス、C.114~43BC、シチリア総督の時代に農民から不正に富を強奪し、農民からの訴えを受けたキケロによって告発された。≫の行政上の不正行為によってレオンティノイの公有地の農民が[84人中の]52人減らされており、つまりその52人の農民はそこから追放された、ということである。”ita…, ut his ne vicarii quidem successerint” [それ故、(52人の農民が追放され)、その後を継ごうとするものも誰も居なかった]原則であったのはそれ故に所有状態をそのまま維持することであった。
20) キケロのすぐ前の引用箇所。
カンパニアの耕地はそれに対してより小規模な小作人によって所有されていたことが多かったように思われるが 21)、その小作人達の有能さをキケロが称賛している;しかしそこでもまた、公有地の小作人達はその多くが生まれてからずっと賃貸借契約をした地所にて過ごしていたのである。
21) キケロ、農地法について、2, 31, 84。
そのことはまた発展の道筋にも沿っていた。監察官の管理する賃貸借は収穫物の一定割り合いの貢納を条件とする占有と同じ位置もしくはそのすぐ隣に来るものとして登場した。それは一般的に言えばまずは国家によって整理され規制された形態の占有であり、定期的な改訂を伴うものであった。シチリアの公有地の賃貸しは特に耕地を元々の所有者 22)に返還する形式として把握され、また測量人達も占領された領土の公有地の賃貸しの形での利用について、何も所有状態の革命的な変化を思わせるような表現は使っておらず、それについて”agrum vectigalibus subjicere”[その土地を使用料付きのものに組み入れる]と表現している 23)。
22) キケロのウェッレス弾劾演説 3, 13。
23) ヒュギヌスのp.116。
それ故にこれらの処置は、採用された形式と、ひょっとするとわずかな額であったかもしれない使用料という点で見た場合、トリウスが(公有地を不法に占拠した形の)私有地を使用料支払い月の賃貸しの公有地に変えた時に、ager publicus に対する占有についての権利状況の改善とみなすことが出来るであろう 24)。
24) トリウスがつまりそういう風に変えていたら、ということである。しかし後述の箇所で、使用料の強制による権利状態の変更については更に先へ進んだ、ということが確認される。
それ故に私には、マルクヴァルトの説明である、賃貸期間がより長く設定されたことによって公有地における賃貸対象の土地について相対的に安定した性格が得られた、については全く根拠不明であるように思える。現時点でただ記憶に留めておくべきなのは、ここで扱われているのは一般的にある本当に形だけの、個々の賃貸借対象区画に対する新規の使用料設定ではなく、法律上期間が終了する契約 24a) がその規則によって単純に確認されたに違いない、ということである。
24a) 一般的にはなるほどこのことは暗黙の現状維持[relocatio tacita]≪明示的な更新手続き無しに契約が自動更新されること≫によって行われている。”Locare”[契約する]の意味はモムゼンの訳によれば「保管する」「配置する」ということであり、その含意としては、監察官が規則的に土地を、それらは「配置」され、現状のままに留められた、ということである。その他公的な業務を他人に引き継ぐということ自体に関しては厳格に取り扱われていた。(キケロ、ウェッレス弾劾演説 2,1,130)
というのは私には次のことを前提にするということを無理に想定する必要はないと思われる。つまり国家全体での個々の賃貸対象の土地について、それぞれの賃貸期間が満了した後に、競売によるような新規の授与が行われたに違いない、ということであるが 25)、そうではなくむしろ、私はそう信ずるが、決定的に様々な理由がそれと反対のことを語っている。
25) キケロによる注釈(農地法について、1.3.7と2,21,55)は授与に基づく賃貸しが引き合いに出されている。公有地におけるこういったやり方の賃貸しが例外なく等しく行われていたと考えることは出来ないということは、疑いようがない。または公有地を賃借する者はまたその土地に対して保証人や担保を差し出さねばならなかったのであろうか?監察官が公有地の賃貸しを競売のようなやり方で行い得たということは、間違いなく監察官が賃貸借契約を大規模にかつ長期間に行おうとするものと締結しようと意図した時には、そうするしかなかった、というのが非常に確からしいことである。
まずは次のようなことは事実上不可能であった。つまり土地を借りたいと思った者がその土地には住んでいない場合で、かつそのような広大な土地の複合体の全体の権利を与えられるのではない場合に、その対象の土地を実地に検分するためにそこに行ってみる価値があると考え、それを実際にやってみる、ということである。しかしながら次に:これについては後で更に述べるが、アフリカにおける国有地について、643年の土地改革法によって 26) 公有地の賃借人のためにある一定の貸借期間分として先払いとして支払う賃借料の総額が決められたということは、その場合それは該当の領域の土地についてそれが法によって規定されていた性格を変更することなく決められたが、――そのことは当時の競売による新規譲渡とどう矛盾しないように行われたのであろうか?≪競売ということは貸借料額は入札または応募によって行われその時々で異なる筈であるので、土地改革法でそれが決めらたというのは矛盾する。≫そしてまた次の事実はどう解釈すべきであろうか。つまりカンパニアの公有地では部分的に私的な占有によって元々公有地であるということが隠蔽されていて 27)、もし全ての土地区画が明らかに規則的に5年毎に新たな賃貸契約が行われていたのであれば、それは果たして矛盾なしに実行可能であったのだろうか?
26) C.I.L., I の Z.85, 86 の箇所についてのモムゼンの解釈による。
27) これまでに何度も引用したリチニアヌスの文章(前掲:p.123{原文})を参照。それ自体が意味しているのはまた:その該当の公職人が賃借しようとする農民に対して公定価格でそれを行ったということである。しかしその場合競売によって行われたのではなかったということである。
監察官による賃貸が経済上もたらした影響
しかしながら自然なこととして考えられるのは、このように(国家によって賃貸されるようになった)対象の土地領域においての所有状態の革命的な変化は、たとえそれが当面影響する範囲が特に広いものではなかったとしても、それが継続して行われる性格のものであるということは、むしろそれだけ人々が感じ取るようになったに違いない。ゲマインデ諸団体を法的に取り潰した結果、事実上時の経過に連れて古い諸ゲマインデの成員であった人々がお互いに混じり合うという結果になった。というのもキケロが次のように述べているからである。つまりレオンティノイの耕地においては、公有地の賃借人の下に、更に元々あったゲマインデ出身である家族が(土地を又借りして)暮らしていた、ということである 28)。
28) ウェッレス弾劾演説 1.3, 109
更にまたもう一つの経済的な帰結は「事物の本性」≪既出≫に沿うものであった。それはそれぞれの広大な領域の売却(賃貸)においてより好都合なことであったのであり、それは(広大な)公有地をごく小さな面積の土地に分割し、それによって多くの小規模の賃借人が入手しやすいようにし、それは監察官がローマにおいて、公有地について競売的なやり方で賃借人を募集することを真剣に試みた時に実際に行われていたことである。それ故に一般的に所有状態が時の経過の中で変わっていった限りにおいて、(分割された多数の土地をまとめて借りる)大規模な賃借人の数が増加していくという傾向が強く出てきており、それと適合していることは、キケロのウェッレス弾劾演説の中 29)シチリアのゲマインデにおいて賃借人として土地を所有している者の数がそれほど多くないと言及されていることである。
29) ウェッレス弾劾演説 1.3, 120
その他(地方総督の)個々の行政上の失策は直ちに小規模な土地所有者(賃借人)への圧迫につながったし、そしてその結果当然のこととして大規模経営者の数の増加 30) となった。
30) もちろんこの後者の現象はまた、所有する耕地がローマの公有地にはなっていなかった課税対象の諸ゲマインデ(の土地)にも関係することであった。キケロによる(前出の)申し立てによれば、ウェッレスによる統治は賃借人の減少という結果につながっていた:レオンティヌス人の土地においては84人が32人に減少し、ムーティカ人≪現代のイタリアのシチリアのモディカ≫の土地では188人が88人に、ヘルビタ人≪シチリアの中の町≫の土地では250人が120人に、そしてアジーク人≪シチリア島中央部の町≫の土地では250人が80人にまで減少していた。減少した人数の内、何パーセントが小規模経営者を犠牲にしての大規模経営者の増加によるものか、あるいは何パーセントが耕作地放棄によるものか、もちろん不明であるが、しかしキケロが深く考えないで全体の減少は後者によってであるとしているのは、正しいとは認め難い。
そしてローマの地方総督の行政において一つも失策が無かったなどということがあり得るだろうか?≪ウェッレスの例にも見られるように、共和制時代の属州の総督の地位は不正蓄財の温床となっていて、後にアウグストゥスが税の徴収を専門の官吏が行うように改めるまでそれが続いた。≫そういった類いの大規模賃借人達はもちろん次のことを強く望んでいた。それは彼らの土地所有をまた長期貸借において法的に保証してもらうことであった。こうした連関については、ヒュギヌスの次の箇所(p.116、ラハマン)において確認することが出来る(モムゼンの R. Staatsr. II. p.459 での補完に基づく):
Vectigales autem agri sunt obligati, quidam rei publicae populi Romani, quidam coloniarum aut municipiorum aut civitatium aliquarum, qui et ipsi plerique ad populum Romanum pertinent. Ex hoste capti agri postquam divisi sunt per centurias, ut adsignarentur militibus, quorum virtute capti erant, amplius quam destinatio modi quamve militum exigebat numerus qui superfuerunt agri, vectigalibus subjecti sunt, alii per annos (quinos), alii[vero mancipibus ementibus, id est conducentibus], in annos centenos pluresve: finito illo tempore iterum veneunt locanturque ita ut vectigalibus est consuetudo.
[使用料支払い義務のある土地とは、次のものに対して支払い義務がある土地で、あるものはローマの人民の共和国に、またあるものは植民市に、さらにあるものは何らかの地域コミュニティに対して支払い義務があり、中でもそういった土地自体の大部分はローマの人民に対して義務があるものである。敵国を占領して得た土地は後に、その武勇によってその土地を勝ち取った兵士に割当てるためにケントゥリアで分割され、(元々割当て用として)指定された全面積より大きいか、あるいは兵士全員に割当てた分以外の面積の土地は余った土地とされ、それらの土地に対しては誰かが使用する場合には使用料の支払い義務が課され、ある者には5年の期間で賃貸され、またある者には[間違いなく manceps に対して売却され、それはつまり{握取}契約によってという意味であるが]、100年間以上の長期間で:その期間が終了すると再び売却または賃貸契約され、それ故に使用料支払いについては慣例的なルールとなった。」
公有地における大規模賃借人
(ラテン語原文の引用で)[]内の部分はモムゼンが抹消したものである。≪握取契約は本来所有権の完全移転のためであるのに、この場合はあくまで賃貸契約で国家が持ち主であることが変わらないのが矛盾すると考えたのであろうか?≫この抹消について同意する場合、私はそれに賛成であるが、その場合は次のことも最低限読み取ることが出来ると思われる。それはつまりまた、”finito”以下の最後の文[訳文で「その期間が終了すると」で始まる文]はただ長期の方の賃貸契約についてのみ言っていると解釈した場合、2種類の賃貸契約が言及されている箇所が言っているのは、片方は法律上では5年間という短期間に制限されていて、他方は100年以上もの長期間が許されている、ということである。この長期間の方については、賃貸契約が大規模な引き受け者、つまり mancipes [manceps、(握手行為による)契約者]に、それ故に競売方式によって行われたのであり、同様に契約期間が満了した場合の再契約も最初の時と同じやり方で行われており、これ以外の場合でも公有物についての賃貸契約についてと同じであったと考えられる。以上のことは先の文章に続く数行の内容と矛盾していない:Mancipes vero, qui emerunt lege dicta jus vectigalis, ipsi per centurias locaverunt aut vendiderunt proximis quibusque possessoribus. [契約者たちは実際のところ、決められた法律によって地代の徴収の権利を獲得し、その者達はケントゥリア単位でお互いに隣接している占有者のそれぞれに、それを再度賃貸または売却した。]つまり大規模な公有地の賃借契約者達がその借りた公有地を更に二次賃借人達に譲渡し、そしてそこでまさに行われていることは、大規模賃借人達がその購入した権利(jus vectigalis)をあたかも元々それが自分達の権利であったかのように再度賃貸契約している、ということである 31)。
31) このような賃貸契約をケンススの期間である5年の期限で行ったということは、監察官の意向によるものではなく、元老院の決議によるものと思われる。しかしそれは法律ではなく、というのはそういう法律はこの場合以外に trientabula ≪既出、国の債務の1/3を土地で返すもの≫の制度の全体設計をする際に初めて本当に必要になったに違いないからであり、というのもその場合は常に債権者に対して[土地による]返済を[法律により]承認させる必要があって、官庁への土地の後からの取戻しについての承認を取り付ける必要があったのではないからである。
――その他にも賃貸契約の2種類のやり方の間で同じような対立が起きている:競売方式で5年間の期間で契約者に貸与されるやり方と、そういった短期の制限のない公有地の賃借人(「(5年を超える)長い年に及ぶ賃貸契約」[annua conductio])として貸与されるやり方と、またそれ以外にウェスタの処女≪神に使える乙女で30年間処女であり続ける必要があった≫に[その犠牲の代償として]与えられた土地についてのやり方について、ヒュギヌスが言及している(p.117, 5ff)。――公有地賃借人の実際の状況の全容は、先の箇所で一度述べようと試みたが、また彼らの権利がどう守られていたかを見た場合、私法上の権利[私権]が与えられていた、と見なすことが出来る。市民の訴訟手続きにおいてはそういった賃借契約付きの国家の土地についての占有として、その状態に対してのある種の侵害に対しての禁止命令によって保護されていた。Interdictum de loco publico fruendo [公有地の違法な使用を防止する命令]32) がどれくらい前からあったかについては不確かである;それはソキウス≪ソキエタースの成員≫という概念が法規定の中に採用されたことが示しているのと同じく、本質的にはその命令は大規模賃借人の、つまり企業家達の利益に資するために発せられたのである。≪ソキエタースは複数の人間が共同で何らかの経済行為を行う目的で結成されるものであり、それと同じく企業家のための命令であるとヴェーバーは言っている。≫
32) Quo minus loco publico, quem is, cui locandi jus fuit, fruendum alicui locavit, ei qui conduxit sociove eius e lege locationis frui liceat, vim fieri veto.[ある公有地について、その賃借権を持っている者がそれを誰かに更に貸した場合、その(新たな)契約人や共同の借主がその賃借契約に基づいてその土地を使用することを暴力によって妨げることを禁ずる。] (レネル≪Otto Lenel、1849~1938年、ドイツの法学者・法制史家》、Edikt p.368)
こうした大規模賃借人にとってそういう禁止命令は望ましいものであった。何故ならば、既に見て来たように、彼らは賃借した土地を次の二次賃借人に譲渡し、そしてそれらのそれぞれの土地も、かつその土地全体も自分で経営(耕作)しようとはしなかったからであり、それ故「賃借契約をしていること」[frui e lege locationis]が保護の対象であり、「占有していること」が対象ではなかったのであり、さらにまた契約の直近の年度における所有状態の保護は、占有状態が彼らからみて[長期間]継続したことに見られるように、その下位の賃借人の所有状態に関係なく行われねばならなかったであろうからである。 禁止令はそれ故に大規模賃借人に対しては(実質的に)時間的な制限無く保護を与えたが、その一方で(その下の)小規模賃借人に対しては占有についての禁止令はただ直近の契約年度についてだけその所有状態が保護される、としたのである。小規模賃借人にこの禁止令が等しく効力を持つものであったかどうかということは、言い回しの上ではそう解釈することも出来ようが、実際には疑わしい。もしそうでなかったとしたら、通常の小規模賃借人は公有地において市民の権利としては、既に述べたように、ただ占有状態のみが保護されたのであり、そして占有状態の保護が相続人に対して相続財産を違法な形で奪われることを防止するのに有用である限りにおいて(D.1. §44 de vi 43, 16)、相続人への事実上の財産の移行がまた保護されたのである。その他ここでもまた、公有地に対しての通常の占有の場合と同様に、Interdictum Quorum bonorum[法務官による相続財産の引き渡し命令]が関係している。こういった[公権力によって保護された]譲渡は当たり前のことであり、というのは賃借契約というものはそれ自体は単純に移転するということはなく、国家権力に対してはより不安定なものに過ぎなかったし、監察官ないしは執政官のみが別の賃借契約人を指定出来たからである。実務的には賃貸契約関係はこれまで述べた結果で行われた結果、上位の公職人は賃貸契約の相続人との再契約については、特別な場合にのみそれを拒否することが出来たのであり、それは例えば多くの相続人がその権利の継承について、誰がそれを受けるのかについて合意がなされておらず、そしてそれによって国家は誰と賃貸契約を再度締結するかについて疑いがあったような場合である。全く同様のやり方で、賃借中の土地をどのように賃借契約者から[相続人などに]譲渡するかの手続きも整備された。純粋に法律上にはそういった手続きに関する規定が存在していなかったことは、敢えて言うまでもないことである。実務上では、権利の相続人[Remplaçant、フランス語で代理人、代表者の意]33)が、一人の者に決められていた場合は、公職人はその者を賃貸契約者として認めないことはなかった。
33)キケロのウェッレス弾劾演説 3, 120 で賃貸契約の相続人に対して “vicarii” [代理の]という表現を用いている。
lex censoria censoria≪成立年不明、監察官制度が出来たのがBC5Cなので、その後とすれば共和制の中期。監察官が公共財や公有地を貸し出すことについての規定と思われる。≫がそういった相続人への賃借権の譲渡について規定していたかどうかは全く不明であるが、公職人達はこの場合についての間違いなく存在していた諸原則を遵守していた。というのもそういった状況には一般論としてローマ社会の特質を良く示しているものであるからである:ある規定すべきことについて、それに対して市民の権利に関する法文が存在していないことは、そのことが直ちに公職人が好き勝手に振る舞えたということを意味せず、行政上の様々な根本原則がそこでは目差すべき尺度として使われていたのであり、そしてモムゼンが正しく注記しているように、関係者はある規則的に発生する状況に対しては、それを悪化させるのではなく良い方向に持っていこうと努めていたのである。もしある公有地の賃借人がその土地を誰かに取られた場合、その取上げの行為が正当な権利を持っていた賃借人に対しての占有状態を否定するような侵害で無かったのであれば、その場合行政当局は新たな占有者を[新たな]賃借人としてその占有を認めることが出来たのであり、そして元の占有者からの保護の訴えを拒絶出来た。しかしいつもそうしなければならなかった訳ではなく、確かなこととしては、行政上の根本原則に従うのと同様に、行政手続きを進めるためにも、こういったケースでどちらを保護するかについての慣習法的な判定手続きが生み出されていた。
公有地においての無期限の所有状態/個人による労働力の提供を条件とする土地割当て 1. viasii vicani
我々はここまで通常の、法律上ある決まった期間に対して土地を譲渡された貸借小作人の状況について見て来た。しかしながら遅くともグラックス兄弟の頃からもう一種類の公有地が出現して来ており、それは ager publicus である一方でしかし期限の設定無しに個人に譲渡された土地であるが、それはペルニーチェ 34)≪Alfred Pernice、1841~1901年、ドイツのローマ法学者≫の表現に従えば、「留保条件付きで」割当てられた土地である。
34) Parerga≪ヴェーバーはこれをイタリック(この日本語訳では下線)にしているが人名ではなく書名、ギリシア語で「副次的な研究」、の意味≫, Zeitschrift der Saviny-Stiftung für Rechtsgeshichite Rom. Abt, V, p. 74ff。
そういった土地に分類されるものとしては、まずは viasii vicani として割当てられた土地があり、それについては知ることが出来るのはただ a.u.c. 643年の土地改革法 35) のみである。
35) Z. 11-13(モムゼンの補完に基づく、≪≪≫内はさらに全集の注による≫): (Quei ager publicus populi Romanei in terram Italiam P. Muucio L. Calpurnio cos. fuit … quod ejus IIIviri a. d. a. ≪=agris dandis adsignandis≫ viasiei)s vicaneis, quei in terra Italia sunt, dederunt adsignaverunt reliquerunt: neiquis facito quo m(i)nus ei oetantur fruantur habeant po(ssiderentque, quod ejus possessor … agrum locum aedifici)um non abalienaverit, extra eum a(grum … extra) que eum agrum, quam ex h. l. ≪=hac lege≫ venire dari reddive oportebit. — Quei ager locus aedificium ei, quem in | //AG144// (vi)asieis vicanisve ex s. c. ≪=senatus consulto≫ esse oportet oportebitve (ita datus adsignatus relictusve est eritve … quo magis is ag)er locus aedificium privatus siet, quove ma(gis censor queiquomque erit, eum agrum locum in censum referat … quove magis is ager locus aliter atque u)tei est, siet, ex h. l. n. r. ≪= hac lege nihilum rogato≫
[このイタリアにあるローマ人民の公有地について、それが Publius Mucias Scaevola と Lucius Calpurnius Piso Frugi が執政官であった年≪BC133年≫において、土地の割当て・譲渡を担当する三人委員会が、イタリアにある街道と地方道の沿線にある土地を割当てて譲渡し[その地域の住民の住居用として]残しておいた:誰もその土地を割当てられた者について、その者がその土地を使用し、そこから利益を得、それを占有し所有することを妨げることは出来ない。但しその占有者が…その土地、場所、建物を売却していない限りにおいてであり、その場合その土地やその他がこの法律の規定によって売却されたり、譲渡されたり、返還される場合を除く。――街道や地方道沿いにある土地、場所、建物が、元々元老院の決議によって譲渡され割当てられそこの住民に残されたものであった場合は…その土地、場所、建物が私有地とされるべきか、あるいは監察官が、それが誰であっても、土地と場所をケンススに登録すべきか、またそれらが現在[ケンススに]登録されているものと違っているかどうかは、この法律の関知するところではない。]
十二表法が道路の維持の責任を “amsegetes” に、つまりその道路の側に住んでいる者に課し、特徴的なこととしてまたこの命令の実施を次の規定によって確実なものにした。その規定とは、十分な道路改修を行う人手や必要資金の不足によって、その業務はその道路沿線の耕地の所有者に課され、そのことは大規模な国家の街道網が建設された結果として、直接国がそれをメンテナンスする以外のやり方でそれを行うことが必要となり、そして結局それは次のやり方で実現されたということである。つまり街道沿いの公有地を与えることの引き換え条件として、その公有地に隣接する道路の維持管理を義務付けたのである。この義務がそういう場所に位置していた地域コミュニティ[vics]の全体に課され、その義務の履行が労働の提供によってかあるいは[外部委託のための]資金の提供によったのか、あるいは地域コミュニティ全体ではなく個々の地所に対して義務が課されていたのか、それらについては何も知られていない;navicularius ≪船の持ち主に港町の土地を提供する代償としてローマに穀物を輸送する義務を負わせた制度≫の例(後述)から類推すると、考えられ得る発展の形は、まずは最初の方、つまり地域コミュニティ全体に義務が課されたというのがより確からしく思われる;もちろん法規定から発生することとして、道路改修義務が個々の土地区画の権利上のランクに影響を及ぼしており、そのことからこの負荷が個々の土地区画に課されていると容易に解釈出来るが、しかしその場合ももしかすると義務を負わされた土地所有者達が当番制で実際の作業または支払いを行っていたのかもしれない。
この viasii vicani の耕地の権利上のランクに関係するその他のこととして、土地改革法はむしろこの種の土地に逆に不利になる事項を規定しており、それはつまり viasii vcani は私有地ではないとされ、ケンススに登録出来るというメリットも提供されなかった。その他そういった土地はその権利上のランクについてただ次のように言い換えることが出来た、その土地は「そのように[特殊な用途で]利用されている」と。これらのことからはっきりと分ることは:この土地は全くもって私権に属するものではなく、土地所有においての行政法上のカテゴリーである、ということである。
こういった耕地は “ex senatus consulto” [元老院の決議に基づいて]割当てられている。その際に与えられた条件としては、この割当てに対して所有権は全く与えられず、また民会の決議によってこの割当てが別の種類の割当てによって無効とされることもあり、つまりは「当面の間での」割当てに過ぎなかった。そこで更に言及されていることは、占有者以外の市民による訴訟手続きが適用出来るかということ――それはまさに全ての耕作されている「場所」を保護していたが――についてではない、ということである。同様にローマでの取引きの形式、つまり握取行為[mancipatio]がその場合に使われたということもあり得ず、また一般的に土地の譲渡が国家当局の関与無しに行われるということが許可されていなかったのであり、それは確実に法規 36) 自体から派生していることであった。この viasii vicani による土地所有が相続の対象となることは、この制度自体の特性から考えて当然のことであった。もちろんこの手の土地所有が相続遺産分割裁判の正規の手続きにおいてどのように扱われたかについては、きわめて曖昧なままのように思える。後にまた論ずることになるが、劣位法で規定されている土地所有についての任意の分割は一般的には許可されていなかった。次のこともまた同様に許可されていなかったと考えられる。つまり正規の判決がそのような土地所有について[の争いに関して]調停する、ということである。というのは判決による調停というものは法的には所有権に対しての判決なのであり、一般的にまずはより古くからある遺言と遺贈の形式と調和せず、また市民の権利として遺言においてそういった土地について直接的に言及するということも適当ではなかったからである。
36) 前注の”…um non abalienaverit” [~が売却されていない限りにおいて]の箇所を参照。
この法律の viasii vicani について規定している箇所には、他の所有形態についての規定に出て来る文言が多く繰り返されているが、しかし遺産が遺言や譲渡によって獲得されること[hereditate testament deditone obvenit]が保護される、という文言は出て来ない。しかし相続財産獲得の許可は、それが Interdictum Quorum bonorum による保護で根拠がきちんとある限りにおいて、賃借人にとっての賃借契約の相続がそうであったように、自明のことであった。もちろん相続順位という点で、無遺言の場合と遺言有りの場合で全く差がなく扱われたということから、一般論として次のことは疑いようがない。つまり市民である遺言に基づく相続人もまた権利の承継者として財産を問題なく受け取ることが出来たということで、その理由は所有しているという状態が相続可能であるということは、法にも規定されている通り、疑いの余地がないからである。しかしながら相続人が多数いた場合には面倒なことになった。相続についての法規制は、相続人が一人でなかった場合には、誰が土地を受け取るかという決定については公権力の介入なしではほとんど不可能であったし、同様の事態はローマ法での全ての同様の関与者に係わる所有状態について繰り返されており、それはドイツ法他の全ての法において同じであった。ここにおいてはまた、行政官の自由裁量に基づいてではなく、こうした状況を取り締まる上での何らかの共通の行政上の原則が存在していてそれに従って行政処分が行われていたに違いないが、それについては何も知られていない。重要であろうと思われるのは、まず何よりも次の問いに答えることで、それは土地に付随している義務が履行されなかった場合に何が起きたのかということであり、つまり義務を強制的に果たさせるための何らかの執行がされたのか、あるいは義務を果たさない者に対してその者に委託された土地を取り上げたか、である。おそらくは両方とも行われていたのであろう 37)、というのもこの二つの直接的または間接的な強制が、最初の文献としては帝政期のものに並記されているのが見いだされるからであるが、その始まりはもっと以前から行われていた制度に遡る:navicularii
である。
37) 当該の法規は ager privatus vectigalisque の所有者に対する権利の剥奪を規定しており、そしてまた虚偽の占有または賃借料支払いの遅延に対しても同様であり、それらは明らかに次の処置からの類推として決められており、それはケンススへの未登録の場合とか、相続の結果引き継いだ何らかの支払い義務についての支払い遅延の場合(後述の箇所参照)とか、しかしそれは賃借料の支払いではない場合のもので、更には購買した者がその代金に対しての担保を提供しておらずかつ支払いが遅れている場合に、即時の現金払い[pecunia prasenti]を求めること、などからの類推である。シチリアにおいては徴税請負人は貸借農民から担保を取ったが、しかし誰に対してであれその者の所有権がどうなっているかということは全く考慮していなかった。
2. navicularii と穀物調達に関する労役
navicularii とは次のような団体のことである。それは外海に面している港のある場所に設置されており、その港に到着した穀物のローマへの輸送を実行しており、また外国からその港まで穀物を輸送する船の調達とその運航にも従事していた。そういった制度が作られた理由を確認してみたい。C.I.L., VIII, 970の碑文が示しているように、誰が制定したかは不明であるが、その内容は transvecturarius et navicularius secundo [陸上・海上輸送を推進する]というもので大体AD400年頃のもので、義務を負わされる者が順番に担当するようになっていた。しかしテオドシウス法典典≪438年に公布された東ローマ皇帝テオドシウス2世によるローマ法典≫のXIII, 6 の標題が示しているのは、[そういった義務の]執行[functio]は個々の土地区画に対して昔から[antiquitas]その土地区画の価額に応じて[secundum agri opinionem]課されており(399年の1. 81. c)、そしてその団体のための義務を果たさない場合はその土地は取上げられたということである。
その規定に並記して、Nov. Theodos. 36 は義務を遂行させるための強制執行を許可している。実行義務を果たさない場合に、その当時は移行期間ではあったが、またその者の土地を売却することも許されていた。(引用書1. 8)強制執行がどういった形で行われたかについては 38)、それはまず何よりは帝政期に初めて行われるようになったものである。――テオドシウス法典 1 の de aquaed[uctu] の 15, 2 は同様に労役を行わない者の土地を取上げることを許可している。――
38) 強制的に土地を放棄させ返却させること。
我々は第1章で次のことを確からしいとして来た。つまり土地の配分がまた別のケースとして何らかの労働提供に対して行われており、取り分け港がある町において穀物の収穫作業との関連でそれが行われている、というのを見て来たが、しかしそれについての確実な資料は不足している。帝政末期になって出て来た agri limitrophi ≪ベテラン兵士達に定期借地権の土地として与えられたもので、ライン川やドナウ川などのローマにとっての前線に位置する場所に多く配置された。≫は年間の収穫高[annona]と[賃借料が]関係付けられており、軍隊に対して食料を供給する目的で、牛馬を使った耕作を行うことを条件として与えられたものであった 39)。
39) テオドシウス法典のXI, 59の表題を参照。
3.城主の封土と辺境の封土
agri limitrophi と同じ権利形態[の土地貸与]は帝政期においては更に一般的な他の用途にも使われるようになっていた。デクリオーネスによる徴税義務に加え、大土地所有者の徴兵義務 40) ですら土地に付随した義務として扱われるようになり、そして最終的に、agri limitanei [国境に接した土地]において、また軍隊の駐屯地において、国境の防衛義務までが相続による権利継承を通じて、その封ぜられた土地区画に切っても切り離せない物的な負担として課され 41)、更には≪ガリアなどの≫蛮族の諸部族がローマの軍役に服することと引き替えに大規模な領地を封ぜられた時に 42)、そういった状況はもはやほとんど “beneficium” 43)[特権の受益者]概念の統一的な発展の開始地点に立っているようなものであるが、その概念からゲルマン民族の王達の征服した領土においての行政法的な意味での封建制度が成長して来たのである。
40) テオドシウス法典の13の de tiron[ibus][徴兵について]VII, 13, そこでは元老院所有の土地についての新兵徴兵義務が定期金の支払いによって免除されている。
41) アレクサンデル・セウェレス≪Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus、209~235年、第24代ローマ皇帝≫が国境の住民に対して土地を授与した時、”ut eorum essent, si heredes eorum militarent, nec unquam ad privatos pertinerent” (Lamprid. Alex. c. 57)[彼らの相続人が軍役に従事していたならば、それらの土地は彼らのものであり続け、決して(別の)個人の所有物にされることはない。](Aelius Lampridius による Alexander の伝記のc.57≪Historia Augusta という皇帝列伝の中の一つ≫)、プロブス≪Marcus Aurelius Probus, 232~282年、276年から282年までローマの軍人皇帝≫がイサウリア≪小アジアの南東部の地名≫のベテラン兵に土地を授与した時のもの、”ut eorum filii ab anno XVIII ad militiam mitterentur.”[彼らの息子達は18歳になると軍役に従事させられた。]更には軍の城砦に付属する土地について、参照:テオドシウス法典、1 de burgariis VII, 14と同法の2, 3 de fundis limitrophis et terris et paludibus et pascuis et limitaneis et castellorum XI, 59[国境に接する土地、領域、沼地、牧草地と城砦の土地について]。至る所で土地の譲渡が行われた場合と土地の相続において、国家当局が介入して逃れることの出来ない義務を負わせるやり方で、その行政の実施においての原則に従って、そういった土地の権利全てに本質的に関わることを定めていた。
この場合の本質的に同質な点は、まず第一に何らかの国家に関係する業務を遂行することを条件とした封土としての土地の授与というだけに留まらず、取引きにおいての所有権の移転という点でもまたそうであったし、更には当該の土地区画についての権利関係、つまりそれの私権と法的な取扱いの形態と規制についてもそうであったし、
そういった権利関係はこのような劣位の権利保持状態においては重要なものとして扱われるのであるが、ローマの行政法はこうした方向への発展の基礎を整備していたのであった。最も重要でかつ独特で新しい要素は、それはゲルマンの法概念から取り入れられたに違いなく、そしてそれは社会的・政治的な意味においてその他の部分では同レベルであったゲルマン法の発展の中で、他に卓越して優位なものとなることの基礎を作ったのであるが、それは独特の形で作り出された個人間の信義関係であり、それは当時の古代世界においては[他では]もはや復活することは出来なかったものである。≪この辺り、ギールケの言うゲノッセンシャフト的人間関係を思わせる。あるいは原始共産制から社会が発展したという発展段階説も思わせる。≫
43) “beneficium” についてテオドシウス法典がまず第一に想定しているのは次のような土地区画に対してである。それは世襲財産としてかまたは永代借地契約に基づいて貸与される土地であってかつ永代借地料を支払う必要がないものである。(テオドシウス法典 5 de coll[atione] don[atarum vel relevatarum possessionem][税の支払いを免除されたか軽減された占有地について] XI, 20の424);次に(c.6, 同じ箇所の430)全ての形式での relevatio[軽減策]、adaeratio [現金払いの代用]であり、つまり私有地においてか、より優遇された課税カテゴリーにおける国家によって保証される土地についての、土地に付随する負担の軽減策としてである。
地代支払いを条件としての無期限の土地の譲渡
我々は法律の上では期限付きの公有地の賃貸制度について概観して来て次のような公有地の割当てについて論じるまでに至った。それはある種の継続的な労役を引き受けることの引き替えとして無期限の賃貸を受けるものであった。そしてこうしたやり方についてここまで次のようなものとして詳論して来た。それはその実際の労役の内容が本質的には個人が行う種類の労役、奉仕として成立しているものである。続いて我々は再び国家所有の土地区画を金銭の支払いまたは収穫物の貢納を条件として引き受けるやり方に立ち返る。その理由は、この形の土地の授与においてもまた、権利の期限が設定されない所有状態が存在していたからである。
名目地代。Trientabula。
権利として次のケンススまで有効期限を持った通常の公有地の所有状態は、事実上多くのケースで、というより大部分のケースでと言ってよいだろうが、家族においての相続可能な所有権となった、ということは既に前述の通り詳論して来た。次に論じるべきなのは利子の支払いまたはその土地からの収穫物の一定割合の納付を条件として、つまり代々の賃借人に対して与えられる土地についてである。イタリアでは次のようなケースは全く知られていない。つまり国家からの土地の授与であって、その条件として国庫に入る永久に支払う必要がある、そして名目的なものではない地代を確実に支払うという仕組みが確立していたケースである。それとは反対に多くの事例があったのは、土地の授与が期限の設定無しに、名目地代≪実質的な土地の価値に比べて非常に低額な地代≫だけを課すことで行われていた場合である。既に先に、そのような形での土地の授与として trientabula について詳論して来た。この制度は元老院決議に基づき、そのことによって次のことが最初から当然のこととされた。それは私権が、それはローマの訴訟においては占有以外の理由として有効とされた可能性があるが、その制度においては与えられなかった、ということであり、更に同様に最初から当然のこととされたのは、民会での決議を通じて私権を毀損することなしに、一旦授与した後にその土地を取り戻すことが可能であった、ということである 44)。(Trientabulaで授与された土地の)売却が制限されていたか、ということは明らかではない。そして少なくとも事実上 ager quaestorius という形の土地の売却のやり方に torientabula のやり方が使われた(第1章参照)ということは、売却が可能であったことを裏付ける事例である 45)。
44) それ故にそういった場合は技術的にはただ「trientabula で利益を得ること」[frui in trientabula]であり、(モムゼンによる部分的な補完による)土地改革法のZ. 32においてそう呼ばれており、それ故にまた諸ゲマインデに譲渡された公有地としての一つのまとまりの中に入れられていた。
45) 先に引用した測量人の記述の箇所では、土地区画の売却について言及されている。しかしそれ故に可能であったであろうやり方は、ager quaetorius は法律上はある地域の土地の全体がまとめて譲渡されたということであり、そうでない場合は行政官の同意が必要だったということである。そのため ager quaestorius についてはまた名目地代が課されたのであろう。
次のことはしかしこのケースの独自性において全く可能なことであり、また確かなことであるのは、そういった売却制限が実際に行われていたということであり46)、そして売却制限が、グラックス兄弟による名目地代を支払うことを条件とした土地の割当てと全く同様に、そういった制限は通常の ager quaetorius においては伝えられていないが――可能ではあったろうが(参照:シクルス・フラックスの p.151, 20; 154,1)――、言葉として表現されていたに違いないのである。
46) それについて言及しているのはただ土地改革法の先に引用済みの箇所の ex testamento, hereditate, deditione
[遺産、相続、占有に基づく]獲得、の箇所のみである。”ex deditione”による獲得の部分は、モムゼンは(C. I.L., Iの土地改革法の註解にて)それを総督補佐官からのもので、また死因贈与≪ある者が死の直前に意思表示し、その者の死後贈与が行われるもの。もし死ななかった場合は取り消すことが出来た。≫と解釈しようとしている。私から見てより確からしく思われるのは、生前の包括承継[Universalsuccession inter vivos]、つまり養子縁組による財産の承継のケースが想定されている、ということである。
そうした売却の制限はあるいはここではただ通常の賃借農民においてと同じ意味を持っていて、というのもいずれの場合でも禁止令という観点からはただ行政上の権利保護が行われただけであり、それ故行政官は売却を自身の裁量で許可出来たからである。同様にそういう制限は相続に関しての規制手続きとも関係があったに違いない;遺産の包括的獲得は認められており、また遺言による獲得も同様であり、しかし遺産の分割と遺産に関する争いについての判決がその点についてどのように行われていたかは不明であり、ここにおいて行政の協力が無くても済んだ、ということは考えにくい。
グラックス兄弟による公有地割当て
グラックス兄弟による Viritan-Assignation≪既出≫においての名目地代の賦課は trientabula において売却が出来ないことと間違いなく関係があった。この2つにおいての違いはただ、グラックス兄弟による割当てにおいてはそれが民会の決議に基づいて行われたということと、それと関連して土地を取り戻すことが私権の毀損無しに可能であったかもしれない、ということである。このことが”ager privatus vectigalisque”≪私有地でありながら地代が課された土地≫という表現が意味する所であり、この形の土地こそがまさにグラックス兄弟による土地の割当ての際に適用されたのである(後述の箇所参照)。その法的な地位については、その所有状態をそれ以前に想定されていたものと区別することは出来ず、ただ手続きのためだけに、それはこのグラックス兄弟による土地割当ての時にも等しく使われたのであるが、グラックス兄弟による法規で決められた3人委員会――IIIviri agris iudicandis adsignandis ≪土地について判定し割当てる≫あるいは adtribuendis ≪割当てる≫と呼ばれたが 47) ――この種の土地に対して権限を持っていた。
47) C.I.L., I, 554-556, IX, 1024-1026の境界石上に書かれたもの、a.u.c. 624/5年。
2.実質地代。永代借地。
しかし確かに次のことは非常に特異に響くであろう。つまりある法的な形態が、地代を条件として無期限に授与された耕地の形態と同様に、ただ名目的に法的仮構≪事実とは異なるが法律上はそれがあるかのように扱うもの≫の形態として特定の目的のために、それが実際には本当の制度としては存在していないかのように仮定されて使われたのであろう、ということである。そして実際のところ先行したケースとしては、確かにほぼ確実にそれが起きたとは言えないまでも、全く低い確率でもないと思われることは、国家による永代貸与地のシステムが実際に成立していたことが推測出来るということである。
lex Thoria に基づく占有
――まず第一に挙げられるのは lex Thoria による、地代支払いを条件とする占有を通じて獲得された所有権であり、それは公有地においてこのlex Thoria (BC118年)から643 a.u.c.(BC111年)まで存在していた。そういった所有権がそれに対して地代を課されることで、その法的な地位がより良いものになった、というのは確かである 48)。
48) 先に引用した(原文p.218の注14)のアッピアヌスとキケロの文章の該当箇所を参照。
更にはこの場合の地代が単なる名目的なものであったに違いないという見解は、アッピアヌスの見解(引用済みの箇所)である。しかしそれはこの地代収入がローマ人民への無料の穀物給付の財源に使われた、というのと矛盾している。この地代の名目性という点において、収穫物の内の一定割合の物納から固定額の地代への変更が行われていたとしたら、次のケンスス実施までの期限付きの賃貸契約の決定においては占有ということはほとんど考慮されていなかったのと、またこの制度が[占有という]不安定な所有権状態を保持したままで継続するということがもはや不可能になっていたという二つの理由で、グラックス兄弟[の兄]がこの制度においての補償としてはただ占有状態の回復のみを規定しようと欲した後では、そこで規定されていたのは、lex Thoria の時代から lex agraria (a.u.c. 643年)での[公有地の不法]占有は、それらの法は占有を完全な私的所有権という観点ではその定義を変更したのであるが、もっとも確からしいのは ager privatus vectigalisque として扱うようにして、しかし名目的な地代ではなく実質的な地代を支払う義務のあるものに変えたということが起きた、ということであろう。以上のことは法の制定目的にも合致しているし、その法は一旦地代付きの私有地に変更された占有地の取り戻しを法律上不可能にしようとしたのである 49)。
49) というのもアッピアノスによれば(先に引用した箇所のI, 27)その中身は:
τῆν μέν γῆν μηκέτι διανέμειν, ἀλλ’ εἰναι τῷν ἐχόντων, καί φόρους ῷπέρ αὐτῆς τῷ δῆμῶ κατατίθεσθαι.
[その土地をもはや分配せず、それを市民のためにそのままに保持し、市民の利益になるようにする(課税する)べきである。]
より広範囲においての同様の所有状態がイタリアに存在していたことのはっきりした証拠は存在しない。というのは次のような仮定をするのは不当であるからである。つまり測量人達がイタリアにおける国有地としてしばしば言及している ager vectigales が、vectigalibus obligati agri [支払いを義務付けられた土地]という永遠に支払い義務のあるレンテン[定期支払い金]を思い起こさせるような表現にもかかわらず、法的には取り消し可能な貸借契約に基づく土地とは少し違うものと考えることである。この表現がこういった借地が事実上相続出来るものとされたことの結果であり、そのことについては先に論じた。
アフリカでの Ager privatus vectigalisque
これに対して一つの難問があり、それは次のような次のような国家の領土をどのように理解出来るかということで、その領土とは[ポエニ戦争の最終的な勝利の結果としてカルタゴが滅びローマの領土となった]属州アフリカにおいて a.u.c. 643年の土地改革法の規定によって、ローマ国家による公的な売却の形で私有の所有地へと変えられたものであり、そして同法によって agri privati vectigalesque と表現されたものである。――その法の該当部分の[不完全な現存テキストの]補完と解釈において 50)、何らかのより確実性の高いと表現してもよい前進を、次のものを越えて行うことは、それはつまりモムゼンがCorpus Insc. Lat. (Vol. I p.175 n.200)で述べていることであるが、あるいはそれ以外に追加の何かのもっともらしい仮説を立てることは、元資料の状態を考えれば私には不可能である。しかしいくつかの注記は述べておくことにする。
50) その内容はモムゼンの前述の箇所での補完に従えば以下の通りである:≪以下の日本語訳は参考程度。他のラテン語引用箇所と比べても抜けが多く、非常に意味を取りづらい。またヴェーバーによるイタリック体への変更箇所は、単語の途中でされていたりして意味不明なため、特に下線には変えていない。また原文の番号分けと日本語訳の分け方は必ずしも完全には一致していない。≫
49. esto, isque ager locus privatus vectigalisque u. … tus erit; quod eius agri locei extra terra Italia est … [socium nominisve Latini,
[(ローマの公有地である属州アフリカの土地は)それらは ager locus privatus vectigalisque として扱われる..;それらの土地と場所≪以前の議論で土地は割当てや売却の際にただ面積のみがそうされるのと、具体的な位置が割当てられることの両方があったことを参照≫がイタリアの領土外にある場合、ラテン同盟や同盟市の人々、]
50. quibus ex formula t]ogatorum milites in terra Italia inperare solent, eis po[puleis], … ve agrum locum queiquomque habebit possidebit
[また通常ローマ市民としてイタリアの領土での軍役に従事する人々に対して、…また誰であれ土地や場所を所有し、占有し、]
51. [fruetur, … eiusv]e rei procurandae causa erit, in eum agrum, locum, in[mittito … se dolo m]alo.
[それによって利益を得る者は、…またはその土地を管理するために、その土地または場所に悪意無く立ち入ることが出来るとする。]
52. Quei ager locus in Africa est, quod eius agri [… habeat pos]sideat fruaturque item, utei sei is ager locus publi[ce … IIvir, quei ex h. l. factus creatusve erit,] in biduo proxsumo,
アフリカにある土地や場所で、その土地を…誰かが所有し、占有し、またそこから利益を得るものについては、その土地や場所は公有地として扱われる…。この法律により選出された2人の者(担当官)は、選出されてから2日以内に、
53. quo factus creatusve erit, edici[to … in diebus] XXV proxsumeis, quibus id edictum erit [… datu]m adsignatum siet, idque quom
[公告を出し、そしてその公告が出されてから25日以内に、その土地が与えられ割当てられるようにすること、]
54. profitebitur cognito[res … ] mum emptor siet ab eo quoius homin[is privatei eius agri venditio fuerit, … L.] Calpurni(o) cos.
[(その割当てられた土地を割当てられた者から買った者の)代理人がその土地をケンススに登録する申告を行う時に、その土地の売却が私有地として行われていた場合は、その代理人が売却した者から(元々 ager privatus vectigalesque として割当てられた)その土地の購入者であることを確認してもらうことになる, …ルキウス・カルプルニウスが執政官であった年に]
55. facta siet, quod eius postea neque ipse n[eque …] praefectus milesve in provinciam er[it … colono eive, quei in coonei nu]mero
[行われたことのうち、その後に彼自身も…その代理官や兵士も属州において…(その土地が)植民者や植民者名簿に]
56. scriptus est, datus adsignatus est, quodve eius … ag … [u]tei curator eius profiteatur, item ute[i … ex e]o edicto, utei is, quei
[記載されている者に割り当てられたものである場合は、またはその土地についてその土地の管理人が申告するようにし、同様に…その公告に基づいて]
57. ab bonorum emptore magistro curato[reve emerit, … Sei quem quid edicto IIvirei ex h. l. profiteri oportuer]it, quod edicto IIvir(ei) professus ex h. l. n[on erit, … ei eum agrum lo]cum neive emp-
[またはその土地をその土地の売却管理人か売却責任者から購入した者が、…そしてもしこの法律を基いて出された2人の担当官の公告に従って何かを申告する義務のある者が申告を行わなかった場合は、その者に対してその土地や場所が]
58. tum neive adsignatum esse neive fuise iudicato. Q … do, ei ceivi Romano tantundem modu[m agri loci . . .] quei ager publice non venieit, dare reddere commutareve liceto.
[購入されたものでも、割当てられたものでもなかった、あるいは存在していなかったと判断されるものとする。Q…がそのローマ市民に対して、同じ面積の土地または場所を与えるものとする…その公有地が売却されていなかった場合には、その者はその土地を譲渡、返却、または交換することが認められる。]
59. IIvir, q[uei ex h. 1. factus creatusve erit … de] eis agreis ita rationem inito, itaque h…. et, neive unius hominis nomine, quoi ex lege Rubria quae fuit colono eive, quei [in colonei numero
[この法律により任命され選出された2人の担当官は、これらの土地について次のように会計上の処理を行い、…ただ一人の名前だけでそういった処理を行うことは出来ず、その者がルブリア法≪南ガリアに作られた植民市についての法≫に基づいて、植民者や植民者として登録された者に対して]
60. scriptus est, agrum, quei in Africa est, dare oportuit licuitve … data adsign]ata fuise iudicato; neive unius hominus [nomine, quoi … colono eive, quei in colonei nu]mero scriptus est, agrum quei in Africa est, dare oportuit licuitve, amplius iug(era) CC in [singulos
[アフリカにある土地を与えることが必要とされたり許可されたりすることがないようにするものとする…与えられ割当てられたと判断されるべきである;どのような一個人の名義においても、ルブリア法に基づき植民者とされたかあるいは植民者として登録された者に対してアフリカにある土地を割当てる必要があった場合でも、その個人に対して割当てられる土地は200ユゲラを超えないものとし、]
61. homines data adsignata esse fuiseve iudicato … neive maiorem numerum in Africa hominum in coloniam coloniasve deductum esse fu]iseve iudicato quam quantum numer[um ex lege Rubria quae fuit . . . a IIIviris coloniae dedu]cendae in Africa hominum in coloniam coloniasve deduci oportuit licuitve.
[(もし超えていた場合には)その土地がその者に割当てられているかあるいは割当てられていたと判断してはなならない。アフリカに入植した人の数が、過去に存在したルブリア法に基づいてアフリカに入植するために…植民市の三人委員会によって入植許可が与えられた人数よりも多い、または多かったと判断されるべきではない。]
62. Iivir, quei [ex h. 1. factus ereatusve erit …] re Rom … agri [… d]atus ad[signatus … quod eiu]s agri ex h. l. adioudicari
[この法律によって選ばれ任命された2人の担当官は、ローマ国家の権限で…その土地の授与または割当てについて…その土地が追加で与えられることが]
63. licebit, quod ita comperietur, id ei heredeive eius adsignatum esse iudicato [… quod quand]oque eius agri locei ante kal. I [… quoiei emptum] est ab eo, quoius eius agri locei hominus privati venditio
[許可されるならば、その土地がその者またはその者の相続人に割当てられたと判定すべきである…そしてその土地や場所が1月1日よりも前の時点で、その土地や場所の元々の私有地を売却した者から購入した者の所有となっていること、]
64. fuit tum, quom is eum agrum locum emit, quei [… et eum agrum locum, quem ita emit emer]it, planum faciet feceritve emptum esse, q[uem agrum locum neque ipse] neque heres eius, neque quoi is heres erit abalienaverit, quod eius agri locei ita planum factum
[ならびにその者がその土地や場所を購入した場合に、その土地または場所が存在していたならば、その土地についての測量図を作成するか、または既に作成していて、その購入の事実を明確にするであろう。その土地または場所は、彼自身も彼の相続人も、また彼の相続人となる者も譲渡しておらず、そしてその土地または場所についての測量図が作られている場合は、]
65. erit, IIvir ita [… dato re]ddito, quod is emptum habuerit quod eius publice non veniei[t. Item IIvir sei is] ager locus, quei ei emptus fuerit, publice venieit, tantundem modum agri locei de eo agro loco, quei ager lo[cus in Africa est, quei publice non venieit,
[2人の担当官が、その土地をその者に与え返還することとする…更に2人の担当官はその者が購買したことになっているが公的にはその者に売却されていないことになっている土地や場所について、その土地や場所が公的に別の者に売却済みの場合は、その者に対してその土地や場所と同じ面積のアフリカにある場所か土地で公的に未売却のものを、改めて割当てそれらをその者に戻すこととする。]
66. ei quei ita emptum habuerit, dato reddito … Queique ager locus ita ex h. l. datus redditus erit, ei, quoius ex h. l. f]actus erit, HS n(ummo) I emptus esto, isque ager locus privatus vectigalisque ita, [utei in h. l. supra] scriptum est, esto.
[この法律でによってそのように割当てられたか返還された土地や場所が、この法律に基づいて、それらを与えられた者達に、一単位≪おそらく200ユゲラ≫あたり1,000セステルティウス≪ローマの銀貨、奴隷一人が約6,000セステルティウスぐらい≫で売却され、そういった土地や場所はこの法律に書かれているように ager locus privatus vectigalisque とされる。]
先に言及した同法の規定によって通常の公有地賃借人のアフリカにおける賃借地の購入金額は、それぞれの土地での lex censoria に定められて決まっていた。それによって当時の公有地においての財の所有者は、その所有を事実上相続可能な財産とすることが出来、ただその所有状態に関していつでも取り消し可能という純粋に法的な不安定さがそれを他の所有状態から区別するものとなっていた。こういった不安定さが無いということと、無期限の所有割当てが、今や明らかに ager privatus vectigalisque の所有者を他の一般的な公有地賃借人から区別するものとなっている。
ager privatus vectigalisque における賃借料の性質
この ager privatus vectigalisque という土地については、法が明確に規定しているように、疑いなく資本払い込みに対しての土地授与という点が肝要である。このことからまた、こういった形での土地の授与は、我々が先に ager quaestorius の特徴として見出したこととまさに同じなのであり、そしてモムゼンも2つを同種のものとして総括している。しかし私にはこの ager privatus vectigalisque をその意味で理解することが出来るかどうかについては、全く確実とは思っておらず、そしてそのことは次の疑問と関係している。それはここでの賃借料が単に名目的なものだったのか、あるいはその額がごくわずかであったとしても実際に支払うものだったのか、という疑問で、それは検討してみるべきである。ager quaestorius が一般的に賃借料を条件とされていたのであれば――そのことによってその制度においては何も無条件には引き渡されてはおらず――、そのためその制度はある名目的なものと特徴付けることが出来、それは torientabula の場合においてモムゼンが確からしいと認めていることであるのと同じであるが、このことはまたアフリカでの ager privatus vectigalisque においても同じだったのである。ともかくも通常の ager quaestorius はそれ以外の点においては決して ager privatus vectigalisque と呼ばれることはなかったし、モムゼンもまたアフリカにおいて購入された土地について次のことまでは主張していない。つまりそれが一旦売却したものを将来再度買い戻す前提での担保という性格を持っていた、ということである。この名称は、前半部の”privatus”は一旦割り当てられた土地が取り消されることがないということを意味し、後半部の”vectigalis”は何らかの公租公課の負担義務があることを意味しているが、しかしこの2つをくっつけた場合には、それは不適切な(矛盾する)名称となってしまっているのでないだろうか。しかし特記すべきなのは、そういった所有状態で ager quaestorius が実質的にその中身と同じものを新たに作り出すにあたって、立法は必要とされず、ただ元老院決議にだけ基づいていた、ということである;法律はただ割当ての取り消しが出来ない、ということを定めたに留まっており、更にはローマの人民にとっての nudum jus Quiritium ≪ただローマ法上の虚構的な理論として存在していて実質的には存在しないクイリーテース所有権≫に留まっていて、その結果必然的なこととして、グラックス兄弟による土地割当ての際と、Lex Thoriaの時においてでは、ager privatus vectigalisque という表現の意味するところは変化していた。しかしながら次のことは確かに可能である。つまりモムゼンの仮説である、この制度における vectigal の性質としては、単なる仮課税と見なし得る、ということであるが、――グラックス兄弟においての土地割当てのやり方はアフリカに対して植民を進めるようなものと言え、そこで行われたのは、法においての資本家的な精神に沿っていて、土地が貧困者に割当てられたのではなく、富裕者に割当てられた、ということである。私は次のことを可能であると考え否定するものではない。それは、私にとっては主観的には以下のことが確からしいと考えられるということで、つまりは既に述べたことではあるが、賃借する土地の授与においてはまず次のやり方が先行したということで、そのやり方とは、ある契約者が個々の土地区画ではなく複数の土地のまとまりを長期間である確定した賃借料という形で競り落とした、ということである。次のことについては不確かなままである。つまり土地の競売において一対何に対して参加者は価格を提示したのか、ということである。我々は≪ヴェーバー当時の≫現代の競売についての知識から次のように考えがちである:賃借料の金額がそれであると 50a)。
50a) ヘラクレイア≪現代のトルコのマルマラ海の北岸の都市≫においての寺院領が競売された場合はそうであった。参照:カイベル≪Georg Kaibel、1849~1901年、ドイツの文献学者で古代ギリシアの金石文の専門家≫のギリシア碑文集の中の彼の担当部の Tabula Helacleensis に対しての注記。イタリアでの同様の例は同じ書の No. 645 を参照。碑文についてはしかしそれ以外で我々にとって重要な情報を提供してくれていない。競売対象を個別化して分けるということが同様に先に引用したエドフ神殿≪ナイル川西岸に位置するエドフの町にある古代エジプトの神殿 ≫の碑文において認めることが出来る。土地区画は大半が長方形で通路によってお互いに分離されていた。カイベルの書のP. 172、173の図を見よ。
しかしながら、こういったやり方はローマでの慣習的なやり方とほとんど合致していなかったように思われる。後にはもちとん、ヒュギナス(原文の P. 204)の印刷本の P. 121 にあるように、個別の、区画分けされた土地が、その面積と肥沃さに応じた地代を課されており、つまり個々人毎に異なっていた 50b)。
50b) 更に詳しい例は後述箇所を見よ。
しかし当時更にまた、ユゲラ[面積]あたりの地代も規定されており、こちらの起源は間違いなくより古いものであった。同様に土地の購入にあたってユゲラあたりの価格で取り決めて行ったように、賃貸借でも同じやり方が用いられた。それ故に、また trientabula においても、名目地代は1ユゲラあたり1セステルティウスとされ、引渡される土地区画全体でいくら、という決め方ではなく、しかしその一方でその他の場合として、引渡される土地の価格がその土地の実勢価格に基づいて査定され、その時々の購入価額で担保に供されたということもあった。そのため、先に言及したルキウス・カエキリウス・メテッルス・デルマティクス ≪Lucius Caecilius Metellus Delmaticus、BC119年の執政官≫とグナエウス・ドミティウス・アヘノバルブス≪Gnaeus Domitius Ahenobarbus、BC122年の執政官≫の[2人が執政官であった]時に制定された lex censoria 50c) がアフリカにおいての賃貸耕地からの賃貸収益について規定しているのであれば、これは収穫物の一定割合か――法規は1/10税について言及しているが――あるいは固定額の(相対的にはより少額の)金銭地代であったかどちらかであり、その金銭地代は少なくとも地域毎に統一され、そしてあるいはまた二三の土地価額のクラスで分けられて、同じクラスであれば1ユゲラあたり同一価格で(その時は)あったか 51)、あるいは継続してそうであった可能性があり、というのはその公有地全体の全ての賃借耕地に対してそれぞれ個別に金額を提示するということまでは、そういった lex censoria の規定には含まれていなかった可能性があるからである。
50c) a.u.c. 693年(BC115年)
51) たとえばパンノニアにおいての耕地への貸借料設定は何段階かのクラスに分けられていた。
それ故にまた、より大きな面積でのまとまった土地を契約者が引き受けた場合には、貸借期間は100年とされ、ユゲラあたりのより低い固定額での地代が課され、競売において入札するものとしてはただ全体の購入価格のみ、とされたのである。そういった購入価額は、ただ保証人によってかあるいは所有資産(の証明)によって保証されたのであり、100年で満期となる毎年の賃借料の総額の支払いが必要だったのではない。このことによってさらに明らかになるのは、こうした公有地の賃借人は[通常の毎年の]賃借料を支払う小作人のように扱われたということであり(上述箇所参照)、同様にこの種の賃貸しの手続きは、”vectigalibus subjicere”[賃借料を条件とした]という表現と矛盾していない。このことが正しいと認められるなら、私の考える所では、次のことはかなりの程度確からしくなる。それは ager privatus vectigalisque についても手続きは同様のものであった、ということである 51a)。
51a) 法はおそらくZ.52 の:”(habeat pos)sideat fruaturque item, utei sei is ager loucs publi(ce a censoribus mancipi locatus esset ?”[その土地や場所を所有し、占有し、かつそこから利益を得ることが出来、それはまるでその土地や場所が監察官によって購入者に公的に貸借されているかのようである。]の所で暗に賃貸し耕地の競売による授与のことを述べていた。
いずれにせよ私見では、モムゼンがこの法において実質的な地代が定められていたという可能性を疑っていることは、意味をなさなくなるであろう。次に考えられるのは、法は現在失われている箇所(特にZ.51、52の欠落部)52) において、いずれにせよ相当な額のユゲラまたはケントゥリアあたりの地代を、おそらくはその際に初めて課していて、その結果として永代賃借料を引き上げた形になった、ということである 53)。
52) 確かに次のことは疑わしい。それは引用文献中の証拠の箇所として、その碑文中の欠落部分を使うことである。しかしそれにもかかわらず、この場合には次のことは確かである。つまりこの法がこの制度とそれに伴う該当する耕地についての、地代納入義務の規定を含んでいるということである。というのはこの規定について Z. 66 において参照されているからである。
53) 次のことがもし明らかになるのであれば、この地代の額についてもう少しはっきりしたことが分かるであろう。それは競売されている耕地を購入しようとする者が、この法の Z. 53 以下に従って何を公的に申告しないといけないか、ということである。私が信じたいのは、後のパンノニアにおける占有と同様に、その際の申告内容としてヒュギナスが p. 121 で言及しているが(更に後で引用する箇所を参照)、それはその耕地、牧草地、森、牧場の面積――あるいはまた同様のカテゴリーの――であるが、そしてその面積を購買者は所有することになったのであるが、その面積[とカテゴリー]に従って地代が課されたのである;というのも私がこの論文で統一的な地代の存在を確からしいものとして述べた際には、こうした原始的な諸カテゴリー、それらについては後で扱うことになるが、による地代の差異の可能性を決して排除していないからである。確からしいのは、土地購入についての公的な申告は、本質的にはこの目的[購入した土地のカテゴリーをはっきりさせて地代の額を決める]のためであったろう、ということである。その他のことについてこの法が規定しているのは、全体の処置においてまた、それどころかひょっとしたら主要目的として、所有者のことを規定しているのであり、その所有者達はこの法の発布の前から既に「購買」によって[本来は公有地である]土地を獲得していたのである。先に記述した貸借対象耕地の契約者についての注釈≪国家が土地斡旋によって資本家を作り出そうとしていたこと≫が正しかったとすれば、ここで扱われているのは、次の者達(注51a参照)に対して、その者達はアフリカの公有地における耕地を永代賃借料を支払う条件で貸借したのであるが、その者達自身に対してまた、取り消し不能な有限の所有状態が保証された、ということであり、そしてこのことがもし正しければ、その場合はここにおいてこの立法の前代未聞な資本家支援的な傾向が剥き出しの姿で登場してきているのである:なるほど立法家は公有地の大規模な土地所有者に対して直ちに地代を免除することは、イタリアでの例のように、躊躇していたが、しかし立法家は lex Thoria によって彼らに対してイタリアにおいての[大規模]占有者の地位を認めたのである。これに対して、次のような公有地の所有者、つまりその者の土地が監察官によって与えられることが多かった者[a censoribus locari solet]、つまり小規模の賃借人のことであるが、そしてそれは古くからのその土地の住民またはイタリア人であったが、その者達に立法家は保証(前述箇所を見よ)を与えこそしたものの、かつその者達はそれまでのような額の賃借料を支払う必要はなくなったものの、その代わりその所有状態は法的には不安定なものに留まった。――
もしハラエサ≪シチリア島北部のギリシア人による植民都市≫の碑文に――カイベル、ギリシア碑文集、シチリアとイタリア、Nr. 352――事実上、カイベルがそう想定しているように、作り出された土地区画についての地代に関する記載が含まれているのであれば、そのことは自然に考えればただ名目的に設定された一般的な価格であった可能性がある。その他、この碑文での κλᾶροι と δαίθμοι の制度については≪全集の注によれば、前者[クラーロイ]は単に(籤で)割当てられた土地の一単位、後者[ダイスモイ]はその内で賃借人に割当てられた区画のこと≫ここでの土地の位置決めは本質的には元々の所有者達の間での配置換えだったのであり、そこには[競売という]競争が入り込む余地は全く無かった。有名なアクラエ≪シチリア島南部のギリシア植民都市≫の碑文(カイベル、前掲書、Nr. 217)については作り出された土地の所有状態がどのような種類のものであったかについては不明であり(参照:ゲットリング≪Karl Wilhelm Göttling、1793~1869年、ドイツの言語・古典学者≫のアクラエ碑文、そしてデーゲンコルプ≪Karl Heinrich Degenkolb、1932~1909年、ドイツの法学者≫の先に引用した lex Hieronica に関する論文)我々にとってはそれらの情報は意味が無い。
永代賃借料は次の場合には当然のことながら課されなかった。それは同じ土地授与対象物全体を様々な購買者に何度も売却した結果として、ある者が購入済みで(既に代金も支払った)土地[が誰か別の者に与えられてしまった場合]の換わりに、別の土地が改めて授与された場合である:それがこの法の Z. 66 においての購買者に1セステルティウス[の形だけの代金]を支払わせた、ということの意味である。
測量地図
これらの耕地の測量はケントゥリア単位で行われており、それは完全な所有権を入手出来る土地割当ての場合のケントゥリアと区別されていなかったように思える(Z. 66)、故にその面積は200ユゲラであり ager quaestorius の場合のようにただ50ユゲラだけではなかった。土地の授与は取り消せない性質のものであり、それは “privatus”という表現が示す通りである。ager vectigalis としての性質は次のような結果を生んだに違いない。つまり土地の授与は握取行為の形式では行われなかったし、そういった土地の相続に関しての規制においては、それが国家当局の干渉無しに行われることもなかった、ということである 54)。
54) このことは、Z. 62、64の相続人に関する規定で言及されているようなやり方で法規中に出現している。このことが意味したことは単純に、属州の知事は次のことを行いうる立場にあったということであり、それはその者が土地の授与を許可したり、また誰にその土地を相続させるかについて原則を作り、それを布告する、ということである。というのはその者は行政担当官であるのと同時に裁判官でもあったからである。ager quaestorius と更に違うことは、ここでは limites viae publicae [公共の道路による境界線]であり、何故ならばZ. 89 とそれに続く部分でそのような補足を加えている規定は、[元の]カルタゴの領土だけでなく全てのケントゥリアに対して適用されていたからである。というのも賃借料は――我々の仮定では――ユゲラあたりで等しかったので、このことは課税可能な対象物を個々の購買者それぞれに十分に行き渡るまで分割することを可能にし、個々の購買者から単純にどの位の税が取れるか、その者が1ケントゥリアの中で何ユゲラを所有しているのか、それから1ケントゥリアあたりで[分割して]割当てた土地の合計が200ユゲラであることの確認、などについての管理を非常に楽にした。属州アフリカにおける土地の分割と土地制度全体の安定した状態は、あり得ないくらい長期に渡って変更されることなく維持されていたように見え、つまりは皇帝ホノリウス≪在位393~423年の西ローマ皇帝≫の時代まで続いたのであった。その当時(422年)に実施された改定が及んだのはテオドシウス法典の13の de indulgentis debitorum [借金返済の猶予について]によれば:アフリカ総督の管轄下:課税対象地として9002ケントゥリアと141ユゲラ、荒れ地として5700ケントゥリアと144 1/2ユゲラ、ビサンチンにおいて:課税対象地として7460ケントゥリアと169ユゲラ、荒れ地として7715ケントゥリアと3 1/2 ユゲラであり、合計でアフリカ総督管轄下で:16703ケントゥリア≪計算上は14703≫と85 1/2 ユゲラ、ビサンチンでは:15175ケントゥリア≪計算上は15075≫と172 1/2 ユゲラが課税対象領域において測量済みの土地面積である。
以上の記述からはまだその当時でも税の計算上は[ほぼ]1ケントゥリア=1ケントゥリア、つまり1ユゲラ=1ユゲラとして計算されていた、という印象を受ける。≪おそらくは実面積に何かの係数をかけて補正した形での面積を使って税が計算されてはいなかった、ということであろう。≫このようにして税額が決められ課税された全体の領域の面積は、ほぼ≪ヴェーバー当時の≫東プロイセン州の(例えばポーゼン≪現在のポーランドのポズナン≫の鋤で耕された耕地の大きさと同じであり、当時の制度に従ったやり方として、ただアフリカの耕された土地の大半について一部のみが、そうではあってもまたかなりの大きさのものではあるが、ここでは描写されている可能性がある。その他の部分の土地についての記述は後述の箇所で扱う。ここで述べられていることの全ては、私には何よりも次のことについて語っているように見える。つまりここで言及されている耕地に対しては、実質的な賃借料が課されていた、ということである。同様に次のことも述べている。つまりここでは境界線がまた道路として直線のまま保たれていた、ということである:そのことは既に注記したように、課税の管理を楽にしていた≪中世のドイツの農地では牛が鋤を牽いて蛇行して耕す結果として境界線が波状になっている土地が多かった。≫;これに対して通常の ager quaestorius においては、境界線は同じようにその土地の範囲を確定させるために厳格に管理されるべきであったが、しかし確からしいことと思われるのは、実質的な地代がそこでは課されなかったがために、その境界線を直線のまま保つことに対しての利害関心が全く生まれていなかったことになり、結果としては直線性は失われてしまったのである。同様に次のこともまた何より不可思議なことであろう。それは国家によって永代賃借人として認められた者で、全くその永代賃借料を支払わない者が存在していたに違いない、と仮定することである――というのは永代賃借人というのは法律が規定するところの ager privatus vetigalisque の占有者であったろうからであり、もしこの土地の法的な性質を市民の権利としての売却可能性が与えられない形の永代貸借と仮定する場合は、賃借料がただ名目的なものかどうかという検討は無意味になるからである 55)。
55) 先の箇所(第1章)でもここでも次のことが確からしいと想定される。それは通常の ager quaestorius は「事実上は」売却において制限が加えられていなかった、ということである。このことについての本質をより明らかにする必要がある。法的には ager quaestorius は ager publicus におけるある所有状態であり、他の全ての所有状態と同じく「所有し、占有し、使用し、そこから利益を得ること」が許されているが、握取行為による売却や占有状態以外に関する物権的な訴訟は許されていなかったのであり、そして行政上の保護下にだけ置かれるのみであり、その≪譲渡・売却の≫承認についてはおそらくは執政官の管轄だったのであろう(Liv. 31, 13によれば trientabula の土地の授与の承認も執政官が行っていたからである)。というのも国家にとってその土地が誰の所有物になるのかということへの利害関心は、trientabula の場合においてすら存在していなかったのであり、そのためそういった行政上の保護は一般に次のような者に与えられたのである。その者とはその場所を正規の書面以外を根拠として――つまりそれ以外の正当と見なされる理由に基づく引き渡しによって――やはりその前の不当にその土地を得たのではない所有者から獲得したそういう者である。しかしこのことがただ不安定な状態であるとのみ見なすのは困難であり、それは測量人達が ager quaestorius においての emtio venditio [獲得と引き渡し、売却]の形での売却を、規則的に行われているものとして言及していることからも分かる。ヒュギヌスが次のように注記している場合には:non tamen universas paruisse legibus quas a venditoribus suis acceperant [それにもかかわらず彼らの全員が売却者から受け取った土地について必ずしも法の定めるところに従っていた訳ではなかった]、その場合には≪正式な購買にいよる土地のケンススへの登録ではなく≫何かの土地の利用についての届出や何か類似のことが行われていた、と理解出来よう。――そういう意味で ager quaestorius の「売却可能性」は理解することが出来、またそう確認されなければならない。しかしこうした制限付きであっても、私には売却が実際に行われていたことについては疑いようがない。何故ならば ager queaestorius の譲渡不可という原則に固執することは、そこに貸借料が課されていないのであれば、それに対して≪国家の≫実際的な利害関心が存在したということはほとんど信じ難いからである。しかながらもちろん、こういった ager queaestorius の ager privatus vectigalisque との差異は法学原理から作り出されたものではなく、ただ実務的なものとして徐々に形成されたものである――注56a)を参照。
永代貸借権について後の売却可能性
永代貸借権の法律上の売却不可、という特徴がそもそも本当に行われていたのか、あるいは行われていた場合にはどのくらいの期間に渡ってそうであったのかについては、確かなことは分かっていないが、後の時代にはそういう禁止は無くなっており、というのは帝政期の法資料の中でそれについての記載が見られないからであり、そしてコンスタンティヌス大帝の下で売却の許可が確立したように見える。私見ではテオドシウス法典のある解釈に基づくテキストの p.186 ≪全集の注によれば正しくは p.97≫がこのことを規定しており、その部分からまた同時に分かることは、賃貸料支払いの義務のある土地区画の握取行為による譲渡はその時までは許可されていなかった、ということである。何故ならば ager queaestorius の土地の売却について課税上の利害関心を扱っている箇所については、それ以外では scamna 56) の売却については特別に詳しく規定する必要性を感じていなかったように思われるからである。
56) ここでは scamna =地代の支払い義務のある土地区画、の意味で使われており、それはケンススとの関連を示しているのであり、ケンススという語がこの規定が含まれている章のタイトルに含まれている。ここでは2つの種類の土地区画が扱われている:一つは握取行為によって譲渡可能なものであり、市民への課税を決定する国家のケンススに登録されるものであり、もう一つは個別の土地で、その土地の使用に対して税≪貸借料≫が課されるものである。しかし売却に関しての二つの実質的な違いは:前者の土地については所有権が握取行為によってケンスス上の登記を変更するという形で移転し、引き渡しについてはただ所有権移転の実施だけが行われ、それはつまりある通知で、その通知の内容としては握取行為に該当する面積の土地が、今や購入者の自由な処分に供される、ということである;こういった”vacuae possessionis traditio”[実質を伴わない形式的な所有状態の引き渡し]は、根本的には訴訟に備えたものではなく、それによって所有状態の保護を得るという意味だけを持っていた。それに対して scamna、つまり握取行為による譲渡が出来ない土地の場合は、引き渡しはただ所有権移転の具体的な行為だけであり、つまり前述した emtio venditio[購入-引渡し-売却]であって売却代金についての債務から発生する行為であった。法のこの部分が次に規定しているのは、既に前述の箇所(第2章)で詳しく論じたが、今後は握取行為によって売却しようとする土地の面積の、売却に先立つ測量または境界線に関しての通知を行うことを義務付けていることで、そしてこの規定によって握取行為が本来持っていた古くからの性質である、ただ割当てられた面積のみの売却、という性質を取り除いたのである。scamna の場合にはこういった視点に基づく規定は見られないが、というのは同意に基づく emtio[購入と引き渡し]は何らの所有権の移転を含んでいなかったからであるが、しかし同一の原則が――間違いなくコンスタンティヌス大帝によって――ここでも適用されるべきとされたのである。
推測されること、あるいはむしろ確かであるとさえ言っても良いことは、後の時代の同意に基づく emtio venditio と最終引渡しという流れによる売却の通常の形式は、場所の獲得の形式として一般的なものになっており、≪クイリーテース所有権≫より劣位の権利を持った所有状態について全体において唯一の売却形式だったのであり、その権利についての一般的な売却可能性は行政当局の裁量に基づくものとなっていた、ということである。。
その当時の人々は次のような内容を規定として定めていたに違いない。つまり「売却対象からの除外」というのはこの場合単純に次のことと同じ意味なのであり、それは握取行為からの除外であり、正規の訴訟手続において物権として正規の所有権が認められていない土地に対して保護が与えられない、ということであり、つまりは売却に対しての「法」規範の欠如を意味するのであり、そのためにこの売却が行政当局の実務で扱われるものである、ということは、それをどういった前提条件から導くべきなのか、あるいはそもそもそういう前提条件が存在するのか、という問題であった。「法的な」意味での売却性が認められるようになるのは次の時点からである。それは行政での実務上の原則が法としてきちんと確立する時点であり、そういった諸々の状況がもしかすると ager quaestorius の状況だったのであろう 56a)。
56a) モムゼン(C. I. L. Iの土地改革法の箇所)は、ager privatus vectigalisque の売却性をZ. 54. 63 においての表現から結論付けている:”cujus ejus agri hominis privati venditio fuerit”[その土地が私有のものであってそれが売却されていた場合]。私はこの表現はむしろ次のことを意味しているのではないかと考える。つまりこの法が売却に関しての何かの「特別な」意味を示しているということで、――もしかすると後の時代の Emphyteusis ≪土地の長期または永久貸借≫に似たようなもの――を意味していたのではないかと。この法がまたこの形式の耕地に対する権利の有効化について別に何らかの原則を定めていたかどうかは不明である。Z.93 での”in ious adire”[法的権利を主張する]という表現はおそらくはまさしくこのすぐ前の箇所にて言及した”ager ex senatus consulto datus assignatus”[元老院決議に基づく土地割当て]に関しての表現と思われる。この表現が具体的な耕地との関連で意味することを、モムゼンは引用済みの箇所でそれを公有地占有の形の土地についての表現と見なしている。この ex senatus consulto による土地に関する記述は、viasii vicani が出て来る箇所よりも先であるので、私は次の考え方はそう間違っていないと思う。つまりこの表現は先に既に述べた navicularii の耕地について言っているのではないか、ということである。この法にてこの部分に続く箇所では、ひょっとすると後の時代ではしばしば皇帝の命令によって出された業務である、非常に負担の重い農作物の輸送義務について述べているのかもしれない。
地税の中での vectigal の変遷
法律上の売却性という点について、地税の一種という分類においての vectigal の永代貸借料に関する規範という性格は変動していた。もちろんこの売却性というのはアフリカにおいての所有者達においては、もし私が先に述べた見解が正しいなら≪執政官 Ahenobarbus の時の lex censoria がアフリカでの賃借耕地からの収益に関して規定しているという見解≫、次のような我々が慣れ親しんでいる課税方法とは異なっている性格も持っており、つまり≪我々が親しんでいるように≫土地区画あたりの収穫高に応じて土地に課税上の等級を設定するのではなく、その土地の合計面積、つまり総ユゲラ数に応じて、均等にかあるいは耕地、牧草地、森林などについてそれぞれに大まかな税率が設定されて課税されていた。ここにおいてようやく公有地の価額の査定においての綿密に検討された行政上の技術が登場して来ているのであるが、それは単に定量的なもので根本原則的なものではなかった。もしかすると既にカンパーニャ地方の土地において――正確なものではなかったにせよともかくも推進された――譲渡金額についての査定と個々の区画に対しての決定についての何らかの手続きが行われていたのかもしれない。少なくとも測量地図の作成と”pretium indictum”[公示価格]はヒュギヌスの印刷本の p.121 に出て来る表現である”certa pretia”[固定価格]を思い出させるものである。この固定価格という表現は同じ本の p.119 との関連でどちらも同じケースを扱っているが、トラヤヌス帝の時代においてパンノニアにおける≪退役兵士への≫譲渡の対象とする土地に対して、次の6種の分類が行われていた:arvum primum[第1級の平地]、arvum secundum[第2級の平地]、pratum[牧草地]、silva glandifera [木の実が採取出来る森林地]、silva vulgaris [その他の森林地]、pascua [(共同の)放牧地]である。一人一人に割当てられた土地の面積である――66 2/3、80、100 ユゲラについては――それらの面積の土地が常にただ一つのこれらの課税クラスのどれかでなければならない、という考え方はされておらず、それよりむしろそれぞれの割当て地の税の総額が計算され、その計算はその土地の各部分での分類上のクラスで決められていた「それぞれのユゲラあたりの単価」 X 「それぞれに該当するユゲラ数」、の総計という形で行われていた。測量地図上には各割当て地について、その土地の中の arvi primi ≪arvum primum の複数形≫が何ユゲラ、prati が何ユゲラ、といった風に記載され、その情報に従って各クラスによって固定されていたユゲラあたりの税額を使って、その割当て地の合計税額は簡単に計算することが出来た。ではもし土地所有者がその土地の利用方法を≪例えば農耕から牧畜に≫変更した場合、その場合でも税額の総額は同じままであっただろうか?もし近代的な意味での土地税の話をしているのであればこの問いに対しての答えは間違いなくイエスであろう。しかしここで課されている賦課については次のことを考慮することが必要であろう。つまり歴史的にはこの賦課の制度は永代貸借の規範の中間形成段階から、それが最終的に確定した段階へと発展し変化し続けていた、ということである。そういった状況に即して考えてみれば、次のことは全く首尾一貫していると言えるだろう。それはその土地の利用方法が変わる度に、賃借料もそれぞれの土地の分類に従って総額が変更された、ということである。賃借人の土地の利用方法の変更による賃貸料収入の減少リスクに対しては、≪民間の≫賃貸し人もその立場での国家も次の手段でそのリスクを回避しようとした。それはその種の土地利用の変更について、賃借人がローマの規則一般にほぼ従わざるを得なかったという状況を利用して、土地利用の変更をさせないようにする≪圧力をかける≫、というやり方によってである――そのことについては最終章で再度扱う――そしてまた属州の住民に対して、代々の皇帝は周知のように次の権利を当然のものとして保持していた。つまりその住民達に対して土地利用の内の一定の種類のものをイタリアの土地全体の所有者としての利害関心からそれを禁止することが出来る、という権利である。それ故に次のことは全く可能であったであろうし、またもしかすると実際にはもっとも広く行われたケースであったかもしれないのであるが、個々の土地からの賃借料の額は、ヒュギヌスが記しているように、それぞれの利用方法の違いに応じて≪固定額として≫土地台帳に記入されたということであり、そして土地の利用の仕方、つまりワイン作りのためのぶどう畑などとして利用された面積のユゲラ数こそが、本質的にはヒュギヌス(既引用分)が言及しているように土地の占有ということの本質的な内容だったのである。しかしながらそういった土地利用の仕方の変更の禁止が行われていたとしても、それはいずれにせよただ経過的な措置に過ぎなかった。何らかの理由で起きたかもしれないある耕地の一部分についての利用の中止は、間違いなく税金の軽減の理由としては決して認められなかった。arvum primum と secundum といった土地の分類は、その土地の収穫「可能高」に基くその土地からの継続的な税徴収を意味していたし、そしてこうした分類基準については時間の経過に従いその分類を増やすという形で更に細分個別化されていったのであり、それについては後で論じる通りである。そういった税額を維持しようとしたことと、個々の土地区画の種別が非常に容易に変更されるものであったということは、矛盾しているように思われる。更に言えばこの時代の法学の文献が “tributum soli”[土地税]について言及している箇所では、今指摘したことは次のような形で現れている。つまりは土地税というのものが、個々の具体的な土地区画に対しての固定された公課という前提で扱われているように見える、ということである57)。
57) 学説彙纂のD. 39、§ de legat[is] I, 30。それについて新カルタゴの碑文 C. I. L., II, 3424, によれば、ある者が神殿を建てようとした時に、総督補佐官の指示に従い、(5%税としての)20デナリウスの金額または土地税(つまりある固定額の)の控除無しにそれを行っている(モムゼンの同箇所への注釈を参照)。Vectigal と土地税は引用した学説彙纂の箇所では並記されている。この2つの対立については、vectigal の相対的に見て流動的な性格から考慮してみることが必要であろう。コンスタンティヌス大帝の統治下のフリギア≪小アジア中西部≫のナコレイアとオルキストゥス≪どちらもフリギアの都市≫の碑文が言及している tributum … ubertatis [土地の肥沃さに基づく土地税](C.I.L.,III,352)がまさしく、土地の価値によって固定額として定められた土地税に関することを確かに述べている。≪全集の注ではここは ubertatis ではなく libertatis(自由な) が正しいとされているので、ヴェーバーの推論は成立しない。≫同様の例として水道橋の側の土地に住んでいる者への土地税がある(p.348、ラハマン)。そしてまた D.42. 52,§2 de pact[is], 14 でも土地税が固定額の公課として扱われている。
最終的には税額の査定は一定の書式に基づいて行われ、それはウルピアーヌスが描写している(D.4 de censib[us])通りであるが、そこにはっきりと注記されていることは(前掲書§1)、ワイン用ブドウ畑とオリーブ栽培畑を――それらがもっとも高い地代を課されたカテゴリーであったが――それより低い地代のカテゴリーに変更する場合には、何故その変更が必要なのかについての十分な理由付けが必要であり、そしてそれは税査定官に対して良く説明されねばならず、そうでない場合はその変更申請は却下された。それによって税額が低くなる土地利用方法の変更の際には、それはただ relevatio [救済]または peraequatio [税の不平等の是正]という行政措置を利用してのみ可能であったが、それについてはすぐこの後で更に論じることになる。土地の利用方法の変更の結果としての、その土地の課税カテゴリーの高い方への移行に際してはしかしながら、徴税担当官は税の引き上げの実施を peraequatio による全体の税の見直しの機会まで待ったりはしなかった 58)。
58) どのような事情があろうと、それ故にこの種の土地税(他の全ての土地税と同じく)は、それがあまりにも実態より高く査定されていない限りにおいては、ともかくもそれはその耕地において行われている耕作を維持させるために手段だったのであり、というのも全体の税額が同じままで耕地を拡張することは、相対的に見てより多くの場合認められていたからである。この視点はハイスターベルク≪Bernhard Heisterbergk、1841~1898年、ドイツの古代史家、古典文献学者≫が適切に指摘しており、次のことは疑いようがない。つまり特にアフリカに関しての彼の本質的な視点である、収穫物に対する一定割合の現物貢納が、同地における穀物栽培をもしこの課税が仮に行われていなかった場合よりもより強固にしたに違いない、ということであるが、いずれにせよこの視点は非常に注目に値するものであるが、しかしまたコローヌス≪ローマ末期に現れて来る隷属的小作農民≫の制度の発展にとって本質的なものであったか、という点については、私は一般論としてそうは考えない。
添付の図面1のアラウシアの碑文[地図]の中に事実上、私にはいずれにせよ非常に確からしくそう思われるのであるが、割当てられた土地とそのそれぞれに課税合計額が記載されているとするならば、その場合そこから導かれることは、その課税額は常に固定されていた、ということである。ある特定の土地区画である特定のカテゴリーの耕作が行われているものに対して土地税を固定するという傾向は、土地税を変更する全ての理由を除外して考えると、全くのところ一般に安定していたものであり、またその傾向はゼノン≪東ローマ皇帝、在位474~491年≫の法(C.1 de j[ure] emph[yteutico] IV, 66)からも生じており、それに従って土地区画を(永代賃貸地に)転換する際の土地税の免除の根拠付けとして使われていた。その当時においては土地税の固定は既にそのずっと前の時代から一般的なものとして確立していたに違いない。それに適合していることとして既に皇帝スカエウォラの時に土地税を支払わなかったことによる法的な結果としての税徴収の資格を持つ者によるその土地区画の競売(D.52 pr. d[e]a[ctione] e[mptio] v[enditi] 19,1)が起きており、それ故に強制執行は≪ローマの中で≫統一的に実施されるように≪制度的に≫整備されていた。それと並んで C.Th.1 de aquaed[uctu] 15,2 (320年のもの)において見出すことが出来ることは、水道周辺の土地に義務として課されている清浄維持義務を果たさなかった場合のその土地の差し押さえである。しかしこちらは古い法により多く依存している。
公有地の所有状態の法的性格
我々はここまで次のような劣位の権利しかない所有状態について語って来た。それは国家の公有地を利用するという形で発展して来たものであり、そしてこの性格をたとえ個々の場合でかなりの程度変更が加えられた場合でも、本質においては保持していた、ということである。そういった所有状態のゲマインシャフトという観点から見た法的な特性は、一般的に言うならば、ただ否定的な方向に作用した、ということである。既にここまで次のことを見て来た。クイリテース所有権の欠如によってこの所有状態はケンススから、また握取行為[Akten per aes ut libram]からも根源的な原則として除外されただけでなく、またその他の私権に基づく譲渡行為や物権一般からも除外されたのである。その例外は占有そのものに関することが問題になっている場合と、そういう所有状態の一部となっている、ある地域の地所全体をまとめて獲得する場合であった。
行政上の手続き
今挙げたような様々な除外と同様に、それと関連する正規の法的手段からの原則的除外について既に色々な角度から論じて来た。訴訟の争点が占有に関することでない限りにおいては、そういった所有状態についての争い事に対して権限を持っていたのはただ行政当局の判断だけであり、従ってそういう争い事は「特別審理」[extraordinaria cognito]の領域に属していた。どういった官吏がその時々にそういう権限を与えられていたかについては、ここでは詳しく論じない、――グラックス兄弟の改革の時の三人委員会や643年の土地改革法の時の二人委員会のような特別な権限を与えられた者ではない限りは、それはその時々に暫定的に作り出されたのであり、一般的には部分的に監察官の権限であり、また別の部分では上級官吏、つまり執政官の権限として与えられていた。属州の長官の場合はこの二者の権限が一人の人間にまとめて与えられていた。ここにおいての違いというのは管轄権の範囲の違いであって、手続きの進め方の違いではない。これを理解することは非常に重要である。
というのはこの権利状態の正規の法的手段からの閉めだしは modus procedendi [契約の進め方、契約当事者の双方の義務]に関して大きな意味を持つことになったからである。特別審理[extraordinaria cognito]については、その特徴は全くもって単に訴訟手続き及びそれに関連した手続きだけが欠けている、ということではないのである。特別審理におけるこうした欠如は概して言えば不可欠なのにもかかわらず許されていなかった、ということではなく、ただ無くとも問題にはならない、という性質のものであった:また行政上の審理について決定権を持つ官吏は、その審理を陪審員に対して委託する命令を出すことが出来た。我々にとってより重要なのはひょっとするとこの手続きのもう一つの特性:現物に対する強制執行の可能性、であろう。
現物に対する強制執行
行政上の審理において決定権を持つ官吏はまた、法廷での決定に不服な者に対して、ただ罰金刑の宣告のみに留めることも出来、それは民事裁判での罰金刑の宣告に相当するものであった。しかしそういった官吏は疑いなくまたその宣告において現物で執行することが出来、つまり係争の対象になっていた土地区画を敗訴した者から取り上げ勝訴した者に与えることが出来たのである。特別審理においてこういった現物での処置が本質的なものであったことは、疑いの余地が無い。現物執行は地方総督の管轄となる訴訟においても完全に無くなることはなく、またそういった訴訟に先行して法で規定されている事例 59)とは違い、特別訴訟[Prozedur extra ordinem]の性格を事実上持っていた、ということも無かった。
59) D.2,§8 testam[enta] quemadmorum] 29, 3 (“omnimodo compelletur”); D.3,§9 de tab[ulis] exh[ibendis] 43,5 (“coërceri debere”); D.1,§3 de insp[iciendo] ventr. 25,4 (“cogenda remediis praetoriis”); D.5,§27 ut in poss[essione] leg[atorum] c[ausa esse liceat] 36,4 (per viatorem aut officialem); D.3,§1 ne vis fiat 43,4 (extraordinaria executio); D.1,§1 de migrando 43,32 (“extra ordinem subvenire”).
その際に扱われているのは本質的には審理を主導している者の判断に基づく執行である;それに対して特別訴訟や一般的な行政訴訟における手続きとしての現物執行は規定を設けてそれに則る形で行われていた。監察官は確かなこととして、次のことを必要であるとは認めなかった。つまり国家の賃貸人が土地を奪った方からその土地を取り上げ、代償として金銭で弁済する、ということで、そうではなくて監察官が出来たことは、国家の賃貸人に倒して≪土地を奪われた方に≫別の地代付きの土地を割当てさせることであった。グラックス兄弟による土地割当てにおいては、土地区画の譲渡不可という状況では執行は争いとなっている土地の価額の金銭での見積もりという形で、それは訴訟の目的を部分的に無効にさせる≪土地そのものは諦めさせるという意味で≫のと同じことを意味していたのかもしれない。controversia de territorio [領土を巡る争い]においては、それは同様に特別審理という形で決着を付けられたが、それについては碑文によれば執行が現物で行われた 60) ということが確認出来る。
60) C.I.L.,X, 7852 とそれに対するモムゼンの Hermes ≪当時の古典研究の雑誌≫II の注釈参照。
この現物執行ということは、その対象がまず第一に場所[locus]であり、一定の地代を課された、課税される、等々の全ての所有状態の土地に対して行われていた。面積[Areal]についても現物執行は有用なものとして扱われた。というのはそれは丁度、本来はただ場所についてのみ占有を保護する禁止令が、その強権的な罰金支払い誓約≪訴訟においてどちらか一方が判決で宣告されたある義務を果たさなかったり、あるいは違法行為を行った場合に罰金を支払うことを訴訟開始前に誓約すること≫などの威力も利用して、現物執行に近付こうとする努力と、現物での解決について服従を強いるということから発生して来たように、そういった事情は面積についても同じであったからである。訴訟手続きの更なる発展については、この現物執行はしかしながら大きな意味を持っており、というのはほとんどの属州においての土地区画は劣位の権利しか持たない状態で占有されていたからであり、物的訴訟においての現物執行の許容は時が経つに連れ共通の法≪ユス・コムーネ≫として扱われるようになり、それはウルピアヌスの D.68 de r[ei] v[indicatione] (VI, I)で既に見て来た通りである。
以上述べて来たことは大法官がこのような所有状態に対して、通常の裁判手続きに基づく訴訟を許可した場合は、当然のことながら事情が違っていた。しかしながらそういうケースで知られているものは無い。所有権という点において本来の≪クイリテース≫所有権の次に来るグラックス兄弟による土地の割当て自身が、法的な処理という点で、既に注記したように、彼らからして見れば管轄外だったのである。また擬制的な規定が作り出されたかどうかについても知られていない。ただまだ論じていないケースに該当する所有状態についての、正規な手続きに基づく物権訴訟が後になって現れてくるが、このケースでは国家が関与するものではなくて、諸ゲマインデが関与していた劣位の権利を持った所有状態であった。
ムニキピウムによる Ager vectigalis
それは “si ager vectigalis petatur” [もし賃貸借料が課されている土地に対してその占有の取り消しが行われたら]≪法規の中の章名≫という場合においての形式である。この形式はレーネル≪Otto Lenel、1849~1935年、ドイツの法学者、法制史家≫によれば、疑い無く次のような場合においての耕地の占有を回復することに該当する。それはつまり貸借地あるいはむしろ永代貸借地であったものがゲマインデによってそれを取り消された場合であると。このケースについては後でより詳しく検討することにするが、というのもイタリアにおいてはいずれにせよ疑い無く、同盟市戦争の後ではローマ国家が認めた貸借人というものがもはや証明不能になり、アフリカにおいての ager privatus vectigalisque の資格証明はともかくも疑わしき状態に留め置かれたのであり、それ故にこの形式による手続きが、ローマ法が改正された時代においての、永代貸借権の全体の状態を明らかにする唯一のやり方だったのである。
以上述べた形式の行政法的な起源については、ここにおいて疑いようがない:どのような私人もこういった永代貸借権を与える側になることは出来ず、このやり方の制度化はそうではなくて国家の大権に基づくものであり、諸ゲマインデにおいてはそれは昔の国家主権の遺物と見なされていた 61)。
61) しかしながらまた、市民植民市もまた永代貸借権を賦与する側になることが出来たが、それについては既に注記した通りである。――Leibrenten≪一生支払い続ける義務のあるレンテ=定期支払い金≫で一まとまりの fundus に対して課せられるものも、また個人に対してのものとしても制度化出来ていた、参照:D. 12. 18 pr., 19 pr. de annuis 33, 1、C.I.L., V, 4489。しかしながらその類いの永久レンテは実際には存在しておらず、無期限のレンテの遺贈もそういった形では存在しておらず、ただ終身レンテの信託遺贈のみが行われていた、D. 12 前掲部参照。
諸ゲマインデはこの ager privatus vectigalisque の制度を彼らに元々帰属する土地として利用するのと同時に、ローマ国家の公有地から彼らに譲渡された土地として――しかも常に無期限にそうされたものとして――利用した。
ゲマインデの税とゲマインデの財産
ローマ領内の個々のゲマインデがどのようにしてそれぞれの必要物を調達していたのか、その方法については周知のようにほとんど知られていない。その構成員の大部分が夫役制への移行へと追い立てられ、そこに一方ではそのゲマインデに所属する人員と、他方でその人員と一緒に働いている家族や奴隷も引き入れられた、ということを、スペインにあったカエサルによって建設された市民植民市のウルソ 62)≪セビリア東方100Kmの所にあった、現在のオスナ≫の碑文として残されている法規から知ることが出来る。
62) Lex coloniae Genetivae, Ephem. epigr.≪Ephemeris Epigraphica、ヴェーバーの当時古代の碑文の解読を集めた雑誌≫ II, p.221f., c,98. 99。
そこにおいては、割当てることが認められた週あたりの夫役の日数は一人あたりが5日、1ユゲラの面積あたりでは3日と定められていた。こういった夫役と並んで、その夫役ではカバー出来ない需要について、先行して金銭による賦課も行われていたことは、同様に確実である 63)。
63) キケロ、Del. agr. ≪De Lege Agraria contra Rullum≫2, 30, 82, Verr. ≪In Verrem≫IIの53, 131, II, 55, 138, Pro Flacco の 9, 20; 更に C.I. 10. De vectig[alibus] IV, 61。
更に知られていることは、諸都市においての貧民救済施策≪ローマでは共和政末期から帝政期に、貧民に小麦を安価で支給した、いわゆる「パンとサーカス」政策。≫は、土地所有者に穀物の備蓄をさせ、それを特価で提供させる、という形で行われており 64)、あるいは現物貢納という形でも先行して行われていた 65)、ということである。しかしこういった賦課、特に金銭賦課がどのようにして徴収され、またどのような原則に基づいていたのかということについては知られていない。しかしながら古代の諸都市は中世の諸都市と次の点は共有しているように思われる。つまり全てのこういった直接税は都市の予算の均衡を作り出すための特別な手段という性格を持っていたということであり 66)、この関係でそれらの直接税は都市による借款に等しいものであり、ひょっとするとローマにおいてそうであったように、強制的な公債として通用していたのかもしれない。
64) D. 27, §3 de usufr[uctu] は属州による穀物の購入に相当する。
65) キケロの Verr. III, 42, 100 (ここではローマに支払うべき公課を補完するものとして)
66) このことに該当するのは、それがもしゲマインデに対する課税について扱っている場合は、徴税官の時限的措置である l. 28 de usu 33, 2 の箇所である。
いずれにせよこうした直接税が結果としてもたらしたものは、我々の把握するところでは、ゲマインデの財産を出来る限り吸い上げる結果として税額を非常な程度まで増大させようとする動きが各所で熱心に行われていた、ということである。間接税、とりわけ関税・通行税は、それらは土地の所有の結果として生じるものとして捉えられるが、ここでは詳細に論じず、ただ諸ゲマインデのレンテ収入のみを扱う。――中世の諸都市においてはそれらの財産の管理において、高度の、部分的には天才的と言ってよいほどの業務と権利の形態を創造したことが記録されている。その中でも特に不動産を活用したレンテ≪定期的に入って来る不労所得≫の業務を発展させ、それは相対的に見て安定した公債制度を作り出したという観点で理解されるべきである。ローマの領土内で諸ゲマインデが財政をどのように運用していたかについてはほとんど知られていないが、しかし次のことはそれでも確かである。それはこのレンテを利用した収入の手段の運営という意味では、相対的には非常に遅れていた、ということである。
レンテ業務
ローマの諸ゲマインデにおいての公債制度はおそらくは大部分はレベルの低いもので 67)、諸ゲマインデは確かに能動的なレンテ業務を発達させたことはさせたが、それはまだ非常に原始的なものであり、つまりはただの賃貸しであり、まだレンテ≪地代の徴収権≫そのものが売買の対象とされる段階には至っていなかった。
67) 小アジアの諸都市は、≪兵士への≫賃金を支払うことが出来なかった時に、高利貸しから資金を借りる羽目に陥った、(Plut. Lucull 7, 20)
通常のゲマインデの財についての賃貸権と永代賃貸借と並んで 68)ここで見出すことが出来るのは、土地区画を個人が経営している場合に、そしてその土地区画を地代を課すという形でその個人に≪正式に占有を認めて≫返還することが行われており、それはゲマインデの資金 69) という形であるか、あるいはひょっとしたら特定の公的なあるいは福祉目的のための永久レンテの形であり、その中でも特に貧困家庭に対して子供の養育費を援助するという目的であった 70)。
68) これらについては、たとえば D. 219 の de v[erborum] s[iginigicatione] では契約者による貸し出しの結果として成立すると説明されている。
69) 皇帝は総統とゲマインデの管理者に次のことを指示した。つまり以下について尽力せよということで、それは擬制的に投資されたゲマインデの資金が可能な限り元の債務者≪元々土地を使用していた者≫の手に残るようにする、ということである。≪永久レンテの設定は、本来なら資金をその土地の所有者に与え、それに対する永久の利子の支払いとして定期的に金を支払う、ということであるが、この場合資金の貸し付けは実際には行われておらず、土地の占有と使用を前のまま認めることがどの代替の方法となっている。≫D. 33 de usur[is] (32, 1)参照。
70) そのようにアティーナ≪ローマとナポリの中間に位置する都市≫の C.I.L., X, 6328 他はなっている。
帝政期においては中央権力の干渉が見られ、それはある観点では貧困者救済という利害関心によっての、資本の前払いという形で土地区画への利子を条件とする貸付投資を進めさせたということであり、それは福祉目的のためと定められていたが 71)、別の観点ではそれによってゲマインデの財の投資を監視しようとしたのである。
71) 知られているのはネルウァ帝≪在35~98年≫からアレクサンデル・セルウェルス帝≪在222~235年≫までに導入された離別された妻や私生児を扶助するための大規模な基金であり、それについての碑文としてはトラヤヌス帝≪在98~117年≫の時のものが2つC.I.L. に含まれている。C.I.L., IX, 1455、参照:デジャルダン≪Ernest Dejardins、1823~1886年、フランスの歴史家、地理学者、考古学者≫の De tab. alim. パリ、1854年。ヘンツェン≪Wilhelm Henzen、1816~1887年、ドイツの碑文研究家≫の arch. Inst. in Rom の1844年の年報。土地区画に課された使用料を財源とする基金の資金は低い利率で貸し出された。土地区画の所有者がこの課された使用料を免れることが許されていなかったことは、確かなことと見なすことが出来、それはまた別の点では低利率によって償還金額の合計額を一定の額以下に抑えるという効果もあった。
そういった形で部分的に土地の売却や永代貸借権の付与が制限され 72)、諸ゲマインデが独自に税を課すことも禁じられ 73)、また部分的に vectigal による収益は諸ゲマインデとローマ国家の間で分けられ 74)、その結果としてゲマインデからのその分の税収入が国家の税にとって追加分となったように見える。
72) lex. col. Genetivae c.82 では売却と永代貸借は5年以上その土地を借りてい場合にのみ許されていた。
73) セウェルス帝≪在193~211年≫とカラカラ帝≪在209~217年≫の c. 2 vectig[alia] nov[a] IV, 62。
74) テオドシウス帝≪在379~395年≫ウァレンティニアヌス朝≪ウァレンティニアヌス1世、ウァレンス、グラティアヌス、ウァレンティニアヌス2世の4人の在位の364~392年のこと≫での c.13 de vectig[alibus] IV, 61(1/3 がゲマインデに、2/3 が国家にとなっている)。
どのように税がゲマインデから国家に吸い上げられたかという権利の侵害については、後に論じる。ここではゲマインデから利子を代償として与えられた土地について詳細に論じることにする。
ager vectigalis の法的性格
まずは次のことは確かである。それは諸ゲマインデがそういった土地区画の本来の所有者であった、と認められていたということである。確かに、次のような時々には利子≪税金≫を徴収する権利はゲマインデの権利の対象であるように見える。その時々とは、スペインのムニキピウムの Cartimitatum≪Cartima、現在のスペインのマラガ近郊のカルタマ≫の女性司祭が “vectigalia publica vindicavit”[公的な賃貸料を取る権利を主張した]と述べている場合(C.I.L., II, 1956)や、あるいはウェスパシアヌス帝≪在69~79年≫によって作られたスペインのあるゲマインデがその賃貸料徴収の権利を行使していなかった場合(同資料の1423)、あるいはティスバイの住民が元老院決議によってその者達が持っていた賃貸料徴収権を今後も継続して持つことを認可されている場合 75)、またドイツ語の表現で文書によって呈示される利子について “von Eigenschaft wegen”[所有権を持つことによって(その権利として派生する)]もこのことに適合しているし、またポンペイにおいてある者がゲマインデに対して利子≪使用料≫を支払っていて、その理由が “ob avitum et patritum fundi Rhdiani”[祖父と父がRudhiani≪正しくは Audiani≫に持っていた土地のため]となっている場合(Nr.123のポンペイの税受領書、モムゼンの Hermes XII p.88f と比較せよ)などである。しかしながら、ゲマインデが利子徴収権を持っているからといって、そういった土地の権利状態が曖昧になっている訳ではない。
75) Eph. epigr. I, p.279f。
ある者が自分の占有する土地区画に永久レンテを設定しようと欲した場合≪その土地区画をレンテ売買の形で売却しようとした場合≫、その者はその土地区画をゲマインデに売却せねばならず、次にその者は土地をこの永久レンテという形での≪永久≫利子支払いという条件の下で≪自分の土地の実質的な使用権を≫取り戻すことになる 76)。
76) C.I.L., IX≪正しくはX≫, 5853. Plinius, Ep. I, 8, 10; VII, 18, 2。
これに対して永久レンテが設定された土地区画の所有者は、用益権は留保しつつもその土地自体の所有権はゲマインデに対して放棄するのであり、それ故に[元の]所有者はもはやその土地を譲渡することが出来ない、というのは既にゲマインデがその所有権者になっているからである 77)。
77) C.I.L., X, 1783のプテオリ≪ポッツオーリ、前掲の地図参照≫での例。
そういった言い回しはよりむしろ次のことを意味しているのに等しい。つまりゲマインデの所有権の主張を、現物の土地の押収という形でか、あるいは土地への vectigal [地代、税、利子]を課する形で行うことが出来る、ということである。vectigal は公的な所有物を実質的に売却する上でのもっとも分かりやすい形式である。ある、既に vectigal が課されている fundus をゲマインデに対して遺贈することは、その有効性が疑わしいものとされた。何故ならばそういった土地は既にムニキピウムに属するものとされていたからであり(D. 71 §5, 6 de legat[is] I.30)、しかし更にはまた次のことも示唆されていた:ある植民市において水道橋の設置が必要となった場合は、その植民市の規約で決められていることとして、土地の強制収用権がその植民市自身(たとえば植民市ウル≪現スペインのオスナ≫)に帰属し、モムゼンが妥当な理由を持ってそれを主張しているように、水道橋が建設される fundus 全体に対してその権利が及んだ。その土地の側に住んでいる住人は今や(P.348, 6f. ラハマン) 水道橋の維持管理義務を負わされ、その者達にはそれ故に一種の税が課されたのと同じである。明らかなことであるのはその者達にそういった義務を課することを可能にするには、まずは補償を前提にその者達の fundus に対する所有権を取上げ、そしてその fundus を今度は fundus vectigalis という地代支払い義務のあるものとして戻すのであるが、もちろんその際には同様にその地代支払い義務の対価を支払うのであるが、その対価には強制収用の全支払金の中から補償金としての分が含まれていた。水道橋の建設を進めるためには、それらの土地に対する地役権≪他人の土地を利用出来る権利≫を設定することで十分であった。
レンテを課する時に使われた法的な形式は、もちろん握取行為の際に使用される既に述べた法規が定める形式である 78)。それによってレンテの権利を擬制的に持つことと、土地の用益権が等置されたということは、しかしただ次のことの理由となっていた。それは握取行為の形式がそれによって個人間で土地区画に対する継続的な権利が一つの行為によって設定されるただ一つの法的形式だったということである。というのはその形式は諸ゲマインデに主権とそこからまたある種の絶対的な行政権をもたらしたからである。
78) D.61(スカエウォラ)de pignor[ibus]。キケロの、De l. agrar. III, 2, 9。参照:C.I.L., V, 4485。それについてはまた 1. 219 D. de v[erborum] s[ignificatione] にある”locare”[契約する、契約して貸す]としても理解すべきであり、このことがまた C.I.L., X, 5853 のフェレンティヌム≪ローマの北北西70Kmの所にある、現在のヴィテルボ≫の碑文にある “redemit et reddidit”[買い戻して返却する]の意味である。この手続きは次のような内容を考えると常にかなりの不透明さを持ったものであり、つまりまずはゲマインデが所有している fundus をこの手続きである個人へ譲渡し、次にその個人からその fundus を一旦返却させ、更に今度はそれに vectigal を課した形で戻す、というものである。また≪単に≫”redimere”[買い戻す]はそれとは反対の手続きである。それに対して個人によるゲマインデへの土地の返却が、当事者の目には本質的にはただ形だけの手続きと映っていたとしたら、もし”redimere”[買い戻す]が先に来て、次に”reddere”[戻す、引渡す]と述べられているのであれば、その返却の手続きは特に注意すべきようなものではないのである。Redimere はこの一連の手続きの中での義務的なものを指し示し、reddere はその手続きの中での物権的な部分の最初の半分を指し示し、この部分の2番目のものは既に述べた法規に規定されている握取行為として成立していた。
――それ以外にもちろんまた、永代賃借においてそれが賃借料に依拠したものであることを明白にするために Remission[軽減](D.15 §4 locati 19, 2)という考え方が適用されていたのである。――他方ではこの形式は次の側面も持ったものとして現れて来ていた。つまり諸ゲマインデにおいては、vectigal が一見したところ益々ある一定の資本総額に対しての利率のように思われるようになり、更にはそれは文書による裏付けのある購入資金に対しての抵当権、という性格のものに近付いていった、ということである。この形式はその根拠をおそらくは国家による長期の賃貸しへの依存ということの中に持っていたのであり、そこにおいての代償としては、それはおそらくはそのようにして作り出されることが試みられたのであるが、永代の貸借権を得るために支払うお金とまたその利子として成立していたのである 79)。
79) そこから更にユスティニアヌス帝の法学提要によれば(§3 de loc[atione] III, 34) … familiaritatem aliquam inter se habere videntur emtio et venditio, item locatio et conductio, ut in quibusdam causis quaeri soleat, utrum emtio et venditio contrahatur an locatio et conductio. Ut ecce de praediis, quae perpetuo quibusdam fruenda traduntur.
[契約に基づく売買と、賃貸借とそれに基づく貸し出しとは、お互いに良く似た行為であると見なされる。ある取引きでそれが前者なのか後者なのか、どちらに基づいて行われたかが問題となることが多い。例えばある不動産について、それがある者に対して永久に使用させるために引渡された場合などである。]
発展の過程では実務的な観点に立てばいずれにせよ、vectigal 付きの fundus の占有者が次第に所有者と同一視されるようになっていった。その占有者自身による、あるいはその占有者に対しての境界線確定訴訟が起されることがあり得たということは、何も特別なことではない。何故ならその者はその場所の占有者として保護されており、その場所の境界線に関しての訴訟は、その場所の保護によって利益を享受する者に対して全面的かつ唯一帰属するものだったからである(D. 4 §9 fin[ium] reg[undorum] 10, 1)。
ただ、またそういった土地に関する訴訟としては、公有地分割訴訟(D. 7 pr. §1 h.t. 10, 3 )や更には家族間での遺産分割訴訟(D. 11 h.t. 10, 2)の対象となることも説明されており、vectigal 付きの fundus は遺贈することが可能であり(D. 219 de v[erborum] s[ignificatione])、更にはその vectigal 付きの fundus について、売却を許可された確定的な物権として訴訟を起すことも可能であった(D. 1 pr. de cond[itione] trit[iciaria] 13, 3)。しかし、もちろん該当する諸法規からは次のことを見て取ることが出来る。つまりはこの制度全体での諸関係の中には、実務上では疑問になる部分がある、ということである。特に土地分割訴訟を扱っている箇所(D. 7 pr. comm[uni] div[idundo])は改ざんされたのではないかという印象を与える:確かに根源的にはまだウルピアヌスの時代までにはムニキピウムの当局による認可と vectigal を分割した土地それぞれに対してそちらも分割して課す、ということが先に行われることが必要であった。土地の譲渡性が関係するものは、C. 3 de jure emphyteutico IV, 66 の規定であり、それは agri vectiglaes を基礎といている法規則に依存しており、この譲渡に関しては諸ゲマインデの同意が必要だったのである。そこで規定されている制度における予審上の処理、つまりこういった審理において代理人を立てるということは、単に正当な理由があるというだけでは許可されなかった、ということは、こうした全ての劣位の権利を持った所有状態においての全体の進め方に関する行政上の規則について、その本質をもっとも良く説明している。laudamium ≪土地の買取り権を行使しない場合に、元の地主に支払う補償金≫については、emphyteuse ≪永代賃貸借≫の場合と同じく、ager vectigalis においては何も知られていない。
結局問題となるのは、vectigal が支払われない場合に、その土地区画はゲマインデに戻されるのかどうかということで、それは当然ながらまだユスティニアヌス帝の法規の中でも言及されている論点の実際的な側面であり、つまりは契約を購入と見なすべきか貸借と見なすべきか、ということである 80)。
80) 先の注で引用した箇所の更に先の部分。
これらの全ての土地の授与においての主要な難点は、おそらくはまたまさに次の点にあった。つまり多くの場合は永代貸借の権利金が支払われており、それ故に vectigal の支払いはその土地を与えられた者の唯一の金銭支払い義務としては説明されておらず、従ってその理由から vectigal の不払いがあったからといって直ちに土地を取上げることは出来なかったのである。文献史料では(スカエウォラの D.31 de pign[oribus])支払い遅延の場合の財産取戻し権は、前述の法において構成要素として言及されているが、それは自明なものではないし、またマティアス≪Bernhard Matthiaß、1855~1918年、ドイツの法学者≫が主張しているような、この制度全体を構築する上での出発的としても見なすことは出来ない 81)。
81) このことはペルニーチェの Parerga (Z. f. R. G., Rom. V)において正当に主張されている。
ゲマインデそれ自体については、単に強制手段に訴える資格を与えられただけであるが、しかしながらおそらくは D. 31 の引用済みの箇所で述べられている規定は、永代貸借権に関する前述の法規のかなりの部分においての構成要素となっているのであり、それ故に後に時代にはこれらの制度全体は利子支払いという制約を付けられた上での土地の授与と把握することが可能であり、それは例えばパウルス≪Julius Paulusu、3世紀のローマの法学者、ユスティニアヌス法典でその著作が引用される5人の法学者に準ずる存在≫の D. 1 si ager vectigalis VI, 3 に現れている通りである。
永代賃貸借
次のことはこれまで既に指摘して来たし、また疑いようのないことでもある。それは、後の皇帝による法規での永代貸借権が歴史的にそして法的にムニキピウムの agri vectigales に依拠していて、属州の土地税を課された耕地に依拠するのではない、ということである。このことは次の現象に対して特徴的なこととなっており、その現象については最終章でもう一度扱うが、それはつまりプリンケプス≪市民の中の第一人者という意味で、元々初代皇帝アウグストゥスが自身のことをそう称したが、実質的には皇帝のこと≫はその土地所有についてゲマインデの諸団体からそれを分離しようとしたり、またはそこの権利から取り除こうと強く試みたのであり、そして地主としてのそれらの団体の地位、それは元々ゲマインデの当局が元の地主から奪い取ったように、ゲマインデの当局へその地位の返還を要求した、ということである。
Empyteuse[永代貸借権]は、その名称自体は、元々はオリエントのギリシア語から取られたものであり、まず最初は属州においての新規開拓地に対して使用された語であり、そこではそういった新規開拓を自分で行って自分の土地とした者が、地代[税金、利子]を継続して固定額にすることを望んだのである。この制度が ager vectigalis と違う点はまさに本質的には譲渡の、元の地主の先買権の、名義変更の2%の手数料の、そして[通常の土地としての登録からの]免除の理由の確認の、そういった諸前提全てについての確固たる標準規定が存在しているということである。そういった規定は永代貸借権を受ける者にとってはまことに好都合で、その者達に釣りあった、この制度全体の諸関係についての規制形式であった。その形式は諸ゲマインデの agri vectigales に対してのものであるのと同様に、国家の agri vectigalesque に対してのものでもあったが、しかしそれはまた、通常土地が大規模な経営者に与えられるという形式に過ぎず、それは明確なこととしては、D. 1 si ager vect[igalis petature] における、vectigales とそうでないものとの区別以外の何物からも発生していないように、そこでの区別は明確に主張されているように、次のような土地同士の区別と同じことであり、それは一方は契約者、つまり土地の貸借契約を引き受ける者に対して永代または有期で貸し出される土地であり、もう一方は耕地であって、農民、つまり独立の小農場経営者に、”colendi dati sunt”、つまり耕作目的で与えられたものであり、その相互の土地の区別と同じである。後者の区別の法的に不安定な位置付けは、その表現の中に明確に現れている。一方では農民の間で、他方では土地所有者と公有地貸借人との間で、法的な位置付けとしてその2つの間隙を橋渡しするような中間連結物は存在していなかった。
公有地ではない属州の土地
ここまで公有地とそれに倣った土地においての所有状態の法的形式について我々は見て来たのであるが、そうであれば次に我々は属州の土地においての同様な部分へと目を転ずることとするが、その部分はまたここでも土地の譲渡形態と私権的関係の間に因果関係が成立しているかどうかを調査するための属州の特別な性格となっているのである。そのような属州の土地は狭義の公有地、つまり ager publicus ではない。何故ならばその種の土地は[ager publicus ではないものとして]イタリアにも存在していたからである。他方でははっきりした契約による売買に基づく土地や、属州の総督の行政方針によって認可された租税免除の諸ゲマインデの土地もまたそういった類の土地には属しておらず、属州の土地の内そういった部分として見なすことが出来るのは、ローマの国家主権がそれらの土地を当然の自分達の土地として権利を主張し、しかしその場合でもその領域が ager publicus の根本原則に従った土地として利用されないか、あるいはそのようなものとしてローマの官吏によってローマの所有形態に沿った形では与えられていなかったものである。ここで消去法的に、かつまた不正確に描写された制度をいかに肯定的に理解すべきかということは、次に挙げるような属州についてその実態を一瞥することが必要で、そうした属州とはそれらが共和政期にどのように設立されたかについて多少は情報が残されている、シチリア、アジア≪アナトリア半島西部の属州、旧フリギア≫とアフリカである。
シチリアにおける1/10税地[Zehntland]
シチリアにおいては 82)、一部のゲマインデは租税を免除され、また一般的に言ってローマの行政権力が直接そこに及ぶことから免れていた。シチリアでの他の領域で戦争≪主に第一次ポエニ戦争≫によってローマのものとなった諸都市は、その領土に関する所有権を失い、その土地はローマによって没収され、ager publicus となり、監察官によって何らかの形で使用料を課され、それについては上述の箇所で見て来た通りである。その場合にそうした耕地が改めて測量されたかどうかは、つまりはカンパーニャ地方の土地の場合のようにであるが、何も知られていない。しかしフロンティヌスの arva publica [公有の耕地]についての注記がその他の場合を説明しているかもしれない。
82) 次のことは自明である。つまり属州に関する事実については、キケロのウェレス弾劾演説が決定的な文献情報であり、しかしそれはただここで取り扱っている問題に関係する箇所を検討する場合のみである。
いずれにせよしかしながら成立していたのは、それをこれから見て行く訳だが、この種の耕地についての何らかの統一的な所有権で、それは国家から土地を借りている者のものとしての、期限付きの所有権である。古くからの住民が元来はその多くが土地の賃借人であったということは、この辺りの事情を何ら変えることはない。また個々の土地区画の権利に関しての裁判権もまた、それが必要である限りにおいて、ローマの行政当局の手中にあった。
第三のカテゴリーの土地は、ローマに没収されなかったものの、非課税のままとされることもなかった領域である。まったく確かなのは、ローマ人がここではまた理論上は土地の所有権を書き換えて自分達のものにしたのではなく、それまでの土地の主人の、つまりシラクサのヒエロン王の所有権についてそれをそのまま継承したように思われる、ということである。特にその中でもローマ人がヒエロン王から受け取ったものは、王の租税に関する規定、つまりいわゆる lex Hieronica 83)である。
83) 参照:デーゲンコルプ≪Karl Heinrich Degenkolb、1832~1909年、ドイツの法学者≫、Die lex Hieronica、ベルリン、1861年;ペルニーチェ、Parerga、Z.f.R.G.,Rom. V, p.62f。
ヒエロン王の租税規定はまた、既に十分に検証されているように、王の1/10税に基礎を置いている。個々のゲマインデではそれぞれの地区の1/10税を課される農民の人数を毎年確認することになっており、そしてそのリストを公的に閲覧出来るようにしていた(Verr. acc の 3, 120)。農民の側からは、この目的のために使われる土地の面積のユゲラ数(同一書の53)と蒔いた種子[の種類](同一書 102)を申告することになっていた。次に一定の収穫が見込まれるシラクサ 84) のゲマインデ毎の領域が属州総督の名前で競売方式によって落札者に貸し出され、それについては見込みの収穫の一定割り合いの量を貢納し、また収穫が見込みよりも減った場合でも同じ量の貢納義務を負うリスクを受け入れるという条件付きであった。
84) キケロ、Verr III, 33, 77;III, 44, 104; III, 64, 149。
収穫に際して1/10税を徴収する権利のある者は、その耕地での収穫の1/10を取ることが出来、穀物を収穫に先立って受け取ることは許されていなかった。しかし事実上は一般的には収穫量の1/10が徴収されたのではなく、1/10税の義務を負う賃借人は個々の1/10税の徴収権利者と、収穫が予定より少なくなった場合にも変動しない一定の額の納付について取り決めていた。
法的な所有権
この手続きにおいて行政法的に本質的なことは、農民と1/10税を課された土地区画との関係が未確定のままにされた、ということである;1/10税を徴収する者は、その年にその土地を耕作する者に対して、その者がその土地の所有者であるか、あるいはある個人またはある自治体からその土地を賃借している者であるか、ということにはまったく無関心であった 85)。
85) Verr. III, 8, 20にて。
こういった私法的な関係についての裁判権は、その所有の権利についての基準の設定と同様に、それ故にそれぞれの自治体の手中に委ねられていた 86)。
86) Verr. II, 13, 32にて。
他方では所有権を回復しようとする者[Rekuperatoren]による訴訟が起きており、それは次の者達の組み合わせによって(ここについては十分な情報はないが、例えば以下のように)、つまり2つの利害集団、つまり[土地の]販売人と農民という、1/10税に関係する者達を≪原告と被告として≫ペアにして、しかし議事取り仕切りはローマの官吏の元で、1/10税の義務を負う者とその徴収の権利を持つ者との間で発生した争点について、決定が為された 87)。
87) デーゲンコルプの前掲書の既引用部参照。
――次のことは明らかである。つまりこの2つの利害集団の衝突が、それぞれの特別な観点において決定的な争いが避けられなかった、ということであり、というのも所有権回復訴訟においては納税義務者についての問題は、しばしば土地区画そのものへの権利の問題から分けて扱うことが不可能だったのであり、つまりは例えば業務上の犯罪が刑事訴訟案件として扱われる場合があるのと同様に 88)、取り扱われた、ということである。
88) 参照:Verr. III, 22, 55 にて。
どのようにしてこのような利害対立の関係が解決されたのかについては知られておらず 89)、しかしいずれにせよ我々がここで見てとることが出来るのは、ゲマインデの自治と国家による直接の課税を一つのものに統合しようとする試みの例であり、そしてこのような異なる考え方を混ぜて一つのものにするということは、属州における土地区画の権利状態を、統一された観点で遡及して研究する上での本質的な部分となっているのである。
89) 先に引用した箇所が示す所によれば、根本的な解決は出来ていなかったように見える。
一方では国家の個々の土地区画に対しての直接的な関係で、それはより後の時代に使われた課税地を意味する別の表現である praedium stipendiarium が既に当時使われ始めていたかのように思わせるのであるが、他方ではしかし諸ゲマインデが自治を望んだこと、つまりは[ローマ市民以外の]の外国人としての権利の維持であるが、この双方が属州における土地所有の権利状態を曖昧にしていることは否定できない。既に言及したケンススは形の上では国家による地方自治体へのケンススであったが、しかしそれは実質的にはその属州で支配的なゲマインデの実態を調べる属州によるケンススと言えるものであった。というのも属州総督側からの監査は、当然のこととして国家による課税がされている土地の場合でも無しで済ますことは出来なかったからであり、キケロが注記しているのは、この監督権に基づいて属州総督は事実上徴税簿の内容を把握していたのであり(Verr. acc. のII, 53, 131; II, 55, 138 にて)、そしてこのことは総督が土地所有者の利害を自分の管理下に置くことをそれだけ容易にしたのである。しかしその場合でも諸ゲマインデはまた自分達自身の必要物を調達するために土地台帳も必要としたのであり、それは間接税≪関税、通行税など≫とゲマインデの財産からの収益では十分ではない場合においてであるが、その場合次のことを認めるのは難しいであろう。それはその土地台帳がローマが自身の公課の目的で使っていたものとは別のものであるということである。キケロによる個々のケースの説明もまた、その2つの土地台帳が同一のものであったことを裏付けている(Verr. acc. III, 42, 100 にて)。
もちろんこういった関係は本質において人為的に作り出されたものであり、後の帝政期においても再度繰り返されている:この土地という領域におけるゲマインデの自治は形の上だけで成立していたものであり、その実質的な中身は何もなかった 90)。こういった状態についてはここではしかし保留とし、また別の所で扱うこととしたい。
90) 確かなこととしてこうした手続きは u.a.c.548年≪BC204年≫[の第二次ポエニ戦争の時]にローマに対して反乱を起こした 12 のラテン植民市に対して行われたものと同様のものであった。リヴィウスの 39, 15 で述べられているように、その 12 の植民市に対してその財産[の金銭換算額]1000に対して1の割合いの継続的な税が新たに課せられ、また次のように規定された:censumque in iis coloniis agi ex formula ab Romanis censoribus data [これらの植民市においてローマの監察官によって与えられた形式に基づいてケンススが実施されるべきである]、この句が意味するのは植民市がローマの一般的なケンススの形式におってではなく、ローマとその植民市の関係に合わせた、ローマの監察官側ら支給される特別の規則に従って評価されたということで、それはシチリアの諸都市がローマの側から定められた形式、つまり lex Hieronica によって評価されたのと全く同じである。元々そこの住民であった監察官達は、誓約下で彼らが実施したケンススの調査結果をローマに対して報告することになっていた。それに対してのある種の監査は法的に認められていたに違いない。
諸ゲマインデは民衆からの耐え難い圧力と属州総督の恣意に対抗して次のやり方で自衛しようとした。それは諸ゲマインデ自身が自分達の領域において競売に付された公有地を競り落としたり、あるいは最高価格を付けた入札者からその土地を買い取ることである 91)。
91) Ver. III,33,77; III, 39, 88; III, 42, 99 等にて。
これらのことが実際に起きたことだとしたら、諸ゲマインデは当該の年について、まるで彼ら自身が収穫物の内の固定の割合の貢納の義務を負っていて、かつそれは更に別の者に再割当てして負担させることについて正当な権利を持っているかのように振る舞うことを意図していたと言える。このようなケースバイケースで起きていたようなやり方は次の段階では――それも遅くともカエサルによって――継続的に行われるように変わって行ったのであり、それは現物貢納から現金地代へと変わったのと時期を同じくしていた 92)。
92) プリニウス、H. N. III, 91。
というのはこの変化した形が、より後の時代におけるシチリアの諸ゲマインデの状態となったからである。これによってその地方の土地の権利がより後の時代まで保証されることになり、実際の所シチリアにおけるその地方での土地の権利、例えば jus protimiseos [買占め権]の形で中世に入っても残っていた。≪全集の注は jus protimiseos はイタリア半島の制度が伝わったもので、シチリア島固有の制度ではないとしている。≫
アジア属州≪アナトリア半島(いわゆる小アジア)西部に存在した元老院管轄の属州≫における1/10税地
アジア属州における同様の発展はシチリアにおいてよりも早く完成したように見える。アジア属州はまた、[グラックス兄弟の]センプロニウス法によれば1/10税の対象地とされ 93)、更にはしかしここではこういった税の形式はより以前からあったの他の形式の税より有利なものとして位置付けられるように見え、しかしその以前の税の個々の事例については知られておらず、王の恣意的な課税権に基づいて導入されたものであったように思われる。Vectigal による賃貸借にはローマの騎士階級≪世襲貴族と平民の中間の階層で商業などに従事した≫のローマ国家への利害関心から、ガイウス・グラックス≪弟≫の同じ法が使われ、それは実際的にはただ属州自身による諸ゲマインデ向け及び個人向けの土地の、競売においての競争を激化させた、という意味しか持っていなかった。その場合キケロ(弟クイントゥスへの書簡集、1,11 §33)がアジア属州の諸ゲマインデについて次のように言っているのであれば:nomen autem publicani aspernari non possunt, qui pendere ipsi vectigal sine publicano non potuerint, quod iis aequaliter Sulla descripserat,[しかし公有地貸借人という名前(立場)を拒絶することは出来ない。何故ならばその公有地貸借人という契約無しには、地代を払って公有地を借りて耕作することが出来なかったからであり、それはそういった者達に対してスッラが公平に制度化したものである]、そうであればここで言及されているのはほぼ次のことと同じで、つまり属州となった地域から得た[領土という]収入を個々のゲマインデに対してその元々の大きさに基づいて、元の面積の単位面積あたりに平均で決めた地代付きで改めて割当てるというやり方について言及されているのであり、つまり諸ゲマインデが決まった額の賃借料を支払うことを承諾し、その支払い[による公有地貸借契約]がその者達に対して認められたのである。しかしこの試みは、キケロの引用文を見る限りでは失敗したように思える。何故ならば後の時代になってもアジア属州に公有地貸借人が存在しているが、その者達については元々の所有状態を回復するということと関連付けられる必然性はもちろん無かったからである;いずれにせよ公有地の貸借料付き貸し出しは、地域毎に徐々に導入されたように思われる(キケロ フラックス弁護 37, 91)。というのもシチリアと同じくここでも固定額の使用料への移行が行われており、それもBC48年のカエサルによってである。(アッピアノス、1.1. 5,4)。
93) アッピアノス 内乱記 5,4
キケロによる有名な記述(Verr. III,6,12 94))によれば、次のような印象を得ることが出来る。つまりこうした状態は、それはカエサルがシチリアとアジア属州で構築したもののように見えるのであるが、他の属州でもその設立当初から存在していたのであり、それ故に属州全般で収穫高とは連動していない固定額の使用料の支払いという形で、諸ゲマインデ自身に割当てられた税というものが、属州の土地に対しての唯一の課税のやり方だったのである。
94) Ceteris impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispaniae et plerisque Poenorum.
[更には(シチリアとアジア属州以外の属州でも)課される土地使用料は固定額であり、その税はヒスパニア(スペイン)でも、また大部分のアフリカでも課された。]
しかし以上のような結論は少し早まったものであるかもしれない。例えばサルデーニャ島では反対の例が知られている 95)。
95) リヴィウス、36,2,13。同様にスペインにおいても1/10税地が存在しており、C.I.L.,II,1428 の碑文によれば、皇帝クラウディウス≪在AD41~54年≫が≪ケンススを行った≫監察官としてAD49年に記録している。≪実際のケンスス自体はAD48年。≫
しかしこのことは次のように解釈することが出来るだろう。つまり帝政期の始まりまでは、課税の発展傾向は次の方向に向かっていたということで、それはその属州に従属する諸ゲマインデに対して、税徴収に関しての自治権を与えそしてその税徴収の総額を固定化しようとすることである。≪面倒な個々の税徴収は諸ゲマインデに任せ、ローマ国家としてはその総額だけをもらえれば良かった。≫それについての例としてはアウグストゥスがガリアに対しての基本法の制定時に、そういった土地の年当たりの使用料(税)をその属州としての総額4千万セスティルティウス≪アウグストゥスが大型化した黄銅貨で 2+1/2 アエスに相当≫で導入しようとした際に 96)、個々の納税義務者の集団を分類する作業はローマの行政当局は全く関与しておらず、その分類はただ諸ゲマインデと諸種族に分ける、ということだけが行われていた可能性がある。≪参考:アウグストゥスは共和政期に属州長官となったものが税徴収のルートに入ることで中間で不当な利益(ピンハネ)を得ていたのを直接ローマに納入させるようにしている。≫
96) エウトロピウス、ローマ史概説、6.17。スエトン、De vita Caesarum, 25。
同様により確かなこととしてもちろん次のことは妥当であろう。つまりローマの国家の行政当局は税徴収に関する管理権を放棄したなどということはまったく無く、行政の根本原則が変わっていくのに合わせて、税徴収に関する自治権を取り上げることになった、ということであり、それについては既に見て来たし、また後述の箇所でも見ることになる。
アフリカにおける税の現金納入義務者
キケロが述べている箇所に拠れば、固定額の現金による税が課されていた属州に含まれるのは、大部分のアフリカ属州(”plerique Poenorum”)≪Ponenorum = フェニキアの、の意味は元々カルタゴを含めて北アフリカでフェニキア人が開いた都市、地域ということ≫もまたそうであった。アフリカ属州において知られていることとしては、そこにおいてポエニ戦争の後に7つの civitates liberae et immunes [自由でかつ免税の都市]が存在していたということで、それはウティカ≪Utica、現代のチェニジア、アフリカでもっとも古いローマの植民市≫、ハドルメトゥム≪Hadrumetum、チェニジアの港湾都市スースの古称≫、タプスス≪Thapsus、現代のチェニジアのベカルタの近くの港湾都市≫、レプティス≪Leptis minor (Parva)、現代のチェニジアのレムタ≫、アチョラ≪AchollaまたはAchilla、Achulla、現代のチェニジア東岸の港湾都市≫、ウセリス≪Usellus または Uselis、Usellis、サルディーニャ島西部の都市≫とテウダリス≪Theudalis または Theudali、チェニジアにあったローマの植民市≫の7市である。これらの都市は税支払いが完全に免除されていた。それに対してその他の都市ゲマインデはアフリカでは存在せず、全ての他の諸ゲマインデ団体はポエニ戦争の後に解体させられた 97)。
97) アッピアノス、ポエニ戦役、135:”κ α θ ε λ ε ῖ ν ἁ π ά σ α ς”[徹底的に破壊する]≪該当箇所のChatGPT4o訳:彼ら(元老院の使節)は、カルタゴでまだ残っていたものが何であれ、スキピオの指揮のもと徹底的に破壊することを決定した。そして、誰にもカルタゴに居住することを禁じた。その際、特にビュルサや「メガラ」と呼ばれる場所に住む者には呪いをかけた。ただし、土地を訪れることまでは禁じなかった。(但しスキピオがカルタゴの農地全てに塩を撒いて二度と作物が獲れないようにした、という伝説は有名であるが、それを証拠付ける資料は戦争後すぐのものは残っておらず、後世になって言われたこと。そもそもグラックス兄弟がそのすぐ後にカルタゴに入植を進めたというのと矛盾する。)≫
アフリカにおいて国家に直接対抗する位置に置かれたのは、[もはやゲマインデや都市ではなく]ただ個々の人間集団であった。そういった人間集団の一部を成すのがグラックス兄弟の改革によって実現したカルタゴへの植民者であり、その者達は土地改革法によって viritane Assignation [小規模な非定期的な土地割り当て]によってその地に移住した(モムゼン C.I.L. I. p.97):その者達は税を免除されていた。
また免税の耕地の別の例として確かなものは、スキピオによってマシニッサ≪Masinissa、BC238~BC148年、第二次ポエニ戦役でローマに協力した功績でスミディア王となった。≫の後継者達≪マシニッサの死後、ヌミディアは彼の3人の息子であるミキプサ、グルッサ、マスタナベルがそれぞれ支配する王国に分割された≫に与えられた耕地かあるいはカルタゴからの投降者に対して割当てられた耕地であり、そしてまたローマ人の居留地であって、イタリア半島でも例があるように、公有地から免税のゲマインデに変更されたものである 98)。
98) 土地改革法の Z. 79. 80. 81。”perfugae”[(カルタゴ軍からの)脱走兵]の国法的な位置付けについては問題が多いように思われる。可能と思われるのは、モムゼンが推定しているように、その者達は自分達のゲマインデを作った、ということである。私にとってより確からしいと思えるのは、大土地所有者[(後の)ラティフンディウムの所有者]と関連があり、その者達は小作人を伴ってかつグーツヘル≪中世ドイツでの大地主≫として歴史に登場してくるのであるが、stipendiarii[現金による納税義務者](後述の文を参照)と同じであり、ただ税は免除されてその土地に留まっていた、ということである。そしてその者達に認められていた土地の所有状態とは、これもまたモムゼンが推定しているように、公有地の所有者ではない。
全てのこの種の所有状態は法的には取り消されることがあるものであり;法によっていつでも行政当局が意のままに処理することが可能だったのであり、そのことから既に次の状況が生じていた。それは土地改革法の規定がこういったカテゴリーの土地の所有者に対する補償について取り決めていたということであり、土地割当てまたは土地売却の結果としてそういった土地の所有権は部分的に取上げられた場合があり、――しかしながらそういった補償が法的に規定されていたという事実は、次のことを示している。つまりその所有状態は少なくとも行政法的には保証されており、それ故に法に基づかないで単なる行政処分によってその所有が否定されるということは許されていなかったのである 99)。
99) このことは私の考えでは、その権利状態は次のような者のそれと同じであり、それについて土地改革法が次の箇所で言及している(Z. 91):Quibuscum tran]sactum est, utei bona, quae habuisent, agrumque, quei eis publice adsignatus esset, haberent [possiderent fruerentur, eis … quantus] modus agri de eo agro, quei eis publice [datus adsign]atus fuit, publice venieit, tantundem modum [agri de eo agro, quei publicus populi Romani in Africa est, quei ager publice non venieit, … magistratus commutato.
[その者達について次のことが行われた。その者達が持つ財産、及びその者達に公的に与えられ割当てられた土地を所有、占有、利用することが出来る、とされた。その者達に公的に与えられ割当てられた土地が公的に売却される場合は、その土地と同じ面積の別の土地を、ローマ人民のアフリカにおける公有地の中で公的にまだ売却されていない土地を、交換として土地売却担当官が与えるものとする。]
モムゼンが推定しているのは、ここではその者達との間で課税方法について協議され、取り決めがされた、そういう者達について扱っているのであるということである。私が信じたいのは、ここでは(納税義務のある)公有地の占有人達を扱っていて、その者達について行政の手法においてその所有権が整備され、その結果その者達は納税義務という点において、カルタゴ軍からの脱走兵と同等に扱われたのであるということである。その者達は stipendiarii (後述の文参照)ではない。何故ならばその者達の土地はローマ人民の公有地だからである。土地改革法の Z. 92/ 93 は通常の占有について述べている。そういった土地について公有地の貸借管理人は[その占有を]法的に無効にすることが出来た。監察官による公有地の賃貸しと不安定な公有地の占有への認可が根本的に全く同じことであるのは、ここでは極めて明白である。
納税義務のある所有形態として我々は先の箇所で ager privatus vectigalisque の永代貸借人と取り消し可能な ager publicus の賃借人について見て来た。しかしながら更に別のカテゴリー 100) として存在するのが “stipendiarii” [現金による土地への税の納入を義務付けられた者、そういう土地の占有者]である。
100) しかしながら注釈 99 も参照すること。公共の放牧地についてはここでは扱わない、何故ならばここでは単に色々な所有状態について論じているからである。
この現金による納税を義務付けられた諸ゲマインデについて非常にしばしば耳にする一方で、土地改革法においての表現はゲマインデのことなど何も言っておらず、現金納税を義務付けられた諸個人の土地所有についてのみ言及している 101)。
101) 土地改革法の Z. 77: II]vir, quei ex h. l. factus creatusve erit, is in diebus CL proxsumeis quibus factus creatusve erit, facito, quan[do Xvirei, quei ex] lege Livia factei createive sunt fueruntve, eis hominibus agrum in Africa dederunt adsignaveruntve, quos 78. stipendium || [pro eo agro populo Romano pendere oportet, sei quid eius agri ex h. l. ceivis Romanei esse oportet oportebitve, … de agro, quei publicus populi Romanei in Africa est, tantundem, quantum de agro stipendiario ex h. 1. ceivis] Romanei esse oportet oportebitve, is stipendiarieis det adsignetve idque in formas publicas facito ute[i referatur i(ta) u(tei) e r(e) p(ublica) f(ide)]q(ue) e(i) e(sse) v(idebitur).
[2人委員会は、この法律によって決められ任命されたのであるが、その委員会が決められ任命されてから150日以内に次のことを行わなければならない、つまりリウィウス法≪Lex Livia de coloniis deducendis(植民市建設についてのリウィウス法)、BC122年≫によって決定・任命されているかされていた10人委員会が、アフリカにおいて土地を与え割当てた者達について、その者達の土地がこの法律によってローマの人民のものとされるか、あるいはされていた場合は、その土地について税金をローマの人民に対して支払うことを義務付け、…≪もしその者達の土地が何らかの理由で没収された場合は≫ その土地がアフリカにあるローマ人民の公有地である場合、その税金分に相当する大きさの土地医をそれらの納税義務者に与え割当て、そして公共の測量図に記録し、公益と信義の観点から適切に実施されるようにしなかればならない。]
こういった所有関係についての法的な所有権を確認しようとした場合、まず最初に受ける印象は、この税金付きの土地の仕組みが、公有地売却担当官による公有地賃貸しのために使われる公有地の利用促進を目的として構築されたのではない、ということである。私がそこから考えたのは、この種の課税は一般論として公有地に対する使用料ではなく、純粋な土地税として理解すべきであろう、ということである。他面、次のことは疑いようもなく確かである。つまりこの種の税金付きの土地の法律上の所有権がローマ人民に属している、と見なし得る、ということである。というのも土地改革法で規定されているのは、この種の土地については部分的には売却と割当てによって処理されるということで、そのためこの土地の所有状態については[永代貸借が多くの場合認められていた]ager privatus vectigalisque とは反対に、いつでも取り消されることが可能だった、ということであり、そこから結果として出て来たことは、まず第一に、土地改革法の規定によればこの種の耕地については公的な測量図を作成して登録しなければならないという義務である。補足的に書かれている”utei e re publica fideque ei esse videbitur” [公益と信義の観点から]という表現から考えられることは、測量図の作成については十分な慎重さをもって行う必要性があったであろう、ということである。実際には、通常の測量方法であるケントゥリアを使ったものはこの場合は採用されていなかった。先の箇所(第1章)で既に測量の方法については論じて来たが、ここで言及されている測量の方式が per extremitatem mensura comprehendere [全面積が測量されているが区画に分けられておらず、その境界が自然物{川など}による土地]であり 102)、その場合はより広範囲での耕地の法的な定義付けがおそらくは地図上に記録されている可能性がある。
102) フロンティヌス p. 5, 6 : eadem ratione et privatorum agrorum aguntur. [同じ方法で個人所有の土地の測量も行われる。]
ager privatus vectigalisque と ager stipendiariorum を区別するものは、前者は[一度契約したら]没収されることがない、ということである。それに対して後者を通常の賃借耕地から区別しているのは、所有についての期限が定められていないことと、そして一旦譲渡された土地の法的な地位の固定とそれによって監察官による賃貸し地としての管理下に置かれない、という2点で国家が課税対象とする他の土地一般から違っているということであり、更にはまた同様に耕作という本来の目的以外には全く使用出来ないということで、それは[抵当設定するといった]法律上の手段も含んでおり、またそれに関する訴訟も行うことが出来ない、ということである。そのことから私にはこの状況は次のように把握出来ると思われる。それはローマの国家に対しての解体された諸ゲマインデの位置に大地主[グルントヘル]が登場して来ている、ということであり――というのは多数の小区画の土地所有者に対する[まとめての]土地の譲渡においては、それらの者がシチリア島での例のように無条件に法的に賃借人として取り扱われた、ということは考え難く、――またこういった地域が本来であれば諸ゲマインデにされたであろうやり方と同じように、ある決まった継続的な税支払いを現金でかあるいは農作物、アフリカでは穀物で、行うということを引き受けることと引き替えに譲渡されたのであると。
以上のことによって譲渡された所有地はローマの領土として取り扱われたのであり、従ってそういった大土地所有制度[グルントヘルシャフト]での所有物については正規の法的手段による訴えを起すことは出来ず、そういった土地に対してはただ公的測量図に基づく行政上の処理だけが許されていたのであり、その処理については測量人達は controversia de territorio [領土についての争い]として知っており、第1章で詳しく述べたサルディーニャ島の Patukenser と Galienser ≪どちらもサルディーニャ島に住んでいた種族≫の間での土地の境界を巡る争いについてその語が使われているのを見て取ることが出来るが 103)、それは結局は公的測量図に記載された境界について、行政処分としての現物執行と土地の返還という結果につながったのである 104)。
103) C. I. L., X, 7852
104) この制度が実際の所、本質的な傾向として見た場合に際立って特徴的なことは、しばしば他の関連で引用して来たフロンティヌスの著作の次の部分(ラハマンの p. 53):
Inter res p[ublicas] et privatos non facile tales in Italia controversiae moventur, sed frequenter in provinciis, praecipue in Africa, ubi saltus non minores habent privati quam res p[ublicae] territoria: quin immo multis saltus longe maiores sunt territoriis: habent autem in saltibus privati non exiguum populum plebeium et vicos circa villam in modum munitionum. Tum r[es] p[ublicae] controversias de iure territorii solent mouere, quod aut indicere munera dicant oportere in ea parte soli, aut legere tironem ex vico, aut vecturas aut copias devehendas indicere eis locis quae loca res p[ublicae] adserere conantur. Eius modi lites non tantum cum privatis hominibus habent, sed ed plerumque cum Caesare, qui in provincia non exiguum possidet.
[イタリアにおいては公共の土地と個人の土地との間で、争いが容易に起きることはないが、しかし属州、特にアフリカではそれがしばしば発生する。そこでは[測量されていない]森林や放牧地が私有地として公共の領域よりも大きくなっている:いや実際にはそれどころか、多くの者にとってはその広大な森林や放牧地の方が公共の領域よりもはるかに大きい:しかしながらそういった私有の森林や放牧地には相当数の平民が住んでおり、またそういった平民の家の周りにはまるで砦を成しているかのように村落が形成されている。同様に諸ゲマインデは領域についての争いを起すことが良くある。それはある土地について、その一部だけがローマによって与えられて割当てられたとすべきだと宣告したり、村から徴兵したり、または輸送を行わせたりそのための多くの者を徴用すると宣告する場合であり、その土地を自分のものだと主張しようとする場所でそれらのことを行うのである。こういった土地に関する訴訟事は、個々の人間が所有している土地に関してだけでなく、多くの場合属州において少なからぬ土地を占有している皇帝との間でも起こる。]≪res publicae は通常は共和国であるローマのことであるが、ここでは文脈から、「諸ゲマインデ」、つまり元々その土地にあった地域集団、と解釈した。≫
同様に当然のこととして大土地所有制度[グルントヘルシャフト]の中でのその他の土地の権利に関することの調整はその大土地の地主の責務であったに違いなく、しかし常にそこから除外されるのは、また課税されている諸ゲマインデにおいては、当然のことながらそういった調整は属州総督の管轄であったということであり、それはローマ国家の利害に関わることが問題になっている場合や、あるいは関係者の請願に応じてそういった案件に関わることになったのである。そういった類いの土地所有について相続と売却が可能であったということは非常に疑わしく思える。複数の土地区画の一部を切離して売却することは、ローマの国家に対しては存在しなかった行為として見なされたが、それはその売却者が地主への税金支払いが出来なかったために拘禁された場合に限ってのことである。その結末がどうなったかは最終章にて取上げる。相続人への土地の所有権の移転はそれとは違って疑わしく思われるものではなかった;国家の側から見れば、税金さえきちんと支払ってもらえるのであれば、国家が行う調整の中身としては相続関係者の要請に基づいてそれを認可する、ということだけであった。おそらく可能であったと思われることは、売却にあたっては元々所有権の確認が必須だったということで、そこからおそらく生じたのは後の永代小作制[Emphyteuse]においての領主への、公有地の優先買取権を行使しなかった場合の手数料の支払いである。というのは後の時代には次のことが見出されるからである。それはゲマインデの団体には明らかに許されなかった元老院によるアフリカにおいての大規模な土地所有について、それが封土を与えられた者の名簿に基づいて、それぞれの者に対して土地が与えられており、その中では該当する地主に帰属する権利として、特に非定期的な市(いち)の開催権が記録されており 105)、そのことから考えて自由な売却が許されていた可能性は、全体のこの制度のその他の部分の状況から見て、ほとんど無かった、と言えよう。
105) C. I. L., VIII, 270 のBeguensis ≪不明、おそらく北アフリカの地名≫の放牧地での市(いち)について、参照:ヴィルマンス≪Gustav Wilmanns, 1845 ~ 1878年、アフリカの碑文の研究者≫、Ephemeris Epigraphica, II, p. 278。
その他の点では、そういった名簿は全ての土地割当てに対して公式の測量図に添付すべきとされた公文書と言える。ここにおいてこの制度で生み出された土地所有者の全体像を一言で言えば、これまで記述した理解の仕方が正しければ、納税義務者であり、ここでは従って大規模な永代貸借料の支払い者達、それについては ager privatus vectigalisque の制度においての実質的な土地の所有者であったろうと推定して来たのであるが、その者達に類似した者達であり、しかしながらただ法的には所有者としてそこまではっきりと確立されたカテゴリーではなかった、ということである。次のことは特徴的である。つまり、この手の小規模な土地の所有者について、それが属州の元々の住民であろうとローマ市民であろうと、同じく取り消し可能な賃借人として扱うことは、一方では大規模な地主は国籍によって区別されていたのであるが、両方を小規模地主としてまとめて考えた方がよりよく理解出来る、ということである。この制度についての結論については、つまりここで主張して来た小作農の個人的な権利設定のための課税義務付き土地所有という法的概念の形成があったに違いなく、かつ実際にそうであったと言うことであるが、それについては最終章で論じる。―帝政期の時の経過の中で、都市ゲマインデにおける属州の土地の大部分は、そして取り分け植民市においても、組織化が進んだのである。―
課税業務においてのゲマインデ自治のその後の運命
これまでの詳述の後で、ローマでの元首制≪初代皇帝アウグストゥスは自身をプリンケプス=第一人者と呼んで公式には皇帝とは称さなかった。このため帝政ではなく元首制と呼ぶ場合がある。≫の始まりまでの時代について、次のことが確からしいのであれば、即ち一般論として、そして例えばアフリカの属州での特別な事情から見て、発展傾向として属州のゲマインデの固定化とそれに伴った税収入の分配においての(相対的な)自治が、そのゲマインデ独自の税と同様に国税においても進行したということであるが、その場合でも帝政期が更に進行するにつれて、本質的には全く逆の発展が始まっていた。例えばアジア属州では疑いなくカエサル以降は課税地であった一方で、それ故に諸ゲマインデ自身による税徴収が復活していると、ヒュギヌスは何度も言及して来たある土地税についての箇所である p.204 で述べているが、そこでは不正な占有の結果として地主達の間での訴訟が起きていたらしいのであるが、それもヒュギヌスは土地の測量方法に関連付けているのであり、そこから分かるのはここにおいてはローマ国家による土地への課税がいずれにせよ相当程度までその時点で成立していたに違いない、ということである。概してヒュギヌスは ager arcifinius vectigalis ≪未測量であるが使用料を課せられた土地≫について語っており、そのカテゴリーがローマの測量上の分類に追加されたのであるが、それが追加されたのは、それが全くもって常に繰り返されるような現象として見て取れるものであったからに違いない。アウグストゥスによる測量もまた、土地税についての規則に拠ったという以外の意味は全く無かったのである。ごくわずかな文献資料が、それは土地税の成立に関したものであるが、どういうことかというと、税の対象である土地を、ある財産の集合に対して一定の額を課税する中での一つの構成要素として関係付けるのではなく、それ自体に対して課税するのであり、それはカラカラ帝≪カラカラ帝は属州民にもローマの市民権を大盤振る舞いした。≫よりも先の時代に成立したのであるが、今やそれは例外なく植民市に対して適用されたのである。まさにその例であるのが付図1として添付したアラウシオの碑文[地図]であり、更には新カルタゴの碑文もそうであり 106)、同様にシリアのカイサリア≪現在のイスラエルの領土内にあったカエサルにちなむ植民市≫ 107) に関しての学説彙纂の de censibus のタイトルの箇所もそうである。
106) 注釈57参照。
107) Divus Vespasianus Caesarienses colonos fecit, non adiecto, ut et juris Italici essent, sed tributum bis remisit capitis; sed Divus Titus etiam solum immunem factum interpretatus est. D. 8, § 7 de cens. 50, 15. [神君ウェスパシアヌス帝はカイサリアを植民市としたが、しかしイタリア権≪ローマ以外の都市に与えられた特権で、免税と住民へのローマ市民権の授与が行われた。≫は与えなかった。しかし住民に対して人頭税は免除した;しかし神君ティトゥス帝はまた、そこの土地も免税になったと解釈した。]
更にはイタリア権と土地への非課税が法的な要件として結びつけられていたのであれば、それはある土地がクィリタリウム所有権の法的有効性についての要件を満たしているのと同じことであったが、そしてそれらが実際に導入されたのであれば、更にはこの権利がまた疑いなく圧倒的に多くの事例で植民市に対して与えられたのだとしたら、その場合は次のことが想定出来よう。つまり地所の分配と測量が、それは間違いなく(第2章)帝政期における植民市での変化の実際的な中身となっていたが、具体的な土地区画に対しての課税額の固定化とまたはパンノニアでの状況からの類推としてある決まった土地の品質等級毎の1ユゲラ当たりの[固定]税額と、更には土地税に関しての国家の徴税義務の制限、それらと結びつけられていた。次のことはまた目的に適合していた:ローマの市民は[彼らにとって都合が良かったという意味で]より良き帝政期には、理論的なローマ市民の税として考えた場合、より一層直接税へと関係付けられたのであり、ある市民が土地を所有していて、そしてその土地に対して土地税が課せられていた場合は、あるいはその市民の土地に小作人が居た場合は 108) 、その市民は人頭税支払いの義務もあり、小作人への人頭税は地主としてその市民が立て替えて払っていた。
108) こうしたケースはアフリカにおいて起こったことであったに違いない、そこでは第三次ポエニ戦役の後に人頭税が一般的に課せられるようになっており、そうしたケースであった。
――その他の点についてはこうした状況がどのように発展したかについては知られていることが少なく、ただ皇帝直轄の属州に対しての属州税[provinciae tributarie]についての記述から推測することが出来るのは、そこでは土地に対しての課税の規制が、パンノニアに見られるような方向に向かって、非常な速度で進んでいた、ということである。個々の課税の実情が非常に多様であったことはしかし、それは実際に存在していた課税システムからの類推で結論付けられるように、ずっと継続してそうであったに違いないのであり、そしてディオクレティアヌス帝≪在位284~305年。四分割統治を初めて採用するなどの改革を進め、「3世紀の危機」という状況をひとまず乗り越えた。≫による改革がそれに続いてのであり、それについては新テオドシウス法典の 23 が述べている通りであるが、そこではヌミディアに対する課税の規制において様々に異なった課税方法を統合したが、しかしそれでもお互いに異なる3種類の方式を残した:固定額の現金による納税、annona ≪一年毎の穀物等の収穫高に応じた課税≫と capitatio ≪その土地で耕作する農民の一人当たりいくらで行う課税≫の3種である。特に、非常に良く知られているカラカラ帝によるローマ帝国住民[で属州民などこれまでローマ市民権を持っていなかった者]へのローマ市民権の授与は、ロードベルトゥスがその背後で起こったと推測しているような、急激で根本的な変化をもたらしたりはしていなかった。その市民権の授与は税制上の意味としては、少なくとも土地に関するものについては、次の点においてはるかに進歩した、とは言えないものであった。それはつまり、その授与がそれまで免税でないしは課税であった諸ゲマインデの土地について、その土地の占有を行うことを許したり、そしてそのことによって課税に関する別のやり方を採用したり、あるいは新しい税を作りだしたり、また同様に諸ゲマインデ自身においてのその成員への課税についての非常に大きな相違を均等化する、といった点である。その諸ゲマインデへの課税と諸ゲマインデ自身の課税についての改革はしかし、既にアウグストゥスが着手しており、その後もそうした改革は西ローマ帝国の滅亡の日まで粛々と進められていたのである。しかしもちろんローマ市民権授与の結果であったのは、その際に土地に関する申告のやり方についての統一原則を作り出す、ということが試みられたことであり、その具体的な内容としては、個々のゲマインデにおいての土地所有権について、土地をある者が占有している場合には、それをケンススに登録することが義務付けられた、ということである。
ウルピアヌスの時代までの土地税
こういった自己申告は、それはウルピアヌスがまさに彼の時代において、丁度ロードベルトゥスが正当な理由があって推測したように、彼によって出版された法律書である de consibus ≪学説彙纂の中に収録されている≫の中でこれらの新しい申告方式について引証≪自分の論の根拠として引用すること≫を行っているが、そういった申告の仕組みは何よりも次のことと関連が深かった。それはヒュギナスの記述に従えば、使用料[土地税]支払い義務が課せられた属州における土地区画に対して適用されたに違いない、ということである。ウルピアヌスがその著書で引証に使ったものは 109)、以下のようなものと考えて間違いないであろう。つまり耕地の面積[ユゲラ数]でその時点で10年以内に耕作が開始されたもの、ブドウの樹の本数とオリーブの樹の本数、そして植え付け済みの耕地の面積[ユゲラ数]、牧草地、牧場と森林の面積である。
109) D.4 de censibus 50, 51。
そしてウルピアヌスが更に次のように述べている場合には:”ominia ipse, qui defert aestimet“[申告を行った本人が全てを評価すべきである]、そこから想定されることは、属州の住民達が、ローマの市民税の古くからの自己申告原則について、耕地の使用方法についても自己申告が可能とされて、申告者に占有が許されていた耕地の面積に関しての何らかのもっと概略的な規則と結び付けて、属州による土地評価に委ねてしまおうと試みた、ということであり、その評価に基づいて昔の tributum の税のように、単純に土地の評価額の単純合計[simplum]またはその2倍の額[duplum]等々に対する千分率[‰]という税率で課税することが出来るようにしたのである。ロードベルトゥスは正当に、この点についてLampridus 110) ≪6人の皇帝についての伝記の内の一つ≫からの引用部について確かと思われる解釈を述べている。
110) Lampr. Alex. 39 :Vectigalia publica in id contraxit, ut qui X aureos sub Heliogabalo praestiterant, tertiam partem auri praestarent, hoc est tricesimam partem. Tuncque primum semisses aureorum formati sunt, tunc etiam cum ad tertiam partem auri vectigal decidisset, tremisses …
[彼≪アレクサンデル・セウェレス帝、在位222~235年≫は、元々ヘリオガルス帝≪在位218~222年≫の時代には(土地税として)10アウレリス≪金貨で、1アウレリスは25デナリ≫を支払っていた場合、それを 1/3 の 3.33 アウレリスの支払いへと減税した。これは元々の 1/10 税から考えれば 1/30 税になった、ということである。それからその支払いのためセミッシウス金貨(1/2 アウレリス)が初めて鋳造され、また地代(土地税)が 1/3 に減額された際にはトレミッセス(1/3 アウレリス)金貨も鋳造され…]
[こういったラテン語文献の解読では]常にあることだが、この箇所を本当はどう解釈すべきかという判断を保留とした場合、その場合でも次のことはまず確かであろう。それは最初の文で言われているのは、金貨で支払うように決められていた税が 10 アウレウスから 3.33 アウレウスへの減税が行われ、それはつまり地所の課税基礎額の3.33 % への減税が意図されていた、ということである。しかしながらこういった政策がどの範囲にまで使われたのかや、その実施の程度については非常に疑わしいことが多く、それは先に引用したヌミディアに関する箇所が示している通りである。特にこの政策は、実際に即して上記で簡単に説明した意味で考察した場合、それは課税対象物について実際上個々のものの価額の見積もりを課税される側の自己申告によって行おうとした試みであるが、それは貫徹されることはなかった。というのは、ディオクレティアヌス帝が制定した規則の中ではそのことは全く触れられていないからであり、そしてそのことと矛盾していないのは、ウルピアヌスが述べているように、この新しいやり方では平均的な土地の価額が長期に渡って保持されるということを前提としており、つまりは土地台帳に記載された土地という財産の状態を継続的に固定化することをおそらくは意図していたのである。ティオクレティアヌス帝の改革でも引き続きこういった考え方に結びつけられていたが、法的史料が示すように、次のような考え方は消失してしまった。それはつまり、法的には、全ての土地所有において、他の負荷も課されている者自身が 111)、土地税も課されるべきという考え方である。
111) 参照、例えばテオドシウス法典 13 de senat[oribus] 6, 2, そこでは特に navucularii の財産の自由が定められている。
ディオクレティアヌス帝による土地税制度
ディオクレティアヌス帝による税制は、今さら論証するまでもなく、土地台帳を作成するというのと同じ試みから始っており、その土地台帳は土地への課税をその台帳に記載されているその土地の価額に対して何%かを掛けるという単純な税額決定法を可能にしていた。この目的のために新しい税制は juga ≪土地の生産力に比例して設定された単位となる地積≫と capita≪耕作者一人が決まった時間で耕作出来る面積≫という課税のための面積単位を作り出し、それぞれが同じ価額を持つようにした。この2つの caput [カピタティオ]と jugum [ユガティオ]は常に併用され完全に同じものとして使われ、そのために二つが全く同じ金額であったことについては事実上何の疑いも持ち得ない。しかしながらこの2つの課税用の面積単位がどのように作り出されたかは、難しい、完全に正しい答えを得ることがほとんど不可能な問題である。一方でこのことについてはっきりと述べている情報 112) が存在しており、それによると、ユガティオの場合はそれぞれの土地の等級に応じて異なった単位面積が測量で決められ、それぞれ等級毎の異なる単位面積がお互いに価額として等しいものとされた。≪例えばオリーブ畑の単位面積は小麦畑の単位面積より小さい、など。≫他方ではカピタティオについてはいくつかの所見が存在するが、それらはカピタティオを何らかの課税対象となり得る対象物と同一視することは考えにくいと思われる、といった説明をしている 113)。
112) モムゼンの Hermes III, 430 の中に翻訳として収録されている、いわゆるシリア・ローマ法律文書[syrisch-römischen Rechtsbuch] より。
113) 特に Eumenii gratiarum actio 11。≪EumeniusのPanegyrici Latini、ラテン語称賛演説集。≫
ここでほとんどユガティオとカピタティオの意味を無条件に同一視することから議論を始めたが、その場合には矛盾が生じ、それはかなり力ずくな方法でもない限り解決出来ないように思われる。もしかすると真相についての確からしいと思われる推測を次の場合にはすることが出来るかもしれない。それはディオクレティアヌス帝によって導入された課税方法について、それがどのような先行物から作られたのかということと、税制上の関係でその方法がどのような社会状態に対応させられていたに違いないか、ということを考えてみる場合である。
“jugum”という表現は「一人の一日分の仕事量」という意味で、共和政期と帝政期の早期に夫役の概念に結び付けられて登場して来ていたが、その表現は個々の耕地について、ある部分はその者が属するゲマインデに対して、別の部分はその土地の地主に対する関係で税[使用料]を課せられていた、ということである。lex coloniae Genetivae 114) ≪カエサルが作ったスペインの Genetiva Iuria の植民市法≫に示されているように、公的な賦課については、特別な原則によって規制された兵役義務は例外として、ローマ市民による植民市の初期の形態においては、その植民市の市民とその家族に対しては、手作業による夫役と牛馬を使った耕作の夫役が次のようなやり方で課せられていた。つまり1日の作業量に対して、同じく一人当たりの人員に対して、国家当局の要求に基づいての何らかの現物が固定量で課せられていたに違いない。植民市というのはいわば首都ローマのコピー都市でもあったので、こうした課税方式はローマでも全く異なるところなく実施されていた。ウルソの法律では≪前述の lex coloniae Genetivae の中の1章。ウルソは現代でのスペインのオスナであり、Genetiva Iuria が存在した場所≫――同じことがこの時代どこの植民市でも行われていたのであるが――一人当たりの一月の、そして一日の作業量当たりの、最大日数と最大時間がそれぞれ定められたのである 115)。
114) C. 98
115) 一人当たり月5日、一日あたり3時間。
家父はまたいずれにせよ、耕作能力がある場合には、自分の作業と、かつ家父の指示に従わなければならない成年の人員――[成年の]子供・孫達、奴隷――の作業をそういった夫役に割当て、そしてまた手仕事による夫役も行わせることになった。全く同様に大地主制において地主によって土地の使用料を設定された農民達も、彼らの作業能力に対する一定の割合で設定された夫役とかつまた手仕事による夫役について彼ら自身の家族と更に家族に従属する人員に対して義務付けられた 116)。
116) C.I.L,. VIII, 10570;参照、モムゼンの Hermes XV, p.385ff, 478ff。
ゲマインデが貨幣経済への移行を欲して、自然物による貢納の要求を[貨幣による]税としての支払い要求に置き換えを図った場合は、あるいはそれが必要不可欠であった場合は、何らかの必需品でそれが自然物の貢納では徴収され得ないものについては、それらを提供する[ための労働]義務を課すことで代替手段とし、その結果としてまず行われた可能性があるのは、次のようなやり方である。それは1日の作業量(jugum)と同じく一人当たりの人員(caput)当たりの義務を果たすために、ある一定額の現金支払いやその他の物の納付が行われるようになった、ということである。実際の所は、次のことは除外されていない。つまりローマにおいてもまた、この手の課税方式は一旦採用されたのであり、少なくともタルクィニウス王≪ローマの王政時代の最後の王。在位BC535~509年。圧制で民を苦しめたことで有名。≫が試みたような、課税方式で全ての市民が[働けない老人や子供も含めて]一人当たりで等しく課税された 117) という暗い圧制の残滓を同類のものとして思い起こさせるのである。
117) Dionysios 4, 43の確かに非常に混乱している箇所にて。また独立の未成年(孤児)と被後見者と寡婦についての特別な意味付けは、課税を成人のローマ市民の夫役義務と根本的に結び付けることによって説明される。
またそのような課税方式の変更は、かつて、つまり耕地ゲマインシャフトの成立の際に、常に考えられるものであったのであり、ケンススによって利益を生み出す能力があるとされた最古の対象物は、実際の所は荷物を運ばせるための牛馬など、車を引かせる牛馬など、そして奴隷、それらと並んでもちろん自由ではあるが暴力によって従属させられた市民達 118) である人間である。
118) また homo liber in mancipio [隷属状態の自由人]、つまり日雇い作業に貸し出された家の息子。
事実上はこうした変更された課税方式は、フーフェの耕地の中で個々人に与えられた持ち分についての権利に基づいた課税と比較した場合、最初から本質的には異なったものではなかったのであろうし、というのはその新しい方式では夫役と本来の個々人の耕作の維持という観点でバランスを取ったものであったからである。ケンススに登録された財産のリストが実際には元からの土地所有の情報を含んでいなかったとしたら、それはただ夫役を課する上で役立っただけであり、そのことと符丁が合っているだろうことは、ただ夫役の義務を負うことが可能な財産≪例:奴隷≫のみがケンスス登録の対象とされたことである。しかしながら次のことは非常に確かである。それは昔から相続人を登録することがフーフェの農民による報告として行われていた以外に、このことについてまたケンススへの登録も必要とされた、ということである。もしかするとケンススのリストというのは[フーフェの共同体単位で]相互に独立したものとして作られていて、それは後の時代の有権者リストや納税者リストと同様であった。というのも相続人登録というのは、まず第一に政治的な権利の継承という意味合いが強かったからである 119)。
119) というのは植民市においては、ユガティオとカピタティオに基づく夫役については、そもそもそこの住民への税はいずれにせよローマにおいて元から存在する tributum という税の課税のやり方を真似する形で課されたのであり、公的な業務の必要性を満たすために、その業務を行わせる対象者のリストを作成せよ、という指図については、そういったものがあったとしたら、植民市では重複した作業となっていたに違いない。
しかし明らかに既にかなり早期からフーフェでの土地の権利という尺度に対して関係づけられていたのである。ディオクレティアヌス帝の税制において、juga に基づく負担というものが再び登場した際には、それはまず第一には[フーフェの]耕地所有面積に比例した形の税だったのである;そのため実際に何が起きたかというと、1日の作業量という原則に忠実に従おうとした場合、その計算根拠に使われたのは本当の個々の農民の作業実績に基づいた[平均的な]作業量ではなく、[何らかの取り決め基準に基づく]仮想的な作業能力だったのである。大地主達は疑いなく、その配下の小作人に対して行政当局からの命令に基づいて――そのことについては最終章で再度取り上げるが――作業夫役を課したのであるが、その際にも同様にこうした仮想的な計算方法が使われていた 120)。
120) 一度作業夫役が課された植民市は、何らかの理由でそれに充当すべき実際の労働力が不足することになっても、それを理由に夫役を免除されることはなかった。このことと符合するのは、後に植民市に対して[夫役を課す上での根拠となっていた]”peculium” [個人資産]の売却が禁止された、とうことである。
土地所有面積に比例した課税の他に存在していた税は、またローマにおいての元々の税である tributem であった。その、より後の時代においての実態は、1000アウレウス当たりで――「一人当たり」[caput]121) で――その市民の持つ課税対象の資本について、それはその市民の生業に基づいてケンスス上で確認されるものであったが、必要に応じてその都度異なる金額で課されていた。この税制にて、土地台帳上での評価額の1,000アウレウスという金額は、丁度ケントゥリア[百人組]の中での軍事的な階級と同様に、土地財産に対する公的な評価レートに対して相当分の土地を言っているのであり、そのことは既にフシュケ≪Eduard Huschke、1801~1886年、ドイツの法学者≫(Ritters u. Schneiders krit. Jahrb, XVIIIm P.617)によって主張されている。ただ私はその場合に、それがある決まった面積の土地に対する金銭評価の始まりであった、という考え方は正しいとは思わない。類推出来ることの全ては、むしろ次のことを示唆している。つまりここでは土地の金銭評価をフーフェでの権利に比例したものとして扱っている、ということであり、それはつまり個々人に対してその者が属するフーフェの全耕地の中で、その者に割当てられ帰属した耕地、放牧地、そして他の用益権 122) に比例していた、ということである。
121) フロンティヌス P.364(モムゼンの補完による Abhandl. d. Berl. Ak. der Wissenschaften 1864, P.85):tributorum collatio cum sit alias in capita, id est ex censu …[税の支払いはまたある場合には人数当たりとして、それはケンススに登録してある人数に基づいて…]
Liv. 29, 15, 9. 39, 7, 4 vv.”in milia aeris”[1000アウレウス当たりで]。
122) このことはまた何故古くからの共同経済的なフーフェの農民の用益権に代わって地方の農地の地役権[servitutes praediorum rusticorum]がケンススに登録可能な手中物[res mancipi]≪渥取行為によらなければ所有権の移転が出来ない財産≫として登場して来たかの理由である。
任意の土地区画の所有で、それがフーフェの取り決めに全く関係ないものは、もっとも古い規則によれば、第2章で詳しく述べたように、私法上の保護も受けられなかったし、ケンススに登録することも出来なかった。ようやく Uskapion[土地の時効取得]が許可されるようになった時に、フーフェに属していない者の土地であっても物権的に保護されるようになり、それによってフーフェ制度全体が崩壊し、土地の面積当たりでいくらという評価に基づいた土地の金銭価値への換算が行われるようになったに違いない。フーフェ制度はしかし確からしくは既に耕地ゲマインシャフトの分割の際に、その際には何らかの形での地所の価値評価がまずは必要となったのであるが、それはケンスス制度に対しての基礎となったのであり、その際には農地の分配において、フーフェの成員全員の個々のフーフェの権利が、ある決められた価額である一人当たり 1,000 アウレウス分の土地が等しく設定され、そして各人に地所の評価に基づいてその者に与えられるべき額に合わせて、それに相当する面積の土地が割り当てられ、それ故に 1,000 アウレウスに対してそれぞれの地所の評価額が異なっていたことにより、割当てられた土地の面積もそれぞれ異なっていたのである。この耕地ゲマインシャフトの分割の際のやり方は、それ故にまたティオクレティアヌス帝による税制における jugum の性質でもあったのである。こうした土地の金銭価額評価は、しかしながら次のことを可能にした。つまり財産ではあるが、土地所有としては認められていないかあるいはただ半端な面積の土地区画であって土地台帳に載せるほどの大きさではないものについて、アエラリウス≪ローマの最下層民で兵役に就くことが出来ないが納税義務はある。≫に対して同じ尺度で評価して課税する、ということである。このことが実際に起きたということは次のことから分かる。それはケンススの実施の結果として、トリブスでのゲノッセンシャフトからの懲罰としての追放が、その罰を受けた者へのケンススの原則の乗算的な適用≪おそらくはケンススによってまずそういう半端な土地まで課税対象として調査されただけではなく、更に財産の申告に虚偽があったり、あるいは財産の総額が一定額をし給わせる場合にプレブスからアエラリウスへ降格させられたことを言っていると思われる≫と結び付いていたのが常であった、ということである。そのことから分かるのは、アエラリウス[に降格するような貧しい者]に対しても同じ原則で課税していた、ということである。アエラリウスに属する者達については一人あたり 1,000 アウレウスは現実の土地の面積と同等ではなく、それはむしろ土地台帳上だけの概念的・仮想的なフーフェの土地として見なされた。こうした土地の金銭価額評価に基づく課税方式は、それはそれ故実質的に財産税という性格を持っていたが、疑い無くその発展は非常にゆっくりだったのであり、この発展が一般的に言ってどのレベルにまで達したのかもはっきりしない。こうした課税方式はもしかすると、”capite censi”[ケンススでの人員登録に基づいて]という表現が土地台帳に登録する地所を持っていない市民の存在をほのめかしているように、そうした市民のただ頭数だけを登録し、そしてその者達を土地税徴収の対象にしない場合も夫役を義務付ける対象とする、という手続きとして登場したのかもしれない。以上をまとめて言うなら、tributum というものはいずれにせよ土地所有に対する課税形式であり、それは元々のフーフェでの権利に対しての課税だったのであり、それが後には大規模な土地経営全体に対して適用されるようになったものであり、vectigal のように個々の具体的な面積の土地に対して課される税ではなかった。この課税方式と vectigal の関係に相応しているのは、割当てを受けた私有地の面積と国有地という所有状態の土地[で貸し出されたもの]との関係であり、更に同様の関係としては Hufenschoß ≪16世紀以降のプロイセンとブランデンブルクなどでのフーフェの土地への課税≫と”walzenden Grundstück ≪どの大地主の所有にも属さない自由に売買可能な土地≫への課税の関係が挙げられる。その他、この課税方式はもちろん、不完全ではあるが、一般的財産税と言い表すことが出来る。
属州における juga と capita、そして課税
ディオクレティアヌス帝の改革はローマ帝国全体に対して一般的な課税標準を定める必要性から始まっており、それは丁度カール大帝≪8世紀後半から9世紀後半にかけてのフランク国王、神聖ローマ帝国初代皇帝、「ヨーロッパの父」と呼ばれる≫がそういった標準を彼の帝国の大部分でドイツのフーフェ制度の中に見出したのと同様であったが、その改革は同じものをおそらくは1,000アウレウスの価値を持つ[仮想的な]税制上のフーフェの中に見出そうと試みたのである。≪元々1フーフェの土地とは、一家族がその土地を耕作することで食べていける広さの土地を指していた。≫そこではまず耕作の成果としての juga に税制が結び付けられ、更にそれによって耕作能力の概念にも結び付けられたのである。大地主に対しての課税は明らかに牛馬を使った耕作に従事可能な小作人の数と共に、大地主自体が雇い人を使って行っている耕作、それは大地主制の中に含まれるものであるが、その雇い人の数も基準として行われ、更に地主達は capitatio plebeja [平民に課された人頭税]という人頭税をその者達が所有している奴隷達とその他の手作業を行うことが出来るその大地主制の中の人員の分として支払うことが求められた 123)。
123) 夫役への関連付けは、412年のテオドシウス法典 5 de itin[ere] mun[iendo] 15, 3にて示されており、それによればビテュニア≪小アジアの北西にあったローマの属州≫において道路関係の作業が土地の占有者達に対してその支配の及ぶ所の juga 及び capita の数に比例する形で課されていた。その際にその義務の賦課が一人当たりの一日当たりの作業量ベースではなかったことは、関連個所であるテオドシウス法典 4 de equorum coll[atine][税支払いの公平性について]11, 17が明らかにしており、そこでは一日の作業能力について言及しているのであるが、表題が示唆している通り、しかしながら実際の一人一人の作業量ベースではなかったということは、possessionis jugationisve modus [占有されていて区画分けされた面積に基づいて]という表現から分かる。
耕地において juga に相当する面積を実際に測量するということは確かにこの場合では行われておらず、そうではなくて juga のみが数えられており、その juga は個々の土地ではなく、占有者がそれを全体として占有しているまとまりであった 124)。
124) このことはトラレス≪ギリシア、ローマ、ビサンチン帝国の植民市、現在のトルコのエフェレル(2012年まではアイドゥン)≫の専制がどのように保護されたのかを明らかにしている。(次の注を見よ。)
その土地の品質等級に応じた vectigal[使用料]を支払っていた耕地においては、新たに juga が個々の品質等級毎にある一定数のユゲラが換算表によって等価とされる形で設定され、それからその土地がその地区において測量され(”emesum”)、あるいはより現実的にそれを言い表すならば、何区画かの土地が juga にまとめられたということである。更に諸ゲマインデにおいて税の査定を受けることになった場所においては、それらの諸ゲマインデはそれまで全く税を支払っていなかったか、あるいはただゲマインデ全体から徴収した stipendium [税]のみを支払っていたのであるが、そこの人々は多くの場合、次のことで満足していた。それはそのゲマインデが支払うべき税の総額がある決まった数の simpla [等倍]に等しいとされ、そしてその者達にその徴収が委託された、ということである。この場合当然のことであるが caput は純粋に数による価値の大きさを表すものであったのであり、おそらくはそこではこの表現はまさにこのような場合において juga と並んで使われたのであるが、その一方で catpitatio は属州全体での人頭税を意味していたのである。そうであれば先に言及した文献史料においての capitatio の意味の説明の不適合を説明できる 125)。
125) アスティパレア島≪エーゲ海南東部のドデカネス諸島の一つ。BC105年にローマとの間で条約が結ばれ、ローマの自由州とされた。オリエント諸国との関係でローマのために何らかの軍事的な役割を果たしていたと言われている。≫の土地台帳の断片を含む C.I.Graec. 8657 の碑文は、課税された土地区画の存在を次のように証拠付けている:
(Δε)σπο(τί)ας Θεοδούλου.
χω. Ἀχιλλικὸς ζυ. ….
χω. Βάρρος με … ζυ … ἄνθρωρ . κϑ
χω. Βατράχου με …. δ, ζυ … ἄνθρωρ . κ
χω. Δάρνιον ζυ….
[テオドゥレスの地主達。
場所 アキッリコス 牛馬…
場所 バッロス 区画…牛馬…人間。κϑ
場所 バトラク 区画…δ、牛馬…人間、κ
場所 ダルニオン 区画…]
ζυ. = ζυγά は耕作用の牛馬やロバなどの動物であり、ἄνθρω(ωποι)は植民者(小作人)と奴隷達である。με.についてはベック≪August Baeckh, 1785~1867年、ドイツの古典文献学者≫は μέρη の略である割合で課税される土地区画として解読を試みている。トラッレス≪Tralles、古代フリギアの都市、正確な場所は不明≫の土地台帳の断片(Bulletin de correspondance hellénique IV, p.336f., 417f.)は同様に土地区画を地主の人名毎に記録しており、それぞれの地主の支配地において ἀγροί[耕地] と τόποι[その他の土地]があってこれらは ζ(υγά = juga)に従って数えられ、また奴隷とζῶα [家畜]は κ(εφαλαί)[合計数]で数えられ、総合計を求める際には,ζυγά と κεφαλαί は同一視された。アスティパレアはトラッレスのように自由都市だったのであり、そこでは確からしくは税の合計額は総人口数に比例して課税されたのであり、そしてこの課税方法が彼ら自身によるそこの住民への課税においては単に juga と capita に比例して割当てられたのである。――これに対してテラ≪Thera、現在のギリシアのサントリーニ島≫とレスボス島の土地台帳の断片は、その二つの都市においては周知のように αὐτονομία[自治権]が与えられていなかったのであり、そこの耕地はそれ故に昔から使用料の支払いを義務付けられていて、専制政治によって納税義務を課された土地区画及びその中の耕地(γῆ σπόριμος [耕されていた土地])、そしてブドウ畑(ἄμπελος [ワイン]) はユゲラ当たりで、そしてオリーブ畑(ἐλαία [野生のオリーブの樹])は樹木の本数またはγυρά[環濠]の数当たりで、同様に[レスボスでは]牧草地と牧場地はユゲラ当たりで課税されていたことが示されており、それに並んで申告した年齢毎の奴隷、牛、ロバ[πρόβατα]、そしてついには[トレッラにて]πάροικοι[外国から来た小作人]が示されている。ここにおいてはそれ故に専制政治によるユガティオとカピタティオが初めて税額として一緒にまとめて計算され、その中にその対象の耕地の品質についての情報が含まれる形で伝えられているに違いない。この最後の事例において juga の確定のやり方は、そこではつまり個々の土地区画に対する土地税の割当てが juga に統一されていたのであるが、それはシリア・ローマ法律文書(モムゼン、Hermes III、430)の次の箇所と関連がある: agros vero rex Romanus mensura perticae sic emensus est. Centum perticae sunt πλέθρον (das griechische Wort steht im Original). Ἰοῦγον autem diebus Diocletiani regis emensum et determinatum est. Quinque iugera vineae, quae X πλέθρα efficiunt, pro uno iugo posita sunt. Viginti iugera seu XL πλέθρα agri consiti annonas dant unius iugi. Trunci (?) CCXX(V) olearum vetustarum unius iugi annonas dant: trunci CDL in monte unum iugum dant. Similiter (si) ager deterioris et montani nomine positus (est), XL iugera quae efficiunt LXXX πλέθρα, unum iugum dant. Sin in τρίτη positus seu scriptus est, LX iugera, quae efficiunt (CXX) πλέθρα, unum iugum dant. Montes vero sic scribuntur: Tempore scriptionis ii, quibus ab imperio potestas data est, aratores montanos ex aliis regionibus advocant, quorum δοκιμασία scribunt, quot tritici vel hordei modios terra montana reddat. Similiter etiam terram non consitam, quae pecudibus minoribus pascua praebet, scribunt, quantam συντἐλειαν in ταμιεῖον factura sit, et postalatur pro agro pascuo, quem in ταμιεῖον quotannis offerat, denarius (d.h. aureus) unus seu duo seu tres et hocce tributum agri pascui exigunt Romani mense Nisan (April) pro equis suis.
[ローマ王(皇帝)はこのように土地を測量棒を使って測量した。100ペルティカは1プレスロンに相当する。(πλέθρον≪ギリシアの面積単位。≫ は元々の文献に登場するギリシア語)しかしユグムはディオクレティアヌス王(皇帝)の時に測量され決められた。5ユゲラのブドウ畑は10プレスラ≪プレスロンの複数形≫になり、それが1ユグムとして設定された。20ユゲラまたは40プレスラの耕地は1ユグム分の(年間の)穀物の収穫量を供給する。220(225)本の老木のオリーブの樹は1ユグムの収穫量を供給する:山中のオリーブの樹は450本で1ユグム分を供給する。≪山の中のオリーブの樹は生産効率が約1/2ということ。≫同様に(もし)土地の質として劣るもの、あるいは山地として分類された場合、40ユゲラ、つまり80プレスラに相当、が1ユグムを供給する。しかし三級の土地と分類されたりまた記録された場合は、60ユゲラ、つまり(120)プレスラが1ユグムを供給する。山地については次のように記録される:その記録の際に、ローマ帝国から権限を与えられた者は、山地での耕作者を他の地域から呼び寄せ、彼らによる評価結果を記録し、その山地が小麦または大麦を何モディウス産出するかを記録する。同様にまた、耕作されていない土地で、小家畜の牧草地になるものも記録される。いくらの共同納付税を国庫に納めることになるかが記録される。そして牧草地に対して国庫に毎年納めるものとして、1または2または3デナリウス(つまりアウレウス)が課される。この牧草地税はローマ人が自分達の馬のためにニサンの月(4月)≪元はユダヤ教の正月≫に徴収される。]
これに対して最初の方法について語っているのは、つまりある決まった割当て額の capita がある場所全体に課されていた場合であるが、Eumen. gratiar. actio のある箇所で、そこ自身による記述ではそれをコンスタンティヌス1世≪在位306~337年、4つに分裂していたローマを再統一した。またローマ皇帝で初めてキリスト教徒になった。≫の命令としているが:septem milia capitum remisisti … remissione ista septem milium capitum ceteris viginti quinque milibus dedisti vires, dedisti opem, dedisti salutem.
[あなた(=コンスタンティヌス一世)は7,000人分の人頭税(カプティオ)を免除した…この7,000人分の免除によって残った25,000人に力を与え、支援と救済をも与えた。]
エデュアー≪Aedeur または Haeduer、ガリアにおけるケルト人の最大の部族≫は、ここはその者達について語っているのであるが、つまり合計で32,000人分の人頭税を課せられていたのを、その内の7,000人分を免除されている。この人頭税は実際にこの部族のフーフェに対して課せられた税とは一致していない。32,000人分の人頭税について更に分割するということは語られておらず、分割の結果は25,000人に留まっている。ここにおいてのように純粋な価値の大きさ、つまり実際は「概念的な課税対象のフーフェ」が扱われている場合は caput という表現が用いられ、それに対して具体的な大地主の土地所有について言う場合は jugum という表現が用いられる。確からしいのは、このことが2つの表現の根本的な相違点なのであるということである。価値という観点からのこの区別から分かることは、この区別が、この時代のローマで共通して[promiscue]用いられていたということである。――Vokeji≪詳細不詳≫(C.I.L., X, 407)の323年の土地台帳の断片は、個々の土地をユゲラを使って表現しており、その土地の価額を千単位で報告している。こういった土地区画を全体として価値評価しているということは、同様にそれらの土地がより古い時代に非課税のものであったということと関連しており、それに対しての課税はこのやり方のみが許されていたのである。それ故にイタリア半島においては後に jugum の代わりに millena が登場しているが、それは事実上は jugum と差が無いものであり(Valent. nov. Tit. V, § 4. Nov. Major. Tit. VII, §16 とユスティニアヌス帝の国事詔書≪554年、ゴート戦争後のイタリア再編についてのユスティニアヌス1世による勅令≫の554、c. 26)、例外として相違するのは通例異なった品質等級を持つ複数の耕地が組み合わされ、その結果違うやり方が採用されたという点であるが。
こうした改革は全体として、自然なこととして徐々に進められ、決して完了に至ることなく、多くの場合で反動が起きていた。ここにおいてその時々に見られたこととしては、属州の破産という事態の結果として、ローマ国家によるその属州への税査定を放棄し、改めて属州に対して、それ自身による税負担能力の申告に基づいて税の総額を改めて割当て直す、ということが必要になり、それは先に引用したヌミディアについての箇所でも同様であり、また同じ時代(テオドシウス2世≪東ローマ帝国テオドシウス朝の第2代皇帝、在位408-450年≫、424年)の別の例としてマケドニアとアジア属州での例を確認出来る 126)。
126) テオドシウス法典 33 de annon[a] et tribut[is] 11, 1。そこでは更に次のことが特別に主張されている。つまりどのような検査官[inspector]も属州の財の評価をしてはならないと。
同時に最初に引用した箇所が示しているのは、ヌミディアでは税フーフェのシステムの導入という意味での税制改革はまだようやく始められたばかりの状態であったということである;他の固定された税以外では、全ヌミディア人はわずか200人分の人頭税しか払っていなかった。同様にアフリカでは税額の計算はその時点でもケントゥリア当たりでいくらの使用料支払いの原則に従っていたのであり、それは部分的には、以前主張したように、もしかするとグラックス兄弟の時代のやり方をそのまま継承していたのかもしれない 127)。
127) カエサルによるカンパーニア地方でのヴィリタン土地割当てにおけるケントゥリアについては、ごくわずかな不連続になっている部分を除いて今日でもその跡ははっきりと分かるものであり、それは[ヴェーバーの当時の]今日のカプアの地図が示している通りである。≪Googleマップで現在のカプアの古カプアに相当するサンタ・マリーア・カプア・ヴェーテレ周辺の地図を確認した限りでは、ケントゥリアによるいわゆる条里制の痕跡は確認出来なかった。≫(尊敬する枢密参事官のマイツェン教授は、私に同様の事例についての記述を参照する機会を与えてくれた。それは間もなく教授の著作として刊行される。≪おそらくマイツェンの Siedelung und Agrarwesen 、1895年のAnlage 29、”Reste der Assignationen Caesars um Capua”のこと。2ページ半のテキストのみで特に地図や図は付いていない。”um”という前置詞の意味から、カプアの中心地ではなくその周辺のことであろう。≫)ケントゥリアは一般に200ユゲラと見なされた。それ故にカンパーニアでもまた常に正確に次のことを計算することが出来た。それはある土地での総課税対象額がいくらであったかというのと、課税対象の土地の面積が何ユゲラであったかということである。――参照:D. 2 de indulg[entis] deb[itorum](ホノリウス帝とアルカディウス帝≪ホノリウス帝はテオドシウス1世の次男、アルカディウス帝は長男で前者が西、後者が東を治めてローマは再び分裂した。≫ 395)、そこでは528,042ユゲラ分の税が砂漠と荒れ地に対して免除されている――アフリカでの例と同じく。
そして結論としては言及した箇所は次のことを証明している。それはその当時であってもまだ植民市に対する課税方法はその他のゲマインデに対するそれとは違いが存在していた、ということである。というのはこの[改革された]税制は、もちろんそれは部分的には修復不可能なほど壊れていたのであるが、植民市のルシカデ≪現代のアルジェリアのスキクダにあったローマの植民市≫とチュル≪プリニウスの書籍に出てくるヌミディアの町≫においては、あ特別な課税用の面積算定方法で統一的に simplumに基づく土地台帳を使ったものが前提とされていたからであり、それについての規定が存在する 128)。
128) そこでは5%[centesimae]の税について規定されている。
ゲマインデの税制上の自治の廃止
しかしながらもちろんディオクレティアヌス帝による税制改革は様々に異なった課税方式の統一を図る試みを更に先に進めていた。まず第一に土地区画に対する国家の直接的な課税が広範囲に渡って導入された。課税されていたゲマインデの税制上の自治は常に不安定な形で成り立っており、それはそのゲマインデに対して税の総額の徴収が委託されていた場合でもそうであった。そういったゲマインデが全体として統一された税対象物をまとめ上げていた限りにおいて、その全体としての状態の変更はいずれにせよ――例えばそれまでのその町の課税用の地図を破棄するなど≪町を一度取り壊して再度建設する場合≫129)――そのゲマインデを支配している国家の同意なしには決して行われることはなかった。
129) そのようにウェスパシアヌス帝はある碑文に含まれた(C. I. L., I, 1423)スペインのサボーラ≪スペインのヒスパニア・バエティカにあった町≫の処置について許可しているが、その処置とはその町を一度取り壊し同じ平野の中で再度建設するというものであり、それは壊す前の現状の土地使用料をそのまま保つという確約の元で行われた。もしその町の者達が新たな税を設けようと欲した場合には、その町を管轄する総督に対して許可を請わなければならなかった。
しかしながら国税の割当てにおいての税制の自治の原則全体は、一般的に次々に制限されるようになっていた。同じことが自治団体の公共組織からの解放によっても生じていた。コンスタンティヌス1世の治世において知られているのは、課税方法についてある種の濫発が起き、それは諸ゲマインデにおける富裕者の金権政治的な制度によって引き起こされていた 130)。
130) テオドシウス法典 3 de extr[aordinariis] et sord[idis] mun[eribus] 11, 16(コンスタンティヌス1世 324)では追加の税を取り立てており、その理由はカルケドン≪小アジアのビチニア地方の港湾都市≫とマケドニアでは、権力者(金持ち)が他者の納税義務を勝手に軽減したり、あるいは自身への munera[義務]の割り当て分をゲマインデを通じて軽減したりしていたからである。諸ゲマインデにおいては以前から税負担を平等にするという目的での管理が行われていたが 131)、その後コンスタンティヌス1世の治世においては税支払いの義務の割当て方法について部分的ではあるが正式なやり方が規定された 132)。
131) テオドシウス法典 4 de extr[aordinariis] et sord[idis] mun[eribus] 11. 16 (コンスタンティヌス1世 328)。まず最初に確認されなければならなったのは、富者が、それから平均的な人が、そして貧者がそれぞれ何を負担すべきか、ということである。この点で夫役との関連が再度明らかになっている。明らかに富者はそういう夫役の負担の順番において常に下層の者より開始することにしており、その結果として自分には順番が回って来ないようにしていた。
132) 注130と131の文献の箇所を参照せよ。後者においてはただ属州の総督によって定められた規準のみが権威のあるものとされた。
最終的には部分的にゲマインデの10人組の長[decurio]から税割当てと徴収の権利が有無を言わさず取上げられ 133)、つまりは国家による直接課税が導入されたのである。
133) 同じくより小規模の占有者もテオドシウス法典 12 de exact[ionibus] 11, 7 (383年)によってそれらの権利を取上げられた。
しかしそれにもかかわらず、stipendium をまとめて支払う場合には、そのゲマインデの領域についての税の総額に対しての自明の責任はなお残ったままだった 134)。
134) コンスタンティヌス1世(319年)の治世のテオドシウス法典 2 de exact[ionibus] 11, 7 はデクリオーネスのその配下の者に対する責任を限定していたのであるが、しかし Nov. Major. 4, 1 はデクリオーネスを正当にも「公僕」[servi reipublicae]と表現しており、つまりデクリオーネスの徴税についての責任がなおも継続したことは疑いようがないのである。コンスタンティヌス1世による規定の意味はまさに次のようなものである:税に関しての規制においては、ある所有者の土地区画であってそれを一つのまとまった jugum として評価されなかったものは、そして一般的にデクリオーネスではなかった者達の全ての土地は、税制上の扱いとしては地域毎に特定のデクリオーネスに割当てられ、これによっていまやそれらの地域について委託されたそれぞれのデクリオーネスはその税を立て替えて先払いすることを義務付けられたのであるが、それでももはやその各人がそれらの税額全体に対して責任がある訳ではなかった。そしてこのような納税組織はまた、税を jugera 単位で課したことの帰結であった(注137を見よ)。――既にコンスタンティヌス1世はデクリオーネスが旅に出ることについてはただ許可を受けた休暇の際のみに許可していたが、(テオドシウス法典 12 de decur[ionibus] 12, 1, 319年)、そしてテオドシウス法典 96 前掲の箇所の 383 はそういったデクリオーネス達の旅の際に逃亡の虞がある場合の強制的な連れ戻しについて規定している。
税はゲマインデのデクリオーネスが徴収すべきことになっており、またあるいは立て替え払いすることになっていたため、そしてこのことは土地の占有状態に付随する事柄であったので 135)、それ故に税についての責任はそれ以前から既に事実上土地区画そのものが負うべきものであり 136)、小規模の地主であってその土地への税はデクリオーネスがその面積に比例した額で徴収するようになっていた者は、それについては最終章で取り扱うことになるが、次のような者とおおよそ同じような位置に追いやられたのであり、その者とは大土地所有制においての地主の支配下にあって、税を地主から取り立てられていた者達である 139)。
135) テオドシウス法典の 72 de decur[ionibus] 12, 1(370年より前)は次のことを特別に規定している。つまりある商人で土地を入手した者は、デクリオーネスのリストの中に登録されることが可能であった場合があった、ということである。――我々が碑文の中に含まれている掲示用の白板に書かれたアフリカのタムガディ≪Thamgadi, 現在のアルジェリア東部にトラヤヌスス帝によって建設された植民市≫の360 – 67 年(Ehp. epigr. I)の記録から知ることが出来るのは、デクリオーネスは次のような者達そのものではないということで、その者達とはクリア≪ローマの行政上の最小の単位≫の成員であり、デクリオーネス自体ではなくデクリオーネスとなる資格を持つ者達であり、その2つの人間集団の関係は、元老院議員資格者と実際の元老院議員の関係と同じであった。(モムゼン、前掲書)テオドシウス法典 33 de decur[ionibus] 12, 1 (342年の)は 25 ユゲラの土地所有をおそらくはデクリオーネスが徴税の義務を負うことになる最低ラインとしている。
136) テオドシウス法典 1 de praed[iis] et manc[ipiis] cur[ialium] 32, 3(386年の)は、それ故にデクリオーネスの管轄する財産を売却する時の当局の許可を要求しており、それはこの財産を現物が負うべき義務を付加された、土地と一体となっている何か別の物として扱っている。
137) 注134を見よ。ここでもまた参照出来た先に引用した諸都市の土地台帳の断片は、常に専制君主によって納税義務のある土地というものが設定されていたことを示している。より小規模な土地所有者はその土地について、注134で詳しく論じたように、ケンススの登録において専制君主の財産に書き換えられたのであり――censibus adscribere [ケンススによって土地の所有権を登録する]、そこから adscripticii [名簿に登録された者達]という表現が生まれ(第4章を参照)――確からしくは πάροικοι、つまり小作人[coloni]として扱われたのである;それ故にこうして土地占有者を plebs rustica[地方の農民]から決定的に区別する身分としての違いが法的に正当化されたのであり、また税の徴収上でその区別がはっきりと表現されるようになったのである。このことはつまり、ディオクレティアヌス帝による改革は事実上大地主制による小作人への課税が成立する上での重要なポイントなのだということだが、私の考えるところでは、この点はこれまで十分に強調されていない。その他の重要な帰結、それは別の観点で扱うべきことであるが、それらについては最終章で再度取り上げる。――そういった関係自身は、つまり大多数の小作人の義務を代わって負う納税義務者の当然なのは責任は、その他の場合として既により先の時代に、D. 5 pr. de cens[ibus] (50, 15)でパーピニアーヌス≪142?~212年、ローマの法学者≫によって言及されている:
Cum possessor unus expediendi negotii causa tributorum jure convenitur, adversus ceteros, quorum aeque praedia tenentur, ei qui conventus est, actiones a fisco praestantur, scilicet ut omnes pro modo praediorum pecuniam tributi conferant.
[もしある一人の占有者が税の支払い義務の問題の解決のために、仮に法的に訴えられた場合、逆に他の者も農地を占有しているので、その者は国庫から他の者を訴える権利を与えられることになる。当然なのは、全ての者がその農地の面積に応じた税金を支払うべき、ということである。]
ここで更に語られているのは占有者(=デクリオーネス)相互の関係についてである。ここにおいてはデクリオーネス達については明らかに一人は全員のために、そして全員は一人のために、その自治体の領域についての税に対して責任を負わされているのであり、それに対して既に述べて来たように注134で引用したコンスタンティヌス帝の法律は逆の方向に向かおうとしていたのである。
それ故に納税義務を負う者としての内外でいまや二つの身分が対立して存在していた。一つは占有者のそれで国家に対して直接的に納税義務を負い、もう一つは平民、tributarii [納税義務者]、小作人のそれで間接的に納税義務を負う者達である。占有者は更に次の2つに分かれ、クリアに対して徴税の義務を負っている者達と負っていない者達である。より規模の大きい占有者達は、彼らの土地所有についてゲマインデ団体からの税を免除してもらうことをあらゆる手段を使ってでも達成しようとしていたので、そしてまたそれに一部は――例えば元老院議員の場合は常に 138)――成功しており、そのために税負担の恐るべき負担は本質的には中規模の地主達の上に集中したのであり、そしてこのことはそういった地主達の大量の破産という事態をもたらし、そういった地主達により放棄された土地のゲマインデのクリアに処分のために渡り 139)、クリアによって可能な限りにおいて貸し出されたのである。
138) テオドシウス法典 3 de praed[iis] senator[um] 6, 3(396年の)。次の年にはもちろん元老院議員の土地は再びクリアの管理下に入れられたが、しかしこれは長くは続かず、というのはその同じ年に(テオドシウス法典 13 de tiron[ibus] 7, 13)元老院議員は新兵の徴集に関して特権を与えられているからである。
139) ユスティニアヌス法、XI, 58. C. 8 de exact[ionibus] trib[utorum] 10, 19。
土地税の一本化
そしてまた土地税の一本化を進めていこうとする動きは、文献史料において明確に確認出来る。皇帝から土地を借りた大規模な永代借地人の賃借料、古くからの国有地の賃借人の支払う固定額の賃借料、契約が取り消されることがある国有地を借りている小規模な賃借人の支払う賃借料、取り消し可能な借地として割当てられた土地所有に対しての税金[stipendium]、scamna によって区切られた属州の耕地に対しての使用料、全てのこいういった税金の類いは実際にはお互いに似通ったものとなって行き、そしてそれが可能であった場合には、お互いに tributum soli [個々の者への税]として融合されたのである 140)。
140) そのためテオドシウス法典 1, 2 de extr[aordinariis] et sord[idis] mun[eribus] 11, 16 においては、永代賃借、父系支配での相続地への税、そして同一法典の 13 では他の全ての praedia perpetuo jure possessa [法的に永代の占有権を与えられた農地]は extraordinaria onera[特別税]という枠組みの中に等しく入れられた。
それらはそれでもなお土地税を負担する土地の中のそれぞれ異なったカテゴリーのものとして扱われていたが 141)、状況に応じてある土地区画をある特定のカテゴリーから別のカテゴリーへ移すということが行われていた 142)。
141) その結果として、テオドシウス法典 5 de censitor[ibus] XIII, 11 は永代貸借の賃借料と異なる土地税を一緒のものとしている。別の混同の例は、テオドシウス法典 1 de coll[atione] don[atarum…possessionum] XI, 20 にて見ることが出来る。既にユスティニアヌス法 13 de praed[iis] 5, 71 (ティオクレティアヌス帝とマキスムス帝≪西ローマ帝国、在位383~388年≫)において農地の賃借料[vectigal]、永代賃借料と父系支配での相続地への税は全て等しく扱われている。
142) このことはテオドシウス法典 6 de coll[atione] don[atarum…possessionum] 11, 20にて言及されている。
その際にはあるカテゴリーの法的な特性が別のカテゴリーへと転用された。その点に関して次のことは既に見て来た。それは経済的な土地利用の仕方の変更で、そいれがより低い方の税クラスの土地利用に変わってしまうかもしれなかったものは、賃借料の義務のある土地から税支払いの義務のある土地への変更の場合から類推して、税務当局からの同意が必要とされた、ということである。後の時代になって一般に使われるようになった制度で、それはまずは公的な、つまり皇帝から土地を借りた永代賃貸借人の場合に見出されるようになったのであるが、それはいわゆる έπιβολή 143) ≪耕作が放棄された土地をその隣接する土地の所有者に割当て、その分の土地税をその所有者から徴収した制度≫である。
143) テオドシウス法典 4 de locat[ione] fund[orum] j[uris] emph[yteutici] (383年の)においては、έπιβολή は自治市における vectigal 払いの土地にて見ることが出来、それ以前でもテオドシウス法典 4 de annon[a] et trib[utis] 11. 1 (337年の)において永代賃借地と父系相続の土地への税についての規定で見られる。
不耕地強制割当て [έπιβολή]と税の等額負担[peraquatio]
使用料支払い義務のある土地の売却についての行政当局の認可の権利によって、確からしいことは税務当局といずれの場合でも皇帝の直轄地管理当局は昔から次の前提条件の上に成り立っていた。つまり永代賃借地の内の賃借料負担能力のある土地が分割して売却され、その結果として残った土地が賃借料の合計額を負担できなくなる事態が起きないようにする、ということである。そういった部分的な土地を購入しようとする者は、時によっては全体の土地を購入することが要求された。この手続きは後に一般化し、更に次のように拡張された。つまり誰であっても他人の土地を購入した者は、その他人の他の土地全部を含めて έπιβολή [不耕地の強制割当て、ギリシア語での意味は追徴課税。]の付加条件を受け入れることを余儀なくされた、ということである 144)。
144) テオドシウス法典のコンスタンティヌス帝の 1 sine censu 11, 3。
放棄された納税義務のある土地の断片については古くから ager publics の場合と同様に占有対象として開放され、あるいはその土地に隣接する土地の所有者にその者の意思にかかわらず競売の形で割当てられた 145)。
145) ユスティニアヌス法、Tit. XI, 58 に引用されている。
このような新たな制度の源泉で同様なものとして、税の等額負担[praequatio]の制度を挙げることが出来る。国家または皇帝の公有地の賃借人で非常に多額の賃借料支払いの義務のある土地区画を所有していた者は、次のことを阻止することは出来なかった。それは行政当局が使用料の総額を計算上個々の土地区画に別々に分割して割当てるということと、そして賃借料支払い義務のある土地の一部が譲渡されたりまたは他の方法で分割された場合に、この方法を応用して使用料を分割してそれを新しい所有者に割当てる、ということである。この種の賃借料の分割においてのきちんとした計算方法の必要性はしかしながら、一般的に様々な形で表面化するようになった。既に見て来たことだが、ager provatus vectigalisque においてと握手行為によって所有権を得た大規模な公有地においては、相続対象の金額という点で流動的な要素が存在しており、その賃借料は布告された法律によってユゲラ当たりいくらと一様に定められていた。それにもかかわらず確からしいこととしては、その場合には賃借料は低めに見積もられていたのであり、しかしそうとはいえ次第に継続する賃借料支払いの不均等さが感じられるようになってきていたに違いない。それ故に行政当局はそういった土地をそれぞれの品質等級に合わせて均等に分割しようと努力していたが、それは特にアフリカにおいて永代賃借地として所有されたケントゥリアにおいて文献史料の中で見出すことが出来るものである。
146) テオドシウス法典 14 de censitor[ibus] 13, 11はそれ故に次のことを定めている。つまりある者でその所有地の一区画についてケンススでの税額評価の軽減を要望したものは、その者の所有する全ての土地の評価をやり直し、場合によっては税額をそれぞれの土地毎に以前とは違う形で分割することを是認しなければならなかった。
147) テオドシウス法典 10 de anno[a] et trib[utis] 11, 1(365年の):アフリカにて豊饒なケントゥリアと荒れ地のケントゥリアの両方を持っていた者は、”ad integrum professionis modum”[(豊かな方の)土地の等級に合わせた全体の面積分の]税金を支払わなければならなかった。しかしながらテオドシウス法典 31 の同じタイトルの部分は再びこのやり方を取りやめており、荒れ地の方のケントゥリアについて免税とすることを許可していた。最初の箇所は私の考えではまだ当時でも均等な、面積当たりで課された vectigal が残っていたことの証明であり、それは丁度先に述べた u.c.643年の土地改革法によって ager privatus vectigalisque に課せられたと推定されるものと同様である。
この種の制度はしかしながら全ての課税対象の所有地に対して一般に必要なものとされるようになった。課税対象のゲマインデにおいて国家が税の賦課の方法を規則によって定めていたかあるいは自らの手中において自由に出来た場合には、この方策はいずれにせよ praequatio の性格を持っていたし、またそのように表現されていた。
仮に土地所有者の努力が次のことを目的としていたら、つまり個々の土地区画への税額を近代的な土地税のやり方に従って可能な限り固定額とするということであるが、他方では juga を使った徴税の体制は次の目的を持っていたといえ、それはその時々の等倍の係数[simplum]に基づいた土地台帳に関しての必要に応じて、より少ないあるいはより多くの税を徴収するとことが出来るようにするということであるが、その結果としてこの2つの目的は両方を実現することは不可能であり、そして比較的高額の土地への税賦課においては一般にそのような土地台帳の新しい方法は、それはディオクレティアヌス帝が何とか実施しようと努めたものであるが、それが可能となったのはただ個々の土地の税額を定期的に見直すことが出来た場合だけだった。その目的のために peraequatio は使われたのであり 148)、それ故に個々の土地区画の面積を組み合わせてそれを juga ベースに変更し、その際に元々の jugum の値がある程度変更されることは許容されていたのである。しかし更には一般に次のことが古くからの ager privatus の分類の土地にも導入されたのであり、そういった土地分類は元々使用料だけを支払うべき土地として通用していたものだけに認められていたのであるが、それはまず税負担を個々の土地のそれぞれの部分に分割することがそういった土地を分離売却する場合に先行して行われるべき、ということと 149)、そして税務当局への届け出と全ての売却においての元々のカピタティオを新しい所有者の負担にするという書き換えの申請が一般的にはされるべきこととなった、ということである 150)。
148) クリアーレス≪クリアの指導者達≫はこの目的のための請願を行っている。テオドシウス法典 3 de praed[iis] senator[um] 6, 3 (396年)。
149) このことが先に引用したテオドシウス法典 2, §1 de contr[ahenda] empt[ione] 3, 1の規定の目的であった。その文献の引用済みの箇所の更に先を参照せよ。
150) テオドシウス法典 5 sine censu 11, 4
そのことと結び付いているのは先に言及した握手行為の禁止≪337年のコンスタンティヌス大帝の法による≫であり、それは土地の面積、つまり locus に応じた課税の際にはもはや準拠すべきではないとして許可されていなかったように見られた可能性がある。
ユガティオ以外の特別税
ここではディオクレティアヌス帝の税制改革についてはこれ以上深入りすることはしないが、ここまで問題として来たことはただ次のことである。それはその改革の特徴として部分的にはただ古い時代からの様々に異なった課税方法を一まとめにしたものを含んでいるということと、更にはその改革が直面した非常に異なった様々な課税に関する状況をある統一された課税制度にまとめることが出来なかった、ということであり、――それ故に全ての個々の文献史料の箇所をバランスを取ってある一つの原理に還元するという試みは、単に非常に近似的なやり方でのみ実行可能なのであり、ユガティオというやり方に対しての個々の土地と土地所有のあり方はよりむしろその地方で必要とされたやり方に従いそれぞれに異なった状態になっていたに違いない、ということである。唯一統一性を把握出来る点はかつて存在した土地所有に関しての諸状況からの論理的な帰結を引き出す、ということであり、それは特に大地主制度に向かう方向での課税傾向である。
その他次のことは言うまでもないことであるが、ここでの考察は土地に課された義務について、それを完全に汲み尽くすようなものでは全くない。
自然物の納付
Adaeratio≪現物納から同等の価値の金銭による納税に変えること≫
ここでは特に難解でかつ包括的な自然物貢納のシステムについてはごくわずかに言及することを試みるに留めた。ディオクレティアヌス帝による改革においては自然物貢納義務の土地を(金銭による)土地税の義務というやり方に組み入れようとする試みがなされたが、しかしそれはすぐに断念され、それによって一定割合(%)による財産税の一般原則を免除する事例が数多く作りだされた。他方では(新しい方式の)税負担義務は他の共通の賦課の免除につながった場合もあり、それは例えばデクリオーネスの所有物への税やあるいは新兵徴収の義務の免除さえも行われた 151)。
151) テオドシウス法典 1 qui a praeb[itione] tiron[um] 11. 18 (412年の)。
ここで見て取れるのは、こういったディオクレティアヌス帝の改革がしかしどのようにして至る所で個々の所有者の分類において特別な地位を認めなければならなかったかである。共和国の属州の一部においては古くからの穀物購入のやり方での自然物貢納がユガティオによる税への付加税とされた。しかし確かなこととして自然物貢納は部分的にはまた古くからの収穫物の一定割合を納める、という形で存続した。一般論として次のことを主張するのはおそらく間違っているであろう。つまり自然物貢納が金銭納と比較してより軽い税負担の形態である、ということである。この主張はより小規模な自営農民である土地所有者一般には当てはまるであろうし、そのために時々に地主またはゲマインデによって課されていた現物貢納を金銭納付に変更すること(adaeratio)は禁止されており、その理由はこの場合にはそこに居住する者達が等しく現金支払いを強制されるのであり、そのことはその者達から非常に困難なことと受け止められていたであろうからである。これに対して大土地所有者達の努力はそれとは逆にその者達に課されていた様々な義務を一つにまとめて固定額の現金による定期支払金[rente]にしておらう方向に向かっており、そうすることはその者達にとっては実質的にほとんど義務の軽減と同じことだったのである 152)。
152) それ故にテオドシウス法典 1 [de] erogat[ione] 7, 4(325年)の adaeratio は義務を課しているもののように見えるが、それに対してテオドシウス法典(新)の23(最後の所)とテオドシウス法典 4 tributa in ipsis spec[ibus] inf[erri] 11, 2(384年)と同法典 2 de eq[uorum] coll[atione] 11, 17(367年)においては義務の軽減のようであり、同法典 6 de coll[atione] don[atatrum … possessionum]11, 20(430年)では税負担においての特典のようである。同法典(新)の 23 はrelevatio[何かの控除]、adaeratio[現金納税]、donatio[贈与の控除]、translatio[所有権移転の控除]による税の軽減措置を終了させようとしていた。
次のことについては既に主張してきた。つまり元老院議員及びその他のカテゴリーに属する占有者達が、新兵の徴集義務ですれその者達にとって金銭払いで置き換え可能にする、ということを徹底して推進していた、ということである。
自然物貢納を非常な程度までに強要するということは本質的には、そういった穀物が消費される場所までの現物の輸送の義務化ということであった。特記すべきことは、”vectigal”という名称は元は文法的には vehi から来ている――”Fuhren”[運搬する]とモムゼンは訳している――ということであるが、目下の所の仮説ではその表現は取るに足らない程の距離ということを言っている考えられる。それに対して、金銭にて見積もれば、自然物のその消費地にまで届ける輸送のコストは、帝政期においては間違いなく、その輸送距離が相当程度あった場合には、元々の自然物自体のコストを大幅に超えるものになっていた。行政当局がもはや投機の介入や税としての賃借料の大規模な引受人を利用することを止め、その代わりに自然物輸送に関わる全ての業務を国有化し、それによって変動する収穫高と商況への適応が困難になった時に、輸送に関連した困難さと摩擦は至る所で高まっていた。しかし更に無統制の状況と数の多い役人達を経由して業務を引き受けた大規模な業者の側からの、その業務負担を割り当てられた者への耐えがたい圧迫により、しかしながら個々の官庁とその属官の何重にもなった管轄の下においては、巨視的で統一的な業務遂行上の視点を持つことなく、そしてそれはその事業を引き受けた大規模業者いにおいても同じであったが、この業務をともかくも実施することが取り決められたのである。というのもテオドシウス法典の自然物輸送を扱っている表題の部分は、十分にはっきりと輸送の賦課が如何に過酷なものとして受け取られていたかを示している。そういった類の現物経済というものは、その当時のローマのような世界的国家において、また当時の交通手段をもってしてはほとんど不可能だったのであるが、――しかしながらまた新兵徴集においても、その手続きについて地方における兵の徴集というやり方を使わざるを得なかったのであり、それはハドリアヌス帝の時代まで続いたのであるが、――古代国家ローマはザクセン王ハインリヒ4世≪ザクセン公ハインリヒ、ハインリヒ敬虔公、1473~1541年、フリースラントの領主となったがフリース人の反抗によって結局その支配権を兄に譲ることになった。≫がそれが原因で失敗したのと同じ困難に直面していたのであり、その解決はただ特別な領土を解体させることにしか見出せなかったのである。
動産への課税
ここまで属州においての人頭税についてそれが後の時代のカピタティオになるまで、それが財産税の性格を持っている場合に限定していたが、更に詳しくは論じて来なかった。ディオクレティアヌス帝の tributum capitis が単純に言えば属州においての人頭税であったことは疑いようがないように思われるが、それは確かに自由な日雇い労働者と小作人、奴隷と運搬用家畜の頭数に対して等しく課され 153)、夫役に相当するものであった。ディオクレティアヌス帝の改革はただ次の場合においてのみ変更を加えようとしたものであり、それは既に進行してい発展の実質に沿った形で 154)、彼が小家畜もその人頭税の対象に組み入れ、そしてこれらの対象物を全体で財産目録化して税額を見積もらせた、そういう場合である 155)。
153) 都市 Zarai ≪ダルマチアの都市≫は碑文として残されているその税額表の中で明確に、奴隷、馬、そしてらばに対して同じ条件を適用して税を徴収している。(1 Sest.)該当する税額表の断片は lex capitularis という名前であり、まさしくカピタティオに関連付けられている。
154) 前注で引用した碑文は同じ章にまたロバ、牛、豚、羊、ヤギに対しても課税している。
155) 先に引用したレスボス島における土地台帳の断片(Bull. de corr. hell. IV, p. 417f.)はこのことを示している。
ディオクレティアヌス帝の改革はまた土地税の改革であり、彼が一般的に動産に対しての税もその中に含めようとしていたかについては、確からしいとは思われない。動産への課税の取扱いについての何らかの基本原則は、いずれにせよ我々には情報が残されておらず、一般的にはこういった類いの財産については言うならば「対象物税」[Objektsteuern]として把握することが試みられていた。しかしそのことは次の可能性を排除していない。それはその土地で、ゲマインデによってそのゲマインデ全体に総額として課せられた税の全体を、個々の頭数に割当てていた場所においては、こういった類いの財産は異なったやり方で扱われていた、ということである。しかしそういった解明が困難な状況は、それを詳しく述べるためには古代社会においての労働の割り振りについての産業史的な分析が必要なのであり、土地制度史の研究の範囲には含まれない。
土地所有権の統合
我々はむしろ最後にただ良く知られた次のような事実について確認することとしたい。それはディオクレティアヌス帝による土地税の統合の試みと、土地についての所有権を大体において等しく扱うことは、相互に関係しているのであり、そしてこの所有権の平等視は本質的には、所有権の獲得のやり方と抵当権に関係するものとして、善意に基づく(ボニタリー)場所の所有権[bonitarisches locus-Eigentum]という形で発生した、ということである。またそれは時効取得の学説においては、属州において皇帝が制定した法規中の法文に依拠しており、更には奴隷制度においては、重要な点において ager privatus の分割という状況を作り出した所有権のあり方に依拠した、ということであり、そしてまたついには、ローマの所有に関する法においては、所有権についての、理論を作り出していた法律家による抽象概念の中から成長して来た、諸法規においての[所有に関する]法文の一般化が生じていた、ということである。またそれは根源的には非常に現実的な、そして帝政期には既に消え去っていた古いローマの土地法から発生して来たものである、ということである。諸税と土地税の支払い義務のある所有状態の扱いをこのような ius gentium ≪万民法、市民だけではなく、ローマ帝国全体の住民に適用される法。≫へ移すことは、一部は属州総督の布告を通じてと、また皇帝による積極的な立法によって 156)、また一部はそれに依存している司法においての判例と法学者による法解釈によって、徐々に、部分的にはようやくディオクレティアヌス帝の治世の後になって発生して来ており、また古くからのイタリア法による特権の残余物の除去は、ユスティニアヌス帝によって行われた 157)。
156) 例えば Vat. Fragm. 283、285、286、293、313、315、326。
157) Tit. Cod. VII, 31, 40。
ユスティニアヌス帝の法規の集成においては、そうした古くからの法律による相違の残存物は細心の注意をもって除去されている。
――――――――
我々はここではそうした発展について追いかけることはしない。何故なら文献史料の不足のためにどの時代に個々の所有状態のカテゴリーが万民法の一般的規則の中に吸収されたかを決定することは不可能だからである。ウェスパシアヌス帝による土地に対する課税の継続という事情下での、スペイン(の都市)に対してのラテン市民権賦与の布告は、ローマのボニタリー所有権(物権)の原則の一般適用という結果になったが、植民市と他の都市ゲマインデにおいての段階的なアフリカの組織化は、それが進行した場所においては、またこれらの属州に対してと同じ結果となったが、このことは統一された方法による訴訟についての許可を通じて、属州総督の布告の中で明記されていた。この布告のその他の点については良く知られていないが、レネル≪Otto Lenel、既出≫がそう主張しているように、ハドリアヌス帝の治下では、その中に全ての農場税[praedia stipendiaria]と税一般[tributaria]についての統一された様式が含まれていたかもしれない。そこではそれぞれの法的な性格は異なっていた:考慮すべきこととしては、次の全ての種類の土地が並立していたということである。それはアフリカにおいては、自由市民の耕地、ペリグリヌス≪非ローマ市民の帝国民≫に与えられた権利に基づく耕地、ローマの個人の権利としてカルタゴにおいて割当てられた領域、国家当局の恣意に左右される大土地所有法に基づく課税対象の土地としての大地主の領地、個人の権利と行政権的な規則の結合である ager privatus vectigalisque、純粋に行政権上の規則に基づくものとして扱うべき賃貸借された耕地である。属州総督各人において起きたことは、行政のもっとも高次の部分と司法的な管轄を一つにまとめた、ということであり、そのため実務においてはこの二つを区別することは困難だったのであり、実際はまた布告においてもこれら二つが等しいことと把握されていたのである。以上見てきたような様々に異なった所有状況について、唯一の共通点と言えるのは、それらが “possessiones” [占有物、資産]であったということである。全ての possessiones はしかし、元々は民法上は、その場所に対してのみ、特定の性質の侵害から保護された。そのことに符合するのはその場所の測量が strigae と scamna を用いて行われた、ということである:訴訟に対して判決を下す担当官はその指示を明確に固定された[certi rigores]土地区画に対して出したのであり、それは面積だけで分割された土地に対しては行うことが出来なかった。そのことに合わせてローマ人民に対しての、時効取得の認められていない個々のカテゴリーの耕地において、民法上の「場所の」保護が最初から行われていたかどうかについては、何も知られていない――確からしいこととしてはほとんどのケースはその答えは「否」である。というのはムニピキウムのager vectigalis に対しての訴訟は、その本質的な特徴は次の点にあるからである。それはそういった訴訟においてムニキピウム自身が訴えられることが可能であったということであり、それ故にそういった土地の保護は必須のこととなった。それに対して国家に対して納税義務を負っている者は、その者の最重要の権利関係において、その権利関係とは国家に対してあるいはその他の税徴収の権利者に対してのものであるが、単なる行政当局による審理か、あるいは最も恵まれたケースでは所有権回復手続きを期待することが出来た:一定のカテゴリー、例えばアフリカにおける stipendiarii [貢納]は、特別な行政手続きとしての controversia de territorio [領土に関しての訴訟]によって審理された。他方では少なくとも、次のような試みが行われていた。それは公有地の所有状態について、部分的にもっとも強い権利を持つ耕地と同じ測量原則を適用して取り扱うことである。ager privatus vectigalisque はケントゥリアを単位として測量され、その売却は面積単位で行われ、確からしいことは賃借料の賦課もそうであり、――そして測量人達は controversia de modo を ager quaestrius と ager vectigalis に適用することについて言及しており、――その際にはもちろん、まさに行政管理上の手続きについて語っていたのである。しかしながらこのやり方の課税も更に広範囲で行われるようにはなっておらず、そしてその理由は私有地における面積原則自体が衰退していっていたからである。既にアウグストゥス帝とティベリウス帝が、先に述べたように、所有地の境界の(有効性の)有期限化の指令によって ager assignatus の古い性質の除去ということを強調していたが、そこで判明するのは、帝政期が更に進行するにつれて面積原理が除去されていった、ということである。属州においての期限の無い所有状態については、その他ハドリアヌス帝の時代から 158) ローマの万民法の応急的な適用が確定したものとなっており、つまりはそれは場所原則に起因する、正当事由に基づく所有権の放棄という形での所有権移転という、応急的な適用であった。スカエウォラはボニタリー所有権に基づく抵当権を、賃借料支払い義務のある大地主の所領となっている土地区画の上に適用しており 159)、そしてウルピアーヌスとパーピニアーヌスにおいて見出されるのは、明確に民法上の制度が問題にされているのではない場合には、ローマ法が課税される(属州の)土地区画に直ちに適用されている、ということである。ディオクレティアヌス帝はこうした税制の統合をシステマチックに更に推進したように思われるが、少なくとも諸制度で、貢納義務のある属州の土地を取扱い、またほとんど全ての属州において、数は多いがなお疑問の多い個々の観点においての、ただそういった土地とイタリアの土地との同一視に関するものは、主としてディオクレティアヌス帝によって作り出された。
この章で我々にとって重要なのは、結果として生じたことより、むしろその結果を生み出した状況であり、それについては私が考えるところでは次のように正確に規定されなければならない:量的に圧倒的大部分のローマ帝国での所有状態は、行政法的な規則によって統制されていたのであり、そして私法に基づく部分はただ行政上の実践としてのみその作用を受け入れることが出来る、ということである。そこから導かれることとしては、私法的な観点から全ての諸制度を構成することは、たとえば土地に対する権利の概念から封土の権利を構成するのと同様に、不可能なことである 160)。
160) ここで試みているのは本質的には次のことである。つまりペルニーチェ(ローマ法制史雑誌 V)の注釈に関連して、こういった諸状況についての純粋に行政の実践に関連する規則を十分に把握する、ということである。その際に純粋に関連する法学的な理論構成が伴っていないということは、次のことに起因するのではない。それはそういったことが不可能だということではなく、私見では不当である、ということである。事実上ここで扱っているのは行政上の原則であり、そしてそういったものの論理的帰結としては、様々なやり方で市民法的に構成可能なものであるが、しかしそれは何らかの包括的な、全ての諸状況をカバーする法理論的な構成には至らないものである。
IV. ローマの農業と帝政期における大地主制
経営方法の発展
この章においては主として帝政期における現象を取り扱うこととするので、それより古い時代のローマの農業について振り返ってみることは、概観的なものになる。特に次のことについては取り扱うつもりはない。テッレマーレ≪黒い土の意味で、ポー平原での中後期青銅器文化のこと≫においての発掘物調査と、ヘーン≪Victor Hehn、1813~1890年、エストニア・リトアニアのドイツ語話者在住地出身の文化史学者≫とヘルビヒ≪Wolfgang Helbig、1839~1915年、ドイツの考古学者≫の才知あふれる調査の成果を利用して、最初期の定住から一般的な農業の発達史を論じることである。史書に記録されている時代になると、ローマの農業が示しているのは、それは農業書の著者達[scripstores rei rusticae] が我々に示してくれているように、それが特別に珍しい性質を持っていない、ということである。先に次のことが時折主張されていたとしたら、つまりローマ人がゲルマン人に三圃式耕作≪中世ヨーロッパで、耕地を夏蒔きの穀物用、冬蒔きの穀物用、休耕地の3つに分け、この内休耕地は牧草地として利用し、これらを毎年入れ替えて連作障害を防止する農法≫をもたらしたとしたら、そうすると今述べたことはそれ故に理解不能となる。何故ならば最古のゲルマン人の制度として問題にされるような三圃式耕作は、個人による耕作の方式では全くなく、村ゲマインシャフトによって行われるものであり、(村ゲマインシャフトによる耕作強制と分かち難く結び付いているものだからである。ローマの農業書の著者達がしかし知っていたのはテューネン≪Johann Heinrich von Thünen、1783~1850年、マイツェンに先立つドイツの経済地理学の先駆者≫が「自由耕作」とでも呼ぼうとしたものだけであった 1)。
1) 大カトーの「農業について」は冬営地の軍への飼料の販売の議論において、灌漑された牧草地[prata irrigua]について述べているが、その際に飼料の刈り取りを請け負った者[redemtor → ヴェーバーの引用ミスで正しくは redemptor]は隣接する土地の所有者が許可した場所に限って隣接地に立ち入ることになり、――そして「両者は確定した日付を決めろ」[vel diem certam itrique facito]とされている。ここで扱われているのはゲノッセンシャフト的な共用の灌漑設備と相互利用している牧草地の区画である。ここではある権利を持った者が、いつ刈り取りをするつもりであるかの申し立てについてであるかのように見えるが、その確実な効果について詳細は不明である。この推測が正しいのであれば、次の結論は明らかである。つまり元々は刈り取りの日というものは耕作強制と同じくゲノッセンシャフトによって確認されるものであるが、ここで述べられている手続きは、その本来の手続きの個々の耕作者による代行の手続きだということである。
農業書の著者達は輪作についてはただ時折語っているだけであり、それ故にこの方向に進んで行く習慣が確実に存在していたということを議論の前提にすることは出来ない。彼らは次のような耕地を知っていた。それはそこで毎年(春と冬との2回)穀物の種を蒔き(連作地[ager restibilis])、そしてそのことで毎年施す肥料が最終的に穀物へと転換される土台を作っている、そういう耕地であり、それ以外に彼らが知っていたのは純粋な休耕であった 2)ー;一般的に言って施肥された飼料の栽培 3) ≪積極的に肥料をやるというより家畜がそこで糞尿をすることで自然に肥料となる≫で中断される穀物類の栽培 4) が農場経営の中核を成しており、その穀物栽培とは冬蒔き小麦と夏蒔き小麦(timestris [3ヵ月で]収穫出来る)で個々にかなりの程度まで品種改良されたものであり、それは必要を満足する程十分な家畜の頭数およびそれらの家畜の厩舎の中での飼育 5)、そしてその結果としての(家畜の糞尿を利用した)高頻度の施肥と有機的に結び付いている 6)(ウァッロー≪Marcus Terentius Varro、BC116~BC27年、ローマの政務官・学者、「農業論 Rerum rusticarum」の著者。≫ 第2章)。
2) カトー、農業論、35
3) カトー、農業論、29
4) 鋤いて埋める目的ではルピナス≪荒地でも育つ。根粒菌が窒素固定を行う作用を利用して緑肥として利用される。≫、インゲン豆類≪同じく緑肥として利用。≫、ヤハズエンドウ≪俗称ピーピー豆≫の栽培。カトー 農業論37。干し草の収穫 同じ章の53。
5) カトーの農業書の13:牛類のための冬用、夏用の家畜小屋。――家畜小屋での飼育 農業書4――乾燥地での飼料[pabulum aridum]農業書29以下――飼料:新鮮な葉(ニレの若葉[frons ulmea]、ポプラ、オークとドングリ、ワインの搾りかす(農業書54)、まぐさまたはその代用品としての塩漬けの麦わら、その間にルピナスとクローバー、またはヤハズエンドウとソバ。――刈田飼い≪畑に少し残した穀物で家畜を飼うこと≫はわずかに例外的に行われた。ウァッロー農業書I、52。
6) カトー農業書29以下:ハトと羊の糞。C.I.L.XIII, 2642の碑文はほとんど中国においての糞尿利用の状態を思い出させるが、その中に、羊などの家畜を放牧しているエリア[campus pecuarius]の中への資格の無い者の立ち入りに対しての警告板が含まれている。その警告板に記載されている脅し目的の罰則は、罰金が強制的に徴収される以外に、現行犯だった場合には、その者自身の(その者自身のと更に?)1日分の糞尿が取上げられる、とされていた。
穀物類の耕作方法で、そこへ投入された労働力についての我々の概念からすると集約的と言うことが出来、また常にそうであったということを、ロードベルトゥスが正しく主張している;そこで既に述べられているのは、輪作が普通に行われていたということと 7)、そのことと農機具が非常に未発達であったということは関連しているということであるが:犂板(りとう)は鋤によって耕す際にまだ一度も広く使われるようにはなっておらず 8)、しかしこの当時の鋤はゾムバルトの観察によればカンパーニャ地方において(ヴェーバー当時の)現代でもなお使用されている 9)。穀物類の栽培の農場経営の技術的な側面については、農業書の著述家達が述べているところによれば変化が少なく、このことは利益を増大させるために穀物栽培の比率を減らしていったのと関係している。
7) このことによって必然となる細心の注意が要求される耕作方法のために、奴隷による農作業の不都合な点についての嘆きが述べられている。コルメッラ 農業書I第7章。
8) 種蒔きのための鋤返しの目的で”Tabellis additis ad vomerem simul et satum frumentum in porcis et sulcant fossas, quo pluvia aqua delabatur.”
[鋤の刃に小さな板を加えることによって、種蒔きにおいて蒔かれた穀物の種を土で覆い、そして鋤で引いて畝を作り、そこに雨水が流れ込むようにする。]ウァッロー 農業書I、23。
9) また打穀≪棒などで穀物を叩いて脱穀する方法≫の際には、家畜の力を使った打穀も既に行われており、家畜にローラーを引かせる以外に板に(金属の)歯を付けたものも使われていた。ウァッロー 農業書I、52。穀物は多くの場所で半月状の鎌(利鎌)を使って刈り取られていた;大鎌を使った刈り取りについては言及されていない。ウァッロー I、50によれば刈り取り作業は左手で穀物の茎をつかんだ状態で切断を行っていたが、それは収穫作業として非常に時間のかかるものであった。多くは先に穂の所だけを切断し、藁の部分は後で別に刈り取っていた。
もしそういった記述の際に穀物栽培が農場経営の中核として描写されている場合には、それはただ次のことを意味しているに過ぎない。つまりまた経済状況が不利であった場合でも、また大規模経営(で自給自足的な性格が強かった)の場合は家族(奴隷などを含めて)を養うという観点でそれが不可避であった、ということであり、特に古代において穀物中心の食事が一般であった場合にそうであった、ということである。≪ヴェーバーは「菜食主義」と書いているが、「穀物中心の食事」と解釈した。≫ここでカトーの農業書での農場経営の予算の立て方についての記述を見てみると、そこで見出されるのは、一人の労働者当たりの月ごとの小麦消費量は夏が4 1/2モディウスで冬は4モディウスとされており、そして足枷を付けられた奴隷についてはパンが相対的にそれより多くの量で想定されており、それ以外にはただ2番搾りのワインとそして副食物(pulmentarium)としてオリーブの落果≪自然に落ちたオリーブの実は油が取れる量が少ないため、塩漬けや酢漬けにして苦みを取って食用にした。≫があるだけであり、時々は塩漬けの魚、またオリーブ油と塩が供せられたが、しかしチーズ、モチノキの実、肉類については言及されていない。そこからまとめとして言えることは、コルメッラ 10) の時代には、面積1ユゲラ当たりで、最初の鋤き返し(proscindere、耕起)で2-3人日、2番目の作業である畝立て(iterere)が1-2人日、3番目の作業である再耕起≪土を更に細かくして整地する≫に1人日、種蒔き用の溝作り(lirare)について2.5ユゲラで1人日、以上を合計して耕起関連の作業だけで1ユゲラ当たり通常4人日が見込まれており、それ故に6-7ユゲラの耕地を一人が作業した場合は、その同じ期間に1ユゲラ当たり4-5モディウスの小麦が蒔かれたのであり(コルメッラ、II、9章)、そしてその種蒔きの量のせいぜい3-4倍強の収穫を計算することが出来たのであり、その結果として生じたことは、大体の正確な見積もりをすることは出来ずに、純益となる部分はいずれにせよ地主が労働者を養っていく上で必要としていた仮構のものに過ぎなかったのであり、もしその地主がその所有地の内で半分以下の部分にワイン、オリーブ油、そして他の園芸作物を育てようと欲した場合には、その時には例えばカトーの例では100ユゲラの土地のブドウ畑については、もっとも上手くいった場合で 10a) 16人の常勤の労働者を確保しなければならなかった(カトー 農業書10)。その他に明らかなこととしては、既にカトーにおいて穀物栽培への関心がブドウや特にオリーブの耕作のために背後に追いやられている、ということである。穀物についての記帳が単にある種の単式簿記でただ収入と支出を記入したものであった一方で、ブドウとオリーブの勘定は売り上げ、購入物に対しての支払金、売り上げの状態を示している売掛金が分かるようになっている(カトー 農業書2)。さらにオリーブ油の販売がその時々のオリーブ油の市況に合わせて調整されるべきとされていた一方で、穀物と(その当時はまだ)ワインの販売も定められた規則に従う業務の流れに沿ったものではなく、余剰のものが存在していることを前提として、古くなった在庫品の売却という扱いで、病気であったり年老いた奴隷がその業務を行っていたものだった 11) 。
10) コルメッラ II、4。
10a) コルメッラはまた7ユゲラのブドウ畑に対して一人の固定した、経験豊かな労働者をあてがうことを想定している。1,III、第3章。
11) カトー 農業書2。
そうした穀物やワインなどの販売は、定期的な決まった場所での競売という形で行われていたように思われ 12)、明らかに遠方の買い手と取引するということはほとんど想定されていなかった。なるほどカトーは農場が海や船が航行可能な河川あるいは交通量の多い街道の近くに位置している場合には、そうした遠方との取引は利益の上がるものとして言及している。しかしそれを行うことは刈り取りのための十分な労働者を確保できるかどうかにより依存していた 13)。
12) カトー 先の引用箇所。
13) カトー 農業書1。
陸上輸送について実際の所、何れかのかなりの距離の遠隔地が想定されている場合には、敢えてやってみようということには通常ならず 14)、そしてコルメッラは、海の近くや大きな河川の側に農場があるということが、原材料と商品の交換取引を容易にすると言っている一方で、大きな街道の近くということは兵士の宿泊を強制されたり、そういった街道に出没するならず者の存在のため、望ましいことではないとしている 15)。いずれにせよローマにおいての穀物市場はそれをローマの農業全体で見た場合、海上輸送により国家のために輸入された≪ポエニ戦争などの勝利などによって獲得したシチリア、北アフリカ、エジプトなどから≫穀物によって失われることとなったのである。それに対して地方市場においては、こういった海外から輸入された食物が十分需要を賄うほど入って来ることは稀だったので、それ故に定期的な、規模は大きくないにせよ、しかし確実に行われる販売は、農業での穀物の場合でも確実な需要があったのである。
14) ウァッローの計算によれば、海沿いの土地については、贅沢品や嗜好品の栽培に適した土地で取ることが出来る地代については、内陸部の同様の土地と比べ5倍も高かったのであり(ウァッロー 農業書III、2)、大量に栽培される食品についてはこの差の意味するところは更に大きかったに違いない。
15) コルメッラ I、5。
それ故に非常にしばしば語られてきてまた一般に否定することも出来ない海外からの輸入農作物との競争の作用については、そこまで緊急に対応が必要なものではなかったとも考えることが出来よう。国内の大部分の場所において情勢としては安定したものに留まっており、農業書の著者達はその時点でもまだ良く知られた近隣団体との秩序ある一致団結を前提として話を進めており、隣人達との良い関係を継続することに価値が置かれており、農機具や穀種についてお互いに融通しあう相互扶助は自明のことであり 16)、そして各人の間での無利子の(相互の)借金(mutum)の依頼は、こうした確固たる隣人団体の片鱗が残っていなかったらあり得ないことであった。
16) カトー 農業書5と142。カトーはもちろん相互扶助というものを、ある確固とした諸家族の集まりの間に限定して理解しようとしている。しかし運搬用の家畜の相互の貸し借りについての支持は農業書4で規則的に言及されている。
穀物、オリーブ、ブドウ栽培の運命
しかしもちろん穀物栽培が死刑宣告されていたということは疑いようがなく、何故ならば生産者の側から見て業務として(穀物を)売却することはされておらず、地方市場で売却する品目としても、ただ条件が揃った婆にのみそう扱われていたからである。そのことは次の場合により一層重要なこととなった。それは土地に関する事情という点で都市的なものの見方が流入して来た場合にであり、それは定住方法とか都市の市場に対しての政治的な関わり方をどのように一緒に持ち込んで来たかということであり、しかしその上に更に、ローマに定住している大地主達にとっては土地貸し代という現金収入は差し迫って必要なものであったからであり、土地貸しの代金の額はその者達の利害関心にとってもっとも重要なものとなったに違いない。カトーの著書やその他の農業書の著者達はある一定の方向で、例えばテール≪Albrecht Daniel Thaer、1752~1828年、ドイツの農学者>の「合理的な農業」と同様のことを要求しており、それらは次の事から発生しているものである。つまり、投資として農地を購入しようと意図している者に、本の中で助言を与え、そして次のことを詳しく説明している。その内容は常に実践の中で積み上げられた好事家によるノウハウという形で、農場経営を始めようとする者が知っておかねばならないことであり、その目的はその者が使用する農場の管理人を大枠で上手に管理出来るようにすることであった 17)。
17) カトーの助言――農業書2――は農場の管理人を訪ねてその者がどのように農場を管理しているかの監査についてのものや、そしてその管理人がそこで働く家父長達からどのようにその専門的知識を吸収出来るようにするかの方法についてであり、それが非常に特徴的である。
穀物栽培が収益を生み出さないということは、既にカトーの時代において次の結果をもたらしていた。それはつまり、農場経営者達が穀物を栽培している耕地に対して土地改良のために資金を投入することを多くの場合ためらわせた、ということである 18)。その者達はむしろ重点を農場経営の他の分野に移していっていた。良く知られた例として、時間が経過するほど盛んになっていくブドウとオリーブの栽培については既に述べた。それと並んでまた豆類、野菜、そして樹木の栽培が前面に登場して来ていた 19)。
18) カトー 農業書1:scito…agrum…quamvis quaestuosus siet, si sumtuosus siet, relinquere non multum. [心得よ…土地を…それが収益が上がるものであっても、もし多くのコストがかかるのであれば、利益として残るものは少ないのである。]
19) カトー 161でのアスパラガス、156以下でのキャベツ。豆類は最初にコルメッラ(II、10以下)の農業書においてより多く前面に登場している。同様に野菜または花卉は明らかに生産量が増えていっていた(コルメッラ、I、10巻)。樹木の苗圃においての種子の利用や逆に海外からの購入はウァッロー I、41に出ている。樹木の栽培についての詳細な記述は既にカトーの40以下に出て来ている。(接ぎ穂そのもの、接ぎ木はウァッローのI、40にて、植木鉢による栽培はカトーの52.)都市の近郊では、カトーの書にまた植林が利益性の高いビジネスとして≪薪の生産のため≫推奨されている(農業書7);それと並んで建築材料としての利用やザルなどの製造のための葦と柳の栽培が多く言及されている(salictum[柳林]は農業書1にて耕地においての自明のカテゴリーの一つとして登場している)。
ブドウやオリーブ栽培の畑を所有するということは、穀物栽培との比較で、ローマのこの時代では、最近の言い回しを許容するならば、そういった穀物以外の栽培は労働集約的ではなく資本集約的ということである。コルメッラによる計算では、ブドウ畑の場合には苗とその他ユゲラ当たりで必要なものの費用は地代の3倍にまでなっていた、ということである 20)。
20) コルメッラは1、IIIの第3章で次のように計算している:7ユゲラのブドウ畑に対しては一人のブドウ畑専門の農夫[vinitor]が必要であり、共和政期のような足枷を付けられた罪人の奴隷[noxius de lapide]ではもはや駄目で、その当時は経験豊かな労働者を雇うことになったのであり、それには6-8,000セスティルティウスの費用がかかった。≪通常の農場奴隷の約3倍≫それに加えて更に地代が1000ユゲラ当たりで7,000セスティルティウスかかった。そこに更にかかる費用が vineae cum sua dote [自分自身の持参金付きのブドウ]≪持参金は文脈によってはジョークとしてコストの意味でも使われた。≫、つまり「支柱と苗木」[cum pedamentis et viminibus]の費用で、2000ユゲラ当たりで14,000セスティルティウスが必要だった。ここまでで合計29,000セスティルティウスになり、それに更にブドウが実際に収穫出来るようになるまでの2年間の期間利息で6%で3,480セスティルティウスがかかった;――合計の投下資本は32,480セスティルティウスとなる。6%の利息をカバーするには収益として1,950セスティルティウスが(1年当たり)必要となる。1ユゲラ当たり1クレウス[culleus](=525.27リットル)、1クレウス当たりの最低価格は当時300セスティルティウスであり、利益は2,100セスティルティウスになる。この全く面白くはないが仕方なくそこで行われている計算は、明らかに次のことを前提としていた。つまりブドウ専門の農夫と非常勤の労働者の扶養料を――というのもブドウの木というのは幹を作らず蔓で支柱に巻き付くのであるが(カトー 32)、しかしそれでも一人の労働者が7ユゲラ全てをカバーすることは不可能だったのであり――耕地全体で追加の労働力を見込んでおく必要があった。そのためこの費用はブドウ畑のみの勘定には付けられていなかった。
そういうことがあっても、コルメッラとカトーの述べる所によれば、人数に関してはブドウやオリーブ栽培は、同面積での穀物栽培と比べてより少ない人数しか必要ではなく、そしてオリーブ栽培の場合は労働力という点で見る限り、特に有利だったのである 21)。
21) カトーは240ユゲラのオリーブの栽培に13人、100ユゲラのブドウ畑には16人の常勤の労働者が必要だと見積もっている。オリーブとブドウの栽培はプランテーション的なやり方で鋤を用いて(ウアッロー 1,8)、より多くの肥料が投入され、そして共和制期には最低レベルのコストの奴隷を使って行われた可能性がある(後述の箇所参照)。
こうした事情は農業技術と同じくカトーの時代からコルメッラの時代まで大きく変わることはなかった可能性がある。
牧草栽培、大牧場の経営と牧草農場
全く同様にこういった事情は集中的な牧草栽培の場合にも見られるものであり、それはカトーにおいて、またウアッローにおいて更に前面に登場している 22)。
22) カトーによる農場経営での収益性の高いものの順番は(農業書1):ブドウ、灌漑された耕地での野菜・果物栽培、柳の林、オリーブ、牧草地、穀物畑、伐採林≪薪の採取≫、雑木林、ドングリ林(林の中の牧草地≪豚にドングリを食べさせて飼育した。≫)。ウアッローは1、7でbona parata [良質な牧草地]、――先祖代々の良く整備された牧草地(つまりゲノッセンシャフトによって十分に灌漑された牧草地)――特に記載している。
ここにおいてもまたかなりの程度の資本投下が必要だったのであり、特に灌漑設備への投資がそうであり、それについてはゲマインデの公共水道から水が1時間当たりいくらの料金で供給されたのであり 23)、そして土地の境界線をまたぐ水道管の敷設が地方条例によって 24) 承認されたのである。
23) C.I.L.、XIV、3649。また3676他多くの箇所でも。
24) ゲネティヴァ・ユリアの法規(Eph. epigr. II, p.221以下)第100章。
先に詳述したローマにおいての対物信用の特質からすると、土地改良が目的で個人資本を継続的に課税される所有地に投資することは簡単に出来ることではなかったので、このような集中的な土壌改良へと移行するためには現金が必要だったのであり、それを行うことが出来たのはただ大地主のみであったのである。他方で中小の地主が労働力と資金の両方を同時に節約しようとした場合に可能だった方法は、牧場経営に移行することであった。しかしこの牧場経営というのもまた大規模経営という形でのみ行われ事実上そういった中小の地主達によって行われることはほとんど無かったのであり、そのことは折々主張されて来たが、その理由はイタリア半島でそういった牧畜という経済活動に適していたのは一部だけであり、古代においては特にアプリア≪現在のプーリア州でイタリア半島を靴としたら踵の部分≫においては、そこで見出されたのは calles、つまりアルペン山脈の中の牧草地においては≪ヴェーバー当時の≫今日なおそうであるように、≪定住して牧場を営むのではなく≫多数の家畜を引き連れて山中を移動していく移牧という形の牧者である 25)。
25) 帝政後期にそこで発達したのは、組織化されて他人に危害を及ぼす追剥の群れであった。テオドシウス法典のタイトル29、30、31を参照。ウァッローの農業書の第2巻は移牧者についての一般的な状況が説明されている。80-100匹の羊については1人、50頭の馬については2人が平均的な人員の数であった。アプリアでは馬追いが行われ、また同じくそこで輸送手段として使用するためのロバの移牧も行われた。ロバの価格はこのために高かった。ウァッローの p.207 (Bipont)によれば、一定の距離当たり40,000セスティルティウスであり、コルメッラの時代ではよく訓練された奴隷の5倍の価格であった。家畜の群れは夏に高地にある公有地へと追い立てられる際に、徴税人によって牧畜税取り立ての目的で登録された。家畜の群れは冬にはアプリアでは、そこでは土地が小道で区切られて分割されていたが、より面積の広い、古代では800ユゲラの、後の時代では5,000ユゲラに達する農地・牧草地・家畜小屋が複合したものに留まった。この地域においては通常の農耕を主とする植民の試みは、どこにおいてもほとんど成功することはなかった。皇帝もまたアプリアでは山中の道と大規模な移牧用の家畜の群れを所有していた。そういった道が公有地化されることは、確からしいこととしては多くの場合起きておらず、むしろそれらの道全体はイタリアのムニキピウムにおいて、その領土に含まれない土地の中で最大のものとなったのであり、それ故にそれらは一般的に私財領域という名前で呼ばれていたのである。移牧者は武装しており、リーダー[magistri pecudis]に率いられて行動し、そのほとんどは奴隷であった。カエサルはそういった移牧者のグループの労働者の1/3は自由民にしなければならない、という法律を通そうとしていた。≪だが実現していない。没落農民の救済が目的。≫炊事などのために移牧者の群れに一人の女性が付けられ、1日の内のメインの食事はリーダーの下で全員が一緒に取り、それ以外の食事は各人がそれぞれ家畜の群れの側で取った。このようにまとめられた家畜の群れは、それが皇帝の所有物だった場合には、請負業者[conductores]に全体として任された。参照C.I.L., IX, 2438、そこではサニピウム≪現在のモリーゼ州のカンポバッソ県のセピーノ≫の地方官吏が請負業者への嫌がらせを中止するよう命じられている。その他の場合については、先に引用したウァッローの箇所と比較せよ。
ついには主要都市や交通量の多い街道の近くでは、特別に主要都市の贅沢品の表に載せられたようなものが生産され、そこにおいては実際大規模な家畜の飼育場が存在し、――いわゆる villiticae pastiones [ヴィラ内の飼育場]であるが――、それらに対しては多額の使用料が課せられていた 26)。
26) 参照ウァッローの1. IIIの冒頭と第1章にて。
こういった方向の発展は文献史料においてもまた現れており、というのは一方でカトーが牧畜をまだ農耕との有機的なつながりの中で取り扱っているのに対し、ウァッローは res pecuaris [牧畜]に既に独立した位置づけを与えており、その方針で独立した章を与えて詳述しているが、そして同様に villitane pestiones についても更に詳細に説明している。しかしその他の点では耕作の技術については農業書の著者達の記述を見る限りでは、カトー、ウァッローとコルメッラの時代においては本質的な違いは存在しない。もっとも叙述された農場経営の次元の拡がりという点ではカトーと比較してコルメッラにおいての方がより拡がっている。ワインとオリーブの製造は、カトーの記述(農業書3)によれば、まだ段階としては我々の時代で言う自家製造に留まっていた。最も頻繁に行われた業務としてのオリーブとブドウの収穫物の販売は青田売り≪まだ実が枝に残っている状態での売却≫であったように思われ、そしてこのような形での売却はまたコルメッラによれば収益性計算の基礎でさえあった;しかしながら全ての大規模経営者はブドウ搾り場やオリーブ油搾り機を、自前の専門作業者を確保していたのと同様に、自分自身で保有していた。私の考える所では、読者は次のような印象を持たれるであろう。それは、このようなやり方で経済における需要充足を自分の独占販売という形で取り込み、そして製品を市場で売れるものに仕上げていくという傾向が、大規模な経営においては拡大しつつあった、ということであるが――それは国家行政においては賃借料としての税を廃止することと並行して起きた現象であるが――その原因については後で更に取り上げる。――
大小の経営
今や次のことを確実に行わなければならない。それはこういった大規模な事業がその他の点では、特に事実上それが単なる大規模所有に留まったのではなく、大規模経営であったかどうかを考えてみることであり――それがもし正しいのであればどのような形態でそれが行われたのか――、そしてその大規模経営が帝政期における所有権についての法形成をどう導いたか、ということである。その際に十分考えてみるべき問題は、どのような人達が、独立してまたは誰かに従属して、農業経営に従事したか、ということである。ここにおいて特に問題とすべきなのは:自営する農民達であって生計を維持していけるような身分というもので、我々の時代の(独立)農民に比肩するような者達が、存在していたのか、ということである。確実であるのは、小規模な地主の身分が、第二次ポエニ戦争以来、非常な程度にまで失われつつあったと把握されていた、ということで、その結果として立法上はそれらの者を保護する必要性があるように見なされていた、ということである。
こういった傾向は後には見られなくなっており、モムゼンによる統計的な食料配分表 27) のおかげでそれが明らかになっている。そしてこのことはなおトラヤヌス帝の時代においても、≪貧窮した独立農民救済のための≫三人委員会が廃止された時期と比較しても、更に減少していた。
27) ヘルメス XIX、p.395以下。(食料配分表とローマの土地分割)。
こうした考え方が消滅していくという傾向は、ベネヴェント≪カンパーニャ地方のアッピア街道沿いの都市≫の山沿いの地方ではよりゆるやかに進行し、ポー平原でがより速く進んだ 28)。
28) ベネヴェントに(強制)移住させられたリグリア族≪ローマ北西部に住んでいたローマの先住民の一つ≫に対しては約40万セスティルティウスの資本が66人に対して分割されて与えられており、またウェレイア族≪Velejaten、リグリア族の支族≫に対しては52人に対して100万セスティルティウスが与えられていた。ベネヴェントにおいてはまだ農民が個人で所有していたものの方が多く、ウェレイア族については受領者がもらった金額はそこの農民の≪土地に換算して≫半分で10万セスティルティウス以下であり、多くの農民が所有していた土地の合計は元老院がケンススに登録した土地よりはるかに多かった。広大な(公有地化された)山岳地帯の土地の評価額は最大で125万セスティルティウスに達していた。
このことは先の注記の内容から引き出される仮説を証明することになっている。それは交通量の非常に多い街道の近くでは一般的な発展傾向が加速された、ということである。こうした傾向のもたらしたものが、多少の程度の違いを無視すればほぼ完全なものだったとしたら、いずれにせよそこで見て取れるのは、自営の小規模地主(自作農)の身分というものが、更なる土地制度の発展の中ではもはや存続し続けていけるものではない、ということである。―経済面での更なる発展についてはむしろ次の形の経営の在り方が目に付くようになっている。それは地方の土地での villa rustica[地方の農園]と並んで更に villa urbana[都市圏での農園]を所有することであり、またそれまでの耕作においては使われていなかった1年の中での特定の期間について、新たな業務に従事することであり、地主が1年の内の全期間都市に住みつくという状態は、しばしば不在地主という呼び方で非難されることとなった。(しかし)それによって地主達は経営の範囲を拡大することが出来たのである。土地貴族による政治的支配ということは、その者達が常にローマに滞在して政治活動に参加することに基づいていた。そのような人物としては、リヴィウスが描いたキンキナトゥス≪BC5世紀の伝説的政務官≫のように、あるカテゴリーを形成するものであり、実際にはそのカテゴリーに多数の者が属しているということはなかった。このような地主としてのその所有地の場所での不在は、むしろ意味するのは土地の投機目的での利用であり、また資本家的なビジネスに参加することであるが、このことは次のような結果をもたらした。それは大地主の地位というものが本質的には土地から上がる賃借料をただ消費するだけで、自分の農場はめったに訪れない、都市における資本家になっていた、ということであり、そのことはカトーとウァッローがその農業書の中でそういった傾向を嘆いていることから判明するのである。ある継続的な、彼ら自身による合理的な経済活動の推進は、一般的に言ってそういった土地所有について何かを期待するのではなく、定期的にある決まった額の賃貸料を得るというだけのものであり、しばしば単にその時々に収益が上がれば十分と考えられていたこともあった。
共和政期の小作人
それに対して検討してみる価値が十分にあると思われるのは、「農民」と「小作人」――colonus――という呼び方で――それぞれがこの表現で呼ばれているような身分としてあったとして――それぞれの自己認識[アイデンティティー]において、それぞれが社会的に重要な農民としての特性を保持していたかどうか、ということである。それを否定することとしてはまず第一に、既にローマにおいての小作権の法学的構成において現れている。小作人は概して第三者に対抗出来る法的手段を持っていなかっただけでなく――また暴力による権利の侵害に対しても無力であり――、その者達には地主[dominus]に対抗するための所有権上の保護も与えられていなかった。我々の時代に通用している法から見れば、あり得ないほど苛酷な条件で締結された賃借契約は、それは大家の組合とか似たような利害団体がたくらみそうなことであるが、次のようなことを目的とすることが可能になっていた:それは(契約解除の際は)賃借人は直ちに借りている物件を明け渡さねばならず、そしてそこには何らの自力救済の手段もなくそれが強制され得たのであり、その後になってもしその賃借人がそこに引き続き住み続けることの権利を立証出来た場合には、その退去によって被った損害についての補償を受けることが出来たのであり、こういったことは賃借人だけではなく小作人に対してもローマ法の基本原理として適用されたのである。次のことは言うべきではない。つまり平均的な事例を見る限りでは、このような劣悪な扱いは自明のこととしてまでは起きていなかった、ということであるが――いずれにしても次のことは確かである。つまり社会的に重要でかつその自覚も持っていた者達は、そのような劣悪な権利状態を甘受しようとはしなかったのではないか、ということである。国家から公有地を借りていた者は確かに国家に対しては不安定な状態に置かれており、特に契約がケンススでの登録期間が満了した場合に解除される可能性があって、そしてただ行政上の保護のみを受けられた場合にそうであり、その他の点ではしかしその者達はただ場所[locus]としての保護を、それが元々ただ一般的に存在していたもの、つまり占有されていたものとして、という範囲での保護を受けられるだけであった。個人の土地を借りていた者達については、こういったレベルの保護すら与えられておらず、そのことからはっきり分かることは、その者達の他の全ての社会的条件が劣位にあったことと、経済的に弱者であった、ということである。このことからすぐ明らかなこととして結論付けることが出来るのは、我々は大規模な賃借人の身分について、それが≪ヴェーバー当時の≫今日のイタリアにおいて大地主達と部分的に対立しているということを、そのまま古代ローマでも同様であったろうと考えるべきではない、といことである。≪ヴェーバーが言っているのは19世紀のイタリアでのメッガドリーナという分益小作制度を古代ローマの小作制度と同一視すべきではない、ということ。≫カトーは賃借人について、自分自身でその土地を耕作しないで、その土地を一族郎党に耕作させようと欲している者を厳しく諫めている。そしてまた確かに公有地が資本家達に対してかなりなまで大規模に提供され、その使用目的は個々の土地区画の大規模な複合体を賃貸目的で使うことであり、またそういった土地を次の程度までに投機のために使い尽くす(搾取する)ことであり、その程度とは個人の小地主には決して利用させてもらうことができないものであり、またその一方で manceps[中間契約者]の仲間たちが利用出来る公有地の管理については、その使い方について厳しくチェックされることがほとんどなかった、そういう程度である。lex censoria はなたそれについての条項などをその中に含めようとしていた。一般的にそういった状況に適合する形で、大地主達に対して、その者達がその土地の多くを賃貸ししている所では、それに対して小規模な賃借人が対置され 29)、そして土地区画の面積という点でより大規模な所有地の貸出しは、今日と同じく当時も相対的に高い賃料が課せられることが多く、このことはまた事業としても見ても有利なことだったからである。
29) 特にまた、これについては次に述べることになるが、継続して定住させられた小作人達は、圧倒的に小規模の賃借人であったに違いなく、中規模以上の家長達ではなかった。全ての我々が持っている知識(例えばメクレンブルクにて≪メクレンブルクは19世紀後半になってもグーツヘルによる大農場が継続し、農奴解放が遅れていた。≫)によれば、次のことが知られている。それは継続的な植民というものは、国家がより大規模経営の可能な農民をそこに公有地の領主または非常に大規模なグーツヘル、例えばプレス公のような地位の者≪プレス公ハンス・ハインリヒII世はシュレージエン地方に数万ヘクタールの土地を所有していた。≫、を送り込むことで行われ得たのであり;より小規模のグーツヘル達は常にただ小作人または小農民という立場にされたのであり、そういったことが植民地化という作業を非常に容易にした可能性がある。
何よりもまず土地区画について賃貸料を取ることは、定常的な土地レンテ≪労働を伴わないで定期的に入ってくる収入≫を取ることが出来るようにすることを目指すことを可能にし、そしてこのことは共和政期と帝政早期においては本質的な観点であったに違いなく、というのはそこから上がる収益はそこ以外で――つまりローマで――消費されることになったであろうからである。確からしいこととしてこの理由から、分益小作≪地主が土地を提供し、小作人が耕作し、収穫物を地主と小作人で分け合うという一種の共同事業形式の小作≫はその完成形までの発展はほとんど起きなかった、――分益小作は法律史料にただ一度だけ次のような内容で言及されていた。つまりそのことの法的な構成が――場所についてなのかソキエタース≪地主と小作人の事業組合≫についてなのか――疑わしく思われる、そういった内容である。地主が――その者が非常に規模の大きな地主階層に属していなかった場合に――確実な現金収入を得るための手段としてのオリーブ油とワインの製造を保留にして放棄したように、小作人との≪共同事業的≫関係もまた進展しなかった。そのことに符合していることは、地主(自身)が農業に必要な土地以外の装備一式[instrumentum fundi]を用意したということと、また小作人に対しては、一般に農場経営を立ち上げる際に、小作人の自由に任せて好きにさせることはほとんどなかった、ということである:小作制度の本質的な目的は、リスクを地主が負うのではなく小作人に押しつけるということと、また地主の方にとっては確からしいことは、大きな金額ではないにせよ確実な現金収入を得る保証を得ることであった。というのも、こういった関係の全体は、また地主が自分の土地で農耕を行う方法・やり方として把握されるからである 29a)。
29a) コルメッラ 1, 7。
土地区画賃貸の存在条件
以上述べて来たことの中には、本質的に既に後の時代の変化の萌芽が見られるのであり、それは農地においての労働のあり方が変わったことと関連している。たった今論じて来たように、土地区画単位の賃貸について、いずれにせよ最も頻繁に行われた土地の現金化の手段として語ることが出来るのであれば、しかしその場合でも次のようなことまでは言うべきではない。つまり全体の所有地の個々の土地区画への分割がしばしば行われた可能性がある、ということである。また次のことも考えられよう。つまり特に土地の大規模所有が発生しておらず、土地が多くの者に分割して所有されていた場所において、しかしながら農業書の著者達によって一般的に、地方の農場で、管理人と多少の範囲の差はあっても広範囲の家族集団によって形成されていた人間集団が常に、より広範囲な土地においての農業事業の中心としてどこにおいても前提として扱われているのであり、そしてまたコルメッラはただ agri longinquiores [longinqui fundi]、つまりその農場経営の中心地から地理的に離れた場所にある、相対的に小さな土地区画と分農場を小作人へ≪小作地として≫譲渡することについてのみ語っている 30)。
30) コルメッラ、先に引用した箇所。
特にブドウとオリーブの栽培は、非常に規則的に大地主の本来の支配領域で行われており、全体の事業においてのその部分は、投機的かつ収益の上がるものと評価されて最も高度に統合されていたのであり、その一方次のような耕地の耕作については、それは多くの労働力を必要とししかし高い賃貸料を取ることが出来ないような耕地であるが、ブドウやオリーブの耕作とは反対に、相対的に見て自立していて、自分自身のリスクで耕作を行う小規模の家長で自分の家族をそれで養っていた者、つまり小作人に≪小作地として≫譲渡されたのである 31)。
31) もちろんここにおいても大地主は自分の所有する地所で、より良いものは出来るだけ自分の元に残しておいたのであり、その場合その者達はそこを貸して得られる小作人の賃借料の金額よりも多い金額を自分自身で稼ぎだそうとしたからである(コルメッラ 前掲箇所)。その他の点ではしかし彼らはまさに穀物用の土地[ager frumentarius]を≪小作地として≫譲渡したのであり、というのも小作人は少なくとも濫作によって万一の損害を受ける場合にその程度を最小に抑えることが出来たが、≪雇い入れる≫奴隷を使った場合にはしかし、必要不可欠な人数を細心の注意を払って注文した場合であっても、経済的には非常に損する結果となる場合もあったからである。(コルメッラ 前掲箇所)。
このやり方ではまた適当な額の賃貸料をそれに加えて獲得することが出来たが 32)、その理由は地方においての諸市場が、それは穀物取引については全体にほとんど扱われていなかったのであるが、農民による市場での直接的な穀物販売については、先に注記したように、恒常的な可能性が存在していたのである。
32) そういった地主達は次の理由からもこのやり方を採用出来るようになっていた。というのは近頃ゾムバルト(sen.≪=ヴェルナーの父であるヴィルヘルム・ゾムバルト≫)によって世の中に認められるようになった”Kuhbauern”≪直訳は雌牛農民。酪農を兼業して不作の時も何とか自活していくようなしっかりした農民のこと。≫を似たような農民層として見なすことが出来、そういった農民達は自分とその家族郎党の労働力だけを用い、一般に他人を雇い入れることが無く、それ故に固定費の支払いが無く、不作の時にはその者達自身だけで何とかやり繰りし「飢餓を耐え凌いで」[durchzuhungern]いたのである。結局のところは小作人の生存能力にとって、それにもかかわらず、またはむしろまさしく、小作人達の非独立的な経済的地位によって、次の要素が考慮されることになる。その要素とは小規模の地主に対して大地主の賃料の、他が同一条件の場合での優位性を基礎づけたのであり、そしてまたそれが次のことの基礎にもなっている:小作人達の生存能力についての地主自身の利害関心が、この者達に経済状況の厳しい際に一定の土台を与え、また非常に程度の大きい危機の衝撃を、地主達が所有している土地全体の経営においての諸要素の弾力性によって分散した、ということである;他方では土地を小区画に分割してそれぞれを賃貸して小資本を得ることによって、結果として小規模地主が持つことが出来ない事業の運転資金を確保出来るためより経済的に上手くやっていけるのであり、そして相続開始の際の不動産債務のリスクも取り除くことが出来た:大地主は、その者の意に適うように見える者、多くの場合は相続人の一人を小作人にしたのである。≪相続は今日と同じで財産だけでなく負債も引き継ぐが、小作人になるのであれば負債を引き継ぐことなく、土地の利用権だけが入手出来る。≫
地方における労働者
それでは大地主のその支配地に存在している農地で、そこで耕作を行った者達は一体どういった人員であったのだろうか?大地主の農場には、ほぼ自由民であるような日雇い労働者を見出すことが出来ないということは改めて強調する必要もないことである。奴隷による農場経営と、借金が返却出来なくなって強制労働を命じられたプロレタリア、または不法行為または握手行為の結果としてその農場の家族に加えられた市民の家の息子≪まだ独立していない息子≫達、それらがほぼ農業を事業として行う場合の主要な労働力の形態であった、――そのことについては農業書の著者達は全く疑念をはさんでいない。しかしながらもっぱら奴隷だけを使用することは、奴隷労働の上に本質的に構築された経営方式それ自体にとって、きわめて不利益な点が存在した。まず第一の点は奴隷が死亡した場合の資本損失である。ウァッローはそのため次のようにアドバイスしている 33)。それは健康に害があるような場所での作業には、奴隷ではなく自由労働者を使うということで、何故ならば万一その者達が病気になったり死亡した場合でも地主がそれを補償する必要は無かったからである。
33) ウァッロー 1, 17。
もう一つのより重要性の高い要素は、ローマの全時代を通しての農業における労働者確保の基本的かつ完全に普遍的な困難さと関係している:それは労働力の需要と供給のミスマッチで、種蒔きの時、更にはむしろ収穫時、そしてその他の時季であってもそうであった。多くの奴隷を例えば収穫時に必要な人数だけ確保しておかなければならない、ということは、何もしない労働力を数ヶ月間も扶養し続ける、ということを意味していた。カトーの時代にはブドウとオリーブの栽培を一括して請け負い業者に任せることでこの労働力不足を何とか乗り切ろうとしていた。同時に耕地の土地造成・土壌改良の作業も専門業者[politores]に≪次に栽培する作物用の耕地について≫任せることが行われ、また最初の植え付け作業、つまり種蒔きと耕耘も当時一部は業者に委託されていた 34)。
34) 土地改良[politio](カトー 農業書136)の代金は、良質の耕地の場合は収穫の 1/8、質の劣る耕地の場合は 1/5であった。ブドウの栽培を部分的に外部の業者に委託するのは同書の 137 に出ている。オリーブ収穫作業の請け負いは:カトーの 145、オリーブ油の圧搾作業は 146、まだ樹に成った状態のオリーブの販売は同じ箇所、在庫しているワインの販売は 147、――ブドウを搾り器で搾った後に 148本単位で容器に詰めることは厳密な先物取引的性格の手続きとして行われた。牧場での冬期の食料の販売は 149 に出ている。羊毛や羊肉など[fructus ovium]については 150に出ている。どこにおいても地主は労働者の扶養料の一部を負担していたし、さらには多くの場合は必要な道具も供給しており、例えばまた部分的な作業の委託業者に焼成した石灰を供給≪イタリア半島では多く採れる石灰岩を高温で焼くと土壌改良用の生石灰ができる。≫していた場合もあった(カトー 16)。明白なのはただ(具体的な)労働がこういった形で作り出されねばならなかった、ということであり;農場主は必要な労働力を確保していなかったというだけの理由で、その者は現場の労働者にとって都合の良い形での請け負いを収穫の一部を支払いに当てるという形で準備しなければならなかった。労働者にその際にその他扶養料も支払うことになっていたのは、多くの場合自明のことであった;ディオクレティアヌス帝の布告である de pretiis rerum venalium [雇用者の賃金について]が示していることは、このことは自由民の労働者を雇用する場合の規則であった、ということである。
その際に農場主達は次のことを強制的に行わなければならない状態に置かれていた。つまり収穫物を無条件で安値で叩き売り、農地での作業についてそれぞれに対価を支払わねばならなかった。その理由は農場主達は自分達の力だけでは収穫させることも作業させることも出来なかったからであり、その結果として事業の収益は望ましくないほど低水準に留まった。穀物の収穫に至っては更に、それは営利事業としての可能性がほとんどなかったのであるが、それを行わずに済ますことは出来なかったし、かつまた家族を養うという意味でも必要であった。それ故に自由民の労働者が必要とされたのであり 34a)、その者達は多くの場合収益の点でそれなりに主要となる部分の労働に従事させられたので、それ故にカトーは十分な数の労働者[operariorem copia]を確保出来る地方を賞賛している。
34a) このことは我々≪ヴェーバー当時のドイツ≫の大土地所有者においての「自分の本来の」労働者に加えての「外部の(外国人の)」労働者の需要と適合している。東プロイセンにおいては、この外部労働者の必要性について全体の労働者の約1/4までの人数を使うことが許されている。≪ここでの外部労働者はおそらくポーランド人のこと。≫
しかしながらまた、こうした外部の労働者の使用を継続して行うことも不可能であった。定期的に現金で払わなければならない支払金の額が地主にとって大きな問題になって来れば来るほど、それだけいっそう奴隷、つまり「言葉をしゃべる財産」 34b)(instumentum vocale[言葉をしゃべる道具])の労働力の酷使は激しくなっていったし、それ故にまた農場経営のその他の世界からの隔離もいっそう厳しいものとなっていったのである 35)。
34b) それに対比されるものとしては “instrumentum semivocale” [半分しゃべる道具](家畜)と “instrumentum mutum” [物言わぬ道具](通常の道具類)があった。
35) 全ての農業書の著者達は次の点で意見が一致している(参照:コルメッラ 1, 8)、つまり農場の管理者は農場を市場から、そしてまた周辺の領域から出来るだけ遠ざけるように管理しなければならず、いずれの場合でも付き合うことを許された人間というのは農場主が許可した者に限られた。来客は原則として農場の中に迎え入れることが許されておらず(カトー 5と142、ウアッロー 1, 16)、奴隷達は一般に農場を離れることが出来なかった(ウアッロー、前掲箇所)。このことが次のことの主要な理由の一つであり、つまり何故、そういった農場が自分達自身の手工業者を育成することによって、町の手工業者を使わなくていいようにすることを試みたか、ということである(ウアッロー 1, 16)。
農場経営者達は無条件で、その農場の経営を自由民の労働者をより長い間雇って働かせてやっていく 36)ということを避けていた。
36) カトー 農業書5:(vilicus) operarium, mercenarium, politorem, diutius eundem ne habeat die.[(農場管理人)作業者、雇い人、土地改良人については同じ者を一日でも長く使い続けるべきではない。]
その結果起きたことは、自由民の労働力の供給が自然に減っていった、ということである。特に収穫期のような特別に労働力が必要だった場合以外でも、農場主達にとっては奴隷以外に農業で使えるものは存在しなかったし、都市のプロレタリアートは農業を好まなかったし、また実際に使うことも出来なかった 37)。
37) このことが示しているのは農業のための労働力への全ての需要が陥った運命であり、その労働力とは都市での浮浪者の収容所や同様の場所に収容されていた者達のことであり、また無料の交通手段が提供されたばあいに独力で農場まで行けた者達のことである。都市においての無職者で農場で使用可能であったのは全体の1%にも満たなかった。帝政期の末期には無職者は精力的に農場へと移動しそこで自身の労働力を地主に無条件に[brevi manu]提供した(後述の箇所を参照せよ)、――このことはその他の時代では地主達にとってほとんど起きなかったことである。
この結果として起きたことはまず第一には、周知のように、奴隷の労働力の搾取が一層強められた、ということである。その当時地主達が購入した奴隷は最低レベルの価格のものであり、それは noxii と呼ばれた罪人の奴隷であり、その目的はその者達をブドウとオリーブの栽培に使用するためであり、それについてはコルメッラにおいては審理として説明出来る動機が存在したのであるが 38)、この手の罪人連中は一般論として抜け目がない性格を持っており、それ故にブドウやオリーブの栽培に適している者として使われたのであるが、一方で穀物の栽培については手堅い性格の作業者が求められたのである。
38) コルメッラ 1, 9 Plerumque velocior animus est improborum hominum, quem desiderat hujus operis conditio. Non solum enim fortem, sed et acuminis strenui ministrum postulat. Ideoque vineta plurimum per alligatos excoluntur. (Aus Anstandsrücksichten setzt er hinzu): Nihil tamen ejusdem agilitatis homo frugi non melius, quam nequam, faciet. Hoc interposui, ne quis existimet, in ea me opinione versari, qua malim per noxios quam per innocentes rura colere.
[一般に悪人の頭脳は敏捷に働くのであり、この仕事(=ブドウ栽培)にはそういった敏捷さが望ましい。実際の所、力があるだけでなく、鋭敏であり活動的な奉仕者をこの仕事は必要とするのである。このため多くのブドウ畑が鎖につながれた者(有罪奴隷)によって耕作されている。道徳的配慮からコルメッラは次のように付け加えている:しかしながら同じ程度に敏捷さを持ち善良な者は、悪い者と比べてより良い仕事をするであろう。このことを追加で述べたのは、私の意見が無実の者より罪人に農場の作業をさせるのが良いと主張していると思われたくないからである。]
コルメッラがそこで更に推奨しているのが奴隷達を原則的に疲労困憊の状態になるまで働かせることで、そうすれば奴隷達は働いた後はただ眠るだけで余計なことを考える暇がなくなるから、ということである 39)。
39) コルメッラ 1. 8(p.47 Bipont)。
農場主達はその配下の奴隷について出来るだけ沢山の子供を産ませようとした 40)。
40) コルメッラ、前掲箇所。
農場主達は農場の管理人に対し、男女の奴隷の間での結婚に相当する確定した関係になることを、そういった事情から規則的に認めており、むしろそういった関係を奨励するだけではく、要求すらした 41)。
41) コルメッラ 1, 8。ウアッロー 1, 17。管理人達は “conjunctas conservas (habeant) e quibus habeant filios” [親密な女奴隷を内縁の妻として持ち、その者から息子達を得る。]
それ以外では男性奴隷は、無秩序なあるいは恣意的に統制された男女交際の結果として息子達の父親となることはなく、ただ女性奴隷だけが息子達の母親となった。≪この説明はヴェーバーが母権制の成立の理由とするものと同じである。実際にはローマの農場では奴隷が法的な父親になることはなかったものの、いわゆる乱婚関係ではなかったとされ、ヴェーバーの議論はある意味想像に基づいている。≫というのは彼女達が産んだ子供達のみの養育が彼女達に任され、そしてそれが報賞の対象になっていたからである(コルメッラ 前掲書)。その他の点ではしかし、一般に農業書で描写されているのは、というのは奴隷達は兵舎のような住居に一緒に入れられていたのであるが 42)、しかし同じ宿舎の住人同士の連帯についてはあり得ず、そうではなくてただ女性奴隷にその産んだ子供の数に対して報賞を与えていた、ということであり、――それは時には一時的な休業を与えたり、時にはその女奴隷を解放してやる場合もあった 43)――そして男女奴隷の交際の規制については自由競争に任せるようにしており、ただもちろん目的に沿うように農場管理人の監視の下にそうしていた。
42) 奴隷 “instrumentum vocale” の住まいは家畜小屋の中に設けられていた。奴隷達は有罪奴隷ではない場合は、南に面した部屋[cellae meridiem spectentes]で寝て、鎖につながれた有罪奴隷は地下にある囚人部屋で寝(”quam saluberrimum subterraneum ergastulum, plurimis, idque angustis, illustratum fenestris, atque a terra sic editis, ne manu contingi possint”[出来る限り健康的に作られた地下の奴隷部屋を、多くの狭い窓で採光するようにし、しかもその窓は床から十分高く設けられていて手が届かないようにすべきである])ていた。農場管理人は農場の門の隣に住んでいた。監視人は我々の≪ヴェーバーの≫時代の兵舎における室長用の仕切部屋と同じような個室を与えられていた(コルメッラ 1, 6)。食事の時はしばしば家族と見なせるようなメンバーが一緒に食べ、監視人は特別なテーブルで食べたが、しかしそれは奴隷達を見渡せるようにするためであった(コルメッラ 11, 1)。
43) コルメッラ 1, 8。 Feminis quoque foecundioribus, quarum in sobole certus numerus honorari debet, otium nonnunquam et libertatem dedimus, cum complures natos educassent. Nam cui tres essent filii, vacatio, cui plures libertas quoque contingebat. Haec enim justitia et cura patrisfamilias multum confert augendo patrimonio.
[またより多くの子供をもうけた女奴隷について、一定の数の子供によって報賞に値する者は、もし何人かの子供を育て上げた場合には、時々の労働の免除やあるいは奴隷身分からの解放を我々は与えて来た。例えば3人の子供がいた場合には労働が免除され、それ以上であれば自由さえ与えられたのである。このような公平さと家父長としての配慮は、結局は財産を増大させることになる。]
奴隷の身分からの解放は、年老いてもう子供を産めなくなった女奴隷を自由にするという人道的な形で行われた。それ以外でも農場主達は高齢になった奴隷達を何らかの形で処分することを試みた。(カトー 2)。その他の場合でも、農場主達は昔から年老いた病弱な奴隷を農場から追い出して来ており、それは自分自身の子供と奴隷の子供がもはや使用出来なくなった時と同様であった(ユスティニアヌス法典 8, 151)。そういった不要になった者達を殺害することをクラウディウス帝は禁止し(スエトニウス「ローマ皇帝伝」25)、そしてそういった者達を追い出す際にはその者達が自由の身分となることが出来るよう規定した。
しかし更には――このことがより重要な点であるのだが――収穫時に必要となる労働力の大部分を恒常的に保持しておく必要性によって次の傾向がより顕著に現れて来たに違いない、つまり出来る限り全ての必需品を自分自身の経営の中で手に入れ、さらに生産物を市場で売れるものに自らがしていくということであるが、その理由はこのようなやり方によって通常は余っている労働力を繁忙期以外の月であっても活用出来たからである。ギリシア語における ἐργαστἠριον 44)[作業場、工房]に相当する ergastulum というラテン語が昔から農場において使用されていたが、そこでは鎖を付けられた奴隷、債務者、そして罪人が働きかつ寝泊まりしており 45)、また他の禁固刑に該当するものがそこで刑に服したのであり 46)、それは多くは天窓付きの地下室であった。
44) 同じ語が碑文では公的または私的な工房(=パラディウス≪4世紀のローマの農学者≫の言う fabrica)の意味で使われることは稀ではなかったし、またある種の土地の使用方法も意味し、その例として C. I. Gr. I. 1119 には、耕作や施肥――κὀπρον εἰσἀγειν [肥料を加える]――が禁じられた場所について、その土地区画の隣りに ἐργαστἠριον が置かれていた、というものがある。
45) 鎖に何か不具合がないかどうかの確認は農場管理人の義務となっていた(コルメッラ 11, 1)。
46) そういった刑罰を科すことは農場管理人の権限であった。ただそういった罪人を許すことはただ農場主自身のみが出来た(コルメッラ 11, 1)。元々は ergastulum はまた隔離棟≪特にハンセン病患者の≫の意味でも使われた。後には患者は valetudinarium [回復中の病人の収容施設]に入れられ、そこではまさに多くの軍事的な隔離棟と同じく食事制限と拘禁が治療法として実施されていた(コルメッラ 12, 1);そういった隔離棟の病人の世話を一緒に住んでいる奴隷が行うことは、それは病人には望ましいことではあったろうが、許可されていなかった。≪この記述はヴェーバーのコルメッラの書の誤読。実際にはvaletudinariusという名前で呼ばれた専任の奴隷が病人の世話をしたのであり、誰も世話しなかったということではない。おそらくヴェーバーは valetudinarium と valetudinarius を同じような意味と勘違いしている。後者は「隔離棟係」といった意味。≫
そこで行われた受刑者達の労働は、必ずしも常に特別に決められたものではなかった、ということは考えられることである。しかしウァッローがその農業書の1年の農業暦の中で、耕作に必要な労働力についてほんの少ししか言及していない一方で、コルメッラが要求しているのは、洗濯は全て農場の中で行うことであり、そしてパラディウスは次のことを主張している。つまり農場主は自前の鍛冶屋、大工、桶屋、そして陶工を備えるべきということで、そういった作業を町の職人に依頼することを完全に無しで済ますことである 47)。
47) パラディウス 1, 60。次のことは知られている。それはアウグストゥスが自分の家で織った衣服だけを着用していたことである(スエトニウス 「ローマ皇帝伝」アウグストゥス第73章)。≪スエトニウスの書に書いてあるのは、アウグストゥスがただ家族が織った衣服だけを着用していた質素な人であったというだけで、別にアウグストゥスが自分の農場で織物を内部でやらせていたという意味ではまるでなく、無関係で余計な注釈である。≫
オイコス≪ギリシア語で「家」のことで、閉鎖的な家族経済から、大規模な家産制まで広く示す概念≫の自給自足、それをロードベルトゥスが、その他の部分では非常に才知あふれる古代の経済史の全体の過程についての議論において、基本的要素としており、彼によればそれはしかし帝政期には消滅してしまったと把握する必要があるとしているが、しかしながらそれはまた地方においての大土地所有においては、本質的な部分においてはまだ発達中であった。カトーの時代になると、次のような非常に目的合理的なことが利害関心の最前面に来るようになった。それはつまり、経営において産品の再加工・追加加工を減らすこと、分業においてそういった業務を解消すること、農園主のリスクを除去すること、そして農園主自身に定期的な現金収入を確保することである 48)。
48) コルメッラにおいてもまたウァッローからの伝承として、次の農場管理人への指示を引用している、それはどんな時でも農場主の資金流動性を保ち、いつでも出金可能にしておくこと、それ故に主人のお金を何かの購入や業務のための何かに使わないということで、それ以外にもいつも前提とすべきことは “ubi aeris numeratio exigitur, res pro nummis ostenditur”(コルメッラ 11, 1)。[現金が不足する場合は、物を現金の代わりに支払うことになる。]≪コルメッラが言っているのは、まさしく現金が手元に無い時は現物で支払わざるを得なくなる、というだけであり、ヴェーバーの文脈から想像される「現金を支払わないようにするため、なるべく現物で支払うようにせよ」という意味ではまったく無いことに注意。≫
カトーはこういった目的がどうやったら達成されるかについて、非常に詳細に記述している。後の時代になるとこうしたこと≪何でも自給しようとすること≫は非常にはっきりと分かる形で後退し、本来の業務が前景に来るようになった。農場の組織については、この後再度手短に見ていくこととする、――いずれにせよ私には出来るだけ目的のために労働力を使い尽くすことが出来るかどうかが、大地主型経営の課題を引き受ける上での本質的な基礎であると思われ、そういった大地主型経営は先進的な分業システムによって都市部の様々な職人達を使わないで済ませたのである。しかしながら収穫時の労働力についての本来の需要は、こうした分業システムによって解決されることはなかった。というのはこの需要を満たすためには、言って見ればある種の産業の先進化が必要とされたからであり、またその需要を満たすことによって損失を出すのも許されず、手工業の技術を取得した奴隷達が、純粋に農業的な労働力需要に対して、安価な単純労働力として使用されたのである。
帝政開始期に起きた農業危機
しかしながらこうした農業での危機は、ローマにおいての元首制の確立の結果として起きた様々なことによって、緊急に解決が必要な急性のものとなった。この状態は次の条件が満たされる限りは持ちこたえ得るものであった。その条件とは、侵略戦争と内乱の結果として奴隷市場に継続して労働力が供給されることである。アウグストゥスとティベリウスの下でのローマ帝国の国境の更なる拡張の断念は、こうした奴隷の供給を著しく減少させた。それはある時急に起きたことではないにせよ、一定の時間をかけて徐々に起きていた。その状況の結果として起きたことは、農業にとって耐えがたい状況であったに違いない。既にアウグストゥス帝の治下において、土地の占有者達が労働力を暴力(拉致)によって確保している、という訴えが成されている。アウグストゥスはそれに対してイタリア半島での罪人の名簿を作らせそれを調査している 49)。
49) スエトニウス「ローマ皇帝伝」アウグストゥス 32:rapti per agros viatores sine discrimine liberi servique ergastulis possessorem opprimebantur. Infolgedessen: ergastula recognovit. [農地を通行する者が自由人・奴隷の区別なく土地占有者によって捕らえられて奴隷収容所に入れられた。その結果として:罪人名簿が作られ調査された。]
ティベリウスの治下でも同じ訴えが繰り返された:旅行者や、更には軍隊への応召義務に応えないで逃亡している者が待ち伏せられ、――馬に乗ったならず者が、財産を盗もうとするのではなく労働力を確保しようとし、その者達はおそらく土地所有者達が街道に派遣したのであるが――そしてティベリウスは全てのイタリア半島の罪人名簿を、そのための臨時の官吏を任命することによって調査しその内容を改訂した、――それはほとんど農場調査官という言葉を使ってもいいようなものだった 50)。
50) スエトニウス「ローマ皇帝伝」ティベリウス 8:curam administravit … repurgandorum tota Italia ergastulorum, quorum domini in invidiam venerant, quasi exceptos opprimerent, non solum viatores sed et quos sacramenti metus ad ejus modi latebras compulisset. [(ティベリウス帝は)責任を持って監督した…イタリア半島全土の奴隷部屋について粛正を実施した。それらの奴隷部屋の主人達は、その者達が捕らえた者達を抑圧していたと非難されていた、。その捕らえられた者達は単に旅人だけでなく、また兵役への応召を拒否して逃亡していた者達までも含まれており、このような拘束部屋に強制的に監禁されていた。]
大規模な奴隷の反乱が≪再度≫起きることが懸念されていたが≪BC73~71に古代ローマでの最大の奴隷反乱であるスパルタクスの乱が起きている。≫、それは実際に起きる前に抑圧された(タキトゥス、年代記IV、27)。ティベリウスは全体としては大規模な奴隷を使った農場経営の規制を目論んでいたが、しかしながら元老院からの消極的抵抗により、その規制を土地所有者達に対して実際に行うことは敢えてしなかったのであり、またティベリウスは積極的な是正を行うことは不可能であると感じていたので、元老院に対して当時の土地制度の問題点を指摘する布告を出すことに留めた 51)。
51) タキトゥス、年代記II、33;III、53。
当時のイタリア半島においてはおそらく不動産価格は大幅に下落し、また信用需要は大であったであろう。というのは元老院はティベリウス帝の治下で貸金業者に対しその資本の内の1/3を不動産に投資するように命じているからである 52)。
52) タキトゥス、年代記、IV、23。アウグストゥス帝の治下ではアレキサンドリアの占領の後≪正しくはアエギュプトス{=エジプトの旧名}全体の私領化の後≫、金がそこからローマに流入し、それが≪豊富な資金によって≫一般的な不動産価格の上昇を引き起こしていた(スエトニウス、「ローマ皇帝記」、アウグストゥス、41)。
既にアウグストゥスが、アレキサンドリアの例では、地主に対しての無利子の貸し付けを認可しており 53)、そしてトラヤヌス帝による子弟養育支援制度≪地主に資金を融資し、その利子を貧しい人の子弟への義援金とした制度≫も、利率が低い状態に留まっていた
54) 状況において、同様の目的を持っていたと認め得る。
53) スエトニウス、前掲箇所。
54) Veleja においては 5%、もしかしたら更に低い 2.5% の可能性もあるが、確からしいのは 5%。
こうした共和制から帝政への移行期に起きた農業危機は深刻なものであった。しかしながら更に別の契機も影響を及ぼしていたのであり、農場経営を担った組織の重心の移動ということを検討する必要がある。
続き。夫役義務を負った農民を使用した農場経営の発展
ローマ帝国における平和の到来と元老院(貴族)支配が取り除かれたことにより、こうしたローマにおける障害に対してそれまでに水面下にあった政治的な利害関心が表面化することになった。大地主の純粋に経済的な利害関心が再びより前面に登場したに違いなく、それはドイツにおいての「永久ラント平和令」≪Ewige Landfriede。1495年に神聖ローマ帝国のマクシミリアン1世が、ウォルムスの帝国議会において、フェーデと呼ばれる私的復讐行為を全面的に禁止したもの。≫の後の状況と類似している。その時と同様にこのローマの時でも結果として起きたことは、大土地経営[Gutswirtschaften]が基礎付けられたことで、この表現はクナップ≪Georg Friedrich Knapp、1842~1926年、ドイツの経済学者、貨幣国定説で有名≫が使っている意味でのものであり、それはつまり労働者を使って経営する大農場と夫役義務を負った農民達が結合したものである。コローヌス≪完全な農奴ではなく、自由農民としての性格も持っていた小作人≫達は農場に隷属する農民と同様、収穫期における労働力の不足を補うために、手作業の、及び牛馬を使った夫役へと召集された。ある程度まで確からしいこととして、このことはほぼ常に起きていたことであった。古代ローマでのプレカリスト[Precarist]≪地主から恩恵として土地を借りて耕作している農民≫は、我々の意味での小作人では全くなく、農業労働者であって、地主からいつでも契約を取り消されることがある形で土地を借りている者で、――少なくとも私としてはこの制度について他の統一的な経済上の目的を考えることが出来ず、そしてその制度が隷属やそれに類したものと必ずしも関連したものではないということは、それがなお古典法学の時代にあっても存続していたことの理由となっている 55)。
55) D. 10 a[dquirenda] p[ossessione] 41, 2(ウルピアヌス)に次のような事例が詳しく述べられている。それは、まず誰かが小作人となって土地を借り、それから≪その期限が切れる時に≫プレカリストになることを要請した、ということである。≪rogiert はラテン語の rogo{依頼する}をドイツ語風にしたヴェーバーの造語。≫そこで扱われているのはまさに、小規模地主が、まず賃借料を払って土地を≪別に≫借り、そしてその契約が切れる時に、その地位の代わりにいつでも契約を打ち切られることがあり得る労働者の地位に留まる、ということである。それと適合するケースとしては、契約上地主がコローヌスに地代を請求してはならない(D. 56 de pact[is])≪地代の代わりに労働力を提供させるので≫、というものがある。
またここで重要なのは、この制度はコローヌスの労働の成果次第である、ということで、それ以外でそういった仕事がどういった意味を持っていたのかは、私には良く分からない。このプレカリストというものは、まさしくローマ的な純小作人の最初の形態である。共和制期にはコローヌスは一定の労働の成果に縛られていたということは、その者の地位はそのまま≪帝政期に≫持ち越されたのではなく、事実上はコローヌス達はいずれにせよ、子供達やあるいはその者自身が、場合によっては大地主のための単なる労働者となってしまう可能性を計算していた。しかしながら、当時重点が置かれていたのは支払われた賃借料であった。それに対してより目的に合った形の大土地経営の組織は、それは大地主達が自分達にとって、農場経営者としての性格がより重要になった時に構築したものであるが、もはやその第一の目的としては外部から定期的な現金収入を得ることが出来るという意向には重きが置かれていなかった。コルメッラはそのため次のように注意している。つまり農場経営者は、コローヌスの主な利用価値は賃借料ではなく、労働の成果[opus]に置くべきであると 56)。
56) コルメッラが注意している本質的な部分(農業書 I, 7の)は以下の通りである: Atque hi (scil. homines) vel coloni, vel servi sunt, soluti, aut vincti. Comiter agat (scil. dominus) cum colonis, facilemque se praebeat, et avarius opus exigat, quam pensiones: quoniam et minus id offendit, et tamen in universum magis prodest. Nam ubi sedulo colitur ager, plerumque compendium, nunquam (nisi si coeli major vis, aut praedonis incessit) detrimentum affert, eoque remissionem colonus petere non audet. Sed nec dominus in unaquaque re, cui colonum obligaverit, tenax esse juris sui debet, sicut in diebus pecuniarum, ut lignis et ceteris parvis accessionibus exigendis, quarum cura majorem molestiam, quam impensam rusticis affert … L. Volusium asseverantem audivi, patrisfamilias felicissimum fundum esse, qui colonos indigenas haberet, et tanquam in paterna possessione natos, jam inde a cunabulis longa familiaritate retineret … propter quod operam dandam esse, ut et rusticos, et eosdem assiduos colonos retineamus, cum aut nobismetipsis non licuerit, aut per domesticos colere non expedierit: quod tamen non evenit, nisi in his regionibus, quae gravitate coeli, solique sterilitate vastantur. Ceterum cum mediocris adest et salubritas, et terrae bonitas, nunquam non ex agro plus sua cuique cura reddidit, quam coloni: nunquam non etiam villici, nisi si maxima vel negligentia servi, vel rapacitas intervenit … In longinquis tamen fundis, in quos non est facilis excursus patrisfamilias, cum omne genus agri tolerabilius sit sub liberis colonis, quam sub villicis servis habere, tum praecipue frumentarium, quem minime (sicut vineas aut arbustum) colonus evertere potest, et maxime vexant servi.
[そしてこの者達というのはコローヌス達であるか奴隷であり、拘束されていないか、あるいは鎖でつながれている者達である。農場主はコローヌスに対して親切にし、寛大な態度を取るべきであり、そして地代の支払いよりも労働の提供をむしろ貪欲に求めるべきである:何故ならば労働の提供の依頼の方がコローヌス達にとってはより不快を感じにくく、更に全体ではより好意的に受け止められるからである。というのは、土地がきちんと耕作されており、利益が出ている場合は、ほとんどの場合で(悪天候に大きく影響を受ける場合や盗賊が襲撃して来た場合を除いて)損害は発生しないために、コローヌスス達が地代の減免を敢えて要求することはまずないからである。しかしながら農場主達は、その者達がコローヌス達に権利を持っている全てのことがらについて、それを執拗に求めるべきではなく、例えば地代の支払日についての注意だとか、または焚き木やその他の些細な付属物について、それらをしつこく催促すべきではなく、そういったことが地方に住むコローヌス達には単純な出費よりも重荷となるのである…私はかつて L. ヴォルシウス≪Lucius Volusius Sturninus, BC38または37~AD56年、ローマの元老議員≫は]が次のように熱心に語っているのを聴いたことがある。彼が言っていたのは、農場主にとって、自分の土地で、そこのコローヌス達が生まれついてそこでコローヌスとして暮らしているのがもっとも利益を生む種類の土地であり、そこではコローヌス達がまるで自分の父親の資産である土地で生まれたかのように感じており、また赤児の時にまだゆりかごの中にいた時からずっと長く親しんでいる状態を保っているのである…このことから次のことについて努力しなければならない。地方の農民、つまり彼ら自身が定住しているコローヌス達をそのまま暮らしていけるようにするということである。何故ならば農場主自ら農場で耕作を行うとか、あるいは家人に耕作させることが得策ではない場合があるからである。そういったことが実際に起きるのは、その地域の天候が農耕に対して向いていないとか、また土地がやせていて荒廃している場合である。しかしそれ以外で良い気候とほどほどに肥えた土地に恵まれている場合には、それぞれの地主の管理の仕方によっては、コローヌス達に耕作させるよりも、多くの利益を得ることが出来る:また土地管理人が奴隷を使って耕作させる場合でも、その奴隷達が非常に怠惰であったり、収穫物の窃盗を行ったりしないのであれば同様の結果が得られる…にもかかわらず、遠く離れた場所にある土地での耕作の場合で、地主がそこまで監督に行くのが容易ではない場合には、土質の良否にかかわらず、管理人の下で奴隷を働かせるより、自由民であるコローヌス達に任せた方が良い。特に穀物栽培の場合は(ブドウやオリーブの栽培の場合とは違って)コローヌス達がそれを駄目にする可能性は低く、逆に奴隷に任せた場合は駄目にする危険性がある。]
その際にこの”opus”という語がコローヌスによる賃借料を課された土地の耕作についての言及と考えることは可能であり、しかしそれがただ賃借料付きの土地についてのみ言及していると考えるのは不確かであり;確からしいのはその際に収穫と耕作のための夫役も考慮されているということで、事実上そこから結論付けられることは、コローヌス達がそれぞれ農場主の土地の一定の場所について受け持ち、同時に他のコローヌス達が別の場所を受け持っていて、一緒に耕作し収穫していた、ということである。この状況はつまり小土地区画の賃貸と、農場耕作と収穫作業の一部を請負業者に請け負わせることを結合させたものであり、カトーの時に既に知られていたように、ただこの段階では請け負う者が地主に対して事実上の従属関係にある小規模のコローヌスになっており、そしてそのコローヌス自身の、その者によって耕作される土地でそれに対して賃借料を支払っているものについては、そのままの賃借料支払い[Ablöhnung]が続いたのである。≪Ablöhnungという語をヴェーバーが用いているのはおそらくは農場での作業賃との相殺のようなケースも想定している可能性がある。≫私の考える所 、文献史料は確かに次のことを述べている。つまり事実上はこうした状況はこれまでの所で概観して来たように発展したのであろう、ということである。コルメッラがある箇所で示していることは、コローヌス達は土地を耕作することによって食べているのであり 57)、それは奴隷も同じであるが、――もちろんそれはその者達が農場主のために働いている間に限られてのことであるが、その労働は他の夫役と同様に普通のことだったのである。
57) コルメッラ II, 9。前注で引用した箇所が次のことを意味しているとすれば、つまりコローヌスがその借りている土地を良い状態に維持している場合は、remissionem petere non audit [賃借料の減免を敢えて要求したりしない]のであり、私がそこから想定することは、ここで扱われているのは農場主の土地の耕作である、ということである。もし農場主の土地が上手く管理されているのであれば、その場合コローヌスはたとえ凶作の時であっても自分が借りている耕地について賃借料の免除を求めないであろう。
こういった状況はビジネスとして見た場合は次のように把握することが出来よう。つまりコローヌス達が労働者として農場主の土地の耕作や収穫の作業を行うことを受け入れ、そしてその者達への賃金は収穫物の一定量に対して、ある決まった割合を受け取るという形で成立していた。こういった実態は、経済的に重要なことという観点では、作業義務のある農民を使った農場経営の成立と、従来の定住している農場労働者との間の関係を関係を動揺させることとなった。コローヌス達によって耕作された農場主の土地が、確からしくはコモドゥス帝の時代≪在位180~192年≫のある碑文に見られる ”partes agrariae” [開拓地の一部]という語の意味であろう。それはモムゼンによって説得力がありかつ目覚ましいやり方で補完・解釈されたものであるが 58)、先に仮定した意味での農場経営の成立は、つまり中心にある自分自身の農場経営と、(とりもなおさず経済的には)従属しているコローヌス達の夫役労働を有機的に結び付けたものとして、きわめて明確に説明出来るものである。
58) Hermes XV, P. 390以下。
この碑文はアフリカにおていの皇帝領である山がちの土地のコローヌスが皇帝直轄地の賃借人(conductor)についての苦情を申し立てたものである。その請願者達 59) に対しての保証の点で、その賃借人はその者達に対して不正を働き、そして労働を強制したのであり、その者達はその土地に対する諸条件を規定している法規、つまりハドリアヌス法の中の一つであるが、それによって≪契約に無い追加の≫労働の義務は負っていなかったのである。
59) “Ita tota res compulit nos miserrimos homines iussum divinae providentiae tuae invocare. Et ideo rogamus, sacratissime Imperator, subvenias. Ut capite legis Hadrianae quod supra scriptum est, adscriptum est, ademptum sit jus etiam procuratoribus, nedum conductori, adversus colonos ampliandi partes agrarias aut operarum praebitionem jugorumve: et ut se habent litterae procuratorum, quae sunt in tabulario tuo tractus Carthaginiensis, non amplius annuas quam binas aratorias, binas sartorias, binas messorias operas debeamus itque sine ulla controversia sit, utpote cum in aere incisa et ab omnibus omnino undique versum vicinis visa perpetua in hodiernum forma praescriptum et procuratorum litteris, quas supra scripsimus.”
[こういった全ての状況がこの上なく哀れな人間である我々をして、皇帝陛下の神聖なるご意志である命令をご行使賜るというお願いに駆り立てたのです。それ故にこの上なく神聖なる皇帝陛下のご支援を願い奉るものです。既に上で述べましたハドリアヌス法の法文に規定してあるように、たとえ皇帝の代理の監督官でも、ましてや賃借人は言うに及ばず、コローヌスに対して耕作させる土地の面積や夫役やまた夫役に使う耕作牛の数などを勝手に増やす権利はありません。それからカルタゴ地区の陛下の文書保管庫に入っている代理の監督官たちの書面に記載されている通りに、1年の内開墾≪鋤でやる作業≫、播種≪種蒔き前後の鍬でやる作業≫、収穫の作業についてそれぞれ2日を超える労働の義務は負っていない筈であり、そのことは議論なく認められるべきです。何故ならばそれは銅板に記され、全ての近隣の者がどの場所からも見える形で恒久的に掲示されており、現在に至るまで有効な形式で決定されているからで、そしてそれは前記した代理の監督官の書面にも記載されています。]
自ら働くことによって生計を立てている者は、富裕な賃借人で皇帝の代理の監督官と親交が深い者に対しては反抗しなかった。
同法によればコローヌス達の夫役は年当たり2日の開墾≪鋤を使った作業≫、2日の整地と種蒔き≪鍬を使った作業≫、そして同様に収穫期の作業も2日分としてカウントされ、しかも人間による夫役と牛馬を使った夫役の両方であった。賃借人はそれから”partes agrariae”[土地の一部]を拡張した。それは私の考える所では、その賃借人が直接管理している主人の土地を拡げたのであり、新たな土地を開墾したのである。それと同じことがドイツの改革期≪ナポレオンに敗退したプロイセン王国が1807年から農奴解放などの近代化を図った時期≫にも行われており、次に夫役義務のある農民に対してこの拡大された部分の土地も、それまでのより少ない面積の土地と一緒に耕作し、収穫することを要求した。我々が考察しているローマの場合ではまた、人間による夫役と牛馬を使った夫役の両方を増やすことになったのは先行する事実からの当然の帰結であった。土地区画の賃借料と大農場経営においての播種と収穫の時期においての労働力需要の並存関係は、私が碑文の内容から考察する限りにおいて、非常に明確に成立している。
こうした大土地経済においての夫役に従事するコローヌス達を使用した組織は、それは農業においての労働者不足の問題の効果のある解決策となっているのであるが、おそらくそれは帝政期における全ての大規模土地所有において通常のことだったのである。法的文献史料においては、常に次のことが見出される。つまり、まとまった数のコローヌス達が大農場主の一人の請負人、代理人、そして管理人と一緒にされていることで、更にこのまとまった数のコローヌス達とは別に、一団の奴隷達が請負人または代理人の管理下にある土地において存在しているのであり、そして法的文献史料からは詳細な点は知ることが出来ないが、コローヌス達が大土地所有制に従属している、ということである 60)。
60) コローヌスを大土地所有制の中で使用することになったことの結果は、D.9, §3 locati で述べられているように、農園に対して適用される統一法規である lex locationis に基づいて(この表現に該当するのは、その前の時代の国家的大賃借人に適用された lex censoria、皇帝領だった Brunitanus ≪現チェニジア≫での saltus Burunitanusu ≪注59の碑文のこと≫についての lex Hadriana)、コローヌス達がある種のゲマインシャフト、つまり colonia [植民地]を形成したということである(D.84, §4 前掲箇所)。その者達に並べて考えられているのが、大規模賃借人、請負人とそれと一緒の奴隷の一団(D.11 pr. 前掲箇所)、あるいは農場主の代理人[procurator]である管理人(D.21, de pign[oribus])である。コローヌスに対しては以上述べて来たことに適合することとして、大農場の一部の土地が割当てられ、残りの部分の土地は農場主の代理人[actor]である管理人が管理した(D.32 de pign[oribus])。≪procurator はより大規模な領地の管理・代理人、actorは現場レベルの管理人。≫Relica colonorum [コローヌス達の残り]は、つまり賃借料滞納者のことであるが、そこからある一定のやり方で土地の従属物と見なされた可能性があり、それはその者達が厳密な法的な意味ではそれには該当しない場合にもそうであった(D.78, §3 de legai[is] III)。コローヌスと奴隷はお互いにその土地の住人として2つの異なるカテゴリーと見なされていた(D.91, 101 前掲箇所;D.10,§4 de usu et hab[itatione] 7, 8)。コローヌスは奴隷と同じく土地の売買の際にはその土地区画の価値にプラスされる付属物として扱われていた(D.49 pr. de a[ctionibus] e[mpti] v[enditi])。こういったコローヌスと、先に言及した長期契約を前提とした握取契約に基づく公有の農場での二次賃借人との関係について、D.53 locati が説明している。皇帝領の請負人については、それに対して通常はより短期の契約が結ばれ、法律上では5年であり、その契約期間はコローヌスへの再賃貸の場合にも適用された(D.24, §2 locati)。時々は混乱した表現が使われることもあり、例えば “colonus” がその領域全体の賃借者を指すものとしても使われていた場合がある:D.19, §2 locati; D.27, §9, §11 ad l[egem] Aquil[iam]。しかしながら明らかなこととして、fundi[土地]が一般的に大土地所有制として組織化されていない場合には、これから更に述べる意味での大土地所有制でコローヌスは全く使われていなかった。大土地所有制と自由なコローヌスとの意味の混同は、文献史料の位置付けを不明瞭にしている。――他の多くの箇所と同様に D.19, §2 locati の引用箇所が示しているのは、Location[土地の場所]を常に英語の joint business を思わせるような大地主とその賃借人のゲマインシャフト的な関係として説明していることである。ここにおいて経済的な諸関係にそのまま適合する形で、こうした形での個々の関係形成が、そのまま直ちに無数の類似の関係の形成の機会を与えたのであることは、明らかである。我々がここで論じる関係形成には、相対的に規模の大きい大地主の政治・経済的優位性が内包されており、そしてそれ故に賃借契約の関係がそのままヴェールに覆われた労働契約関係となっているのである。コローヌスはそのあてがわれた土地に対しての耕作義務を持つ者として D.25, §3 locati と D.30 の前掲箇所(ユリアヌスの、またそれ以外で引用して来た箇所であるスカエウォラ、パピニアヌス、ウルピアヌスそしてパウルスのもの)で把握されている。 それに適合するように、D.24, §2 locatiでは農場主は次の権利を持つものとされている。つまりコローヌスがその借りた土地を契約が満期となる前に放棄する場合は、直ちに、そのコローヌスに何か別の立ち退き理由があるのか、または賃借料の不払いに該当するかどうかの判定を待つことなしに、そのコローヌスに対して訴えを起こすことが出来るという権利である。何について訴えるのかということは書かれていない。しかし明らかに単なる利害関心の及ぶ所からの訴えであり、何故ならばその訴えの際の賃借地については、それが契約上どう定義されていたか、ということは含まれていないからである。それと並んで§3の前掲箇所で、コローヌスが成すべき労働について言及されており、そのことを理由として同様に訴えが行われているからである。農場主の土地の耕作者と賃貸している土地のそれはそれ故に同等のものとして扱われており、ただ原則として前提とされているのは、農場主は賃貸している土地の耕作の仕方についてはただ契約が終了した時に初めて何らかの形で関与する、ということである。その外に農場主はもちろん賃貸対象の土地を別のやり方でも譲渡することも出来た。このことは後の時代にはコローヌスの連れ戻しという形で起こったのであり、それは navicurarii [小麦の海上輸送]のための小麦栽培の耕地について、コローヌス達を徐々に強制的に連れ戻し再度耕地を与えた、というやり方であった。最初の土地契約終了時の例は市民法的な、navicurarii の例は行政上の強制行為であった。コローヌスが不自由な立場の奴隷に対して自由な農場での労働者であり、それは自由意志の賃借契約に基づいて賃借料を支払う代わりに土地をあてがわれたというのの類推として扱われた。実際の所、奴隷が地方の農園の中に住んでいた状態から、自分自身の家に移された場合には、その奴隷は直ちにコローヌスと同等に扱われたのである。――以下のことは明らかである。つまりコローヌスの土地との関係が、こういった状況下でその関係が純粋な貸借人という性格で前面に出てくる場合には、自然なこととしてその権利を金銭的報酬を得ることから収穫物の一部を得ることに移行したと把握されるが、それがいまや逆に、法的な取扱いが原則的に変更されることなく、しかしながらコローヌスの労働力を農場主のために使用することが大地主であるその農場主の主たる利害関心となっていた場所では、コローヌスと土地の関係はある土地区画を適価で貸してもらうことの条件として、自己の借りた土地と農場主の土地の両方を耕作する義務を引き受けるものと直ちに把握されるのであり、そのことは本質的な意味では既にコルメッラの書からの引用箇所≪注56≫において起きていた、ということである。事実上コローヌス達は、相続対象になる土地に定住し、小農民と日雇い農業労働者のほぼ中間に位置する、大地主に従属する農民となっていた 61)。
61) 事実上相続可であることは自明のことであるが故に、D. 7. §11 comm[uni] difid[undo] においては、貸借権について分割の訴えを起こすことが出来ないことが特別に詳細に述べられている。何度も引用した 1, 112 de legat[is] は総督補佐官が貸借契約に相当する土地を実際には持っていない貸借人については、この後すぐの所で述べる農場地区に関連付けている。イタリアにおいて先行して存在している長期年度契約のコローヌスについては、モムゼンが saltus Burunitanus について考察している論文の中で言及している。
しかし最も重要なことは、巨大な地所の複合体の一部においてのこういった状態は、また大地主の土地の賃借人に対する、法的に保証された権力による支配関係としても見なすことが出来る、ということである。このことを論証するためには、次のことを考慮する必要がある。つまりどのように大規模農業事業の異なったカテゴリーがそこに生まれて来ているのか、ということと、それが法的には所有としてどのカテゴリーに属していたか、ということである。
大土地所有制の法的位置付け
こうした大規模農業の最古の形態は、以前論じた公有地[ager publicus]の占有である。この形態が奴隷を使った大規模農園の経営を指していることは全く疑いようがない。それと同様におそらくそうであったと思われるのは、既に注記したように、賃貸地を割り当てることによって生み出された、いつでも取り消し可能な契約に基づいた定住の小作人という身分の者が存在していた、ということである。占有は疑いなく、貴族政にとって実質的にもっとも重要な土地所有形態であった。占有者という者は、いくつかの私有地をまとめたもの以外に、自分自身をケンスス上での第一の階級に置くために、多くの土地を≪実質的に≫所有した者であり、その者はグラックス兄弟の改革より前の「古き良き時代」においてはトリブス民会≪選挙区であるトリブスでの貴族と平民の両方の意向をまとめるための集会≫に対しての活動において、次のような者と同様に見られていた。それは例えば≪ヴェーバー当時の≫今日の騎士領の領主であり、その者は村落においていくばくかのフーフェの土地を所有し、あるいはフーフェの他の農民と混じり合って存在している者である。≪騎士領は特に神聖ローマ帝国で領邦の君主が騎士資格のある農民貴族に公認している領地で、ヴェーバーの時代にもまだ存続していた。≫占有が市民法上では除外されているということと 61a)、そしてそれによって生じる無数の立法上の面倒さと課税の手間は、privilegium odiosum≪憎むべき特権、本来は認められるべきではないのに何らかの理由で認められている特権で、法的には最小限に解釈すべきもの、とされた。≫として捉えるべきでないのは、言うまでもないことである。≪ヴェーバーは占有をローマでは決して本来違法なものと位置付けられていなかった、と言っている。≫
61a) 市民法が占有について規定しているのはただ、占有の形で保護された、事実上成立している権力関係についての注意があるだけであり、このことがフーフェにおいての”locus” [場所]に対しての権利とはっきりと対立しているということは、私の考える所では、「物」に対する権利と「所有」の間の対立が先鋭化しているということである。”Pro herede”[相続人として]占有するということと、”Pro possessore”[占有人としてのみ]占有する≪相続人は相続の際にどちらかを選択出来た≫ことの分裂状態は、相続に関する訴訟において判例に依存する性格と結び付けられた、そういった所有状況の両方の性格が等しいという二重性に起因している。以上のことは、ここではただその可能性を示唆することが出来るだけである。
それ故に、まさに革命的なこととして受け止められたグラックス兄弟の改革が打ち出された時に初めて、フーフェの農民達が状況によっては、その者達が動産である資本を自分達の方に持ってくることが負担であると感じたであろうということは≪占有していた土地を売却して現金を得ることが大変であると感じていたであろうということは≫、そのことは改革を革命的な変革と見なすことはなく、ただその占有していた土地を私有地に転換する、ということにつながった。
Fundi excepti [例外として扱われた土地]
前章で見て来たように、こういった占有地について一部はイタリア半島においてムニキピウムへと組織化され、特に土地割当ての際に fundi excepti [例外として扱われた土地]としてゲマインデ団体の外側に留まったということは、――それは測量人達の表現によれば:in agro publico populi Romani [ローマ人民の公有の土地の中にある]となるが、そのことがここで意味するのは、占有地というものはただ中央官庁の行政上かつ裁判権上でのみの要請に応じるものとして理解されるものである、ということである 62)。
62) フラックスは p. 157, 7 でこのように述べている: Inscribuntur quaedam “excepta”, quae aut sibi reservavit auctor divisionis et assignationis, aut alii concessit.
[ある種の「除外地」として記録されている土地があり、土地の分割や割当ての実施者が自分のために取っておいたか、あるいは誰かに譲渡したものである。]
ヒュギヌスは p. 197, 10でこう書いている: excepti sunt fundi bene meritorum, ut in totum privati juris essent, nec ullam coloniae munificentiam deberent, et essent in solo populi Romani, —
[除外された土地とはそれを受けるに値する者に与えられた土地であり、これらは完全に私有地とされ、一つの植民市に対して何らの義務も負わず、ただローマ人民の公有地の中にあるもので、――]
ここで言っているのはつまり、そうした土地がムニキピウムの裁判管轄権外にあった、ということである。≪原文は植民市に対して義務を負わない、なのにヴェーバーはムニキピウムに言い換えている。そもそも植民市とムニキピウムの違いこそが、ヴェーバーの博士論文審査の時以来のモムゼンとヴェーバーの論争の争点であったことに注意。≫碑文としては2つの少なくともある一定の観点で除外された土地が、アウグストゥス帝の Venafrum ≪現在のイタリアのモリーゼ州にあたる土地にあった古代都市≫の水道橋についての命令の中に先行して見出される(C. I. L., X, 4842)。フロンティヌスの p. 36, 16:Prima … condicio possidendi haec est ac per Italiam, ubi nullus ager est tributarius, sed aut colonicus etc. … aut alicujus … saltus privati.
[(占有地というものを)可能にする第一の条件は、イタリア全土でそれは課税地ではなく、しかし植民市等々の土地であるか…あるいは誰かの土地である…私有の大区画の土地≪saltus は25ケントゥリアの正方形の土地区画≫である。]
Controversia de territorio [領土を巡る争い]については前章を見よ。またテオドシウス法典 18 de lustr. coll. 13, 1 はアフリカについて territoria [主として属州の領地]と civitates [ローマ市民の土地である占有地]を区別している。
こういった形の土地で重要なカテゴリーとなっていたのは、何よりもまず皇帝の直轄地そのものであり、それはこのような形の占有地として確かにその当時から――後の時代になるとそれは文献で立証されるが――可能な限りゲマインデ団体からは除外されていたのである 63)。
63) この手の皇帝領の土地は controversia de territorio [領土を巡る争い]を引き起こしている。この点については先に引用したラハマンの p. 53 を参照せよ。クラウディウス帝は(スエトニウス、「ローマ皇帝伝」、クラウディウス帝 12)自身の皇帝領において市場を開設する権利を元老院に対して請願している。
同様のいくつかのカテゴリーをより広範囲において属州において見出すことが出来、皇帝の直轄地自身が、一部は永代貸借契約に基づいたものであり、また一部は fundi dominici (国庫に属する)≪皇帝の直轄領の中で、皇帝に任命された管理官が経営する農地≫であり、さらにまた一部は fundi patrimoniales (皇帝が私的に領有していた土地)であり、しかし全てのこれらのカテゴリーは皇帝の配下の役人によって管理されるものであり、ムニキピウムに属するものではないとして理解される。そこにはそれと並んで、我々が先に見て来たように、まとめて賃借料を払うことで長期間貸し出された国有地や、また皇帝の直轄地で5年間貸し出されたものがあった。どちらのタイプの土地も通常はいかなるゲマインデ団体にも組み入れられることは全くなく、というのはそれらの土地は公有地だったのであり、公有地についてはその他のやり方で譲渡されなかった場合に限って、ゲマインデに対して与えられたからである。
現金による納税義務者。国有地の貸借人。
更に以前見て来たもので、確からしくはアフリカにおいての現金による納税義務者が、同じような位置付けのゲマインデには所属させられなかった土地を受領しているということと、また ager privatus vectigalisque の土地の大規模な永代貸借人については、これまで述べて来た状況に対して不適合である事例として取り扱われるべきではない。これら全ての土地所有のカテゴリーは、以前そう主張して来たように、それぞれがただ一人の占有者に結び付けられている、という傾向を持っていた。国有地の皇帝直轄地の土地の貸借人は、しばしば次のことを貫徹した。それはそういった土地の賃貸料を固定額にすることと 64)、そして同様に統治者からその者達の土地所有を継続的に認可する約束を取り付けることであり、それはフランク王国の王がその封臣に対して認めたのと同じである;時には次のことが再度試みられた。つまり5年毎に土地の再割当てを競売方式で行うという原則を確立することであり 65)、それは間を空けないですぐに再割当てを実施させることが目的であった。
64) テオドシウス法典 3 de locat[ione] fund[orum] jur[is] emph[yteutici] (380年の)。参照:テオドシウス法典 1, 2 de pascuis, 7, 7。同法 5 de censitor[ibus] 13, 11。
65) テオドシウス法典 1 de vectig[alibus] 4, 12。
現金による納税義務者とその他の除外扱いの私有地は、その次の段階ではユガティオの税制に従わされることとなった;その者達は税額を、自分達の占有する土地領域全体の分を、その領域に住んでいてその者達に従属している人員の分のカピタティオと一緒に支払うこととなった 66)。
66) テオドシウス法典 14 de annon[a] et trib[utis] 11, 1。この法規に従った場合、コローヌス達は、もしその者達が占有地以外に更に小区画の土地を所有していた場合は、その土地の分として通常の徴税人に対して税を支払うように仕向けられた。しかしこのことはテオドシウス法典の 1 ne col[onus] insc[io] dom[ino] 5, 11 からの類推によれば、実際にそうであったとは信じ難い。
占有されていた領域の居住者の法的な状態
次のことを頭に思い浮かべてみた場合、つまりそういった土地領域の居住者、とりわけコローヌスの法的状態がどういったものであったかということであるが、その場合まず明らかなのは、全ての国家の土地による賃貸地においては、そういった居住者と元請けの契約者との間での正規の訴訟手続きを取ることは、その争点がコローヌスの労働提供義務にあった限りにおいては不可能であった、ということである。皇帝直轄地の賃貸人の場合にも同様に、納税義務のある農民[publicanus]のようなコローヌスと≪直接≫契約を取り交わすことはほとんどなかった。測量人達が言及している握取契約を二次賃借人が≪直接≫取り交わした限りにおいては、賃貸契約が満期になった後は、その場合に存在していた小規模の賃借人は国家に所属するコローヌスとなったのである。大規模な賃借人は国家または国庫によって、元々は lex censoria に従って、後の時代にはアフリカの広大な土地において碑文として残されているハドリアヌス法の例のような類似の法規に従い、更にはその法文が銅板や石板の上に刻まれてその地方固有の法規として、その地位を定められるということが常に起こり、そしてコローヌスの義務もそこで定められており、賃借料支払い義務も負わされていた;大規模な賃借人は、コローヌス達に負荷を負わせ、その者達が得るものよりも多くのものを要求した。その結果として、更に後の時代にはもっともコローヌスにとって有利なケースで、国民の土地の受領人との間の行政手続きとしての解決が図られた事例が発生し 69)、帝政期においては常に直轄地の管理当局への行政上の租税関連案件としての訴えのみ、皇帝による最終審で審議される、ということが起きていた。
69) 例えば 1/10税の課税者と納税義務のある農民との間で。
コローヌスの夫役はそこから、既に引用済みのアフリカの碑文にて、モムゼンが主張したように、ゲマインデ、例えば Genetiva≪Julia Genetiva Ursonesis、スペイン≫によって課された夫役に完全に相似するものとして取り扱われ 68)、まるで公的に課された労働であるかのように見なされ、その場合には請負人[conductor]にそれを扱う職権が与えられたのである。
68) Genetiva の法規、c.98。
コローヌスの土地に関しての所有権についての全ての法的な争いが行政的に解決された、ということは、第三章にて詳論した内容によって明らかである。請負人が賃借している土地の内の一区画を誰か他の者に与えることを許すのを望んだかどうかは、もちろんその請負人の意向によるものであった。アフリカにおける現金での税支払者の土地区画の状況も前の章で詳しく述べた通り同様であった。ここでの土地の所有は属州総督の職権と行政が関与するものとしてのみ可能となっていた。というのは結局のところは、イタリアにおける例外扱いの土地や、アフリカにおいて永代小作地とされた ager privatus vectigalisque においてのように、コローヌス達は事実上は地主から土地を借りているだけの存在であり、いずれの場合もムニキピウムの司法当局が関与することはなく、可能であったのはより上位の裁判所への訴えであり、それは何よりもただローマの中央裁判所への訴えであった。後の帝政期にはこの制度は色あせたものとなり、コローヌスに留保条件付きで許されたのは、正規の裁判官に対して地主を訴えるということで、特にそれはまた次のケース、つまり地主がコローヌスへのそれまでの賃貸料を引き上げようとした時 69) に起きていた。
69) ユスティニアヌス法典のXIの章の49。
つまりまたここで起きていたことは、元々の国家の賃貸人と元々の私的な賃貸人の区別が無くなって一まとめに扱われているということであり、国家の直轄地の大規模賃借人がその下の小規模な賃借人に対して行うことが許されていなかったこと――つまり賃貸料の値上げが――他の占有者達に対しても禁じられていた、ということである。他の条件においても同じにすることが行われていたが、この値上げ禁止ということはしかしコローヌスにとって有利なことだった。次のことは既に何度も主張して来た。つまり分割されていないまとまった土地の所有には、明らかに個々の土地領域 70) を測量によって境界線をはっきりさせるということは必要ではなかった、ということである。
70) 何度も考察して来たアフリカの saltus Brinitanus の碑文は、確からしいこととして、測量が行われており、その碑文は tabularium principis ≪銅板に刻まれた法規≫を引用してかつ測量地図を参照しており、このケースでは2種類の書類上にその法規に近い規定が含まれていた。
いずれの場合も使用料として税金を払う土地領域とそしてまた例外扱いされた土地においては、コローヌスがその土地の所有権を得るということが起きていた可能性がある。この点については、コローヌスが自分の所有する土地を任意に売却出来るかどうかということは、恐らくは後に、コローヌスの大地主への依存関係が深く根を下ろした状態になった時には、疑義が生じていた。そしてそれは結局は許されない、ということで決定され 71)、それ故に所有権のある所有というものは、土地所有の変更という点においては、元々の貸借地としての所有ということと同一視され、何故ならば明らかにコローヌスの労働奉仕はその者が所有する全ての土地所有に課せられている負荷として、10人組による奉仕やそれに類似のものとして取り扱われたからである 72) 。
71) テオドシウス法典 1 ne col[onus] insc[io] dom[ino] 5, 11 (ウァレンティヌスとウァレンス):”non dubium est quin non licet “[合法的でないことは疑いの余地がない。]。
72) テオドシウス法典 2 de pign[oribus] 2, 30 は奴隷、代理人、コローヌス、管理人、請負業者が地主の土地を担保にして借金することを禁じており、そしてテオドシウス法典 1 quod jussu 2, 31 は次のように規定している。それは今挙げた者達が借金をしたことについては、地主は義務を負わない、ということである。これらの法文は明らかに次のことによって生じた混乱について扱っている。それはコローヌスが所有権を保持する土地と賃借料を払わなければならない地主の土地が明確には区別されていなかった、ということである。
出生と行政管理上の出生地への送還
また別の方向への動きとして次のことが登場して来る。つまり、公的な負荷を負わされた者に対して、10人組ないしはそれに似た制度による取扱いの一つで、それはこれまで述べて来た地主とコローヌスとの間の関係形成と類似している。あるゲマインデに所属しているということとそこから生じる全ての帰結は、ローマ帝国に属する者の出生地と結び付けられていた。コローヌスにおいてはこのことは、その者がそこで生まれた土地領域が存在する地域、ということであった。他の全てのゲマインデについては、それが許されていた場合には、自由に≪名目上の出生地を≫設定することが出来た。しかしここにおいてまた見出されることは、公的な労働奉仕を義務付けられていた者の自由移住権は、帝政期には事実上まだ非常に強く制限されていた、ということである。ある確実な程度まで、このことは常に起きていたことである。元老院議員に対しては、まだ会期が先に残っているのに帰郷する場合には、周知のように先行して≪ローマに戻ってくる保証のための≫担保を取ることが行われていた。元老院の会議に直接的な強制で連行するのは、適当な手段ではなくかつ実行不能とおそらく考えられていたのであり、また法的には許されないこととされていた。帝政期になると一般にはこうした担保による間接的な強制に代わって、違反の際には行政的な現物執行が行われることとなった。新約聖書のルカによる福音書が書かれた頃においては≪ヴェーバーはここをマタイによる福音書と間違えていた。正直な所、とてもキリスト教徒とは思えない初歩的なミスである。クリスマスイブの教会では必ずルカ福音書の第2章が朗読される。参考:ルカ福音書の第2章冒頭「イエスの誕生 1そのころ、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に、登録をせよとの勅令が出た。 2これは、キリニウスがシリア州の総督であったときに行われた最初の住民登録である。 3人々は皆、登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。 4ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレから、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ上って行った。 5身ごもっていた、いいなずけのマリアと一緒に登録するためである。」新共同訳≫、一般的な意識として次のことが許可されていると考えられていた。つまりケンススのために属州民が自分の出生地に赴くことが必要とされる、ということであり、それについてはアウグストゥスによるケンススの記録が示している。ウルピアーヌスの時代になると、次のことはもう疑義を持たれなかった。つまり10人組は自分の出生地が属しているゲマインデに強制的な形で帰されることが行われ得たということである。もし諸ゲマインデが相互にまたはある土地領域について、次の点で訴えを起こした場合には、つまりある土地区画及びそこに見出される人員が、そのゲマインデの領地に属しているのかということと、それ故にその人員はそのゲマインデに対して納税と兵士への応召義務があるのか、という点であるが、その場合は controversia de territorio に基づいて行政上の手続きとして裁かれたのである。既にウルピアーヌスの時代にはそういった争いの際には、”vindicatio incolarum” [住民の返還請求]という言葉が使われていた。次のことは自明である。つまり土地に依存しているコローヌス達の場合は10人組の一員以外の何者でもないとして取り扱われ、それはその者達が公的なまた準公的な義務、例えば夫役、を行うべきとされている限りにおいてそうであった。コローヌス達は行政的な方法でその出生地に送還された 73)。
73) Revocare ad originem bei Curialen [元のクリアに呼び戻すこと]D.1 de decurionibus 50, 2 (ウルピアーヌス)。テオドシウス法典 16 de agent[ibus] in re[ebus] 6, 27。そこから派生して curiales originales [元々のクリア]テオドシウス法典 96 de decur[ionibus] 12, 1。鉱夫のその出生地への変換 テオドシウス法典 15 de metallar[iis] 10, 19。こういった手続きの行政的な性格を記述している箇所は 1.1 de decur[ionibus] の本文にある。コローヌスにおいてのこの手続きが、本来行政上の処理であったことを記述しているのは、そのことを扱っている箇所の本文全体であり、同様に、行政法において元々の出生地を再確認するということを扱っているのは:テオドシウス法典 1 de fugit[ivis] col[onis] 5, 9。ここにおいてもまた個人の身分に基づく権利と私権として通用する規範を作り出すための行政上の手続きが形成されているのであり、更にはあるゲマインデへの帰属に対して婚姻が果たす作用についても同じであり、というのもケンススへの登録にあたっては、ゲマインデへの帰属と土地への帰属が規制されねばならなかったからである。次のことは非常に自然なことである。つまりその際に奴隷が持つ権利からの類推によって関係付けられた、ということである。仮に我々の国家権力が弱体化して個人の自由移住権が制限されていたとしたら、その場合は我々も自分の属する土地領域において全く同じことを経験するであろうし、特に次のこともまた経験するであろう。つまり農民としての大地主に対しての私法的な義務と、公法上の大地主への義務の2つが、行政当局には継続して識別することは出来なかったであろう、ということであるが――夫役義務のある農民については、例えばローマ国家の土地領域においては、ここではそういうことを扱っているのでは全くない、という可能性がある。結婚についての規制の行政上の由来は、またテオドシウス法典の 1 de inui[inis] et co[lonis] 5, 10 に示されており、特に次の規定で:つまりある者で、女性のコローヌスの返還を義務付けられた者は、代理の者を立てることでその義務を免れることが出来、そして年齢制限にかかる場合も同じであった、ということである。その他の点についての参照 Nov. Valent ≪ウァレンティヌス3世、在位425~455年、がテオドシウス法典の後に出した新勅法 [novella constitutio]≫ I, II、第9章、更にユスティニアヌス法典の 11, 50 の de col[onis] Palaest[inis] の唯一の条文――そこでは”lex a majoribus”≪祖先によって制定された古き良き法≫がアフリカの大土地区画[saltus]についてのハドリアヌス法典と並置されており、同様に章 11,51、そしてユスティニアヌス法典の 11, 47 の章の全文もそうである。何度も登場する “inquilini”[同宿人、下宿人]は「借家住まいの農民」、つまりコローヌスとしては扱われず、その土地区画に従属する居住者のことであり、本質的にはコローヌスの成れの果てである。ユスティニアヌス法典 13 de agric[olonis] 11, 47 はそれ故に次のように注記している、問題が出生地への帰還に関係するのであれば、コローヌスとインクイリニの2つのカテゴリーは等しいものとして扱う、と。
ディオクレティアヌス帝の時代になって市民の裁判と行政上の処理が混ざり合って一つになった時には、そこから “vindicatio”[返還請求]が起き、その際にゲマインデのクリエがそのゲマインデの参事会に対して所有権の訴えを、まるで可愛がっている家畜を一緒に追い立てるかのように行い、その結果コローヌスはそれだけいっそうほとんど家畜と同様の法的な扱いを受けるようになったのである。最終的には Interdictum Utrubi [どちらがその動産をより長く所持していたかによって所有権を確定させる命令]が奴隷に対してと同じようにコローヌスに対しても下され、それによってまた再びコローヌスの性格が定住の農業に従事する農場労働者であるということが明確に現れるようになっていた 74)。
74) テオドシウス法典 1 utrubi 4, 23。善意の占有者はまずはそのコローヌスを取り戻し、それからその訴えは “causa originis et proprietatis” [出生地と所有権に基づく訴え]として取り扱われた。
そのコローヌスがその大地主に「属する」とういうことは無条件に宣言され 75)、そして事実上そのことは実際の状況に合致していた。何故ならばそのコローヌスがその農場に従事しているということは、いまや十分に明白になっていたからである 76)。
75) テオドシウス法典 2 si vag[um] pet[atur mancipium] 10,12 の “cujus se esse profitetur”[それがその者に属すると宣言された]。
76) それ故に次のケースではその当時の見解に従えば農業従事者のカテゴリーを移動させることであった。その場合とは、テオドシウス法典 1 の de fugit[ivus] col[onis] 5, 9 によれば、逃亡したコローヌスは奴隷に落とされねばならず、その箇所での表現によれば、その目的は行政当局が次のことを認めることで、それはまた自由な農場への従属者であったに違いない者を、奴隷として新たに整理し直す、という場合である。Nov. Major. ≪マヨリアーヌス帝新法典、同帝は西ローマ皇帝、457~461年在位≫4, 1 のクリア民がクリアの奴隷として表現されているように、そしてテオドシウス法典 39 の de decur[ionibus] 12, 1 にてその者達に拷問を加えてはいけないことが特別に規定されているように、この場合のコローヌスは「領地に属する奴隷」となっていた。このようなコローヌスの取り戻しの現実的な可能性は、大地主にとっては本質的な利害に関係するものであり、それはまた特に次の理由で、つまり大地主はコローヌスの税率について責任を負っていたからである。このような――土地税と人頭税――はコローヌス達が使用している土地のユガティオとしてケンススに登録され(adscribere) 77)、コローヌス達はそのことによって adscripticii[登録された者]と呼ばれた。大地主に対して諸ゲマインデに対するのと同様に次の義務が課された。つまりその大地主の責任となる新兵徴集ノルマという義務であるが、このことは土地それ自体が負担すべき現物的な義務として把握されており、そして大地主達は何とかこの義務を免除してもらおうとし、それは定期的な金銭支払いに代えてもらうことで部分的には成功したのである 78)。
78) Adscribere の手続きについては常に――テオドシウス法典 26 de annon[a] 11, 1;同法典 3 de extr[aordinariis] et sord[idis] mun[eribus] 11, 16;同法典 51 de decr[ionibus] 12, 1;同法典 7 de censu 13, 10;同法典 34 de op[eribus] pub[icis] 15, 1;同法典 2, 3 de aquaed[uctu] 15, 2;同法典 2, sine censu 11, 3 (servi adscripti censibus)――占有者やデクリオーネスによる夫役や税の負担についてケンススに登録することが必要とされた。
78) テオドシウス法典 1 qui a praeb[itione] tiron[um] 11, 18、は帝政期の土地の例によれば、それについては同法典 2 de tiron[ibus] 7, 13 が制定された後は免除されるようになっていた。同法典 13 の同じ箇所の Adaeration [adaeratio]≪金銭の支払いによって免除された義務≫を参照。
属州におけるコローヌスについては、一般に人頭税が課せられた状態になっていたと思われるが、そのコローヌスはそのことによって censiti と呼ばれており、その結果としてコローヌス達はその者達の市民的な権利が弱められた階級に所属することになっており、それがこの状態の帰結であった 79)。
79) より下のクラスの者の人頭税免除については、その者達に拷問を加えることを可能にするという目的で、censiti の階級に入れられたということが、テオドシウス法典の 3 de numerar[iis] 8, 1 にて特別に規定されている。
大地主に属するコローヌスと自由なコローヌス
次のことは明らかである。それは以上のことをもってコローヌスとして知られた法的な状態についての全ての本質的な外形的特徴が与えられている、ということである。この状態がまさしく大地主の土地区画において発生していたということは、それによって説明されるのは次のことである。つまり帝政期の法律文献において、そういったコローヌスと並んで自由な期間限定賃借人の通常の賃貸借関係が見出される、ということである。
大地主に土地に従属するコローヌスの所有権について法学者がほとんど言及していないことの理由は、このコローヌスという状態について特別に適用されるように作られた規則の行政処理的な性格にある。ひょっとしたらコローヌスの法律上の状態は当時まだ実務的な処理においては様々に解釈し得るものだったのであり、それ故に該当する法学者達がその著作の編集においてはそれを扱わなかったのである。
類似の状態。軍事上の城砦。蛮族の定住。
コローヌスと同等の状態にあるものとして、一連の他の組織について見て行くこととする。その場合アフリカでの軍事上の城砦の住民は明らかにその土地に従属するコローヌスであったのであり、夫役の義務を課せられかつ皇帝によって任命された特別官の管理下に置かれた 80)。
80) アレクサンデル・セウェルス帝≪第24代ローマ皇帝、在位222~235年。≫は234年に “per colonus ujusdem castelli”[コローヌスを使って同じ城を]、――つまりマウリタニアの Dianense ≪現在のアルジェリアにあった属州マウレタニア・カエサリエンシスの都市≫の城――城壁を建設し、つまりそれはコローヌスを使役することによってであった。(C.I.L., VIII, 8701。参照 8702, 8710, 8777。)
また取り分け辺境の蛮族はコローナートゥス制≪コローヌスを使った小作制度≫の権利でそこに定住していた。ホノリウス帝≪西ローマ帝国皇帝、在位393~423年、暗君であって西ローマ帝国滅亡の原因を作り、在位中にローマが蛮族に占領された。≫はスキリア族≪東ゲルマンの部族で現在のウクライナに住んでいたが、フン族に追われて西ローマ帝国領に侵入した。≫を彼らがローマに屈服した後に、大地主の下にコローヌスとして置いて分割したが 81)、それは労働忌避者を大地主の下に送って使役させたのと同様である。
81) 409年のホノリウスの法とテオドシウス法典 V, 4, 1. 3:Scyras .. . imperio nostro subegimus. Ideoque damus omnibus copiam, ex praedicta gente hominum agros proprios frequentandi, ita ut omnes sciant, susceptos non alio jure quam colonatus apud se futuros.
[スキリア族を…我々の支配権の下に服属させた。それ故に全ての者に次の許可を与える。つまり、先に述べた民族について、その者達を自分の土地に住まわせることである。その際に全ての者が知っておくべきことは、こうして受け入れられた者は法的にはその受け入れられた者の下でコローヌスとなる、ということである。]
≪この例は、西ローマ帝国末期の暫定的な処置であったと思われ、実際にこの409年にはローマは蛮族の占領を受けている。またスキリア族も一旦ローマに恭順の意を示したが、すぐ後にフン族と共謀してローマに再度反旗を翻しており、決して安定的に持続した法的制度ではなかったことに注意。≫
既にこのことに遡って同様の処置が既に行われていた可能性がある。モムゼンはコローヌスの起源をマルクス・アウレリウス帝の時の蛮族の定住に求めているが、ガリアでのラエティア人≪元々ポー川流域に住んでいたエトルリア系と言われている部族で、ガリア人の侵入により山地に移動した。≫をコローヌスと見なすことは否定されるであろう。そういう議論にもかかわらず、私には蛮族とコローヌスには本質的な違いがあると思われる。というのはラエティア人とローマ帝国領内に定住した蛮族は全体で、我々が知る限りでは、より上位の農民に従属する土地付属の人間集団ではなく、[軍事力を提供する代わりに土地を与えられた]封土の所有者であったからである。次のことは完全に可能と思われる。つまり蛮族の定住が物権の発展の一般的傾向としての個人的及び公的な義務を本質的に強化した、ということであるが、しかし私が信ずるのは、コローヌスの権利状態というものは、そういう蛮族の定住のことを特に考慮しなくとも、法制史・経済史の観点で説明しうる、ということである。いずれにせよ定住させられた蛮族は、つまり gentiles は、文献史料の中でコローヌスとは区別され、gentiles については特別な個々人の身分を規定する法が存在した 82)。
82) 蛮族との結婚の禁止 テオドシウス法典 1 de nupt[iis] gent[ilium] 3, 14。
占有の法的位置付け
大地主のコローヌスに対しての権利の状態は完全に官憲的な性格を持っていた。一般論として大地主には警察力が与えられていたに違いなく、その力に基づいて saltus Burunitanus の請負人[conductor]はその配下のコローヌス達を棒で打ったりしていた。クラウディウス帝は元老院に対して、自身の土地においての一般的な市場開催権を認めさせており、その権利にはいずれの場合でも市場警察の権利が結びつけられており、そして大地主についてもまた次のような権利が与えられていた。それは市場で販売される家畜や奴隷について、商品そのもの、あるいはその商品の品質や員数不足に対しての購入者からの苦情に対して、按察官[アエディリアス]≪建築、道路、水道、市場などの管理を担当するローマの官吏≫のやり方に倣ってそれに対処する、という権利である。同様に市場においての司法権もまた私人である大地主に与えられた(C.I.L. VIII, 270)。大地主達は彼らに与えらえた警察権力を使ってその配下の者達に対して、それが適当と思われる場合においてはコローヌス達を奴隷のように収用部屋に監禁したのであり、このことは皇帝の立法によってこういったケースで監禁された私人に対して干渉し、そういった行為を越権行為[crimen laesae majestatis]≪元々の意味は国家に対する反逆などの重大な犯罪のこと≫として国家大権に基づく介入を行って調停しようとすることが試みられるまで続いた 83)。
83) テオドシウス法典 1 de privat[is] carc[eribus] 9, 5。
同様に明確に起きたことは、国家の行政当局と大地主の土地で官憲の関与を免除された領域の管理人との間の争いである。農場管理者の側は次のことを要求した。それは犯罪者の追及とその他の必要な措置をその領域の中ではただ要請を当局に対してするだけで出来るようにすることであり 84)、言い換えれば、農場管理者達はフランスにおいて治外法権[Immunität]と呼ばれているのが常であることを行使することを、当然の権利として要求したのである。
84) テオドシウス法典 11 de jurisd[ictione] 2, 1。大地主の代理人たちは一般的に全ての上位の裁判から免除されるように努力した。それとは反対のことがテオドシウス法典 1 の前掲部にある。
それについては皇帝の側から拒絶されたのである。他方では大地主達は部分的には次のことをやり通すことが出来た。つまりその配下の者達に対しての裁判を行うことであり、それも民事と刑事の両方についてであり、原則的にはグーツヘルシャフト制を先取りした形で公判を行っていた。大地主はコローヌスを法廷に出頭させ、その者達に[裁判によって]庇護を与えた 85)。
85) テオドシウス法典 de actor[ibus] 10, 4 の皇帝の配下の者についての規定。しかし私人である大地主達が同じことをやろうと努力しかつまたそれにある程度成功していた、ということは、その者達が精力的な弁護を行い、また部分的には法廷への出頭義務を免除してもらおうともしており、また部分的には小規模地主を保護しようとしており、そして自身で所有する土地領域に定住しようとしていること、あるいは自身の大地主としての地位を認識しようとしていたことを示している。テオドシウス法典 1, 2 de patroc[iniis] vic[orum] 11, 24 ;同法典 5, 6 前掲部;同法典 21 de lustr[ali] coll[atione] 13, 1;同法典 146 de decur[ionibus] 12, 1 (「有力者の庇護の下に」[sub umbram potentium]逃亡したデクリオーネスに対して)。ユスティニアヌス法典1, §1 ut nemo 11, 53 においては”clientela”[庇護民]という関係の表現が使われている。参照 D. 1, §1 de fugit[ivis] 11, 4。
所有する土地領域をムニキピウムの裁判管轄区域から除外してもらうという動きは、完全にそれ自身の意志だけによる発展であった。徴兵は更にまた税の徴収管理と同様大地主制にのみ関係することであった。地主はその者なりにその領域のケンススのリストへの登録を導入し、税を徴収し法の執行権を持っていた 86)。
86) D. 52 prd[e] a[ctionibus] e[mpti] v[enditi]、そこではある請負業者が saltus の土地区画を税を滞納したという理由で競売にかけている。地主が自身の官憲的機能の利用を奴隷やコローヌスに委託することがよく行われており、そのためにユスティニアヌス法典の 3 de tubular[iis] 10, 69 は、地主が奴隷やコローヌスが行ったことに対して地主自身が責任を負う、ということを規定している。その結果として起きたのは、諸都市から属州への大量の人口流入が、それらの諸都市は剣闘士の競技が行われなくなったこと、及びゲマインデにおいての同族間の争いへの関心が弱まった後は、その争いは今や政治的な意味でのみ支配しているデクリオーネスの一族郎党の内部でのみ起きたのであるが、そして諸都市の市場が占有者達の農場においての農業に必要なものを自給する組織の形成によってその意味を失ったという状況により、大規模な占有者の保護の下に逃げ込むことが始まったことによって、その吸引力を失った、ということである 87)。
87) 注85の関連箇所を見よ。
占有者は次のことに利害関心を持っていた。つまりその配下の者達とその土地で使用出来る労働力について出来る限り徴兵されないようにする、ということであり、そして一般論としてその者達を暮らしていけるように保ち、その者達が負担出来る範囲の義務を課す、ということである。占有においては国家による課税のための組織化を免れており、その組織化の内容は都市の住民の大部分とまさにその者達が労働力を持っているという要素を、ある種の国家への従属者のように行政組織の中に組み入れたのであり、また産業における生産を一部国有化し、それに対して部分的にはある種の官憲的性格を刻印し、そしてそれらを国家による厳格な管理の下に置いた、ということである。資本形成は一般的には、次のような属州においてはかなりの程度まで妨げられていた。その属州とは辺境の諸邦のように植民を目的とした飛躍的な発展が見られたものとしては把握出来ないものである。資本形成が妨げられた理由としては、占有の土地においての自給自足と、大規模の産業分野での国有化、そういった理由の中でも取り分けまず生計を立てていくことを優先することが資本形成を妨げていた。またデクリオーネスに対してはより高い階級での軍役への参加は認められていなかったので、諸都市はそういった者達に対して実際の所より高い地位の市民になるための相対的にごくわずかなチャンスしか与えなかったか、あるいは場合によっては全く与えていなかったのである。このことは地主達において、特にデクリオーネスにおいての、諸都市から概して距離を保つという傾向を強めたのである。次のことについては既に上述の箇所で言及した。つまり帝政期の開始により貴族政治の可能性が失われたことによって、大地主が再び農場経営者に戻った、ということである。コルメッラはその時代に既に次のことを推奨している。つまり大地主がその所有する土地で快適に過ごすための設備を整備することで、それがまた農園主の家族に対しても継続してその土地に滞在し続けられる環境を提供したのである 88)。
88) コルメッラ、1, 4, 参照 1, 6。
パラディウスの場合は、主要な邸宅[praetorium]89) の存在――Palais[宮殿]――と更にそれと並んで fabrica90) ――工房――がきまって[農場経営の]前提条件とされていた。
89) パラディウス 1, 8.1, 33。彼によれば[主たる邸宅から]糞尿小屋は遠くに離して設置すべきものとされていた。
90) パラディウス 1, 8。
帝政期のより後の方になると、全く一般的な現象として次のことが登場する。それは占有者達が絵画、家具、大理石の壁板、そして他の装飾品一般を都市の住居から取り去ってそれらを地方の邸宅に移送して、都市の住居については一部では完全に退去する、ということである 91) 。
91) 既に 1, col. Genet, c.75, Eph. epigr. III の p.91 以下;C.I.L., X, 1401(44/ 46 年の元老院決議)。都市の住居の装飾品を地方に移すことについては、ユスティニアヌス法典 6 de aedif[iciis] priv[atus] 8, 10。高い身分の人の地方での滞在についてはユスティニアヌス法典の VI, 4 で述べられている。
特にまたデクリオーネスはこういったやり方で自分達の所有物をムニキピウム団体から分離することを進めていた。国家による法制定と地方の法規は、既に帝政期のより早い時期においてこれらの動きに干渉しており、都市においての建物やあるいは建物一般を行政当局の許可無しに取り壊すことを禁じており、同様に占有者達の都市の住居からの家具調度品の除去も禁止した。しかしながら都市の崩壊の進行は類を見ない程激しいものであった。このことは次のことと矛盾していない。つまり一方ではその人口と物質的な豊かさが増大していると把握されていた都市が存在していたということであり、それは例えばマイラント[ミラノ]であり、それは諸街道の結節点に位置しており、その諸街道は強力な植民政策による人口増大と建造物の密度の上昇が起きていた辺境の属州に向かって延びていたのであり、また一般的にそういった辺境の属州において都市としての持続的な発展が起きていた、ということともまた矛盾していない。ガリアにおいては、土地制度的な要素の優勢と結び付いた自然経済的な状態が衰え始めたのは、ようやくメロヴィング朝≪481~751年でフランク王国の最初の王朝≫においてであった。しかしながら中央において出ていた傾向を見た場合、諸封と古くからの属州においては、既に帝政後期においてまさに上述したような状態になっていた。有名な標語[都市の空気は自由にする]は次のように言い換えることが出来よう:「田舎の空気は自由にする」と。そしてこの状態が完全に解消されるまで状況が成熟するには実に500年が必要だったのである。≪中世イタリアの自治都市の興隆を踏まえて言っていると思われる。≫。この2つのケースにおいて自由というものは我々の個人主義的な意味で、次のことを指しているのではない。つまり占有者の保護の下でコローヌスになる形で逃げて来た都市住民とか、あるいは地方の農奴が都市の中に都市外在住市民として引き込まれた者としての自由ではない、ということである。そうではなくて、こういった何百年にも渡った[都市の]上昇と沈下の現象は次のことに帰属する。つまり個々の人間が何をもって「自由」と見なすのかと言うことと、そして何についてその者が自由でありたいと欲したのか、しかし取り分け関心を持たれていたのは、こういった発展が将来はどうなるのかということと、その時々の時代においてのイメージに合わせての、生きる価値のある生存という希望がどこにあるのか、ということである。ローマ帝国が没落した時代にはしかしながら発展の将来性は荘園制にかかっていた。
我々が文献史料から見て取ることは、地主に従属するコローヌスと「半地主従属的ー半自営農民的」状態にある者を、我々の[プロイセンの]農地法≪19世紀の初め頃からプロイセンでは農奴解放運動が起きていた。≫の用語で語ろうとする試みは成立せず、そういった者達においては地主との関係は純粋に契約に基づくもので、相互に独立して存在していたのであり、その関係は地主の農場の外側に存在していた。しかしここで第3章において述べた次のことが関係して来る。つまりデクリオーネスが納税義務を課せられていたことは、その結果として起きたことは諸都市の領土が何十にも分割された専制[者の土地]へと解体された、ということであり、こういった専制はより小規模の地主をその中に囲い込んだのであり、そしてそれぞれの専制政治を行う者によってその専制領域の税は、その者自身が経営する農場に対するものと、また中に囲い込まれた小規模地主に対してのもの、そしてコローヌスに対してのものを含む形に拡大されており、そのことによってその専制領域に属する納税義務者は事実上統合されたのである 92)。
92) テオドシウス法典 2 de exact[ionibus] 11, 7 (319年のコンスタンティヌス帝の立法による):いかなるデクリオーネスも次のこと以外で訴えられることはない、それはその者に課せられた人頭税についてと、その者の配下のコローヌスと人頭税を課せられた者達についてであり、「他のデクリオーネスやまたはその領地を理由として」[pro alio decurione vel territorio]訴えられることはない。デクリオーネス自身に全体責任が課され、[各デクリオーネスの中から更に]一人の長が選び出されてそのゲマインデの全体での税の総額に対してその者に責任が課されたのであり、それは既に D. 5 de cens[ibus] 50, 15 に規定されていた。今や各都市の領土は専制者の領土 [territoria] [の集合]に変わってしまって破壊され、それぞれのデクリオーネスが自分の領域について責任を負うようになっていた。このことは先に(第3章で)扱った土地台帳の断片の内容と矛盾していない。πάροικοι [傍に住む者→市民権は持っていないが住み着いている者]自身は単なるコローヌスであるということはあり得ず、この表現はマルクス・アウレリウス帝の時代のボイオーティア地方≪古代ギリシアの地方名で中心都市はテーバイ≫の碑文に同様に出てくる(C. J. Gr. 1625)。そこでは誰かが次の者達、つまり πολεἰταις [正規の市民に対して]、かつ παροίκοις [正規の市民ではない居住者に対して]、かつ ἐκτημένοις [正規の市民ではないが土地だけを取得した者に対して]贈与を行っている。ここでは πάροικοι はコローヌスとはほとんど見なし難く、それ以上に C. I. G. 2906 が確認しているようなデクリオーネス(πολεῖται)として直接納税の義務のある住民ではなく、ここで πάροικοι として語られているのは18~20歳の青年[Epheben]≪軍事訓練を受け成年になる準備をしている青年≫のことである。πάροικοι はよりむしろ受動的な資格の市民であり、つまり確からしいのは、tributarius [現物貢納の義務を負った者]と表現されている者達と同じであり、そしてこれらの者は(上述の箇所参照)コローヌスに並置されており、ムニキピウムの租税に関連付けられた者としてそう名付けられている。既に述べたことではあるが、私には次のように思える。つまりそういった者の中には、専制下に置かれるようになった小規模の地主が含まれており、その者達はそれ故に占有者ではなくなっているのであるが、そういった者達が規定されており、そのこととテオドシウス法典 2 si vag[um] pet[atur mancipium] 10, 12 の規定は矛盾していないであろう。地主への現物貢納の義務については、それは文献史料を一瞥すれば明らかなことであるが、コローヌスに関する全ての状況の中で非常に重きが置かれていたのであり、全てのケンススでの納税義務のある登録者[adscripticii]というものの実体がコローヌスに接近していった、ということは不思議なことではないのである。コローヌスという表現は一般に時においてはその土地に定住している訳ではないその土地の従属者に対してもまた用いられていた(テオドシウス法典 4 de extr[aordinariis] et sord[idis] mnu[eribus] 11, 14 とGothofredus≪Iakobus Gothofredus、 1587~1652年、ジュネーブ生まれの法学者・法制史家≫)。――コローヌスとして扱われた者についてではなく、ただある占有者の専制の中に囲い込まれた者の不完全に併合された納税義務は私には、その他の点では不明確で全く破綻しているユスティニアヌス法典 2 in q[uibus] c[ausis] col[onii dominos accusare possunt] の法令に関連しているように思われる。その法令は coloni censibus dumtaxat adscripti [ケンススだけによってコローヌスとして登録された者]について規定しており、またその者達が負わなければならない現物貢納についても扱っており、更にはその者達がコローヌスと同様にその主人に対して訴えを起こす権利が無く、ただ限定された、コローヌスにも許された場合にのみ特別な法的保護が与えられることを規定している。 ここについての法規の目的はそういった単なる adscripti をコローヌス一般と平等に扱うことであったように思われる。この章句に続く部分はおそらくは トリボニアン ≪ビサンチン帝国の法学者達でユスティニアヌス法典の編纂に従事した。≫によって書き加えられたものであり、その時代にはこの2つの集団の差異はもはや無くなっており、そこについて トリボニアン はこの部分は奴隷についての記述だと思っていたのであろう。
納税義務者[tributarii]とは占有者に従属するこういった身分の者達であった。占有者の身分直接的な納税義務を負う土地所有者としての特別な身分として他からはっきりと区別される際立った存在となった。占有者の各都市のクリエへの帰属はもはやそれらの都市の領土では無くなった占有された土地についての税負担 93) という風に見なされることが可能になっており、そのことは占有者の義務、例えば新兵募集の義務、をその者達の土地が直接負担するものでないように切り離すこと 94) を動機付けた。
93) テオドシウス法典 33 de decur[ionibus] 12, 1;同法典 1 de praed[iis] et manc[ipiis] cur[ialium] 12, 3。
94) テオドシウス法典 1 qui a praeb[itione] tir[onum…excusentur] 11, 18。
次のことは言うまでもないことである。つまりこうした展開は各地方において非常に異なった程度にそれぞれ到達しており、一部ではまだ始まったばかりであったし、それは当時ローマ帝国の領土の全てをムニキピウム領域において一つの組織で統一するという皇帝の理想の進展と同様であった、ということである。この発展傾向をより押し進めようと欲した場合、常にそれは次の留保条件付きとなったのであり、つまりそれはただ傾向に過ぎず、そしてその実施の程度は地方毎に異なっていたのであり、その傾向というのは完全に純粋な形ではもしかするとどこにおいても実現してないと見えるものとして、つまりは理想像として形作られており、それ故に、私は信じるが、それほど大胆ではなくとも次のように言うことが出来るであろう:皇帝の考えはもしかすると元々は次のようなものであったのかもしれない、つまりローマ帝国を自己管理し自治を行う諸ムニキピウムと、その諸ムニキピウムが負担する国家への分担金と結び付けたものにする、ということであるが、しかし帝政期にはそういう自己管理は次第に無効にされていったし、そして諸ムニキピウムは通常の場合はローマ帝国の行政管理の及ぶ領域とされたのである。しかし事実上はローマ帝国全体に荘園制度網が張り巡らされたのであり、その状況において諸ムニキピウムは産業的な生活や、資本形成という欠くべからざる中心点を自分の中に置くことなく、また市場という不可欠なものにもなることもなく、結局のところは国家の税収管理においての単なる税金吸い取り装置という状態に留まったのである。
大地主制の内部の組織
ここで我々は占有の内部の状況についてそれを観察する必要がある。占有者達は自分の地所を、それについては既に見て来たが、次のように管理していた。つまりムニキピウムの官吏を真似してその土地領域に管理人を置いて管理させたのである。管理人[villicus]は確かに帝政期においてもなお、大地主制においての業務遂行者であるのを見て取ることが出来るが 95)、しかしながらその者と並んでそして事実上はその地位を置き換えているように見える者として、”actor”[代理人]が登場して来ており 96)、それはムニキピウムの同名の役職に相当しており、既にその名前にほのめかされているように、その者は官庁の業務について、準国家的な行政管理業務を委託されていたのであり、それは文献史料にも示されている 97)。
95) C.I.L., V, 878.7739; X,1561.1746.4917。
96) C.I.L., V, 90.5005.1939; VIII, 8209; XII, 2250。
97) この後に引用する箇所を参照せよ。コルメッラの 1, 7では actor は familia [一族郎党]に並記されている。
Villicus の場合と同様に actor は通常奴隷であった。管理規模の大きい農園においては actor の上位または actor の代わりに procurator [上級管理人]が置かれ 98)、それは皇帝に所属する官吏の名称を借用したのであるが、その者は解放奴隷であった。
98) 私人である Prokurator については C.I.L., V, 4241.4347; VIII, 2891.2922.8993。皇帝の官吏である Prokurator については例えば X, 1740.6093。
こうした上級の管理人は一般的な管理業務は免除されており、また人員や資産のリストを作成することになっており、その者達は国家のまたは皇帝の管理担当の官吏と全く同等に扱われた 99);現金の出納業務については規模の大きい、特に皇帝領の土地においては、dispensator [管財人]100) がその者達を支援したが、その管財人も多くの場合は奴隷であり、財産目録の作成においては fabularius [会計士]がその者達を支援していた 101)。
99) C.I.L., X, 3910:ある者で、元々公的な官吏であった者がある(もちろん非常に重要な)私人の “praefectus”[任命された者]になったのである。このことは明らかに次のケースと同じである。つまり[ヴェーバー当時の]今日ある者が国の官吏からある貴族の所有する森林の管理人になって登場することである。”praefectus”という表現は当時間違いなく官職としての仕事を意味していた。ウァッローの 1, 17 によれば”praefecti”[praefectusの複数形]は農場経営においての監督者であって villicus の下に置かれたが、しかしやはり奴隷であり、しかしながら一般には一夫一婦制を取っていた。”Procuratores”[ procurator の複数形]はウァッロー(3, 6)においては鳥小屋の管理人として登場し、コルメッラの(9, 9)においては養蜂場の管理人として現れ、それ故に当時はまだ純粋に経済的な機能を果たす者であった。
100) C.I.L., V, 83; XIV, 2431。
101) C.I.L., VIII, 5361(私人の)、3290 (皇帝の)。
こうした農場における官吏達の干渉については度々訴訟沙汰となっており 102)、それもその理由の大部分はアフリカにおいての夫役への苦情と同じであった。コローヌスの位置付けは、特にムニキピウムによる管理外とされた個人地主によって支配されていた場合には、色々な面で不安定なものであった。
102) テオドシウス法典 I, 7, 7。そこでは有力な procuratores が拘束され受刑することになっている。同法典 1 de jurisd[ictione] 2, 1;同法典 1 de actor[ibus] 10, 4。
以前見て来たように、コローヌス達は事実上その耕作する地所に縛り付けられていたのであり、それはつまりまず第一に、その土地領域から切り離されて立ち去ることが出来るような状態にはなかったということである。それにもかかわらず、こうした自由な移動権の制限はほとんど負担になるものとしては受け取られておらず、というのもここでの自由な移動権は単なる可能性としての意味しか持っておらず、その可能性としては耕作している土地を放棄する、ということであるが、それ故に価値の高い権利としては全く受け取られていなかったのかもしれない。コローヌス達にとってはるかに重要であったのは次のことで、つまりその者達が地主の意向に逆らってまでなおその耕作地との結び付きを許されるかどうかであり、それ故に地主達にとってはコローヌス達は、通常の自由民である賃借者のように、解約の予約をしたり、あるいは賃借期間が満期になった時に賃借料を引き上げることを許された、そういう存在ではなかったのである。ある土地領域に定住している人が、猶予期間無しにその土地領域から退去させられることが可能であったということは明らかである。というのはどのゲマインデもその者を受け入れることを義務とはしていなかったからである。先ほどのコローヌス達にとってはるかに重要であったことが実務的に意味していたのはつまり:地主が農民をその土地に「配置」し、そして日雇い労働者についてはその扱いを改めるなどしてその土地区画を取り上げ他の者に与えることが出来たかどうか、ということである。明らかなのは、地主が[その従属下の]誰かが死んで相続が行われる時に、そのやり方に干渉し、かつ土地の引継ぎについて取り決めることが、ほとんど随意に行うことが出来るものであった、ということである。その他第3章で我々は次のことを見て来た。つまり土地改革法[lex agraria]はアフリカの国有地の賃借人あるいは 1/10 税の義務のある占有者に対して、lex censoria によって賃借料他を値上げすることを禁止することに利害関心を持っていた、ということである。leges censoriae には渥取行為に基づく国有地の賃貸借契約において、確かに同様に大規模賃借人が小規模[2次]賃借人 に要求出来る賃料の上限を定めた条項が含まれており、このことは皇帝領の賃貸しの場合にも同様であったし、更にまた同様にコローヌスから土地を奪うことについての許可についても、それに関する規定が含まれていたのである。そのようにコンスタンティヌス帝のシチリア、サルディーニャ、そしてコルシカの国有地の管理についての指示を規定しているので(テオドシウス法典、[de] comm[uni] div[idunde] 2, 25)、その結果として土地を分割する際には家父長達と永代借地契約者達は奴隷達の血縁者 [agnatio]を一緒のままで居られるようにし、恣意的にその者達を分割することが禁じられた。こういった純粋に訓令的でかつ奴隷に関しての規定からトリボニアンは良く知られた “coloni adscripticae condicionis”[ケンススに登録された身分としてのコローヌス、実際にはコローヌスではないのにケンスス上でそう扱われた者を含む]に関しての法律(C.I.II comm[uni] div[idundo] 3, 28)を作り出し、そしてその規定は全く一般的に個人である占有者達に関連付けられた。この規定は本来は全くもって私人に関するものではなかった。より一層私人に対して関係付けられていたのは、コンスタンティヌス帝による法規であり(C.I. 2 de agric[olis], 11, 47)、その中で禁止されたのは、ある土地を売却した者がその土地のコローヌスを自分の元に引き留めて他の目的に使用することであった。そういった禁止は市民法やまた行政法に従った場合には、それ自体必要不可欠なものであったことは全く無いと思われるが、――というのは土地に従属するコローヌス達は元々その土地に対して自分の出生地として確かに縛りつけられているからであり、――もし私法と行政法の複合したものが先の禁止に相当する解釈に達し得なかった場合でも、コローヌス達は所属という観点では私法的な意味においてのその主人[地主]に属していたのである。奴隷に関する法をコローヌスに対しても適用するというまさに法律の濫用は、コローヌス達を人員として奴隷と同様に売却することを可能にしようとする試みであった。コローヌス達はその土地に本来は単に住民として所属するものであったので、このことは法学的には問題外であった。しかしその後試みられたことはコローヌスの状況について次の混同を引き起こすことであり、それはつまりある者が小さな土地区画を売却した際に、その土地区画と共にその土地を耕作していたコローヌス達についての主権と処分権をも一緒に移転させた、ということであり、その結果として事実上コローヌス達も売却可能にする、ということが試みられたのである 103)。
103) 似たような困難さは、尚≪ヴェーバー当時の≫今日我々≪プロイセン≫においても、大地主の土地領域を構成している土地を分割する際には生じている。実務的な取扱い方法はその際にぞれぞれの地方にて異なっている。
この方向を歓迎し、そしてユスティニアヌス法典 7 の前掲部がこの禁止令を更に servi rustici adscripticae condicionis [ケンススに登録された身分としての地方の農場の奴隷]に拡張適用しようとしたものであり、これが意味しているのはコローヌスと奴隷という者達は、地主の財産のケンススへの登録リスト上、特別にその[人頭税の]税率と共に記帳された、ということである。コローヌス達とこれらのコローヌスに接近したものとなった奴隷達は土地の分割売却の際にはぞれぞれの面積に応じて[pro rata]分割されて引き渡されることとなった。コローヌスの地位を奪うことの禁止は、それ以外では文献史料において明確に記載しているものはない。しかしながらただ現にある耕作地についてそれをその耕作者の土地とみなすことを許す行政上の保護が行われていたようには思われ、何故ならば地主が[購入した土地に付属している]コローヌス達を競り落とそうとする試みに対してある種の特別な手続きが許されていたからである 104)。
104) ここでは市民への裁判について述べているのではなく、「犯罪行為を立証する」[facimus comprobare]ことについて述べているのであり、そしてまた任意の判決内容を求めることが許されていたのであり、――もちろん、というのも地主の土地領域においては正規の司法当局というものは成立していなかったからであり、そしてもまた裁判を行えるかということについても疑わしいものであったに違いないからである。
そういった干渉行為はただ任意のものであったので、その結果現金による納税義務者による大土地経営においては例えば第3章で述べたことに従って≪ager stipendiariorum はローマの領土として取り扱われており、そこでは法的な訴えは起こすことが出来ず、ただ行政上の処理のみが適用可能であったということ。≫おそらくは常に許可されており、そしてもしかするとそこからそういう状況が生じて来た可能性もある。[コローヌスの家父長の]死亡の場合においては地主に対して次の可能性が与えられた。つまり相続資格のある者達について、誰を相続者にするかと指定する、ということで、それは決してその者達の中から人を削減することが可能になったのではなく、相続者以外の残った者達は結局 “inquilini” [同居人]となったのである。私人の土地領域でどの程度まで実際に「農民保護」が行われたかについて、知り得る情報は無い。その他の点では地主は一般的にコローヌスの扶養までは必要とされておらず、というのは農場主自身が、既に論じたように、自費と自己責任で生活して耕作している農場の従属者であって、種蒔きと収穫の際に労働者として使用出来る者達の扶養の方に関心があったからである。――コローヌス達の独立性の程度とその一般的な状態は非常に様々であったのであり、もしかするとそのためにある土地への植民のやり方もまた非常に様々であったかもしれない。アフリカにおいては――しかしながらまた砂漠の諸部族からの襲撃を考慮して―― die vici der plebeji [平民の住む村々]が置かれており、というのはそこでは現金による納税義務者について言っているのであるが、全ての居住者、コローヌス、手工業者、商人が住む村々がそういった納税義務者の邸宅を取り囲むようにして防御する形になっており、それを”in modum munitionum” [要塞の境界線上に]と測量人達は先に引用した箇所において描写していた。そういった居住の仕方は次のような場合にもまた同じであった。つまりコローヌスが奴隷の進化した者として現れており、かつそれ故にまず第一には労働者である場合で、そういった労働者は土地の管理人である actor や villicus の厳しい監督下に置かれており、それはコルメッラが前提としていることであるが、特にそのコローヌス達の食事が農場の側で供給されねばならなかった場合にそうであり、そうされた理由は夫役の日数が自由な日の日数より多かったからである 105)。
105) ガリアでは次のことが起きていたと思われ、それについては敬愛する顧問官のマイツェン教授が私に気が付かせてくれたものであるが、ある邸宅を取り囲むような集住が次のようなやり方で、つまりコローヌス達が農場主の邸宅の周りを囲むように集住して村落を形成し、また方形の耕地がそこに置かれる、というやり方で起きていたということである。このことは私の考える所では、ただ次の意味だけを持っていた。つまり大地主が奴隷をもはや相当な程度の数で抱えておくことがなく、そのために今や全ての耕地にただ夫役に従事するコローヌス達のみを配置し、要するにこういった好都合な、夫役に従事する農民とまさに同じ者達を使うしかなかったのであり、そしてコローヌス達のフーフェ制度のやり方に従って形成された村落によっての地主の邸宅の囲い込みが要望され、そしてその結果土地のの新たな分割割当てが行われ、その際に他方では大地主その配下の者達を、軍事上の理由から自分の邸宅の近くに集めたのである。しかしながらこのことが起きたのはドイツの植民地建設[民族大移動の結果による]の後であり、それ故この時代に起きたことではない。
コルメッラはそれ以外に次のことも規則的に起きたこととして認めている。それはコローヌス達が大地主が管轄する領域から離れた場所に居住していた場合もあった、ということである。それ故にコローヌスの大地主に対しての位置付けというものはもはや、コローヌスに対して実際に成立していた従属性の程度と社会的な状態については、一般化出来るようなことはほとんどない。glebae adscriptio [土地の付属物]という表現は、それが何らかの新しい要素を包含している限りにおいては、コローヌス達の地位が悪化したという意味は持っていない。
地方における労働者という身分の運命
そういったコローヌスの状況に対して、奴隷の状況についてはいくつかの発展傾向が新たに確立されていた。我々が先に見て来たように、奴隷を使った農場経営はその頂点を極めた時、つまり帝政期の初期においては、強度に軍隊風であった。奴隷達は兵舎のような共同の宿舎で眠り、一緒に食事を摂り、単婚制的な男女の関係は一般的にそこではほとんど見られなかった。≪これはヴェーバーの思いこみで正しくない。実際は同棲形態で暮らす男女の奴隷は多くいた。≫軍隊での10人組風のやり方で朝になると集まり、男性または女性の管理人によって点呼を受け、そして3-10人の単位で仕事場に連れて行かれ、「現場監督」(monitores)の監視の下で働かされた 106)。
106) コルメッラ 1, 9;12, 1。
労働のためのグループ分けは各奴隷の体力に応じて行われ――体力のある者は穀物畑に、逆に体力に劣る者はブドウ畑に振り分けられ 107)、――更には残った者はブドウ畑とオリーブ畑に割り振られ、また先に詳述したように、価格の安いかつほとんどが鎖につながれたままの通称有罪奴隷もそちらに回された。
107) コルメッラ 1, 9。
――奴隷に与えらる衣服は、我々が兵舎で支給されるものと同様のもので、その兵舎[宿舎]の中での決まった場所に保管されていた。奴隷は毎年チュニック≪2枚の長方形の布を肩で結んだトーガの下に着る内着≫を、2年に1回サガ≪外套≫(カトー 59)を受け取っておあり、それと並んでその者は仕事の時に使うための継ぎを当てた上着(centones)を所有していた。月に2回員数点検が行われた 108)。
108) コルメッラ 11, 1。
祝祭日用の飾りつけは男性奴隷は女性の管理人に対して「部屋の中で」行うことになっていた。女性の管理人達は調理場を共有し、同様に機織り機もであり、それを使って女性の奴隷が衣服の必要を満たすために機を織っており、また病室も同様に共有していた 109)。
109) コルメッラ 12, 1。
通常の奴隷の上に、既に言及したように、管理人である villicus がおり、大抵はその農場で生まれ育った奴隷の一人であり、後にはより上位の管理人である actores が出現している。後者については、コルメッラが言及するところでは、より上質の衣服を着用していたとされている(12, 3)。actores は単婚制を取っており、時には農場主の食卓に招かれることもあり 110)、そして大地主と共有する財産というプレミアムを与えられていた。≪全集の注によればこのプレミアムはインセンティブ的に一般の奴隷にも与えられていた。≫全く同じことが奴隷の区分けに権限のあった praefecti [praefectus の複数形]にも言え、その者達も単婚制を取っており≪ヴェーバーは単婚制を actores や praefectus の特権であったように書いているが、一般の奴隷においても婚姻権こそ無いものの、contubernium 、字義としては「同じテントで寝る」、という同棲婚が多く行われていた。これは奴隷に子供を作らせる上でも有効なため、コルメッラの農業書などでも奨励されていた。≫、また同じくプレミアムを与えられていた 111) 、――この二つの身分はしばしば同列に扱われていた。
110) コルメッラ 1, 8。
111) ウァッロー 1, 17。
奴隷の供給が封印されればされる程、そのために地方の奴隷達がまさしく自分達だけで何とかやって行くしか方法が無くなった程、そしてそれによって耕地で農作業を行う奴隷の人口が減っていけばいく程、それだけ一層奴隷達の組織は確固たる形で構築されねばならなかった。コルメッラの農業書では magistri officiorum ≪ローマ帝国の最後期での最上位の行政管理官≫が言及されているが 112) 、奴隷達はそれ故にただ純粋に「会社組織のように」階級や10人組制度に従って組織化されたのではなく、そうではなくまたその仕事の内容に従って、またその労働力の種類によって組織化されたのである。
112) コルメッラ 11, 1。
そのことは農場で必要とされる技術がより一層細かくなり高度化したことと関係がある。カトーやウァッローのようなより早い時期の農業書においては、多くの場合ただ家畜の世話をする飼育係だけが他と区別されており、他の全ての人員は operarii [作業者]として一まとめにされていた。コルメッラがしかし言及しているのは、新たに次のことにより重点を置かなければならない、ということで、それは例えばブドウの栽培であり、それに対してそれまでは最低価格で購える人員が使われていたのであるが、熟練の vinearii [ブドウ栽培人]を雇い入れなければならないと主張しており 113)、そういった者達は当然のこととしてその部門に継続して留まったのである。
113) コルメッラ 3, 3。
そういった人員間の区別は次の場合にはより一層はっきりしたものになったに違いない。それはより規模の大きな農場で、自前の手工業者を組織化し始めた時である。コルメッラが更に言及していることは 114)、fabri [手工業者]は多くの場合購入奴隷であったということで、――もしかするとそういう者達は相当規模の学校出身であり、しかしより確からしくは都市の親方達の元で技術を取得した者達であっただろう 115)。
114) コルメッラ 11, 1。
115) 法的史料にしばしば見られるのは手工業に従事する奴隷の訓練についての契約書である。
しかし後の時代になるとこれに対して、既にパラディウスの時代には、上述したように、手工業者を自分の農場内で養成するようになった。より後の時代の農場の組織においては、農業労働者の部門の――officia――と手工業者の部門――artificia 116)――がはっきりと区別されるようになった。
116) D. 65 de legat[is] :ある奴隷が officium から artificium に異動させられた場合は、その労働の対象が変わることによってその奴隷が持っていた[土地などの]相続対象物の権利は消失した。familia rustica 「地方での一族郎党]と familia urbana [都市での一族郎党]の明確な区別についてはより古くからあるものであるが、後の時代のものについては D.99 pr. de legat[is] 3;D.10, §4, de usu et habit[atione] 7, 8 と比較せよ。共和制期においては、不要となった人員を familia urbana から地方へ持って行くことが行われていたが、これは後になると変わり、コルメッラは familia rustica が基本的にはより高い地位に置かれるようになっていたことを確認しようとしていた(コルメッラ 1, 8)。
二つの部門のどちらに所属しているかということは、いずれの場合もその奴隷の奴隷舎からの解放が実現するとすぐに明らかにされ、そして手工業者にとっては一般的に行われたことは、その所属の地位が事実上相続可能なものとなったことである。農場での共通の奴隷舎からの解放が一般論として決定的な発展の主因となっていた。農場の管理人達、つまり officiales においては、既に述べたように、それらが確立したのはコルメッラの時代であり、その者達は単婚制を取っており農場主からプレミアムを受け取っていた。≪先に書いたようにどちらも管理人達だけの特権ではない。≫既に帝政の初期においてその者達と自由民の結婚が行われていたし、≪奴隷には正式な婚姻は認められておらず、ここでの話はおそらく解放奴隷のことと思われる。≫大地主経営する農場に属している者達は、こういった形でまさに大農場の中で組織分けされている限りにおいて、その状態を一種の身分と捉えており、共同宿舎からの解放はただその農場の中においての昇進と思われていた 117)。
117) 奴隷と自由民の結婚については C.I.L., X, 4319.5297.6336.7685。villicus と自由民の結婚を記録しているのは C.I.L., II, 1980。自由民と管理人の結婚については C.I.L., X, 6332、actores の単婚状態については:C.I.L., V.90.1939; XII, 2250。通常の奴隷の確固たる同棲婚の例としては C.I.L., V, 2625.3560.7060。servi dispensatores [財務担当の奴隷]はしばしば富裕な者達であり(ヘンケン≪1816~1887年、モムゼンと一緒に古代ローマの碑文の解読を行った文献学者≫, 6651)、そしてそれらの奴隷が解放されなかった理由は、モムゼンの推測によれば(C.I.L., V, 83)、その者達が会計管理人として場合によって[不正なことをした場合には]拷問にかける可能性があったからではないかとしている。確固たる同棲関係が古典法学の時代に規定として認められていたとしたら、その場合には既にその当時そういった関係を継続性があるものとし、良く知られた「奴隷の内縁者」として認めていたのかもしれない。
こうした発展の道徳的な意義については、ここでは特段何かを述べる必要はないであろう。
次のことを頭の中に思い浮かべなければならない。つまり古代の世界では帝政期の初期においてべーベルの理想≪アウグスト・べーベル、1840~1913年、マルクス主義者でドイツ社会民主党の創始者。その主著の「女性と社会主義」で、男女の自由意志に基づく平等な結婚を主張した。≫に合致するような結婚の法的構成は上述したような状態で de facto [事実上]のものとなっており、その後一般的にまた de jure [法律上]でも有効なものとなっていった。その結果として起きたことは周知のこととなっている。こうしたローマにおける労働の実態という枠組みの中で、このような経済的発展とキリスト教的な結婚の理想の関係を評価することは不可能である。しかし次のことは明らかである。つまり農場の経営者が奴隷という存在を解体したことが、それらの奴隷にとっては内面深くにおいての精神の健全さの回復につながったのであるが、それはしかし社会の最上位層1万人[権力者・大富豪]の没落の中で、諸蛮族はそういった結婚の理想を高く評価して自分達の制度として受け入れる、ということは全くしなかった、ということである。外面的には既に注記したように、奴隷を使った自営的農業経営の確立は、それは労働力調達コストの高騰とそれによる大農場制による自分の土地の耕作で上がる利益の減少と共に現われたことから分かるように、帝政期においての農業発展の結果であった。こうした発展が次に向かったのは、当然のことながら次の地点であった。それは奴隷達が奴隷舎を出て、自分自身の家に住み単婚状態で暮らしている「解放農奴」――[ヴェーバーの時代の]現代的な例えを使うならば≪プロイセンでは19世紀初頭から社会改革として農奴を自営農民に解放する政策が進められていた。≫――に成ったという地点である。奴隷の農場主に対しての権利状態が同様に示していたのは、その農場主の経営を固定地代に基づくものに変えていく方向に導いていた、ということである。文献史料は次の二つの場合を区別している。一つは奴隷が固定地代を支払うことを条件としてある土地区画に留まる状態であり、もう一つは奴隷が “fide dominica” 117a)[主人=地主に対して忠誠を誓った状態]で、ある土地区画をその地主自身の経営のために耕作している状態である。
117a) D. 20 §1 de instructo 33, 7 (スカエウォラ)。ある者がある土地をそこで使う農具と一緒に遺贈した、――”quaesitum est, an Stichus servus, qui praedium unum ex his colonit … debeatur. Respondit, si non fide dominica, sed mercede, ut extranei coloni solent, fundum coluisset, non deberi. [奴隷のスティクス≪典型的な奴隷の名前。同名の奴隷を主人公にした喜劇有り。≫に関して次の問いが発せられた。その者はこの土地のある区画に住んでいたのだが…~をする義務があるか、という問いである。(裁判において)法学者は答えた。その者が地主に対して忠誠を誓っているのではなく、地代を支払っているだけで、それは外部のコローヌスが通常そうするように、そうやって農地を耕作していたのであれば、その義務を負うことはない。]
それに対して D. 18 § 44 の前掲部(パウルス)では: Quum de vilico quaereretur, et an instrumento inesset, et dubitaretur, Scaevola consultus respondit, si non pensionis certa quantitate, sed fide dominica coleretur, deberi. — [農場の管理人から(その奴隷の)農具がその者に属するか疑わしい、という疑義が提示された時に、法律の専門家であるスカエウォラは答えた。もし固定額の地代を支払っているのではなく、農場主に忠誠を誓った状態でそこに住んでいたのであれば、(その農具を返却する)義務があると。]――最初の箇所が述べているのは、”dotes colonorum”[コローヌスの嫁資=結婚相手の女性が自分の財産として持参するお金。夫と離婚したり死別した場合にはその女性に返却される。]が一緒に遺贈された、ということであり、つまり独立してある土地を耕作しているコローヌスにとっては、嫁資もその他の財産と一緒に遺贈すべき財産の一つであった、ということである。これらのことほど、次のことをはっきりと示しているものはない。一つにはコローヌス達がここで地主による奴隷を使った経営を単純に置き換えている、ということであり、もう一つはまたこうした奴隷を使った経営が次の傾向を持っていた、ということで、つまりそれが[コローヌス毎に]独立した土地区画に基づく経営で、そこから大地主が固定額の地代を取る、という形式に変わっていく、という傾向である。次の段階での更なる発展の進行においては(後述のテキストを参照)、その他の政治的な要求が農場主にとって自分自身で耕作を行っていくことを不可能にしたのであり、また “fide dominica” として働いていた奴隷による耕作について、その奴隷をどうしても解放せざるを得なくなり、そしてただ政治的な従属、つまりは隷属だけが後に残ったのである。
後者の場合は奴隷は農場主の財産目録の中の一つに過ぎなかったが、前者の場合はそうではなかった。この “fides dominica” とフランク族が征服した地域における “in truste dominica” を比較するのは、ここは適当な場所ではない。≪ヴェーバーはおそらく “in truste dominica” を「領主による農民の保護」と誤解しているように見える。しかし全集の注他によれば、この表現はフランク王国の6世紀のメロヴィング朝にて制定された lex salica に出てくるもので、その意味は「王に忠誠を誓った貴族による親衛隊、従士団」であり、農民に関係したことではなく、 “fides dominica” とは dominica が共通するだけでそもそも比較対象になるようなものではない。≫奴隷達のコローヌスへの接近は、すなわち地方においての農業従事者においてのこうした変化は、しかしながらローマの帝政期の歴史においての、もっとも重要なものの一つであり、また疑いようもなく確実に起きた事実である。
紀元後の最初の世紀において、奴隷達は既に一種の同業者組合[ギルド]のような団体を結成しており、その目的は部分的には相互扶助・葬儀共済のためであり、また他の部分では狭い個人また知り合いとの交わり以外のものであって 118)、それはしかしながら一般的に言えば、諸家族の自発的な組織化の始まりということが出来る。
118) プテオリにおける皇帝領において、奴隷達と自由民達は、モムゼンの C. I. L., X, 1746 – 48 への注記によれば、西方の地の評議会[ordo]とデクリオーネス達と collegium ≪一種のギルド、後には大学や会社という意味でも使われるようになる。≫を組織化していた。バウリ≪ナポリの西20Km、現在のポッツォーリの一部≫の農場においては、C. I. L., X, 1447 によれば collegium Baulanorum [バウリのギルド]が見出され、また ordo Baulanorum [バウリの評議会]もである。同じように見たところでは存在していたようであるのは(モムゼンによる)、C. I. L., X, 1748 での ルクッルス≪BC118~BC56年、共和制ローマの政治家・軍人。美食と豪華な別荘で有名。≫の別荘のある地≪おそらくナポリ湾沿岸の高級別荘地≫でのデクリオーネスである。C. I. L., X, 1746 ではバウリのある一族の管理人[villicus]が墓所を買い求めている。参照:ブリタニアでの碑文 C. I. L., VII, 572 (collegium conservorum [奴隷仲間のギルド])とC. I. L., X, 4856 の collegium familiae publicae [公共的な存在である諸家族のギルド]。C. I. L., XIV, 2112 の法規ではギルドの構成員が他の構成員の恥ずべき行為に対して罰金を科している(参照:C. I. L., II, 27)。ギルドの成員が死んだ場合には、その葬儀がギルドの費用で執り行われ、もし農場主がその奴隷の死体を引き渡さなかった場合には、死体無しでの仮想的な告別式が行われた。プテオリの土地においてのギルドはいずれの場合も公的な性格を持っていて、ゲマインデ団体の形式を真似た諸家族を集めた組織であった。
既に早い時期においてローマの大地主はその配下の手工業者達がまた市場で販売するものを製作するために働くことを承認しており、あるいはよりむしろ、このことは色々な意味で地主にとっての収益源であり、奴隷達に手工業者の技術を学ばせることの目的であった。都市において大地主はそういった産物の販売のための小規模店舗を持っており、その店について大地主は自分の家の息子達や奴隷達を責任者[Institor]にして管理していた 118a)。
118a) 比較する上でもっとも統合された例としては、ロシアのオブロク≪Оброк、ロシア語で賦役や貢納という意味で、農奴に課せられていた義務のこと。≫を課せられていた農奴において同様の状態を見出すことが出来る。
部分的には大地主はこういった者達に対してその店舗を独立採算で営むことを許していた。そのことに関する法律上の概念であるいわゆる adjektizischen Klagen ≪ラテン語で actiones adjecticiae qualitatis, 付随的な資格に基づく訴権、つまりこうした奴隷や息子が行った商売上の不法行為に対して取引相手が実質的な権利者・責任者である大地主を訴えることが出来る権利。「中世合名・合資会社成立史」の中でも連帯責任の議論の中で登場している概念。≫についてはまだ採用されるまでには至っていなかった。中世においての土地に従属している手工業者と、この当時の手工業者との本質的な違いは、古代における大地主の経営が持っていた意味の中に存在しており、それはその当時決して消え去ることがなかったものであり、それが継続して存在したことには次の理由があった。つまり皇帝による有給の官吏を使った国家の行政とまた軍隊の存在が、占有に対してより上位に立っていた、という理由である。そういった占有というものは一旦崩壊し、また至る所でその本来の性質に従って相互に競い合うように地方においての大地主の自治的支配権が確立し、自らリスクを取るようになったに違いないのであるが、――その次の段階が到来し、そこでは占有者達が自らの農場内での工房において自ら武器を鍛造させるようになり、そして大農場経営制による自給自足がそれらの工房を、その地域での権力を掌握するための新しい組織の唯一可能な細胞であるように見せつけるようになるのであり、そこではしかしながら大地主にとって農業的なそして産業的な発展が弱体化してしまい、そして占有者にとっては大土地所有の政治的な意味が再び前面に登場してくるのであるが、一方ではそうした産業上の発展は今やその土地に隷属している手工業者自らが担うことになったのである。
結論
ローマにおける国家意識が、共和国をしてムニキピウムの各ゲマインデ団体の集合としての世界[orbis terrarum]という考え方を意識的に捨てさせることになった。次に長く続いた帝政期には、国家ゲマインシャフトによる狭い地域に限定された愛国主義というものを、有効的な国家の推進力としては排除した。世界市民という考え方は、その本来の性質から、政治的なイデオロギーではなく、宗教的な推進力の根底にあるものとして把握され、また同時に成果をもたらすこととなった。至る所で遅延し、そして財政についての行政上の必要性と混ぜ合わされて一体化した、そういった世界市民という考え方を、単なる理想論から現実的なものにしていこうとする試みは、帝国全体の住民の過半数に対して、その者達をローマの領地と国家的な強制組織の中に併合すること≪カラカラ帝による属州民へのローマ市民権の付与などを言っていると思われる。≫と組み合わされた形で実施された。ただその者が耕作している足元の土塊を、ローマの世界帝国の住民は再び勝ち取ったのであり、そういった土塊がその住人にとって、そこからその者の思考や利害に関係することごとが生み出されるものとして再び把握され始めたのである。新しい発展が引き起こされるためには、領土と地方での権力の両方においてのローマ帝国の没落が必須だったのであり、その発展の過程においては、更にまた古くからの帝国の統一状態というものが、もはや皇帝による課税と行政管理の機構としてではなく、ある種の統一された世界という観念的な像として人々の前に現れて来たのであり、その結果とそれが作用する領域を拡大することが出来たのである。
付記 アラウシオの碑文 C.I.L., XII, 1224
(参照 上記文献への追記部)
上記の文献情報にある以下に掲げる碑文の断片のオリジナルは、全体が失われている碑文の2部分を一つにしたものであるが、元々はヒルシュフェルト≪Gustav Hirschfeld、1847~1895年、ドイツの考古学者≫教授が所有されていたものを氏のご厚意でご提供いただいたものである。私はこの断片についてそのサイズのため、それについてはC.I.L.が情報を付けていないのであるが、ただ概略的なコピーとしてここに掲載したが、それ故にその他の諸点で全くもって正確な複製品ではない。最後の点はテキストが何とか読めることから、そこまでの正確さを期す必要性はないであろう。二番目に右隣にある断片[二つ目の断片]はC.I.L.の追記部からのものであるが、それについてはヒルシュフェルト教授は模写のみを提供されている。この断片の原寸は私には不明である。そのサイズについて考えられることは、次のことが私には非常に確からしいと考えられる。つまりはこの2番目の断片は1番目の断片の右下に元々あったものが欠落した部分だということである。上方の部分の境界内に書いてあるテキストの解読は確実性が高いとは全く言えない。しかしながら私はこの断片上のテキストを継ぎはぎしてみることは試みなかった。というのは私個人ではこの断片の中のそれぞれの領域の面積について論証することが出来ないからである。しかし私が考えたそれぞれの部分の組み合わせ方が正しいとしたら、この碑文は1ケントゥリアの領域をほぼ丸ごと含んでいることになる:S. D. X. C. K. Ex tr. XII. col. XCVIII. (XC. VIII?) Colvarius (col. Varius?) Calid xx. a. IIX. 𐆖[Xに横棒を引いたものでこれは通貨単位のデナリを表す。ちなみにMax Weber im TextのCD-ROMはここを10の1000倍で10000としているが、そうも解釈出来るが全集の注によれば間違い。]. XXVI. n. a. II. XII. Appuleja Paula XLII. a. IIX. 𐆖. …. a. II. XII. Valer. Secundas IV. a. IIX. 𐆖. II.(もちろん次のことは目に付く。つまり横線の下にある左側の部分は右側の部分よりも一列分大きいということである。)長方形の区画部分についてその縦横比は約6 : 5(14 : 11.6 cm)となっており、これはつまり24 : 20 ローマフィートに相当し、偶然ではなく、故意にそうされたもので,何故ならこの略地図上では水道の位置がずらされているように見えるからである。というのはそのような引き方が意図的に引かれたということは、私にはこの断片の左下の部分が全く断片とはなっていないことから疑いようないと思われる。3番目の断片、下にある方はC.I.L.によればそれはただより古い版のものがそのまま使われている可能性があり、テキストが破損しているように思われる。――補完がほとんど試みられていないということはそれ自体当然のことであろう。この断片に書かれたテキストからすれば、この碑文は帝政期の盛期に作られたものであろう;というのはこの測量地図はしかし青銅と亜麻布の上に描かれており、よってこれは単なるコピーであって原本は更にかなり古いものである可能性があるからである。この碑文の解釈にあたっては、その最も重要なことの理解に成功したとすれば、それは属州の植民市での課税状況と、全体の土地の分割の仕方についてであり、a. IIXが3回繰り返し登場しているということが特に注目に値するであろう。人名から始まる部分でそれが10ユゲラの面積を持っているとするならば、それは次のことに適合するであろう。つまりこのケントゥリアはニプススによって言及された240ユゲラの面積のものであり、それは課税対象の土地として規定されたものである(ニプススはこれらの土地を単に”ager scamnatus”として描写している)。これらの土地の全体の面積は、それは先に引用したa または DX とは合致していないが、20+12+42+12+4 = 90 ユゲラとなり、つまりは、この数字が二列目のXC[= 90]の意味するもので、そして次の VIII は次の領域に属するものとすれば、その計算となる。もしかすると a. IIX が意味するのは耕地に対しての現物貢納[octava = 1/8]の率であり、その隣にデナリウス記号の下に書かれた数字によって固定の税額が示されているのであろうと思われ、そして a. II. (arvum secundum [二級の耕地]?) は XII[= 12]の意味であるか、あるいは税が課せられない狭小な土地であろう。a. は “asses”[銅貨]と解釈すべきとモムゼンが主張している。しかしそうでないことは非常に確からしいと思われる。いずれにせよ私の考えでは名前の後に続く数字はその名前の者に割当てられた土地の面積である。≪全集注によればここはモムゼン説よりヴェーバーの見解が正しいとされている。≫左側の[実際の図では下の]ケントゥリアの断片図は、ある者に割当てられた土地が複数のケントゥリアにまたがっていることを示している。モムゼンがこの断片に対して前書きとして補足していることは: ex tributario (scil. agro) redactus in colonicum[植民市の tributario (すなわち土地)から減らされた部分]であり、それはつまりヒュギヌスが203ページ以下で言及しているケースを扱っている図である:つまりローマの測量地図を使った課税対象の農地の分配である。その際にそれぞれ割当てられた土地が異なった面積であるに違いないことは明白である。しかしながら一般的に言って、いずれにせよこの碑文においての数字の記載の仕方から、ここではボニタリー所有権として把握された土地割当てが行われているように想われる(Calidus は XX[= 20] と XXIV [= 24]デナリの税金を課され、Secundusは IV [= 4]と II [= 2]デナリである)。このコピーが作られた目的は同様に不明であるが、他のことと同様に、前述の通り解釈して注記したことは、依然疑わしさを含むものである。
