前回が2022年7月でしたから、約一年半開きましたが、「ローマ土地制度史」の日本語訳の12回目です。その間、自宅を購入し引っ越したり、会社を変わったりで色々と大変でした。ようやく落ち着いたので翻訳を再開します。ここはほとんど ager quaestorius に関する記述です。
===============================================
ager quaestorius の法的な性質については、これまで不十分な形でしか解明されていない。当時の測量人達の情報によれば、それは征服によって獲得された耕地に対して、ローマ市民から財務官(クワエストル)への委任に基づいて売却された土地であるとなっている。しかし私はモムゼンの推定 (C. I. L., I の lex agraria の c. 57. 66)と一致して、ager quaestorius はローマ市民の決定に基づくのではなく、元老院が決定し財務官に委任したものであると考える。更には次のことも想定できよう。それはこのやり方と関連がある trientabula (後述)≪国家債務の返済の際にその金額の内の1/3を現金ではなくそれに相当する価額の土地で返済すること≫のやり方を参考にすると、lex agraria の規定から派生したこととして、その土地の所有権を完全に購入者に与えるのではなく、ただ “uti frui licere”[使用する権利、(貸すなどして)利益を得る権利、売却する権利]だけが約束されている[つまり買い戻す権利が留保されている]ものであるということである。従ってここで扱われているのは、[完全な]売却という行為ではなく、財産管理上の[ある意味で勘定科目の変更のような]行為なのであり、それはケンススを実施する上での[ある土地の]場所の確定という目的にも沿っていた。何故ならば、ager quaestorius は財務官が国家の財産を[一時的に]売却することにより現金を得る形態なのである。それは言い換えれば資本の払い込みに対し使用権を引渡すことであり、ケンスス上の扱いでは、それは賃貸し、つまり使用権を与える代わりに使用料を取るということである。モムゼンが述べているこのことについての理由以外に、またそこからさらに発展させ、私はまた次のことが確かに言えると考える。つまり ager quaestorius は、例えば名目的な承認に基づく使用料(地代)の支払いという観点では、使用料(地代)支払いを義務として強制するような性格のものではない、ということである。それではこの場合、[土地を購入した]ローマ市民に対して継続的な所有権が認められるという[法的な]効果[通常の売却-購入との違い]は、この方式のどこにおいて現れるのであろうか?純粋に私法的な関係においては、所有権の移転[vindikation]と握取行為[物件を移転させる際に契約以外に必要とされる一種の儀礼的行為]が行われない、という点にそれは現れている。国家権力との関係については、再度モムゼンによって示された(C.I.L、上掲箇所)推定と一致するが、次のことが非常に確からしいと思われる:それは ager quaestorius の trientabula との類似ということで、そのようにモムゼンは引用の箇所で主張している。trientabula が最初に行われたのは a.u.c. 552年[B.C. 200年]のことであると、リヴィウスは1. 31の13章で述べている。
”Cum et privati aequum postularent nec tamen solvendo aeri alieno res publica esset, quod medium inter aequum et utile erat, decreverunt, ut, quoniam magna pars eorum agros vulgo venales esse diceret et sibimet emptis opus esse, agri publici, qui intra quinquagesimum lapidem esset, copia iis fieret. Consules agrum aestimaturos, et in jugera asses vectigales testandi causa publicum agrum esse imposituros, ut si quis, cum solvere posset populus, pecuniam habere quam agrum mallet, restitueret agrum populo.” [その市民達の要求は正当であり、そしてそれにも関わらずローマ共和国が要求された金額を支払うことが出来なかったので、元老院は次の処置を行ったが、それは正当性を実現しようとしたのとその場しのぎの中間にあるようなものだった。それは国家の土地で、大部分が公的に売りに出されており、その購入には現金での支払いが必要とされたもので、ローマから50番目の里程標の内側にあるものが、それらの市民に対し[現金で返済する代わりに]与えられることが出来るとされた。コンスルはそういった土地の価額を見積もり、そしてその土地について課税対象として使用料金を定めることとなった。その理由はそれらの土地が元々国家の土地だからである。そしてローマ市民でありローマ共和国への債権者である者の内の誰かが、土地よりも現金を選んだ場合には、その者は土地をローマ市民に返却することが出来た。]
法的な観点で分析した場合、ここでの手続きはつまり次のようなものである。ここで描写されている耕地は、ローマ国家に対する債権者達に後で買い戻すことを前提として売却されている。その土地の売却価格としては、借り入れ金の内未返済のものの1/3の金額が使われており、そこから trientabula [triens = 1/3]という名前で呼ばれた。土地を再度買い取らせる権利を持っていたのはその土地を買った者達だけであり、それもローマの人民がその資金を払うことが出来る場合のみであり、売主である国家がではなく、ローマ人民が、である。このように全くのところ国家の債務の整理を目的とした業務、まあそう言っても構わないであろうが、国家による個人への土地の売却という形を取っている。そしてそれはその法的な本質としては明らかに売却という大きな枠組みの中でのみ行われ、そして個別の特別な事例に適合する協定を取り結ぶことによって、ager quaestorius においての売却のやり方とは異なっていた。その当時債務者であった国庫は、この方法を非常な困窮の中でやむを得ず行ったのであり、だからこそ次のことが理解出来る。つまりこの売却の特殊性が協定という形を取らざるを得なかった理由であり、その場合に買い主は一般的な場合と比べてより有利な形で土地を買うことが出来た、ということである。次のことは自明である。つまり、こういう買い主に対する特別扱いに見出すことが出来るのは、土地の買い戻しを実行させる権利を持っているのは、買い主であって国家ではない、ということである。私見ではその他の場合ではこれは逆であったであろう。この点について考えられるのは、ager quaestorius の本来の法的な特性は、国家に帰属する買戻し権であった、ということである。41) この一度売却した土地の買い戻しの権限は、ローマ法の規定にもある”habere uti frui licere”[所有すること、使用すること、それを使って利益を得ること、それを売却すること]≪元は”habere possidere uti frui licere”であり、 possidere =占有すること、を抜いた形で引用されている≫にも合致している。その規定は公法的には不安定な土地所有というものを言い表した”εχειν εξειναι”[所有すること、占有すること]という S. C. de Thisbaeis ≪引用元は後述される≫の表現と法的には同じである。更に ager quaestorius [の買戻し権]が本来国家に帰属する権利であるということは、次のこととも矛盾しない。つまり、この形での土地の授与の基礎が築かれたのは元老院勧告によってであり、(明らかに)民会の決議によってではない。しかも更に、おそらく次のことも想定出来る。それは国家が所有権を購入という形で移転させるのであり、そのため公的な建造物の贈呈と引き渡しの際には、[それに付随する]余剰の土地は監察官[ケンソル]によって「(公有地から)私有地に転換する」形で売却されたということである。(Liv. AG40 40. 51, 5. cf. 41. 27. 10)しかしながらこの贈呈の手続きについては民会の決議を必要としたので、この場合の[土地の売却の]手続きもまた前もって特別な売却として[法的な]効力を与えられていた。42) いずれの場合でも元老院勧告は国家の所有物[である土地]を、規則に沿った形で完全に私有物化することを認めるまでには至っておらず、一方民会の決議は更に厳格に無条件に売却した土地の買い戻しを定めており、その当然の結果として土地の購入者はその購入の際に支払った金額全額の返還を要求するようになった。このことにより、推定して来た本質的な土地の買戻し権というものが成立しているのである。モムゼンが仮定しているように、ager quaestorius による土地の売却がローマの国庫の一時的な資金需要に応えるものであったとしたら、その場合我々は信用引き受けのこうした原始的な形態を見ると、直接的に中世における金融経済においての Satzung [不動産を抵当に入れた借り入れで、占有を条件とする古質(こしち)とそれを条件としない新質がある]及び買い戻しが前提である土地売却が思い起こされる。中世における諸都市においてと同様に、より洗練されたやり方であるRenteによる借り入れ[地代徴収権売買、レンテンカウフ]がまだ認められていなかった限りにおいて、古代ローマの場合はそれ故特別な場合での資金創造の形態としては次の2つに限定された:強制税(=tributum )と土地の買い戻しを約束した上にで売却するという形態での自然物の質入れである。その他の ager quaestorius による売却のやり方としては、当時の測量人達が述べているように、征服し占領した土地について即時に現金化するやり方もあった。――実際に存在したのは、前述の箇所で確認を試みたのであるが、国家のそのような買い戻し権の方であり、それはそれ自身がある種の土地の強制収用権であり、ager privatus に対して[の公有地化の方法としては]それ以外のものは知られていなかった。――そして植民市の耕地についてである限りは、例えば水道を設置するという目的等で行われたに違いなく、[ローマ法の]建築に関する法規の中で特別な権利として留保された。その例としては lex colon[iae] Genetivae c. 99 (Eph. epigr. II, p.221f.)があり、――そして次のことが考えられる。つまり何かの代償と引き換えによる、三頭政治の時代における強制収用が、ある場合はこの ager quaestorius において生じた[買い戻しの]権限に関連付けられ、また別の場合には古くからのやり方である占有による所有の不確実性に関連付けられた。そして後者の場合は、強制収用は統治者[三頭政治の政治家]の特別に完全な権力により、それによって収用された土地は ager privatus per nefas [違法な私有地]へと転換されたのである。43)
41) ルドルフ[Rudorff, Adolf]は(Gromatischen Institutionen の中で)次のことを仮定している。つまり国家は購買しようとする者との関係に応じて、それぞれ異なる内容の協定を締結していたと。売却対象の耕地のみが、我々には唯一の統一された制度として把握される。
42) Liv. 40, 51, 5 の場合は”M. Fulvius … locavit … basilicam … circumdatis tabernis, quas vendidit in privatum” [M. フルヴィウスは…契約した…その会堂を…その周りにある小さな建物については、私有物化する形で契約した]という箇所は、つまりある国家の所有物の譲渡が民会の決議無しに行われており、またそこに見出されるのは、その建築物の敷地については建物を譲渡する前に始めて購入されたのであり、その建造物の完成と譲渡の認可を得るまでの過程において、敷地については売却側の役所がそれを自由に処分出来るものであったと思われる。Liv. 41, 27, 10については、譲渡に際して in privatum [私有物化された]とは書かれておらず、おそらくそれは実際にそうであったのであろう。
43) 三頭政治の時代の土地の強制収用の法的根拠は、それが[征服した]敵の所有物を没収するのではない場合にははっきりしない。そういったケースの一部ではそもそも法的根拠がまるで存在しなかった。強制収用が如何に容赦なく行われたかをもっとも良く示しているのは Siculus Flaccus (p.160, 25)の注記である:ある数の土地占有者は公的な宣告を受けて[zur professio]その占有地を召し上げられた。その表向きの理由は土地の[再]割当てとケンススへの登記である。しかしそれが宣告された後に、その土地の占有者は宣告に基づいてその土地の税金相当額が支払われた上で没収された。その没収について裁判となった場合にも、それは結局[没収した側に]罰金刑が言い渡されるだけであり、その金額は当初の宣告の際のその土地の評価額に一致していた。ここではただ強制的な購買について述べられているのであり、また別の土地占有者への補償について言及されている箇所では、その補償自体が問題とされている。こうした土地の占有者に関しては、測量人達の間では、以前グラックス[兄弟の兄]が使った表現である「以前の占有者」[vetus possessor]が思い起こされていた。(C. Ⅲ 参照)

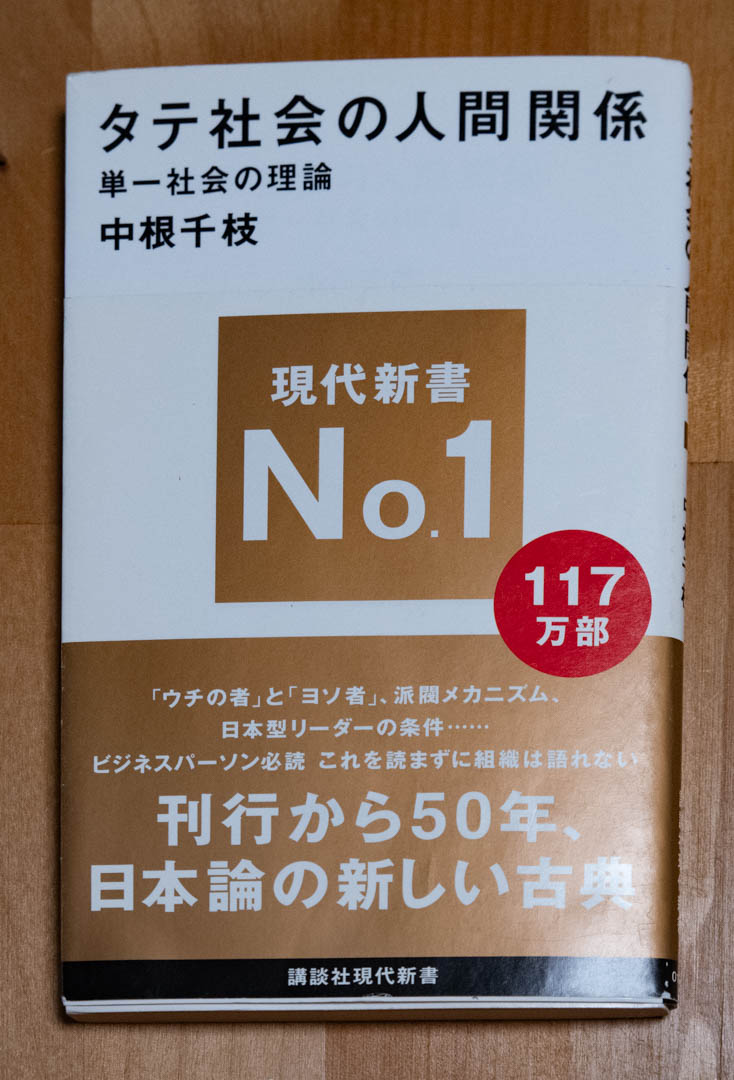
 佐藤俊樹の「社会学の新地平 ――ウェーバーからルーマンへ」を読了。この本を読んだのは、どうも私が日本語訳した「中世合名・合資会社成立史」を読んだ上で議論している様子が伺い見えたからです。そしてそれはその通りで、「プロテスタンティズムの倫理の資本主義の精神」を理解する上に、ヴェーバーの会社制度の研究を考慮に入れなければならない、という主張が含まれており、そういう風に活用していただけると訳した方としても張り合いがあります。また「丁寧で精度の高い日本語訳」(P.117)とお褒めの言葉もいただいているので、その点については感謝したいと思います。
佐藤俊樹の「社会学の新地平 ――ウェーバーからルーマンへ」を読了。この本を読んだのは、どうも私が日本語訳した「中世合名・合資会社成立史」を読んだ上で議論している様子が伺い見えたからです。そしてそれはその通りで、「プロテスタンティズムの倫理の資本主義の精神」を理解する上に、ヴェーバーの会社制度の研究を考慮に入れなければならない、という主張が含まれており、そういう風に活用していただけると訳した方としても張り合いがあります。また「丁寧で精度の高い日本語訳」(P.117)とお褒めの言葉もいただいているので、その点については感謝したいと思います。