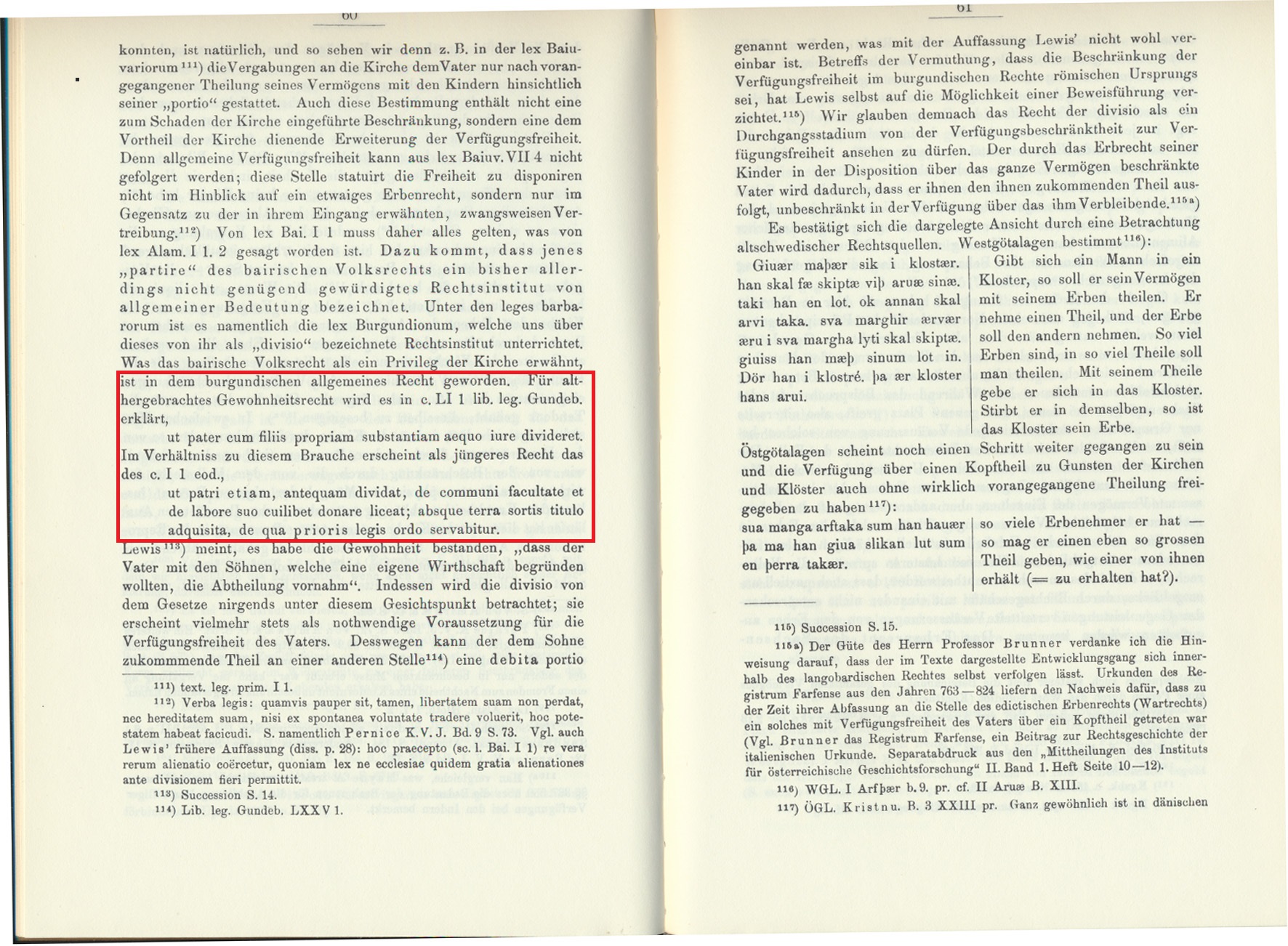ドイツ語原文の第20回目です。
================================================
2. Persönliche Haftung der Genossen.
Dies ist also Haftung des gemeinsamen Vermögens und Haftung der Genossen mit ihrem Anteil an demselben füreinander, noch nicht direkte Beziehung der Schuld eines Genossen auf den andern als Selbstschuldner.
Den Unterschied beider finden wir deutlich erkannt in den Statuti del paratico e foro della Università de’ mercatanti von Bergamo (revid. 1479, der Inhalt ist älter, Ausg. v. 1780):
c. 92: … quod patres et filii masculi … et fratres stantes ad unum panem et vinum … talium fugitivorum teneantur et obligati sint creditoribus in solidum et contra eos procedi possit … realiter tantum … sed si intromiserint se de negociatione, tunc … teneantur sicut eorum ascendentes pp.
Also: die Schuld eines Genossen an und für sich macht die anderen noch nicht zu Schuldnern, sondern belastet nur — „realiter“ — das gemeinsame Vermögen.
Es kommt uns aber gerade auch auf die persönliche Haftung an. Die Haftung der Sippschaftsgenossen war eine solche, und ebenso wird sich zeigen, daß es die Haftung der Hausgenossen und später der socii der offenen Gesellschaft auch in ihren frühesten Gestaltungen stets gewesen ist.
Es ist keineswegs ohne weiteres zulässig, auch diese persönliche Haftung auf die Beziehung der Genossen zu dem gemeinschaftlichen Vermögen juristisch zu fundieren; wenn insbesondere Sohm in der soeben erscheinenden Abhandlung 32) aus dem Prinzip der gesamten Hand, welches diesen Gemeinschaften zugrunde liege, die „Schuldengemeinschaft“ der Genossen, als Korrelat der Erwerbsgemeinschaft, ableitet, so soll der Verwertung des Gesamthandsbegriffs an dieser Stelle nicht entgegenzutreten versucht werden 33), indessen würde zunächst logisch doch zu postulieren sein, daß diese Schuldengemeinschaft sich eben auch nur so weit erstrecke, wie die Erwerbsgemeinschaft, d.h. eben auf das Vermögen, welches gemeinsam war und gemeinsam wurde. Darüber aber geht die Solidarhaftung gerade grundsätzlich hinaus. Wenn ferner Sohm das Mitglied der Gesamthand in Ausübung eines ihm, als Mitglied, zuständigen Verwaltungsrechts [“] handeln läßt, so ist dies, auf unsere Fälle angewendet, für die Erklärung der Belastung des gemeinsamen Vermögens in späterer Zeit und bei der heutigen offenen Handelsgesellschaft wohl verwertbar; ist indessen die im folgenden versuchte Darstellung richtig, wonach die Beschränkung der Haftung auf die „für das Geschäft“ geschlossenen Kontrakte eine zwar im Wesen der Sache liegende notwendige, aber doch erst historisch entwickelte Einschränkung der alten unbedingten Haftung bedeutet, so ist die Anwendbarkeit jener Formulierung für diesen älteren Rechtszustand, die historische Grundlage des späteren, nicht unbedenklich (wo bleibt dabei die Haftung für Delikte?). Vollends ist sie, soweit die persönliche Solidarhaftung in Frage kommt, zu beanstanden: aus einem „Verwaltungs“-Recht können Konsequenzen logisch doch nur für das verwaltete Vermögen eintreten 34). Es ist daran festzuhalten, daß bei der Haushaltsgemeinschaft nicht sowohl das etwa vorhandene gemeinsame Vermögen, als die damit von alter Zeit her verbundene Arbeitsgemeinschaft, die Gemeinschaft des gesamten Erwerbslebens 35), ein in der Tat wohl „personenrechtlich“ zu nennendes Verhältnis, das Maßgebende war, und dies Moment findet sich auch bei den späteren Gestaltungen bis zur heutigen offenen Handelsgesellschaft wieder und bildet den wesentlichen Gegensatz gegen die Kommanditverhältnisse.
32) Die deutsche Genossenschaft, aus der Festgabe für Windscheid.
33) Cf. den Schluß.
34) Cf. Sohm S.30: „die Gewalt, über die Vermögensanteile auch dieser (der anderen) Mitglieder zu verfügen“.
35) Dies ist auch die Auffassung der zeitgenössischen juristischen Literatur. Baldus, Consilia III 451.
Ursprung und Entwickelung der Haftung der Hausgenossen.
Die persönliche Haftung der Genossen knüpft nun in den Quellen gerade an den mehr oder weniger deliktartigen Fall des Konkurses an. Es ist nicht ausgeschlossen und — etwas Bestimmteres nach der positiven oder negativen Seite hin kann nicht behauptet werden — es spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Erinnerung an die alte Haftung der Versippten füreinander von Einfluß auf die Rechtsbildung gewesen ist bzw. dieselbe erleichtert hat. Aber mehr auch nicht. Die Entwicklung selbst hat sich zweifellos außerhalb der Sippschaftsgedanken vollzogen und erst, als das verwandtschaftliche Moment nicht mehr geeignet war, eine Rolle zu spielen. Der eine Gedanke war nicht „aus dem anderen hervorgegangen“, sondern an seine Stelle getreten. Wie in den Gemeindeverhältnissen an Stelle der sippschaftlichen Genossenschaft die lokale Flurgemeinschaft auf Grundlage der Vizinität trat, welche bei der Besiedlung vermutlich regelmäßig mit jener koinzidierte, so hier an Stelle der Familie deren für das Geschäftsleben wichtigste vermögensrechtliche Eigentümlichkeit, der gemeinsame Haushalt und die Gemeinschaft des Erwerbslebens. Daß der neuere Grundsatz sich aus dem älteren entwickelt habe, kann nicht erwiesen werden und ist schwerlich eine zutreffende Kennzeichnung der Veränderung. Der vicus enthielt vermutlich nie ausschließlich Sippschaftsgenossen, der gemeinsame Haushalt war sicher nie ein ausschließlich bei Versippten vorkommendes Verhältnis. Dort hat die definitive Seßhaftwerdung und die Art der agrarischen Wirtschaft, hier die Art, wie das Erwerbsleben der Gemeinschaften in den Städten sich äußerlich gestaltete, andere und neue Grundlagen, welche ihrem Wesen nach von den alten prinzipiell differierten, an die Stelle der letzteren gesetzt 36).
36) Die Formulierung des Verhältnisses bei Lastig erscheint mir hiernach nicht durchweg annehmbar.
Daß nun die Haftung der Hausgenossen im älteren Recht eine prinzipiell unbeschränkte war, geht schon daraus allgemein hervor, daß die Richtung der statutarischen Rechtsentwicklung andauernd auf Beschränkung dieser Haftung ging. Daß dem so war, lag in den Verhältnissen. Ein volles Einstehen des einen Genossen für den anderen hatte in alter Zeit, bei primitiven Handels- und Kreditverhältnissen, nichts Bedenkliches; die damals vorkommenden Verbindlichkeiten des einzelnen gingen ebenso selbstverständlich zu Lasten der gemeinsamen Kasse, wie etwa heute der Hausvater die Krämer- und Handwerkerrechnungen der Familienglieder mit oder ohne Murren begleicht; die Konsequenz des Lebens auf gemeinsamen Gedeih und Verderb ist eben, daß die Kontrakte eines alle angehen 37).
37) Das Constitum Usus Pisene civitatis definiert die häusliche Gemeinschaft: „si de communi in una domo vixerint et contractus et similia communiter fecerint, sive absentes sive praesentes, sive uno absente, altero praesente etc.“
Schwerlich hat, das ist zuzugeben, das Rechtsbewußtsein dabei in älterer Zeit zwischen den beiden prinzipiell verschiedenen Gedanken: Haftung des gemeinsamen Vermögens und Haftung aller Genossen, stets geschieden 38). Die Unterscheidung lag fern, solange die Vermögensgemeinschaft eine im wesentlichen vollständige war. Dagegen mußten — und im Verhältnis nach außen noch mehr als unter den socii — Schwierigkeiten entstehen, als mit wachsender Bedeutung des Kredits die Schuldverbindlichkeiten des Einzelnen einen Charakter gewannen, welcher die Haftbarmachung der Genossen für dieselben lediglich auf Grundlage des gemeinsamen Haushalts häufig unbillig erscheinen ließ. Andererseits war gerade die unbedingte Haftung geeignet, die Gemeinschaft im Geschäftsleben, als Kreditbasis, aktionsfähig zu machen. Diese Kreditwürdigkeit wäre auch bei Beschränkung der Haftung auf den Betrag des Anteils des Einzelnen — ein sonst naheliegender Gedanke — aufgegeben worden. Für die Fälle, in welchen das Interesse des Kredits der Gemeinschaft überwog, mußte also die Haftung festgehalten werden. Wie löste die Rechtsentwicklung dies legislatorische Problem?
38) Soweit dafür juristisches Verständnis vorhanden war, betrachtete man letzteres als juristische Konsequenz des ersteren, so Baldus, Consilia V 125: die socii sind verhaftet, weil das corpus societatis, das Gesellschaftsvermögen, verhaftet ist.