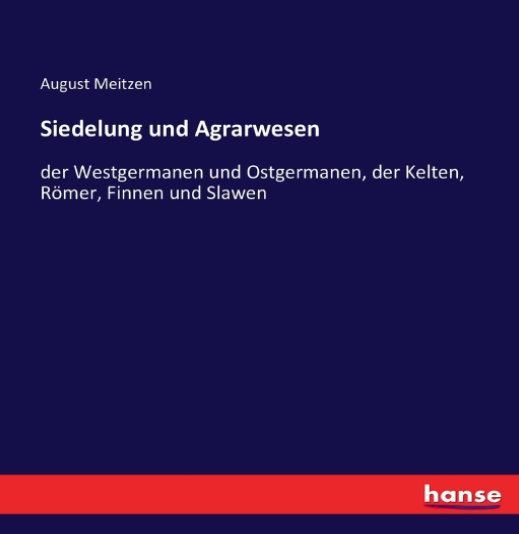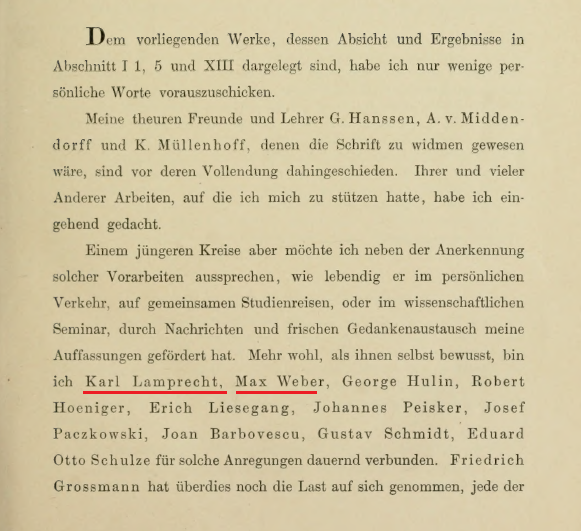「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第42回です。今回も、ager privatus vectigalisque についての議論が続きます。この「私有地」と「(地代付きの)公有地」という曖昧な性格を持っている土地がヴェーバーの興味を惹いてヴェーバーがある意味乗って筆を進めている箇所のように思えます。
ヴェーバーも言及していますが、土地というのはそれを持っているだけでは、今の日本でも固定資産税がかかるだけのある意味負の資産であり、農地を除けば、自宅を建ててそこに住む、賃貸住宅や商業ビルなどを建ててそこから家賃を得る、そこまでお金がなければコイン駐車場にする、コインランドリーを作る、コンテナ倉庫にするなどでお金を得る手段を模索する必要があります。
==================================
同様に次のこともまた何より不可思議なことであろう。それは国家によって永代賃借人として認められた者で、全くその永代賃借料を支払わない者が存在していたに違いない、と仮定することである――というのは永代賃借人というのは法律が規定するところの ager privatus vetigalisque の占有者であったろうからであり、もしこの土地の法的な性質を市民の権利としての売却可能性が与えられない形の永代貸借と仮定する場合は、賃借料がただ名目的なものかどうかという検討は無意味になるからである 55)。
55) 先の箇所(第1章)でもここでも次のことが確からしいと想定される。それは通常の ager quaestorius は「事実上は」売却において制限が加えられていなかった、ということである。このことについての本質をより明らかにする必要がある。法的には ager quaestorius は ager publicus におけるある所有状態であり、他の全ての所有状態と同じく「所有し、占有し、使用し、そこから利益を得ること」が許されているが、握取行為による売却や占有状態以外に関する物権的な訴訟は許されていなかったのであり、そして行政上の保護下にだけ置かれるのみであり、その≪譲渡・売却の≫承認についてはおそらくは執政官の管轄だったのであろう(Liv. 31, 13によれば trientabula の土地の授与の承認も執政官が行っていたからである)。というのも国家にとってその土地が誰の所有物になるのかということへの利害関心は、trientabula の場合においてすら存在していなかったのであり、そのためそういった行政上の保護は一般に次のような者に与えられたのである。その者とはその場所を正規の書面以外を根拠として――つまりそれ以外の正当と見なされる理由に基づく引き渡しによって――やはりその前の不当にその土地を得たのではない所有者から獲得したそういう者である。しかしこのことがただ不安定な状態であるとのみ見なすのは困難であり、それは測量人達が ager quaestorius においての emtio venditio [獲得と引き渡し、売却]の形での売却を、規則的に行われているものとして言及していることからも分かる。ヒュギヌスが次のように注記している場合には:non tamen universas paruisse legibus quas a venditoribus suis acceperant [それにもかかわらず彼らの全員が売却者から受け取った土地について必ずしも法の定めるところに従っていた訳ではなかった]、その場合には≪正式な購買にいよる土地のケンススへの登録ではなく≫何かの土地の利用についての届出や何か類似のことが行われていた、と理解出来よう。――そういう意味で ager quaestorius の「売却可能性」は理解することが出来、またそう確認されなければならない。しかしこうした制限付きであっても、私には売却が実際に行われていたことについては疑いようがない。何故ならば ager queaestorius の譲渡不可という原則に固執することは、そこに貸借料が課されていないのであれば、それに対して≪国家の≫実際的な利害関心が存在したということはほとんど信じ難いからである。しかながらもちろん、こういった ager queaestorius の ager privatus vectigalisque との差異は法学原理から作り出されたものではなく、ただ実務的なものとして徐々に形成されたものである――注56a)を参照。
永代貸借権について後の売却可能性
永代貸借権の法律上の売却不可、という特徴がそもそも本当に行われていたのか、あるいは行われていた場合にはどのくらいの期間に渡ってそうであったのかについては、確かなことは分かっていないが、後の時代にはそういう禁止は無くなっており、というのは帝政期の法資料の中でそれについての記載が見られないからであり、そしてコンスタンティヌス大帝の下で売却の許可が確立したように見える。私見ではテオドシウス法典のある解釈に基づくテキストの p.186 ≪全集の注によれば正しくは p.97≫がこのことを規定しており、その部分からまた同時に分かることは、賃貸料支払いの義務のある土地区画の握取行為による譲渡はその時までは許可されていなかった、ということである。何故ならば ager queaestorius の土地の売却について課税上の利害関心を扱っている箇所については、それ以外では scamna 56) の売却については特別に詳しく規定する必要性を感じていなかったように思われるからである。
56) ここでは scamna =地代の支払い義務のある土地区画、の意味で使われており、それはケンススとの関連を示しているのであり、ケンススという語がこの規定が含まれている章のタイトルに含まれている。ここでは2つの種類の土地区画が扱われている:一つは握取行為によって譲渡可能なものであり、市民への課税を決定する国家のケンススに登録されるものであり、もう一つは個別の土地で、その土地の使用に対して税≪貸借料≫が課されるものである。しかし売却に関しての二つの実質的な違いは:前者の土地については所有権が握取行為によってケンスス上の登記を変更するという形で移転し、引き渡しについてはただ所有権移転の実施だけが行われ、それはつまりある通知で、その通知の内容としては握取行為に該当する面積の土地が、今や購入者の自由な処分に供される、ということである;こういった”vacuae possessionis traditio”[実質を伴わない形式的な所有状態の引き渡し]は、根本的には訴訟に備えたものではなく、それによって所有状態の保護を得るという意味だけを持っていた。それに対して scamna、つまり握取行為による譲渡が出来ない土地の場合は、引き渡しはただ所有権移転の具体的な行為だけであり、つまり前述した emtio venditio[購入-引渡し-売却]であって売却代金についての債務から発生する行為であった。法のこの部分が次に規定しているのは、既に前述の箇所(第2章)で詳しく論じたが、今後は握取行為によって売却しようとする土地の面積の、売却に先立つ測量または境界線に関しての通知を行うことを義務付けていることで、そしてこの規定によって握取行為が本来持っていた古くからの性質である、ただ割当てられた面積のみの売却、という性質を取り除いたのである。scamna の場合にはこういった視点に基づく規定は見られないが、というのは同意に基づく emtio[購入と引き渡し]は何らの所有権の移転を含んでいなかったからであるが、しかし同一の原則が――間違いなくコンスタンティヌス大帝によって――ここでも適用されるべきとされたのである。
推測されること、あるいはむしろ確かであるとさえ言っても良いことは、後の時代の同意に基づく emtio venditio と最終引渡しという流れによる売却の通常の形式は、場所の獲得の形式として一般的なものになっており、≪クイリーテース所有権≫より劣位の権利を持った所有状態について全体において唯一の売却形式だったのであり、その権利についての一般的な売却可能性は行政当局の裁量に基づくものとなっていた、ということである。。
その当時の人々は次のような内容を規定として定めていたに違いない。つまり「売却対象からの除外」というのはこの場合単純に次のことと同じ意味なのであり、それは握取行為からの除外であり、正規の訴訟手続において物権として正規の所有権が認められていない土地に対して保護が与えられない、ということであり、つまりは売却に対しての「法」規範の欠如を意味するのであり、そのためにこの売却が行政当局の実務で扱われるものである、ということは、それをどういった前提条件から導くべきなのか、あるいはそもそもそういう前提条件が存在するのか、という問題であった。「法的な」意味での売却性が認められるようになるのは次の時点からである。それは行政での実務上の原則が法としてきちんと確立する時点であり、そういった諸々の状況がもしかすると ager quaestorius の状況だったのであろう 56a)。
56a) モムゼン(C. I. L. Iの土地改革法の箇所)は、ager privatus vectigalisque の売却性をZ. 54. 63 においての表現から結論付けている:”cujus ejus agri hominis privati venditio fuerit”[その土地が私有のものであってそれが売却されていた場合]。私はこの表現はむしろ次のことを意味しているのではないかと考える。つまりこの法が売却に関しての何かの「特別な」意味を示しているということで、――もしかすると後の時代の Emphyteusis ≪土地の長期または永久貸借≫に似たようなもの――を意味していたのではないかと。この法がまたこの形式の耕地に対する権利の有効化について別に何らかの原則を定めていたかどうかは不明である。Z.93 での”in ious adire”[法的権利を主張する]という表現はおそらくはまさしくこのすぐ前の箇所にて言及した”ager ex senatus consulto datus assignatus”[元老院決議に基づく土地割当て]に関しての表現と思われる。この表現が具体的な耕地との関連で意味することを、モムゼンは引用済みの箇所でそれを公有地占有の形の土地についての表現と見なしている。この ex senatus consulto による土地に関する記述は、viasii vicani が出て来る箇所よりも先であるので、私は次の考え方はそう間違っていないと思う。つまりこの表現は先に既に述べた navicularii の耕地について言っているのではないか、ということである。この法にてこの部分に続く箇所では、ひょっとすると後の時代ではしばしば皇帝の命令によって出された業務である、非常に負担の重い農作物の輸送義務について述べているのかもしれない。
地税の中での vectigal の変遷
法律上の売却性という点について、地税の一種という分類においての vectigal の永代貸借料に関する規範という性格は変動していた。もちろんこの売却性というのはアフリカにおいての所有者達においては、もし私が先に述べた見解が正しいなら≪執政官 Ahenobarbus の時の lex censoria がアフリカでの賃借耕地からの収益に関して規定しているという見解≫、次のような我々が慣れ親しんでいる課税方法とは異なっている性格も持っており、つまり≪我々が親しんでいるように≫土地区画あたりの収穫高に応じて土地に課税上の等級を設定するのではなく、その土地の合計面積、つまり総ユゲラ数に応じて、均等にかあるいは耕地、牧草地、森林などについてそれぞれに大まかな税率が設定されて課税されていた。ここにおいてようやく公有地の価額の査定においての綿密に検討された行政上の技術が登場して来ているのであるが、それは単に定量的なもので根本原則的なものではなかった。もしかすると既にカンパーニャ地方の土地において――正確なものではなかったにせよともかくも推進された――譲渡金額についての査定と個々の区画に対しての決定についての何らかの手続きが行われていたのかもしれない。少なくとも測量地図の作成と”pretium indictum”[公示価格]はヒュギヌスの印刷本の p.121 に出て来る表現である”certa pretia”[固定価格]を思い出させるものである。この固定価格という表現は同じ本の p.119 との関連でどちらも同じケースを扱っているが、トラヤヌス帝の時代においてパンノニアにおける≪退役兵士への≫譲渡の対象とする土地に対して、次の6種の分類が行われていた:arvum primum[第1級の平地]、arvum secundum[第2級の平地]、pratum[牧草地]、silva glandifera [木の実が採取出来る森林地]、silva vulgaris [その他の森林地]、pascua [(共同の)放牧地]である。一人一人に割当てられた土地の面積である――66 2/3、80、100 ユゲラについては――それらの面積の土地が常にただ一つのこれらの課税クラスのどれかでなければならない、という考え方はされておらず、それよりむしろそれぞれの割当て地の税の総額が計算され、その計算はその土地の各部分での分類上のクラスで決められていた「それぞれのユゲラあたりの単価」 X 「それぞれに該当するユゲラ数」、の総計という形で行われていた。測量地図上には各割当て地について、その土地の中の arvi primi ≪arvum primum の複数形≫が何ユゲラ、prati が何ユゲラ、といった風に記載され、その情報に従って各クラスによって固定されていたユゲラあたりの税額を使って、その割当て地の合計税額は簡単に計算することが出来た。ではもし土地所有者がその土地の利用方法を≪例えば農耕から牧畜に≫変更した場合、その場合でも税額の総額は同じままであっただろうか?もし近代的な意味での土地税の話をしているのであればこの問いに対しての答えは間違いなくイエスであろう。しかしここで課されている賦課については次のことを考慮することが必要であろう。つまり歴史的にはこの賦課の制度は永代貸借の規範の中間形成段階から、それが最終的に確定した段階へと発展し変化し続けていた、ということである。そういった状況に即して考えてみれば、次のことは全く首尾一貫していると言えるだろう。それはその土地の利用方法が変わる度に、賃借料もそれぞれの土地の分類に従って総額が変更された、ということである。賃借人の土地の利用方法の変更による賃貸料収入の減少リスクに対しては、≪民間の≫賃貸し人もその立場での国家も次の手段でそのリスクを回避しようとした。それはその種の土地利用の変更について、賃借人がローマの規則一般にほぼ従わざるを得なかったという状況を利用して、土地利用の変更をさせないようにする≪圧力をかける≫、というやり方によってである――そのことについては最終章で再度扱う――そしてまた属州の住民に対して、代々の皇帝は周知のように次の権利を当然のものとして保持していた。つまりその住民達に対して土地利用の内の一定の種類のものをイタリアの土地全体の所有者としての利害関心からそれを禁止することが出来る、という権利である。それ故に次のことは全く可能であったであろうし、またもしかすると実際にはもっとも広く行われたケースであったかもしれないのであるが、個々の土地からの賃借料の額は、ヒュギヌスが記しているように、それぞれの利用方法の違いに応じて≪固定額として≫土地台帳に記入されたということであり、そして土地の利用の仕方、つまりワイン作りのためのぶどう畑などとして利用された面積のユゲラ数こそが、本質的にはヒュギヌス(既引用分)が言及しているように土地の占有ということの本質的な内容だったのである。しかしながらそういった土地利用の仕方の変更の禁止が行われていたとしても、それはいずれにせよただ経過的な措置に過ぎなかった。何らかの理由で起きたかもしれないある耕地の一部分についての利用の中止は、間違いなく税金の軽減の理由としては決して認められなかった。arvum primum と secundum といった土地の分類は、その土地の収穫「可能高」に基くその土地からの継続的な税徴収を意味していたし、そしてこうした分類基準については時間の経過に従いその分類を増やすという形で更に細分個別化されていったのであり、それについては後で論じる通りである。