 ここの所、宗教社会学研究の準備として、旧約聖書やクルアーン、そして神道の本などを読んでいますが、その関連で清水俊史の「ブッダという男 ――初期仏典を読みとく」というのも読了しました。ところがこの本の後書きにとんでもないことが書いてあって、この著者がある本を出そうとし、その中である有名な仏教学者の説を批判していたところ、その学者とその指導教官から呼び出しを受け、本を出せば大学教官の職に就けないようにする、と脅かされたそうです。折原浩先生が日本の学者が論争しないことを嘆かれていますが、論争しないどころか裏でそんなまさしくアカハラをやっているということに暗澹たる思いでした。
ここの所、宗教社会学研究の準備として、旧約聖書やクルアーン、そして神道の本などを読んでいますが、その関連で清水俊史の「ブッダという男 ――初期仏典を読みとく」というのも読了しました。ところがこの本の後書きにとんでもないことが書いてあって、この著者がある本を出そうとし、その中である有名な仏教学者の説を批判していたところ、その学者とその指導教官から呼び出しを受け、本を出せば大学教官の職に就けないようにする、と脅かされたそうです。折原浩先生が日本の学者が論争しないことを嘆かれていますが、論争しないどころか裏でそんなまさしくアカハラをやっているということに暗澹たる思いでした。
その関連で折原浩先生の批判を読み直していたのですが、ただ先生の批判にも問題と限界を感じました。それは論争しない学者を、学者にももとる、といった道義的・個人的な批判に終わっていることです。折原浩先生から大学でデュルケームの「自殺論」について学びましたが、そこで一番目からうろこが落ちた思いだったのが、冒頭の個人の性格の問題と考えられがちな自殺が実は巨視的に統計をからめて眺めれば、立派な社会現象である、ということでした。社会学であるならば、日本の学者が論争しないことを非難するだけではなく、それがどういう社会構造・社会風土に関連しているのかを分析し、個人の努力だけでなく社会として改善していくのにはどうしたらいいか、という方向に発展させるべきと思いますが、実際は残念ながらまるで進んでいません。古来からの日本論で、アメリカのルース・ベネディクトの「菊と刀」、土居健郎の「甘えの構造」、中根千枝の「タテ社会の人間関係」に匹敵するような日本社会論・日本人論を日本の社会学者が出したという例を私は寡聞にして知りません。また最近ビジネスの世界では非常に有名になった「心理的安全性」も提唱者のエドモンドソンは組織行動学・心理学者ですが、その内容はまさに社会学が扱ってしかるべきものだと思います。上記の清水俊史の例で見る限り、日本でもっとも心理的安全性の無い組織がアカデミズムの世界なんでしょうけど。
ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳(42)P.244~247
「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第42回です。今回も、ager privatus vectigalisque についての議論が続きます。この「私有地」と「(地代付きの)公有地」という曖昧な性格を持っている土地がヴェーバーの興味を惹いてヴェーバーがある意味乗って筆を進めている箇所のように思えます。
ヴェーバーも言及していますが、土地というのはそれを持っているだけでは、今の日本でも固定資産税がかかるだけのある意味負の資産であり、農地を除けば、自宅を建ててそこに住む、賃貸住宅や商業ビルなどを建ててそこから家賃を得る、そこまでお金がなければコイン駐車場にする、コインランドリーを作る、コンテナ倉庫にするなどでお金を得る手段を模索する必要があります。
==================================
同様に次のこともまた何より不可思議なことであろう。それは国家によって永代賃借人として認められた者で、全くその永代賃借料を支払わない者が存在していたに違いない、と仮定することである――というのは永代賃借人というのは法律が規定するところの ager privatus vetigalisque の占有者であったろうからであり、もしこの土地の法的な性質を市民の権利としての売却可能性が与えられない形の永代貸借と仮定する場合は、賃借料がただ名目的なものかどうかという検討は無意味になるからである 55)。
55) 先の箇所(第1章)でもここでも次のことが確からしいと想定される。それは通常の ager quaestorius は「事実上は」売却において制限が加えられていなかった、ということである。このことについての本質をより明らかにする必要がある。法的には ager quaestorius は ager publicus におけるある所有状態であり、他の全ての所有状態と同じく「所有し、占有し、使用し、そこから利益を得ること」が許されているが、握取行為による売却や占有状態以外に関する物権的な訴訟は許されていなかったのであり、そして行政上の保護下にだけ置かれるのみであり、その≪譲渡・売却の≫承認についてはおそらくは執政官の管轄だったのであろう(Liv. 31, 13によれば trientabula の土地の授与の承認も執政官が行っていたからである)。というのも国家にとってその土地が誰の所有物になるのかということへの利害関心は、trientabula の場合においてすら存在していなかったのであり、そのためそういった行政上の保護は一般に次のような者に与えられたのである。その者とはその場所を正規の書面以外を根拠として――つまりそれ以外の正当と見なされる理由に基づく引き渡しによって――やはりその前の不当にその土地を得たのではない所有者から獲得したそういう者である。しかしこのことがただ不安定な状態であるとのみ見なすのは困難であり、それは測量人達が ager quaestorius においての emtio venditio [獲得と引き渡し、売却]の形での売却を、規則的に行われているものとして言及していることからも分かる。ヒュギヌスが次のように注記している場合には:non tamen universas paruisse legibus quas a venditoribus suis acceperant [それにもかかわらず彼らの全員が売却者から受け取った土地について必ずしも法の定めるところに従っていた訳ではなかった]、その場合には≪正式な購買にいよる土地のケンススへの登録ではなく≫何かの土地の利用についての届出や何か類似のことが行われていた、と理解出来よう。――そういう意味で ager quaestorius の「売却可能性」は理解することが出来、またそう確認されなければならない。しかしこうした制限付きであっても、私には売却が実際に行われていたことについては疑いようがない。何故ならば ager queaestorius の譲渡不可という原則に固執することは、そこに貸借料が課されていないのであれば、それに対して≪国家の≫実際的な利害関心が存在したということはほとんど信じ難いからである。しかながらもちろん、こういった ager queaestorius の ager privatus vectigalisque との差異は法学原理から作り出されたものではなく、ただ実務的なものとして徐々に形成されたものである――注56a)を参照。
永代貸借権について後の売却可能性
永代貸借権の法律上の売却不可、という特徴がそもそも本当に行われていたのか、あるいは行われていた場合にはどのくらいの期間に渡ってそうであったのかについては、確かなことは分かっていないが、後の時代にはそういう禁止は無くなっており、というのは帝政期の法資料の中でそれについての記載が見られないからであり、そしてコンスタンティヌス大帝の下で売却の許可が確立したように見える。私見ではテオドシウス法典のある解釈に基づくテキストの p.186 ≪全集の注によれば正しくは p.97≫がこのことを規定しており、その部分からまた同時に分かることは、賃貸料支払いの義務のある土地区画の握取行為による譲渡はその時までは許可されていなかった、ということである。何故ならば ager queaestorius の土地の売却について課税上の利害関心を扱っている箇所については、それ以外では scamna 56) の売却については特別に詳しく規定する必要性を感じていなかったように思われるからである。
56) ここでは scamna =地代の支払い義務のある土地区画、の意味で使われており、それはケンススとの関連を示しているのであり、ケンススという語がこの規定が含まれている章のタイトルに含まれている。ここでは2つの種類の土地区画が扱われている:一つは握取行為によって譲渡可能なものであり、市民への課税を決定する国家のケンススに登録されるものであり、もう一つは個別の土地で、その土地の使用に対して税≪貸借料≫が課されるものである。しかし売却に関しての二つの実質的な違いは:前者の土地については所有権が握取行為によってケンスス上の登記を変更するという形で移転し、引き渡しについてはただ所有権移転の実施だけが行われ、それはつまりある通知で、その通知の内容としては握取行為に該当する面積の土地が、今や購入者の自由な処分に供される、ということである;こういった”vacuae possessionis traditio”[実質を伴わない形式的な所有状態の引き渡し]は、根本的には訴訟に備えたものではなく、それによって所有状態の保護を得るという意味だけを持っていた。それに対して scamna、つまり握取行為による譲渡が出来ない土地の場合は、引き渡しはただ所有権移転の具体的な行為だけであり、つまり前述した emtio venditio[購入-引渡し-売却]であって売却代金についての債務から発生する行為であった。法のこの部分が次に規定しているのは、既に前述の箇所(第2章)で詳しく論じたが、今後は握取行為によって売却しようとする土地の面積の、売却に先立つ測量または境界線に関しての通知を行うことを義務付けていることで、そしてこの規定によって握取行為が本来持っていた古くからの性質である、ただ割当てられた面積のみの売却、という性質を取り除いたのである。scamna の場合にはこういった視点に基づく規定は見られないが、というのは同意に基づく emtio[購入と引き渡し]は何らの所有権の移転を含んでいなかったからであるが、しかし同一の原則が――間違いなくコンスタンティヌス大帝によって――ここでも適用されるべきとされたのである。
推測されること、あるいはむしろ確かであるとさえ言っても良いことは、後の時代の同意に基づく emtio venditio と最終引渡しという流れによる売却の通常の形式は、場所の獲得の形式として一般的なものになっており、≪クイリーテース所有権≫より劣位の権利を持った所有状態について全体において唯一の売却形式だったのであり、その権利についての一般的な売却可能性は行政当局の裁量に基づくものとなっていた、ということである。。
その当時の人々は次のような内容を規定として定めていたに違いない。つまり「売却対象からの除外」というのはこの場合単純に次のことと同じ意味なのであり、それは握取行為からの除外であり、正規の訴訟手続において物権として正規の所有権が認められていない土地に対して保護が与えられない、ということであり、つまりは売却に対しての「法」規範の欠如を意味するのであり、そのためにこの売却が行政当局の実務で扱われるものである、ということは、それをどういった前提条件から導くべきなのか、あるいはそもそもそういう前提条件が存在するのか、という問題であった。「法的な」意味での売却性が認められるようになるのは次の時点からである。それは行政での実務上の原則が法としてきちんと確立する時点であり、そういった諸々の状況がもしかすると ager quaestorius の状況だったのであろう 56a)。
56a) モムゼン(C. I. L. Iの土地改革法の箇所)は、ager privatus vectigalisque の売却性をZ. 54. 63 においての表現から結論付けている:”cujus ejus agri hominis privati venditio fuerit”[その土地が私有のものであってそれが売却されていた場合]。私はこの表現はむしろ次のことを意味しているのではないかと考える。つまりこの法が売却に関しての何かの「特別な」意味を示しているということで、――もしかすると後の時代の Emphyteusis ≪土地の長期または永久貸借≫に似たようなもの――を意味していたのではないかと。この法がまたこの形式の耕地に対する権利の有効化について別に何らかの原則を定めていたかどうかは不明である。Z.93 での”in ious adire”[法的権利を主張する]という表現はおそらくはまさしくこのすぐ前の箇所にて言及した”ager ex senatus consulto datus assignatus”[元老院決議に基づく土地割当て]に関しての表現と思われる。この表現が具体的な耕地との関連で意味することを、モムゼンは引用済みの箇所でそれを公有地占有の形の土地についての表現と見なしている。この ex senatus consulto による土地に関する記述は、viasii vicani が出て来る箇所よりも先であるので、私は次の考え方はそう間違っていないと思う。つまりこの表現は先に既に述べた navicularii の耕地について言っているのではないか、ということである。この法にてこの部分に続く箇所では、ひょっとすると後の時代ではしばしば皇帝の命令によって出された業務である、非常に負担の重い農作物の輸送義務について述べているのかもしれない。
地税の中での vectigal の変遷
法律上の売却性という点について、地税の一種という分類においての vectigal の永代貸借料に関する規範という性格は変動していた。もちろんこの売却性というのはアフリカにおいての所有者達においては、もし私が先に述べた見解が正しいなら≪執政官 Ahenobarbus の時の lex censoria がアフリカでの賃借耕地からの収益に関して規定しているという見解≫、次のような我々が慣れ親しんでいる課税方法とは異なっている性格も持っており、つまり≪我々が親しんでいるように≫土地区画あたりの収穫高に応じて土地に課税上の等級を設定するのではなく、その土地の合計面積、つまり総ユゲラ数に応じて、均等にかあるいは耕地、牧草地、森林などについてそれぞれに大まかな税率が設定されて課税されていた。ここにおいてようやく公有地の価額の査定においての綿密に検討された行政上の技術が登場して来ているのであるが、それは単に定量的なもので根本原則的なものではなかった。もしかすると既にカンパーニャ地方の土地において――正確なものではなかったにせよともかくも推進された――譲渡金額についての査定と個々の区画に対しての決定についての何らかの手続きが行われていたのかもしれない。少なくとも測量地図の作成と”pretium indictum”[公示価格]はヒュギヌスの印刷本の p.121 に出て来る表現である”certa pretia”[固定価格]を思い出させるものである。この固定価格という表現は同じ本の p.119 との関連でどちらも同じケースを扱っているが、トラヤヌス帝の時代においてパンノニアにおける≪退役兵士への≫譲渡の対象とする土地に対して、次の6種の分類が行われていた:arvum primum[第1級の平地]、arvum secundum[第2級の平地]、pratum[牧草地]、silva glandifera [木の実が採取出来る森林地]、silva vulgaris [その他の森林地]、pascua [(共同の)放牧地]である。一人一人に割当てられた土地の面積である――66 2/3、80、100 ユゲラについては――それらの面積の土地が常にただ一つのこれらの課税クラスのどれかでなければならない、という考え方はされておらず、それよりむしろそれぞれの割当て地の税の総額が計算され、その計算はその土地の各部分での分類上のクラスで決められていた「それぞれのユゲラあたりの単価」 X 「それぞれに該当するユゲラ数」、の総計という形で行われていた。測量地図上には各割当て地について、その土地の中の arvi primi ≪arvum primum の複数形≫が何ユゲラ、prati が何ユゲラ、といった風に記載され、その情報に従って各クラスによって固定されていたユゲラあたりの税額を使って、その割当て地の合計税額は簡単に計算することが出来た。ではもし土地所有者がその土地の利用方法を≪例えば農耕から牧畜に≫変更した場合、その場合でも税額の総額は同じままであっただろうか?もし近代的な意味での土地税の話をしているのであればこの問いに対しての答えは間違いなくイエスであろう。しかしここで課されている賦課については次のことを考慮することが必要であろう。つまり歴史的にはこの賦課の制度は永代貸借の規範の中間形成段階から、それが最終的に確定した段階へと発展し変化し続けていた、ということである。そういった状況に即して考えてみれば、次のことは全く首尾一貫していると言えるだろう。それはその土地の利用方法が変わる度に、賃借料もそれぞれの土地の分類に従って総額が変更された、ということである。賃借人の土地の利用方法の変更による賃貸料収入の減少リスクに対しては、≪民間の≫賃貸し人もその立場での国家も次の手段でそのリスクを回避しようとした。それはその種の土地利用の変更について、賃借人がローマの規則一般にほぼ従わざるを得なかったという状況を利用して、土地利用の変更をさせないようにする≪圧力をかける≫、というやり方によってである――そのことについては最終章で再度扱う――そしてまた属州の住民に対して、代々の皇帝は周知のように次の権利を当然のものとして保持していた。つまりその住民達に対して土地利用の内の一定の種類のものをイタリアの土地全体の所有者としての利害関心からそれを禁止することが出来る、という権利である。それ故に次のことは全く可能であったであろうし、またもしかすると実際にはもっとも広く行われたケースであったかもしれないのであるが、個々の土地からの賃借料の額は、ヒュギヌスが記しているように、それぞれの利用方法の違いに応じて≪固定額として≫土地台帳に記入されたということであり、そして土地の利用の仕方、つまりワイン作りのためのぶどう畑などとして利用された面積のユゲラ数こそが、本質的にはヒュギヌス(既引用分)が言及しているように土地の占有ということの本質的な内容だったのである。しかしながらそういった土地利用の仕方の変更の禁止が行われていたとしても、それはいずれにせよただ経過的な措置に過ぎなかった。何らかの理由で起きたかもしれないある耕地の一部分についての利用の中止は、間違いなく税金の軽減の理由としては決して認められなかった。arvum primum と secundum といった土地の分類は、その土地の収穫「可能高」に基くその土地からの継続的な税徴収を意味していたし、そしてこうした分類基準については時間の経過に従いその分類を増やすという形で更に細分個別化されていったのであり、それについては後で論じる通りである。
ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳(41)P.240~243
「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第41回です。
一般にグラックス兄弟や後のカエサルによる土地改革法の目的は、海外から安い小麦が入って来たり、貴族による大規模農園の経営によって競争力が無くなり没落して都市プロレタリアートとなった独立農民の救済と、かつ市民の数を維持してローマ軍の人数を確保することだったと説明されますが、ヴェーバーはそこに国家による資本家支援という非常にユニークな視点を提供しています。要するにローマが敵に打ち勝って新規に獲得して土地が、国家がきちんと使用方法を決める前に既に貴族などの富裕層による奴隷を使った農場経営が占有の形で行われていて、土地改革法はそういう占有を一方では上限を設けて制限する一方で、また改めて正式に認知した、という面があるのでしょう。
なお、vectigalというラテン語ですが、これの日本語訳は苦労します。小作料と訳すと、この時代に貧農層が多くいたような感じがしますし、地租と訳すと明治の日本みたいですし、現代の日本で言うなら固定資産税みたいなものですし、訳文中では賃借料と訳したり税金、地代と訳したり色々です。
==================================================
しかし当時更にまた、ユゲラ[面積]あたりの地代も規定されており、こちらの起源は間違いなくより古いものであった。同様に土地の購入にあたってユゲラあたりの価格で取り決めて行ったように、賃貸借でも同じやり方が用いられた。それ故に、また trientabula においても、名目地代は1ユゲラあたり1セステルティウスとされ、引渡される土地区画全体でいくら、という決め方ではなく、しかしその一方でその他の場合として、引渡される土地の価格がその土地の実勢価格に基づいて査定され、その時々の購入価額で担保に供されたということもあった。そのため、先に言及したルキウス・カエキリウス・メテッルス・デルマティクス ≪Lucius Caecilius Metellus Delmaticus、BC119年の執政官≫とグナエウス・ドミティウス・アヘノバルブス≪Gnaeus Domitius Ahenobarbus、BC122年の執政官≫の[2人が執政官であった]時に制定された lex censoria 50c) がアフリカにおいての賃貸耕地からの賃貸収益について規定しているのであれば、これは収穫物の一定割合か――法規は1/10税について言及しているが――あるいは固定額の(相対的にはより少額の)金銭地代であったかどちらかであり、その金銭地代は少なくとも地域毎に統一され、そしてあるいはまた二三の土地価額のクラスで分けられて、同じクラスであれば1ユゲラあたり同一価格で(その時は)あったか 51)、あるいは継続してそうであった可能性があり、というのはその公有地全体の全ての賃借耕地に対してそれぞれ個別に金額を提示するということまでは、そういった lex censoria の規定には含まれていなかった可能性があるからである。
50c) a.u.c. 693年(BC115年)
51) たとえばパンノニアにおいての耕地への貸借料設定は何段階かのクラスに分けられていた。
それ故にまた、より大きな面積でのまとまった土地を契約者が引き受けた場合には、貸借期間は100年とされ、ユゲラあたりのより低い固定額での地代が課され、競売において入札するものとしてはただ全体の購入価格のみ、とされたのである。そういった購入価額は、ただ保証人によってかあるいは所有資産(の証明)によって保証されたのであり、100年で満期となる毎年の賃借料の総額の支払いが必要だったのではない。このことによってさらに明らかになるのは、こうした公有地の賃借人は[通常の毎年の]賃借料を支払う小作人のように扱われたということであり(上述箇所参照)、同様にこの種の賃貸しの手続きは、”vectigalibus subjicere”[賃借料を条件とした]という表現と矛盾していない。このことが正しいと認められるなら、私の考える所では、次のことはかなりの程度確からしくなる。それは ager privatus vectigalisque についても手続きは同様のものであった、ということである 51a)。
51a) 法はおそらくZ.52 の:”(habeat pos)sideat fruaturque item, utei sei is ager loucs publi(ce a censoribus mancipi locatus esset ?”[その土地や場所を所有し、占有し、かつそこから利益を得ることが出来、それはまるでその土地や場所が監察官によって購入者に公的に貸借されているかのようである。]の所で暗に賃貸し耕地の競売による授与のことを述べていた。
いずれにせよ私見では、モムゼンがこの法において実質的な地代が定められていたという可能性を疑っていることは、意味をなさなくなるであろう。次に考えられるのは、法は現在失われている箇所(特にZ.51、52の欠落部)52) において、いずれにせよ相当な額のユゲラまたはケントゥリアあたりの地代を、おそらくはその際に初めて課していて、その結果として永代賃借料を引き上げた形になった、ということである 53)。
52) 確かに次のことは疑わしい。それは引用文献中の証拠の箇所として、その碑文中の欠落部分を使うことである。しかしそれにもかかわらず、この場合には次のことは確かである。つまりこの法がこの制度とそれに伴う該当する耕地についての、地代納入義務の規定を含んでいるということである。というのはこの規定について Z. 66 において参照されているからである。
53) 次のことがもし明らかになるのであれば、この地代の額についてもう少しはっきりしたことが分かるであろう。それは競売されている耕地を購入しようとする者が、この法の Z. 53 以下に従って何を公的に申告しないといけないか、ということである。私が信じたいのは、後のパンノニアにおける占有と同様に、その際の申告内容としてヒュギナスが p. 121 で言及しているが(更に後で引用する箇所を参照)、それはその耕地、牧草地、森、牧場の面積――あるいはまた同様のカテゴリーの――であるが、そしてその面積を購買者は所有することになったのであるが、その面積[とカテゴリー]に従って地代が課されたのである;というのも私がこの論文で統一的な地代の存在を確からしいものとして述べた際には、こうした原始的な諸カテゴリー、それらについては後で扱うことになるが、による地代の差異の可能性を決して排除していないからである。確からしいのは、土地購入についての公的な申告は、本質的にはこの目的[購入した土地のカテゴリーをはっきりさせて地代の額を決める]のためであったろう、ということである。その他のことについてこの法が規定しているのは、全体の処置においてまた、それどころかひょっとしたら主要目的として、所有者のことを規定しているのであり、その所有者達はこの法の発布の前から既に「購買」によって[本来は公有地である]土地を獲得していたのである。先に記述した貸借対象耕地の契約者についての注釈≪国家が土地斡旋によって資本家を作り出そうとしていたこと≫が正しかったとすれば、ここで扱われているのは、次の者達(注51a参照)に対して、その者達はアフリカの公有地における耕地を永代賃借料を支払う条件で貸借したのであるが、その者達自身に対してまた、取り消し不能な有限の所有状態が保証された、ということであり、そしてこのことがもし正しければ、その場合はここにおいてこの立法の前代未聞な資本家支援的な傾向が剥き出しの姿で登場してきているのである:なるほど立法家は公有地の大規模な土地所有者に対して直ちに地代を免除することは、イタリアでの例のように、躊躇していたが、しかし立法家は lex Thoria によって彼らに対してイタリアにおいての[大規模]占有者の地位を認めたのである。これに対して、次のような公有地の所有者、つまりその者の土地が監察官によって与えられることが多かった者[a censoribus locari solet]、つまり小規模の賃借人のことであるが、そしてそれは古くからのその土地の住民またはイタリア人であったが、その者達に立法家は保証(前述箇所を見よ)を与えこそしたものの、かつその者達はそれまでのような額の賃借料を支払う必要はなくなったものの、その代わりその所有状態は法的には不安定なものに留まった。――
もしハラエサ≪シチリア島北部のギリシア人による植民都市≫の碑文に――カイベル、ギリシア碑文集、シチリアとイタリア、Nr. 352――事実上、カイベルがそう想定しているように、作り出された土地区画についての地代に関する記載が含まれているのであれば、そのことは自然に考えればただ名目的に設定された一般的な価格であった可能性がある。その他、この碑文での κλᾶροι と δαίθμοι の制度については≪全集の注によれば、前者[クラーロイ]は単に(籤で)割当てられた土地の一単位、後者[ダイスモイ]はその内で賃借人に割当てられた区画のこと≫ここでの土地の位置決めは本質的には元々の所有者達の間での配置換えだったのであり、そこには[競売という]競争が入り込む余地は全く無かった。有名なアクラエ≪シチリア島南部のギリシア植民都市≫の碑文(カイベル、前掲書、Nr. 217)については作り出された土地の所有状態がどのような種類のものであったかについては不明であり(参照:ゲットリング≪Karl Wilhelm Göttling、1793~1869年、ドイツの言語・古典学者≫のアクラエ碑文、そしてデーゲンコルプ≪Karl Heinrich Degenkolb、1932~1909年、ドイツの法学者≫の先に引用した lex Hieronica に関する論文)我々にとってはそれらの情報は意味が無い。
永代賃借料は次の場合には当然のことながら課されなかった。それは同じ土地授与対象物全体を様々な購買者に何度も売却した結果として、ある者が購入済みで(既に代金も支払った)土地[が誰か別の者に与えられてしまった場合]の換わりに、別の土地が改めて授与された場合である:それがこの法の Z. 66 においての購買者に1セステルティウス[の形だけの代金]を支払わせた、ということの意味である。
測量地図
これらの耕地の測量はケントゥリア単位で行われており、それは完全な所有権を入手出来る土地割当ての場合のケントゥリアと区別されていなかったように思える(Z. 66)、故にその面積は200ユゲラであり ager quaestorius の場合のようにただ50ユゲラだけではなかった。土地の授与は取り消せない性質のものであり、それは “privatus”という表現が示す通りである。ager vectigalis としての性質は次のような結果を生んだに違いない。つまり土地の授与は握取行為の形式では行われなかったし、そういった土地の相続に関しての規制においては、それが国家当局の干渉無しに行われることもなかった、ということである 54)。
54) このことは、Z. 62、64の相続人に関する規定で言及されているようなやり方で法規中に出現している。このことが意味したことは単純に、属州の知事は次のことを行いうる立場にあったということであり、それはその者が土地の授与を許可したり、また誰にその土地を相続させるかについて原則を作り、それを布告する、ということである。というのはその者は行政担当官であるのと同時に裁判官でもあったからである。ager quaestorius と更に違うことは、ここでは limites viae publicae [公共の道路による境界線]であり、何故ならばZ. 89 とそれに続く部分でそのような補足を加えている規定は、[元の]カルタゴの領土だけでなく全てのケントゥリアに対して適用されていたからである。というのも賃借料は――我々の仮定では――ユゲラあたりで等しかったので、このことは課税可能な対象物を個々の購買者それぞれに十分に行き渡るまで分割することを可能にし、個々の購買者から単純にどの位の税が取れるか、その者が1ケントゥリアの中で何ユゲラを所有しているのか、それから1ケントゥリアあたりで[分割して]割当てた土地の合計が200ユゲラであることの確認、などについての管理を非常に楽にした。属州アフリカにおける土地の分割と土地制度全体の安定した状態は、あり得ないくらい長期に渡って変更されることなく維持されていたように見え、つまりは皇帝ホノリウス≪在位393~423年の西ローマ皇帝≫の時代まで続いたのであった。その当時(422年)に実施された改定が及んだのはテオドシウス法典の13の de indulgentis debitorum [借金返済の猶予について]によれば:アフリカ総督の管轄下:課税対象地として9002ケントゥリアと141ユゲラ、荒れ地として5700ケントゥリアと144 1/2ユゲラ、ビサンチンにおいて:課税対象地として7460ケントゥリアと169ユゲラ、荒れ地として7715ケントゥリアと3 1/2 ユゲラであり、合計でアフリカ総督管轄下で:16703ケントゥリア≪計算上は14703≫と85 1/2 ユゲラ、ビサンチンでは:15175ケントゥリア≪計算上は15075≫と172 1/2 ユゲラが課税対象領域において測量済みの土地面積である。
以上の記述からはまだその当時でも税の計算上は[ほぼ]1ケントゥリア=1ケントゥリア、つまり1ユゲラ=1ユゲラとして計算されていた、という印象を受ける。≪おそらくは実面積に何かの係数をかけて補正した形での面積を使って税が計算されてはいなかった、ということであろう。≫このようにして税額が決められ課税された全体の領域の面積は、ほぼ≪ヴェーバー当時の≫東プロイセン州の(例えばポーゼン≪現在のポーランドのポズナン≫の鋤で耕された耕地の大きさと同じであり、当時の制度に従ったやり方として、ただアフリカの耕された土地の大半について一部のみが、そうではあってもまたかなりの大きさのものではあるが、ここでは描写されている可能性がある。その他の部分の土地についての記述は後述の箇所で扱う。ここで述べられていることの全ては、私には何よりも次のことについて語っているように見える。つまりここで言及されている耕地に対しては、実質的な賃借料が課されていた、ということである。同様に次のことも述べている。つまりここでは境界線がまた道路として直線のまま保たれていた、ということである:そのことは既に注記したように、課税の管理を楽にしていた≪中世のドイツの農地では牛が鋤を牽いて蛇行して耕す結果として境界線が波状になっている土地が多かった。≫;これに対して通常の ager quaestorius においては、境界線は同じようにその土地の範囲を確定させるために厳格に管理されるべきであったが、しかし確からしいことと思われるのは、実質的な地代がそこでは課されなかったがために、その境界線を直線のまま保つことに対しての利害関心が全く生まれていなかったことになり、結果としては直線性は失われてしまったのである。
ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳(40)P.236~239
「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第40回です。
ここは今まで一番苦労しました。というのは注50で細かい字で延々と1ページ以上に及ぶ、かつ断片的な土地改革法の引用文が出て来たからです。ChatGPT4oの助けを借りながらなんとか訳しましたが、訳中にも注記したようにこれまで以上にここは参考訳です。
その内英訳等を探して再チェックしたいと思います。なお全集の注によるとヴェーバーはモムゼンの原文をそのまま引用したのではなくBrunsの本の引用から孫引用した上に、更には自分に都合の悪い所は抜いた、といったことが書いてあります。ヴェーバーの知的誠実性がどうの、というしょうもない本が過去にありましたが、しかしヴェーバーも軍役で忙しかったのかもしれませんが、決して完璧な仕事とは言えません。
============================================
この地代の名目性という点において、収穫物の内の一定割合の物納から固定額の地代への変更が行われていたとしたら、次のケンスス実施までの期限付きの賃貸契約の決定においては占有ということはほとんど考慮されていなかったのと、またこの制度が[占有という]不安定な所有権状態を保持したままで継続するということがもはや不可能になっていたという二つの理由で、グラックス兄弟[の兄]がこの制度においての補償としてはただ占有状態の回復のみを規定しようと欲した後では、そこで規定されていたのは、lex Thoria の時代から lex agraria (a.u.c. 643年)での[公有地の不法]占有は、それらの法は占有を完全な私的所有権という観点ではその定義を変更したのであるが、もっとも確からしいのは ager privatus vectigalisque として扱うようにして、しかし名目的な地代ではなく実質的な地代を支払う義務のあるものに変えたということが起きた、ということであろう。以上のことは法の制定目的にも合致しているし、その法は一旦地代付きの私有地に変更された占有地の取り戻しを法律上不可能にしようとしたのである 49)。
49) というのもアッピアノスによれば(先に引用した箇所のI, 27)その中身は:
τῆν μέν γῆν μηκέτι διανέμειν, ἀλλ’ εἰναι τῷν ἐχόντων, καί φόρους ῷπέρ αὐτῆς τῷ δῆμῶ κατατίθεσθαι.
[その土地をもはや分配せず、それを市民のためにそのままに保持し、市民の利益になるようにする(課税する)べきである。]
より広範囲においての同様の所有状態がイタリアに存在していたことのはっきりした証拠は存在しない。というのは次のような仮定をするのは不当であるからである。つまり測量人達がイタリアにおける国有地としてしばしば言及している ager vectigales が、vectigalibus obligati agri [支払いを義務付けられた土地]という永遠に支払い義務のあるレンテン[定期支払い金]を思い起こさせるような表現にもかかわらず、法的には取り消し可能な貸借契約に基づく土地とは少し違うものと考えることである。この表現がこういった借地が事実上相続出来るものとされたことの結果であり、そのことについては先に論じた。
アフリカでの Ager privatus vectigalisque
これに対して一つの難問があり、それは次のような次のような国家の領土をどのように理解出来るかということで、その領土とは[ポエニ戦争の最終的な勝利の結果としてカルタゴが滅びローマの領土となった]属州アフリカにおいて a.u.c. 643年の土地改革法の規定によって、ローマ国家による公的な売却の形で私有の所有地へと変えられたものであり、そして同法によって agri privati vectigalesque と表現されたものである。――その法の該当部分の[不完全な現存テキストの]補完と解釈において 50)、何らかのより確実性の高いと表現してもよい前進を、次のものを越えて行うことは、それはつまりモムゼンがCorpus Insc. Lat. (Vol. I p.175 n.200)で述べていることであるが、あるいはそれ以外に追加の何かのもっともらしい仮説を立てることは、元資料の状態を考えれば私には不可能である。しかしいくつかの注記は述べておくことにする。
50) その内容はモムゼンの前述の箇所での補完に従えば以下の通りである:≪以下の日本語訳は参考程度。他のラテン語引用箇所と比べても抜けが多く、非常に意味を取りづらい。またヴェーバーによるイタリック体への変更箇所は、単語の途中でされていたりして意味不明なため、特に下線には変えていない。また原文の番号分けと日本語訳の分け方は必ずしも完全には一致していない。≫
49. esto, isque ager locus privatus vectigalisque u. … tus erit; quod eius agri locei extra terra Italia est … [socium nominisve Latini,
[(ローマの公有地である属州アフリカの土地は)それらは ager locus privatus vectigalisque として扱われる..;それらの土地と場所≪以前の議論で土地は割当てや売却の際にただ面積のみがそうされるのと、具体的な位置が割当てられることの両方があったことを参照≫がイタリアの領土外にある場合、ラテン同盟や同盟市の人々、]
50. quibus ex formula t]ogatorum milites in terra Italia inperare solent, eis po[puleis], … ve agrum locum queiquomque habebit possidebit
[また通常ローマ市民としてイタリアの領土での軍役に従事する人々に対して、…また誰であれ土地や場所を所有し、占有し、]
51. [fruetur, … eiusv]e rei procurandae causa erit, in eum agrum, locum, in[mittito … se dolo m]alo.
[それによって利益を得る者は、…またはその土地を管理するために、その土地または場所に悪意無く立ち入ることが出来るとする。]
52. Quei ager locus in Africa est, quod eius agri [… habeat pos]sideat fruaturque item, utei sei is ager locus publi[ce … IIvir, quei ex h. l. factus creatusve erit,] in biduo proxsumo,
アフリカにある土地や場所で、その土地を…誰かが所有し、占有し、またそこから利益を得るものについては、その土地や場所は公有地として扱われる…。この法律により選出された2人の者(担当官)は、選出されてから2日以内に、
53. quo factus creatusve erit, edici[to … in diebus] XXV proxsumeis, quibus id edictum erit [… datu]m adsignatum siet, idque quom
[公告を出し、そしてその公告が出されてから25日以内に、その土地が与えられ割当てられるようにすること、]
54. profitebitur cognito[res … ] mum emptor siet ab eo quoius homin[is privatei eius agri venditio fuerit, … L.] Calpurni(o) cos.
[(その割当てられた土地を割当てられた者から買った者の)代理人がその土地をケンススに登録する申告を行う時に、その土地の売却が私有地として行われていた場合は、その代理人が売却した者から(元々 ager privatus vectigalesque として割当てられた)その土地の購入者であることを確認してもらうことになる, …ルキウス・カルプルニウスが執政官であった年に]
55. facta siet, quod eius postea neque ipse n[eque …] praefectus milesve in provinciam er[it … colono eive, quei in coonei nu]mero
[行われたことのうち、その後に彼自身も…その代理官や兵士も属州において…(その土地が)植民者や植民者名簿に]
56. scriptus est, datus adsignatus est, quodve eius … ag … [u]tei curator eius profiteatur, item ute[i … ex e]o edicto, utei is, quei
[記載されている者に割り当てられたものである場合は、またはその土地についてその土地の管理人が申告するようにし、同様に…その公告に基づいて]
57. ab bonorum emptore magistro curato[reve emerit, … Sei quem quid edicto IIvirei ex h. l. profiteri oportuer]it, quod edicto IIvir(ei) professus ex h. l. n[on erit, … ei eum agrum lo]cum neive emp-
[またはその土地をその土地の売却管理人か売却責任者から購入した者が、…そしてもしこの法律を基いて出された2人の担当官の公告に従って何かを申告する義務のある者が申告を行わなかった場合は、その者に対してその土地や場所が]
58. tum neive adsignatum esse neive fuise iudicato. Q … do, ei ceivi Romano tantundem modu[m agri loci . . .] quei ager publice non venieit, dare reddere commutareve liceto.
[購入されたものでも、割当てられたものでもなかった、あるいは存在していなかったと判断されるものとする。Q…がそのローマ市民に対して、同じ面積の土地または場所を与えるものとする…その公有地が売却されていなかった場合には、その者はその土地を譲渡、返却、または交換することが認められる。]
59. IIvir, q[uei ex h. 1. factus creatusve erit … de] eis agreis ita rationem inito, itaque h…. et, neive unius hominis nomine, quoi ex lege Rubria quae fuit colono eive, quei [in colonei numero
[この法律により任命され選出された2人の担当官は、これらの土地について次のように会計上の処理を行い、…ただ一人の名前だけでそういった処理を行うことは出来ず、その者がルブリア法≪南ガリアに作られた植民市についての法≫に基づいて、植民者や植民者として登録された者に対して]
60. scriptus est, agrum, quei in Africa est, dare oportuit licuitve … data adsign]ata fuise iudicato; neive unius hominus [nomine, quoi … colono eive, quei in colonei nu]mero scriptus est, agrum quei in Africa est, dare oportuit licuitve, amplius iug(era) CC in [singulos
[アフリカにある土地を与えることが必要とされたり許可されたりすることがないようにするものとする…与えられ割当てられたと判断されるべきである;どのような一個人の名義においても、ルブリア法に基づき植民者とされたかあるいは植民者として登録された者に対してアフリカにある土地を割当てる必要があった場合でも、その個人に対して割当てられる土地は200ユゲラを超えないものとし、]
61. homines data adsignata esse fuiseve iudicato … neive maiorem numerum in Africa hominum in coloniam coloniasve deductum esse fu]iseve iudicato quam quantum numer[um ex lege Rubria quae fuit . . . a IIIviris coloniae dedu]cendae in Africa hominum in coloniam coloniasve deduci oportuit licuitve.
[(もし超えていた場合には)その土地がその者に割当てられているかあるいは割当てられていたと判断してはなならない。アフリカに入植した人の数が、過去に存在したルブリア法に基づいてアフリカに入植するために…植民市の三人委員会によって入植許可が与えられた人数よりも多い、または多かったと判断されるべきではない。]
62. Iivir, quei [ex h. 1. factus ereatusve erit …] re Rom … agri [… d]atus ad[signatus … quod eiu]s agri ex h. l. adioudicari
[この法律によって選ばれ任命された2人の担当官は、ローマ国家の権限で…その土地の授与または割当てについて…その土地が追加で与えられることが]
63. licebit, quod ita comperietur, id ei heredeive eius adsignatum esse iudicato [… quod quand]oque eius agri locei ante kal. I [… quoiei emptum] est ab eo, quoius eius agri locei hominus privati venditio
[許可されるならば、その土地がその者またはその者の相続人に割当てられたと判定すべきである…そしてその土地や場所が1月1日よりも前の時点で、その土地や場所の元々の私有地を売却した者から購入した者の所有となっていること、]
64. fuit tum, quom is eum agrum locum emit, quei [… et eum agrum locum, quem ita emit emer]it, planum faciet feceritve emptum esse, q[uem agrum locum neque ipse] neque heres eius, neque quoi is heres erit abalienaverit, quod eius agri locei ita planum factum
[ならびにその者がその土地や場所を購入した場合に、その土地または場所が存在していたならば、その土地についての測量図を作成するか、または既に作成していて、その購入の事実を明確にするであろう。その土地または場所は、彼自身も彼の相続人も、また彼の相続人となる者も譲渡しておらず、そしてその土地または場所についての測量図が作られている場合は、]
65. erit, IIvir ita [… dato re]ddito, quod is emptum habuerit quod eius publice non veniei[t. Item IIvir sei is] ager locus, quei ei emptus fuerit, publice venieit, tantundem modum agri locei de eo agro loco, quei ager lo[cus in Africa est, quei publice non venieit,
[2人の担当官が、その土地をその者に与え返還することとする…更に2人の担当官はその者が購買したことになっているが公的にはその者に売却されていないことになっている土地や場所について、その土地や場所が公的に別の者に売却済みの場合は、その者に対してその土地や場所と同じ面積のアフリカにある場所か土地で公的に未売却のものを、改めて割当てそれらをその者に戻すこととする。]
66. ei quei ita emptum habuerit, dato reddito … Queique ager locus ita ex h. l. datus redditus erit, ei, quoius ex h. l. f]actus erit, HS n(ummo) I emptus esto, isque ager locus privatus vectigalisque ita, [utei in h. l. supra] scriptum est, esto.
[この法律でによってそのように割当てられたか返還された土地や場所が、この法律に基づいて、それらを与えられた者達に、一単位≪おそらく200ユゲラ≫あたり1,000セステルティウス≪ローマの銀貨、奴隷一人が約6,000セステルティウスぐらい≫で売却され、そういった土地や場所はこの法律に書かれているように ager locus privatus vectigalisque とされる。]
先に言及した同法の規定によって通常の公有地賃借人のアフリカにおける賃借地の購入金額は、それぞれの土地での lex censoria に定められて決まっていた。それによって当時の公有地においての財の所有者は、その所有を事実上相続可能な財産とすることが出来、ただその所有状態に関していつでも取り消し可能という純粋に法的な不安定さがそれを他の所有状態から区別するものとなっていた。こういった不安定さが無いということと、無期限の所有割当てが、今や明らかに ager privatus vectigalisque の所有者を他の一般的な公有地賃借人から区別するものとなっている。
ager privatus vectigalisque における賃借料の性質
この ager privatus vectigalisque という土地については、法が明確に規定しているように、疑いなく資本払い込みに対しての土地授与という点が肝要である。このことからまた、こういった形での土地の授与は、我々が先に ager quaestorius の特徴として見出したこととまさに同じなのであり、そしてモムゼンも2つを同種のものとして総括している。しかし私にはこの ager privatus vectigalisque をその意味で理解することが出来るかどうかについては、全く確実とは思っておらず、そしてそのことは次の疑問と関係している。それはここでの賃借料が単に名目的なものだったのか、あるいはその額がごくわずかであったとしても実際に支払うものだったのか、という疑問で、それは検討してみるべきである。ager quaestorius が一般的に賃借料を条件とされていたのであれば――そのことによってその制度においては何も無条件には引き渡されてはおらず――、そのためその制度はある名目的なものと特徴付けることが出来、それは torientabula の場合においてモムゼンが確からしいと認めていることであるのと同じであるが、このことはまたアフリカでの ager privatus vectigalisque においても同じだったのである。ともかくも通常の ager quaestorius はそれ以外の点においては決して ager privatus vectigalisque と呼ばれることはなかったし、モムゼンもまたアフリカにおいて購入された土地について次のことまでは主張していない。つまりそれが一旦売却したものを将来再度買い戻す前提での担保という性格を持っていた、ということである。この名称は、前半部の”privatus”は一旦割り当てられた土地が取り消されることがないということを意味し、後半部の”vectigalis”は何らかの公租公課の負担義務があることを意味しているが、しかしこの2つをくっつけた場合には、それは不適切な(矛盾する)名称となってしまっているのでないだろうか。しかし特記すべきなのは、そういった所有状態で ager quaestorius が実質的にその中身と同じものを新たに作り出すにあたって、立法は必要とされず、ただ元老院決議にだけ基づいていた、ということである;法律はただ割当ての取り消しが出来ない、ということを定めたに留まっており、更にはローマの人民にとっての nudum jus Quiritium ≪ただローマ法上の虚構的な理論として存在していて実質的には存在しないクイリーテース所有権≫に留まっていて、その結果必然的なこととして、グラックス兄弟による土地割当ての際と、Lex Thoriaの時においてでは、ager privatus vectigalisque という表現の意味するところは変化していた。しかしながら次のことは確かに可能である。つまりモムゼンの仮説である、この制度における vectigal の性質としては、単なる仮課税と見なし得る、ということであるが、――グラックス兄弟においての土地割当てのやり方はアフリカに対して植民を進めるようなものと言え、そこで行われたのは、法においての資本家的な精神に沿っていて、土地が貧困者に割当てられたのではなく、富裕者に割当てられた、ということである。私は次のことを可能であると考え否定するものではない。それは、私にとっては主観的には以下のことが確からしいと考えられるということで、つまりは既に述べたことではあるが、賃借する土地の授与においてはまず次のやり方が先行したということで、そのやり方とは、ある契約者が個々の土地区画ではなく複数の土地のまとまりを長期間である確定した賃借料という形で競り落とした、ということである。次のことについては不確かなままである。つまり土地の競売において一対何に対して参加者は価格を提示したのか、ということである。我々は≪ヴェーバー当時の≫現代の競売についての知識から次のように考えがちである:賃借料の金額がそれであると 50a)。
50a) ヘラクレイア≪現代のトルコのマルマラ海の北岸の都市≫においての寺院領が競売された場合はそうであった。参照:カイベル≪Georg Kaibel、1849~1901年、ドイツの文献学者で古代ギリシアの金石分の専門家≫のギリシア碑文集の中の彼の担当部の Tabula Helacleensis に対しての注記。イタリアでの同様の例は同じ書の No. 645 を参照。碑文についてはしかしそれ以外で我々にとって重要な情報を提供してくれていない。競売対象を個別化して分けるということが同様に先に引用したエドフ神殿≪ナイル川西岸に位置するエドフの町にある古代エジプトの神殿 ≫の碑文において認めることが出来る。土地区画は大半が長方形で通路によってお互いに分離されていた。カイベルの書のP. 172、173の図を見よ。
しかしながら、こういったやり方はローマでの慣習的なやり方とほとんど合致していなかったように思われる。後にはもちとん、ヒュギナス(原文の P. 204)の印刷本の P. 121 にあるように、個別の、区画分けされた土地が、その面積と肥沃さに応じた地代を課されており、つまり個々人毎に異なっていた 50b)。
50b) 更に詳しい例は後述箇所を見よ。
ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳(39)P.232~235
「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第39回です。
前回あたりからグラックス兄弟の公有地分配政策が登場します。ご承知の通り、この政策はある意味ローマにおいて階級闘争的な大混乱を引き起こし、グラックス兄弟は二人とも殺されてしまい、改革は中途半端で終わり、最終的な政策の完成はカエサルを待たないといけません。しかしその法的解釈となるとなかなか難解です。ager privatus vectigalisque ≪私有地であるが課税される土地≫というのが出て来ますが、考えてみれば現代の日本の私有地も、私有地といいつつ固定資産税という名前の名目地代を永遠に支払わないといけません。このルールはやはりローマなのでしょう。
=====================================
帝政末期になって出て来た agri limitrophi ≪ベテラン兵士達に定期借地権の土地として与えられたもので、ライン川やドナウ川などのローマにとっての前線に位置する場所に多く配置された。≫は年間の収穫高[annona]と[賃借料が]関係付けられており、軍隊に対して食料を供給する目的で、牛馬を使った耕作を行うことを条件として与えられたものであった 39)。
39) テオドシウス法典のXI, 59の表題を参照。
3.城主の封土と辺境の封土
agri limitrophi と同じ権利形態[の土地貸与]は帝政期においては更に一般的な他の用途にも使われるようになっていた。10人組長による徴税義務に加え、大土地所有者の徴兵義務 40) ですら土地に付随した義務として扱われるようになり、そして最終的に、agri limitanei [国境に接した土地]において、また軍隊の駐屯地において、国境の防衛義務までが相続による権利継承を通じて、その封ぜられた土地区画に切っても切り離せない物的な負担として課され 41)、更には≪ガリアなどの≫蛮族の諸部族がローマの軍役に服することと引き替えに大規模な領地を封ぜられた時に 42)、そういった状況はもはやほとんど “beneficium” 43)[特権の受益者]概念の統一的な発展の開始地点に立っているようなものであるが、その概念からゲルマン民族の王達の征服した領土においての行政法的な意味での封建制度が成長して来たのである。
40) テオドシウス法典の13の de tiron[ibus][徴兵について]VII, 13, そこでは元老院所有の土地についての新兵徴兵義務が定期金の支払いによって免除されている。
41) アレクサンデル・セウェレス≪Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus、209~235年、第24代ローマ皇帝≫が国境の住民に対して土地を授与した時、”ut eorum essent, si heredes eorum militarent, nec unquam ad privatos pertinerent” (Lamprid. Alex. c. 57)[彼らの相続人が軍役に従事していたならば、それらの土地は彼らのものであり続け、決して(別の)個人の所有物にされることはない。](Aelius Lampridius による Alexander の伝記のc.57≪Historia Augusta という皇帝列伝の中の一つ≫)、プロブス≪Marcus Aurelius Probus, 232~282年、276年から282年までローマの軍人皇帝≫がイサウリア≪小アジアの南東部の地名≫のベテラン兵に土地を授与した時のもの、”ut eorum filii ab anno XVIII ad militiam mitterentur.”[彼らの息子達は18歳になると軍役に従事させられた。]更には軍の城砦に付属する土地について、参照:テオドシウス法、1 de burgariis VII, 14と同法の2, 3 de fundis limitrophis et terris et paludibus et pascuis et limitaneis et castellorum XI, 59[国境に接する土地、領域、沼地、牧草地と城砦の土地について]。至る所で土地の譲渡が行われた場合と土地の相続において、国家当局が介入して逃れることの出来ない義務を負わせるやり方で、その行政の実施においての原則に従って、そういった土地の権利全てに本質的に関わることを定めていた。
この場合の本質的に同質な点は、まず第一に何らかの国家に関係する業務を遂行することを条件とした封土としての土地の授与というだけに留まらず、取引きにおいての所有権の移転という点でもまたそうであったし、更には当該の土地区画についての権利関係、つまりそれの私権と法的な取扱いの形態と規制についてもそうであったし、
そういった権利関係はこのような劣位の権利保持状態においては重要なものとして扱われるのであるが、ローマの行政法はこうした方向への発展の基礎を整備していたのであった。最も重要でかつ独特で新しい要素は、それはゲルマンの法概念から取り入れられたに違いなく、そしてそれは社会的・政治的な意味においてその他の部分では同レベルであったゲルマン法の発展の中で、他に卓越して優位なものとなることの基礎を作ったのであるが、それは独特の形で作り出された個人間の信義関係であり、それは当時の古代世界においては[他では]もはや復活することは出来なかったものである。≪この辺り、ギールケの言うゲノッセンシャフト的人間関係を思わせる。あるいは原始共産制から社会が発展したという発展段階説も思わせる。≫
43) “beneficium” についてテオドシウス法がまず第一に想定しているのは次のような土地区画に対してである。それは世襲財産としてかまたは永代借地契約に基づいて貸与される土地であってかつ永代借地料を支払う必要がないものである。(テオドシウス法 5 de coll[atione] don[atarum vel relevatarum possessionem][税の支払いを免除されたか軽減された占有地について] XI, 20の424);次に(c.6, 同じ箇所の430)全ての形式での relevatio[軽減策]、adaeratio [現金払いの代用]であり、つまり私有地においてか、より優遇された課税カテゴリーにおける国家によって保証される土地についての、土地に付随する負担の軽減策としてである。
地代支払いを条件としての無期限の土地の譲渡
我々は法律の上では期限付きの公有地の賃貸制度について概観して来て次のような公有地の割当てについて論じるまでに至った。それはある種の継続的な労役を引き受けることの引き替えとして無期限の賃貸を受けるものであった。そしてこうしたやり方についてここまで次のようなものとして詳論して来た。それはその実際の労役の内容が本質的には個人が行う種類の労役、奉仕として成立しているものである。続いて我々は再び国家所有の土地区画を金銭の支払いまたは収穫物の貢納を条件として引き受けるやり方に立ち返る。その理由は、この形の土地の授与においてもまた、権利の期限が設定されない所有状態が存在していたからである。
名目地代。Trientabula。
権利として次のケンススまで有効期限を持った通常の公有地の所有状態は、事実上多くのケースで、というより大部分のケースでと言ってよいだろうが、家族においての相続可能な所有権となった、ということは既に前述の通り詳論して来た。次に論じるべきなのは利子の支払いまたはその土地からの収穫物の一定割合の納付を条件として、つまり代々の賃借人に対して与えられる土地についてである。イタリアでは次のようなケースは全く知られていない。つまり国家からの土地の授与であって、その条件として国庫に入る永久に支払う必要がある、そして名目的なものではない地代を確実に支払うという仕組みが確立していたケースである。それとは反対に多くの事例があったのは、土地の授与が期限の設定無しに、名目地代≪実質的な土地の価値に比べて非常に低額な地代≫だけを課すことで行われていた場合である。既に先に、そのような形での土地の授与として trientabula について詳論して来た。この制度は元老院決議に基づき、そのことによって次のことが最初から当然のこととされた。それは私権が、それはローマの訴訟においては占有以外の理由として有効とされた可能性があるが、その制度においては与えられなかった、ということであり、更に同様に最初から当然のこととされたのは、民会での決議を通じて私権を毀損することなしに、一旦授与した後にその土地を取り戻すことが可能であった、ということである 44)。(Trientabulaで授与された土地の)売却が制限されていたか、ということは明らかではない。そして少なくとも事実上 ager quaestorius という形の土地の売却のやり方に torientabula のやり方が使われた(第1章参照)ということは、売却が可能であったことを裏付ける事例である 45)。
44) それ故にそういった場合は技術的にはただ「trientabula で利益を得ること」[frui in trientabula]であり、(モムゼンによる部分的な補完による)土地改革法のZ. 32においてそう呼ばれており、それ故にまた諸ゲマインデに譲渡された公有地としての一つのまとまりの中に入れられていた。
45) 先に引用した測量人の記述の箇所では、土地区画の売却について言及されている。しかしそれ故に可能であったであろうやり方は、ager quaetorius は法律上はある地域の土地の全体がまとめて譲渡されたということであり、そうでない場合は行政官の同意が必要だったということである。そのため ager quaestorius についてはまた名目地代が課されたのであろう。
次のことはしかしこのケースの独自性において全く可能なことであり、また確かなことであるのは、そういった売却制限が実際に行われていたということであり46)、そして売却制限が、グラックス兄弟による名目地代を支払うことを条件とした土地の割当てと全く同様に、そういった制限は通常の ager quaetorius においては伝えられていないが――可能ではあったろうが(参照:シクルス・フラックスの p.151, 20; 154,1)――、言葉として表現されていたに違いないのである。
46) それについて言及しているのはただ土地改革法の先に引用済みの箇所の ex testamento, hereditate, deditione
[遺産、相続、占有に基づく]獲得、の箇所のみである。”ex deditione”による獲得の部分は、モムゼンは(C. I.L., Iの土地改革法の註解にて)それを総督補佐官からのもので、また死因贈与≪ある者が死の直前に意思表示し、その者の死後贈与が行われるもの。もし死ななかった場合は取り消すことが出来た。≫と解釈しようとしている。私から見てより確からしく思われるのは、生前の包括承継[Universalsuccession inter vivos]、つまり養子縁組による財産の承継のケースが想定されている、ということである。
そうした売却の制限はあるいはここではただ通常の賃借農民においてと同じ意味を持っていて、というのもいずれの場合でも禁止令という観点からはただ行政上の権利保護が行われただけであり、それ故行政官は売却を自身の裁量で許可出来たからである。同様にそういう制限は相続に関しての規制手続きとも関係があったに違いない;遺産の包括的獲得は認められており、また遺言による獲得も同様であり、しかし遺産の分割と遺産に関する争いについての判決がその点についてどのように行われていたかは不明であり、ここにおいて行政の協力が無くても済んだ、ということは考えにくい。
グラックス兄弟による公有地割当て
グラックス兄弟による Viritan-Assignation≪既出≫においての名目地代の賦課は trientabula において売却が出来ないことと間違いなく関係があった。この2つにおいての違いはただ、グラックス兄弟による割当てにおいてはそれが民会の決議に基づいて行われたということと、それと関連して土地を取り戻すことが私権の毀損無しに可能であったかもしれない、ということである。このことが”ager privatus vectigalisque”≪私有地でありながら地代が課された土地≫という表現が意味する所であり、この形の土地こそがまさにグラックス兄弟による土地の割当ての際に適用されたのである(後述の箇所参照)。その法的な地位については、その所有状態をそれ以前に想定されていたものと区別することは出来ず、ただ手続きのためだけに、それはこのグラックス兄弟による土地割当ての時にも等しく使われたのであるが、グラックス兄弟による法規で決められた3人委員会――IIIviri agris iudicandis adsignandis ≪土地について判定し割当てる≫あるいは adtribuendis ≪割当てる≫と呼ばれたが 47) ――この種の土地に対して権限を持っていた。
47) C.I.L., I, 554-556, IX, 1024-1026の境界石上に書かれたもの、a.u.c. 624/5年。
2.実質地代。永代借地。
しかし確かに次のことは非常に特異に響くであろう。つまりある法的な形態が、地代を条件として無期限に授与された耕地の形態と同様に、ただ名目的に法的仮構≪事実とは異なるが法律上はそれがあるかのように扱うもの≫の形態として特定の目的のために、それが実際には本当の制度としては存在していないかのように仮定されて使われたのであろう、ということである。そして実際のところ先行したケースとしては、確かにほぼ確実にそれが起きたとは言えないまでも、全く低い確率でもないと思われることは、国家による永代貸与地のシステムが実際に成立していたことが推測出来るということである。
lex Thoria に基づく占有
――まず第一に挙げられるのは lex Thoria による、地代支払いを条件とする占有を通じて獲得された所有権であり、それは公有地においてこのlex Thoria (BC118年)から643 a.u.c.(BC111年)まで存在していた。そういった所有権がそれに対して地代を課されることで、その法的な地位がより良いものになった、というのは確かである 48)。
48) 先に引用した(原文p.218の注14)のアッピアヌスとキケロの文章の該当箇所を参照。
更にはこの場合の地代が単なる名目的なものであったに違いないという見解は、アッピアヌスの見解(引用済みの箇所)である。しかしそれはこの地代収入がローマ人民への無料の穀物給付の財源に使われた、というのと矛盾している。
ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳(38)P.228~231
「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第38回です。今回は、主要街道などの沿線の土地が割当てられる場合は、その占有者に道路改修の義務が課せられたというのと、小麦などの穀物の輸送に従事するものに土地を与えた、というどちらも何らかの労役提供義務が伴う土地についての分析です。
なお、この翻訳で「小作人」という言葉が出て来ても、いわゆる零細農民のイメージで解釈しないでください。公有地を借りている農民は、自営農民に限りなく近いです。後に大土地所有が進んで、現代のイメージでの小作人が出てくることになります。
=====================================
もしある公有地の賃借人がその土地を誰かに取られた場合、その取上げの行為が正当な権利を持っていた賃借人に対しての占有状態を否定するような侵害で無かったのであれば、その場合行政当局は新たな占有者を[新たな]賃借人としてその占有を認めることが出来たのであり、そして元の占有者からの保護の訴えを拒絶出来た。しかしいつもそうしなければならなかった訳ではなく、確かなこととしては、行政上の根本原則に従うのと同様に、行政手続きを進めるためにも、こういったケースでどちらを保護するかについての慣習法的な判定手続きが生み出されていた。
公有地においての無期限の所有状態/個人による労働力の提供を条件とする土地割当て 1. viasii vicani
我々はここまで通常の、法律上ある決まった期間に対して土地を譲渡された貸借小作人の状況について見て来た。しかしながら遅くともグラックス兄弟の頃からもう一種類の公有地が出現して来ており、それは ager publicus である一方でしかし期限の設定無しに個人に譲渡された土地であるが、それはペルニーチェ 34)≪Alfred Pernice、1841~1901年、ドイツのローマ法学者≫の表現に従えば、「留保条件付きで」割当てられた土地である。
34) Parerga≪ヴェーバーはこれをイタリック(この日本語訳では下線)にしているが人名ではなく書名、ギリシア語で「副次的な研究」、の意味≫, Zeitschrift der Saviny-Stiftung für Rechtsgeshichite Rom. Abt, V, p. 74ff。
そういった土地に分類されるものとしては、まずは viasii vicani として割当てられた土地があり、それについては知ることが出来るのはただ a.u.c. 643年の公有地改革法 35) のみである。
35) Z. 11-13(モムゼンの補完に基づく、≪≪≫内はさらに全集の注による≫): (Quei ager publicus populi Romanei in terram Italiam P. Muucio L. Calpurnio cos. fuit … quod ejus IIIviri a. d. a. ≪=agris dandis adsignandis≫ viasiei)s vicaneis, quei in terra Italia sunt, dederunt adsignaverunt reliquerunt: neiquis facito quo m(i)nus ei oetantur fruantur habeant po(ssiderentque, quod ejus possessor … agrum locum aedifici)um non abalienaverit, extra eum a(grum … extra) que eum agrum, quam ex h. l. ≪=hac lege≫ venire dari reddive oportebit. — Quei ager locus aedificium ei, quem in | //AG144// (vi)asieis vicanisve ex s. c. ≪=senatus consulto≫ esse oportet oportebitve (ita datus adsignatus relictusve est eritve … quo magis is ag)er locus aedificium privatus siet, quove ma(gis censor queiquomque erit, eum agrum locum in censum referat … quove magis is ager locus aliter atque u)tei est, siet, ex h. l. n. r. ≪= hac lege nihilum rogato≫
[このイタリアにあるローマ人民の公有地について、それが Publius Mucias Scaevola と Lucius Calpurnius Piso Frugi が執政官であった年≪BC133年≫において、土地の割当て・譲渡を担当する三人委員会が、イタリアにある街道と地方道の沿線にある土地を割当てて譲渡し[その地域の住民の住居用として]残しておいた:誰もその土地を割当てられた者について、その者がその土地を使用し、そこから利益を得、それを占有し所有することを妨げることは出来ない。但しその占有者が…その土地、場所、建物を売却していない限りにおいてであり、その場合その土地やその他がこの法律の規定によって売却されたり、譲渡されたり、返還される場合を除く。――街道や地方道沿いにある土地、場所、建物が、元々元老院の決議によって譲渡され割当てられそこの住民に残されたものであった場合は…その土地、場所、建物が私有地とされるべきか、あるいは監察官が、それが誰であっても、土地と場所をケンススに登録すべきか、またそれらが現在[ケンススに]登録されているものと違っているかどうかは、この法律の関知するところではない。]
十二表法が道路の維持の責任を “amsegetes” に、つまりその道路の側に住んでいる者に課し、特徴的なこととしてまたこの命令の実施を次の規定によって確実なものにした。その規定とは、十分な道路改修を行う人手や必要資金の不足によって、その業務はその道路沿線の耕地の所有者に課され、そのことは大規模な国家の街道網が建設された結果として、直接国がそれをメンテナンスする以外のやり方でそれを行うことが必要となり、そして結局それは次のやり方で実現されたということである。つまり街道沿いの公有地を与えることの引き換え条件として、その公有地に隣接する道路の維持管理を義務付けたのである。この義務がそういう場所に位置していた地域コミュニティ[vics]の全体に課され、その義務の履行が労働の提供によってかあるいは[外部委託のための]資金の提供によったのか、あるいは地域コミュニティ全体ではなく個々の地所に対して義務が課されていたのか、それらについては何も知られていない;navicularius ≪船の持ち主に港町の土地を提供する代償としてローマに穀物を輸送する義務を負わせた制度≫の例(後述)から類推すると、考えられ得る発展の形は、まずは最初の方、つまり地域コミュニティ全体に義務が課されたというのがより確からしく思われる;もちろん法規定から発生することとして、道路改修義務が個々の土地区画の権利上のランクに影響を及ぼしており、そのことからこの負荷が個々の土地区画に課されていると容易に解釈出来るが、しかしその場合ももしかすると義務を負わされた土地所有者達が当番制で実際の作業または支払いを行っていたのかもしれない。
この viasii vicani の耕地の権利上のランクに関係するその他のこととして、土地改革法はむしろこの種の土地に逆に不利になる事項を規定しており、それはつまり viasii vcani は私有地ではないとされ、ケンススに登録出来るというメリットも提供されなかった。その他そういった土地はその権利上のランクについてただ次のように言い換えることが出来た、その土地は「そのように[特殊な用途で]利用されている」と。これらのことからはっきりと分ることは:この土地は全くもって私権に属するものではなく、土地所有においての行政法上のカテゴリーである、ということである。
こういった耕地は “ex senatus consulto” [元老院の決議に基づいて]割当てられている。その際に与えられた条件としては、この割当てに対して所有権は全く与えられず、また民会の決議によってこの割当てが別の種類の割当てによって無効とされることもあり、つまりは「当面の間での」割当てに過ぎなかった。そこで更に言及されていることは、占有者以外の市民による訴訟手続きが適用出来るかということ――それはまさに全ての耕作されている「場所」を保護していたが――についてではない、ということである。同様にローマでの取引きの形式、つまり握取行為[mancipatio]がその場合に使われたということもあり得ず、また一般的に土地の譲渡が国家当局の関与無しに行われるということが許可されていなかったのであり、それは確実に法規 36) 自体から派生していることであった。この viasii vicani による土地所有が相続の対象となることは、この制度自体の特性から考えて当然のことであった。もちろんこの手の土地所有が相続遺産分割裁判の正規の手続きにおいてどのように扱われたかについては、きわめて曖昧なままのように思える。後にまた論ずることになるが、劣位法で規定されている土地所有についての任意の分割は一般的には許可されていなかった。次のこともまた同様に許可されていなかったと考えられる。つまり正規の判決がそのような土地所有について[の争いに関して]調停する、ということである。というのは判決による調停というものは法的には所有権に対しての判決なのであり、一般的にまずはより古くからある遺言と遺贈の形式と調和せず、また市民の権利として遺言においてそういった土地について直接的に言及するということも適当ではなかったからである。
36) 前注の”…um non abalienaverit” [~が売却されていない限りにおいて]の箇所を参照。
この法律の viasii vicani について規定している箇所には、他の所有形態についての規定に出て来る文言が多く繰り返されているが、しかし遺産が遺言や譲渡によって獲得されること[hereditate testament deditone obvenit]が保護される、という文言は出て来ない。しかし相続財産獲得の許可は、それが Interdictum Quorum bonorum による保護で根拠がきちんとある限りにおいて、賃借人にとっての賃借契約の相続がそうであったように、自明のことであった。もちろん相続順位という点で、無遺言の場合と遺言有りの場合で全く差がなく扱われたということから、一般論として次のことは疑いようがない。つまり市民である遺言に基づく相続人もまた権利の承継者として財産を問題なく受け取ることが出来たということで、その理由は所有しているという状態が相続可能であるということは、法にも規定されている通り、疑いの余地がないからである。しかしながら相続人が多数いた場合には面倒なことになった。相続についての法規制は、相続人が一人でなかった場合には、誰が土地を受け取るかという決定については公権力の介入なしではほとんど不可能であったし、同様の事態はローマ法での全ての同様の関与者に係わる所有状態について繰り返されており、それはドイツ法他の全ての法において同じであった。ここにおいてはまた、行政官の自由裁量に基づいてではなく、こうした状況を取り締まる上での何らかの共通の行政上の原則が存在していてそれに従って行政処分が行われていたに違いないが、それについては何も知られていない。重要であろうと思われるのは、まず何よりも次の問いに答えることで、それは土地に付随している義務が履行されなかった場合に何が起きたのかということであり、つまり義務を強制的に果たさせるための何らかの執行がされたのか、あるいは義務を果たさない者に対してその者に委託された土地を取り上げたか、である。おそらくは両方とも行われていたのであろう 37)、というのもこの二つの直接的または間接的な強制が、最初の文献としては帝政期のものに並記されているのが見いだされるからであるが、その始まりはもっと以前から行われていた制度に遡る:navicularii
である。
37) 当該の法規は ager privatus vectigalisque の所有者に対する権利の剥奪を規定しており、そしてまた虚偽の占有または賃借料支払いの遅延に対しても同様であり、それらは明らかに次の処置からの類推として決められており、それはケンススへの未登録の場合とか、相続の結果引き継いだ何らかの支払い義務についての支払い遅延の場合(後述の箇所参照)とか、しかしそれは賃借料の支払いではない場合のもので、更には購買した者がその代金に対しての担保を提供しておらずかつ支払いが遅れている場合に、即時の現金払い[pecunia prasenti]を求めること、などからの類推である。シチリアにおいては徴税請負人は貸借農民から担保を取ったが、しかし誰に対してであれその者の所有権がどうなっているかということは全く考慮していなかった。
2. navicularii と穀物調達に関する労役
navicularii とは次のような団体のことである。それは外海に面している港のある場所に設置されており、その港に到着した穀物のローマへの輸送を実行しており、また外国からその港まで穀物を輸送する船の調達とその運航にも従事していた。そういった制度が作られた理由を確認してみたい。C.I.L., VIII, 970の碑文が示しているように、誰が制定したかは不明であるが、その内容は transvecturarius et navicularius secundo [陸上・海上輸送を推進する]というもので大体AD400年頃のもので、義務を負わされる者が順番に担当するようになっていた。しかしテオドシウス法典≪438年に公布された東ローマ皇帝テオドシウス2世によるローマ法典≫のXIII, 6 の標題が示しているのは、[そういった義務の]執行[functio]は個々の土地区画に対して昔から[antiquitas]その土地区画の価額に応じて[secundum agri opinionem]課されており(399年の1. 81. c)、そしてその団体のための義務を果たさない場合はその土地は取上げられたということである。
その規定に並記して、Nov. Theodos. 36 は義務を遂行させるための強制執行を許可している。実行義務を果たさない場合に、その当時は移行期間ではあったが、またその者の土地を売却することも許されていた。(引用書1. 8)強制執行がどういった形で行われたかについては 38)、それはまず何よりは帝政期に初めて行われるようになったものである。――テオドシウス法 1 の de aquaed[uctu] の 15, 2 は同様に労役を行わない者の土地を取上げることを許可している。――
38) 強制的に土地を放棄させ返却させること。
我々は第1章で次のことを確からしいとして来た。つまり土地の配分がまた別のケースとして何らかの労働提供に対して行われており、取り分け港がある町において穀物の収穫作業との関連でそれが行われている、というのを見て来たが、しかしそれについての確実な資料は不足している。
ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳(37)P.224~227
「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第37回です。
今、安西徹雄さんの「英文翻訳術」という本を読んでいます。私が既に自分で考えて実行している翻訳の方法:(1)文章の順番を変えないで、思考の流れを元の文章のまま訳す。(「次のことは確かなことである。つまり…」のように訳し「…ということは確かなことである。」という訳にしないこと)(2)指示代名詞はなるべくそれが指しているものを繰り返して訳す などが重要なルールとして挙げられていて我が意を得たり、という感じでした。
その本に触発されて、今回はなるべく日本語としてこなれた訳になるように努力しましたが、それに成功したかどうかは自信がある訳ではありません。まあこれまで訳した分の見直しも含め、最後まで翻訳の質の向上を図りたいと思います。
====================================
まずは次のようなことは事実上不可能であった。つまり土地を借りたいと思った者がその土地には住んでいない場合で、かつそのような広大な土地の複合体の全体の権利を与えられるのではない場合に、その対象の土地を実地に検分するためにそこに行ってみる価値があると考え、それを実際にやってみる、ということである。しかしながら次に:これについては後で更に述べるが、アフリカにおける国有地について、643年の土地改革法によって 26) 公有地の賃借人のためにある一定の貸借期間分として先払いとして支払う賃借料の総額が決められたということは、その場合それは該当の領域の土地についてそれが法によって規定されていた性格を変更することなく決められたが、――そのことは当時の競売による新規譲渡とどう矛盾しないように行われたのであろうか?≪競売ということは貸借料額は入札または応募によって行われその時々で異なる筈であるので、土地改革法でそれが決めらたというのは矛盾する。≫そしてまた次の事実はどう解釈すべきであろうか。つまりカンパニアの公有地では部分的に私的な占有によって元々公有地であるということが隠蔽されていて 27)、もし全ての土地区画が明らかに規則的に5年毎に新たな賃貸契約が行われていたのであれば、それは果たして矛盾なしに実行可能であったのだろうか?
26) C.I.L., I の Z.85, 86 の箇所についてのモムゼンの解釈による。
27) これまでに何度も引用したリチニアヌスの文章(前掲:p.123{原文})を参照。それ自体が意味しているのはまた:その該当の公職人が賃借しようとする農民に対して公定価格でそれを行ったということである。しかしその場合競売によって行われたのではなかったということである。
監察官による賃貸が経済上もたらした影響
しかしながら自然なこととして考えられるのは、このように(国家によって賃貸されるようになった)対象の土地領域においての所有状態の革命的な変化は、たとえそれが当面影響する範囲が特に広いものではなかったとしても、それが継続して行われる性格のものであるということは、むしろそれだけ人々が感じ取るようになったに違いない。ゲマインデ諸団体を法的に取り潰した結果、事実上時の経過に連れて古い諸ゲマインデの成員であった人々がお互いに混じり合うという結果になった。というのもキケロが次のように述べているからである。つまりレオンティノイの耕地においては、公有地の賃借人の下に、更に元々あったゲマインデ出身である家族が(土地を又借りして)暮らしていた、ということである 28)。
28) ウェッレス弾劾演説 1.3, 109
更にまたもう一つの経済的な帰結は「事物の本性」≪既出≫に沿うものであった。それはそれぞれの広大な領域の売却(賃貸)においてより好都合なことであったのであり、それは(広大な)公有地をごく小さな面積の土地に分割し、それによって多くの小規模の賃借人が入手しやすいようにし、それは監察官がローマにおいて、公有地について競売的なやり方で賃借人を募集することを真剣に試みた時に実際に行われていたことである。それ故に一般的に所有状態が時の経過の中で変わっていった限りにおいて、(分割された多数の土地をまとめて借りる)大規模な賃借人の数が増加していくという傾向が強く出てきており、それと適合していることは、キケロのウェッレス弾劾演説の中 29)シチリアのゲマインデにおいて賃借人として土地を所有している者の数がそれほど多くないと言及されていることである。
29) ウェッレス弾劾演説 1.3, 120
その他(地方総督の)個々の行政上の失策は直ちに小規模な土地所有者(賃借人)への圧迫につながったし、そしてその結果当然のこととして大規模経営者の数の増加 30) となった。
30) もちろんこの後者の現象はまた、所有する耕地がローマの公有地にはなっていなかった課税対象の諸ゲマインデ(の土地)にも関係することであった。キケロによる(前出の)申し立てによれば、ウェッレスによる統治は賃借人の減少という結果につながっていた:レオンティヌス人の土地においては84人が32人に減少し、ムーティカ人≪現代のイタリアのシチリアのモディカ≫の土地では188人が88人に、ヘルビタ人≪シチリアの中の町≫の土地では250人が120人に、そしてアジーク人≪シチリア島中央部の町≫の土地では250人が80人にまで減少していた。減少した人数の内、何パーセントが小規模経営者を犠牲にしての大規模経営者の増加によるものか、あるいは何パーセントが耕作地放棄によるものか、もちろん不明であるが、しかしキケロが深く考えないで全体の減少は後者によってであるとしているのは、正しいとは認め難い。
そしてローマの地方総督の行政において一つも失策が無かったなどということがあり得るだろうか?≪ウェッレスの例にも見られるように、共和制時代の属州の総督の地位は不正蓄財の温床となっていて、後にアウグストゥスが税の徴収を専門の官吏が行うように改めるまでそれが続いた。≫そういった類いの大規模賃借人達はもちろん次のことを強く望んでいた。それは彼らの土地所有をまた長期貸借において法的に保証してもらうことであった。こうした連関については、ヒュギヌスの次の箇所(p.116、ラハマン)において確認することが出来る(モムゼンの R. Staatsr. II. p.459 での補完に基づく):
Vectigales autem agri sunt obligati, quidam rei publicae populi Romani, quidam coloniarum aut municipiorum aut civitatium aliquarum, qui et ipsi plerique ad populum Romanum pertinent. Ex hoste capti agri postquam divisi sunt per centurias, ut adsignarentur militibus, quorum virtute capti erant, amplius quam destinatio modi quamve militum exigebat numerus qui superfuerunt agri, vectigalibus subjecti sunt, alii per annos (quinos), alii[vero mancipibus ementibus, id est conducentibus], in annos centenos pluresve: finito illo tempore iterum veneunt locanturque ita ut vectigalibus est consuetudo.
[使用料支払い義務のある土地とは、次のものに対して支払い義務がある土地で、あるものはローマの人民の共和国に、またあるものは植民市に、さらにあるものは何らかの地域コミュニティに対して支払い義務があり、中でもそういった土地自体の大部分はローマの人民に対して義務があるものである。敵国を占領して得た土地は後に、その武勇によってその土地を勝ち取った兵士に割当てるためにケントゥリアで分割され、(元々割当て用として)指定された全面積より大きいか、あるいは兵士全員に割当てた分以外の面積の土地は余った土地とされ、それらの土地に対しては誰かが使用する場合には使用料の支払い義務が課され、ある者には5年の期間で賃貸され、またある者には[間違いなく manceps に対して売却され、それはつまり{握取}契約によってという意味であるが]、100年間以上の長期間で:その期間が終了すると再び売却または賃貸契約され、それ故に使用料支払いについては慣例的なルールとなった。」
公有地における大規模賃借人
(ラテン語原文の引用で)[]内の部分はモムゼンが抹消したものである。≪握取契約は本来所有権の完全移転のためであるのに、この場合はあくまで賃貸契約で国家が持ち主であることが変わらないのが矛盾すると考えたのであろうか?≫この抹消について同意する場合、私はそれに賛成であるが、その場合は次のことも最低限読み取ることが出来ると思われる。それはつまりまた、”finito”以下の最後の文[訳文で「その期間が終了すると」で始まる文]はただ長期の方の賃貸契約についてのみ言っていると解釈した場合、2種類の賃貸契約が言及されている箇所が言っているのは、片方は法律上では5年間という短期間に制限されていて、他方は100年以上もの長期間が許されている、ということである。この長期間の方については、賃貸契約が大規模な引き受け者、つまり mancipes [manceps、(握手行為による)契約者]に、それ故に競売方式によって行われたのであり、同様に契約期間が満了した場合の再契約も最初の時と同じやり方で行われており、これ以外の場合でも公有物についての賃貸契約についてと同じであったと考えられる。以上のことは先の文章に続く数行の内容と矛盾していない:Mancipes vero, qui emerunt lege dicta jus vectigalis, ipsi per centurias locaverunt aut vendiderunt proximis quibusque possessoribus. [契約者たちは実際のところ、決められた法律によって地代の徴収の権利を獲得し、その者達はケントゥリア単位でお互いに隣接している占有者のそれぞれに、それを再度賃貸または売却した。]つまり大規模な公有地の賃借契約者達がその借りた公有地を更に二次賃借人達に譲渡し、そしてそこでまさに行われていることは、大規模賃借人達がその購入した権利(jus vectigalis)をあたかも元々それが自分達の権利であったかのように再度賃貸契約している、ということである 31)。
31) このような賃貸契約をケンススの期間である5年の期限で行ったということは、監察官の意向によるものではなく、元老院の決議によるものと思われる。しかしそれは法律ではなく、というのはそういう法律はこの場合以外に trientabula ≪既出、国の債務の1/3を土地で返すもの≫の制度の全体設計をする際に初めて本当に必要になったに違いないからであり、というのもその場合は常に債権者に対して[土地による]返済を[法律により]承認させる必要があって、官庁への土地の後からの取戻しについての承認を取り付ける必要があったのではないからである。
――その他にも賃貸契約の2種類のやり方の間で同じような対立が起きている:競売方式で5年間の期間で契約者に貸与されるやり方と、そういった短期の制限のない公有地の賃借人(「(5年を超える)長い年に及ぶ賃貸契約」[annua conductio])として貸与されるやり方と、またそれ以外にウェスタの処女≪神に使える乙女で30年間処女であり続ける必要があった≫に[その犠牲の代償として]与えられた土地についてのやり方について、ヒュギヌスが言及している(p.117, 5ff)。――公有地賃借人の実際の状況の全容は、先の箇所で一度述べようと試みたが、また彼らの権利がどう守られていたかを見た場合、私法上の権利[私権]が与えられていた、と見なすことが出来る。市民の訴訟手続きにおいてはそういった賃借契約付きの国家の土地についての占有として、その状態に対してのある種の侵害に対しての禁止命令によって保護されていた。Interdictum de loco publico fruendo [公有地の違法な使用を防止する命令]32) がどれくらい前からあったかについては不確かである;それはソキウス≪ソキエタースの成員≫という概念が法規定の中に採用されたことが示しているのと同じく、本質的にはその命令は大規模賃借人の、つまり企業家達の利益に資するために発せられたのである。≪ソキエタースは複数の人間が共同で何らかの経済行為を行う目的で結成されるものであり、それと同じく企業家のための命令であるとヴェーバーは言っている。≫
32) Quo minus loco publico, quem is, cui locandi jus fuit, fruendum alicui locavit, ei qui conduxit sociove eius e lege locationis frui liceat, vim fieri veto.[ある公有地について、その賃借権を持っている者がそれを誰かに更に貸した場合、その(新たな)契約人や共同の借主がその賃借契約に基づいてその土地を使用することを暴力によって妨げることを禁ずる。] (レネル≪Otto Lenel、1849~1938年、ドイツの法学者・法制史家》、Edikt p.368)
こうした大規模賃借人にとってそういう禁止命令は望ましいものであった。何故ならば、既に見て来たように、彼らは賃借した土地を次の二次賃借人に譲渡し、そしてそれらのそれぞれの土地も、かつその土地全体も自分で経営(耕作)しようとはしなかったからであり、それ故「賃借契約をしていること」[frui e lege locationis]が保護の対象であり、「占有していること」が対象ではなかったのであり、さらにまた契約の直近の年度における所有状態の保護は、占有状態が彼らからみて[長期間]継続したことに見られるように、その下位の賃借人の所有状態に関係なく行われねばならなかったであろうからである。 禁止令はそれ故に大規模賃借人に対しては(実質的に)時間的な制限無く保護を与えたが、その一方で(その下の)小規模賃借人に対しては占有についての禁止令はただ直近の契約年度についてだけその所有状態が保護される、としたのである。小規模賃借人にこの禁止令が等しく効力を持つものであったかどうかということは、言い回しの上ではそう解釈することも出来ようが、実際には疑わしい。もしそうでなかったとしたら、通常の小規模賃借人は公有地において市民の権利としては、既に述べたように、ただ占有状態のみが保護されたのであり、そして占有状態の保護が相続人に対して相続財産を違法な形で奪われることを防止するのに有用である限りにおいて(D.1. §44 de vi 43, 16)、相続人への事実上の財産の移行がまた保護されたのである。その他ここでもまた、公有地に対しての通常の占有の場合と同様に、Interdictum Quorum bonorum[法務官による相続財産の引き渡し命令]が関係している。こういった[公権力によって保護された]譲渡は当たり前のことであり、というのは賃借契約というものはそれ自体は単純に移転するということはなく、国家権力に対してはより不安定なものに過ぎなかったし、監察官ないしは執政官のみが別の賃借契約人を指定出来たからである。実務的には賃貸契約関係はこれまで述べた結果で行われた結果、上位の公職人は賃貸契約の相続人との再契約については、特別な場合にのみそれを拒否することが出来たのであり、それは例えば多くの相続人がその権利の継承について、誰がそれを受けるのかについて合意がなされておらず、そしてそれによって国家は誰と賃貸契約を再度締結するかについて疑いがあったような場合である。全く同様のやり方で、賃借中の土地をどのように賃借契約者から[相続人などに]譲渡するかの手続きも整備された。純粋に法律上にはそういった手続きに関する規定が存在していなかったことは、敢えて言うまでもないことである。実務上では、権利の相続人[Remplaçant、フランス語で代理人、代表者の意]33)が、一人の者に決められていた場合は、公職人はその者を賃貸契約者として認めないことはなかった。
33)キケロのウェッレス弾劾演説 3, 120 で賃貸契約の相続人に対して “vicarii” [代理の]という表現を用いている。
lex censoria censoria≪成立年不明、監察官制度が出来たのがBC5Cなので、その後とすれば共和制の中期。監察官が公共財や公有地を貸し出すことについての規定と思われる。≫がそういった相続人への賃借権の譲渡について規定していたかどうかは全く不明であるが、公職人達はこの場合についての間違いなく存在していた諸原則を遵守していた。というのもそういった状況には一般論としてローマ社会の特質を良く示しているものであるからである:ある規定すべきことについて、それに対して市民の権利に関する法文が存在していないことは、そのことが直ちに公職人が好き勝手に振る舞えたということを意味せず、行政上の様々な根本原則がそこでは目差すべき尺度として使われていたのであり、そしてモムゼンが正しく注記しているように、関係者はある規則的に発生する状況に対しては、それを悪化させるのではなく良い方向に持っていこうと努めていたのである。
ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳(36)P.220~223
「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第36回です。
ようやく折り返し地点(50%)に到達しました。まだまだ先は長いですが。
ここの部分にはキケロの著作が登場します。キケロという人は文章は見事なのですが、生き方という意味ではあまり好きになれない人です。ここに出て来る「ウェッレス弾劾演説」も純粋に社会正義のためというより、自分の弁護力のアピールという印象をどうしても受けてしまいます。ただ、この演説のおかげでその当時の属州の実情が良く分かるみたいですが。
=================================
ビファンク権はイタリアにおいては ager publicus によって消滅し、それが再度出現するのは辺境の属州の中の Rottland≪荒れ地や森林を新たに開墾した土地≫と荒地においてのみであった(C. Th. 1 de rei vindicatione 2, 23)。ager publicus の運命は、それが開墾出来る土地から成り立っている場合は、イタリア人のために用立てるよう定められた。最後の特筆すべきまとまった土地をカエサルが自分の軍団のヴェテラン兵に割当てた。そして subseciva ≪の占有≫については、既に詳説したように、ドミティアヌス帝がそれを完全に無効にした。それ以後は本質的にはアプリア≪現在のプーリア州、イタリア半島の踵の部分≫に向かう公共の小道が通っている牧場と 14a)、個々の[土地ゲマインシャフトの中にある]放牧地のみが ager publicus 以外の土地として留まった。しかしその時までにはイタリアでは更に別の、今やここで検討すべき所有形態が発達していた。
14a) 碑文としては例えば、C.I.L., IX 2438, 更にはウァッローの res rusticae II, 1がこのことに言及している。
その他の公有地の所有の諸形態
全てのこういった所有形態において何はさておき共通していることは、それらの土地に対する保護はただその場所[locus]に対してのみ与えられた、ということである。古い時代の占有については、次のことは実務的により大きな意味を持っていたに違いない。つまりその占有はただ法務官の権限に基づいて相続財産と認められ、何故なら遺産に対しての法的な保護はただ法務官による相続財産引き渡し命令[Interdictum Quorum Bonorum]の中でのみ成り立っていたからであり、それ故に遺産相続権の認可は法務官のさじ加減次第であったのである。私にはこれは本質的なことではないが、部族や男系氏族に従属しているフーフェの権利から自由な善意に基づく法定相続権の発生についての一つの説明になっているとは思われる。土地貴族については、法務官の布告の中で、その相続のやり方については自分達の裁量によって決定することが出来るとされていた 14b)。
14b) この手段によって相続関係の中で実際に行われた専横的な処置については、キケロの「ウェッレス弾劾演説」≪BC73年から3年間シチリアの総督であって私利を貪ったウェッレスをシチリア島民からの依頼でその当時の担当財務官であったキケロが告発したもの。≫の第1巻と比較すべきである。
個々の場合においては所有状態の法的な性質については様々な発展段階が存在していた。
戦争によって獲得した土地と公的な土地一般の民族ゲマインシャフトの側からの占有による利用以外に、時が経過するに連れ国庫の利害に基づく財政上の理由からの土地の売却が登場した。収穫物全体に対しての一定割合の貢納を条件とする占有を放任したその元々のやり方は、[国家による]この目的に適合した土地のシステマチックな売却及び賃貸しに取って替わられた。その最初のものについては以前(第1章で)取上げたが、これについては更に後述する;ここにおいて我々は賃貸しの農地、つまり ager vectigalis の様々な実際の例における本質的な傾向の観察をひとまず保留しておいて、まずはそこにおいて属州での所有状態の変動が見て取れる権利形態の探求に向かう。
ケンススを実施する場所の決定
次のことは周知のことである。つまり公的な土地を個人が利用するか農作物を栽培する目的で譲渡する、という形態において、それが幾ばくかの(ほぼ例外なく年額での)賃借料の支払いまたは収穫物(の一部)を納めるのを条件とするというのは、ケンスス(への登録)によって取り決められるものであった。この手続きについては2つのステップに分かれていた:まずは耕地の、元々そこを耕作していた農民への(ケンススの登記上の)譲渡と、次にその公有地の総面積に対しての契約によって定められた賃借料による賃貸しの開始である。ここで我々に興味深いのは、この2つのステップの最初のものだけである。公有地の賃貸しの実施は、ローマ国家によって公有地についてのケンススの登記内容(の書き換え)に基づいて行われた 15)。
15) Tabulae censoriae、プリニウス、H.N.18, 3,11。キケロ、農地法について、1,2,4。
こうした個々の土地断片の集合について、全ての個々の土地区画にそういう区分状況を書き込んだ地図の作成は、対象となる土地が恐ろしい勢いで拡大した結果、ただより大きな単位の土地に対してであっても最初から大きな障害として立ちふさがっていた 16)。
16) このことは、C.I.L., VI, 919にて言及されている。帝政期においては、例えばウェスパシアヌス帝の下で(ヒュギヌス p.122, 20)可能な範囲でまあまあ正確である略地図が作成された。
特に収穫高の多い公有地で、そこで(略地図程度では)何か不都合があることが判明した場合は、例えば地味豊かなカンパニア地方≪現在のナポリ周辺、カンパニア州≫においては、第1章で引用したリチニアヌスが示しているように、それ故、測量人はその土地の測量と地図の作成のために土地の中を歩き回ったのであり、そこで既に言及されていたことであるが、そこで使われていた測量の方法は原則的には、実際は全ての場合ではないにせよ、strigae と scamna を使ったものであった。そういった地図が作られていた場合は、その土地での賃貸しの実行は間違いなくその地図に基づいていた。法的には賃貸借関係は各年の3月15日まで継続し、それは[前年の]その日に新しいケンススの登録の適用が開始されてから1年間ということである。この[賃貸借契約の]公的な適用の開始は、モムゼンがそれについて表現しているように 17)、あたかも全ての国家による賃貸借契約の[前年の分の]解約告知としての役割を果たしていた。
17) Staatsr. II, p.347,425 の注4。
実際の所は、賃貸借契約による土地の契約者ないしはその家族による所有は、非常に規則的なこととして、もっとはるかに長い期間継続するものであった。次のことは事物の本性≪既出≫に沿っている。つまり、形の上ではもしかすると新規の賃貸借と考えられたケンススに基づく賃貸しが、実際には圧倒的に多くの場合部分的には既に存在していた賃貸借契約の改定 18)という性格を持っており、更に別の部分では小作人の土地の所有状態の整理という性格も持っていたと考えるべき、ということである。
18) モムゼンが(Staatsr. II, p.428)a.u.c.585/6年の監察官についてのリウィウスの報告(Liv. 43, 14ff)に基づいて主張しているように、既に存在している契約の改定は、その他の監察官による「授業料徴収行為」≪Tuitionsakten, 全集の注によると監察官がゲマインデに対して収入と支出の規制を行ったことをモムゼンがこう表現したもの≫の先駆けとなった。
土地の所有者達に対しての調停と大規模な賃貸料の独力での引上げは、通常の場合は監察官にとっても、丁度フランク王国の国王が一度家臣に与えたレーエン≪土地と役職の両方の意味。フランク王国ではカール大帝の頃から一度家臣に与えられたものが世襲の特権と化する傾向が強かった。≫を取り戻すことがそうであったように、どちらも同じように困難なことであった。というのは ager von Leontinoi ≪レオンティノイの土地、レオンティノイは現在のレンティーニでシチリア島東岸部のコムーネ。元々はギリシアの植民市に由来する。≫というものがあり、それはシチリアの公有地の中で最も重要な部分であったが、事実上はその土地を代々所有している小作人の家族のものとなっており 19)、そしてそのことがより明白にするのは、その全領域がわずか82人に対して賃貸しされている場合に 20)、その者達の各人についてはそれ故、監察官でも無視し得ないような財力を持っていたことを意味したに違いない、ということである。
19) キケロのウェッレス弾劾演説 3, 97、及び3, 120を参照。そこで主張されているのはウェッレス≪ガイウス・ウェッレス、C.114~43BC、シチリア総督の時代に農民から不正に富を強奪し、農民からの訴えを受けたキケロによって告発された。≫の行政上の不正行為によってレオンティノイの公有地の農民が[84人中の]52人減らされており、つまりその52人の農民はそこから追放された、ということである。”ita…, ut his ne vicarii quidem successerint” [それ故、(52人の農民が追放され)、その後を継ごうとするものも誰も居なかった]原則であったのはそれ故に所有状態をそのまま維持することであった。
20) キケロのすぐ前の引用箇所。
カンパニアの耕地はそれに対してより小規模な小作人によって所有されていたことが多かったように思われるが 21)、その小作人達の有能さをキケロが称賛している;しかしそこでもまた、公有地の小作人達はその多くが生まれてからずっと賃貸借契約をした地所にて過ごしていたのである。
21) キケロ、農地法について、2, 31, 84。
そのことはまた発展の道筋にも沿っていた。監察官の管理する賃貸借は収穫物の一定割り合いの貢納を条件とする占有と同じ位置もしくはそのすぐ隣に来るものとして登場した。それは一般的に言えばまずは国家によって整理され規制された形態の占有であり、定期的な改訂を伴うものであった。シチリアの公有地の賃貸しは特に耕地を元々の所有者 22)に返還する形式として把握され、また測量人達も占領された領土の公有地の賃貸しの形での利用について、何も所有状態の革命的な変化を思わせるような表現は使っておらず、それについて”agrum vectigalibus subjicere”[その土地を使用料付きのものに組み入れる]と表現している 23)。
22) キケロのウェッレス弾劾演説 3, 13。
23) ヒュギヌスのp.116。
それ故にこれらの処置は、採用された形式と、ひょっとするとわずかな額であったかもしれない使用料という点で見た場合、トリウスが(公有地を不法に占拠した形の)私有地を使用料支払い月の賃貸しの公有地に変えた時に、ager publicus に対する占有についての権利状況の改善とみなすことが出来るであろう 24)。
24) トリウスがつまりそういう風に変えていたら、ということである。しかし後述の箇所で、使用料の強制による権利状態の変更については更に先へ進んだ、ということが確認される。
それ故に私には、マルクヴァルトの説明である、賃貸期間がより長く設定されたことによって公有地における賃貸対象の土地について相対的に安定した性格が得られた、については全く根拠不明であるように思える。現時点でただ記憶に留めておくべきなのは、ここで扱われているのは一般的にある本当に形だけの、個々の賃貸借対象区画に対する新規の使用料設定ではなく、法律上期間が終了する契約 24a) がその規則によって単純に確認されたに違いない、ということである。
24a) 一般的にはなるほどこのことは暗黙の現状維持[relocatio tacita]≪明示的な更新手続き無しに契約が自動更新されること≫によって行われている。”Locare”[契約する]の意味はモムゼンの訳によれば「保管する」「配置する」ということであり、その含意としては、監察官が規則的に土地を、それらは「配置」され、現状のままに留められた、ということである。その他公的な業務を他人に引き継ぐということ自体に関しては厳格に取り扱われていた。(キケロ、ウェッレス弾劾演説 2,1,130)
というのは私には次のことを前提にするということを無理に想定する必要はないと思われる。つまり国家全体での個々の賃貸対象の土地について、それぞれの賃貸期間が満了した後に、競売によるような新規の授与が行われたに違いない、ということであるが 25)、そうではなくむしろ、私はそう信ずるが、決定的に様々な理由がそれと反対のことを語っている。
25) キケロによる注釈(農地法について、1.3.7と2,21,55)は授与に基づく賃貸しが引き合いに出されている。公有地におけるこういったやり方の賃貸しが例外なく等しく行われていたと考えることは出来ないということは、疑いようがない。または公有地を賃借する者はまたその土地に対して保証人や担保を差し出さねばならなかったのであろうか?監察官が公有地の賃貸しを競売のようなやり方で行い得たということは、間違いなく監察官が賃貸借契約を大規模にかつ長期間に行おうとするものと締結しようと意図した時には、そうするしかなかった、というのが非常に確からしいことである。
マイツェン門下の二人

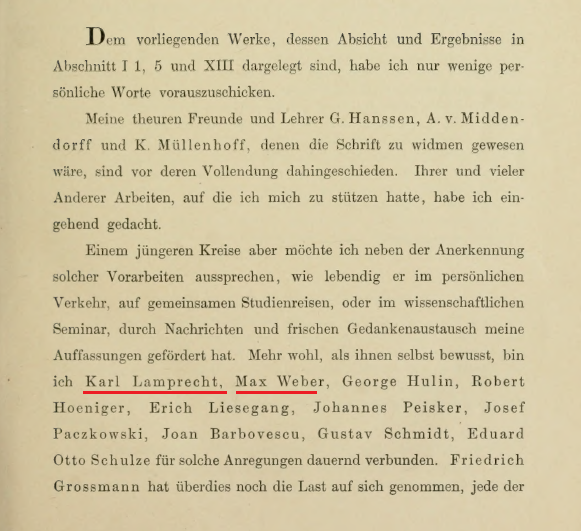 ヴェーバーの「ローマ土地制度史」を訳していて、あまりにもドイツのフーフェ、マルク、アルメンデとかゲノッセンシャフトとかを無邪気にローマ史に適用するのが気になっています。これは明らかにヴェーバーの師であるマイツェンの影響だと思いますが、それを確認したくて、マイツェンの”Siedelung und Agrarwesen”をAmazonで購入しました。ところが、販売ページにはそんなことは書いてなかったのに、届いたものは第3巻だけの内容でした。これは統計とか地図、家屋の絵なんかの資料集みたいな巻で、これはこれで面白いのですが、マイツェンがどういうことを述べていたかは、1、2巻を参照する必要があります。それで調べていたら何とWeb上にフリーのテキストがありました。ドイツ語のWikipediaで、August Meitzenの項の下部にリンクがあります。
ヴェーバーの「ローマ土地制度史」を訳していて、あまりにもドイツのフーフェ、マルク、アルメンデとかゲノッセンシャフトとかを無邪気にローマ史に適用するのが気になっています。これは明らかにヴェーバーの師であるマイツェンの影響だと思いますが、それを確認したくて、マイツェンの”Siedelung und Agrarwesen”をAmazonで購入しました。ところが、販売ページにはそんなことは書いてなかったのに、届いたものは第3巻だけの内容でした。これは統計とか地図、家屋の絵なんかの資料集みたいな巻で、これはこれで面白いのですが、マイツェンがどういうことを述べていたかは、1、2巻を参照する必要があります。それで調べていたら何とWeb上にフリーのテキストがありました。ドイツ語のWikipediaで、August Meitzenの項の下部にリンクがあります。
https://www.archive.org/details/siedelungundagra01meituoft
https://www.archive.org/details/siedelungundagra02meituoft
それで序文をちょっと眺めていたのですが、マイツェンは気さくな人柄なのか、同僚とか自分の先生への感謝だけでなく、多くの年下の自分の学生にも感謝の言葉を贈っています。一緒に調査旅行に行ったり、セミナーを開いたりしていたみたいで、何だか楽しそうです。ヴェーバーはその2番目に言及されていますが、トップに言及されているのが、何とカール・ランプレヒト!ヴェーバーより8歳年長ですが、この二人がいわば同門というのは知りませんでした。ヴェーバーは、いわゆる「ランプレヒト論争」の際にランプレヒトを典型的なディレッタントだとか山師と呼んで批判しています。
本文はちょっとだけ眺めただけですが、いきなり先日調べるのに苦労したReebning(デンマークでの耕地整理)が出て来ましたので、やはりヴェーバーへの影響は大きいようです。(念のため、この本の出版は1895年で、ヴェーバーの「ローマ土地制度史」より後です。第3巻でヴェーバーが附録で付けたアラウシオの耕地図をマイツェンも引用していて、ヴェーバーが使ったことにも言及しています。)
ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳(35)P.216~219
「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第35回です。ager comascuus についての議論の続きです。ここで気になるのが、ローマにおける牧畜の程度です。私は牧草地というのを農耕に使用する牛などに草をやるという風に理解していますが、ローマにおいてどの程度いわゆる牧畜業が行われていたかは、確認する必要があるかと思います。従来は古代ローマではあまり肉食は行われないとされていた一方で、牛乳やチーズは主食の一部として重要であり、また帝政期に入ると食の内容が高度化し肉食の割合いも増えて行ったということのようです。
それからここにアッピアノスのギリシア語のテクストの引用があります。ギリシア語のアクセント記号の入力は非常に大変なのですが、今回、以下の手順で比較的楽に行うことが出来ました。
(1) アクセント無しのテキストを、ChatGPT4oにアクセント付きのテキストに変えてもらう。
(2) (1)で出来たアクセント記号が付いたギリシア語の文を同じくChatGPT4oにすべてHTMLにおける文字参照(コード参照)に変えてもらう。
==================================
土地資本主義
確からしいこととして――そのことは当時の(土地を巡る紛争の)和解についての性格全てに当てはまることであるが――当時の全ての市民の公共の土地への関係における形だけの権利の平等が、自由な牧草地利用を禁ずる制限撤廃の許可と同じく自由な占有の許可によって作り出されており 10)、そしてこのことにより当時の人々は少なくとも理論的な形で導入された土地税の支払いによって、このような類を見ない(土地)資本の獲得の奨励をカモフラージュしようと試みたのである。というのも、この自由な競争が小農民の土地所有者にとって有用だったのではなく、ただ大資本家、つまり世襲貴族とまた(裕福な)平民にとってのみ有用だったということが、しばしば強調されている。そういった自由競争は事実上は土地制度の領域における全く制限の設けられていない資本主義を意味するのであり、それは歴史の中でかつて実際に行われていたのであり、そしてこのことは既に述べた中世末期におけるグルントヘル(大地主)による土地の不法獲得と囲い込みとの対比という意味では、量的にも質的にもほぼ遜色の無いレベルにまで達していたのである。
10) というのも平民に対して、リキニウス・ストロ≪Gaius Licinius Stolo、 正確な生没年不詳、BC4世紀のローマの執政官・護民官。護民官の時にセクスティウスとリキニウス・セクスティウス法を制定した。その法律では500ユゲラ以上の土地の所有が禁じられた。≫が自分自身が制定した法律による土地の占有の上限を超えたことにより罰金を払ったという伝承が示しているように、決定的なこととして考えられるのは、既にそれが起きる以前の時代で占有ということが許可されていたに違いないということである。
経済的かつ社会的な階級の利害とこの自由競争の結果が一緒になって示しているものはまさに、ローマ史を通して一般的に、赤裸々な人間の姿であり、それは古代における政治家と近代の社会史家に等しく利点を提供しているのであるが、それは古典古代のファッションの実態が同時代の芸術を理解する上で有用であるのと同様である。それから ager publicus を巡っての階級闘争がより一層激しい段階へ突入したということは良く知られている 11)。リキニウスの提案は占有の上限を500ユゲラにすることでこれを是正しようと必死に努力していたものである 11a)。
11) ここにおいてはこの階級闘争の個々のケースについて追いかけることはしない。何故ならば土地制度史という見地に立った場合、様々な事実を見出すことが出来るのは確かであるが、それによってこれまで知られている階級闘争の実像について何も新しいものを付け加えることは出来ないからである。
11a) もしかするとこの時に初めて牧草地の使用料(税)というものが導入されたのかもしれない。いずれにせよ伝えられているのは、リキニウス・セクティアヌス法はまた非課税の家畜の飼育を伴う耕作の上限――牛・馬の場合は100頭、鶏などの小家畜の場合は500頭(羽)――を導入しているということである。(参照、アッピアノスの引用済みの1、8)。≪鶏はインド→エジプト→ペルシア→ギリシアのルートで、ギリシアにBC9世紀頃伝わり、その後ローマに入った。≫
公有地の分割割当てを求める声は、共和政の時代を通じて一度も社会から消えてなくなることは無かったが、しかしその声を上げていた多くの無産者が、その元々の性格を次第に失っていった時、その声に応えてローマの内部でその認可が行われることは無くなっていた。以前は(利用出来る)平地に対して植民の人数の過剰という状態があり、そのために廃嫡または遺産分割によって零落した農民である土地所有者の子供達は、耕地の新規分割割当てによって自分自身による耕作の新規開始と、また tribus rusticae に受け入れられることで、彼らの親達が属していた adsidui ≪税を納める義務のある一人前の市民≫に復帰することの可能性を得ようと必死だったのである。ただローマが大都市的な性格を強めていった結果、プロレタリアートはそのエネルギーを増大させていくことが出来なくなり、彼らは近代的な性格での都市の下層民として十把一絡げの状態になっていき、彼らについては土地所有者の身分上の体面という意味は加速度的に失われてしまったのであり、――そうした変化は同様の状況の場所ではどこであってももはや時間の問題であったことであるが、――その者達にとっては農民としての生計の基盤である土地が、より勢いを増しながら(他者の所有物へと)吞み込まれていったのであり、そして彼らの状況により大土地所有のための耕地整理の推進に対抗して自分の土地を守り抜く、というエネルギーが奪い取られたのである。割当てられた土地は色々な意味で投機の対象となり、植民者の所有物から換金の対象に変わり、その目的は大都市(居住者)の(投機という)享楽のためであり、グラックス兄弟、スッラ、そしてカエサルによる、新規植民者が入手した土地の売却についての購買の上限を設けることで制限しようとする試みは、常に失敗に終らざるを得なかった。その理由は、その政策が関係者の利害を、敵対者(世襲貴族)の利害と同じく、著しく損ねたからであり、また確からしいこととしてこの種の土地はケンススへの完全な登録を行うことが出来ず、それ故所有者の政治的な意味での階級としての権利を高めることがなかったからでもあった 12)。
12) 土地改革法の第38条に確かに起因していることである、グラックス兄弟が ager optimo jure privatus ≪非課税の私有地≫についてケンススへの登録を認めたこととはまた別のことである。しかし残念ながら確実なこととして、少なくともケンスス制度の何らかの部分的な改革について、つまりフーフェの土地の登録からある種の財産登録という変化については、何も知られていない。おそらく可能性があると思われるのは、その場合でもクイリーテース所有権による土地の占有はどういう形でも許されていなかったのではないか、ということであり、しかし私が確かなこととして考えたいのは、この種の占有はいずれの場合にも tribus rusticae における assidui ≪軍役を負担する市民≫への登録にはつながらなかったのではないか、ということである。キケロのフラックス弁護の80にて、ある者が小アジアのアポロニア≪現代のトルコのアナトリア半島の北西部にある湖とその周辺≫に土地を所有していて、それがローマでケンススに登録されたことによって、その者が利益を得た、とある。しかしキケロはその弁明に対して次のように異論を唱えている: Illud quaero: sintne ista praedia censui censendo? habeant jus civile? sint necne sint mancipi? subsignari apud aerarium aut apud censorem possint? In qua tribu denique ista praedia censuisti? [私は次のことを問う:その農場は(本当に)ケンススに登録されたのか?それは(本当に)法的な権利を持っていたのか?それは正式な売買手続き(mancipatio)に拠って獲得されたものかそうではないのか?それは国庫に登録されたのか、あるいはケンススに登録される形で獲得されたのか?どの部族にてその農場は実際にケンススに登録されたのか?]
占有と ager compascuus の終焉
土地政策と社会政策の性格を持つ最後の大規模な土地分配の試み、つまりグラックス兄弟の改革によってもたらされた全ての土地所有に関係することがらの大混乱は、先に見て来たように、次のような結果をもたらした。それは3つの新しい土地法であり、その最後のものが u.a.c. 643年の土地改革法であったが、それはそれまでの占有を、ケンススへの登録の許可を与えることと ager privatus の全ての他の特権をそれらの占有された土地にも許可することによって最終的に認可したのであるが、それはつまりグラックス兄弟によって推進された植民者の土地の売却制限 13) をケンススへの登録の許可という形で取り除いたのである。
13) ケンススへの登録許可は3つのここで想定されている法律の最初のもので既に認められていた。643年の法律はただこのことを間違いのないこととして再確認したのであり、その中で――これが第8条のまさに意味する所であるが――そういった占有された土地に対して正規の売却手続きを行う権利を付与したのである。
未来に向けて土地改革法は更にまた農民のアルメンデと徴税権の古くからの対立も取り除き、その中でその法はそういった形でまだ残っていた ager publicus の残りの部分について compascua として使うことと占有を許可すること 14) の両方を等しく終了させたのである。(25条)
14) グラックス兄弟は周知のようにリキニウス・セクスティウス法に修正を加え、その法で認められていた公有地の保有上限500ユゲラ以外に、息子2人まで各250ユゲラを追加で保有することを認めたが、更に修正を加え、その他、他の全ての占有を禁止した(C.I.L., Iのモムゼンの土地改革法への注記)。しかしながら後になって占有の認可が再度討議され、643年の土地改革法では一人あたり30ユゲラまでの占有は許可された。しかしその間に、lex Thoria agraria≪アッピアノスによると lex agraria の後に制定された3つの法の内の2番目≫によって、そのように見えるのであるが、占有に関して重要な変更が加えられており、それについてキケロ(Brutus, 36, 136)は次のように描写している:(Sp. Thorius) … agrum publicum vitiosa et inutili lege vectigali levavit. [ある者がその欠陥の多い無用な法律により公有地に課されていた税金を軽減した。]モムゼンによればルドルフ(Römische Rechtsgeschichte, 1, S41)による説明は以下の通りである:彼≪Spurius Thorius、lex Thoria の制定者とされる者≫は(公有地に)課税することで ager publicus をそのある欠陥の多い無用な法律から解放した。≪公有地の課税率が軽減された結果、私的な占有が加速したのを、lex Thoria が再度税率を戻すことによって、そうした私的占有に歯止めをかけようとした。≫この説明は文法的には全く無理がないとは言い難いように思えるが、しかし文脈の意味に従えば、私はそう信じるが、別の満足の行く説明をこの箇所に加えることは困難であろう。≪元の文章は悪法を制定したということを言っているように思えるが、このルドルフの解釈はそれをまた是正したとしている。levavit =軽減する、解放する、が税率のことを言っているの公有地のことを言っているのかという問題である。≫少なくともこの解釈はアッピアノスの次の説明(引用済みの箇所、1, 27)との連関で:”τὴν μὲν γῆν μηκέτι διανέμειν, ἀλλ’ εἶναι τῶν ἐχόντων, καὶ φόρους ὑπὲρ αὐτῆς τῷ δήμῳ κατατίθεσθαι”[その土地はもはや分配されず、現在その土地を占有している者のものになっており、その土地に関する税金は(本来は)民衆のために納められるべきである(のにそうなっていない)。]良い説明となっており、つまり:ager publicus の占有は ager vectigalis ≪課税される土地≫へと転換させられたのであり、それが意味するのは(理論的には成立していた筈の)現物貢納の支払いの代わりに、それは収穫物の内の一定割合を土地の使用者と親族関係にあるその土地の地主に払うもので、法的には不安定な低位の所有状態の証拠として捉えるべきものであるが、帝政期において非常にしばしば地主達がそれを得ようと努めかつ渇望していたのと同じように≪現物貢納は収穫高とその時々の穀物の相場で取り分が変動するので、地主には固定額の現金払いの方が都合が良かった≫、(現物貢納に換わって)確固たる現金払いが登場するのであるが、つまり adaeratio ≪現金での使用料払い≫が生じていたのである。そして更に、ある土地での使用料取り立て可という認定は、もしかすると使用料免除の場合だけにされた≪本来は使用料を払うべき土地であることを確認してから免除した≫のかもしれないが、しかしその他の場合では所有状態の不安定さを解消したのである。(後述の箇所参照)
同時に lex agraria は ager compascuus に対して次のように取り決めている(第14、15条、モムゼンの補完に基づく):Quei in agrum compascuom pequdes majores non plus X pascet quae(que ex eis minus annum gnatae erunt postea quam gnatae erunt … queique ibei pequdes minores non plus …) pascet quaeque ex eis minus annum gnatae erunt post ea qua(m gnatae erunt: is pro iis pequdibus … populo aut publicano vectigal scripturamve nei debeto neive de ea re sati)s dato neive solvito. [共有放牧地において大きな家畜(牛や馬)を10頭以上放牧しない者で、その家畜の中で生後1年未満のものについては、その後産まれたものについても、それらの家畜について…ローマ人民や公共の徴税人に対して土地の使用税やその他の税を支払う必要はなく、そのための担保を提供したり支払いを行うこともない。]私見としてそこから考えられることは、ager compascuus は、それがある耕地ゲマインシャフトのアルメンデという意味で成立していた限りにおいては――というのはここではただそういう ager compascuus のみを扱っているのであり、任意の個々人により共通に獲得された土地の断片に類したものを扱っているのではないからであり――、ローマの人民の公有地の一部としての意味で把握されるのであり、その土地については国家のための目的という建前で使用することが出来たものである。こういった見方に基づいて明らかに以前の時期よりこの ager compascuus に対しても使用税[scriptura]の支払いを義務化するという試みがなされており、その故にこの法律の中にはこういったアルメンデにおける非課税の牧草地利用の程度に関しての規定が含まれていた。その他、既に述べたように、この ager compascuus という制度はこの法律によって完全に死滅させられた。測量人達の記述によって我々が知っている土地の割当てという形ではアルメンデは上述したような解釈での法的な根拠を与えられることはなかった。Ager compascuus はその結果として、注記したように、ある個々の特定の fundus においての牧草地に過ぎなくなった。その他、こうした法律は、植民市建設が共通の敵に対抗し、かつ都市を新たに建設するという特性に適合しており、牧草地はただ pascua publica ≪公共の牧草地≫という形でのみ、つまりゲマインデに従属して自由に使用出来るものとして、個人の権利[jura singulorum]については、ager compascuus でそれが可能であったように、一部は自由な牧草地の区域が植民市に対して割当てられ、また一部は――既にその前からしばしば起きていたことであるが――取り消し可能な権利としては実際には廃止されていた。
