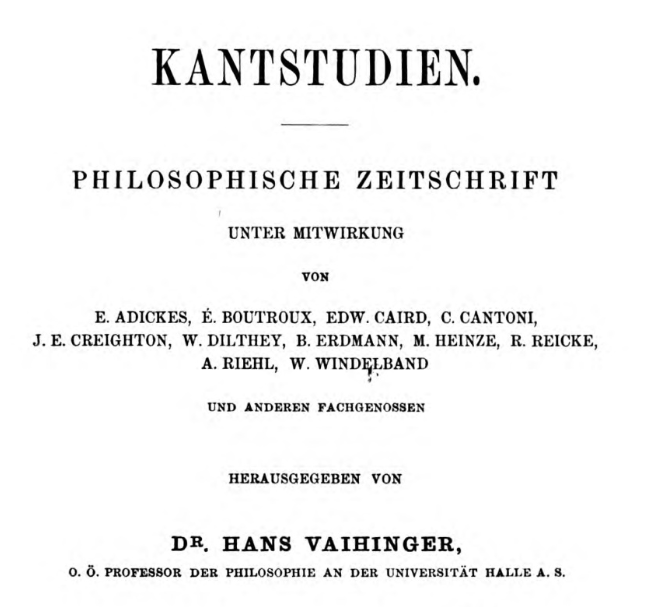ヴェーバーの理念型がファイヒンガーの「かのようにの哲学」の影響によるものだという仮説について、同じことを言っている人を発見しました。
https://www.haujournal.org/index.php/hau/article/view/1675
Reality remodeled
Practical fictions for a more-than-empirical world
Lars Rodseth
Abstract
Most ethnographers have little use for models and other formal abstractions, yet even a staunch empiricist such as Franz Boas could appreciate the “aesthetic” advantages of idealization and simplification. These advantages have been largely ignored in recent decades, as anthropologists have come to favor ever more intricate and encompassing accounts. The resulting “ethnographic involution,” I suggest, has steadily diminished anthropology as a source of usable, socially shared knowledge. Much the same problem, interestingly, was confronted long ago by Max Weber, who developed the method of “ideal types” precisely as a way to grasp, represent, and investigate the complexity of historical reality. Weber converged in this regard with his contemporary at Halle, the neo-Kantian philosopher Hans Vaihinger (1852–1933). Since the late twentieth century, Vaihinger’s “fictionalism” has attracted renewed interest within philosophy and beyond. Yet his notion of “as-if” reasoning—a via media, I would argue, between particularism and positivism—remains virtually unknown within anthropology.
森鴎外は「かのように」の中で、当時の欧州で、ヴェーバーのような社会科学系だけでなく、プロテスタント神学(鴎外は社会を安定させるものとしてプロテスタント神学を「かのように」の中で高く評価しています、要するに神学では神をあたかも存在しているかのように扱う訳です)、それどころか自然科学(例えば当時の物理学でのエーテルとか、電子、陽子などはその存在が確認されていたのではなく、モデルとして考案されたもの)にも共通する考え方であることをファイヒンガーの本を読んで理解しています。ちなみにファイヒンガーのこの本は900ページ近くありますが、鴎外は「かのように」での記述が本人の実体験に基づくものとすると、この2/3を何と一晩で読んでいます。恐るべきドイツ語読解力です。
前の投稿で書いたようにヴェーバーと鴎外はほぼ同世代ですが、この二人色んな意味でそっくりです。
(1)異常なレベルの広範囲な読解力
(2)攻撃的な論争が大好き
(3)高度な語学力
(4)そういった学問の間に女性と…(笑)(ヴェーバ-の場合のエルゼ・ヤッフェとミナ・トープラ-、鴎外の場合のエリスや児玉せき他)
鴎外はおそらくドイツに滞在した時に、ヴェーバーを読んだかどうかは不明ですが、社会科学系もそれなりに読んだのではないかと思います。それを鴎外が帰国後語っていないのは軍医という立場と大逆事件以降の思想取り締まりの影響との両方がありそうです。
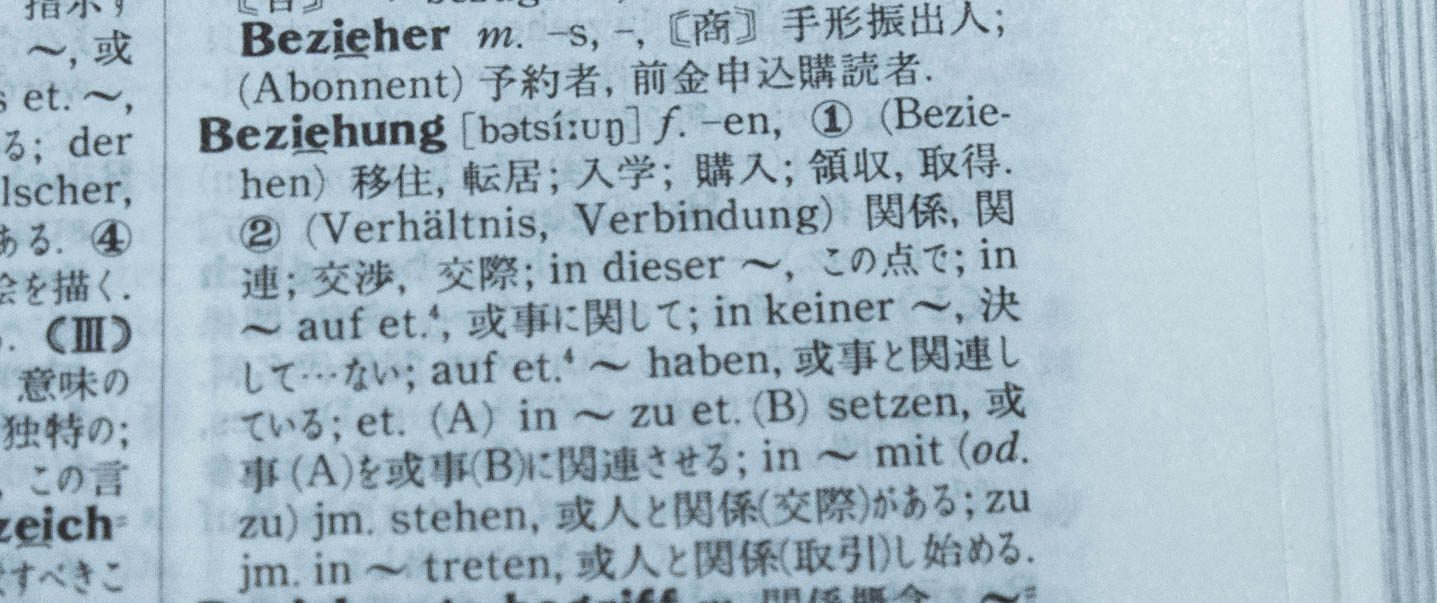 宗教社会学の次の箇所:
宗教社会学の次の箇所: