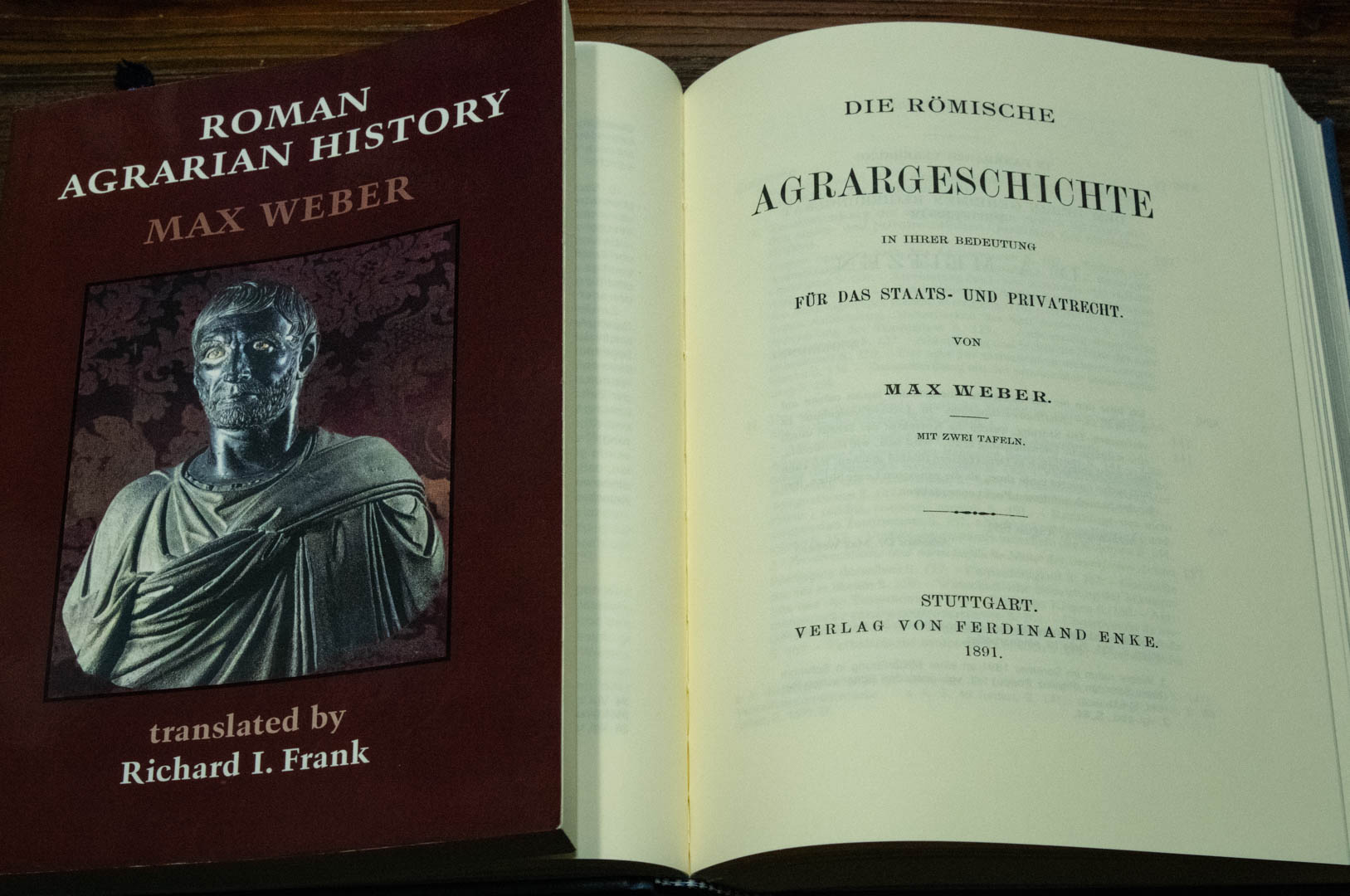長場正利という方が書かれた「コムメンダに關する研究」という1929年の論文があります。それによると、J. Kohlerという人の1885年の”Die Commenda im islamitischen Rechte”という論文で、既にコムメンダのイスラム起源説が唱えられていたようです。しかし、この説は当時のジルバーシュミットなどからは受け入れられなかったようです。ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」が1989年ですから、ヴェーバーもこの論文を読むことは出来た筈です。ですが、何の言及もないというのはちょっと不可解です。
「中世合名・合資会社成立史」についての訳者としてのコメント
ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」について、訳者として思ったことを、素人考えかもしれませんが、紹介してこの翻訳作業の締めくくりとしたいと思います。あくまで翻訳した結果として思った感想であり、下記の個人的意見によって翻訳の内容にバイアスが掛かっているということはありません。
===========================================
1.連帯責任原理について
ヴェーバーは合名会社のメルクマールとして成員間の「連帯責任」を真っ先に挙げるが、法律で規定されている合名会社の責任は「無限責任」であり、二つは決して同じ概念では無い。合名会社は複数の人間の間の連帯責任がメインなのではなく、全ての参加者=無限責任社員が一人一人会社の債務全体に責任を負っているのであり、相互の関係は副次的なものに過ぎない。
また、連帯責任というのは信用創造というプラス面だけでなく、大きなビジネスを行う上ではむしろ制約条件になる面もあり、実際にその後の発展を見ても、合名会社はきわめて規模の小さな商店レベルの会社か(無限責任社員が10人いる合名会社といったものは同族会社を除き聞いたことが無い→レースラーが作った日本最初の商法の草案では合名会社の社員は2人以上7人以下とされていた)、あるいは日本の財閥での持ち株会社に好都合のシステムとして使われただけであり、会社制度全体の発展の中では決して本質的なものにはなっていない。結論部に出て来るが、いわゆる悪名高い連帯保証人の制度も含め、「連帯責任」については法学的には決して好ましい制度としては扱われていない。
さらに付け加えて言えば、現在の日本では合名会社の結社性(複数の社員が必要)の要求は無くなっており、一名の無限責任社員だけの合名会社の設立も可能になっている。この場合連帯責任はそもそも存在しない。
さらには、結論部でヴェーバーが書いているように連帯責任原則はドイツ法の合手原理がベースになっている可能性が高い。何故なら、合名会社の財産は連帯責任というより複数の無限責任社員の「共有」の形態として考えた方が自然だからである。しかしこの論文ではその観点での検討はほとんど行われておらず、連帯責任についての研究が中途半端に終っている。その点が結論部では言い訳のように書かれている。
2.会社の特別財産について
会社の特別財産については、合名会社の会社財産は形式的には独立したものに見えるが、実質的には全て無限責任社員の個人の財産によって担保されているのであり、個人財産と大差無い。その場合合名会社の破産ということは、すなわち個人の破産と同等であり、そこに特別財産が成立しているというのは法的な形式に過ぎないと思われる。現在において個人事業か合名会社かという選択はほとんど税金の問題として選択されるケースが多い。この論文では会社組織への課税という観点はまったく触れられていない。
3.商号について
むしろ会社組織の発展の上では「法人」概念の成立が重要だと訳者は思うが、商号と法人概念に関する分析は限定的である。”corpus mysticum”(神秘的な体)については結論部で少し触れられているだけだが、もう少し突っ込んだ分析が欲しかった。
4.その他
・この論文は当初合名会社だけを扱っており、博士号論文(第3章のみ)を拡大して現在の形にした時に合資会社の分析も追加された。そのためか、合資会社についての分析が突っ込み不足であり、何故無限責任社員と有限責任社員の差異が形成されるのかが、capitaneus等の概念が紹介されるだけである。このために大塚久雄氏が言及しているように、ゴルトシュミットやハックマンの批判を招くことになった。
・この時点では当然のことながら、「会社制度の合理化の段階」といった「合理化」の観点はまだほとんど見られない。
・ただローマ法が持っていた汎用性、つまり新しい経済現象が出て来てもそれを取り込んで対応していく能力ということについては言及されている。
・コムメンダの考え方はイスラム教圏におけるムダーラバ契約の考え方が欧州に入って来て出来たものとする説が現在ではあるが、ヴェーバーの当時、ヴェーバーも含めて誰もこのようなイスラム圏からの影響ということを考慮していない。(コムメンダやソキエタス・マリスが最初に発達したピサもジェノヴァも十字軍の拠点であり、(十字軍が拠点を築いた)イスラム圏との貿易が広く行われていた。)
・中世の法規文献の調査については、論文執筆の開始時点ではヴェーバーはスペイン語・イタリア語の知識に乏しく、その2つの言語を学びながら文献を解読していった努力については、泥縄的とはいえ素直に頭が下がる。
・ただ文献調査に多大な時間と手間を要した割りには、得られた成果は地味で、研究の効率という意味では高くない。ある意味師であるゴルトシュミットの研究の補完として使われたという面があるのを否定出来ない。
・この論文で様々なゲマインシャフトの形態がゲゼルシャフトへと変化して行く実例が多く挙げられている。このことが後年の「理解社会学のカテゴリー」での独特のゲマインシャフト-ゲゼルシャフトの理解(ゲゼルシャフトも一種のゲマインシャフトである)につながったのではないか。実際に、この論文で挙げられている例では、ゲマインシャフトとゲゼルシャフトの境界は流動的であり、テンニースのように対立概念と捉えることはほとんど出来ない。
・この論考で中世の教会法での利子禁止がどのように経済に作用したかという検討がされており、プロ倫の中にそれが活かされている。
・ヴェーバーの研究方法が、最初の論文から決疑論であることは非常に興味深い。
・法制史的観点が中心で、経済史的観点が弱い。例えばコムメンダやソキエタス・マリスについてももっと経済史的に突っ込んだ説明、例えば中世の都市国家の社会背景の説明などが個人的には欲しかった。実際に例えばジェノヴァのジョバンニ・スクリーバの公正証書をいくつか読んで見ると、この論文だけでは得られない当時の実情が良く理解出来る。
・しかしながら、ヴェーバーの関心が法教義学よりも法制史(それも経済ともっとも関係の深い商法の歴史)、そして経済史、さらに歴史そのものという具合に変化していく兆しが最初の論文からもう現れているというのは興味深い。
・ピサのConsitutum Ususについての調査は、最初に法規集を編纂したボナイーニとヴェーバー以外には、インターネットを検索した限りの感触ではきちんと研究している人が見当たらず、そういう意味では貴重な研究と言える。
・テオドール・モムゼンはこの論文の審査にゲストとして出席し、あるローマの植民都市を表す2つの単語の差異についてヴェーバーと討論している。そして周知のようにその討論におけるヴェーバーの主張には納得していないものの、ヴェーバーのザッハリヒな研究態度と論理的な能力については高く評価し、有名な「息子よ我に代わってこの槍を持て」発言につながっている。モムゼンもまた、ある面では膨大なラテン語の碑文の解読を行うプロジェクト(ラテン語金石碑文大成)を立ち上げた、きわめて実証的な学者である。
「中世合名・合資会社成立史」の英訳の評価
「中世合名・合資会社成立史」のこれまでの日本での評価・紹介について、安藤英治氏と大塚久雄氏のものを取上げました。さらには、この際、Lutz Kaelber氏の英訳の質についても評価しておきます。(“The History of Commercial Parntership in the Middle Ages”, Rowman & Littelfiels Publishers, Inc., 2003)
最初に申し上げておくべきなのは、初めて(2003年に)この論文を外国語に翻訳したLutz Kaelber氏の功績は大きいということです。私はこの英訳が無かったら、中世ラテン語、中世イタリア語、中世スペイン語などの法規文献の引用が飛び交うこの論文を最初から一人で日本語訳しようという気にはまずならなかったと思います。その点ではLutz Kaelber氏には非常に感謝しています。また、そういった法規文献の英訳は、おそらく半分以上は別の人が既に訳したものを引用しているものですが、そういった文献を見つける手間だけでも相当なものがあると思われ、最初の英訳者の功績を損なうものではありません。
しかしながら、そういう感謝の気持ちの一方で、Lutz Kaelber氏がご自身で訳されたと思われるドイツ語、ラテン語、イタリア語その他の部分について疑問が無い訳ではなく、残念ながら特に後半の1/3については翻訳のレベルが低下しているように見受けられ、不適切訳や誤訳が散見されました。実は、下記の(1)の誤訳の指摘の時から、氏とは何度かメール(英語)をやり取りしました。一部こちらの指摘を受け入れたのもありますが、多くはまったく回答無しであり、こちらもそうなるとわざわざ英訳の校正を手伝う気も無くなったので、交信は現時点では途絶えています。下記の指摘は一部で、まだまだおかしな部分は多くあります。
ご興味があれば、以下の具体例をご覧下さい。私自身の態度としては、英訳者の対応を他山の石とし、誤訳の指摘には真摯に対応し、必要に応じて修正を図って行くことを心がけたいと思います。
以下、誤訳・不適切訳の具体例。ページ数はドイツ語原文(全集版)-英訳-日本語訳の順。
(1)P.175-P.74-P.35
原文:Unzweifelhaft ist in der Verfassung, in welcher die Kommenda und societas maris uns in den Statuten und Urkunden von Genua, an welches sich die südfranzösischen Statuten anlehnen,
英訳:Without doubt, the statues and the documents of Genoa, following southern French statutes,
日本語訳:ジェノヴァにおいて、コムメンダやソキエタス・マリスを見出すことができる法規や文献史料の中で、それらに南仏の諸法規が依拠しているのであるが 、(中略)、何の疑問も差し挟む余地も無く同意出来る。
英訳は依存関係が逆で、ジェノヴァの法規が南仏の法規に依拠していると訳しています。
ドイツ語からしてもそのような解釈は不可能ですし、また文脈から言ってももし南仏の法規がそのような性格のものなら、ヴェーバーはジェノヴァの法規では無く、南仏の法規について詳細に説明しなければならなくなりますが、当然そのような説明はありません。
これについてはLutz Kaelber氏も誤りを認めました。
(2)P.193-P.87-P.52~53
原文(ラテン語):”si quis ex ipsis duxerit uxorem et de rebus communibus meta data fuerit”
英訳: “If one of the brothers takes a wife and gives her a marriage portion from the common property.”
日本語訳:そして兄弟達の内の誰か一人が妻を娶って[その妻の実家に]共通の財産から[一種の]結納金を払うことになる。
要するにmeta(注:ラテン語ではなくランゴバルド語の単語)を「持参金」と訳すか「(一種の)結納金」と訳すかということです。持参金は文字通り嫁が持参するもので、それを結婚して夫になるものの家の共通の財産から嫁に払うという英訳はおかしく、日本語訳のようにすべきだということです。(ハインリヒ・ミッタイスの本にもmetaは花嫁の父親に対して支払う一種の結納金だと説明されています。父親は受け取った結納金を原資にして、花嫁に一種の財産分与として持参金となるお金を与えます。)
本指摘へのKaelber氏からの回答は3ヵ月以上かかり、その内容は「この部分はKatherine Fischer Drewのランゴバルド法の英訳を写しただけ」というものでした。この英訳は入手しましたが、確かにそう訳していますが、それが正しいという保証はどこにもありません。Kaelber氏がどう考えるのかという回答は結局ありませんでした。この翻訳者の基本姿勢がこれで良く分りました。
(3)P.274-P.141-P.125
原文:Wenn nun der Vater trotzdem, daß das Vermögen ungeteilt ist, mit den einzelnen Söhnen societates einzugehen überhaupt imstande ist, so muß notwendig auch dem nicht abgeteilten Sohne schon jetzt im Rechtssinn Vermögen überhaupt zustehen, sonst könnte er nichts einwerfen.
英訳:If the father at all able to enter into partnership with his sons, in spite of the fact that asssets are undivided, then the son who has not received his share in the property must have a claim to the assets in a legal sense; otherwise, he could not contribute anything.
日本語訳:もしその父親が「それにも関わらず」、家族財産が個々の成員に分けられていないという状態で、かつ個々の息子それぞれとソキエタスを結成することが一般的に不可能な場合においては、その父親は家ゲマインシャフトから独立していない[家住みの]息子に対しては、不可避的にその時点で法律上一般的に財産と認められる何かを譲渡するぐらいしか出来ず、それ以外に何かを[例えば金銭で]息子に対して支払うことは出来なかったであろう。
ここの英訳は、訳者がドイツ語ネイティブとはとても思えないようなひどい誤訳です。原文の主語は一貫してder Vaterです。にも関わらず英訳は後半部分では主語がthe son(息子)に変ってしまいます。原文は息子については3格(与格)で”dem nicht abgeteilten Sohne”(まだ独立していない息子に)となっているので、これは主語にはなり得ません。にも関わらず英訳は「その息子は法的な意味においてのその資産に対しての請求権を持たなければならない(持つことになる)」としています。文法的にも無理ですし、また文脈から考えても意味不明の訳です。
zustehenという単語は他動詞の場合はzugestehenと同義で「譲り渡す」という意味です。その場合、日本語訳の内容で無理なく訳すことが出来ます。
この点についてもメールで指摘しましたが、2020年9月22日現在回答はありません。
(4)P.279-P.144-P.129
原文:Für die von einem Teilhaber auf eigene Rechnung abgeschlossenen comperae haben die anderen ein Eintrittsrecht (nach Art der heutigen offenen Handelsgesellschaft).
英訳:The others are entitled to subrogation for comperae[sales] the partner made on his own account (similar to today’s general partnership.).
日本語訳:ある一人の持分所有者の勘定の中で行われた comperae (訳注252) に対しては、他の持分所有者は介入権を持っていた。(今日の合名会社の場合と同様。)
訳注252:(若干加筆しています。)現代イタリア語の compra に相当するとするすれば「買う」という意味です。但し単純な購買行為ではなく、何かの特別な購買と思われます。何故なら単純な購買はこれに続く箇所で別途説明されているからです。12-14 世紀のジェノヴァやフィレンツェではこの言葉は、国が私的団体に対して債券を発行し、それを買ったものは例えば塩にかかる間接税のようなものを一種の利子として受け取ることが出来た、その債券またはそれを引き受けた団体を意味する特殊なタームです。つまり一種のRentenkauf(定期収入金を一種の利子の代替物にした金銭貸借)になります。ゴルトシュミット他のドイツ歴史学派はこの compera(コンペラ) を株式会社の起源であると考えていました。全集の注はヴェーバーが Consitutum Usus の中の概念を使っているとしていますが、それがどのページなのかをヴェーバー自身も全集の編集者も記載しておらず、本当にそうなのか疑わしいですし、翻訳者の方でインターネットで確認出来る Consitutum Usus を検索してもそのような特別の概念の定義は発見出来ませんでした。ヴェーバーはConsitutum Ususの箇所を参照する時は逐一注を付けていますので、全集の注は根拠不明です。
この部分の英訳でcomperaeを[sales]と真逆の意味に訳していること自体の問題だけでなく、それを指摘したら「じゃあ全集の注に『購買』とあるから購買だろう」という回答でした。英訳については誤訳もともかく、その後もともかく自分で考えようという姿勢が見えません。私が訳注に書いたような情報はKaelber氏にも伝えましたが、その後何の回答もありません。
(5)P.297-P.157-P.147
原文: … quilibet talium sociorum sit … in solidum obligatus.
英訳:…any one of such partners…is to be held liable for the full amount.
日本語訳:…そのようなソキエタスの成員の誰もが…連帯して責任を負うことになる。
何故、in solidumという今日でも使われている「連帯責任で」が「全額で」という訳になるのかまるで理解が出来ません。ドイツ語だけでなくKaelber氏のラテン語もかなり怪しいです。
(6)P.248-P.122-P.101
原文:cujus nomen “expenditur”
英訳:whose name is “hang out”
日本語訳:その者の名前が{重要な情報として}載っている
この部分は商号の初期の段階で、店の看板のような板に無限責任を負う者全員の名前を記載し、それをどこかに看板として掲げたということです。英訳はラテン語のexpenditurを「ぶら下がっている」と訳しています。看板だから店先にぶら下げられているんだろうという解釈です。しかしラテン語のexpenditur(expendoの受動形、3人称単数)の意味は、「1.支払われる 2.重み付けされる」という意味しかなく、「ぶら下げられている」という意味はありません。penditurならそういう意味ですが、英語の相当語であるexpend-expenseにも「ぶら下がる」という意味が無いのはご承知の通りです。
ここで更におかしいのは、
P.327-P.177-P.175にてこの表現が再度複数形で出て来ますが
原文:quorum nomina expendunter
英訳:whose name are held out
日本語訳:その者達の名前が載っている
という風に、まったく同じ表現で主語と動詞(受動形)が単数か複数かの違いですが、英訳は今度は”held out”(提出される)と訳を変えています。要するに訳し方がその場その場の適当な思いつきで左右されているということです。
大塚久雄氏の「中世合名・合資会社成立史」への言及について
安藤英治氏の「中世合名・合資会社成立史」の紹介についての論評に続き、大塚久雄氏の「中世合名・合資会社成立史」への言及について紹介すると共に、その問題点を指摘します。その言及は大塚氏の最初のまとまった研究成果である「株式会社発生史論」(1938)の前篇に、いわば先行研究批判のような形で出て来ます。この二人の研究内容については、次のように表にして比較してみるとわかりやすいかと思います。
| マックス・ヴェーバー「中世合名・合資会社成立史」 | 著者・表題 | 大塚久雄「株式会社発生史論」(前篇部) |
| 1889年 | 発表年 | 1938年 |
| ローマ法の団体概念であるソキエタスから、中世において合名・合資会社がどのように生まれたか。 | 研究の範囲 | 株式会社がどのような歴史的な段階を経ながら発展して来たか、その初期の段階としての合名・合資会社研究を含む。 |
| 法制史を中心としながら一部経済史 | 学問分野 | マルクス主義的経済史 |
| 会社の特別財産と連帯責任原則の発展 | 着目している要素 | 個別資本の集積 |
| 多数の中世の諸都市の法規の実証研究に基づく決疑論で先行研究への批判も含む | 研究手法 | 主に先行研究の文献調査と事例研究 |
| 合名会社の特別財産と連帯責任は、イタリアの諸都市での家計・家業ゲマインシャフトの中から発展した。合資会社はその特別財産の部分は合名会社と共通であるが、その起源はまったく異なる対立概念である。 | 結論 | (前篇部のみ) 株式会社の歴史的な発展段階は、個人企業→合名会社→合資会社→株式会社という単線的なものである。 |
上記の研究の範囲を見ていただければ良く分りますが、ヴェーバーはローマ法から中世の合名・合資会社の成立までで、それに対し大塚久雄氏はその中世から近代の株式会社の発展を追ったものなので、両者の研究対象はずれており、それが重なるのは中世における合名・合資会社の部分だけです。
また学問分野を見てもヴェーバーは法制史がメインで一部経済史を含みます。それに対し大塚久雄氏は経済史のみで、それもマルクス主義的な教条主義に囚われた発展段階論です。ここで言えるのは、合名・合資会社という歴史的な事象を正しく理解する上では、色々な要素を総合的に勘案して判断すべきと考えますが、ヴェーバーは少なくとも経済史的要素を無視することはせずまた様々な法規の事例を地道に調べた決疑論に徹していますが、大塚久雄氏はいかにもマルクス主義的唯物論という感じで、いわば「上部構造」とも言える法制史的側面についてはまったく考察の対象としておらず、またヴェーバーが苦労して調べた具体的事例の数々も参考にした形跡は窺えません。
以上のことから、大塚久雄氏の研究にとっては、ヴェーバーの研究は先行学説とは言い難い部分がありますが、大塚氏は「補注」という形でヴェーバーの研究に言及しています。そこで大塚氏はヴェーバーの研究を「合名会社の発達の起源を家族共同体に求める諸説」として紹介しています。まずはこの「家族共同体」という言い方が既に問題で、ヴェーバーは家族ゲマインシャフトと家計ゲマインシャフトは厳密に区別しており、「家族ゲマインシャフト」から合名会社が生成したなどとは書いていません。もっとも大塚氏はその後の方で「労務共同体」という言葉を使っていますので、大塚氏自体がそのことを理解していない訳ではありませんが、既に最初から読者に対して誤解を与える表現になっています。ヴェーバーが実例として挙げているフィレンツェのペルッツィ家やアルベルティ家は15世紀の段階では、法王や各国の国王に資金を貸付けるいわば財閥ファミリーとなっており、人が「家族ゲマインシャフト」でイメージするような家族数人のきわめて小規模なゲマインシャフトとはまるで異なります。
それから、大塚氏はヴェーバーのこの説にゴルトシュミットとハックマンが反対しているとして、まるでヴェーバーの説が少数意見であるかのような書き方をしています。しかし、大塚氏がこの部分の冒頭で書いているように、中世イタリアのフィレンツェなどの内陸都市で「家計ゲマインシャフト」から発生した「コンパーニア」(原義はパンを共にすること→ヴェーバーが再三引用している” stare ad unum panem et vinum”{一かけらのパンとワインを共にする}、現在のcompanyの語源です)であるということは、私が調べた限り現在でも定説、多数派説です。更にはゴルトシュミットとハックマンの反対意見については、おそらくは家計ゲマインシャフトは合名会社生成の一つの要素であるが、それだけはないという主張であると思われます。また大塚氏はゴルトシュミット・ハックマン側に賛成する理由として、「『会社』なるものが個別資本の集中形態である」からとしています。更にはヴェーバーが法制史的側面だけ見て経済史的側面を見ていないと批判していますが、私に言わせればヴェーバーは少なくとも経済史的側面を無視したりしていませんが、大塚氏は法制史的側面をまるで無視しています。大塚氏が根拠とする個別資本の集中という点でも、ヴェーバーは家族の成員以外とのソキエタスの欠点として、ある成員が亡くなってしまった場合のソキエタスの財産の維持の困難さを挙げており、日本の財閥ファミリーである三井家や住友家の例を挙げるまでもなく、家計ゲマインシャフトは資本の集積には親和的に働いていました。大塚氏のこの観点でのヴェーバー批判は自分で考えたと言うより、ゴルトシュミットとハックマンの尻馬に乗っているだけという風に私には見えます。
それからもっと重要な問題は、これについては安藤英治氏も指摘していますが、大塚氏の結論である、個人企業→合名会社→合資会社→株式会社という発展段階について、ヴェーバーは個人企業→合名会社の部分も合名会社→合資会社の部分もはっきりと否定しているということです。合名会社の発展は先の説にもあるように家計ゲマインシャフトからであり、そこに個人企業といった段階は認められていません。そして何よりも、ヴェーバーは合資会社と合名会社は鋭く対立するものであって、合名会社から合資会社が生まれたというような説を完全に否定しています。第4章の注36:「合資会社が合名会社にとって次の発展段階であるというような、そういう事実は見出せない。そうではなくて、合名会社と合資会社は歴史的にも理論的にもお互いに同じレベルで鋭く対立するものなのである。」私が大塚久雄氏が「中世合名・合資会社成立史」をきちんと読んでいないだろうと推測する最大の理由はこの点です。もし仮に読んでいてそれについて何も言及していないのであれば、学者として失格でしょうし、全部を読まないで批判を書いたとしたら、それもまた学者としては、特に後年ヴェーバー研究者として知られるようになった者としては、怠慢としか言いようがありません。
さらに大塚論文での問題を挙げておくと、用語法の混乱です。大塚氏はソキエタス・マリスを「ソキエタス」と呼び、またコムメンダを「コンメンダ」と呼んでいます。ヴェーバーが「コムメンダは最初からソキエタスと呼ばれていた(コムメンダもまたローマ法のソキエタスの概念の範囲で理解されていた)」と書いていることを考えると、ここからもうおかしな用語法なのですが、問題は歴史的なコムメンダとソキエタス・マリスの実態とはまた別の観念的な定式化であるということです。さらにはその自分で作った定義ですら徹底されておらず、P.116では「ただしこのソキエタスの用語法が…(中略)…この場合の用語法ではむしろソキエタスではなくしてコンメンダであることが注意せらるべきである」などと書いており、混乱しているとしか言いようがありません。また、ヴェーバーがコムメンダにおける様々な要素として「委託販売」「単純な資本『参加』」といった区別を持ち込んでより深く分析しようとしていますが、大塚氏のはむしろ悪しき単純化・定式化にしか見えません。
以上、大塚氏の論文は1938年という時代を考えれば無理もない、という弁護が出来なくもない部分もありますが、その後大塚氏が1960年代にヴェーバーの紹介者・翻訳者として有名になったという経緯を考えた場合、「あの大塚先生がこういう評価をしているのだから、『中世合名・合資会社成立史』は特に読まなければならない本ではないのだな」という間違った評価につながったということは否定出来ません。そしてそういうネガティブな評価が、2020年まで日本語訳が無かったというアンバランスな状態にもつながったのだと思います。教訓としては、「どんな偉い先生がある本について何と言っていようと、評価はまず自分で読んでからにすべきである。」ということかと。
安藤英治氏の「中世合名・合資会社成立史」紹介の問題点
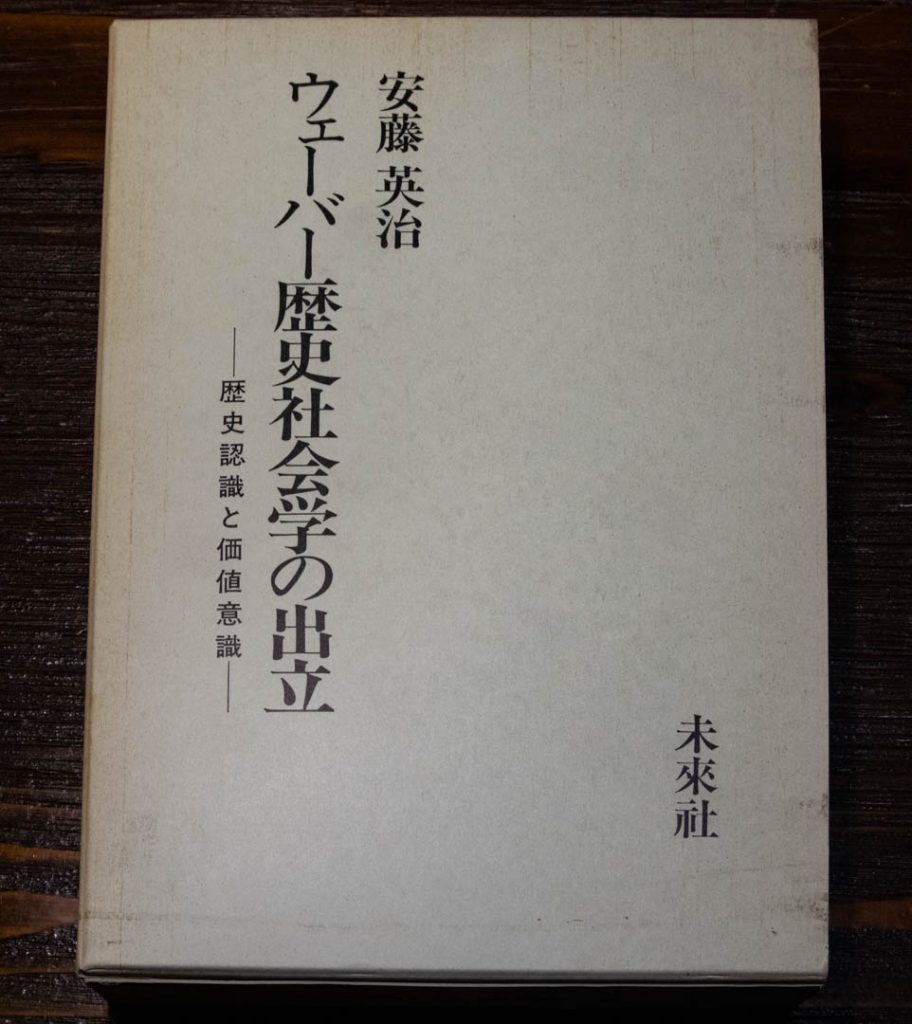 「中世合名・合資会社成立史」のダイジェスト版のアップも終ったので、次はこの論文の日本での受容について論評したいと思います。今まで私が知る限り日本でこの論文について言及したのは、二人だけです。一人はヴェーバー研究者・紹介者として有名な大塚久雄氏であり、もう一人はやはりヴェーバー研究者として著名な安藤英治氏です。今回はまず安藤英治氏の「ウェーバー歴史社会学の出立―歴史認識と価値意識―」を取上げます。この論文は安藤英治氏がヴェーバーの「プロテスタンティズムと資本主義の精神」をヴェーバーの最高の論文として捉え、それに至るまでの道筋を明らかにするという目的で書かれたものです。「中世合名・合資会社成立史」の紹介は、P.108からP.130まで23ページというそれなりのボリュームを費やして書かれています。 結論から先に申し上げれば、これまで大塚久雄氏の論文以外ではまったく言及されておらず、ヴェーバーの研究者の間でもほとんど読まれていなかったこの論文を「ともかくも」読み、その内容を他に伝えようとした努力に対しては敬意をもって接するべきだと思います。しかし、後述するように、この論文のもっとも中心的な論点でまったくの誤解をしたままの紹介であり、読者に間違った情報を伝えている点では問題が多いと思います。以下、その問題点をa potioriに(重要性の高いものから)紹介します。
「中世合名・合資会社成立史」のダイジェスト版のアップも終ったので、次はこの論文の日本での受容について論評したいと思います。今まで私が知る限り日本でこの論文について言及したのは、二人だけです。一人はヴェーバー研究者・紹介者として有名な大塚久雄氏であり、もう一人はやはりヴェーバー研究者として著名な安藤英治氏です。今回はまず安藤英治氏の「ウェーバー歴史社会学の出立―歴史認識と価値意識―」を取上げます。この論文は安藤英治氏がヴェーバーの「プロテスタンティズムと資本主義の精神」をヴェーバーの最高の論文として捉え、それに至るまでの道筋を明らかにするという目的で書かれたものです。「中世合名・合資会社成立史」の紹介は、P.108からP.130まで23ページというそれなりのボリュームを費やして書かれています。 結論から先に申し上げれば、これまで大塚久雄氏の論文以外ではまったく言及されておらず、ヴェーバーの研究者の間でもほとんど読まれていなかったこの論文を「ともかくも」読み、その内容を他に伝えようとした努力に対しては敬意をもって接するべきだと思います。しかし、後述するように、この論文のもっとも中心的な論点でまったくの誤解をしたままの紹介であり、読者に間違った情報を伝えている点では問題が多いと思います。以下、その問題点をa potioriに(重要性の高いものから)紹介します。
1.合名会社の「特別財産」の理解
ダイジェスト版を読んでいただければ分りますが、合名会社において、ローマ法のソキエタースでの財産が、各成員の個人財産を寄せ集めただけで、例えば外部から見て差し押さえが可能であるようなソキエタース自身の財産がどのようにして認められるようになったのかの歴史的経緯を探るのがこの論文の大きな主題の一つです。その財産をヴェーバーはソキエタース(ゲゼルシャフト)の「特別財産」(Sondervermögen)と呼んでいます。 この「特別財産」についての安藤英治氏の紹介はP.117にあり、「だが動産のうちに組合に投資されたものでありながらEinlage(注:投資されたもの)に含まれないものがある。これをcorpo della compagniaという。すなわち二年毎に行われる総合計算(注:一種の決算)の時以外に増減可能な資本があることになる。ウェーバーは丁度今日の常時解約可能な預金の如きものだと解説している。このcorpo della compagniaはラテン語のcorpus societatisに当たる。それは対外関係において会社財産を意味し、『したがってこれは合名会社の特別財産に当たる。』」 この安藤氏の説明は100%間違っています。このcorpo della compagniaについてヴェーバーがこの論文で述べている所を拙訳から引用します。
「 ソキエタースの資本金(注:原文でGrundkapital)――il corpo della compagnia [コンパーニアの実体]――は各ソキエタースの成員の出資金を合計したものとして成立していた。 これらの出資金は、通常の場合認められうる限りにおいて全部をまとめた合計額として表現され、利益が繰り入れられ損失が控除される。各ソキエタースの成員の出資金は総決算[Generalrechnung]、つまり saldament della compagnia 28) [コンパーニアの決算]と呼ばれたもので、一般的に2年に1回行われる決算までは増額も減額もすることが出来なかった。その決算の時までは、またそのソキエタースの成員の死においても、その出資金はソキエタースに縛り付けられ、そして利益と損失を分割する際の基準となった。」
安藤氏が誤って「特別財産」と解釈している財産についてのヴェーバーの記述をやはり拙訳から引用します。
「 それにも関わらず、ソキエタースの成員はゲゼルシャフトの基金以外にも動産を所有している。そしてそうした動産の中で我々にとって取り分け重要なのは、次のような資金である。それはソキエタース[コンパーニア]において何かの目的で自発的に出資されたものであるが、しかしながら出資金としては扱われないものである。ほとんど全てのソキエタースの契約の中にそういった資金についての規定を見出すことが出来る。そういった資金はあるソキエタースの成員が、”fuori del corpo della compagnia” [コンパーニアの資本金の外側で]所有するものである。」
il corpo della compagniaはつまり「そのコンパーニアの実体」という意味であり、つまり現在の用語で言えば会社の資本金であり、これが個人の財産の単なる集合から区別される「特別財産」であることは、普通に読めばすぐに理解されることです。またヴェーバーが”fuori del corpo della compagnia” について「我々にとって取り分け重要なのは」と書いているのは、ローマ法のソキエタースではむしろそういう財産の集合がソキエタースの財産だったのが、この段階ではソキエタースの特別財産である資本金と従来型の各成員の一時的な投下資金の集合がはっきり区別されるようになっているという点においてです。
安藤氏が何故こんな初歩的な読み誤りをしたのかの理由は分りませんが、ソキエタースのメンバーが一時的にソキエタ-スに預けているような財産がソキエタースの実体=「特別財産」と呼ばれることはあり得ないのは常識で考えても容易に理解出来ることです。このような部分だけを拾い読みしてとんでもない誤解を読者に紹介しているという、このことだけでも安藤氏の読解は問題だと思います。
2.Firmaの翻訳
次の問題として、ヴェーバーがゲゼルシャフトの連帯責任が成立するためには外部との契約がFirmaによって行われることが必要だったとしていますが、安藤氏はP.118にて「かくてソキエタスは外に対しては一つの集合名詞をもった一個の全体として、特有の商社 Firma として立ち現われた。」と書き、Firmaを「商社」と翻訳しています。確かに辞書を引けば現在のFirmaの意味はまずは会社であり、商社という訳もあり得ます。しかしながらこの論文では最初から最後までFirmaは「商号」の意味で使われ、商社という意味で使われたことは一度もありません。 私が訳注の中で引用したヴェーバー当時のドイツの商法典の合名会社に関する記載を再度引用します。
「Das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch [ADHGB] 1869年制定、第85条の規程は以下の通り。”Eine offene Handelsgesellschaft ist vorhanden, wenn zwei oder mehrere Personen ein Handelsgewerbe unter gemeinschaftlicher Firma betreiben und bei keinem der Gesellschafter die Betheiligung auf Vermögenseinlagen beschränkt ist. Zur Gültigkeit des Gesellschaftsvertrages bedarf es der schriftlichen Abfassung oder anderer Förmlichkeiten nicht.” [日本語訳] 合名会社とは以下の場合に成立する。2人ないしそれ以上の人員が共通の商号の下で商業を営み、その際にいずれの社員も出資財産に対する責任を制限されない。会社としての契約を有効にするために、書面や他の形式を必要としない。」
合名会社の「合名」とは、無限責任社員の名前をすべて「商号」の中に列挙することが必要とされていたことから来た名前であり(今日でも欧州には二人の名前を&でつないだ会社名は多くありますが、そういう会社は元は合名会社からスタートしたか、あるいはかつてのそういう規則が現在でも真似されているかのどちらかです)、合名会社についての論文で Firma が使われたらまず「商号」という訳しかあり得ないのは常識に近いと思います。もしかすると安藤氏は、商事会社を商社の意味だと誤解している可能性もあります。
3.内陸都市と沿岸都市の対立という構図
安藤氏はヴェーバーがイタリアにおいて、ピサ、ヴェネツィア、ジェノヴァのような沿岸都市と、フィレンツェのような内陸都市を対立概念として捉え、沿岸都市では連帯責任の原則は発達せず、コムメンダやソキエタース・マリースでそれが無いことの確認をしただけで、本論は内陸都市の部分である、という解釈をされています。またP.115では「連帯責任はゲルマン的財産共同体の影響の及ばないイタリアの沿岸都市からは原理的に発生し難いことになろう。」としています。 しかし、こういった対立構図は、ヴェーバーの叙述にはほとんど確認出来ないどころかそれと反対のことが書かれています。第5章のフィレンツェの冒頭では
「フィレンツェにおける商法の発展については、既にラスティヒにより繰り返し主張されているように、カテゴリーとしてイタリアの沿岸[港湾]諸都市のそれと対比されるものとして把握されかつ説明されている。」
とさらりと紹介されているだけで、ヴェーバーは特にこの観点を強調したりはしていません。また第3章の原注12では「海上取引の盛んな都市と産業の発達した都市の対立がラスティヒによって強調されている。Entwicklungswege und Quellen des Handelsrechts[商法の発達の道と源泉])ゴルトシュミットは Zeitschrift für das Gesammte Handelsrecht[総合商法雑誌]の第 23 号の 309 ページ以下で、このラスティヒの論に対し、対立を際立たせるやり方が行き過ぎであり、また一般化も過度であるとして批判している。(以下略)」と書かれており、ヴェーバーの先生であるゴルトシュミットがラスティヒの沿岸都市と内陸都市の対比の仕方が行き過ぎであると批判していることが書かれています。従ってヴェーバーとしては両論併記のような形で特にラスティヒ説を強く支持するようなことはまったく書かれていません。 ここでヴェーバーが言いたいのはフィレンツェのような内陸都市では貿易での必要性から生まれたコムメンダやソキエタース・マリースが発展せず、別の形のゲゼルシャフト形成が主流であったということだけです。また連帯責任原理が沿岸都市には無かったというのもおかしな解釈で、ヴェーバーは沿岸都市のピサで法規上には連帯責任の記載はないがそのことがピサで連帯責任が行われていなかったことを意味しないと書いていますし、またヴェネツィアにも独自の連帯責任があったことが記述されています。またこの連帯責任がゲルマン法由来のものであれば、ゲルマン民族の国であるランゴバルド王国というのは沿岸・内陸を問わずシチリア島などの一部の地域を除いてイタリア全土を6~8世紀に渡って200年以上支配したのであり、ゲルマン法が沿岸都市には影響を及ぼさなかったとする解釈は不可能です。 また、コムメンダやソキエタース・マリースという沿岸都市で発達した新しい一種の会社組織の前形態は、最終的に合名会社や合資会社が成立する上で大きな役割を演じており、単にそこに連帯責任原理の発展が無かったという確認のためだけに取上げられているのでありません。(ただヴェーバーは通説でのコムメンダ→合資会社、ソキエタース・マリース→合名会社を否定して、ソキエタース・マリースから合資会社が生じたとしています。)
4.ローマ法とゲルマン法の対立
安藤氏は内陸都市と沿岸都市の対立以外に、ローマ法とゲルマン法の対立というのもヴェーバーが採用しており、これが後にプロテスタンティズム研究につながるとしています。そしてここでもまたローマ法では家父長権が強く、ゲルマン法では家族の権利が平等で、コムメンダは平等ではない成員間のシステムなのでローマ法から生まれ、そこから合資会社が生まれたとしています。しかし上述したようにヴェーバーは合資会社を産んだのはコムメンダではなくソキエタース・マリースであると明記しており、この点も間違っています。また、ローマ法のソキエタースは対等の人間間を前提としており、コムメンダをソキエタースの枠組みで解釈するには当時の法学者が苦労した旨が記載されています。さらに言うならば、ローマ法とゲルマン法の対立という図式はヴェーバーが改めて持ち出したものでは当然なく、19世紀のドイツの法学においてきわめて激しい論争があった対立であり、その対立がようやく治まってドイツにおける法整備が一応進んだ段階での研究者であるヴェーバーが、両方を考慮して議論を進めるのはある意味当然です。しかしながら結局ヴェーバーはこの論文でゲルマン法の基礎原理である合手制については、きわめて限定的にしか論じておらず、どちらかというとロマニステンに近い立場で論文を書いています。これはおそらく師のゴルトシュミットの影響だと思われます。ヴェーバーはしかし大学で代表的ゲルマニステンであるギールケの講義も聴講しています。
以上4つほど論点を挙げましたが、細かい点を入れればまだまだ誤りはかなりあります。 安藤先生には申し訳ありませんが、私はこの「中世合名・合資会社成立史」の紹介は問題が非常に多く、この論文で展開されたヴェーバーの議論の的確な紹介にはまるでなっていない上に、ヴェーバーがもっとも苦労して論述している「会社の特別財産」や「商号の成立」についてはあり得ないような誤解をし、また「沿岸都市 対 内陸都市」や「ローマ法 対 ゲルマン法」のような本来はヴェーバーがここで初めて言い出したことでもないことを、あたかもヴェーバーが初めて主張したかのように説明するという意味で読者にとって非常に有害と言わざるを得ません。
「中世合名・合資会社成立史」ダイジェスト版
マックス・ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」のダイジェスト版をお届けします。
全体の1/17ぐらいのボリュームになっており、ダイジェスト版といってもMS Wordで17ページ分ぐらいあります。
この論考を現時点で日本で一番精読しているのは最初の日本語への翻訳者である私だと思います。そういう立場にあるものとして、ダイジェストで内容を簡単に参照出来るようにするのもある種の義務かと思ったのと翻訳の正確さの再チェックの意味もこめて作成しました。
この論考の結論部をここにアップしてから、アクセス統計を見ているとそこだけ読んでこの論考の概要を理解されようとしている方が多数いらっしゃるのを発見しました。しかしながらこの結論部は全体で論じたことをもう一度簡略にまとめる、という一般的な結論部とはちょっと異なっていて、ここだけ読んでこの論考の概要を理解するのは難しいと思います。そもそもこの論文の主題が何か新しい仮説を提示してそれを論証するという性格のものではなく、合名・合資会社の成立についての、広範囲での決疑論なので、その意味でも結論部だけ読む意味は薄いです。
以下のダイジェストを読んでいただければ、おおよその全体像はつかめると思います。それによってこれまでの日本人によるこの論考への言及者の代表である大塚久雄氏と安藤英治氏のものが、偏っていてまた多くの間違いも含んでいることが理解していただけると思います。その二人の言及についての論評は別にアップします。
====================================
序文
伝統的な団体に関する法規定である、ローマ法のソキエタースから、中世にイタリアの諸都市で現れた貿易や手工業のための団体がどのように発展してその後合名会社として定義されるようになったのか、商慣習から始まってやがて慣習法として定着し、最終的に商法において会社として定義されるようになるその過程を探ることがこの論文の目的である。合資会社についても合名会社との対比で取上げ、その共通性と差異を論じる。
ローマ法と今日の法。研究の工程。
ソキエタースと合名会社の違いは、まずは合名会社もソキエタースの一種であることに注意。
しかし元々のソキエタースではそこで使われる資金は、構成員の持ち寄りに過ぎず、所有権については各構成員が保持したままである。共通の勘定(arca communis)というものは存在するが、それは必要な費用を各個人が立て替え払いをして後で精算する手間を省く程度の目的のためにあるに過ぎない。
これに対して合名会社では、外部からも認識出来る「合名会社自身の特別財産」というものが存在し、破産の際には差し押さえの対象になり、各構成員の合名会社への債権(出資金)に対し優先される。またある合名会社の社員がその会社の名前で契約したことは、他の全ての社員も拘束し、いわゆる連帯責任の原則が採用されている。また合名会社においては「商号」が使われており、その名前で契約することが連帯責任を発生させる源泉になっている。この「連帯責任」と「会社の特別財産」の存在こそが合名会社と元々のソキエタースの違いであり、この論文ではその発生の過程を探る。
ローマ法における合名会社的な原理の萌芽
ローマ法において、いくつか連帯責任や団体の特別財産を指し示しているかのような法規定が散見されるが、いずれも何かの特殊な場合に限定されたものであり、ローマ法においての合名会社の原理の成立は否定される。
研究の工程。経済的な見地と法的な見地の関係。
この研究は中世のイタリアにおける会社制度の発展の中で最終的に法的に規定される上でどのような標識が重視されたのかという観点でその法規定の発生の歴史を探るのが主目的である。その意味では一見経済とは無関係に思える要素も研究の対象となる。
Ⅱ. 海上取引法における諸ソキエタース
1.コムメンダと海上取引における諸要求
中世のイタリアで貿易(対スペイン、対中東圏)が発展するが、そこでは貿易で発生する危険を分割して対処するためのいくつかの特別な制度が発展していた。
西ゴート法典と海上取引
西ゴート法典において、貿易においての危険と利益の分担についての新たな法形成の萌芽が見られる。
コムメンダの経済的な基礎
そういった危険と利益の分担について最初に登場したのがコムメンダと呼ばれる制度で、資金を準備して商品を買い入れる側と、その商品を船で外国で運んで販売する代理人がパートナーとなり、代理人が利益の一定部分(1/4)を得るのが特徴で、12世紀のジェノヴァでは既に普通に行われていた。
コムメンダのソキエタース的性格
コムメンダも資金提供と労働の分担、利益分割などの点でソキエタースの一種として登場し、実際にソキエタースとして法的に扱われていた。
コムメンダの参加者の経済的位置付け
コムメンダにおいては、やがて被委任者が自分自身の商品を航海に持ち込んだり、複数の出資者の委任を引き受ける形に発展したが、そこにはまだ複数の出資者同士がソキエタースを形成するようなことは見られなかった。
2.ソキエタース・マリース[海のソキエタース]
コムメンダは一方的な出資-委託関係であるが、参加者の双方、つまり委託される側も出資するソキエタース・マリースという制度が続けて登場している。そこでは被委託者の地位が向上し、共同事業者になっている。
ソキエタース・マリースの法的性格
ソキエタース・マリースのコムメンダとの一番大きな違いは、コムメンダでは貿易のリスクは出資者のみが負っていたが、ソキエタース・マリースでは被委託者も出資し危険を分担しているということである。もし貿易で事故があった場合には、その損失は出資者の双方がつまりソキエタース全体が負担する。貿易で得られた利益もまずはソキエタース自身の資本勘定となる。
経済的な意味
ソキエタース・マリースにおいて、被委託者(トラクタートル)が複数の委託者(ソキウス・スタンス)を受け入れるようになると、そのトラクタートル自身が企業家となり、反面委託者は単なる出資者になり相対的に事業における地位が低下する。しかし、法的な位置付けではコムメンダもソキエタース・マリースもまだ同じように扱われていた。
3.コムメンダ関係の地理的領域
コムメンダとソキエタース・マリースの地中海沿岸地域での発展状況の確認。
・スペイン、シチリア島、サルディーニャ島、トラーニ、アンコーナ、アマルフィ→これらの地域では萌芽的なものに留まっていた。
・ピサ→第4章で扱う。(Consitutum Ususという11世紀の慣習法集成の中に2つの制度が登場している。)
・ヴェネツィア→10世紀に既にコムメンダもソキエタース・マリースも存在していた。
・ジェノヴァ→ジェノヴァではこの2つの制度が広く普及し、それに対する国家の法書式も確立しており、それが他の都市でもそのまま使われた。その内容は細かな点で曖昧さを含んでいたが、しかし16世紀の末までほとんど変更されることなく使い続けられた。
4. 海上取引に関係するソキエタースの財産法上の扱い
コムメンダとソキエタース・マリースという制度が合名会社という新しい法的制度についてどういう意味を持っていたかを探求する。
ソキエタースの基金
コムメンダやソキエタース・マリースでは、ソキエタースの財産というものが成立しているように見えるが、それはまだあくまで内部においてのものであり、外部から見てその存在が判別出来るようなものにはなっていなかった。
特別財産形成への萌芽
これらの制度の中では、出資側のソキウス・スタンスがソキエタースの資金で購入されたものに対する別除権(差し押さえの対象から外してもらう権利)が設定されており、トラクタートルの個人的負債に対する差し押さえから保護されていた。ここにおいて、トラクタートル個人への債権と、ソキエタースの財産への債権が分離される萌芽が見出される。
ソキエタースの債務
トラクタートルがソキエタースの業務によって契約した債務はトラクタートル個人の債権に留まっていて、まだソキエタース自身の債務にはなっていない。
成果
コムメンダやソキエタース・マリースにおける特別財産の形成はまだ萌芽的であり、また連帯責任についてはまだまったく見られない。
5.陸上コムメンダと合資会社
陸上コムメンダ
海上取引で始まったコムメンダを陸上での取引きにも転用した陸上のコムメンダが存在する。しかし法的な書式などは海上のものをそのまま転用したものである。ピアチェンツァは自身がジェノヴァの後背地にあたるという取引関係から、コムメンダの制度をジェノヴァとの取引きにおいて採用した。
合資会社の始まり。ピアチェンツァ。
ピアチェンツァにおいて、一人のトラクタートルに対して複数のソキウス・スタンスが存在する場合において、そのソキウス・スタンス達が同盟関係を結んで、むしろトラクタートル自身もその中から任命するようなことが行われており、ここに合資会社の萌芽を見ることが出来る。すなわち複数のソキウス・スタンスが有限責任社員であり、トラクタートルが無限責任社員であるような関係である。
陸上コムメンダの意味
陸上のソキエタースに関する法規定はピアチェンツァではなくジェノヴァの法で規定されている。しかしそれは海上取引に関するソキエタースに比べてまったく副次的なものだった。
結論としてこの章で見て来た制度の中には連帯責任の発生も会社の特別財産の生成も確認出来ない。
III. 家族ゲマインシャフトと労働ゲマインシャフト
共通の家族経済
共通の家族経済というものは通常何世代も続き、共通の業務を通じてゲマインシャフトの財産も蓄積してきていた。
家族経済の財産法上の帰結。夫婦財産共有制[財産ゲマインシャフト]
こうした家族経済の財産法上の扱いは、ゲルマン法では財産ゲマインシャフトとして扱われており、ローマ法との違いは家父長の権限が限定されており、各家族成員がそれぞれ権利を持っているという点である。またゲルマン法で特徴的なことは、支出が共通の勘定にて行われることだけではなく、収入もすべて共通の勘定に入るということである。家族は消費ゲマインシャフトというより、むしろ生産ゲマインシャフトであり、イタリアにおいての様々なゲゼルシャフト形成の基礎になった。
諸ゲマインシャフト関係の法的基礎。家計ゲマインシャフト。
家ゲマインシャフトは家族だけを成員とするのではなく、使用人なども包含しており、共通の労働で結び付けられた家計ゲマインシャフトとなっている。共通の労働は共通の家(作業場)とも結び付いている。
財産法的発展の行程。成員の分け前への権利。
家ゲマインシャフトでの財産共有は次第に制限が加えられるようになり、特に南イタリアのシチリア島では成員のそれぞれの分け前という考え方が普及した。しかし他のイタリアの諸地域ではそういう傾向は見られず、むしろ個々の割り当てを超える無制限の処分権が大規模な商業において有効に利用されていた。
家族以外での諸家計ゲマインシャフト
前項での無制限の処分権を成員が持つゲマインシャフトは家族だけのゲマインシャフトに限定されていなかった。特に手工業において家族以外の職人仲間なども含めた家族ゲマインシャフトと同等のものが形成された。
手工業のソキエタース
手工業で生産された製品についての販売業務の必要性が高まることが、ゲゼルシャフト形成の源流になった。しかしそこでは資金をまとめて共通基金とすることや、コムメンダ的なゲゼルシャフト形成はまだ見られなかった。職人達は同じ住居に起居して仕事を共にすることで家計ゲマインシャフトを形成した。この家計的な要素が手工業のソキエタースの一つの特徴となっている。
これらのゲマインシャフトの共通の土台
外部から経営ゲゼルシャフトとして扱われるには、簿記と外部からひとかたまりのものとして認識されるということが必要であったが、このことは家族によるゲマインシャフトと経営ゲゼルシャフトで同じであった。その意味で家族ゲマインシャフトは経営ゲゼルシャフトの発展の基礎となっている。
共通の特質
家計ゲマインシャフト、労働ゲマインシャフトの二つの特質について。
1.男性 socii[ソキエタースの成員{複数}]への制限
この種のゲマインシャフトでは男性の成人が共通の財産を取り扱う主体として考えられており、またその結果の責任も負うことになっていた。
2. 不動産の除外
この種のゲマインシャフトにとって共通の家は活動の拠点であるが、共通の財産には含まれていなかった。
財産関係における変化
財産ゲマインシャフトが全体をカバーするものではなくなり、個々の成員がそれぞれの勘定を持つに至った場合、それぞれの勘定の独立性を認めそれ自体をその成員が自由に処分するのを認める可能性が出て来た。またそういう風に各成員が全体の中で自分の割り当て分を持つ一方で、自分の資金から新たにソキエタースに投資を行うという二重の関係を持つ場合が出て来た。元々は家ゲマインシャフトとして法律での規定の元自然に成立していたものを新たな契約によりソキエタース関係として定義し直すということも出て来た。
第三者に対する法的関係。血縁を基礎とする責任関係。
連帯責任を元々持っていたのは氏族関係においてであるが、特に殺人の場合に私的復讐の義務が生じていた。この復讐の義務は後に賠償金のように金銭的債権のような形に置き換わって財産権的な性格を持つようになった。しかしながら氏族関係は信用取引の世界ではまったく何の役目も演じることはなかった。
家計ゲマインシャフトを基礎とする責任関係
ある成員の違法行為について家計ゲマインシャフトにおいて他の成員が責任を負うという法規定は様々な法規に見られる。しかしながら単なる債務について違法行為から生じる連帯責任を準用するというやり方は後退して行き、結局行われなくなった。
ゲマインシャフトにおける責任についての二重の意味
ゲマインシャフトの責任(債務)には次の2種類がある。
1) ある成員が契約した結果としてのゲマインシャフトの共通財産に対する債務
2) 成員のそれぞれが個人として他の成員と連帯して負う債務
1.共有財産についての責任
ある成員が契約した債務の不履行で、強制執行が家の全体に及ぶということが法の発展の中で可能になっていた。他の成員が個人で出来るのは調停を申し出て差し押さえられた全体の中から一部を免除してもらうということぐらいであった。
2.成員の個人責任
1.の場合においては強制執行が家全体に及んだが、しかし成員の全てが連帯保証を負わされるという形ではまだなかった。ゾームは合手概念を基礎とする債務ゲマインシャフトというものを提示するが、連帯責任というのはそういう債務ゲマインシャフトよりも更に上位のものである。連帯責任については成員によって「管理された」財産のみに適用出来るという考え方は、後の合名会社形成への萌芽となっている。
家の成員の責任の源泉と発展
業務ゲマインシャフトは家ゲマインシャフトから発生したものではなく、それを置き換えたものである。例えば氏族関係は、やがて近隣関係を基礎とするゲマインデに置き換えられた。新しい、業務を主体とする暮らしの中に共通の家計と業務ゲマインシャフトというものが発生している。元々の家ゲマインシャフトには無制限の相互責任が存在したが、法はそれを制限する方向に進化した。ある成員の債務についてゲマインシャフトが無制限に責任を持つことが制限されることと、信用取引でより大きな信用を必要とするということは矛盾しそれを法的に解決する必要があった。
諸法規における家族ゲマインシャフトと労働ゲマインシャフト。序説。
上記の問題点をどう解決するかという視点を持つことでようやく文献調査に入ることが出来る。
その場合また考慮しなければいけないのは、ローマ法の(再)伝播であり、それは非常に強い影響力を持ったものとして扱うべきである。
スペイン
スペインの法規では連帯責任が広く認められていたが、ローマ法の流入によりそれがほぼ完全に消え去った。
ヴェネツィア
ヴェネツィアにおいては、男性の兄弟同士で結成されるfraterna compagniaという相続ゲマインシャフトが存在し、そこでは父親から相続した財産の共有と連帯責任が行われていた。しかしそれには制限が加えられて行った。しかし、ヴェネツィアの法規は独自の道を行き、一般法の形成に大きな影響を及ぼすことは無かった。
その他のイタリアの地方諸都市における法規
家計ゲマインシャフトでも手工業者のソキエタースでも、成員相互が連帯責任を負うという条項はイタリア各地の法規に見出すことが出来る。
非独立の仲間の責任
上述の連帯責任は家ゲマインシャフトにて家族だけでなく、そこで働く使用人や従僕も拘束するものであった。独立前の家住みの息子もそれらの家族以外のメンバーと同等に扱われていた。
家族ゲマインシャフトにおける財産分与義務
家住みの息子は、例え別居していても共通の家計に関与する限りにおいては家ゲマインシャフトの一員として扱われていた。しかしながら家住みの息子は父親に対して独立を要求することが出来、その場合は父親は例え自分がまだ生きている間であっても息子に正当と考えられる財産を分与しなければならなかった。息子はその場合独立して新たな家ゲマインシャフトを形成する。家住みの息子の債務が連帯責任となるのはあくまで独立前の債務についてのみであった。
個人債務とゲマインシャフトの債務
個人の債務とソキエタースの全体責任の線引きについては、この家住み息子の独立の例にも見られるように、あくまでその成員の割り当てられている資本の分のみが個人債務の担保となっていた。しかし他方では商取引において無限責任の考え方も同時に存在しており、この二つの線引きをどこでするかが問題になる。
家族以外での連帯責任。共通の stacio[工房、店]。
共通の工房や店という意味でのbottega、taberna、stacioというものが経営ゲマインシャフトの中核となっていたが、ビジネスの規模が拡大するにつれ、その意味は具体的な店舗や作業場をもはや意味せず「業務」という意味になっていった。
個人債務と業務上債務
連帯責任については「共通の業務に関係する債務」のみに適用されるというのが法規では一般的であった。しかしそこに、ソキエタースの成員でソキエタースの事業に投資したものの債権や、ソキエタース外でソキエタースの成員の一人の個人に対して債権を持つ者とソキエタースの業務上の債務の関係が問題になった。
ゲゼルシャフトにおける特別財産
諸法規の中に、「ゲゼルシャフトの業務」の結果としての財産形成や債務を負うという内容の「ゲゼルシャフトの特別財産」形成についての契機を見出すことが出来る。
経営ゲゼルシャフトと商事会社
手工業ゲマインシャフトから始まった連帯責任原理の採用が、商業においてもっとも意義を発揮することになった。
合名会社とソキエタース契約の目印。商号。
ある業務がソキエタースのために行われたかどうかの目印は、以前は共通の仕事場(bottega、taberna等)で行われたということがそれであったが、商業分野での業務が拡大するにつれ、共通の仕事場の代わりに、連帯責任を持つ持つ成員の名前全員を含んでいる商号が使われるようになった。また商号を登記することも行われるようになっていた。最終的には商号はそれ自体が公的に認知されたものになり、その際には全員の名前を含んでいることはもはや必要無くなっていた。
ゲゼルシャフトの契約についての文献史料
ソキエタース・マリースにおいては、ソキウス・スタンスがトラクタートルに全権を委任していることの裏付けとして連帯責任が使われた。
いまや連帯責任は法規上でも規定されるようになったが、それはそれまでに既に存在していた商慣習を認めたということであり、むしろ法規は連帯責任に対して制限を加える傾向にあった。
Ⅳ. ピサ。Constitutum Ususにおけるソキエタース法。
Constitutum Usus
ピサの慣習法の集成であるConsitutum Ususを分析する。そこにソキエタース関連の規定が多く見られるし、また歴史的にも古く、さらにローマ法の影響を受けており、さらには法的決疑論として十分に検討された結果としての慣習法が多く見られるからである。
Constitutum Usus の領域
Consitutum Ususは種々雑多な領域を取り入れた慣習法集成であり、そこに商取引において確立した様々な商慣習を確認することが出来る。
Consitutum Usus の条文の性質
Consitutum Ususの中に連帯責任についての規定は存在しない。しかしながらそれは連帯責任の原理がピサでの商取引で採用されていなかったということを意味しない。
ソキエタース法的内容
1.ソキエタース・マリース
Consitutum Ususの中でソキエタース・マリースは詳細に論じられている。そこにおいて、ソキウス・スタンスとトラクタートルのどちらが事業の主体となるかについて、Capitaneus(キャプテン)という概念が使われていた。
法的な区別。Kapitanie[キャプテン]の意味。
トラクタートルとソキウス・スタンスについて、どちらかがCapitaneusである両方の場合が存在していた。トラクタートルがCapitaneusである場合でも、トラクタートルへの監視や損害賠償請求など、ソキウス・スタンス側が元々企業家であったという意識は失われていなかった。
ソキエタース・マリースの財産法
Consitutum Ususでは、ソキエタースの共通財産についてhenticaという出資金の合計を特別なものと見なしていた。
特別財産
ソキエタースが破産した場合の成員同士の優先権と成員と外部の債権者の優先権についての規定がConsitutum Ususに存在する。
1.個人への債権者との関係
ソキエタースの中のある個人への債権者で、その債権がその個人がソキエタースの出資をする前だった場合には、その債権者はソキエタースの財産への差し押さえを行うことが出来ない。
2.ソキエタースの成員達のゲゼルシャフトの基金への位置付け
同一のソキエタースへの出資を行ったソキエタースの成員達の間で、またはソキエタース・マリースの成員達の間で、仮にその中のある成員が他の成員よりも優先権を持ち、またソキエタースの財産を担保として使っていたとしても、その、先に言及された財産(つまりはソキエタースの財産)は成員の全員が受け取る権利を持ち、共有のものと認められ、出資比率に応じて均等に分けられる。
3. ゲゼルシャフトへの債権者への位置付け
Consitutum Ususにおいてはcreditores henticeという言葉が使われており、その名前の通りソキエタースに出資された資金の合計(hentice)に対する債権者というものが成立しており、破産の際にはソキエタースの個々の成員の出資分に対しても、ソキエタースの個人への債権者に対しても優先権を持っている。
4.ゲゼルシャフトの財産の範囲
henticaが成立するのは、ソキエタースの成員によって持ち込まれた商品の価格が決定し、かつそれらが一まとめにされる時である。
ここまでの成果。合資会社。
ここでConsitutum Ususに規定されているのは合資会社の原理であり、すなわちトラクタートルは「個人として」無限責任を負い、ソキウス・スタンスは出資者に留まりその責任は出資分に限定される。
II. 特別財産の無いソキエタース(Dare ad portandum in compagniam)
その他Consitutum Ususには、Dare ad portandum in compagniamというものがあり、それは単にソキエタースへの出資のみを行い、有限責任社員のように経営内容には関与しない、匿名組合におけるような関係のことを言う。この場合henticaは形成されない。ジルバーシュミットのコムメンダ→合資会社、ソキエタース・マリース→合名会社の説は正しくなく、むしろソキエタース・マリースは合資会社の基礎原理である。
III. 固定配当金を持ったソキエタース(Dare ad proficuum maris)
その他、貿易の仕向地までの危険性の度合いによって手数料が変る形の貿易向けの貸し付けである、Dare ad proficuum marisという形態もあった。この形態は後に教会法で禁じられていた利子付き貸し付けと見なされ消えていった。
ソキエタース法に対する利子禁止原理の意義
コムメンダやソキエタース・マリースを、教会法によって禁止されていた利子付き貸し付けの代替物として見なす立場の意見があるが、コムメンダやソキエタース・マリースが発達した主要因は明らかにそれではない。
IV. ソキエタース・マリースと家族ゲマインシャフト
Consitutum Ususの中では、家族関係の中においてソキエタース契約が行われた例があった。
ソキエタース・マリースが家族連合[associationen]から生じたという仮説
ジルバーシュミットがピサの各種ソキエタースが家族法を起源にしているという説を唱えている。しかし家族内でのソキエタース契約はむしろ家族外とのソキエタースの契約内容が修正されて用いられたのであり、その仮説は正しくない。
家族ゲマインシャフトの特性
ピサにおいては、societas inter patrem et filium factaという父親と(独立前の)息子によって作られたソキエタースも存在したが、基本的に家族の成員に対して一定の分け前を与えるのが目的で行われていた。
ピサにおける継承された遺産ゲマインシャフト
家族の中でのソキエタース契約の例としては他にもsocietas inter fratres factaという兄弟間で結ばれるものがあった。その目的は相続した財産の共有である。その結成にあたっても解散にあたっても同意が必要であったが、その同意を代替するものとしてVita communis(共生)という考え方があった。
Vita communis[共生]
1.前提条件
Vita communisの特徴は3つである。
1)一緒に一つの家に暮していること。
2)契約によって共通の勘定を設定している。
3)共通の労働が要求される。
2. その影響
Vita communisの影響としては、次の3つになる。
1)共通の財産の影響は個人の消費支出にまで及ぶ。
2)すべての個々の成員は共通の財産を使って何かの事業を行うことが出来る権利が与えられた。
3)個人レベルの支出は共通の財産から行われたが、もしその金額が多額だった場合には他の成員が異議申し立てをする場合があった。
Societas omnium bonorum [全ての財産が現在及び将来において成員間に共有されるソキエタース]
Consitutum Ususで、家計ゲマインシャフトで非親族と構成されるものについては、societas omnium bonorum[全ての財産を共有するソキエタース]と societas lucri [共同事業で得られた利益のみを共有するソキエタース]についての注釈で触れられているだけである。おそらくそこではVita communisの家族とのゲマインシャフトの原則が準用されたと思われる。
ピサにおける連帯責任原理
Consitutum Ususの中に連帯責任に関する規定は存在しないが、それはおそらくピサで連帯責任原則が存在していなかったことを意味しない。ピサではジェノヴァ同様貿易が主体であったのでコムメンダが主流であり、そこでは連帯責任の必要性が無かった。
V. Compagina de terra [陸上のコンパーニャ]
ジェノヴァやヴェネツィアと同じく、海上取引のための各種ソキエタースがピサでも陸上での取引きに転用されていた。ここにおいてもソキエタース・マリースでトラクタートルが単なるソキウス・スタンスの手足である場合と、独立の企業家である場合の両方がある。トラクタートルが手足である場合は多くはソキエタースがbottegaと結び付けられており、トラクタートルはある意味手工業における雇われた職人の延長にあった。
合名会社と合資会社の原理上の違い
合資会社の出発点では、その結合は社会的に平等ではない者同士の連合であった。これに対して合名会社で連帯責任が発達するのは対等な関係ということによっていた。ピサにおける諸ソキエタースからはともかく連帯責任原則は発達しなかった。
ソキエタースに関する諸文献
ピサでの手工業におけるcompagina de terraの実例。
成果
ピサにおいては合資会社的な関係がはっきり存在していた。このことは合資会社と合名会社の起源がまったく異なっていたことを示している。
V. フィレンツェ
フィレンツェにおける産業上の財産
フィレンツェは、内陸の都市として、また商業による資本の集積ではなく、毛織物産業を中心とした産業が資本の集積をもたらし、また同業者組合(ツンフト、ギルド)が発達したのも特長で、そこからペルッツィ家やアルベルティ家のような財閥家が出て来て、教皇庁や王室にまで資金を貸付けるような巨大な存在になっていた。ここでの主要なソキエタースは家ゲマインシャフト、労働ゲマインシャフトであった。
I. 法規における文献素材。発展段階。
大資本が家ゲマインシャフトをベースにすることで何世代も事業を継続出来たことが文献調査からも裏付けられる。
ゲゼルシャフトの連帯責任についての血縁関係の意味
ここでは古い時代の氏族の間の連帯責任の発展として家ゲマインシャフトにおける連帯責任が発生している。
フィレンツェの家ゲマインシャフトは、成員の死によって事業が停止してしまうというリスクを避けることを可能にしていた。そして家ゲマインシャフトということで、それは使用人等家族以外も含んではいたが、成員間の信頼関係を作り出していた。
家族とソキエタースの類似性について
1.仲裁裁判
家族間でのもめ事は、裁判ではなく家の中の権威者による仲裁で解決されていた。
2.責任と相続財産分与義務
フィレンツェでは都市の法規も、同業者組合(アルテ・ディ・カリマラ)の法規も、連帯責任について規定していた。強制執行に関する規定が出て来るがそれは、ソキエタースの成員個人に対してのもので、その持分を限度としての強制執行である。
3. ソキエタースの成員の個人的関係
家ゲマインシャフトの効力は成員の住む所、結婚、別の職業選択の否定など、成員の生活全体に及んだ。
4. 家住み息子と使用人頭
fattore(使用人頭)と discepolo(徒弟)は、家住み息子と同等に扱われ、ゲマインシャフトの債務については連帯責任を負っていた。しかし法規は後には代表者のみの責任としてこれらの者の責任を免除した。
家族ゲマインシャフトのソキエタース的性格とソキエタースの家族的性格
後に巨大な産業上の連合になるようなゲゼルシャフトは、その出発点で家族的な要素と共通の家計をその中に取り込んでいた。
ソキエタースの財産法
ソキエタースの債務と個人的債務
ソキエタースの連帯責任については、すべての債務についてそれが適用されるのではなく、ソキエタースの債務のみに限定されるようになっていったが、そのためには何がソキエタースの債務となるのかという見分けるための目印が必要とされた。
ソキエタースの債務を判断する目印
1.会計簿への記帳
その目印としてまず登場したのはソキエタースの会計簿へのその債務の記帳であった。しかしそれだけでは十分ではなく、どの債務が記帳されるべきなのかという更に別の目印が必要であった。
2.ソキエタースの名前での契約
その目印として使われたのが、ソキエタースの名前=商号であった。初期の商号は責任を持つ者の名前を全て含んでいた。(合名会社の「合名」の意味)ソキエタースの名前=商号によって契約されたものが、ソキエタースの業務として連帯責任を負うべきものとなった。
ソキエタースの財産に対する差し押さえからの個人への債務者の除斥
ソキエタースの財産がある契約について責任を負う一方で、ソキエタースの成員個人の債権についてはソキエタースの財産は関知しない。ソキエタースが破産した場合は、各成員の財産はソキエタースに関連付けられ優先的に差し押さえられる。
II. 諸文献:アルベルティ家とペルッツイ家における商業簿記
大規模なソキエタースの実例としてアルベルティ家とペルッツイ家に関する文献を確認し、そこに今まで見てきた発展の過程を再確認する。
家計ゲマインシャフト
まずは、この両家において、共通の家計に基づく、共用品についての支出がソキエタースの共通金庫から支払われている例を確認出来る。また共同で行う宴会の費用などがまず共通金庫から支払われ後に各成員の勘定に振り替えられている事例が確認出来る。
ゲマインシャフトの土台としてのソキエタース契約
これらのフィレンツェの大規模ファミリーにおいては、家ゲマインシャフトを基礎にしながらも、そこでは一定年数毎に書面による契約が締結されていた。
資本金と各ソキエタース成員の出資
これらのファミリーにおいては、各成員の出資金を合計した資本金=il corpo della compagnia [コンパーニアの実体]が存在しており、利益が繰り入れられ損失が控除されるが、2年に1回の決算までは増額も減額も出来なかった。
各ソキエタース成員のゲマインシャフトの外部での特別財産。
1.不動産
不動産については、相変わらずソキエタースの財産の外部にあるものとされており、分割や増額・減額の対象外であった。
2.個人の動産
ソキエタースの成員は、本来のソキエタースの出資金以外でのソキエタースへの投資として、短期的な貸し付けを行うことが行われていたが、その貸し付けはいつでも引き出せる預金のような性格のものであり、ソキエタースの資本金の外部にあるものとして扱われた。
1336 年のアルベルティ家の相続協定
ここでは、アルベルティ家のある父親が亡くなった後の、死後17年目にようやく行われた相続財産分割の協定の内容が示される。この例で本来の資本金への出資と、一種のコムメンダ的な預け入れ金がはっきり区別されていることが確認出来る。また、父親が出資していた分について3兄弟で分割して相続している。各成員が所持する財産は次の4種類であった。
1.不動産であって、ソキエタースとは無関係に存在するもの。
2.動産であって、ソキエタースとは無関係のもの。
3.動産であって、ソキエタースにおいて資本金以外の扱いで投資されているもの。
4.コンパーニアの資本金の中での各自の出資金としての財産。
成果
ここに出て来たcorpo della compagniaという資本金こそが、ゲゼルシャフトの特別財産である。
この財産は内部に対しても外部に対してもゲゼルシャフトの財産として認められるものであった。
VI. 法的文献。結論。
法的文献とそのソキエタースへの関係
ここまでで合名会社を特徴付ける、会社の特別財産、連帯責任、商号の発展を明らかにした。
また合資会社をその始まりからある程度まで発展した形までの経緯を明らかにしてきた。
1.合資関係
合資会社は対等ではない成員間のソキエタースであり、ローマ法的には説明が困難だった。また、教会法による高利禁止に該当するかしないかという問題も厄介だった。
2.合名会社
a) 特別財産
合名会社の特別財産については、法規の中ではっきりと扱われているものは見出せない。それはソキエタースの破産の際の債権回収の優先権という形でようやく確認出来る。その後、ソキエタースが “corpus mysticum”(神秘的な体)という言葉で一種の擬人として扱われるようになり、ソキエタースの特別財産はその擬人の財産として理解されるようになり、成員個人の財産から分離された。それが最終的には法人概念の発生につながっている。
b)連帯責任。委任の仮定と代表者[Institorat]の仮定。
連帯責任の法的な説明としては、ソキエタースの成員が代表者を選んでその者に全権を委任したのだ、という現実には存在しない仮構が用いられた。
連帯責任の実質的な根本原理との関係
連帯責任は法的に規定された結果普及したのではなく、商慣習が先行し、法学的な理論付けは後から行われた。
その際に家計ゲマインシャフトでの連帯責任成立の条件としては、単に一緒に住んでいるだけでは不十分で、共同の労働、共同の経営ということが必要とされた。契約書においての「共通の名前で」という記載がそれについての標識とされた。
国際的な発展に対しての法学研究の成果
ソキエタース会社
しかしそうした連帯責任の法的定義はローマ法的な立場からは決して好ましいものではなく、法律はそれを出来るだけ制限しようとしていた。そのために、その契約がソキエタースの名前で行われたかどうかは厳密な形で要求され、それをより明確にするために、参加するソキエタースの成員の名前を全て含んでいる商号が契約に使われるようになった。この点は法学の貢献である。
ジェノヴァ控訴院判例集とジェノヴァの 1588/9 年法
発展の結着
最終的に法律として合名会社や合資会社の定義が確立するのは16世紀のジェノヴァ控訴院判例集とジェノバの1588/9年法においてであった。この二つの会社形態で、ゲゼルシャフトの特別財産が確立していることが確認出来る。
結論。得られた成果の法教義学的利用の可能性。
合名会社における連帯責任概念の成立については、ドイツ法の「合手制」の概念が影響している可能性が高い。しかしながらこの論考ではドイツ法の領域において合名会社に相当するものが平行して発達したかどうかという確認は行っていないので、それに対してはっきりした見解を述べることは出来ない。ただザクセンシュピーゲルに同種の制度が存在していることは確認出来る。
この論文の成果として、合名会社と合資会社に共通する要素としての会社の特別財産の成立の過程を明らかにしたことが挙げられる。その二つの違いとしては合名会社はその特別財産が財産権的な人格を持つに至ったが、合資会社についてはそういった全体としての人格性は無く、有限責任社員の関与は単に参加という次元に留まっている。
「ローマ農業史」の日本語訳プロジェクトのスタート
「中世合名・合資会社成立史」の校正もほぼ終ったので、次のステップとして「ローマ農業史 国法と私法への意味付けにおいて」の日本語訳プロジェクトを開始します。まだ訳せるかどうかは分りませんが、これも英訳が出ているのでそれを読んで訳せそうかどうかを判断してから取りかかりたいと思います。今、一冊訳してドイツ語の読解力は大学卒業直前のレベルにほぼ戻ったと思っていますし、またラテン語も復習出来たので、間を空けるより一気にやってしまった方がいいかなと思います。この論文はヴェーバーの2番目の論文で、これで教授資格を得るのですが、これも何故か今まで一度も日本語訳されていません。ページ数は、「中世合名・合資会社成立史」が約200ページでしたが、こちらは160ページくらいで短いです。
「中世合名・合資会社成立史」のAmazonでのKindle版に付けた説明
Amazonで「中世合名・合資会社成立史」のKindle版につけた紹介文です。この程度でも今までこの論文の内容を的確に説明したものは無かったと思います。
「マックス・ヴェーバーの博士号論文(正確には元々の博士号論文は本論考の第三章のみで他は後から付け加えられたもの)で実質的な学者としての業績のスタートであるZur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter(1889年)の最初の日本語訳です。古典ラテン語、俗(中世)ラテン語、初期イタリア語、初期スペイン語、中低ドイツ語等々で書かれている中世の法規史料の引用部(本文中、注釈中とも)についても全て日本語に訳している完全翻訳です。ヴェーバーが中世の北イタリアの沿岸都市において地中海貿易・中東貿易での危険分担と利益の分割の必要性から生まれて来たコムメンダやソキエタス・マリスといったある種の新しい経済団体や、フィレンツェやピアチェンツァなどの内陸都市で盛んだった手工業における家計・労働ゲマインシャフトが、元々のローマ法のソキエタス(組合)の延長としての解釈を超えて、最終的に合名会社や合資会社という新しいゲゼルシャフトとして法制度の中で定義されるまで、どのように発展し確立していくかという過程を、会社の特別財産と連帯責任と商号の成立という3つの観点で実証的に分析したものです。この論文に出て来るコムメンダやソキエタス・マリス、海事利息等は教会法で禁じられていた利子付き金銭貸借を回避する手段についての議論の中で「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」の中でも言及されていますし、またゲマインシャフトを基礎としそこに契約を契機としてゲゼルシャフトが新たに生成される過程は、後の「理解社会学のカテゴリー」でゲゼルシャフトはゲマインシャフトの特別な場合であるという議論にもつながり、ヴェーバーの学問像全体の研究においては必読の論文です。」
AmazonでKindle版も入手出来るようにしました。
「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳ですが、AmazonでKindle版の販売も開始しました。お金を取るつもりは無かったのですが、無料という設定は出来なかったので、最低価格の$0.99(日本円で105円)になっています。
中世合名・合資会社成立史のPDF版公開
「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳のPDF版を公開します。
まだ校正が十分ではありませんが、取り敢えず訳者注を本文から分離して脚注にしました。また人名をカタカナ表記に変更しました。
追記:2020年9月9日(校正0006版)→書式(フォントサイズ、イタリック下線部分の下線追加など)を一応終了しました。
追記:2020年9月10日(校正0012版)目次が全集版のページ数だけになっていたのを、この日本語訳でのページ数を()で追加しました。
追記:最新の校正版はここです。