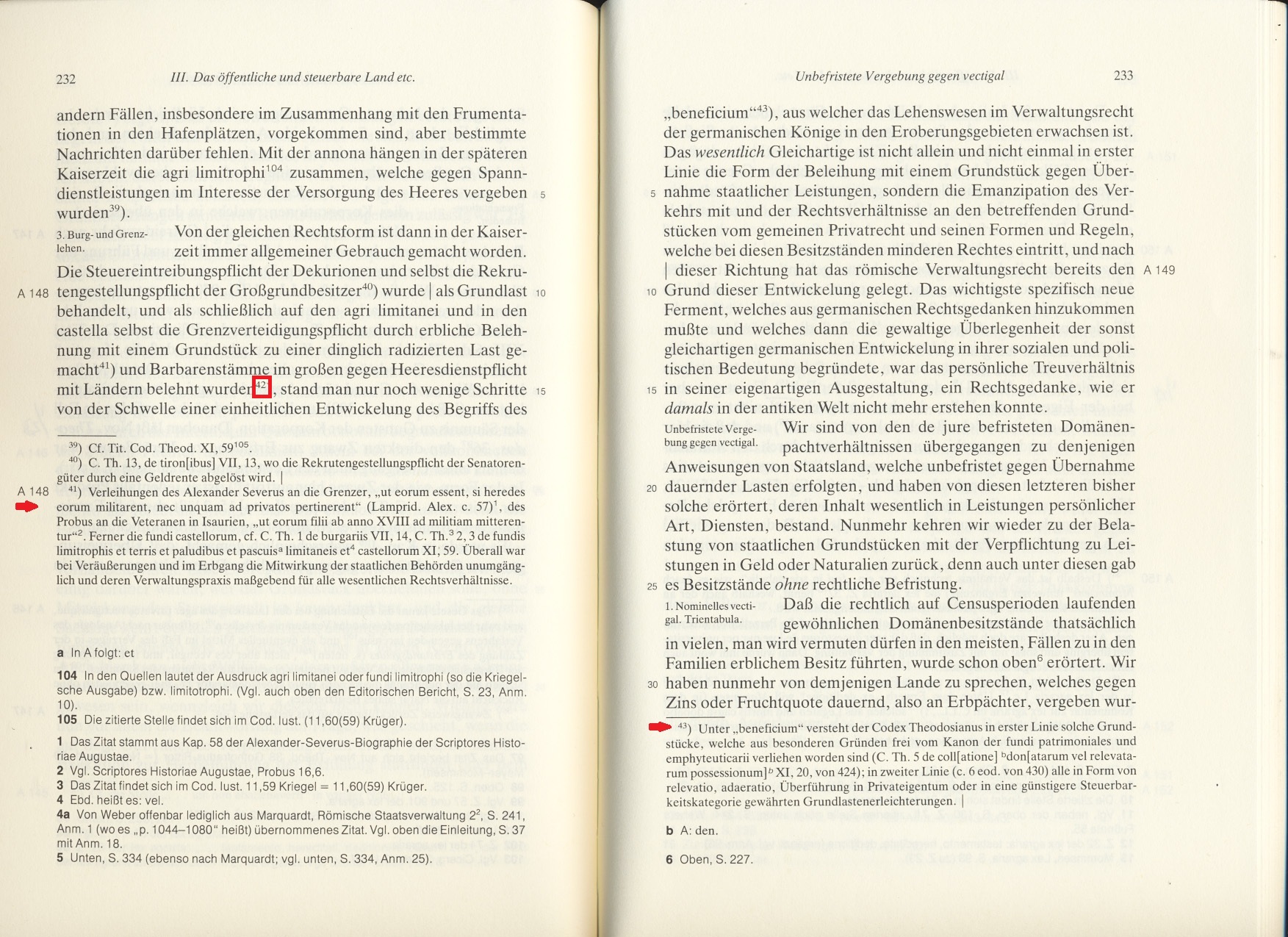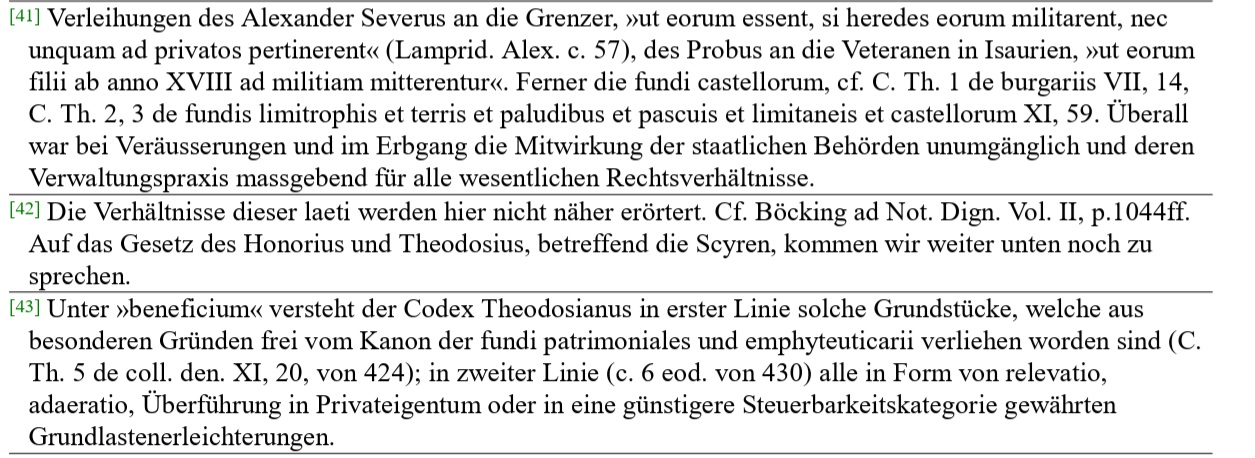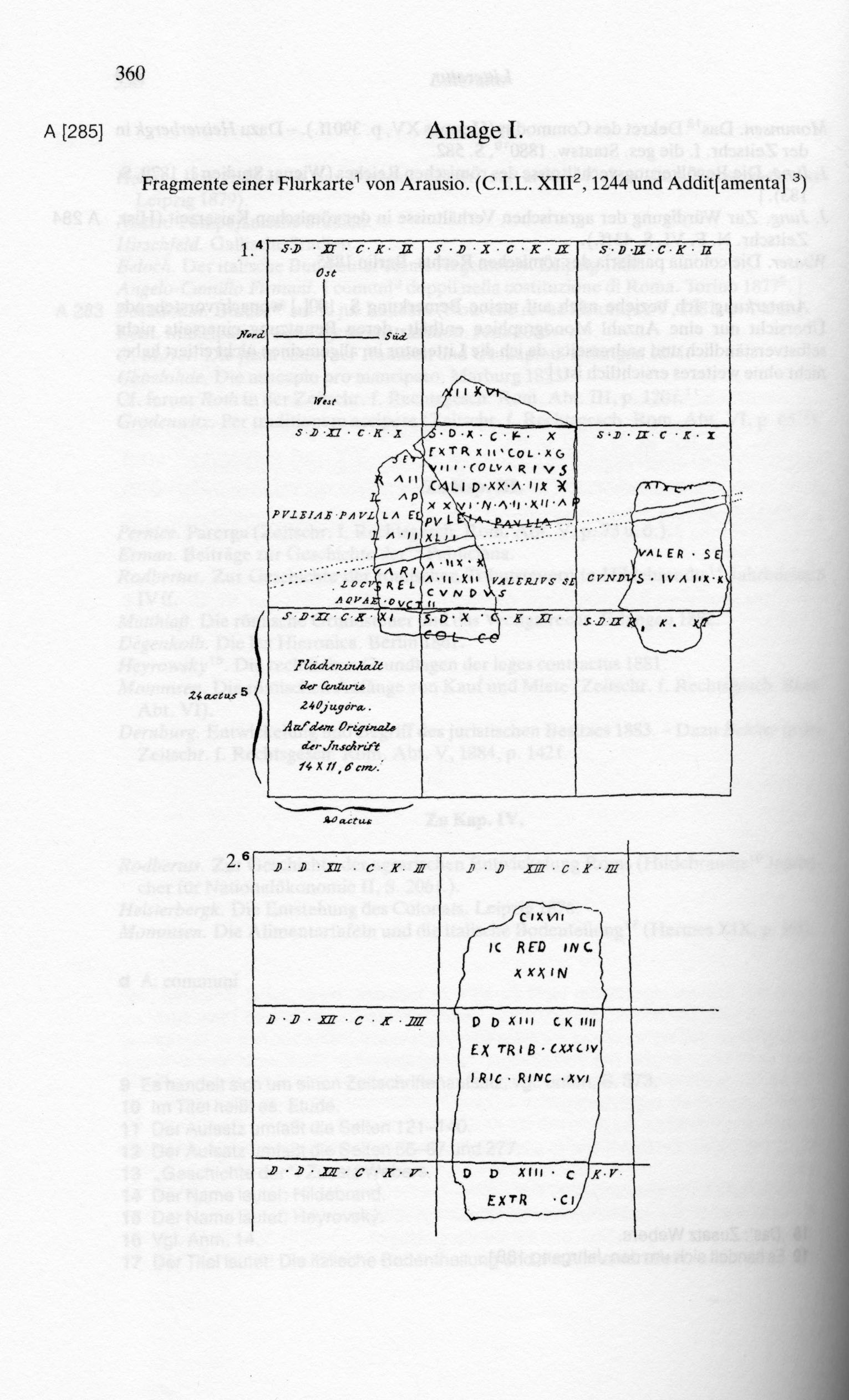「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第64回目です。
ここではコローヌス制と奴隷使役の上に立つ農場経営が次第に自立・自営の動きを強めていって、ローマの国家の中のいわば小さな別の国家になっていく様子が辿られます。ヴェーバーは明らかに中世のグーツヘルシャフト制(荘園制)の起源をローマのこの農場経営に求めています。それはいいのですが、ここでホノリウス帝の時のスキリア族に土地を与えてローマ領内に住ませたことがコローヌスと同様の制度として論じられています。注に書きましたが、これは西ローマ帝国末期のきわめて暫定的な処置と捉えるべきであり、ヴェーバーは法律にだけ注目してそういう背景情報をまったく書いておらず、誤解を招きます。
=================================
このようなコローヌスの取り戻しの現実的な可能性は、大地主にとっては本質的な利害に関係するものであり、それはまた特に次の理由で、つまり大地主はコローヌスの税率について責任を負っていたからである。このような――土地税と人頭税――はコローヌス達が使用している土地のユガティオとしてケンススに登録され(adscribere) 77)、コローヌス達はそのことによって adscripticii[登録された者]と呼ばれた。大地主に対して諸ゲマインデに対するのと同様に次の義務が課された。つまりその大地主の責任となる新兵徴集ノルマという義務であるが、このことは土地それ自体が負担すべき現物的な義務として把握されており、そして大地主達は何とかこの義務を免除してもらおうとし、それは定期的な金銭支払いに代えてもらうことで部分的には成功したのである 78)。
78) Adscribere の手続きについては常に――テオドシウス法典 26 de annon[a] 11, 1;同法典 3 de extr[aordinariis] et sord[idis] mun[eribus] 11, 16;同法典 51 de decr[ionibus] 12, 1;同法典 7 de censu 13, 10;同法典 34 de op[eribus] pub[icis] 15, 1;同法典 2, 3 de aquaed[uctu] 15, 2;同法典 2, sine censu 11, 3 (servi adscripti censibus)――占有者や10人委員会の長による夫役や税の負担についてケンススに登録することが必要とされた。
78) テオドシウス法典 1 qui a praeb[itione] tiron[um] 11, 18、は帝政期の土地の例によれば、それについては同法典 2 de tiron[ibus] 7, 13 が制定された後は免除されるようになっていた。同法典 13 の同じ箇所の Adaeration [adaeratio]≪金銭の支払いによって免除された義務≫を参照。
属州におけるコローヌスについては、一般に人頭税が課せられた状態になっていたと思われるが、そのコローヌスはそのことによって censiti と呼ばれており、その結果としてコローヌス達はその者達の市民的な権利が弱められた階級に所属することになっており、それがこの状態の帰結であった 79)。
79) より下のクラスの者の人頭税免除については、その者達に拷問を加えることを可能にするという目的で、censiti の階級に入れられたということが、テオドシウス法典の 3 de numerar[iis] 8, 1 にて特別に規定されている。
大地主に属するコローヌスと自由なコローヌス
次のことは明らかである。それは以上のことをもってコローヌスとして知られた法的な状態についての全ての本質的な外形的特徴が与えられている、ということである。この状態がまさしく大地主の土地区画において発生していたということは、それによって説明されるのは次のことである。つまり帝政期の法律文献において、そういったコローヌスと並んで自由な期間限定賃借人の通常の賃貸借関係が見出される、ということである。
大地主に土地に従属するコローヌスの所有権について法学者がほとんど言及していないことの理由は、このコローヌスという状態について特別に適用されるように作られた規則の行政処理的な性格にある。ひょっとしたらコローヌスの法律上の状態は当時まだ実務的な処理においては様々に解釈し得るものだったのであり、それ故に該当する法学者達がその著作の編集においてはそれを扱わなかったのである。
類似の状態。軍事上の城砦。蛮族の定住。
コローヌスと同等の状態にあるものとして、一連の他の組織について見て行くこととする。その場合アフリカでの軍事上の城砦の住民は明らかにその土地に従属するコローヌスであったのであり、夫役の義務を課せられかつ皇帝によって任命された特別官の管理下に置かれた 80)。
80) アレクサンデル・セウェルス帝≪第24代ローマ皇帝、在位222~235年。≫は234年に “per colonus ujusdem castelli”[コローヌスを使って同じ城を]、――つまりマウリタニアの Dianense ≪現在のアルジェリアにあった属州マウレタニア・カエサリエンシスの都市≫の城――城壁を建設し、つまりそれはコローヌスを使役することによってであった。(C.I.L., VIII, 8701。参照 8702, 8710, 8777。)
また取り分け辺境の蛮族はコローナートゥス制≪コローヌスを使った小作制度≫の権利でそこに定住していた。ホノリウス帝≪西ローマ帝国皇帝、在位393~423年、暗君であって西ローマ帝国滅亡の原因を作り、在位中にローマが蛮族に占領された。≫はスキリア族≪東ゲルマンの部族で現在のウクライナに住んでいたが、フン族に追われて西ローマ帝国領に侵入した。≫を彼らがローマに屈服した後に、大地主の下にコローヌスとして置いて分割したが 81)、それは労働忌避者を大地主の下に送って使役させたのと同様である。
81) 409年のホノリウスの法とテオドシウス法典 V, 4, 1. 3:Scyras .. . imperio nostro subegimus. Ideoque damus omnibus copiam, ex praedicta gente hominum agros proprios frequentandi, ita ut omnes sciant, susceptos non alio jure quam colonatus apud se futuros.
[スキリア族を…我々の支配権の下に服属させた。それ故に全ての者に次の許可を与える。つまり、先に述べた民族について、その者達を自分の土地に住まわせることである。その際に全ての者が知っておくべきことは、こうして受け入れられた者は法的にはその受け入れられた者の下でコローヌスとなる、ということである。]
≪この例は、西ローマ帝国末期の暫定的な処置であったと思われ、実際にこの409年にはローマは蛮族の占領を受けている。またスキリア族も一旦ローマに恭順の意を示したが、すぐ後にフン族と共謀してローマに再度反旗を翻しており、決して安定的に持続した法的制度ではなかったことに注意。≫
既にこのことに遡って同様の処置が既に行われていた可能性がある。モムゼンはコローヌスの起源をマルクス・アウレリウス帝の時の蛮族の定住に求めているが、ガリアでのラエティア人≪元々ポー川流域に住んでいたエトルリア系と言われている部族で、ガリア人の侵入により山地に移動した。≫をコローヌスと見なすことは否定されるであろう。そういう議論にもかかわらず、私には蛮族とコローヌスには本質的な違いがあると思われる。というのはラエティア人とローマ帝国領内に定住した蛮族は全体で、我々が知る限りでは、より上位の農民に従属する土地付属の人間集団ではなく、[軍事力を提供する代わりに土地を与えられた]封土の所有者であったからである。次のことは完全に可能と思われる。つまり蛮族の定住が物権の発展の一般的傾向としての個人的及び公的な義務を本質的に強化した、ということであるが、しかし私が信ずるのは、コローヌスの権利状態というものは、そういう蛮族の定住のことを特に考慮しなくとも、法制史・経済史の観点で説明しうる、ということである。いずれにせよ定住させられた蛮族は、つまり gentiles は、文献史料の中でコローヌスとは区別され、gentiles については特別な個々人の身分を規定する法が存在した 82)。
82) 蛮族との結婚の禁止 テオドシウス法典 1 de nupt[iis] gent[ilium] 3, 14。
占有の法的位置付け
大地主のコローヌスに対しての権利の状態は完全に官憲的な性格を持っていた。一般論として大地主には警察力が与えられていたに違いなく、その力に基づいて saltus Burunitanus の請負人[conductor]はその配下のコローヌス達を棒で打ったりしていた。クラウディウス帝は元老院に対して、自身の土地においての一般的な市場開催権を認めさせており、その権利にはいずれの場合でも市場警察の権利が結びつけられており、そして大地主についてもまた次のような権利が与えられていた。それは市場で販売される家畜や奴隷について、商品そのもの、あるいはその商品の品質や員数不足に対しての購入者からの苦情に対して、按察官[アエディリアス]≪建築、道路、水道、市場などの管理を担当するローマの官吏≫のやり方に倣ってそれに対処する、という権利である。同様に市場においての司法権もまた私人である大地主に与えられた(C.I.L. VIII, 270)。大地主達は彼らに与えらえた警察権力を使ってその配下の者達に対して、それが適当と思われる場合においてはコローヌス達を奴隷のように収用部屋に監禁したのであり、このことは皇帝の立法によってこういったケースで監禁された私人に対して干渉し、そういった行為を越権行為[crimen laesae majestatis]≪元々の意味は国家に対する反逆などの重大な犯罪のこと≫として国家大権に基づく介入を行って調停しようとすることが試みられるまで続いた 83)。
83) テオドシウス法典 1 de privat[is] carc[eribus] 9, 5。
同様に明確に起きたことは、国家の行政当局と大地主の土地で官憲の関与を免除された領域の管理人との間の争いである。農場管理者の側は次のことを要求した。それは犯罪者の追及とその他の必要な措置をその領域の中ではただ要請を当局に対してするだけで出来るようにすることであり 84)、言い換えれば、農場管理者達はフランスにおいて治外法権[Immunität]と呼ばれているのが常であることを行使することを、当然の権利として要求したのである。
84) テオドシウス法典 11 de jurisd[ictione] 2, 1。大地主の代理人たちは一般的に全ての上位の裁判から免除されるように努力した。それとは反対のことがテオドシウス法典 1 の前掲部にある。
それについては皇帝の側から拒絶されたのである。他方では大地主達は部分的には次のことをやり通すことが出来た。つまりその配下の者達に対しての裁判を行うことであり、それも民事と刑事の両方についてであり、原則的にはグーツヘルシャフト制を先取りした形で公判を行っていた。大地主はコローヌスを法廷に出頭させ、その者達に[裁判によって]庇護を与えた 85)。
85) テオドシウス法典 de actor[ibus] 10, 4 の皇帝の配下の者についての規定。しかし私人である大地主達が同じことをやろうと努力しかつまたそれにある程度成功していた、ということは、その者達が精力的な弁護を行い、また部分的には法廷への出頭義務を免除してもらおうともしており、また部分的には小規模地主を保護しようとしており、そして自身で所有する土地領域に定住しようとしていること、あるいは自身の大地主としての地位を認識しようとしていたことを示している。テオドシウス法典 1, 2 de patroc[iniis] vic[orum] 11, 24 ;同法典 5, 6 前掲部;同法典 21 de lustr[ali] coll[atione] 13, 1;同法典 146 de decur[ionibus] 12, 1 (「有力者の庇護の下に」[sub umbram potentium]逃亡した10人委員会の長に対して)。ユスティニアヌス法典1, §1 ut nemo 11, 53 においては”clientela”[庇護民]という関係の表現が使われている。参照 D. 1, §1 de fugit[ivis] 11, 4。
所有する土地領域をムニキピウムの裁判管轄区域から除外してもらうという動きは、完全にそれ自身の意志だけによる発展であった。徴兵は更にまた税の徴収管理と同様大地主制にのみ関係することであった。地主はその者なりにその領域のケンススのリストへの登録を導入し、税を徴収し法の執行権を持っていた 86)。
86) D. 52 prd[e] a[ctionibus] e[mpti] v[enditi]、そこではある請負業者が saltus の土地区画を税を滞納したという理由で競売にかけている。地主が自身の官憲的機能の利用を奴隷やコローヌスに委託することがよく行われており、そのためにユスティニアヌス法典の 3 de tubular[iis] 10, 69 は、地主が奴隷やコローヌスが行ったことに対して地主自身が責任を負う、ということを規定している。その結果として起きたのは、諸都市から属州への大量の人口流入が、それらの諸都市は剣闘士の競技が行われなくなったこと、及びゲマインデにおいての同族間の争いへの関心が弱まった後は、その争いは今や政治的な意味でのみ支配している10人委員会の長の一族郎党の内部でのみ起きたのであるが、そして諸都市の市場が占有者達の農場においての農業に必要なものを自給する組織の形成によってその意味を失ったという状況により、大規模な占有者の保護の下に逃げ込むことが始まったことによって、その吸引力を失った、ということである 87)。
87) 注85の関連箇所を見よ。
占有者は次のことに利害関心を持っていた。つまりその配下の者達とその土地で使用出来る労働力について出来る限り徴兵されないようにする、ということであり、そして一般論としてその者達を暮らしていけるように保ち、その者達が負担出来る範囲の義務を課す、ということである。占有においては国家による課税のための組織化を免れており、その組織化の内容は都市の住民の大部分とまさにその者達が労働力を持っているという要素を、ある種の国家への従属者のように行政組織の中に組み入れたのであり、また産業における生産を一部国有化し、それに対して部分的にはある種の官憲的性格を刻印し、そしてそれらを国家による厳格な管理の下に置いた、ということである。