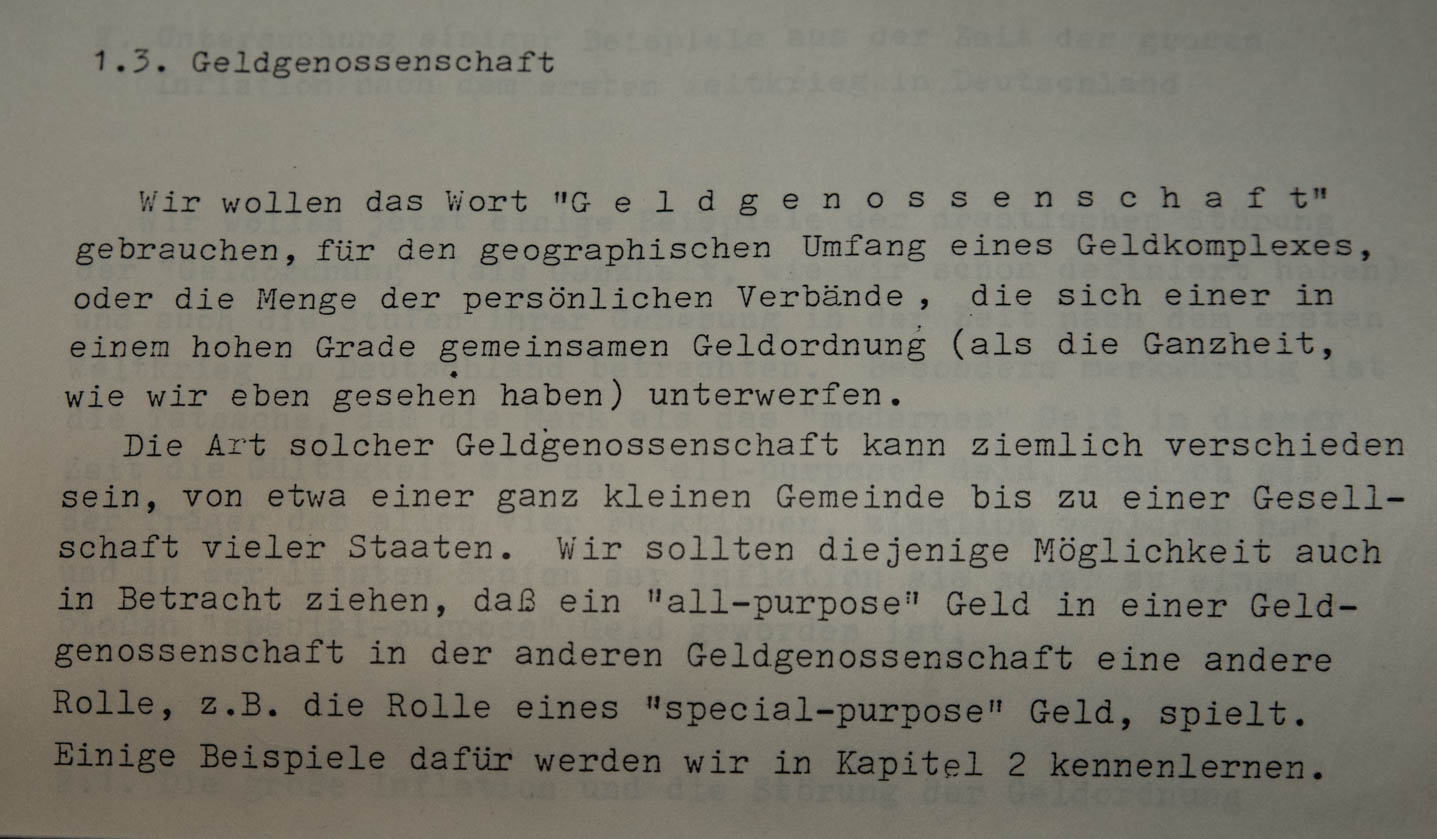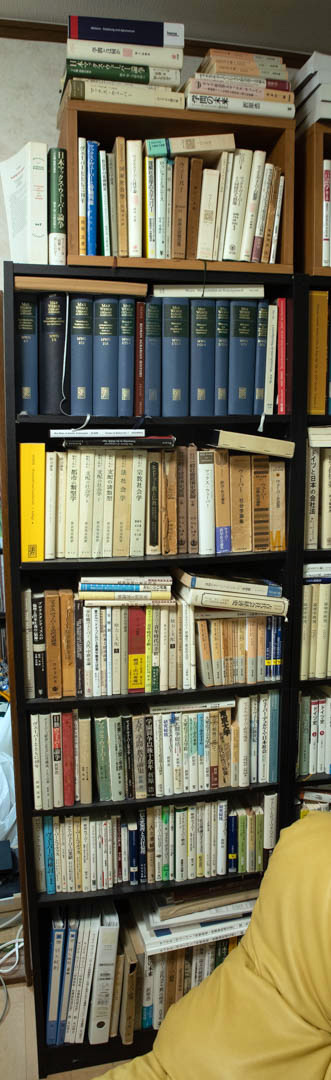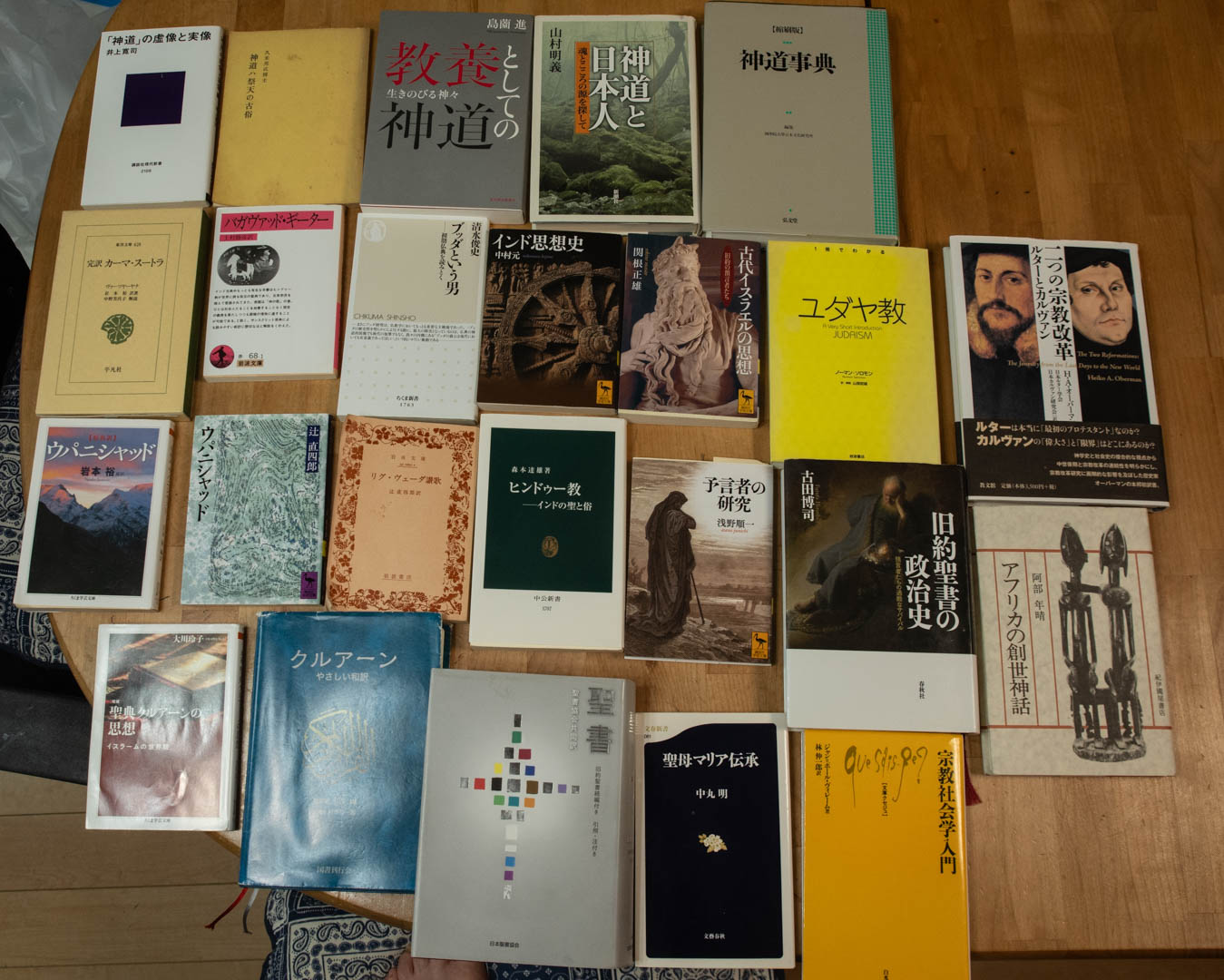ヴェーバーの初期の論文を2本、日本語訳で合計A4で500ページ分も訳すという約6年に渡る「苦行」によって、私はヴェーバーが書いたものについては、頭から信用せず、まずは疑う、という態度で臨むようになっています。それで「宗教社会学」に出てきた「団体」についての訳者注を書こうとして、「理解社会学のカテゴリー」を読み直してみて、この「理解社会学のカテゴリー」にも様々な問題があることを発見しました。以下列挙します。
1.ゲマインシャフト、ゲゼルシャフトの定義
そもそもこの「カテゴリー」論文で奇妙なのは、ゲマインシャフト、ゲゼルシャフトを直接定義するのではなく、ゲマインシャフトの方では「ゲマインシャフト行為」を定義するということが行われます。そこで例として挙げられているのは、自転車に乗った2人が衝突するのはゲマインシャフト行為ではないが、そこでお互いが回避行動を取ればそれはゲマインシャフト行為である、と定義されています。奇妙なのは、ここではゲマインシャフト関係というものには何の定義も与えられていないことです。ゲマインシャフト行為に基づく人間関係がゲマインシャフト関係であるとこちらで考えるなら、「自転車衝突回避ゲマインシャフト」なるものを想定することになりますが、そんなものはあり得ません。また自転車の衝突回避は、酔っ払いか自殺願望の人間でもない限り誰しもが行う反射的な行為であり、そこにゲマインシャフト形成の要素は存在しません。単なる2人の人間が接触した結果起きる事象に過ぎません。またゲマインシャフトというのであればそれなりに時間的な継続性が必須と考えますが、この例にそんなものは存在していません。おそらくはヴェーバーはゲマインシャフトを理論的に定義しようとしながら、その裏では一般的なドイツ語のゲマインシャフトという概念をそのまま利用しています。
もっと変なのはゲゼルシャフト行為、ゲゼルシャフト関係であり、ゲゼルシャフト行為の定義をするにあたり、その中にゲゼルシャフト関係が登場するという、一種のトートロジー、循環論法になってしまっています。(ヴェーバーの定義はゲゼルシャフト関係の中で作られた制定律に準拠しそれを当てにして他人の行動を予測して行うのがゲゼルシャフト行為とされています。)こちらもゲマインシャフトと同様、論理的定義を行おうとしているのに、何故か最初からゲゼルシャフトの一般イメージが借用されています。
2.「諒解」の説明のおかしさ
目的合理的な制定律を欠くにもかかわらず、人々が「あたかもそれがある」ように想定するのがヴェーバーが言う諒解で、ヴェーバーのその典型例として言語と貨幣を挙げています。しかし言語は確かに幼児の時に自然に習得するものですが、そこには教科書、辞書、文法書といった制定律に準ずるものが存在し、必ずしも諒解にだけ基づくものではありません。(でなかったら私たちはどうやって外国語を習得出来るのでしょうか。)更にはエスペラントのような個人によって人工的に作られた=制定された言語も存在します。また貨幣も、そもそもヴェーバーはクナップの国定貨幣(カルタ貨幣)説の支持者ですが、この場合も貨幣制度を創設したのは国というのが前提であり、必ずしも諒解だけに基づいてはいません。現代の日本においても貨幣の価値維持や受領義務というものの決定には国が大きくかかわっています。こういう風に諒解は流動的で曖昧な概念であり、カテゴリーとして使うには問題が多いと考えます。
3.「団体」とは何か
合理的な制定律は持っていないけど、諒解に基づく集団をヴェーバーは「団体」としています。丁度宗教社会学で「団体」が使われている訳ですが、こちらもおかしな用法ではないでしょうか。ユダヤ教だったら律法、トーラー、キリスト教であれば聖書や教父文書などが制定律として機能しており、決して「神があたかも存在するように」という集団ではありません。それにこれらはヴェーバーの用語法ではアンシュタルトです。(人が生まれてすぐそこに所属するようになる集団。)また例えば新興宗教であればそういった制定律に相当するものが存在しない場合もありますが、その場合であっても信仰ゲマインシャフトと考える方が自然であり、諒解に基づく団体と捉えるべきではありません。(ヴェーバーは結局宗教に関してはゲマインデ{教団}という新たなカテゴリーを作り出しており、これを見ても「理解社会学のカテゴリー」は旧稿に登場するカテゴリーを網羅出来ていないのは明白です。)
「理解社会学のカテゴリー」については、従来「経済と社会」のトップに「社会学の根本概念」が据えられていたのが、テンブルック他の批判により、1980年代に「理解社会学のカテゴリー」に準拠すべきと改められました。私が大学の時に丁度折原浩先生が、この「理解社会学のカテゴリー」に基づいた「経済と社会」の再読という作業を開始されました。その時に要するに「根本概念」の方を否定するあまり、上記のような「カテゴリー」の方の問題点を十分考慮することなく、「ヴェーバーが言っているんだから正しいんだろう」という思い込みを前提にして「カテゴリー」論文を受容していたように思います。私はこの時実際に「カテゴリー」論文を読み直すゼミに参加しています。
更に付記しておくべきなのは、「カテゴリー」論文に問題がなければそもそもヴェーバーは「根本概念」を改めて書く必要はなかっただろうということです。自分自身でも薄々欠陥に気づいていて、かつミュンヘン大学で「カテゴリー」を講義した時に、当時の学生(いわばその当時のスーパーエリート層)がまったく理解出来なかった、という事態に遭遇して、「根本概念」の執筆に至っています。
以前、「カテゴリー」論文を「経済と社会」の頭、とする折原説に異を唱えたことがありますが、やはり「カテゴリー」論文は問題を多く含むいわば「頭脳としてきちんと機能していない頭部」なのではないでしょうか。(シュルフター教授の説く、「経済と社会」の旧稿の途中で「根本概念」準拠に変わったという双頭説は、証拠が存在しないと思いますし、またどちらにせよこの「頭」という捉え方には反対です。)