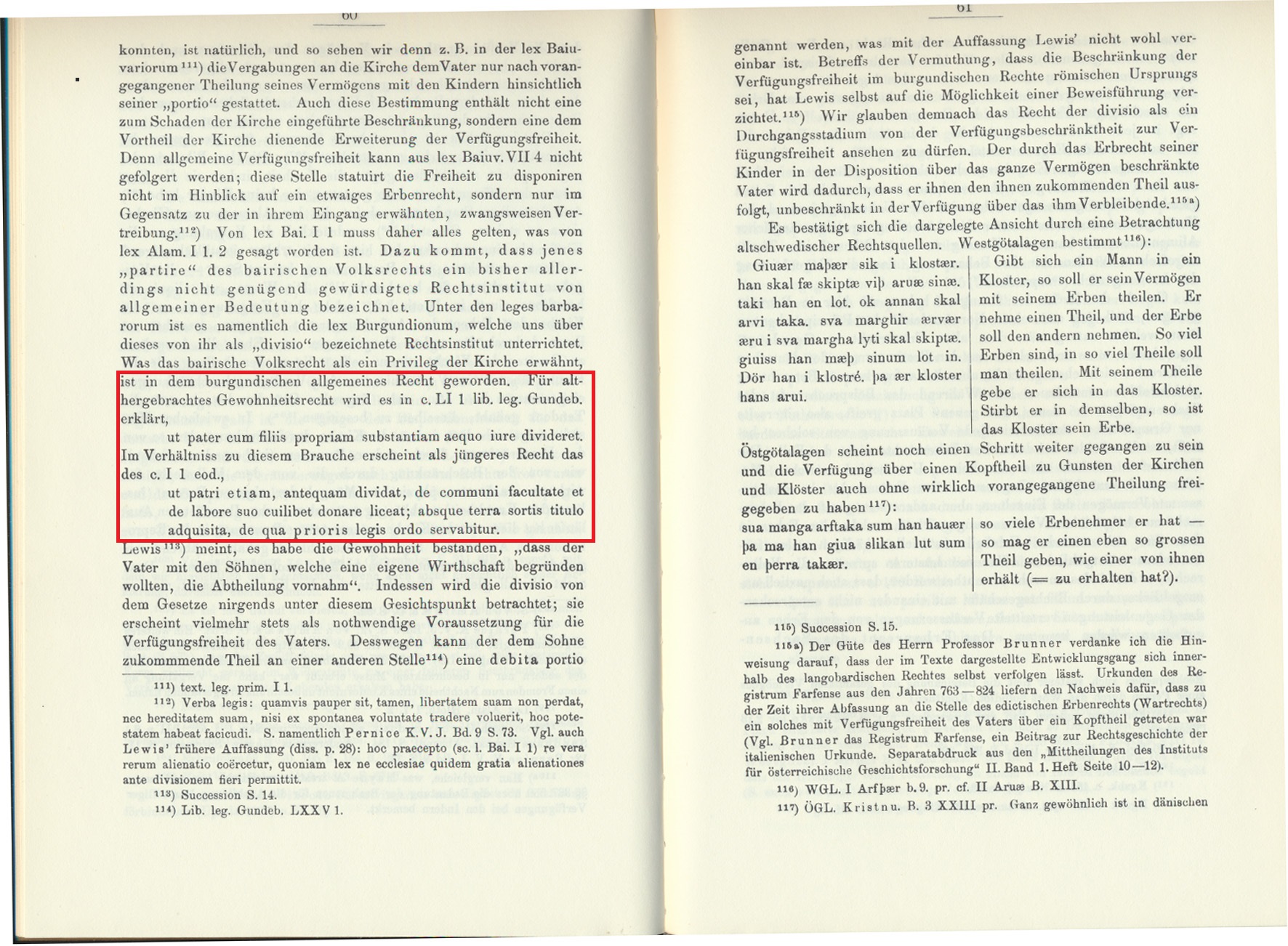日本語訳の18回目です。家ゲマインシャフトと商業におけるゲゼルシャフト形成の関係がより詳細に論じられていきます。
ヴェーバーの「理解社会学のカテゴリー」における、ゲマインシャフトとゲゼルシャフトを対立する概念ではなく、ゲゼルシャフトがゲマインシャフトの特別な場合と考えるのは、この論文での研究が最初のきっかけではないのかと思います。
ドイツ語の原文はここです。
それから今回の分も含めて最初から通して読んでみたい方はこちらを参照願います。
==================================================
これらのゲマインシャフトの共通の土台
この種のゲゼルシャフトの形態の全体構造に対する家ゲマインシャフトという要素の影響は疑う余地の無いものである。というのもそのような(Geselleとしての)ソキエタスの成員の地位は非常に高く、ソキエタスにおいて元々そうであったように、信頼関係に基づいたものでなければならなかったということは明白であり、ソキエタスはそのような(Geselleとしての)成員に対しては、丁度常時雇われている奉公人が都度都度雇われる賃金労働者に対するのと同じように振る舞うのである。これらの関係の家族的な性質もまた明らかである。親族という観点で見た場合、そして家の息子と召使い、またはfactorつまり(Geselleとしての)ソキエタスの成員とまだ独立していない共同相続人が非常に本質的な点で等しく扱われていることが見出される場合、それについては特別な説明は必要無いであろう。ここにおいて「家族法的な」根本原則が他の関係にそのまま応用されたということもまた出来ない。そうではなくて、等しい根本原則が平行的な法形成を導いたのである。というのは財産法において判定基準となるような関係が、二つのケースで同じように存在したからである。仕事を共にする仲間の関係は、本質的に家族による家計の中での構成員である家族同士の関係に似ており、他方ではその家族による家計は同時に何らかの事業経営の基盤でもあろうとした場合、簿記と外部から一つの法的主体として認識されるようにすることの二つの条件が必要であった。要するに、経営ゲゼルシャフトという形で財産法における重要な要素として扱われるために必要な全ての条件がこの二つだったのである。つまりは、家族による家計と経営ゲゼルシャフトの両方にて、法的に重要な要素は同じなのである 16)。ただ、家族ゲマインシャフトにおいては共通の家計という土台は最初から存在しているものであるが、家族以外の人との労働ゲマインシャフトにおいては共通の家計(記帳)は任意のものでしかなく、しかも改めて作り出されねばならなかった。これらのことから、家族ゲマインシャフトは、ある特定の観点から見てそれに該当するものとしての原生的法制度として把握されるのであり、それ故に文献史料にて(家ゲマインシャフトと労働ゲマインシャフトの)2つの集団が共通のものとして記述されている箇所がもっとも重要なのである。
中世における法形成の過程が様々な都市で始まった時、古くからの親族関係に基づく公法及び私法の基礎原理は既に失われており、他の場合と同様にその地位は他の純粋に経済的な原理に置き換えられたのである 17)。
手工業的な労働が家族の内側においても外側においてもゲマインシャフト的関係構築の共通の源泉なのである。
15) この点については後でフィレンツェの章で特別に詳しく扱うことになる。
16) ザクセンシュピーゲルの注釈14を参照せよ。手工業(における労働関係)が財産ゲマインシャフトの中で家族原理と並立するように存在している場合、ザクセンシュピーゲルはこの双方を不可欠なものとして扱っている。
17) この点についてはLamprecht《Karl Lamprecht、1856~1915年、ドイツの歴史家。歴史研究における法則性の発見の重要性を主張し、史料批判を重視するドイツの他の歴史学者との激しい論争を引き起こした。》の”Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter”(ドイツ中世の経済的な生)のIのP.288の注3と、Inama-Sternegg《Theodor Inama von Sternegg、1843~1908年、ドイツ・オーストリアの経済史家。》の”Deutsche Wirtschaftsgeschichte”(ドイツ経済史)のP.75の注1を参照せよ。その意義についてはまたHeuslar《Andreas Heusler、1865~1940年、スイスの中世研究者で特にゲルマンとスカンディナビアを専門とした。》のInstitutionen Des Deutschen Privatrechts(ドイツ私法における諸制度)第2巻のP.304以下で詳細に論じられている。所有されている物が財産の主要部分を占めている場合、傾向としては物を(全体の財産から)分離して個人所有とする方向へ、また動産と手工業的労働の存在は商品ゲマインシャフトへと進んでいる。
共通の特質
これらのゲマインシャフト関係の2つの特質について、ここにおいてまずは手短に確認しておくのが良いであろう。
1.男性socii(ソキエタスの構成員{複数})への制限
まず第1のものはゲマインシャフトの男性 18) 構成員に対する、その個人としての影響力に対する制限である 19)。つまり、働いて収入を得て商業において自発的に活動するゲマインシャフトの成員が、ゲマインシャフトの共通財産に対する考え得る主体なのである。それについて新しく証拠となるのは、共通の業務を執り行うことにより、成功の場合も失敗の場合も運命を共にするということを出発点に置いているということである。
18) Ansaldus de Ansaldisの”Discursus legales de commercio et mercatura.”(1698年、ジェノヴァ)のDisc.49を参照せよ。そこでは姉妹の(共通の財産への)関与の問題が普通法上で議論の余地があるものとされている。
19) Bonani編の”Constitutum Usus Pisanae Civitatis”の”De societate inter extraneos facta”(家族外のメンバーとの間でのソキエタスについて)の章の”inter laicos et masculos”(俗人と男性の間で)を参照せよ。更に別の例は後でまた取上げる。特にヴェネツィアについての議論の所で。またランゴバルド法ではただ兄弟について述べており、ブルグンドの法では父親と子供達から成るゲマインシャフトを規定しているが、しかしそこでは夫婦間での財産共有ゲマインシャフトについては何らの規定も存在しない。
2. 不動産の除外
2つ目は、ゲマインシャフトの共通の基金への帰属という意味での、規則に沿った形での不動産の除外である。既に海上取引に係わる諸ソキエタスにおいて、ソキエタスへの債権者の優先権が動産に対してに限定されたように 20)、ここにおいてもただ動産のみがゲマインシャフトの共通財産とその(各成員が持つ)個別の影響力の対象なのである 21)。共通の家というものは発展における出発点でありかつゲマインシャフトの土台であるが、(不動産としての)それそのものについては非常に明白なこととしてゲマインシャフトの共通財産には算入されていなかったし 22)、その他の動産は常に家の外に存在したのである。それ故に収益を上げる資本がさらなる発展のための材料なのである。
20) Statuta Peraeのc.20を参照せよ。
21) この部分はLattesによる”Il diritto commerciale nella legislazione statutaria”の§6の注5と6において言及されている商法における不動産の除外についての引用の中に含まれている。その他、この論考のフィレンツェの所でも再度言及することになる。
22) 家はそれぞれの持ち分所有者のソキエタスの取り決めに従った処分対象物の特別な一つのものとはならなかった。今日においてもあるソキエタス、例えば会社が不動産を(簡単には)売却することが出来ないように、持ち分所有者はその時々のゲマインシャフトの土台、つまり共通の家を、抵当に入れたり売却することは出来なかった。
財産関係における変化
それ故に財産ゲマインシャフトがもはや単純に全体をカバーするのではなく、構成員の財産のある一部のみを包括するだけになった場合、そして、既に述べたように、個々の成員による財産の分割がそれによって益々進展した形で投資や各成員がゲマインシャフトにおいて保持する一つの勘定としての性質を持つと見なされた場合、この(各員の)勘定を全体として高い程度で独立した法的主体としてみなすのと、取り分けその勘定をそうした独立のものとして(共通財産とは切り分けて)処分する可能性を認める必要性が出てきた。実際の所、フィレンツェのAlbertiという家族 23)においての遺言と遺産相続手続において、(死亡した)持ち分所有者の勘定について、その勘定を利害関係者(相続人)の間で分割しそれぞれの勘定への振り替えが命じられているという事実が見出される。更には、ゲマインシャフトの成員の資金でゲマインシャフトの共有基金には属していないものについても、可能であればそのソキエタス(ゲマインシャフト)において投資させるという需要が生じて来て、その場合には個々の成員が二重の意味でゲマインシャフトの業務に参加するという特別な関係が見出されるのである。つまりはまずはその成員がゲマインシャフトの共有財産の中での持ち分の金額の範囲においての参加と、更にはゲマインシャフトで利用可能な投資された資本において、ジェノヴァでの文献史料 24) においてソキエタス・マリスとコムメンダが同時並行して行われていたという事実に適合するような、ゲマインシャフトの業務への出資者としての参加である。さらに後の時代では、家族において、元々は法律の規定によって成立していたゲマインシャフト関係を、契約に基づいてまたその時々の必要性に応じて作り出す 25) ということも行われるようになり、それによって家族ゲマインシャフトはソキエタス法に準じた形で規定されるようになったのである 26)。それから我々はここにいても「投資」という概念にたどり着いたが、それは全体の共有財産の中での一定の割合としてであり、その割合によって当該のソキエタスの成員の分としての利益、損失、そして資本が分割されるのであり、―それはソキエタス・マリスの場合と同様である。しかしながらここにおいて次のような疑問が出て来る。つまり、この投資とここで呼ぶものがコムメンダ関係におけるものと同じ意味を持っているのかということである。この疑問については他のはるかに重要な人間関係の側面としての、ゲマインシャフトの外部や第三者に対しての作用について考察した後に答えることが出来る。我々はこの目的については、まずは後の時代の発展の最終的に予想出来る結末について述べた後で、再びその結末の開始点へと立ち戻って行かねばならない。
23) Passerini《Luigi Passerini Orsini de’ Rilli、1816~1877年、イタリアの政治家・歴史学者・系譜学者。》の”Gli Alberti di Firenze”(フィレンツェのアルベルティ家)を参照。また下記の本稿でのフィレンツェに関する部分も参照せよ。
24) 下記の本稿でのフィレンツェに関する部分も参照せよ。
25) 注23のAlberti家の史料とPeruzzi《Simone Luigi Peruzzi、1832~1935年、イタリアの歴史家、メディチ家に連なる家系の出身。》の”Storia del Commercio e dei’ Banchieri di Firenze”を参照せよ。
26) それどころか、Registrum Farfense(注11参照)のNo.36の史料が示しているように、家ゲマインシャフトそのものが契約によって創り出されている事例が存在するのである。この文献史料においては、二人の同じ家に住んでいる兄弟が彼らの叔父(伯父)を家ゲマインシャフトに迎え入れている: te … affratamus et in tertia portione … heredem esse volumus.(我々はあなたを家族として迎え入れ、そして相続人として1/3の分け前を持つことを希望する。)このケースは田舎においての家共同体に関するものである。Brunnerの前掲書(注11参照)のP.12以下では血縁関係にある者同士のゲゼルシャフト形成を商業の目的で使うことと家族ゲマインシャフトとの類似について言及している。