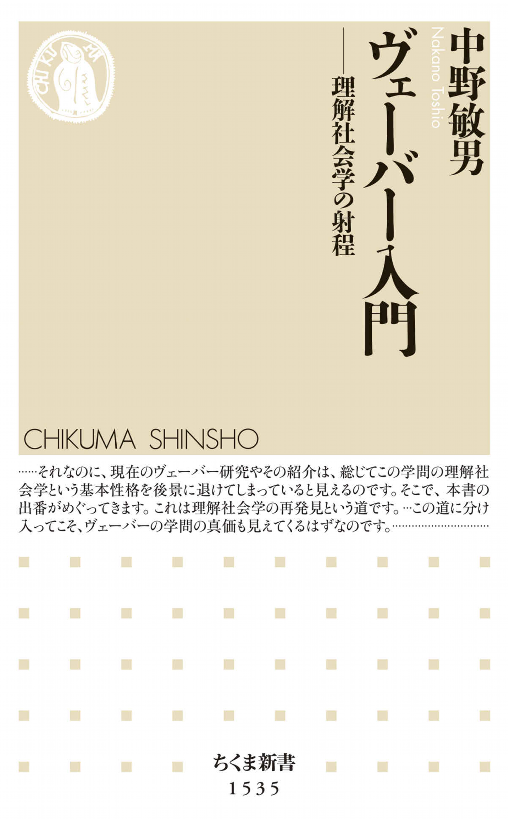 中野敏男氏の「ヴェーバー入門 ――理解社会学の射程」を読了しました。中野氏がヴェーバーにまつわる伝記的なエピソード中心の入門書や、浅く広く色んな学者の見解をただまとめたような入門書ではなく、少なくとも「ヴェーバーの学問」を氏自身の言葉できちんと語ろうとしていることは高く評価すべきでしょう。
中野敏男氏の「ヴェーバー入門 ――理解社会学の射程」を読了しました。中野氏がヴェーバーにまつわる伝記的なエピソード中心の入門書や、浅く広く色んな学者の見解をただまとめたような入門書ではなく、少なくとも「ヴェーバーの学問」を氏自身の言葉できちんと語ろうとしていることは高く評価すべきでしょう。
ですが、大変申し訳ありませんが、この入門書も他の入門書と同じく「群盲象を撫でる(評す)」ではないかという思いを禁じ得ませんでした。(この表現は若干差別的ですが、敢えて使わせていただきます。)同じことをかつて大塚久雄は「鶏がエサをつつき散らすように」と例えましたが、この中野氏の本もヴェーバーの学問の全体像を入門者に的確に説明する、ということに十分成功しているとは言えないと思います。
まずは「ヴェーバー入門」というタイトルで「ヴェーバーの理解社会学入門」ではないのに、何故理解社会学だけをここまで重視して取上げるのかが理解出来ませんでした。確かに理解社会学は特に宗教社会学においては非常に重要な方法論であり、これなくして宗教倫理から生活実践のエートスが生まれる過程を分析することは不可能です。しかし、ヴェーバーの学問の中で理解社会学は、私見ではある一定部分(決して小さくないにせよ)を占めているだけであり、理解社会学だけを押さえていればそれでヴェーバーの学問はほぼ理解出来ました、ということには決してなりません。個人的に、ヴェーバーの学問で、最初の論文である「中世合名・合資会社成立史」から宗教社会学と「経済と社会」まで、全体を貫いているもっとも重要な方法論は「決疑論」であると考えます。各種理念型を思考のスタートにし、歴史における様々な具体的諸事実と照らし合わせて、必要があれば理念型を修正し、様々な類型概念をカタログのように整理・体系化しそれによって歴史上の諸文明の分析・比較を行うというのがヴェーバーにおけるもっとも基本的な方法論であり、理解社会学さえあれば他は要りません、ということにはなりません。ちなみに中野書では「決疑論」についての説明や解説はまったくありません。
それに理解社会学という言葉がそれほど重要なのであれば、ヴェーバーがカテゴリー論を書き直した時に「理解社会学の根本概念」とはせず、「社会学の根本概念」としたのは何故でしょうか。また、私は「理解社会学のカテゴリー」が「経済と社会」の旧稿を理解する上のカテゴリー論として「頭」とされなければならない、という折原説については全面的に賛成です。しかしそうではあっても、この本の正確なタイトルは「理解社会学の二、三のカテゴリーについて」(einige = 二、三の)であり、ある意味非常に限定的な議論であって、これ「だけ」で「経済と社会」全体を完璧に解読出来る、ということでもないと思います。(参考:野崎敏郎「ヴェーバー『理解社会学論』の執筆事情とその定位 : リッケルト宛書簡を手がかりとして」)ちなみに私はここ数年、「経済と社会」の邦訳を折原先生の仮説による順番で読んでいくということを延々とやっており、つい数日前に「都市の類型学」を読了し、ようやくその作業(の一回目)を終えたところです。この「都市の類型学」の大きなテーマは、西洋近代都市の特異性を明らかにすることと同時に、中世の特にイタリアの諸都市と、ギリシア・ローマの古典古代の都市を比較するということであり、その記述の中に理解社会学的な手法は、若干はあるかもしれませんが、ほとんど認めることは出来ませんでした。「理解社会学のカテゴリー」ではゲマインシャフト(行為)、ゲゼルシャフト(行為)、諒解ゲマインシャフト、(目的)結社(Verein)、アンシュタルト(国家、カトリックの教会のように人が生まれながらにして自動的にそのメンバーとされるような団体)のような概念が定義され、もちろん旧稿の中でこれらの概念が使われていますが、それだけではありません。例えばゲノッセンシャフト(Genossenschaft、「(義)兄弟関係」のような対等な人間同士の横のつながりを重視した集団、ヘルシャフト(支配=縦)的集団との対概念)-ケルパーシャフト(Körperschaft、ゲノッセンシャフトが単なる個人の集まりなのに対し、集団そのものが一つの人格{法人格}を持ち、その成員は一定の共通の目的を持って集まったもの。Körper=身体であり、ローマ法でのコルポラチオーン{これも元々ラテン語のcorpus=身体から派生した言葉}にも似ている概念、ちなみにヘルシャフト的集団が進化したものがアンシュタルト)というのが特に都市論で使われていますが、この概念は元々ゲルマニスト(ゲルマン法重視派)のギールケ(ちなみにギールケはゴルトシュミットと並んでヴェーバーの博士号論文の査読者の一人でした)のドイツ団体法論(Das deutsche Genossenschafts-recht)他に出てくる概念であり、ヴェーバーはこの2つが「理解社会学のカテゴリー」の中のどれに当たるか(あるいはそれらでは説明出来ない概念なのか)という説明は一切していません。この例を見ても、「理解社会学のカテゴリー」が「経済と社会」に出てくる全ての概念を網羅的にカバーしているものではなく、研究のスタートにあたっての基礎的な概念整備、立ち位置の確認という性格のものではないかと思います。この点でも「理解社会学」がヴェーバーの学問の最重要の方法論だというのは疑問を呈さざるを得ません。
それから、中野氏は、西洋の近代化、合理化をほぼ物象化(非人間化、物化)とイコールだと捉えているようです。そもそも私はヴェーバーの学問を解釈するのにマルクス主義的な概念を持ち出すことに強い違和感を感じますが、例えば宗教社会学の緒論でヴェーバーが持ち出す西欧近代の色々な分野での合理化が、すべて物象化と説明出来るとはまるで思いません。例えばヴェーバーは「音楽社会学」を書いて、西洋音楽の中での調律の方法についていわゆる「平均律」が作られ使われるようになる過程を分析しますが、この平均律の採用が「物象化」と言うのは無理があり、むしろ和音の調和感(=極めて人間的なもの)と、転調という作曲上・(即興)演奏上の便宜のせめぎ合いの中で妥協的に行われたのが平均律の採用であると思います。(その意味で特殊な合理化です。)それから中野氏は貨幣を別の例として挙げ、もっとも抽象的・非人間的なものと描写しますが、これも私は納得出来ません。ヴェーバーの貨幣論(「経済行為の社会学的基礎範疇」の中の)はクナップの「貨幣国定学説」(貨幣を国家によって定められたシンボルと見るもの、カルタ的貨幣)とほぼ同じですが、それをもっとも抽象化が進んだものとは捉えていません。大体ヴェーバーの時代のドイツは第1次世界大戦後のハイパーインフレの時期を除いて金本位制だったのであり、極めて具体的な「金」が本位貨幣でした。現代の暗号通貨のようなものが他の通貨を全て駆逐するようなことになればそれはもっとも抽象的と言えるでしょうが、ヴェーバーの時代にはそういうレベルにはまるで達していません。また「理解社会学のカテゴリー」の中で貨幣は諒解行為の具体例として言語と共に挙げられており、その意味でも合理化・物象化がもっとも進んだ例として持ち出すのは、言語がそう理解出来ないのと同じで無理があります。
最後に、「プロ倫」が理解社会学か?という問題ですが、この問題については既に折原浩先生が極めて詳細に反論しており、私が特に付け加わることはありません。ただ中野氏を弁護するなら、理解社会学というのは宗教社会学の分析においてもっとも効果的な方法論であり、「プロ倫」を例として使うのは、前提となる説明の仕方が適切に修正されれば、入門書としては有り、と思います。
